複数辞典一括検索+![]()
![]()
くま【隈・曲・阿】🔗⭐🔉
くま [2] 【隈・曲・阿】
(1)(川や道などの)折れ曲がって入りくんだ所。「川の―」「道の―」
(2)奥まったすみの所。物かげの暗い所。「停車場(ステエシヨン)前の夜の―に/歌行灯(鏡花)」
(3)濃い色と薄い色,光と陰などの接する部分。また,濃い色や陰の部分。陰翳(インエイ)。「徹夜で,眼の下に―ができた」
(4)心の中の暗い部分。心中に隠していること。秘密。「まして心に―ある事/源氏(薄雲)」
(5)「隈取り{(2)}」に同じ。
(6)「隈取り{(3)}」に同じ。
(7)片田舎。へんぴな所。「山里めいたる―などに,おのづから侍るべかめり/源氏(橋姫)」
(8)(打ち消しの語を伴って)欠けているところ。「思ひ残せる―もなし/平家 10」
くま-ぐま【隈隈】🔗⭐🔉
くま-ぐま [2] 【隈隈】
あちこちのすみ。すみずみ。「岩の―に濃き陰翳を形りて/即興詩人(鴎外)」
くまぐま・し【隈隈し】🔗⭐🔉
くまぐま・し 【隈隈し】 (形シク)
(1)物かげや暗がりが多い。かくれてよく見えない。「いたく―・しき谷なり/出雲風土記」
(2)心に隠しだてをしているようだ。「なにごとかは侍らむ。―・しくおぼしなすこそ苦しけれ/源氏(梅枝)」
くま-ざさ【隈笹】🔗⭐🔉
くま-ざさ [0][2] 【隈笹】
ササの一種。山地に自生。また庭園に栽培。高さ約60〜150センチメートルで,群生する。葉は冬には縁が枯れて白くなり隈を取ったように見える。
くま-どり【隈取り・暈取り】🔗⭐🔉
くま-どり [0][4] 【隈取り・暈取り】 (名)スル
(1)色をつけて,ある部分をきわ立たせること。「目のまわりを―する」
(2)日本画で,墨や色をぼかして,遠近・高低・凹凸などを表すこと。暈染(ウンゼン)。
(3)歌舞伎で,超人的な英雄や敵役,神仏の化身,鬼畜などの役柄を誇張するために施す独特の化粧法。紅・藍・墨・黛赭(タイシヤ)などの顔料を用いて顔を彩色する。筋隈・剥身(ムキミ)隈・一本隈・公家荒(クゲアレ)・猿隈などがある。
隈取り(3)=1
 [図]
隈取り(3)=2
[図]
隈取り(3)=2
 [図]
隈取り(3)=3
[図]
隈取り(3)=3
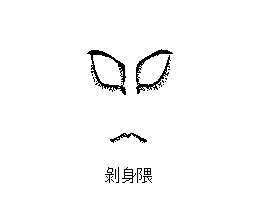 [図]
隈取り(3)=4
[図]
隈取り(3)=4
 [図]
[図]
 [図]
隈取り(3)=2
[図]
隈取り(3)=2
 [図]
隈取り(3)=3
[図]
隈取り(3)=3
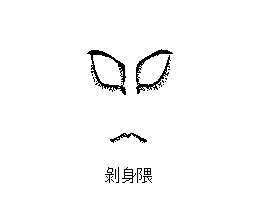 [図]
隈取り(3)=4
[図]
隈取り(3)=4
 [図]
[図]
くまどり-ふで【隈取り筆】🔗⭐🔉
くまどり-ふで [4] 【隈取り筆】
日本画でぼかしに用いる絵筆。柔らかい毛で,穂は短く丸い。くまふで。
くま-ど・る【隈取る・暈取る】🔗⭐🔉
くま-ど・る [3] 【隈取る・暈取る】 (動ラ五[四])
(1)絵画,特に日本画で,遠近・高低などを表すため,墨や絵の具でさかい目をぼかす。くまをとる。「山の端を―・る旭日の色/戸隠山紀行(美妙)」
(2)役者が役柄に応じて,くまどりをする。「―・って恐ろしい顔につくる」
くま-なく【隈無く】🔗⭐🔉
くま-なく [3][2] 【隈無く】 (副)
〔形容詞「くまなし」の連用形から〕
あますところなく。徹底的に。「家中―捜す」
くまな・し【隈無し】🔗⭐🔉
くまな・し 【隈無し】 (形ク)
(1)(月の光が)かげりがない。澄み切って暗い所がない。「花はさかりに,月は―・きをのみ見るものかは/徒然 137」
(2)なんにでも通じている。なんでも知っている。「―・きもの言ひも,定めかねて,いたくうち歎く/源氏(帚木)」
(3)行き届かぬところがない。すみずみまで行き渡っている。余すところがない。ぬかりがない。「おのれも―・きすき心にて/源氏(夕顔)」
くま-ふで【隈筆】🔗⭐🔉
くま-ふで [2] 【隈筆】
⇒隈取(クマド)り筆(フデ)
わいはん-ないかく【隈板内閣】🔗⭐🔉
わいはん-ないかく 【隈板内閣】
第一次大隈重信内閣の通称。1898年(明治31),自由党・進歩党が合同して成立した憲政党を中心とする最初の政党内閣。大隈が首相兼外相,板垣退助が内相を務めた。憲政党内における対立,貴族院・元老の圧迫などによりわずか四か月で崩壊。
くま【隈】(和英)🔗⭐🔉
くまどり【隈取り】(和英)🔗⭐🔉
くまどり【隈取り】
shading (絵の);makeup (顔).→英和
くまどる【隈取る】(和英)🔗⭐🔉
くまどる【隈取る】
⇒隈(取る).
大辞林に「隈」で始まるの検索結果 1-14。