複数辞典一括検索+![]()
![]()
くま【隈・曲・阿】🔗⭐🔉
くま【隈・曲・阿】
①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」
②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」
③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」
④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」
⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」
⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」
⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。
隈
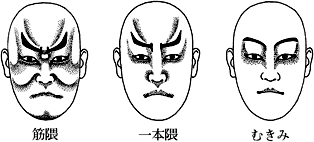
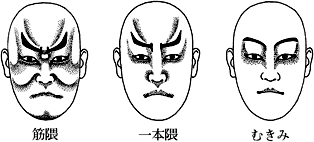
くまぐま・し【隈隈し】🔗⭐🔉
くまぐま・し【隈隈し】
〔形シク〕
①ひどく薄暗い。くまが多くて隠れて見えない。出雲風土記「いと―・しき谷なりとのたまふ」
②うしろぐらいようだ。秘密があるようだ。源氏物語梅枝「深く隠し給ふと怨みて…―・しくおぼしなすこそ苦しけれ」
くま‐ざさ【隈笹・熊笹】🔗⭐🔉
くま‐ざさ【隈笹・熊笹】
ササの一種。山林中に自生し、観賞用に広く栽培。高さ約1メートル。幹は細くて強靱。新葉は緑色だが、秋、縁辺が枯れて白変するのを隈に見たてていう。葉は料理・菓子の装飾用。
クマザサ
撮影:関戸 勇


くま‐じ【隈路】‥ヂ🔗⭐🔉
くま‐じ【隈路】‥ヂ
曲りかどの多いみち。
くま‐で【隈手】🔗⭐🔉
くま‐で【隈手】
曲がりくねって見えないところ。冥界。神代紀下「八十隈やそくまでに隠去かくれなむ」
くま‐と【隈所】🔗⭐🔉
くま‐と【隈所】
くまになっているところ。物かげ。万葉集20「葦垣の―に立ちてわぎもこが」
くま‐どり【隈取り・暈取り】🔗⭐🔉
くま‐どり【隈取り・暈取り】
①くまどること。彩色を加え、ぼかすこと。
②絵画で、遠近・高低・凹凸などを表現するため、墨や彩色の濃淡によってぼかしを加えること。
③歌舞伎や中国の京劇などにおける特殊な化粧法。正義・悪・超人的な力などをもつ役柄を強調するため、紅・青・墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。→隈くま(図)。
⇒くまどり‐ふで【隈取り筆】
くまどり‐ふで【隈取り筆】🔗⭐🔉
くまどり‐ふで【隈取り筆】
ぼかしをするのに用いる画筆。柔毛で製し、穂の形は円く短い。くまふで。
⇒くま‐どり【隈取り・暈取り】
くま‐ど・る【隈取る・暈取る】🔗⭐🔉
くま‐ど・る【隈取る・暈取る】
〔他五〕
①彩色で濃淡をつける。境目をぼかす。為兼集「雲の色は―・る墨の移し絵に」
②顔を紅・墨などでいろどる。特に、俳優が顔の隈取りをする。浄瑠璃、源平布引滝「つらを―・り隠せしは」
くま‐なく【隈無く】🔗⭐🔉
くま‐なく【隈無く】
〔副〕
(形容詞クマナシの連用形から)行き届かぬ所なく。何事にも通じて。「―探す」
くま‐な・し【隈無し】🔗⭐🔉
くま‐な・し【隈無し】
〔形ク〕
①隠れる所がない。陰がない。源氏物語夕顔「八月十五夜、―・き月かげ」
②心にかくす所がない。へだて心がない。源氏物語夢浮橋「聖といふ中にもあまり―・く物し給へば」
③行き届かない所がない。ぬかりがない。何事にも通じている。源氏物語帚木「―・き物言ひも定めかねて」
くま‐み【隈回】🔗⭐🔉
くま‐み【隈回】
くまのあるめぐり。曲り角。くまわ。万葉集2「道の―に標しめ結へわが背」
わいはん‐ないかく【隈板内閣】🔗⭐🔉
わいはん‐ないかく【隈板内閣】
1898年(明治31)6〜11月の、憲政党内閣の俗称。大隈おおくま重信が首相兼外相、板垣退助が内相だったからいう。政党内閣の端緒となったが、旧自由・進歩両党系の内部対立で崩壊。
[漢]隈🔗⭐🔉
隈 字形
 〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕
〔音〕ワイ(漢)
〔訓〕くま
[意味]
山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」
〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕
〔音〕ワイ(漢)
〔訓〕くま
[意味]
山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」
 〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕
〔音〕ワイ(漢)
〔訓〕くま
[意味]
山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」
〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕
〔音〕ワイ(漢)
〔訓〕くま
[意味]
山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」
広辞苑に「隈」で始まるの検索結果 1-15。