複数辞典一括検索+![]()
![]()
○食べ物の恨みは恐ろしいたべもののうらみはおそろしい🔗⭐🔉
○食べ物の恨みは恐ろしいたべもののうらみはおそろしい
食べ物が原因で生じた恨みはなかなか消えないということ。
⇒たべ‐もの【食べ物】
たべもの‐や【食べ物屋】
食事を供する店。飲食店。
⇒たべ‐もの【食べ物】
たべ‐よご・す【食べ汚す】
〔他五〕
食べかたが乱暴で、後をきたなくする。くいちらかす。
た・べる【食べる】
〔他下一〕[文]た・ぶ(下二)
(タブはタマフ(賜)の転)
①飲食物をいただく。「食う」「飲む」の丁寧な言い方。宇津保物語蔵開上「かの蒜ひる臭き御さかなこそ―・べまほしけれ」。平家物語6「酒暖めて―・べける薪にこそしてんげれ」。「御飯を―・べる」
②転じて、生計を立てる。「こんな安月給では―・べていけない」
⇒食べてすぐ寝ると牛になる
だ‐べ・る【駄弁る】
〔自五〕
(駄弁を活用させた語)駄弁を弄する。べちゃべちゃしゃべる。
た‐へん【田偏】
漢字の偏の一つ。「町」「略」などの偏の「田」の称。
た‐べん【多弁】
多くしゃべること。口数の多いこと。おしゃべり。饒舌。「―家」
だ‐べん【駄弁】
むだなおしゃべり。「―を弄する」
たへん‐けい【多辺形】
(→)多角形に同じ。
タホ【Tajo スペイン】
スペイン中部に発して西流し、ポルトガルに入りリスボンで大西洋に注ぐ川。多くの発電用ダムがある。長さ1007キロメートル。ポルトガル語名テジョ。
たぼ【髱】
①日本髪の後方に張り出た部分。髷まげ・鬢びん・前髪とともに結髪構成の主要部分をなす。形状により種々の名がある。たぼがみ。たぶ。つと。→日本髪(図)。
②若い女性の称。東海道中膝栗毛初「いい―でもあつたら、この息子を出し抜くめえよ」
だ‐ほ【拿捕】
①とらえること。つかまえて自由を得させぬこと。
②〔法〕(capture)戦時に、敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や貨物を、封鎖侵破または戦時禁制品輸送などの理由で一時押収すること。広義には、国際法または国内法に違反した船舶を国家が支配下におくこと。
だぼ【太枘・駄枘】
木材や石材を継ぐとき、両方の材にまたがってはめこみ、ずれを防ぐ小片。建物では太さ3センチメートルほど、家具などでは、より小形。木材では硬木部材、石材では鉄の部材を用いる。だぼそ。
たほい‐や【たほい屋】
(静岡県で)(→)遣小屋やらいごやに同じ。
た‐ほう【他方】‥ハウ
①他の方向。他の方面。「―の言い分」「―からの視点」
②(接続詞的に)一方では。別の面から見ると。「頑固だが、―実直である」
た‐ほう【他邦】‥ハウ
ほかの国。異邦。他国。
た‐ほう【多方】‥ハウ
①種々の方面。
②多くの国々。
③いろいろの手段。
た‐ほう【多宝】
〔仏〕(→)多宝如来に同じ。
⇒たほう‐とう【多宝塔】
⇒たほう‐にょらい【多宝如来】
た‐ぼう【多忙】‥バウ
事が多くて忙しいこと。「―をきわめる」「―な毎日を過ごす」
た‐ぼう【多望】‥バウ
将来に望みの多いこと。「前途―の若者」
だ‐ぼう【打棒】‥バウ
野球で、打撃。「―大いに振るう」
たほう‐とう【多宝塔】‥タフ
釈尊・多宝二仏や大日如来をまつる塔。円形平面の単層の宝塔の下層に裳階もこしをつけた塔形で、密教寺院に多い。上に相輪を立て、四隅に鎖をかける。日本では平安前期から造られたが、現存するものでは、鎌倉時代建立の石山寺のものが最古。
多宝塔
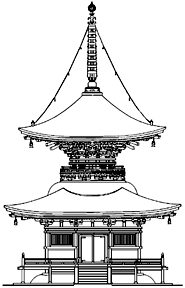 ⇒た‐ほう【多宝】
たほう‐にょらい【多宝如来】
[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。
⇒た‐ほう【多宝】
た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥
多くの方面・分野。「―に活躍する」
たぼ‐がみ【髱髪】
(→)「たぼ」に同じ。
だ‐ぼく【打撲】
体をうちたたくこと。「全身―」
⇒だぼく‐しょう【打撲傷】
だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ
物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。
⇒だ‐ぼく【打撲】
たぼ‐さし【髱差・髱刺】
髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」
だぼ‐シャツ
てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。
たぼ‐しん【髱心】
髱を張り出すために、髪に添える心。
だ‐ぼそ【太枘・駄枘】
⇒だぼ
だぼ‐だぼ
①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」
②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」
③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」
た‐ほどき【田解き】
田の土を細かに耕すこと。
たぼ‐どめ【髱留】
(→)「つとばさみ」に同じ。
だぼ‐はぜ【だぼ鯊】
①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。
②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。
たぼ‐みの【髱蓑】
蓑状に作った毛の髱差たぼさし。
だ‐ぼら【駄法螺】
つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」
た‐ぼん【他犯】
姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」
だ‐ほん【駄本】
役に立たない書物。価値のない本。
たま【玉・珠・球】
①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」
②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」
③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」
④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」
㋐まり。ボール。「―ひろい」
㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」
㋒電球。「―が切れる」
㋓卵。
㋔露・涙などの一しずく。
㋕そろばんの、動かす部分。
㋖レンズ。「眼鏡の―」
㋗きんたま。
⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」
⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。
⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」
⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」
◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。
⇒玉散る
⇒玉とあざむく
⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ
⇒玉なす
⇒玉に瑕
⇒玉琢かざれば器を成さず
⇒玉磨かざれば光なし
⇒玉を懐いて罪あり
⇒玉を転がす
たま【適・偶】
まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」
たま【魂・魄・霊】
(「たま(玉)」と同源か)たましい。
⇒魂合う
たま【攩網】
(→)「たもあみ」に同じ。
た‐ま【手間】
手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」
たま【多摩】
①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。
②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。
だま
だますこと。だまかし。
⇒だまを食わす
だま
小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。
だま
凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」
⇒だまを出す
⇒だまをやる
⇒た‐ほう【多宝】
たほう‐にょらい【多宝如来】
[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。
⇒た‐ほう【多宝】
た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥
多くの方面・分野。「―に活躍する」
たぼ‐がみ【髱髪】
(→)「たぼ」に同じ。
だ‐ぼく【打撲】
体をうちたたくこと。「全身―」
⇒だぼく‐しょう【打撲傷】
だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ
物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。
⇒だ‐ぼく【打撲】
たぼ‐さし【髱差・髱刺】
髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」
だぼ‐シャツ
てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。
たぼ‐しん【髱心】
髱を張り出すために、髪に添える心。
だ‐ぼそ【太枘・駄枘】
⇒だぼ
だぼ‐だぼ
①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」
②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」
③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」
た‐ほどき【田解き】
田の土を細かに耕すこと。
たぼ‐どめ【髱留】
(→)「つとばさみ」に同じ。
だぼ‐はぜ【だぼ鯊】
①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。
②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。
たぼ‐みの【髱蓑】
蓑状に作った毛の髱差たぼさし。
だ‐ぼら【駄法螺】
つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」
た‐ぼん【他犯】
姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」
だ‐ほん【駄本】
役に立たない書物。価値のない本。
たま【玉・珠・球】
①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」
②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」
③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」
④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」
㋐まり。ボール。「―ひろい」
㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」
㋒電球。「―が切れる」
㋓卵。
㋔露・涙などの一しずく。
㋕そろばんの、動かす部分。
㋖レンズ。「眼鏡の―」
㋗きんたま。
⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」
⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。
⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」
⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」
◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。
⇒玉散る
⇒玉とあざむく
⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ
⇒玉なす
⇒玉に瑕
⇒玉琢かざれば器を成さず
⇒玉磨かざれば光なし
⇒玉を懐いて罪あり
⇒玉を転がす
たま【適・偶】
まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」
たま【魂・魄・霊】
(「たま(玉)」と同源か)たましい。
⇒魂合う
たま【攩網】
(→)「たもあみ」に同じ。
た‐ま【手間】
手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」
たま【多摩】
①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。
②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。
だま
だますこと。だまかし。
⇒だまを食わす
だま
小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。
だま
凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」
⇒だまを出す
⇒だまをやる
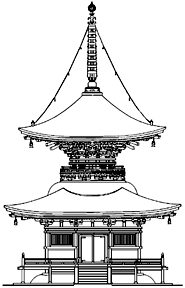 ⇒た‐ほう【多宝】
たほう‐にょらい【多宝如来】
[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。
⇒た‐ほう【多宝】
た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥
多くの方面・分野。「―に活躍する」
たぼ‐がみ【髱髪】
(→)「たぼ」に同じ。
だ‐ぼく【打撲】
体をうちたたくこと。「全身―」
⇒だぼく‐しょう【打撲傷】
だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ
物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。
⇒だ‐ぼく【打撲】
たぼ‐さし【髱差・髱刺】
髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」
だぼ‐シャツ
てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。
たぼ‐しん【髱心】
髱を張り出すために、髪に添える心。
だ‐ぼそ【太枘・駄枘】
⇒だぼ
だぼ‐だぼ
①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」
②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」
③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」
た‐ほどき【田解き】
田の土を細かに耕すこと。
たぼ‐どめ【髱留】
(→)「つとばさみ」に同じ。
だぼ‐はぜ【だぼ鯊】
①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。
②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。
たぼ‐みの【髱蓑】
蓑状に作った毛の髱差たぼさし。
だ‐ぼら【駄法螺】
つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」
た‐ぼん【他犯】
姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」
だ‐ほん【駄本】
役に立たない書物。価値のない本。
たま【玉・珠・球】
①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」
②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」
③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」
④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」
㋐まり。ボール。「―ひろい」
㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」
㋒電球。「―が切れる」
㋓卵。
㋔露・涙などの一しずく。
㋕そろばんの、動かす部分。
㋖レンズ。「眼鏡の―」
㋗きんたま。
⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」
⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。
⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」
⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」
◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。
⇒玉散る
⇒玉とあざむく
⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ
⇒玉なす
⇒玉に瑕
⇒玉琢かざれば器を成さず
⇒玉磨かざれば光なし
⇒玉を懐いて罪あり
⇒玉を転がす
たま【適・偶】
まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」
たま【魂・魄・霊】
(「たま(玉)」と同源か)たましい。
⇒魂合う
たま【攩網】
(→)「たもあみ」に同じ。
た‐ま【手間】
手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」
たま【多摩】
①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。
②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。
だま
だますこと。だまかし。
⇒だまを食わす
だま
小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。
だま
凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」
⇒だまを出す
⇒だまをやる
⇒た‐ほう【多宝】
たほう‐にょらい【多宝如来】
[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。
⇒た‐ほう【多宝】
た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥
多くの方面・分野。「―に活躍する」
たぼ‐がみ【髱髪】
(→)「たぼ」に同じ。
だ‐ぼく【打撲】
体をうちたたくこと。「全身―」
⇒だぼく‐しょう【打撲傷】
だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ
物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。
⇒だ‐ぼく【打撲】
たぼ‐さし【髱差・髱刺】
髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」
だぼ‐シャツ
てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。
たぼ‐しん【髱心】
髱を張り出すために、髪に添える心。
だ‐ぼそ【太枘・駄枘】
⇒だぼ
だぼ‐だぼ
①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」
②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」
③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」
た‐ほどき【田解き】
田の土を細かに耕すこと。
たぼ‐どめ【髱留】
(→)「つとばさみ」に同じ。
だぼ‐はぜ【だぼ鯊】
①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。
②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。
たぼ‐みの【髱蓑】
蓑状に作った毛の髱差たぼさし。
だ‐ぼら【駄法螺】
つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」
た‐ぼん【他犯】
姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」
だ‐ほん【駄本】
役に立たない書物。価値のない本。
たま【玉・珠・球】
①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」
②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」
③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」
④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」
㋐まり。ボール。「―ひろい」
㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」
㋒電球。「―が切れる」
㋓卵。
㋔露・涙などの一しずく。
㋕そろばんの、動かす部分。
㋖レンズ。「眼鏡の―」
㋗きんたま。
⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」
⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。
⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」
⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」
◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。
⇒玉散る
⇒玉とあざむく
⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ
⇒玉なす
⇒玉に瑕
⇒玉琢かざれば器を成さず
⇒玉磨かざれば光なし
⇒玉を懐いて罪あり
⇒玉を転がす
たま【適・偶】
まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」
たま【魂・魄・霊】
(「たま(玉)」と同源か)たましい。
⇒魂合う
たま【攩網】
(→)「たもあみ」に同じ。
た‐ま【手間】
手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」
たま【多摩】
①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。
②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。
だま
だますこと。だまかし。
⇒だまを食わす
だま
小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。
だま
凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」
⇒だまを出す
⇒だまをやる
広辞苑 ページ 12327 での【○食べ物の恨みは恐ろしい】単語。