複数辞典一括検索+![]()
![]()
○東男に京女あずまおとこにきょうおんな🔗⭐🔉
○東男に京女あずまおとこにきょうおんな
男は、気っぷのよい江戸の男がよく、女は、優雅で美しい京都の女がよいということ。また、そのような組合せ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐おどり【東をどり】アヅマヲドリ
東京新橋の芸妓組合が毎年春に新橋演舞場で催す舞踊公演。1925年(大正14)創始。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐おのこ【東男】アヅマヲノコ
(→)「あずまおとこ」に同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐おみな【東女】アヅマヲミナ
東国の女。あずまめ。万葉集4「―を忘れ給ふな」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐おり【東折り】アヅマヲリ
(→)「あずまからげ」に同じ。平家物語8「或は布の小袖に―し」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまかがみ【吾妻鏡・東鑑】アヅマ‥
鎌倉後期成立の史書。52巻。鎌倉幕府の事跡を変体漢文で日記体に編述。源頼政の挙兵(1180年)から前将軍宗尊親王の帰京(1266年)に至る87年間の重要史料。
→文献資料[吾妻鏡]
⇒あずまかがみ‐たい【吾妻鑑体】
あずまかがみ‐たい【吾妻鑑体】アヅマ‥
(「吾妻鑑」に代表されることから)変体漢文のこと。正規の漢文にはない日本的な用字法や語順が用いられる。
⇒あずまかがみ【吾妻鏡・東鑑】
あずま‐からげ【東絡げ】アヅマ‥
着物の裾をからげて帯にはさむこと。あずまおり。あずまばしょり。謡曲、融とおる「―の潮衣」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐がらす【東烏】アヅマ‥
(関西の人が東国方言をあざけり、烏までも奇妙な鳴き方をするという意でできた語)奇妙な鳴き方をする東国の烏。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐かり【東雁】アヅマ‥
東国の、濁った声で鳴く雁。東国人の発音にたとえる。今昔物語集28「―の鳴きあひたるやうにて」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐がろう【東家老】アヅマ‥ラウ
西国大名の江戸詰の家老。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐かん【東艦】アヅマ‥
1867年(慶応3)江戸幕府がアメリカから買い入れたフランス製軍艦。翌年横浜に回航されたが、戊辰戦争後、新政府に引き渡された。原名ストーン‐ウォール。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ぎく【東菊】アヅマ‥
①キク科の多年草。山地の草原に生え、高さ約20センチメートル。葉はへら状。茎葉ともに毛が多い。4〜5月頃、茎頂に1輪の頭花を開く。周囲の舌状花は桃色で糸状、中央の管状花は黄色。〈[季]春〉
②ノシュンギクの別称。
③エゾギクの別称。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐くだり【東下り】アヅマ‥
京都から東国地方、特に鎌倉に下くだること。海道下り。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐げた【東下駄】アヅマ‥
畳表をつけた、薄歯の女性用の下駄。浅い爪掛つまがけをかけて用いる。尾崎紅葉、三人妻「我下駄の見えざれば、小〆こしめの―を突懸け」
東下駄
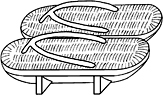 ⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごえ【東声】アヅマゴヱ
東国風の発音。東訛あずまなまり。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐コート【東コート】アヅマ‥
被布ひふより長く裾まである女性の和装用コート。主に羅紗・セルで作る。明治中期より流行。徳田秋声、惰けもの「糸織に一つ紋の黒縮緬の羽織、吾妻あづまコートを乱次だらしなく着て」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごと【東琴】アヅマ‥
和琴わごんの別称。源氏物語手習「―をこそは事もなく弾き侍りしかど」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐じ【東路】アヅマヂ
京都から東国へ至る道。すなわち東海道・東山道などを指す。転じて、東国の意。万葉集14「―の手児てこのよび坂越えがねて」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまし・い
〔形〕
(津軽地方・北海道で)気持がよい。満足だ。
あずまじし【吾妻獅子・東獅子】アヅマ‥
地歌。手事物。峰崎勾当作曲。在原業平を気取った東下りの男が、吉原の遊女との後朝きぬぎぬの別れを惜しんで舞を舞うさまを描く。箏の手付は多種ある。
あずま‐じょうるり【吾妻浄瑠璃】アヅマジヤウ‥
元禄(1688〜1704)頃、上方で行われた江戸浄瑠璃。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐そだち【東育ち】アヅマ‥
江戸で育ったこと。それを誇りにしていう語。梅暦「品やさしきはおのづから―の隅田川」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐っ‐こ【東っ子】アヅマ‥
江戸っ子。江戸の人の自称する語。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐つづれ【東綴れ】アヅマ‥
明治末、栃木県足利市で織り出した女物の帯地。綴錦風に文様を織り出した織物。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ど【東人】アヅマ‥
(アズマウドの約)東国の人。あずまびと。万葉集2「―の荷前のさきの箱の荷の緒にも」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐なまり【東訛】アヅマ‥
東国のなまり。東声あずまごえ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐にしきえ【吾妻錦絵・東錦絵】アヅマ‥ヱ
多色摺りの木版の浮世絵。江戸の名物で、鈴木春信がはじめて売り出した当初から、この名を用いた。錦絵。江戸絵。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ねざさ【東根笹】アヅマ‥
野生のササの一種。関東地方に普通で、いわゆる篠竹しのだけ。地下茎は横に這い、地上茎は直立して強靱、高さ1メートル内外。常緑で、葉は堅く暗緑色。花序は細長くて約15センチメートル、小花を密集し緑色で穂となる。アズマシノ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ばし【吾妻橋】アヅマ‥
東京都台東区浅草と墨田区吾妻橋を結ぶ隅田川の橋。1774年(安永3)初めて架橋。現在の橋は1931年竣工。
あずま‐ばしょり【東端折り】アヅマ‥
(→)「あずまからげ」に同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐はっけい【吾妻八景】アヅマ‥
長唄。1829年(文政12)4世杵屋六三郎作曲(一説に作詞も)。江戸名所をよみ入れた歌詞。長唄を歌舞伎から独立して聴かせる新しい試みとして作られた名曲。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐びと【東人】アヅマ‥
東国の人。あずまうど。源氏物語宿木「―どもにも食はせ」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ひゃっかん【東百官】アヅマヒヤククワン
①室町末期から、関東武士が京都朝廷の官名に擬して用いた私称。伊織・多門・左膳・頼母・求馬・左内・兵馬の類。
②江戸時代に行われた子供の手習い本で、1の名などを集めたもの。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐まい【東舞】アヅママヒ
(→)東遊あずまあそびに同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐むすび【東結び・吾妻結び】アヅマ‥
紐の結び方。輪を左右に出し、中を三巻きにしたもの。几帳きちょう・守り袋・簾すだれの紐などを結ぶのに用いる。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐め【東女】アヅマ‥
東国の女。あずまおみな。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまもんどう【吾妻問答】アヅマ‥ダフ
室町時代の連歌書。1巻。宗祇著。1470年(文明2)自跋。別名、角田川すみだがわ。連歌の代表作家・作法などを問答体に述べる。
あずま‐や【四阿・東屋・阿舎】アヅマ‥
(東国風のひなびた家の意)
①四方へ檐のきを葺きおろした家屋。寄棟よせむねあるいは入母屋いりもや造。正倉院文書「草葺―一間」
②四方の柱だけで、壁がなく、屋根を四方に葺きおろした小屋。庭園などの休息所とする。亭ちん。国木田独歩、夫婦「庭へ出て吾妻屋あずまやに行つて見たが」
③催馬楽さいばらの曲名。
④源氏物語の巻名。宇治十帖の一つ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐やき【吾妻焼】アヅマ‥
旭焼あさひやきの旧称。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまや‐さん【四阿山】アヅマ‥
長野県北東部、群馬県との境にある山。標高2354メートル。西に根子岳ねこだけ、西麓に菅平高原が広がる。吾妻あがつま山。
四阿山
提供:オフィス史朗
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごえ【東声】アヅマゴヱ
東国風の発音。東訛あずまなまり。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐コート【東コート】アヅマ‥
被布ひふより長く裾まである女性の和装用コート。主に羅紗・セルで作る。明治中期より流行。徳田秋声、惰けもの「糸織に一つ紋の黒縮緬の羽織、吾妻あづまコートを乱次だらしなく着て」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごと【東琴】アヅマ‥
和琴わごんの別称。源氏物語手習「―をこそは事もなく弾き侍りしかど」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐じ【東路】アヅマヂ
京都から東国へ至る道。すなわち東海道・東山道などを指す。転じて、東国の意。万葉集14「―の手児てこのよび坂越えがねて」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまし・い
〔形〕
(津軽地方・北海道で)気持がよい。満足だ。
あずまじし【吾妻獅子・東獅子】アヅマ‥
地歌。手事物。峰崎勾当作曲。在原業平を気取った東下りの男が、吉原の遊女との後朝きぬぎぬの別れを惜しんで舞を舞うさまを描く。箏の手付は多種ある。
あずま‐じょうるり【吾妻浄瑠璃】アヅマジヤウ‥
元禄(1688〜1704)頃、上方で行われた江戸浄瑠璃。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐そだち【東育ち】アヅマ‥
江戸で育ったこと。それを誇りにしていう語。梅暦「品やさしきはおのづから―の隅田川」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐っ‐こ【東っ子】アヅマ‥
江戸っ子。江戸の人の自称する語。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐つづれ【東綴れ】アヅマ‥
明治末、栃木県足利市で織り出した女物の帯地。綴錦風に文様を織り出した織物。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ど【東人】アヅマ‥
(アズマウドの約)東国の人。あずまびと。万葉集2「―の荷前のさきの箱の荷の緒にも」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐なまり【東訛】アヅマ‥
東国のなまり。東声あずまごえ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐にしきえ【吾妻錦絵・東錦絵】アヅマ‥ヱ
多色摺りの木版の浮世絵。江戸の名物で、鈴木春信がはじめて売り出した当初から、この名を用いた。錦絵。江戸絵。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ねざさ【東根笹】アヅマ‥
野生のササの一種。関東地方に普通で、いわゆる篠竹しのだけ。地下茎は横に這い、地上茎は直立して強靱、高さ1メートル内外。常緑で、葉は堅く暗緑色。花序は細長くて約15センチメートル、小花を密集し緑色で穂となる。アズマシノ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ばし【吾妻橋】アヅマ‥
東京都台東区浅草と墨田区吾妻橋を結ぶ隅田川の橋。1774年(安永3)初めて架橋。現在の橋は1931年竣工。
あずま‐ばしょり【東端折り】アヅマ‥
(→)「あずまからげ」に同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐はっけい【吾妻八景】アヅマ‥
長唄。1829年(文政12)4世杵屋六三郎作曲(一説に作詞も)。江戸名所をよみ入れた歌詞。長唄を歌舞伎から独立して聴かせる新しい試みとして作られた名曲。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐びと【東人】アヅマ‥
東国の人。あずまうど。源氏物語宿木「―どもにも食はせ」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ひゃっかん【東百官】アヅマヒヤククワン
①室町末期から、関東武士が京都朝廷の官名に擬して用いた私称。伊織・多門・左膳・頼母・求馬・左内・兵馬の類。
②江戸時代に行われた子供の手習い本で、1の名などを集めたもの。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐まい【東舞】アヅママヒ
(→)東遊あずまあそびに同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐むすび【東結び・吾妻結び】アヅマ‥
紐の結び方。輪を左右に出し、中を三巻きにしたもの。几帳きちょう・守り袋・簾すだれの紐などを結ぶのに用いる。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐め【東女】アヅマ‥
東国の女。あずまおみな。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまもんどう【吾妻問答】アヅマ‥ダフ
室町時代の連歌書。1巻。宗祇著。1470年(文明2)自跋。別名、角田川すみだがわ。連歌の代表作家・作法などを問答体に述べる。
あずま‐や【四阿・東屋・阿舎】アヅマ‥
(東国風のひなびた家の意)
①四方へ檐のきを葺きおろした家屋。寄棟よせむねあるいは入母屋いりもや造。正倉院文書「草葺―一間」
②四方の柱だけで、壁がなく、屋根を四方に葺きおろした小屋。庭園などの休息所とする。亭ちん。国木田独歩、夫婦「庭へ出て吾妻屋あずまやに行つて見たが」
③催馬楽さいばらの曲名。
④源氏物語の巻名。宇治十帖の一つ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐やき【吾妻焼】アヅマ‥
旭焼あさひやきの旧称。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまや‐さん【四阿山】アヅマ‥
長野県北東部、群馬県との境にある山。標高2354メートル。西に根子岳ねこだけ、西麓に菅平高原が広がる。吾妻あがつま山。
四阿山
提供:オフィス史朗
 あずま‐やま【吾妻山】アヅマ‥
福島市の西方、福島・山形の県境をなす火山群。最高峰は西吾妻山で、標高2035メートル。磐梯朝日国立公園に属する。
吾妻山(吾妻小富士と浄土平)
撮影:佐藤 尚
あずま‐やま【吾妻山】アヅマ‥
福島市の西方、福島・山形の県境をなす火山群。最高峰は西吾妻山で、標高2035メートル。磐梯朝日国立公園に属する。
吾妻山(吾妻小富士と浄土平)
撮影:佐藤 尚
 あずま‐よじべえ【吾妻与次兵衛】アヅマ‥ヱ
浄瑠璃・歌舞伎の男女の登場人物および二人を主人公とする作品群の通称。江戸初期の歌謡にその情話をうたわれた大坂新町の遊女藤屋吾妻と山崎浄閑の息子与次兵衛。近松門左衛門作「寿門松ねびきのかどまつ」や「双蝶蝶曲輪日記ふたつちょうちょうくるわにっき」などで有名。
アスマラ【Asmara】
アフリカ北東部、エリトリア国の首都。イタリア風の街並で知られる。人口35万8千(1990)。
あずま‐わらわ【東孺・東豎子】アヅマワラハ
内侍司ないしのつかさの女官。行幸の時、騎馬で供奉ぐぶした。一腹三子みつごの小童を使用。姫松。姫大夫ひめもうちぎみ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずみ【阿曇】アヅミ
姓氏の一つ。
⇒あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】
あずみ‐の【安曇野】アヅミ‥
①長野県中部、松本盆地の北半部、梓川あずさがわ以北の通称。稲作、リンゴ・わさび栽培などで知られる。安曇平。
安曇野の山葵田
撮影:佐藤 尚
あずま‐よじべえ【吾妻与次兵衛】アヅマ‥ヱ
浄瑠璃・歌舞伎の男女の登場人物および二人を主人公とする作品群の通称。江戸初期の歌謡にその情話をうたわれた大坂新町の遊女藤屋吾妻と山崎浄閑の息子与次兵衛。近松門左衛門作「寿門松ねびきのかどまつ」や「双蝶蝶曲輪日記ふたつちょうちょうくるわにっき」などで有名。
アスマラ【Asmara】
アフリカ北東部、エリトリア国の首都。イタリア風の街並で知られる。人口35万8千(1990)。
あずま‐わらわ【東孺・東豎子】アヅマワラハ
内侍司ないしのつかさの女官。行幸の時、騎馬で供奉ぐぶした。一腹三子みつごの小童を使用。姫松。姫大夫ひめもうちぎみ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずみ【阿曇】アヅミ
姓氏の一つ。
⇒あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】
あずみ‐の【安曇野】アヅミ‥
①長野県中部、松本盆地の北半部、梓川あずさがわ以北の通称。稲作、リンゴ・わさび栽培などで知られる。安曇平。
安曇野の山葵田
撮影:佐藤 尚
 ②⇒あづみの
あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】アヅミ‥
古代の武人。662年、新羅しらぎと唐とに攻められた百済くだらを救うために水軍を率いて出征、翌年白村江で唐軍に敗北、軍を収めて帰国。
⇒あずみ【阿曇】
アスモデ【Asmodée フランス】
ユダヤ教伝承中の悪魔。旧約聖書外典トビト書を始め、スペインの劇作家ゲバラ(Luis Vélez de Guevara1579〜1644)の「びっこの悪魔」、これを模倣したルサージュの悪漢小説、モーリアックの戯曲などに登場。
あすら【阿修羅】
⇒あしゅら
アスリート【athlete】
運動選手。特に、陸上競技の選手。
アスレチック‐クラブ【athletic club】
各種の運動器具・施設を備え、美容・健康のための運動を行う有料会員制のクラブ。
アスレチックス【athletics】
運動競技。特に、陸上競技。
アズレン【azulene】
分子式C10H8 二つの六員環が縮合したナフタレンの異性体で、五員環と七員環が縮合した構造を持つ。カミルレなどの植物精油を脱水して得られる。深青色板状結晶。抗炎剤として多くの薬剤や化粧品類に用いられる。
アスロック【ASROC】
(anti-submarine rocket)対潜水艦ミサイルの一種。ロケットの先端にホーミング魚雷を装備し、艦艇から発射して潜水艦を攻撃する兵器。
アスワン‐ダム【Aswan Dam】
エジプト、ナイル川の中流にあるダム。1902年完成、貯水容量55億トン、灌漑・発電に利用。その上流に貯水容量1570億トンのアスワン‐ハイ‐ダムが71年完成。
ナセル湖
撮影:小松義夫
②⇒あづみの
あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】アヅミ‥
古代の武人。662年、新羅しらぎと唐とに攻められた百済くだらを救うために水軍を率いて出征、翌年白村江で唐軍に敗北、軍を収めて帰国。
⇒あずみ【阿曇】
アスモデ【Asmodée フランス】
ユダヤ教伝承中の悪魔。旧約聖書外典トビト書を始め、スペインの劇作家ゲバラ(Luis Vélez de Guevara1579〜1644)の「びっこの悪魔」、これを模倣したルサージュの悪漢小説、モーリアックの戯曲などに登場。
あすら【阿修羅】
⇒あしゅら
アスリート【athlete】
運動選手。特に、陸上競技の選手。
アスレチック‐クラブ【athletic club】
各種の運動器具・施設を備え、美容・健康のための運動を行う有料会員制のクラブ。
アスレチックス【athletics】
運動競技。特に、陸上競技。
アズレン【azulene】
分子式C10H8 二つの六員環が縮合したナフタレンの異性体で、五員環と七員環が縮合した構造を持つ。カミルレなどの植物精油を脱水して得られる。深青色板状結晶。抗炎剤として多くの薬剤や化粧品類に用いられる。
アスロック【ASROC】
(anti-submarine rocket)対潜水艦ミサイルの一種。ロケットの先端にホーミング魚雷を装備し、艦艇から発射して潜水艦を攻撃する兵器。
アスワン‐ダム【Aswan Dam】
エジプト、ナイル川の中流にあるダム。1902年完成、貯水容量55億トン、灌漑・発電に利用。その上流に貯水容量1570億トンのアスワン‐ハイ‐ダムが71年完成。
ナセル湖
撮影:小松義夫
 アスンシオン【Asunción】
(聖母被昇天の意)南米、パラグアイ共和国の首都。パラグアイ川に臨む。17世紀までラプラタ川流域の最も重要な港であった。人口51万3千(2002)。
あせ【汗】
①温度刺激により汗腺から排出される分泌液。塩類・ピルビン酸・乳酸・アンモニアなどを含む。気温の高い時、激しい運動をした時などに体温調節の作用をするほか、痛覚・精神的緊張によっても出る。〈[季]夏〉。万葉集9「熱けくに―かきなげ」。「―をかく」→汗腺。
②物の表面に生じる湿滴。「壁が―をかく」「乾物が―をかく」
③(斎宮の忌詞・女房詞)血。
⇒汗になる
⇒汗を入れる
⇒汗をかく
⇒汗を流す
⇒汗を握る
⇒汗を揉む
あ‐せ【吾兄】
男子を親しんで呼ぶ語。歌のはやし言葉などに用いた。古事記中「一つ松―を」
あぜ【畦・畔】
①田と田との間に土を盛り上げて境としたもの。くろ。〈倭名類聚鈔1〉
②敷居または鴨居のみぞとみぞとの間にある仕切り。→樋端ひばた2
あぜ【綜】
機はたの経糸たていとを上下に分け、緯糸よこいとを通す隙間を作る用具。綜絖そうこう。
あぜ【何】
〔副〕
(上代東国方言)
①なぜ。どうして。万葉集14「わがせなは―そも今宵寄しろ来まさぬ」
②どのように。いかに。万葉集14「―せろと心にのりてここば悲しけ」
あせ‐あぶら【汗膏】
汗と膏。辛苦を重ねることのたとえにいう。
アセアン【ASEAN】
(Association of South-East Asian Nations)東南アジア諸国連合。1967年にインドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン・マレーシアの5カ国で結成した地域協力機構。84年ブルネイ、95年ベトナム、97年ラオス・ミャンマー、99年カンボジアが加盟。決定機関である外相会議の下にジャカルタに常設の事務局を置く。
あ‐せい【亜聖】
聖人につぐ賢人。一般に、孔子を聖人とするのに対し、孟子または顔回をいう。
あぜ‐いと【綜糸】
あぜで経糸たていとを上下に分ける糸。
あぜ‐おり【畦織・畔織】
経糸たていとまたは緯糸よこいとのどちらか一方の糸が他の糸数本を跨いで平組織にし、経か緯の方向に畦(畔)が現れるようにした織物。緯に太い畦のあるのを経畦織、経に畦のあるのを緯畦織という。うねおり。
あせ‐かき【汗掻き】
汗をかきやすい人。あせっかき。
あぜ‐がやつり【畦蚊屋吊・畦莎草】
カヤツリグサ科の一年草。湿地や田の畦に多い雑草。茎は高さ約30センチメートル。三稜形で細く硬い。葉は細長く、基部は鞘状となって茎を囲む。夏、穂状の淡黄褐色の花を開く。ホソバガヤツリ。
あぜ‐き【校木】
〔建〕校倉あぜくらを組む材木。
あせ‐くさ・い【汗臭い】
〔形〕
汗のいやな臭いがする。
あせ‐ぐ・む【汗ぐむ】
〔自四〕
汗がにじみ出る。汗ばむ。古今著聞集10「寒げに見えけるが、御馬の数つかうまつりければ、―・みにけり」
あぜ‐くら【校倉】
部材を横に組んで壁を作った倉。部材の断面は三角・四角・円など。甲倉。叉倉。あぜり。→井楼せいろう組。
校倉
アスンシオン【Asunción】
(聖母被昇天の意)南米、パラグアイ共和国の首都。パラグアイ川に臨む。17世紀までラプラタ川流域の最も重要な港であった。人口51万3千(2002)。
あせ【汗】
①温度刺激により汗腺から排出される分泌液。塩類・ピルビン酸・乳酸・アンモニアなどを含む。気温の高い時、激しい運動をした時などに体温調節の作用をするほか、痛覚・精神的緊張によっても出る。〈[季]夏〉。万葉集9「熱けくに―かきなげ」。「―をかく」→汗腺。
②物の表面に生じる湿滴。「壁が―をかく」「乾物が―をかく」
③(斎宮の忌詞・女房詞)血。
⇒汗になる
⇒汗を入れる
⇒汗をかく
⇒汗を流す
⇒汗を握る
⇒汗を揉む
あ‐せ【吾兄】
男子を親しんで呼ぶ語。歌のはやし言葉などに用いた。古事記中「一つ松―を」
あぜ【畦・畔】
①田と田との間に土を盛り上げて境としたもの。くろ。〈倭名類聚鈔1〉
②敷居または鴨居のみぞとみぞとの間にある仕切り。→樋端ひばた2
あぜ【綜】
機はたの経糸たていとを上下に分け、緯糸よこいとを通す隙間を作る用具。綜絖そうこう。
あぜ【何】
〔副〕
(上代東国方言)
①なぜ。どうして。万葉集14「わがせなは―そも今宵寄しろ来まさぬ」
②どのように。いかに。万葉集14「―せろと心にのりてここば悲しけ」
あせ‐あぶら【汗膏】
汗と膏。辛苦を重ねることのたとえにいう。
アセアン【ASEAN】
(Association of South-East Asian Nations)東南アジア諸国連合。1967年にインドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン・マレーシアの5カ国で結成した地域協力機構。84年ブルネイ、95年ベトナム、97年ラオス・ミャンマー、99年カンボジアが加盟。決定機関である外相会議の下にジャカルタに常設の事務局を置く。
あ‐せい【亜聖】
聖人につぐ賢人。一般に、孔子を聖人とするのに対し、孟子または顔回をいう。
あぜ‐いと【綜糸】
あぜで経糸たていとを上下に分ける糸。
あぜ‐おり【畦織・畔織】
経糸たていとまたは緯糸よこいとのどちらか一方の糸が他の糸数本を跨いで平組織にし、経か緯の方向に畦(畔)が現れるようにした織物。緯に太い畦のあるのを経畦織、経に畦のあるのを緯畦織という。うねおり。
あせ‐かき【汗掻き】
汗をかきやすい人。あせっかき。
あぜ‐がやつり【畦蚊屋吊・畦莎草】
カヤツリグサ科の一年草。湿地や田の畦に多い雑草。茎は高さ約30センチメートル。三稜形で細く硬い。葉は細長く、基部は鞘状となって茎を囲む。夏、穂状の淡黄褐色の花を開く。ホソバガヤツリ。
あぜ‐き【校木】
〔建〕校倉あぜくらを組む材木。
あせ‐くさ・い【汗臭い】
〔形〕
汗のいやな臭いがする。
あせ‐ぐ・む【汗ぐむ】
〔自四〕
汗がにじみ出る。汗ばむ。古今著聞集10「寒げに見えけるが、御馬の数つかうまつりければ、―・みにけり」
あぜ‐くら【校倉】
部材を横に組んで壁を作った倉。部材の断面は三角・四角・円など。甲倉。叉倉。あぜり。→井楼せいろう組。
校倉
 ⇒あぜくら‐づくり【校倉造】
あぜくら‐づくり【校倉造】
校倉風の建築様式。古代に多い。正倉院のほか、東大寺・唐招提寺・東寺などに遺構が存する。
⇒あぜ‐くら【校倉】
あぜこし‐たうえ【畦越し田植】‥ウヱ
休まないで続けて隣の田を植えること。凶事があるとして忌む。
あせ‐しずく【汗雫】‥シヅク
雫のようにしたたる汗。
あせ‐ジバン【汗襦袢】
和服の下に着る汗取りの肌着。あせじゅばん。あせとり。
あせ‐じ・みる【汗染みる】
〔自上一〕
衣服などに汗がしみ出てよごれる。
あせ‐しらず【汗知らず】
汗を吸収し皮膚を乾燥させて爽やかにするもの。天瓜粉てんかふん・シッカロールの類。〈[季]夏〉
アセス
アセスメントの略。
アセスメント【assessment】
①評価。査定。見積り。
②⇒かんきょうアセスメント
あせ・する【汗する】
〔自サ変〕[文]あせ・す(サ変)
汗をかく。多く精を出してするのにいう。「額ひたいに―・して働く」
アセスルファム‐カリウム
(acesulfame potassium)人工甘味料の一つ。分子式C4H4KNO4S 白色の結晶。蔗糖の200〜250倍の甘味をもつ。略称、アセスルファムK。
アセタール‐じゅし【アセタール樹脂】
(acetal resin)ポリアセタールの工業上の呼称。
あせ‐だく【汗だく】
(「汗だくだく」の略)汗をびっしょりかいているさま。
あぜ‐たけ【綜竹】
(→)綾竹あやだけ1に同じ。
あぜち【按察使・按察】
(アンセチシの約)奈良時代、諸国の行政を監察した官。719年(養老3)創設。特定の国司の兼任。後には陸奥・出羽だけ実態を残し、他は大中納言の兼ねる名義だけの官となる。→摂官2
あ‐ぜち【庵室】
(アンジチの転)江戸時代、奈良での手習所の別称。手習所を寺と呼ぶことがあったが、奈良で単に寺といえば興福寺をさしたのでこの別称が生まれた。
あぜ‐ち【畔内】
(北陸地方や岐阜県で)分家。あじち。
アセチル‐き【アセチル基】
(acetyl group)酢酸から水酸基を除いた原子団。化学式CH3CO‐
アセチルグルコサミン【acetylglucosamine】
「グルコサミン」参照。
アセチルコリン【acetylcholine】
神経組織に多く含まれる塩基性物質。副交感神経と運動神経の神経末端から刺激に応じて分泌され、神経の伝達にたずさわる。麦角に含まれる。
アセチルサリチル‐さん【アセチルサリチル酸】
(acetylsalicylic acid)分子式C6H4(OCOCH3)COOH 白色の結晶。サリチル酸と無水酢酸との反応により製する。鎮痛解熱作用や抗リウマチ作用があり、アスピリンの名で医薬として用いる。
アセチルセルロース【acetylcellulose】
セルロースの酢酸エステル。綿に無水酢酸・濃硫酸を加えて作る。人造絹糸・不燃性フィルム・プラスチックなどに使用。酢酸繊維素。酢酸セルロース。
アセチレン【acetylene】
分子式HC≡CH 炭化水素の一つ。無色の有毒性の気体。光輝の強い炎で燃える。かつては灯用とした。酸素と混じて鉄の切断や溶接に利用。有機合成基礎原料。カーバイドに水を作用させたり、天然ガス・石油を高温で熱分解したりしてつくる。エチン。
⇒アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】
⇒アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
⇒アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】‥クワ‥
三重結合を一つもつ不飽和鎖式炭化水素の総称。一般式CnH2n−2で表される。アルキンともいう。n=2がアセチレン、n=3がメチルアセチレンである。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
酸素とアセチレンで得られるセ氏約3000度の高温の炎による金属の溶接・切断。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンを燃料としたランプ。電気が使えない大道芸人などが使った。
⇒アセチレン【acetylene】
アセテート‐レーヨン【acetate rayon】
アセチルセルロースを原料とした人絹。丈夫で色つや・手ざわりがよく吸湿性は小さい。アセテート人絹。
アセトアニリド【acetanilide】
分子式C6H5NHCOCH3 アニリンのアミノ基(NH2‐)の水素1原子をアセチル基(CH3CO‐)で置換したもの。アニリンと無水酢酸とを加熱して製する。無色の板状結晶。医薬・染料などの重要な合成原料。アンチフェブリンの名で知られる最初の合成解熱剤であるが、毒性が強いため現在は使用が禁止されている。
アセトアミノフェン【acetaminophen】
解熱鎮痛剤の一つ。分子式C8H9NO2 オルト・メタ・パラの三つの異性体があるが、解熱鎮痛剤として用いられるのは、パラ体のパラアセタミドフェノール。
アセトアルデヒド【acetaldehyde】
分子式CH3CHO 無色の刺激臭ある可燃性液体。エチレンの直接酸化によって製する。有機合成の原料として重要。エタノールの酸化でも生成し、二日酔の原因。エタナール。
あせ‐どの【汗殿】
(汗は血の忌詞)伊勢の斎宮が月経時にこもった御殿。
あせ‐とり【汗取り】
直接肌につけて汗を吸い取らせる肌着。〈[季]夏〉
アセトン【acetone】
分子式CH3COCH3 ケトンの代表的なもの。無色の液体。アセチレン・プロピレンを原料として製造。溶剤として広く用いるほか、アセテート繊維・メタクリル樹脂・医薬品の原料。
あせ‐ながし【汗流し】
兜かぶとの頬当ほおあての下底にあけた穴。
⇒あぜくら‐づくり【校倉造】
あぜくら‐づくり【校倉造】
校倉風の建築様式。古代に多い。正倉院のほか、東大寺・唐招提寺・東寺などに遺構が存する。
⇒あぜ‐くら【校倉】
あぜこし‐たうえ【畦越し田植】‥ウヱ
休まないで続けて隣の田を植えること。凶事があるとして忌む。
あせ‐しずく【汗雫】‥シヅク
雫のようにしたたる汗。
あせ‐ジバン【汗襦袢】
和服の下に着る汗取りの肌着。あせじゅばん。あせとり。
あせ‐じ・みる【汗染みる】
〔自上一〕
衣服などに汗がしみ出てよごれる。
あせ‐しらず【汗知らず】
汗を吸収し皮膚を乾燥させて爽やかにするもの。天瓜粉てんかふん・シッカロールの類。〈[季]夏〉
アセス
アセスメントの略。
アセスメント【assessment】
①評価。査定。見積り。
②⇒かんきょうアセスメント
あせ・する【汗する】
〔自サ変〕[文]あせ・す(サ変)
汗をかく。多く精を出してするのにいう。「額ひたいに―・して働く」
アセスルファム‐カリウム
(acesulfame potassium)人工甘味料の一つ。分子式C4H4KNO4S 白色の結晶。蔗糖の200〜250倍の甘味をもつ。略称、アセスルファムK。
アセタール‐じゅし【アセタール樹脂】
(acetal resin)ポリアセタールの工業上の呼称。
あせ‐だく【汗だく】
(「汗だくだく」の略)汗をびっしょりかいているさま。
あぜ‐たけ【綜竹】
(→)綾竹あやだけ1に同じ。
あぜち【按察使・按察】
(アンセチシの約)奈良時代、諸国の行政を監察した官。719年(養老3)創設。特定の国司の兼任。後には陸奥・出羽だけ実態を残し、他は大中納言の兼ねる名義だけの官となる。→摂官2
あ‐ぜち【庵室】
(アンジチの転)江戸時代、奈良での手習所の別称。手習所を寺と呼ぶことがあったが、奈良で単に寺といえば興福寺をさしたのでこの別称が生まれた。
あぜ‐ち【畔内】
(北陸地方や岐阜県で)分家。あじち。
アセチル‐き【アセチル基】
(acetyl group)酢酸から水酸基を除いた原子団。化学式CH3CO‐
アセチルグルコサミン【acetylglucosamine】
「グルコサミン」参照。
アセチルコリン【acetylcholine】
神経組織に多く含まれる塩基性物質。副交感神経と運動神経の神経末端から刺激に応じて分泌され、神経の伝達にたずさわる。麦角に含まれる。
アセチルサリチル‐さん【アセチルサリチル酸】
(acetylsalicylic acid)分子式C6H4(OCOCH3)COOH 白色の結晶。サリチル酸と無水酢酸との反応により製する。鎮痛解熱作用や抗リウマチ作用があり、アスピリンの名で医薬として用いる。
アセチルセルロース【acetylcellulose】
セルロースの酢酸エステル。綿に無水酢酸・濃硫酸を加えて作る。人造絹糸・不燃性フィルム・プラスチックなどに使用。酢酸繊維素。酢酸セルロース。
アセチレン【acetylene】
分子式HC≡CH 炭化水素の一つ。無色の有毒性の気体。光輝の強い炎で燃える。かつては灯用とした。酸素と混じて鉄の切断や溶接に利用。有機合成基礎原料。カーバイドに水を作用させたり、天然ガス・石油を高温で熱分解したりしてつくる。エチン。
⇒アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】
⇒アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
⇒アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】‥クワ‥
三重結合を一つもつ不飽和鎖式炭化水素の総称。一般式CnH2n−2で表される。アルキンともいう。n=2がアセチレン、n=3がメチルアセチレンである。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
酸素とアセチレンで得られるセ氏約3000度の高温の炎による金属の溶接・切断。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンを燃料としたランプ。電気が使えない大道芸人などが使った。
⇒アセチレン【acetylene】
アセテート‐レーヨン【acetate rayon】
アセチルセルロースを原料とした人絹。丈夫で色つや・手ざわりがよく吸湿性は小さい。アセテート人絹。
アセトアニリド【acetanilide】
分子式C6H5NHCOCH3 アニリンのアミノ基(NH2‐)の水素1原子をアセチル基(CH3CO‐)で置換したもの。アニリンと無水酢酸とを加熱して製する。無色の板状結晶。医薬・染料などの重要な合成原料。アンチフェブリンの名で知られる最初の合成解熱剤であるが、毒性が強いため現在は使用が禁止されている。
アセトアミノフェン【acetaminophen】
解熱鎮痛剤の一つ。分子式C8H9NO2 オルト・メタ・パラの三つの異性体があるが、解熱鎮痛剤として用いられるのは、パラ体のパラアセタミドフェノール。
アセトアルデヒド【acetaldehyde】
分子式CH3CHO 無色の刺激臭ある可燃性液体。エチレンの直接酸化によって製する。有機合成の原料として重要。エタノールの酸化でも生成し、二日酔の原因。エタナール。
あせ‐どの【汗殿】
(汗は血の忌詞)伊勢の斎宮が月経時にこもった御殿。
あせ‐とり【汗取り】
直接肌につけて汗を吸い取らせる肌着。〈[季]夏〉
アセトン【acetone】
分子式CH3COCH3 ケトンの代表的なもの。無色の液体。アセチレン・プロピレンを原料として製造。溶剤として広く用いるほか、アセテート繊維・メタクリル樹脂・医薬品の原料。
あせ‐ながし【汗流し】
兜かぶとの頬当ほおあての下底にあけた穴。
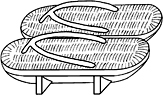 ⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごえ【東声】アヅマゴヱ
東国風の発音。東訛あずまなまり。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐コート【東コート】アヅマ‥
被布ひふより長く裾まである女性の和装用コート。主に羅紗・セルで作る。明治中期より流行。徳田秋声、惰けもの「糸織に一つ紋の黒縮緬の羽織、吾妻あづまコートを乱次だらしなく着て」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごと【東琴】アヅマ‥
和琴わごんの別称。源氏物語手習「―をこそは事もなく弾き侍りしかど」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐じ【東路】アヅマヂ
京都から東国へ至る道。すなわち東海道・東山道などを指す。転じて、東国の意。万葉集14「―の手児てこのよび坂越えがねて」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまし・い
〔形〕
(津軽地方・北海道で)気持がよい。満足だ。
あずまじし【吾妻獅子・東獅子】アヅマ‥
地歌。手事物。峰崎勾当作曲。在原業平を気取った東下りの男が、吉原の遊女との後朝きぬぎぬの別れを惜しんで舞を舞うさまを描く。箏の手付は多種ある。
あずま‐じょうるり【吾妻浄瑠璃】アヅマジヤウ‥
元禄(1688〜1704)頃、上方で行われた江戸浄瑠璃。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐そだち【東育ち】アヅマ‥
江戸で育ったこと。それを誇りにしていう語。梅暦「品やさしきはおのづから―の隅田川」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐っ‐こ【東っ子】アヅマ‥
江戸っ子。江戸の人の自称する語。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐つづれ【東綴れ】アヅマ‥
明治末、栃木県足利市で織り出した女物の帯地。綴錦風に文様を織り出した織物。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ど【東人】アヅマ‥
(アズマウドの約)東国の人。あずまびと。万葉集2「―の荷前のさきの箱の荷の緒にも」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐なまり【東訛】アヅマ‥
東国のなまり。東声あずまごえ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐にしきえ【吾妻錦絵・東錦絵】アヅマ‥ヱ
多色摺りの木版の浮世絵。江戸の名物で、鈴木春信がはじめて売り出した当初から、この名を用いた。錦絵。江戸絵。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ねざさ【東根笹】アヅマ‥
野生のササの一種。関東地方に普通で、いわゆる篠竹しのだけ。地下茎は横に這い、地上茎は直立して強靱、高さ1メートル内外。常緑で、葉は堅く暗緑色。花序は細長くて約15センチメートル、小花を密集し緑色で穂となる。アズマシノ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ばし【吾妻橋】アヅマ‥
東京都台東区浅草と墨田区吾妻橋を結ぶ隅田川の橋。1774年(安永3)初めて架橋。現在の橋は1931年竣工。
あずま‐ばしょり【東端折り】アヅマ‥
(→)「あずまからげ」に同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐はっけい【吾妻八景】アヅマ‥
長唄。1829年(文政12)4世杵屋六三郎作曲(一説に作詞も)。江戸名所をよみ入れた歌詞。長唄を歌舞伎から独立して聴かせる新しい試みとして作られた名曲。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐びと【東人】アヅマ‥
東国の人。あずまうど。源氏物語宿木「―どもにも食はせ」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ひゃっかん【東百官】アヅマヒヤククワン
①室町末期から、関東武士が京都朝廷の官名に擬して用いた私称。伊織・多門・左膳・頼母・求馬・左内・兵馬の類。
②江戸時代に行われた子供の手習い本で、1の名などを集めたもの。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐まい【東舞】アヅママヒ
(→)東遊あずまあそびに同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐むすび【東結び・吾妻結び】アヅマ‥
紐の結び方。輪を左右に出し、中を三巻きにしたもの。几帳きちょう・守り袋・簾すだれの紐などを結ぶのに用いる。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐め【東女】アヅマ‥
東国の女。あずまおみな。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまもんどう【吾妻問答】アヅマ‥ダフ
室町時代の連歌書。1巻。宗祇著。1470年(文明2)自跋。別名、角田川すみだがわ。連歌の代表作家・作法などを問答体に述べる。
あずま‐や【四阿・東屋・阿舎】アヅマ‥
(東国風のひなびた家の意)
①四方へ檐のきを葺きおろした家屋。寄棟よせむねあるいは入母屋いりもや造。正倉院文書「草葺―一間」
②四方の柱だけで、壁がなく、屋根を四方に葺きおろした小屋。庭園などの休息所とする。亭ちん。国木田独歩、夫婦「庭へ出て吾妻屋あずまやに行つて見たが」
③催馬楽さいばらの曲名。
④源氏物語の巻名。宇治十帖の一つ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐やき【吾妻焼】アヅマ‥
旭焼あさひやきの旧称。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまや‐さん【四阿山】アヅマ‥
長野県北東部、群馬県との境にある山。標高2354メートル。西に根子岳ねこだけ、西麓に菅平高原が広がる。吾妻あがつま山。
四阿山
提供:オフィス史朗
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごえ【東声】アヅマゴヱ
東国風の発音。東訛あずまなまり。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐コート【東コート】アヅマ‥
被布ひふより長く裾まである女性の和装用コート。主に羅紗・セルで作る。明治中期より流行。徳田秋声、惰けもの「糸織に一つ紋の黒縮緬の羽織、吾妻あづまコートを乱次だらしなく着て」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ごと【東琴】アヅマ‥
和琴わごんの別称。源氏物語手習「―をこそは事もなく弾き侍りしかど」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐じ【東路】アヅマヂ
京都から東国へ至る道。すなわち東海道・東山道などを指す。転じて、東国の意。万葉集14「―の手児てこのよび坂越えがねて」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまし・い
〔形〕
(津軽地方・北海道で)気持がよい。満足だ。
あずまじし【吾妻獅子・東獅子】アヅマ‥
地歌。手事物。峰崎勾当作曲。在原業平を気取った東下りの男が、吉原の遊女との後朝きぬぎぬの別れを惜しんで舞を舞うさまを描く。箏の手付は多種ある。
あずま‐じょうるり【吾妻浄瑠璃】アヅマジヤウ‥
元禄(1688〜1704)頃、上方で行われた江戸浄瑠璃。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐そだち【東育ち】アヅマ‥
江戸で育ったこと。それを誇りにしていう語。梅暦「品やさしきはおのづから―の隅田川」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐っ‐こ【東っ子】アヅマ‥
江戸っ子。江戸の人の自称する語。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐つづれ【東綴れ】アヅマ‥
明治末、栃木県足利市で織り出した女物の帯地。綴錦風に文様を織り出した織物。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ど【東人】アヅマ‥
(アズマウドの約)東国の人。あずまびと。万葉集2「―の荷前のさきの箱の荷の緒にも」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐なまり【東訛】アヅマ‥
東国のなまり。東声あずまごえ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐にしきえ【吾妻錦絵・東錦絵】アヅマ‥ヱ
多色摺りの木版の浮世絵。江戸の名物で、鈴木春信がはじめて売り出した当初から、この名を用いた。錦絵。江戸絵。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ねざさ【東根笹】アヅマ‥
野生のササの一種。関東地方に普通で、いわゆる篠竹しのだけ。地下茎は横に這い、地上茎は直立して強靱、高さ1メートル内外。常緑で、葉は堅く暗緑色。花序は細長くて約15センチメートル、小花を密集し緑色で穂となる。アズマシノ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ばし【吾妻橋】アヅマ‥
東京都台東区浅草と墨田区吾妻橋を結ぶ隅田川の橋。1774年(安永3)初めて架橋。現在の橋は1931年竣工。
あずま‐ばしょり【東端折り】アヅマ‥
(→)「あずまからげ」に同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐はっけい【吾妻八景】アヅマ‥
長唄。1829年(文政12)4世杵屋六三郎作曲(一説に作詞も)。江戸名所をよみ入れた歌詞。長唄を歌舞伎から独立して聴かせる新しい試みとして作られた名曲。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐びと【東人】アヅマ‥
東国の人。あずまうど。源氏物語宿木「―どもにも食はせ」
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐ひゃっかん【東百官】アヅマヒヤククワン
①室町末期から、関東武士が京都朝廷の官名に擬して用いた私称。伊織・多門・左膳・頼母・求馬・左内・兵馬の類。
②江戸時代に行われた子供の手習い本で、1の名などを集めたもの。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐まい【東舞】アヅママヒ
(→)東遊あずまあそびに同じ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐むすび【東結び・吾妻結び】アヅマ‥
紐の結び方。輪を左右に出し、中を三巻きにしたもの。几帳きちょう・守り袋・簾すだれの紐などを結ぶのに用いる。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐め【東女】アヅマ‥
東国の女。あずまおみな。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまもんどう【吾妻問答】アヅマ‥ダフ
室町時代の連歌書。1巻。宗祇著。1470年(文明2)自跋。別名、角田川すみだがわ。連歌の代表作家・作法などを問答体に述べる。
あずま‐や【四阿・東屋・阿舎】アヅマ‥
(東国風のひなびた家の意)
①四方へ檐のきを葺きおろした家屋。寄棟よせむねあるいは入母屋いりもや造。正倉院文書「草葺―一間」
②四方の柱だけで、壁がなく、屋根を四方に葺きおろした小屋。庭園などの休息所とする。亭ちん。国木田独歩、夫婦「庭へ出て吾妻屋あずまやに行つて見たが」
③催馬楽さいばらの曲名。
④源氏物語の巻名。宇治十帖の一つ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずま‐やき【吾妻焼】アヅマ‥
旭焼あさひやきの旧称。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずまや‐さん【四阿山】アヅマ‥
長野県北東部、群馬県との境にある山。標高2354メートル。西に根子岳ねこだけ、西麓に菅平高原が広がる。吾妻あがつま山。
四阿山
提供:オフィス史朗
 あずま‐やま【吾妻山】アヅマ‥
福島市の西方、福島・山形の県境をなす火山群。最高峰は西吾妻山で、標高2035メートル。磐梯朝日国立公園に属する。
吾妻山(吾妻小富士と浄土平)
撮影:佐藤 尚
あずま‐やま【吾妻山】アヅマ‥
福島市の西方、福島・山形の県境をなす火山群。最高峰は西吾妻山で、標高2035メートル。磐梯朝日国立公園に属する。
吾妻山(吾妻小富士と浄土平)
撮影:佐藤 尚
 あずま‐よじべえ【吾妻与次兵衛】アヅマ‥ヱ
浄瑠璃・歌舞伎の男女の登場人物および二人を主人公とする作品群の通称。江戸初期の歌謡にその情話をうたわれた大坂新町の遊女藤屋吾妻と山崎浄閑の息子与次兵衛。近松門左衛門作「寿門松ねびきのかどまつ」や「双蝶蝶曲輪日記ふたつちょうちょうくるわにっき」などで有名。
アスマラ【Asmara】
アフリカ北東部、エリトリア国の首都。イタリア風の街並で知られる。人口35万8千(1990)。
あずま‐わらわ【東孺・東豎子】アヅマワラハ
内侍司ないしのつかさの女官。行幸の時、騎馬で供奉ぐぶした。一腹三子みつごの小童を使用。姫松。姫大夫ひめもうちぎみ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずみ【阿曇】アヅミ
姓氏の一つ。
⇒あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】
あずみ‐の【安曇野】アヅミ‥
①長野県中部、松本盆地の北半部、梓川あずさがわ以北の通称。稲作、リンゴ・わさび栽培などで知られる。安曇平。
安曇野の山葵田
撮影:佐藤 尚
あずま‐よじべえ【吾妻与次兵衛】アヅマ‥ヱ
浄瑠璃・歌舞伎の男女の登場人物および二人を主人公とする作品群の通称。江戸初期の歌謡にその情話をうたわれた大坂新町の遊女藤屋吾妻と山崎浄閑の息子与次兵衛。近松門左衛門作「寿門松ねびきのかどまつ」や「双蝶蝶曲輪日記ふたつちょうちょうくるわにっき」などで有名。
アスマラ【Asmara】
アフリカ北東部、エリトリア国の首都。イタリア風の街並で知られる。人口35万8千(1990)。
あずま‐わらわ【東孺・東豎子】アヅマワラハ
内侍司ないしのつかさの女官。行幸の時、騎馬で供奉ぐぶした。一腹三子みつごの小童を使用。姫松。姫大夫ひめもうちぎみ。
⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】
あずみ【阿曇】アヅミ
姓氏の一つ。
⇒あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】
あずみ‐の【安曇野】アヅミ‥
①長野県中部、松本盆地の北半部、梓川あずさがわ以北の通称。稲作、リンゴ・わさび栽培などで知られる。安曇平。
安曇野の山葵田
撮影:佐藤 尚
 ②⇒あづみの
あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】アヅミ‥
古代の武人。662年、新羅しらぎと唐とに攻められた百済くだらを救うために水軍を率いて出征、翌年白村江で唐軍に敗北、軍を収めて帰国。
⇒あずみ【阿曇】
アスモデ【Asmodée フランス】
ユダヤ教伝承中の悪魔。旧約聖書外典トビト書を始め、スペインの劇作家ゲバラ(Luis Vélez de Guevara1579〜1644)の「びっこの悪魔」、これを模倣したルサージュの悪漢小説、モーリアックの戯曲などに登場。
あすら【阿修羅】
⇒あしゅら
アスリート【athlete】
運動選手。特に、陸上競技の選手。
アスレチック‐クラブ【athletic club】
各種の運動器具・施設を備え、美容・健康のための運動を行う有料会員制のクラブ。
アスレチックス【athletics】
運動競技。特に、陸上競技。
アズレン【azulene】
分子式C10H8 二つの六員環が縮合したナフタレンの異性体で、五員環と七員環が縮合した構造を持つ。カミルレなどの植物精油を脱水して得られる。深青色板状結晶。抗炎剤として多くの薬剤や化粧品類に用いられる。
アスロック【ASROC】
(anti-submarine rocket)対潜水艦ミサイルの一種。ロケットの先端にホーミング魚雷を装備し、艦艇から発射して潜水艦を攻撃する兵器。
アスワン‐ダム【Aswan Dam】
エジプト、ナイル川の中流にあるダム。1902年完成、貯水容量55億トン、灌漑・発電に利用。その上流に貯水容量1570億トンのアスワン‐ハイ‐ダムが71年完成。
ナセル湖
撮影:小松義夫
②⇒あづみの
あずみ‐の‐ひらぶ【阿曇比邏夫】アヅミ‥
古代の武人。662年、新羅しらぎと唐とに攻められた百済くだらを救うために水軍を率いて出征、翌年白村江で唐軍に敗北、軍を収めて帰国。
⇒あずみ【阿曇】
アスモデ【Asmodée フランス】
ユダヤ教伝承中の悪魔。旧約聖書外典トビト書を始め、スペインの劇作家ゲバラ(Luis Vélez de Guevara1579〜1644)の「びっこの悪魔」、これを模倣したルサージュの悪漢小説、モーリアックの戯曲などに登場。
あすら【阿修羅】
⇒あしゅら
アスリート【athlete】
運動選手。特に、陸上競技の選手。
アスレチック‐クラブ【athletic club】
各種の運動器具・施設を備え、美容・健康のための運動を行う有料会員制のクラブ。
アスレチックス【athletics】
運動競技。特に、陸上競技。
アズレン【azulene】
分子式C10H8 二つの六員環が縮合したナフタレンの異性体で、五員環と七員環が縮合した構造を持つ。カミルレなどの植物精油を脱水して得られる。深青色板状結晶。抗炎剤として多くの薬剤や化粧品類に用いられる。
アスロック【ASROC】
(anti-submarine rocket)対潜水艦ミサイルの一種。ロケットの先端にホーミング魚雷を装備し、艦艇から発射して潜水艦を攻撃する兵器。
アスワン‐ダム【Aswan Dam】
エジプト、ナイル川の中流にあるダム。1902年完成、貯水容量55億トン、灌漑・発電に利用。その上流に貯水容量1570億トンのアスワン‐ハイ‐ダムが71年完成。
ナセル湖
撮影:小松義夫
 アスンシオン【Asunción】
(聖母被昇天の意)南米、パラグアイ共和国の首都。パラグアイ川に臨む。17世紀までラプラタ川流域の最も重要な港であった。人口51万3千(2002)。
あせ【汗】
①温度刺激により汗腺から排出される分泌液。塩類・ピルビン酸・乳酸・アンモニアなどを含む。気温の高い時、激しい運動をした時などに体温調節の作用をするほか、痛覚・精神的緊張によっても出る。〈[季]夏〉。万葉集9「熱けくに―かきなげ」。「―をかく」→汗腺。
②物の表面に生じる湿滴。「壁が―をかく」「乾物が―をかく」
③(斎宮の忌詞・女房詞)血。
⇒汗になる
⇒汗を入れる
⇒汗をかく
⇒汗を流す
⇒汗を握る
⇒汗を揉む
あ‐せ【吾兄】
男子を親しんで呼ぶ語。歌のはやし言葉などに用いた。古事記中「一つ松―を」
あぜ【畦・畔】
①田と田との間に土を盛り上げて境としたもの。くろ。〈倭名類聚鈔1〉
②敷居または鴨居のみぞとみぞとの間にある仕切り。→樋端ひばた2
あぜ【綜】
機はたの経糸たていとを上下に分け、緯糸よこいとを通す隙間を作る用具。綜絖そうこう。
あぜ【何】
〔副〕
(上代東国方言)
①なぜ。どうして。万葉集14「わがせなは―そも今宵寄しろ来まさぬ」
②どのように。いかに。万葉集14「―せろと心にのりてここば悲しけ」
あせ‐あぶら【汗膏】
汗と膏。辛苦を重ねることのたとえにいう。
アセアン【ASEAN】
(Association of South-East Asian Nations)東南アジア諸国連合。1967年にインドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン・マレーシアの5カ国で結成した地域協力機構。84年ブルネイ、95年ベトナム、97年ラオス・ミャンマー、99年カンボジアが加盟。決定機関である外相会議の下にジャカルタに常設の事務局を置く。
あ‐せい【亜聖】
聖人につぐ賢人。一般に、孔子を聖人とするのに対し、孟子または顔回をいう。
あぜ‐いと【綜糸】
あぜで経糸たていとを上下に分ける糸。
あぜ‐おり【畦織・畔織】
経糸たていとまたは緯糸よこいとのどちらか一方の糸が他の糸数本を跨いで平組織にし、経か緯の方向に畦(畔)が現れるようにした織物。緯に太い畦のあるのを経畦織、経に畦のあるのを緯畦織という。うねおり。
あせ‐かき【汗掻き】
汗をかきやすい人。あせっかき。
あぜ‐がやつり【畦蚊屋吊・畦莎草】
カヤツリグサ科の一年草。湿地や田の畦に多い雑草。茎は高さ約30センチメートル。三稜形で細く硬い。葉は細長く、基部は鞘状となって茎を囲む。夏、穂状の淡黄褐色の花を開く。ホソバガヤツリ。
あぜ‐き【校木】
〔建〕校倉あぜくらを組む材木。
あせ‐くさ・い【汗臭い】
〔形〕
汗のいやな臭いがする。
あせ‐ぐ・む【汗ぐむ】
〔自四〕
汗がにじみ出る。汗ばむ。古今著聞集10「寒げに見えけるが、御馬の数つかうまつりければ、―・みにけり」
あぜ‐くら【校倉】
部材を横に組んで壁を作った倉。部材の断面は三角・四角・円など。甲倉。叉倉。あぜり。→井楼せいろう組。
校倉
アスンシオン【Asunción】
(聖母被昇天の意)南米、パラグアイ共和国の首都。パラグアイ川に臨む。17世紀までラプラタ川流域の最も重要な港であった。人口51万3千(2002)。
あせ【汗】
①温度刺激により汗腺から排出される分泌液。塩類・ピルビン酸・乳酸・アンモニアなどを含む。気温の高い時、激しい運動をした時などに体温調節の作用をするほか、痛覚・精神的緊張によっても出る。〈[季]夏〉。万葉集9「熱けくに―かきなげ」。「―をかく」→汗腺。
②物の表面に生じる湿滴。「壁が―をかく」「乾物が―をかく」
③(斎宮の忌詞・女房詞)血。
⇒汗になる
⇒汗を入れる
⇒汗をかく
⇒汗を流す
⇒汗を握る
⇒汗を揉む
あ‐せ【吾兄】
男子を親しんで呼ぶ語。歌のはやし言葉などに用いた。古事記中「一つ松―を」
あぜ【畦・畔】
①田と田との間に土を盛り上げて境としたもの。くろ。〈倭名類聚鈔1〉
②敷居または鴨居のみぞとみぞとの間にある仕切り。→樋端ひばた2
あぜ【綜】
機はたの経糸たていとを上下に分け、緯糸よこいとを通す隙間を作る用具。綜絖そうこう。
あぜ【何】
〔副〕
(上代東国方言)
①なぜ。どうして。万葉集14「わがせなは―そも今宵寄しろ来まさぬ」
②どのように。いかに。万葉集14「―せろと心にのりてここば悲しけ」
あせ‐あぶら【汗膏】
汗と膏。辛苦を重ねることのたとえにいう。
アセアン【ASEAN】
(Association of South-East Asian Nations)東南アジア諸国連合。1967年にインドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン・マレーシアの5カ国で結成した地域協力機構。84年ブルネイ、95年ベトナム、97年ラオス・ミャンマー、99年カンボジアが加盟。決定機関である外相会議の下にジャカルタに常設の事務局を置く。
あ‐せい【亜聖】
聖人につぐ賢人。一般に、孔子を聖人とするのに対し、孟子または顔回をいう。
あぜ‐いと【綜糸】
あぜで経糸たていとを上下に分ける糸。
あぜ‐おり【畦織・畔織】
経糸たていとまたは緯糸よこいとのどちらか一方の糸が他の糸数本を跨いで平組織にし、経か緯の方向に畦(畔)が現れるようにした織物。緯に太い畦のあるのを経畦織、経に畦のあるのを緯畦織という。うねおり。
あせ‐かき【汗掻き】
汗をかきやすい人。あせっかき。
あぜ‐がやつり【畦蚊屋吊・畦莎草】
カヤツリグサ科の一年草。湿地や田の畦に多い雑草。茎は高さ約30センチメートル。三稜形で細く硬い。葉は細長く、基部は鞘状となって茎を囲む。夏、穂状の淡黄褐色の花を開く。ホソバガヤツリ。
あぜ‐き【校木】
〔建〕校倉あぜくらを組む材木。
あせ‐くさ・い【汗臭い】
〔形〕
汗のいやな臭いがする。
あせ‐ぐ・む【汗ぐむ】
〔自四〕
汗がにじみ出る。汗ばむ。古今著聞集10「寒げに見えけるが、御馬の数つかうまつりければ、―・みにけり」
あぜ‐くら【校倉】
部材を横に組んで壁を作った倉。部材の断面は三角・四角・円など。甲倉。叉倉。あぜり。→井楼せいろう組。
校倉
 ⇒あぜくら‐づくり【校倉造】
あぜくら‐づくり【校倉造】
校倉風の建築様式。古代に多い。正倉院のほか、東大寺・唐招提寺・東寺などに遺構が存する。
⇒あぜ‐くら【校倉】
あぜこし‐たうえ【畦越し田植】‥ウヱ
休まないで続けて隣の田を植えること。凶事があるとして忌む。
あせ‐しずく【汗雫】‥シヅク
雫のようにしたたる汗。
あせ‐ジバン【汗襦袢】
和服の下に着る汗取りの肌着。あせじゅばん。あせとり。
あせ‐じ・みる【汗染みる】
〔自上一〕
衣服などに汗がしみ出てよごれる。
あせ‐しらず【汗知らず】
汗を吸収し皮膚を乾燥させて爽やかにするもの。天瓜粉てんかふん・シッカロールの類。〈[季]夏〉
アセス
アセスメントの略。
アセスメント【assessment】
①評価。査定。見積り。
②⇒かんきょうアセスメント
あせ・する【汗する】
〔自サ変〕[文]あせ・す(サ変)
汗をかく。多く精を出してするのにいう。「額ひたいに―・して働く」
アセスルファム‐カリウム
(acesulfame potassium)人工甘味料の一つ。分子式C4H4KNO4S 白色の結晶。蔗糖の200〜250倍の甘味をもつ。略称、アセスルファムK。
アセタール‐じゅし【アセタール樹脂】
(acetal resin)ポリアセタールの工業上の呼称。
あせ‐だく【汗だく】
(「汗だくだく」の略)汗をびっしょりかいているさま。
あぜ‐たけ【綜竹】
(→)綾竹あやだけ1に同じ。
あぜち【按察使・按察】
(アンセチシの約)奈良時代、諸国の行政を監察した官。719年(養老3)創設。特定の国司の兼任。後には陸奥・出羽だけ実態を残し、他は大中納言の兼ねる名義だけの官となる。→摂官2
あ‐ぜち【庵室】
(アンジチの転)江戸時代、奈良での手習所の別称。手習所を寺と呼ぶことがあったが、奈良で単に寺といえば興福寺をさしたのでこの別称が生まれた。
あぜ‐ち【畔内】
(北陸地方や岐阜県で)分家。あじち。
アセチル‐き【アセチル基】
(acetyl group)酢酸から水酸基を除いた原子団。化学式CH3CO‐
アセチルグルコサミン【acetylglucosamine】
「グルコサミン」参照。
アセチルコリン【acetylcholine】
神経組織に多く含まれる塩基性物質。副交感神経と運動神経の神経末端から刺激に応じて分泌され、神経の伝達にたずさわる。麦角に含まれる。
アセチルサリチル‐さん【アセチルサリチル酸】
(acetylsalicylic acid)分子式C6H4(OCOCH3)COOH 白色の結晶。サリチル酸と無水酢酸との反応により製する。鎮痛解熱作用や抗リウマチ作用があり、アスピリンの名で医薬として用いる。
アセチルセルロース【acetylcellulose】
セルロースの酢酸エステル。綿に無水酢酸・濃硫酸を加えて作る。人造絹糸・不燃性フィルム・プラスチックなどに使用。酢酸繊維素。酢酸セルロース。
アセチレン【acetylene】
分子式HC≡CH 炭化水素の一つ。無色の有毒性の気体。光輝の強い炎で燃える。かつては灯用とした。酸素と混じて鉄の切断や溶接に利用。有機合成基礎原料。カーバイドに水を作用させたり、天然ガス・石油を高温で熱分解したりしてつくる。エチン。
⇒アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】
⇒アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
⇒アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】‥クワ‥
三重結合を一つもつ不飽和鎖式炭化水素の総称。一般式CnH2n−2で表される。アルキンともいう。n=2がアセチレン、n=3がメチルアセチレンである。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
酸素とアセチレンで得られるセ氏約3000度の高温の炎による金属の溶接・切断。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンを燃料としたランプ。電気が使えない大道芸人などが使った。
⇒アセチレン【acetylene】
アセテート‐レーヨン【acetate rayon】
アセチルセルロースを原料とした人絹。丈夫で色つや・手ざわりがよく吸湿性は小さい。アセテート人絹。
アセトアニリド【acetanilide】
分子式C6H5NHCOCH3 アニリンのアミノ基(NH2‐)の水素1原子をアセチル基(CH3CO‐)で置換したもの。アニリンと無水酢酸とを加熱して製する。無色の板状結晶。医薬・染料などの重要な合成原料。アンチフェブリンの名で知られる最初の合成解熱剤であるが、毒性が強いため現在は使用が禁止されている。
アセトアミノフェン【acetaminophen】
解熱鎮痛剤の一つ。分子式C8H9NO2 オルト・メタ・パラの三つの異性体があるが、解熱鎮痛剤として用いられるのは、パラ体のパラアセタミドフェノール。
アセトアルデヒド【acetaldehyde】
分子式CH3CHO 無色の刺激臭ある可燃性液体。エチレンの直接酸化によって製する。有機合成の原料として重要。エタノールの酸化でも生成し、二日酔の原因。エタナール。
あせ‐どの【汗殿】
(汗は血の忌詞)伊勢の斎宮が月経時にこもった御殿。
あせ‐とり【汗取り】
直接肌につけて汗を吸い取らせる肌着。〈[季]夏〉
アセトン【acetone】
分子式CH3COCH3 ケトンの代表的なもの。無色の液体。アセチレン・プロピレンを原料として製造。溶剤として広く用いるほか、アセテート繊維・メタクリル樹脂・医薬品の原料。
あせ‐ながし【汗流し】
兜かぶとの頬当ほおあての下底にあけた穴。
⇒あぜくら‐づくり【校倉造】
あぜくら‐づくり【校倉造】
校倉風の建築様式。古代に多い。正倉院のほか、東大寺・唐招提寺・東寺などに遺構が存する。
⇒あぜ‐くら【校倉】
あぜこし‐たうえ【畦越し田植】‥ウヱ
休まないで続けて隣の田を植えること。凶事があるとして忌む。
あせ‐しずく【汗雫】‥シヅク
雫のようにしたたる汗。
あせ‐ジバン【汗襦袢】
和服の下に着る汗取りの肌着。あせじゅばん。あせとり。
あせ‐じ・みる【汗染みる】
〔自上一〕
衣服などに汗がしみ出てよごれる。
あせ‐しらず【汗知らず】
汗を吸収し皮膚を乾燥させて爽やかにするもの。天瓜粉てんかふん・シッカロールの類。〈[季]夏〉
アセス
アセスメントの略。
アセスメント【assessment】
①評価。査定。見積り。
②⇒かんきょうアセスメント
あせ・する【汗する】
〔自サ変〕[文]あせ・す(サ変)
汗をかく。多く精を出してするのにいう。「額ひたいに―・して働く」
アセスルファム‐カリウム
(acesulfame potassium)人工甘味料の一つ。分子式C4H4KNO4S 白色の結晶。蔗糖の200〜250倍の甘味をもつ。略称、アセスルファムK。
アセタール‐じゅし【アセタール樹脂】
(acetal resin)ポリアセタールの工業上の呼称。
あせ‐だく【汗だく】
(「汗だくだく」の略)汗をびっしょりかいているさま。
あぜ‐たけ【綜竹】
(→)綾竹あやだけ1に同じ。
あぜち【按察使・按察】
(アンセチシの約)奈良時代、諸国の行政を監察した官。719年(養老3)創設。特定の国司の兼任。後には陸奥・出羽だけ実態を残し、他は大中納言の兼ねる名義だけの官となる。→摂官2
あ‐ぜち【庵室】
(アンジチの転)江戸時代、奈良での手習所の別称。手習所を寺と呼ぶことがあったが、奈良で単に寺といえば興福寺をさしたのでこの別称が生まれた。
あぜ‐ち【畔内】
(北陸地方や岐阜県で)分家。あじち。
アセチル‐き【アセチル基】
(acetyl group)酢酸から水酸基を除いた原子団。化学式CH3CO‐
アセチルグルコサミン【acetylglucosamine】
「グルコサミン」参照。
アセチルコリン【acetylcholine】
神経組織に多く含まれる塩基性物質。副交感神経と運動神経の神経末端から刺激に応じて分泌され、神経の伝達にたずさわる。麦角に含まれる。
アセチルサリチル‐さん【アセチルサリチル酸】
(acetylsalicylic acid)分子式C6H4(OCOCH3)COOH 白色の結晶。サリチル酸と無水酢酸との反応により製する。鎮痛解熱作用や抗リウマチ作用があり、アスピリンの名で医薬として用いる。
アセチルセルロース【acetylcellulose】
セルロースの酢酸エステル。綿に無水酢酸・濃硫酸を加えて作る。人造絹糸・不燃性フィルム・プラスチックなどに使用。酢酸繊維素。酢酸セルロース。
アセチレン【acetylene】
分子式HC≡CH 炭化水素の一つ。無色の有毒性の気体。光輝の強い炎で燃える。かつては灯用とした。酸素と混じて鉄の切断や溶接に利用。有機合成基礎原料。カーバイドに水を作用させたり、天然ガス・石油を高温で熱分解したりしてつくる。エチン。
⇒アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】
⇒アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
⇒アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンけい‐たんかすいそ【アセチレン系炭化水素】‥クワ‥
三重結合を一つもつ不飽和鎖式炭化水素の総称。一般式CnH2n−2で表される。アルキンともいう。n=2がアセチレン、n=3がメチルアセチレンである。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ようせつ【アセチレン溶接】
酸素とアセチレンで得られるセ氏約3000度の高温の炎による金属の溶接・切断。
⇒アセチレン【acetylene】
アセチレン‐ランプ【acetylene lamp】
アセチレンを燃料としたランプ。電気が使えない大道芸人などが使った。
⇒アセチレン【acetylene】
アセテート‐レーヨン【acetate rayon】
アセチルセルロースを原料とした人絹。丈夫で色つや・手ざわりがよく吸湿性は小さい。アセテート人絹。
アセトアニリド【acetanilide】
分子式C6H5NHCOCH3 アニリンのアミノ基(NH2‐)の水素1原子をアセチル基(CH3CO‐)で置換したもの。アニリンと無水酢酸とを加熱して製する。無色の板状結晶。医薬・染料などの重要な合成原料。アンチフェブリンの名で知られる最初の合成解熱剤であるが、毒性が強いため現在は使用が禁止されている。
アセトアミノフェン【acetaminophen】
解熱鎮痛剤の一つ。分子式C8H9NO2 オルト・メタ・パラの三つの異性体があるが、解熱鎮痛剤として用いられるのは、パラ体のパラアセタミドフェノール。
アセトアルデヒド【acetaldehyde】
分子式CH3CHO 無色の刺激臭ある可燃性液体。エチレンの直接酸化によって製する。有機合成の原料として重要。エタノールの酸化でも生成し、二日酔の原因。エタナール。
あせ‐どの【汗殿】
(汗は血の忌詞)伊勢の斎宮が月経時にこもった御殿。
あせ‐とり【汗取り】
直接肌につけて汗を吸い取らせる肌着。〈[季]夏〉
アセトン【acetone】
分子式CH3COCH3 ケトンの代表的なもの。無色の液体。アセチレン・プロピレンを原料として製造。溶剤として広く用いるほか、アセテート繊維・メタクリル樹脂・医薬品の原料。
あせ‐ながし【汗流し】
兜かぶとの頬当ほおあての下底にあけた穴。
広辞苑 ページ 369 での【○東男に京女】単語。