複数辞典一括検索+![]()
![]()
○柔もまた茹わず剛もまた吐かずじゅうもまたくらわずごうもまたはかず🔗⭐🔉
○柔もまた茹わず剛もまた吐かずじゅうもまたくらわずごうもまたはかず
[詩経大雅、烝民]弱い者でも侮らず、強い者でも畏れない。
⇒じゅう【柔】
しゅう‐もん【宗門】
①宗旨。宗派。
②僧。浄瑠璃、彦山権現誓助剣「―の姿で喧嘩口論ならぬはず」
⇒しゅうもん‐あらため【宗門改】
⇒しゅうもん‐あらため‐やく【宗門改役】
⇒しゅうもん‐うけあい【宗門請合】
⇒しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】
しゅう‐もん【愁悶】シウ‥
うれえもだえること。
じゅう‐もん【十文】ジフ‥
1文の10倍。特に、「十文色」の値段。好色一代女6「定まりの―にて」
⇒じゅうもん‐いろ【十文色】
⇒じゅうもん‐ぎり【十文切り】
⇒じゅうもん‐せん【十文銭】
⇒じゅうもん‐もり【十文盛り】
しゅうもん‐あらため【宗門改】
江戸時代、キリシタン禁圧の一手段として、領民の宗旨を踏絵・寺請てらうけなどによって検査したこと。全国にわたり、毎年各家・各人ごとに宗門人別帳に記載し、檀那だんな寺に仏教宗派の帰依者であることを証明させた。1873年(明治6)廃止。宗旨人別改しゅうしにんべつあらため。→寺請。
⇒しゅう‐もん【宗門】
しゅうもん‐あらため‐やく【宗門改役】
江戸幕府の職名。宗門改をつかさどった。1640年(寛永17)大目付井上政重が任じられたのが初め。のち大目付・作事奉行各1名が担当。初めは吉利支丹御支配・吉利支丹奉行などと称した。1792年(寛政4)廃止。宗旨改役。
⇒しゅう‐もん【宗門】
じゅうもん‐いろ【十文色】ジフ‥
(価が10文だったのでいう)夜、辻に立って売色をする下等な売春婦。惣嫁そうか。浄瑠璃、冥途飛脚「―も出て来るは」
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅうもん‐うけあい【宗門請合】‥アヒ
江戸時代、檀那寺で、当人がキリシタン信徒でないことを証明すること。
⇒しゅう‐もん【宗門】
じゅうもん‐ぎり【十文切り】ジフ‥
(→)「十文盛り」に同じ。
⇒じゅう‐もん【十文】
じゅう‐もんじ【十文字】ジフ‥
①「十」の字の形。縦横に交叉した形。十字。平治物語「腹―に掻き切つて」。「ひもを―にかける」
②身を前後左右にひるがえし縦横に動きまわるさま。また、太刀・槍などを縦横に扱うさま。少数の者が大勢を敵として奮戦するさま。平家物語9「木曾三百余騎、六千余騎が中を、たてさま・よこさま・くもで・―に駈けわつて」
③紋所の名。「十」字を表したもの。丸に十字など。島津氏などの紋。
④楮こうぞを原料として簀すを縦横十文字にゆり動かし、繊維をよく絡め合わせた強靱な紙。美濃・常陸の産が有名。
⑤十文字槍の略。
⑥十文字轡ぐつわの略。
⇒じゅうもんじ‐かみこ【十文字紙子】
⇒じゅうもんじ‐ぐつわ【十文字轡】
⇒じゅうもんじ‐しだ【十文字羊歯】
⇒じゅうもんじ‐やり【十文字槍】
じゅうもんじ‐かみこ【十文字紙子】ジフ‥
美濃・紀伊に産する上製の紙子。美濃十文字。
⇒じゅう‐もんじ【十文字】
じゅうもんじ‐ぐつわ【十文字轡】ジフ‥
鏡板かがみいたに十文字のすかしのある轡。十字轡。近世、一説に「いずもぐつわ」ともいう。
⇒じゅう‐もんじ【十文字】
じゅうもんじ‐しだ【十文字羊歯】ジフ‥
オシダ科のシダ。根茎は短く、葉を束生する。葉柄は長さ約20センチメートル。頂上の大形羽片と側生の小形2羽片が十字形をなす。シュモクシダ。ミツデカグマ。
⇒じゅう‐もんじ【十文字】
じゅうもんじ‐やり【十文字槍】ジフ‥
穂先の下部に左右の枝があって十文字の形をした槍。
十文字槍
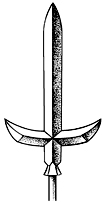 ⇒じゅう‐もんじ【十文字】
じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥
①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。
②明治以後、一厘銭の称。
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ
江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。
⇒しゅう‐もん【宗門】
じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥
顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。
じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥
一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅう‐や【秋夜】シウ‥
秋の夜。
しゅう‐や【終夜】
夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」
⇒しゅうや‐とう【終夜灯】
じゅう‐や【十夜】ジフ‥
〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉
しゅう‐やく【修訳】シウ‥
翻訳ほんやくすること。
しゅう‐やく【集約】シフ‥
あつめてまとめること。「発言を―する」
⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】
じゅう‐やく【十薬】ジフ‥
(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉
じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥
①重い災難。
②重い厄年。
じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥
①重い役目。頭だった役目。また、その人。
②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。
じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥
原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。
じゅう‐やく【銃薬】
小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。
しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ
一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業
⇒しゅう‐やく【集約】
しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥
葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。
しゅうや‐とう【終夜灯】
夜通しつけておく明かり。
⇒しゅう‐や【終夜】
しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥
中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)
しゅう‐ゆ【終油】
〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。
じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥
①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。
②コールタールの蒸留成分。タール油。
⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】
しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ
舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。
しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ
めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」
⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】
しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥
指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。
⇒しゅう‐ゆう【周遊】
じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン
(→)ディーゼル機関に同じ。
⇒じゅう‐ゆ【重油】
しゅう‐よう【主用】
主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」
しゅう‐よう【収用】シウ‥
①取りあげて用いること。
②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。
しゅう‐よう【収容】シウ‥
①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」
②法令により刑事施設に入れること。
⇒しゅうよう‐じょ【収容所】
しゅう‐よう【周揚】シウヤウ
(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)
しゅう‐よう【秋容】シウ‥
秋のすがた。秋のけしき。
しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ
秋の日光。
しゅう‐よう【修養】シウヤウ
(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」
しゅう‐よう【愁容】シウ‥
うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。
しゅう‐よう【醜容】シウ‥
みにくい容貌。醜貌。
しゅう‐よう【襲用】シフ‥
今までのやり方をそのままうけついで用いること。
じゅう‐よう【充用】
本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。
じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥
人を重く用いること。ちょうよう。
じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ
大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」
⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】
⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】
⇒じゅうよう‐し【重要視】
⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】
⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】
⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】
じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ
カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥
「参考人」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥
重要と認めること。重視。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥
(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。
しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥
人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。
⇒しゅう‐よう【収容】
しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ
(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。
じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥
1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
「無形文化財」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよく【十翼】ジフ‥
易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易
じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥
動物的な欲望。肉欲。
⇒じゅう‐もんじ【十文字】
じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥
①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。
②明治以後、一厘銭の称。
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ
江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。
⇒しゅう‐もん【宗門】
じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥
顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。
じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥
一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅう‐や【秋夜】シウ‥
秋の夜。
しゅう‐や【終夜】
夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」
⇒しゅうや‐とう【終夜灯】
じゅう‐や【十夜】ジフ‥
〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉
しゅう‐やく【修訳】シウ‥
翻訳ほんやくすること。
しゅう‐やく【集約】シフ‥
あつめてまとめること。「発言を―する」
⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】
じゅう‐やく【十薬】ジフ‥
(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉
じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥
①重い災難。
②重い厄年。
じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥
①重い役目。頭だった役目。また、その人。
②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。
じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥
原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。
じゅう‐やく【銃薬】
小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。
しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ
一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業
⇒しゅう‐やく【集約】
しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥
葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。
しゅうや‐とう【終夜灯】
夜通しつけておく明かり。
⇒しゅう‐や【終夜】
しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥
中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)
しゅう‐ゆ【終油】
〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。
じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥
①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。
②コールタールの蒸留成分。タール油。
⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】
しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ
舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。
しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ
めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」
⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】
しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥
指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。
⇒しゅう‐ゆう【周遊】
じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン
(→)ディーゼル機関に同じ。
⇒じゅう‐ゆ【重油】
しゅう‐よう【主用】
主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」
しゅう‐よう【収用】シウ‥
①取りあげて用いること。
②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。
しゅう‐よう【収容】シウ‥
①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」
②法令により刑事施設に入れること。
⇒しゅうよう‐じょ【収容所】
しゅう‐よう【周揚】シウヤウ
(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)
しゅう‐よう【秋容】シウ‥
秋のすがた。秋のけしき。
しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ
秋の日光。
しゅう‐よう【修養】シウヤウ
(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」
しゅう‐よう【愁容】シウ‥
うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。
しゅう‐よう【醜容】シウ‥
みにくい容貌。醜貌。
しゅう‐よう【襲用】シフ‥
今までのやり方をそのままうけついで用いること。
じゅう‐よう【充用】
本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。
じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥
人を重く用いること。ちょうよう。
じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ
大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」
⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】
⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】
⇒じゅうよう‐し【重要視】
⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】
⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】
⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】
じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ
カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥
「参考人」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥
重要と認めること。重視。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥
(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。
しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥
人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。
⇒しゅう‐よう【収容】
しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ
(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。
じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥
1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
「無形文化財」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよく【十翼】ジフ‥
易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易
じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥
動物的な欲望。肉欲。
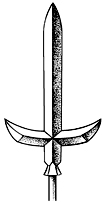 ⇒じゅう‐もんじ【十文字】
じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥
①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。
②明治以後、一厘銭の称。
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ
江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。
⇒しゅう‐もん【宗門】
じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥
顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。
じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥
一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅう‐や【秋夜】シウ‥
秋の夜。
しゅう‐や【終夜】
夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」
⇒しゅうや‐とう【終夜灯】
じゅう‐や【十夜】ジフ‥
〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉
しゅう‐やく【修訳】シウ‥
翻訳ほんやくすること。
しゅう‐やく【集約】シフ‥
あつめてまとめること。「発言を―する」
⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】
じゅう‐やく【十薬】ジフ‥
(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉
じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥
①重い災難。
②重い厄年。
じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥
①重い役目。頭だった役目。また、その人。
②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。
じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥
原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。
じゅう‐やく【銃薬】
小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。
しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ
一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業
⇒しゅう‐やく【集約】
しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥
葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。
しゅうや‐とう【終夜灯】
夜通しつけておく明かり。
⇒しゅう‐や【終夜】
しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥
中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)
しゅう‐ゆ【終油】
〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。
じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥
①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。
②コールタールの蒸留成分。タール油。
⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】
しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ
舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。
しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ
めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」
⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】
しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥
指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。
⇒しゅう‐ゆう【周遊】
じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン
(→)ディーゼル機関に同じ。
⇒じゅう‐ゆ【重油】
しゅう‐よう【主用】
主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」
しゅう‐よう【収用】シウ‥
①取りあげて用いること。
②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。
しゅう‐よう【収容】シウ‥
①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」
②法令により刑事施設に入れること。
⇒しゅうよう‐じょ【収容所】
しゅう‐よう【周揚】シウヤウ
(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)
しゅう‐よう【秋容】シウ‥
秋のすがた。秋のけしき。
しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ
秋の日光。
しゅう‐よう【修養】シウヤウ
(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」
しゅう‐よう【愁容】シウ‥
うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。
しゅう‐よう【醜容】シウ‥
みにくい容貌。醜貌。
しゅう‐よう【襲用】シフ‥
今までのやり方をそのままうけついで用いること。
じゅう‐よう【充用】
本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。
じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥
人を重く用いること。ちょうよう。
じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ
大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」
⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】
⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】
⇒じゅうよう‐し【重要視】
⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】
⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】
⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】
じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ
カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥
「参考人」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥
重要と認めること。重視。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥
(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。
しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥
人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。
⇒しゅう‐よう【収容】
しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ
(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。
じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥
1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
「無形文化財」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよく【十翼】ジフ‥
易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易
じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥
動物的な欲望。肉欲。
⇒じゅう‐もんじ【十文字】
じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥
①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。
②明治以後、一厘銭の称。
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ
江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。
⇒しゅう‐もん【宗門】
じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥
顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。
じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥
一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」
⇒じゅう‐もん【十文】
しゅう‐や【秋夜】シウ‥
秋の夜。
しゅう‐や【終夜】
夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」
⇒しゅうや‐とう【終夜灯】
じゅう‐や【十夜】ジフ‥
〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉
しゅう‐やく【修訳】シウ‥
翻訳ほんやくすること。
しゅう‐やく【集約】シフ‥
あつめてまとめること。「発言を―する」
⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】
じゅう‐やく【十薬】ジフ‥
(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉
じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥
①重い災難。
②重い厄年。
じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥
①重い役目。頭だった役目。また、その人。
②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。
じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥
原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。
じゅう‐やく【銃薬】
小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。
しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ
一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業
⇒しゅう‐やく【集約】
しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥
葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。
しゅうや‐とう【終夜灯】
夜通しつけておく明かり。
⇒しゅう‐や【終夜】
しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥
中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)
しゅう‐ゆ【終油】
〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。
じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥
①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。
②コールタールの蒸留成分。タール油。
⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】
しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ
舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。
しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ
めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」
⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】
しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥
指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。
⇒しゅう‐ゆう【周遊】
じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン
(→)ディーゼル機関に同じ。
⇒じゅう‐ゆ【重油】
しゅう‐よう【主用】
主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」
しゅう‐よう【収用】シウ‥
①取りあげて用いること。
②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。
しゅう‐よう【収容】シウ‥
①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」
②法令により刑事施設に入れること。
⇒しゅうよう‐じょ【収容所】
しゅう‐よう【周揚】シウヤウ
(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)
しゅう‐よう【秋容】シウ‥
秋のすがた。秋のけしき。
しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ
秋の日光。
しゅう‐よう【修養】シウヤウ
(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」
しゅう‐よう【愁容】シウ‥
うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。
しゅう‐よう【醜容】シウ‥
みにくい容貌。醜貌。
しゅう‐よう【襲用】シフ‥
今までのやり方をそのままうけついで用いること。
じゅう‐よう【充用】
本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。
じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥
人を重く用いること。ちょうよう。
じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ
大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」
⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】
⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】
⇒じゅうよう‐し【重要視】
⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】
⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】
⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】
じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ
カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥
「参考人」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥
重要と認めること。重視。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥
(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。
しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥
人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。
⇒しゅう‐よう【収容】
しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ
(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。
じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥
1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥
「無形文化財」参照。
⇒じゅう‐よう【重要】
じゅうよく【十翼】ジフ‥
易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易
じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥
動物的な欲望。肉欲。
広辞苑 ページ 9372 での【○柔もまた茹わず剛もまた吐かず】単語。