複数辞典一括検索+![]()
![]()
つくばね‐うつぎ【衝羽根空木】🔗⭐🔉
つくばね‐うつぎ【衝羽根空木】
スイカズラ科の落葉低木。本州・四国・九州に自生し、庭木としても栽植。高さ1〜2メートル。葉は対生、卵形。花は筒状鐘形で、淡黄白色。萼片は5個、果実の頂に残存して全体がつくばね1状をなす。ウサギカクシ。
ツクバネウツギ(花)
撮影:関戸 勇
 ⇒つく‐ばね【衝羽根】
⇒つく‐ばね【衝羽根】
 ⇒つく‐ばね【衝羽根】
⇒つく‐ばね【衝羽根】
つくばね‐がし【衝羽根樫】🔗⭐🔉
つくばね‐がし【衝羽根樫】
ブナ科の常緑高木。西日本の山地に自生。高さ約20メートル。雌雄同株。長さ1センチメートル余の堅果(どんぐり)をつける。葉は枝端に集まり、(→)つくばね1に似る。材は建築・器具材。
⇒つく‐ばね【衝羽根】
つくばね‐そう【衝羽根草】‥サウ🔗⭐🔉
つくばね‐そう【衝羽根草】‥サウ
ユリ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は長楕円形、4枚が輪生し、つくばね1に似る。5〜6月頃頂上に淡黄緑色の花を開く。花弁状の4萼片があって花弁を欠く。花後、球形、紫黒色の液果を結ぶ。本種に似て6〜8枚のやや細い葉を輪生する別種をクルマバツクバネソウという。
つくばねそう
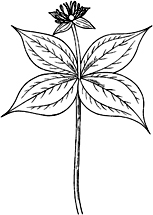 ⇒つく‐ばね【衝羽根】
⇒つく‐ばね【衝羽根】
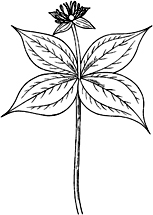 ⇒つく‐ばね【衝羽根】
⇒つく‐ばね【衝羽根】
つくば‐の‐みち【筑波の道】🔗⭐🔉
つくば‐の‐みち【筑波の道】
連歌の別称。日本武尊やまとたけるのみことが筑波を過ぎて甲斐国酒折宮さかおりのみやに着いた時、「新治にいばり筑波を過ぎて幾夜か寝つる」と歌ったのに対して、火ともしの翁が「かがなべて夜には九夜ここのよ日には十日を」と答えたのを、連歌の初めとしたことから。
⇒つくば【筑波】
広辞苑 ページ 13120。