複数辞典一括検索+![]()
![]()
○牛の一散うしのいっさん🔗⭐🔉
○牛の籠抜けうしのかごぬけ🔗⭐🔉
○牛の籠抜けうしのかごぬけ
鈍重なものには手ぎわのよいことはできないことのたとえ。
⇒うし【牛】
うじ‐の‐かみ【氏上・氏長・氏宗】ウヂ‥
氏の首長。大化改新以後は朝廷によって任命されるようになり、平安時代にかけては一族の宗家として、氏人を統率して朝廷に仕え、祖神の祭祀や叙爵推薦・処罰などをつかさどった。平安初期には宣旨によって氏長者うじのちょうじゃまたは氏長うじのおさという称を源・平・藤・橘の諸氏に賜ったが、室町時代以後は藤原氏の摂関となった者および源氏の征夷大将軍となった者だけがこれを称した。うじのこのかみ。
うじ‐の‐かんぱく【宇治関白】ウヂ‥クワン‥
藤原頼通の通称。宇治左大臣源融とおるの旧宅に居住したことによる。
うじ‐の‐きょ【氏挙】ウヂ‥
平安時代、正月6日の叙位の際、氏の長者がその氏人の叙位を申請したこと。→氏爵うじのしゃく
うし‐の‐くるま【牛の車】
〔仏〕声聞しょうもんや縁覚のための小乗の教えを羊や鹿の車にたとえるのに対し、大乗・一乗の教えを牛の車にたとえる。法華経譬喩品にある。→大白牛車だいびゃくごしゃ
うしのこく‐まいり【丑の刻参り】‥マヰリ
(→)「うしのときまいり」に同じ。
うじ‐の‐このかみ【氏上・氏長】ウヂ‥
(→)「うじのかみ」に同じ。天武紀下「因りて―賜ふ」
うし‐の‐した【牛舌魚】
ウシノシタ科の硬骨魚の総称。体は木の葉状で、尾端尖り、左側面に両眼がある。海底の泥の中に潜伏。アカシタビラメ・クロウシノシタなどがある。シタビラメ。鞋底魚。鰈鯊魚。謡曲、河水「白膾しらなます刺し身―」
くろうしのした
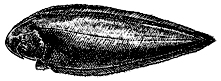 クロウシノシタ
提供:東京動物園協会
クロウシノシタ
提供:東京動物園協会
 うじ‐の‐しゃく【氏爵】ウヂ‥
氏挙うじのきょにより五位に叙せられること。
うじ‐の‐しん【氏の神】ウヂ‥
(→)氏神うじがみに同じ。狂言、拾ひ大黒「これは―より福の神を下されたと思ふが」
うし‐の‐そうめん【牛の索麺】‥サウ‥
ネナシカズラの異称。(物類称呼)
うし‐の‐たま【牛の玉】
①牛の額に生じた毛のかたまり。円く、中に堅いしんがある。牛の玉を牛王ごおうと誤って寺院などの宝物とする。
②牛黄ごおう。
うじ‐の‐ちょうじゃ【氏長者】ウヂ‥チヤウ‥
「うじのかみ」参照。
うし‐の‐つのつき【牛の角突き】
(→)「牛合せ」に同じ。
うしのつの‐もじ【牛の角文字】
(その形が牛の角に似るからいう)「い」の字のこと。一説に「ひ」の字。徒然草「二つもじ―すぐな文字」
うじ‐の‐しゃく【氏爵】ウヂ‥
氏挙うじのきょにより五位に叙せられること。
うじ‐の‐しん【氏の神】ウヂ‥
(→)氏神うじがみに同じ。狂言、拾ひ大黒「これは―より福の神を下されたと思ふが」
うし‐の‐そうめん【牛の索麺】‥サウ‥
ネナシカズラの異称。(物類称呼)
うし‐の‐たま【牛の玉】
①牛の額に生じた毛のかたまり。円く、中に堅いしんがある。牛の玉を牛王ごおうと誤って寺院などの宝物とする。
②牛黄ごおう。
うじ‐の‐ちょうじゃ【氏長者】ウヂ‥チヤウ‥
「うじのかみ」参照。
うし‐の‐つのつき【牛の角突き】
(→)「牛合せ」に同じ。
うしのつの‐もじ【牛の角文字】
(その形が牛の角に似るからいう)「い」の字のこと。一説に「ひ」の字。徒然草「二つもじ―すぐな文字」
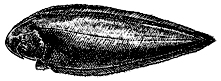 クロウシノシタ
提供:東京動物園協会
クロウシノシタ
提供:東京動物園協会
 うじ‐の‐しゃく【氏爵】ウヂ‥
氏挙うじのきょにより五位に叙せられること。
うじ‐の‐しん【氏の神】ウヂ‥
(→)氏神うじがみに同じ。狂言、拾ひ大黒「これは―より福の神を下されたと思ふが」
うし‐の‐そうめん【牛の索麺】‥サウ‥
ネナシカズラの異称。(物類称呼)
うし‐の‐たま【牛の玉】
①牛の額に生じた毛のかたまり。円く、中に堅いしんがある。牛の玉を牛王ごおうと誤って寺院などの宝物とする。
②牛黄ごおう。
うじ‐の‐ちょうじゃ【氏長者】ウヂ‥チヤウ‥
「うじのかみ」参照。
うし‐の‐つのつき【牛の角突き】
(→)「牛合せ」に同じ。
うしのつの‐もじ【牛の角文字】
(その形が牛の角に似るからいう)「い」の字のこと。一説に「ひ」の字。徒然草「二つもじ―すぐな文字」
うじ‐の‐しゃく【氏爵】ウヂ‥
氏挙うじのきょにより五位に叙せられること。
うじ‐の‐しん【氏の神】ウヂ‥
(→)氏神うじがみに同じ。狂言、拾ひ大黒「これは―より福の神を下されたと思ふが」
うし‐の‐そうめん【牛の索麺】‥サウ‥
ネナシカズラの異称。(物類称呼)
うし‐の‐たま【牛の玉】
①牛の額に生じた毛のかたまり。円く、中に堅いしんがある。牛の玉を牛王ごおうと誤って寺院などの宝物とする。
②牛黄ごおう。
うじ‐の‐ちょうじゃ【氏長者】ウヂ‥チヤウ‥
「うじのかみ」参照。
うし‐の‐つのつき【牛の角突き】
(→)「牛合せ」に同じ。
うしのつの‐もじ【牛の角文字】
(その形が牛の角に似るからいう)「い」の字のこと。一説に「ひ」の字。徒然草「二つもじ―すぐな文字」
広辞苑 ページ 1751。