複数辞典一括検索+![]()
![]()
おおあま‐の‐おうじ【大海人皇子】オホ‥ワウ‥🔗⭐🔉
おおあま‐の‐おうじ【大海人皇子】オホ‥ワウ‥
天武天皇の名。
おお‐うなばら【大海原】オホ‥🔗⭐🔉
おお‐うなばら【大海原】オホ‥
広々とした海。大海。
おお‐うみ【大海】オホ‥🔗⭐🔉
おお‐うみ【大海】オホ‥
①大きな海。
②織物や蒔絵に、大波・磯馴松そなれまつ・貝などの海辺の景をえがいた模様。海浦かいぶ。枕草子一本8「裳は―」
たい‐かい【大海】🔗⭐🔉
○大海の一粟たいかいのいちぞく🔗⭐🔉
○大海の一粟たいかいのいちぞく
広大な所に非常に小さいものがあることのたとえ。
⇒たい‐かい【大海】
○大海の一滴たいかいのいってき🔗⭐🔉
○大海の一滴たいかいのいってき
(→)「大海の一粟いちぞく」に同じ。
⇒たい‐かい【大海】
○大海は芥を択ばずたいかいはあくたをえらばず🔗⭐🔉
○大海は芥を択ばずたいかいはあくたをえらばず
度量が広く、どんな人をも受け入れることのたとえ。
⇒たい‐かい【大海】
○大海を手で塞ぐたいかいをてでふさぐ🔗⭐🔉
○大海を手で塞ぐたいかいをてでふさぐ
到底できないことをしようとすることのたとえ。大海を手でせく。
⇒たい‐かい【大海】
だい‐がえ【代替】‥ガヘ
(ダイカエとも)「だいたい」の重箱読み。
たいか‐きんゆう【滞貨金融】‥クワ‥
滞貨を担保にして融資を受けること。滞貨融資。
⇒たい‐か【滞貨】
たい‐かく【大角】
牛飼座うしかいざの首星アルクトゥールスの漢名。北斗七星の南方に橙色光を発して輝く。古来、方角や暦日を知る目標となる。夏の夕、頭上に輝く。二十八宿中の亢こう宿に属する。
たい‐かく【台閣】
(ダイカクとも)
①たかどの。楼閣。
②政治を行う官庁。内閣。「―に列なる」
たい‐かく【体格】
身体の組みたて。からだつき。筋肉・骨格および栄養状態に現れる身体の外観的形状の全体。「―がよい」
⇒たいかく‐けんさ【体格検査】
⇒たいかく‐しすう【体格指数】
たい‐かく【対角】
四辺形で、互いに向き合った角。また、三角形の一辺に対して向き合った角。
⇒たいかく‐せん【対角線】
たい‐かく【対客】
来客に対面すること。たいきゃく。
たい‐かく【対格】
〔言〕(accusative case)格の一つ。直接目的語がとる格。主に動作の対象を表す。名詞の特別の語形あるいは日本語の助詞「を」のような形式で表される。
たい‐かく【待客】
客を接待すること。お客をもてなすこと。
たい‐がく【大岳・大嶽】
大きい山。
たい‐がく【太学】
中国古代、官吏養成のための学校。前漢の武帝の時、始まる。大学。
たい‐がく【台岳】
①中国の天台山の異称。
②比叡山の異称。台嶺。
たい‐がく【怠学】
勉強を怠けて、学校に行かないこと。
たい‐がく【退学】
学生・生徒が、規定の年限を終わらずに学校をやめること。また、やめさせること。退校。「―処分」
だい‐かく【大覚】
①仏のさとり。大悟。
②正覚を得た人。ほとけ。如来。
⇒だいかく‐せそん【大覚世尊】
だい‐かく【台閣】
⇒たいかく
だい‐がく【大学】
①大学寮の略。源氏物語少女「―の道にしばし習はさむの本意ほい侍るにより」
②(university)学術の研究および教育の最高機関。起源は中世ヨーロッパの大学。教師(パリ大学)や学生(ボローニャ大学)のギルド的団体として発生し、近代国家の発展とともに19世紀以後今日のような形態となった。日本の大学は、明治以後欧米の大学を模範として設立されたもの。その後、1886年(明治19)の帝国大学令、1918年(大正7)の大学令などによって規定され、第二次大戦後は学制改革により学校教育法に基づいて設置され今日に至る。大学には学部のほか大学院を置くことができ、学部の修業年限は4年を原則とするが、ほかに2年または3年の短期大学もある。
(書名別項)
⇒だいがく‐いも【大学芋】
⇒だいがく‐いん【大学院】
⇒だいがくいん‐だいがく【大学院大学】
⇒だいがく‐せい【大学生】
⇒だいがく‐せっち‐きじゅん【大学設置基準】
⇒だいがく‐とうこう【大学東校】
⇒だいがく‐なんこう【大学南校】
⇒だいがく‐ノート【大学ノート】
⇒だいがく‐の‐かみ【大学頭】
⇒だいがく‐の‐じち【大学の自治】
⇒だいがく‐の‐しゅう【大学の衆】
⇒だいがく‐びょういん【大学病院】
⇒だいがくひょうか‐がくいじゅよ‐きこう【大学評価学位授与機構】
⇒だいがく‐ふんそう【大学紛争】
⇒だいがく‐べっそう【大学別曹】
⇒だいがく‐よびもん【大学予備門】
⇒だいがく‐りょう【大学寮】
⇒だいがく‐れい【大学令】
だいがく【大学】
儒教の経書。もと「礼記」の一編。唐の韓愈、宋の二程子に推重され、朱熹が章句を作って四書の一つとなる。明明徳・新民・止至善の三綱領と格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下の八条目を説く。
だい‐がく【大楽】
①雅楽寮ががくりょうの唐名。
②多人数で音楽を奏すること。
だい‐がく【題額】
①額に詩や文章を書くこと。
②氏名や山号などを記して戸口・門などに掲げた額。
だいがく‐いも【大学芋】
乱切りにしたサツマイモを油で揚げ、砂糖蜜をからめて炒りごまをまぶした食品。一説に、大正から昭和にかけて、学生街で好まれたことからの名。
大学芋
撮影:関戸 勇
 ⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐いん【大学院】‥ヰン
一般に大学の学部の上に置かれ、高度の専門的教育・研究を行い、学士より上の学位の授与権をもつ機関。修士課程・博士課程の2段階があり、学術の教育・研究を主とする大学院(アメリカのgraduate schoolに相当)と高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院(アメリカのprofessional schoolに相当)がある。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくいん‐だいがく【大学院大学】‥ヰン‥
学部を持たない大学院だけの大学。1988年創設の総合研究大学院大学が嚆矢こうし。独立大学院。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐けんさ【体格検査】
体格の良否を検査すること。身体検査。
⇒たい‐かく【体格】
だいかく‐じ【大覚寺】
京都市右京区嵯峨にある古義真言宗の大本山。もと嵯峨天皇の離宮であったが、876年(貞観18)淳和天皇の皇后正子が寺とし、恒寂入道親王を開山とする。以後、親王が入寺して門跡寺となる。後宇多法皇以後南北朝時代には南朝の皇統が入寺。嵯峨御所。
大覚寺と大沢池
撮影:新海良夫
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐いん【大学院】‥ヰン
一般に大学の学部の上に置かれ、高度の専門的教育・研究を行い、学士より上の学位の授与権をもつ機関。修士課程・博士課程の2段階があり、学術の教育・研究を主とする大学院(アメリカのgraduate schoolに相当)と高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院(アメリカのprofessional schoolに相当)がある。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくいん‐だいがく【大学院大学】‥ヰン‥
学部を持たない大学院だけの大学。1988年創設の総合研究大学院大学が嚆矢こうし。独立大学院。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐けんさ【体格検査】
体格の良否を検査すること。身体検査。
⇒たい‐かく【体格】
だいかく‐じ【大覚寺】
京都市右京区嵯峨にある古義真言宗の大本山。もと嵯峨天皇の離宮であったが、876年(貞観18)淳和天皇の皇后正子が寺とし、恒寂入道親王を開山とする。以後、親王が入寺して門跡寺となる。後宇多法皇以後南北朝時代には南朝の皇統が入寺。嵯峨御所。
大覚寺と大沢池
撮影:新海良夫
 ⇒だいかくじ‐とう【大覚寺統】
⇒だいかくじ‐は【大覚寺派】
だい‐がくし【大学士】
中国の官名。内閣大学士の略称。宋代まで宰相の兼任であった殿閣大学士を明代に内閣大学士と改称。宰相の廃止に伴い6人の大学士が次第に宰相の実を帯びるに至った。清代にも踏襲。
たいかく‐しすう【体格指数】
(→)BMIに同じ。
⇒たい‐かく【体格】
だいかくじ‐とう【大覚寺統】
亀山天皇の血統。持明院統(兄の後深草天皇の血統)と交替で皇位を継ぎ、吉野の南朝4代はこの子孫。後宇多法皇が大覚寺を仙洞せんとうとしたことからこの名称が起こる。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だいかくじ‐は【大覚寺派】
真言宗の一派。京都大覚寺を本山とする。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だい‐がくしゃ【大学者】
非常にすぐれた学者。
だいがく‐せい【大学生】
大学の学生。
⇒だい‐がく【大学】
だいかく‐せそん【大覚世尊】
(大覚と世尊との合成語)仏の敬称。大覚尊。
⇒だい‐かく【大覚】
だいがく‐せっち‐きじゅん【大学設置基準】
大学設置に必要な最低の基準を定めた文部科学省令。学校教育法に基づき、1956年制定。91年大幅に緩和された。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐せん【対角線】
多角形の隣り合っていない二つの頂点を結ぶ直線。また多面体で、同一の面上にない二つの頂点を結ぶ直線。
⇒たい‐かく【対角】
だいがく‐とうこう【大学東校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1858年(安政5)設立の種痘所が、その後、西洋医学所・医学所と改称され、68年(明治1)医学校、69年大学東校。その後、71年東校、72年第一大学区医学校、74年東京医学校を経て77年東京大学の医学部となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐なんこう【大学南校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1869年(明治2)に開成学校(開成所)を大学南校と改称。その後、71年南校、73年開成学校、74年東京開成学校を経て77年東京大学となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ノート【大学ノート】
大判の筆記帳。通常B5判の大きさ。大学生が使うのでいう。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐かみ【大学頭】
大学寮の長官。また、江戸時代、林羅山の孫鳳岡が従五位に叙せられ大学頭と称してから、林氏が代々任ぜられ、幕府の学問所の一切を統轄した。国子祭酒。祭酒。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐じち【大学の自治】
大学が政治上・宗教上その他の権力または勢力の干渉を受けることなく、全構成員の意志に基づいて研究と教育の自由を行使すること。→学問の自由。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐しゅう【大学の衆】
律令制の大学の学生がくしょう。篁物語「異腹の子の―にてありけり」
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐びょういん【大学病院】‥ビヤウヰン
大学の医学部または医科大学が設置・運営する病院。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくひょうか‐がくいじゅよ‐きこう【大学評価学位授与機構】‥ヒヤウ‥ヰ‥
独立行政法人の一つ。大学等の教育研究活動の評価と、大学以外で行われる高等教育の学生に対する学位の授与を行う。1991年学位授与機構として設立。2000年現機構に改組、04年法人化。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ふんそう【大学紛争】‥サウ
大学のあり方に不満を抱く学生と、大学当局との間で起こる紛争。日本では、1960年代後半に頻発した。
大学紛争
提供:NHK
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐べっそう【大学別曹】‥サウ
(曹は曹司ぞうしの意)平安時代、貴族がその一族出身の大学寮学生のために設けた公認の寄宿施設。奨学院・勧学院・学館院など。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐よびもん【大学予備門】
①(→)予備校2に同じ。
②東京大学予備門。1877年設立。第一高等中学校(後の旧制第一高等学校)の前身。
⇒だい‐がく【大学】
だい‐かぐら【太神楽】
①伊勢神宮に奉納する神楽。だいだいかぐら。
②雑芸の一種。獅子舞のほか、品玉しなだま・皿回しなどの曲芸を演ずるもの。1から出た。大道神楽。代神楽。〈[季]新年〉。好色五人女1「曲太鼓きょくだいこ―の来り」
太神楽
⇒だいかくじ‐とう【大覚寺統】
⇒だいかくじ‐は【大覚寺派】
だい‐がくし【大学士】
中国の官名。内閣大学士の略称。宋代まで宰相の兼任であった殿閣大学士を明代に内閣大学士と改称。宰相の廃止に伴い6人の大学士が次第に宰相の実を帯びるに至った。清代にも踏襲。
たいかく‐しすう【体格指数】
(→)BMIに同じ。
⇒たい‐かく【体格】
だいかくじ‐とう【大覚寺統】
亀山天皇の血統。持明院統(兄の後深草天皇の血統)と交替で皇位を継ぎ、吉野の南朝4代はこの子孫。後宇多法皇が大覚寺を仙洞せんとうとしたことからこの名称が起こる。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だいかくじ‐は【大覚寺派】
真言宗の一派。京都大覚寺を本山とする。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だい‐がくしゃ【大学者】
非常にすぐれた学者。
だいがく‐せい【大学生】
大学の学生。
⇒だい‐がく【大学】
だいかく‐せそん【大覚世尊】
(大覚と世尊との合成語)仏の敬称。大覚尊。
⇒だい‐かく【大覚】
だいがく‐せっち‐きじゅん【大学設置基準】
大学設置に必要な最低の基準を定めた文部科学省令。学校教育法に基づき、1956年制定。91年大幅に緩和された。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐せん【対角線】
多角形の隣り合っていない二つの頂点を結ぶ直線。また多面体で、同一の面上にない二つの頂点を結ぶ直線。
⇒たい‐かく【対角】
だいがく‐とうこう【大学東校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1858年(安政5)設立の種痘所が、その後、西洋医学所・医学所と改称され、68年(明治1)医学校、69年大学東校。その後、71年東校、72年第一大学区医学校、74年東京医学校を経て77年東京大学の医学部となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐なんこう【大学南校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1869年(明治2)に開成学校(開成所)を大学南校と改称。その後、71年南校、73年開成学校、74年東京開成学校を経て77年東京大学となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ノート【大学ノート】
大判の筆記帳。通常B5判の大きさ。大学生が使うのでいう。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐かみ【大学頭】
大学寮の長官。また、江戸時代、林羅山の孫鳳岡が従五位に叙せられ大学頭と称してから、林氏が代々任ぜられ、幕府の学問所の一切を統轄した。国子祭酒。祭酒。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐じち【大学の自治】
大学が政治上・宗教上その他の権力または勢力の干渉を受けることなく、全構成員の意志に基づいて研究と教育の自由を行使すること。→学問の自由。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐しゅう【大学の衆】
律令制の大学の学生がくしょう。篁物語「異腹の子の―にてありけり」
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐びょういん【大学病院】‥ビヤウヰン
大学の医学部または医科大学が設置・運営する病院。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくひょうか‐がくいじゅよ‐きこう【大学評価学位授与機構】‥ヒヤウ‥ヰ‥
独立行政法人の一つ。大学等の教育研究活動の評価と、大学以外で行われる高等教育の学生に対する学位の授与を行う。1991年学位授与機構として設立。2000年現機構に改組、04年法人化。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ふんそう【大学紛争】‥サウ
大学のあり方に不満を抱く学生と、大学当局との間で起こる紛争。日本では、1960年代後半に頻発した。
大学紛争
提供:NHK
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐べっそう【大学別曹】‥サウ
(曹は曹司ぞうしの意)平安時代、貴族がその一族出身の大学寮学生のために設けた公認の寄宿施設。奨学院・勧学院・学館院など。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐よびもん【大学予備門】
①(→)予備校2に同じ。
②東京大学予備門。1877年設立。第一高等中学校(後の旧制第一高等学校)の前身。
⇒だい‐がく【大学】
だい‐かぐら【太神楽】
①伊勢神宮に奉納する神楽。だいだいかぐら。
②雑芸の一種。獅子舞のほか、品玉しなだま・皿回しなどの曲芸を演ずるもの。1から出た。大道神楽。代神楽。〈[季]新年〉。好色五人女1「曲太鼓きょくだいこ―の来り」
太神楽
 ③〔建〕(→)御神楽おかぐら2に同じ。
だいがく‐りょう【大学寮】‥レウ
律令制で、式部省に属する官吏養成機関。はじめ経学・算、のち紀伝・明経・明法・算道の四道を博士・助教らが五位以上の貴族の子弟ほかの学生に教授し、兼ねてこれに関する事務一切をつかさどった。文屋司ふみやづかさ。おおつかさ。大学。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐れい【大学令】
旧制の官立・公立・私立各大学について、その目的・組織および監督の規定を設けた勅令。1918年(大正7)公布。第二次大戦後、学校教育法などがこれに代わって施行。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくわくもん【大学或問】
経世書。熊沢蕃山著。2巻。清の日本侵攻が必至という危機感を根底に、幕府に政治のあり方を述べた上申書を、問答体に書き改めたもの。1687年(貞享4)頃成立。この書のために蕃山は幕府により下総古河に幽閉された。別名「経済弁」。
たいか‐けんちく【耐火建築】‥クワ‥
火災に耐えうる建築。耐火材料を用いた建築。火災の場合、類焼することなく、また、内部が焼失しても補修により使用できるもの。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かこ【大過去】‥クワ‥
(plus-que-parfait フランス)インド‐ヨーロッパ語などの時間表現の一つ。過去の一時点を基準にして、出来事や動作がその時点以前に終了し、その帰結が何らかの形でその時点まで及んでいることを表す。過去完了。
たいか‐こうぞう【耐火構造】‥クワ‥ザウ
建築物の部分について、所要の耐火性能を持つもの。鉄筋コンクリート構造など。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐がさ【台笠】
大名行列などのとき、袋に入れて棒をつけ、供の者に持たせた被笠かぶりがさ。→たてがさ
台笠
③〔建〕(→)御神楽おかぐら2に同じ。
だいがく‐りょう【大学寮】‥レウ
律令制で、式部省に属する官吏養成機関。はじめ経学・算、のち紀伝・明経・明法・算道の四道を博士・助教らが五位以上の貴族の子弟ほかの学生に教授し、兼ねてこれに関する事務一切をつかさどった。文屋司ふみやづかさ。おおつかさ。大学。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐れい【大学令】
旧制の官立・公立・私立各大学について、その目的・組織および監督の規定を設けた勅令。1918年(大正7)公布。第二次大戦後、学校教育法などがこれに代わって施行。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくわくもん【大学或問】
経世書。熊沢蕃山著。2巻。清の日本侵攻が必至という危機感を根底に、幕府に政治のあり方を述べた上申書を、問答体に書き改めたもの。1687年(貞享4)頃成立。この書のために蕃山は幕府により下総古河に幽閉された。別名「経済弁」。
たいか‐けんちく【耐火建築】‥クワ‥
火災に耐えうる建築。耐火材料を用いた建築。火災の場合、類焼することなく、また、内部が焼失しても補修により使用できるもの。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かこ【大過去】‥クワ‥
(plus-que-parfait フランス)インド‐ヨーロッパ語などの時間表現の一つ。過去の一時点を基準にして、出来事や動作がその時点以前に終了し、その帰結が何らかの形でその時点まで及んでいることを表す。過去完了。
たいか‐こうぞう【耐火構造】‥クワ‥ザウ
建築物の部分について、所要の耐火性能を持つもの。鉄筋コンクリート構造など。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐がさ【台笠】
大名行列などのとき、袋に入れて棒をつけ、供の者に持たせた被笠かぶりがさ。→たてがさ
台笠
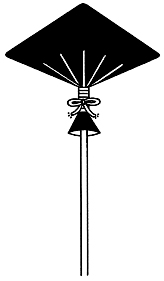 たいか‐ざいりょう【耐火材料】‥クワ‥レウ
火災による高温に耐えうる材料。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かし【代貸】
(ダイガシとも)貸元の代理。
だい‐かしょう【大和尚・大和上】‥クワシヤウ
⇒だいおしょう
たいが‐しょうせつ【大河小説】‥セウ‥
(roman-fleuve フランス)一群の人々の歴史を、数世代にわたって、社会的背景から書いた小説。20世紀前半に続出した。マルタン=デュ=ガールの「チボー家の人々」など。
⇒たい‐が【大河】
だい‐がしら【大頭】
幸若こうわか舞の一流派。名の由来に諸説があるが不確定。現存する福岡県みやま市瀬高町の幸若舞はこの末流という。→幸若舞
ダイカスト
(die-casting)鋳造ちゅうぞう法の一つ。アルミニウム合金・亜鉛合金などを溶融したものを、圧力によって特殊鋼の精密な金型(ダイス)に圧し込んで鋳物を得る方法。寸法が正確で仕上げがほとんど不要、かつ機械的性質が優秀で、大量生産に適する。ダイキャスト。
たいか‐ぜんだい【大化前代】‥クワ‥
古代の時期区分の一つ。氏姓制度の矛盾が激化し官司制度が進展した大和時代末期、6〜7世紀の頃を指す。
⇒たいか【大化】
だい‐かぞく【大家族】
①多人数の家族。
②一対の夫婦とその子供以外に、傍系血族とその配偶者までも含んでいる家父長制的家族。「―制」
たい‐がため【体固め】
レスリングの技の一つ。相手をいったんうつ伏せに抑え、腕と足を使って仰向けに返して固める。
だい‐かつ【大喝】
大声で叱りつけること。
⇒だいかつ‐いっせい【大喝一声】
だいかつ‐いっせい【大喝一声】
大きなひと声で叱りつけること。正岡子規、月の都「修行の妨すなと―」
⇒だい‐かつ【大喝】
だい‐がっく【大学区】‥ガク‥
①1872年(明治5)の学制に定められた大学校設置の区域。また同時に教育行政の単位区画。初めは全国を8大学区とし、後に7大学区に改めた。→学区。
②小さい地域の学区(小学区)に対して大きい地域の学区。
だい‐かっこ【大括弧】‥クワツ‥
角かく括弧。ブラケット。[ ] 数式で、小括弧・中括弧よりも大きなくくりを示す。
だい‐がっこう【大学校】‥ガクカウ
学校教育法(旧制では大学令)によらないで、省庁など行政機関が管轄している大学程度の学校。気象大学校・防衛大学校など。第二次大戦前では陸軍大学校・海軍大学校。
たいか‐ど【耐火度】‥クワ‥
耐火の程度を示す度合。その物質が軟化変形をおこす温度で表し、ふつうはゼーゲル錐すいの溶融する温度と比較する。
⇒たい‐か【耐火】
たいが‐どう【大雅堂】‥ダウ
①池大雅の号。
②池大雅の旧居。京都東山双林寺の境内にあった。
⇒たいが【大雅】
たいが‐ドラマ【大河ドラマ】
NHKのテレビ番組。1年間かけて放送する歴史ドラマの称。第1作は1963年の「花の生涯」。大河小説にちなんだ名称とも。
⇒たい‐が【大河】
たいか‐にじゅういっかじょう‐ようきゅう【対華二十一カ条要求】‥クワ‥ジフ‥デウエウキウ
(→)二十一カ条要求に同じ。
たいか‐ねんど【耐火粘土】‥クワ‥
高熱を加えても溶融しないため、耐火煉瓦・坩堝るつぼなどの製造に用いられる粘土。アルミナを多量に含む。木節きぶし粘土の類。
⇒たい‐か【耐火】
たいか‐の‐かいしん【大化改新】‥クワ‥
大化元年(645)夏、中大兄皇子(のちの天智天皇)を中心に、中臣(藤原)鎌足ら革新的な豪族が蘇我大臣家を滅ぼして開始した古代政治史上の大改革。孝徳天皇を立て都を難波に移し、翌春、私有地・私有民の廃止、国・郡・里制による地方行政権の中央集中、戸籍の作成や耕地の調査による班田収授法の実施、調・庸など税制の統一、の4綱目から成る改新の詔みことのりを公布、古代東アジア的な中央集権国家成立の出発点となった。しかし、律令国家の形成には、壬申の乱(672年)後の天武・持統朝の改革が必要であった。大化新政。大化革新。
→文献資料[改新の詔]
⇒たいか【大化】
たいか‐ざいりょう【耐火材料】‥クワ‥レウ
火災による高温に耐えうる材料。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かし【代貸】
(ダイガシとも)貸元の代理。
だい‐かしょう【大和尚・大和上】‥クワシヤウ
⇒だいおしょう
たいが‐しょうせつ【大河小説】‥セウ‥
(roman-fleuve フランス)一群の人々の歴史を、数世代にわたって、社会的背景から書いた小説。20世紀前半に続出した。マルタン=デュ=ガールの「チボー家の人々」など。
⇒たい‐が【大河】
だい‐がしら【大頭】
幸若こうわか舞の一流派。名の由来に諸説があるが不確定。現存する福岡県みやま市瀬高町の幸若舞はこの末流という。→幸若舞
ダイカスト
(die-casting)鋳造ちゅうぞう法の一つ。アルミニウム合金・亜鉛合金などを溶融したものを、圧力によって特殊鋼の精密な金型(ダイス)に圧し込んで鋳物を得る方法。寸法が正確で仕上げがほとんど不要、かつ機械的性質が優秀で、大量生産に適する。ダイキャスト。
たいか‐ぜんだい【大化前代】‥クワ‥
古代の時期区分の一つ。氏姓制度の矛盾が激化し官司制度が進展した大和時代末期、6〜7世紀の頃を指す。
⇒たいか【大化】
だい‐かぞく【大家族】
①多人数の家族。
②一対の夫婦とその子供以外に、傍系血族とその配偶者までも含んでいる家父長制的家族。「―制」
たい‐がため【体固め】
レスリングの技の一つ。相手をいったんうつ伏せに抑え、腕と足を使って仰向けに返して固める。
だい‐かつ【大喝】
大声で叱りつけること。
⇒だいかつ‐いっせい【大喝一声】
だいかつ‐いっせい【大喝一声】
大きなひと声で叱りつけること。正岡子規、月の都「修行の妨すなと―」
⇒だい‐かつ【大喝】
だい‐がっく【大学区】‥ガク‥
①1872年(明治5)の学制に定められた大学校設置の区域。また同時に教育行政の単位区画。初めは全国を8大学区とし、後に7大学区に改めた。→学区。
②小さい地域の学区(小学区)に対して大きい地域の学区。
だい‐かっこ【大括弧】‥クワツ‥
角かく括弧。ブラケット。[ ] 数式で、小括弧・中括弧よりも大きなくくりを示す。
だい‐がっこう【大学校】‥ガクカウ
学校教育法(旧制では大学令)によらないで、省庁など行政機関が管轄している大学程度の学校。気象大学校・防衛大学校など。第二次大戦前では陸軍大学校・海軍大学校。
たいか‐ど【耐火度】‥クワ‥
耐火の程度を示す度合。その物質が軟化変形をおこす温度で表し、ふつうはゼーゲル錐すいの溶融する温度と比較する。
⇒たい‐か【耐火】
たいが‐どう【大雅堂】‥ダウ
①池大雅の号。
②池大雅の旧居。京都東山双林寺の境内にあった。
⇒たいが【大雅】
たいが‐ドラマ【大河ドラマ】
NHKのテレビ番組。1年間かけて放送する歴史ドラマの称。第1作は1963年の「花の生涯」。大河小説にちなんだ名称とも。
⇒たい‐が【大河】
たいか‐にじゅういっかじょう‐ようきゅう【対華二十一カ条要求】‥クワ‥ジフ‥デウエウキウ
(→)二十一カ条要求に同じ。
たいか‐ねんど【耐火粘土】‥クワ‥
高熱を加えても溶融しないため、耐火煉瓦・坩堝るつぼなどの製造に用いられる粘土。アルミナを多量に含む。木節きぶし粘土の類。
⇒たい‐か【耐火】
たいか‐の‐かいしん【大化改新】‥クワ‥
大化元年(645)夏、中大兄皇子(のちの天智天皇)を中心に、中臣(藤原)鎌足ら革新的な豪族が蘇我大臣家を滅ぼして開始した古代政治史上の大改革。孝徳天皇を立て都を難波に移し、翌春、私有地・私有民の廃止、国・郡・里制による地方行政権の中央集中、戸籍の作成や耕地の調査による班田収授法の実施、調・庸など税制の統一、の4綱目から成る改新の詔みことのりを公布、古代東アジア的な中央集権国家成立の出発点となった。しかし、律令国家の形成には、壬申の乱(672年)後の天武・持統朝の改革が必要であった。大化新政。大化革新。
→文献資料[改新の詔]
⇒たいか【大化】
 ⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐いん【大学院】‥ヰン
一般に大学の学部の上に置かれ、高度の専門的教育・研究を行い、学士より上の学位の授与権をもつ機関。修士課程・博士課程の2段階があり、学術の教育・研究を主とする大学院(アメリカのgraduate schoolに相当)と高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院(アメリカのprofessional schoolに相当)がある。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくいん‐だいがく【大学院大学】‥ヰン‥
学部を持たない大学院だけの大学。1988年創設の総合研究大学院大学が嚆矢こうし。独立大学院。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐けんさ【体格検査】
体格の良否を検査すること。身体検査。
⇒たい‐かく【体格】
だいかく‐じ【大覚寺】
京都市右京区嵯峨にある古義真言宗の大本山。もと嵯峨天皇の離宮であったが、876年(貞観18)淳和天皇の皇后正子が寺とし、恒寂入道親王を開山とする。以後、親王が入寺して門跡寺となる。後宇多法皇以後南北朝時代には南朝の皇統が入寺。嵯峨御所。
大覚寺と大沢池
撮影:新海良夫
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐いん【大学院】‥ヰン
一般に大学の学部の上に置かれ、高度の専門的教育・研究を行い、学士より上の学位の授与権をもつ機関。修士課程・博士課程の2段階があり、学術の教育・研究を主とする大学院(アメリカのgraduate schoolに相当)と高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院(アメリカのprofessional schoolに相当)がある。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくいん‐だいがく【大学院大学】‥ヰン‥
学部を持たない大学院だけの大学。1988年創設の総合研究大学院大学が嚆矢こうし。独立大学院。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐けんさ【体格検査】
体格の良否を検査すること。身体検査。
⇒たい‐かく【体格】
だいかく‐じ【大覚寺】
京都市右京区嵯峨にある古義真言宗の大本山。もと嵯峨天皇の離宮であったが、876年(貞観18)淳和天皇の皇后正子が寺とし、恒寂入道親王を開山とする。以後、親王が入寺して門跡寺となる。後宇多法皇以後南北朝時代には南朝の皇統が入寺。嵯峨御所。
大覚寺と大沢池
撮影:新海良夫
 ⇒だいかくじ‐とう【大覚寺統】
⇒だいかくじ‐は【大覚寺派】
だい‐がくし【大学士】
中国の官名。内閣大学士の略称。宋代まで宰相の兼任であった殿閣大学士を明代に内閣大学士と改称。宰相の廃止に伴い6人の大学士が次第に宰相の実を帯びるに至った。清代にも踏襲。
たいかく‐しすう【体格指数】
(→)BMIに同じ。
⇒たい‐かく【体格】
だいかくじ‐とう【大覚寺統】
亀山天皇の血統。持明院統(兄の後深草天皇の血統)と交替で皇位を継ぎ、吉野の南朝4代はこの子孫。後宇多法皇が大覚寺を仙洞せんとうとしたことからこの名称が起こる。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だいかくじ‐は【大覚寺派】
真言宗の一派。京都大覚寺を本山とする。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だい‐がくしゃ【大学者】
非常にすぐれた学者。
だいがく‐せい【大学生】
大学の学生。
⇒だい‐がく【大学】
だいかく‐せそん【大覚世尊】
(大覚と世尊との合成語)仏の敬称。大覚尊。
⇒だい‐かく【大覚】
だいがく‐せっち‐きじゅん【大学設置基準】
大学設置に必要な最低の基準を定めた文部科学省令。学校教育法に基づき、1956年制定。91年大幅に緩和された。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐せん【対角線】
多角形の隣り合っていない二つの頂点を結ぶ直線。また多面体で、同一の面上にない二つの頂点を結ぶ直線。
⇒たい‐かく【対角】
だいがく‐とうこう【大学東校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1858年(安政5)設立の種痘所が、その後、西洋医学所・医学所と改称され、68年(明治1)医学校、69年大学東校。その後、71年東校、72年第一大学区医学校、74年東京医学校を経て77年東京大学の医学部となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐なんこう【大学南校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1869年(明治2)に開成学校(開成所)を大学南校と改称。その後、71年南校、73年開成学校、74年東京開成学校を経て77年東京大学となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ノート【大学ノート】
大判の筆記帳。通常B5判の大きさ。大学生が使うのでいう。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐かみ【大学頭】
大学寮の長官。また、江戸時代、林羅山の孫鳳岡が従五位に叙せられ大学頭と称してから、林氏が代々任ぜられ、幕府の学問所の一切を統轄した。国子祭酒。祭酒。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐じち【大学の自治】
大学が政治上・宗教上その他の権力または勢力の干渉を受けることなく、全構成員の意志に基づいて研究と教育の自由を行使すること。→学問の自由。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐しゅう【大学の衆】
律令制の大学の学生がくしょう。篁物語「異腹の子の―にてありけり」
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐びょういん【大学病院】‥ビヤウヰン
大学の医学部または医科大学が設置・運営する病院。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくひょうか‐がくいじゅよ‐きこう【大学評価学位授与機構】‥ヒヤウ‥ヰ‥
独立行政法人の一つ。大学等の教育研究活動の評価と、大学以外で行われる高等教育の学生に対する学位の授与を行う。1991年学位授与機構として設立。2000年現機構に改組、04年法人化。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ふんそう【大学紛争】‥サウ
大学のあり方に不満を抱く学生と、大学当局との間で起こる紛争。日本では、1960年代後半に頻発した。
大学紛争
提供:NHK
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐べっそう【大学別曹】‥サウ
(曹は曹司ぞうしの意)平安時代、貴族がその一族出身の大学寮学生のために設けた公認の寄宿施設。奨学院・勧学院・学館院など。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐よびもん【大学予備門】
①(→)予備校2に同じ。
②東京大学予備門。1877年設立。第一高等中学校(後の旧制第一高等学校)の前身。
⇒だい‐がく【大学】
だい‐かぐら【太神楽】
①伊勢神宮に奉納する神楽。だいだいかぐら。
②雑芸の一種。獅子舞のほか、品玉しなだま・皿回しなどの曲芸を演ずるもの。1から出た。大道神楽。代神楽。〈[季]新年〉。好色五人女1「曲太鼓きょくだいこ―の来り」
太神楽
⇒だいかくじ‐とう【大覚寺統】
⇒だいかくじ‐は【大覚寺派】
だい‐がくし【大学士】
中国の官名。内閣大学士の略称。宋代まで宰相の兼任であった殿閣大学士を明代に内閣大学士と改称。宰相の廃止に伴い6人の大学士が次第に宰相の実を帯びるに至った。清代にも踏襲。
たいかく‐しすう【体格指数】
(→)BMIに同じ。
⇒たい‐かく【体格】
だいかくじ‐とう【大覚寺統】
亀山天皇の血統。持明院統(兄の後深草天皇の血統)と交替で皇位を継ぎ、吉野の南朝4代はこの子孫。後宇多法皇が大覚寺を仙洞せんとうとしたことからこの名称が起こる。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だいかくじ‐は【大覚寺派】
真言宗の一派。京都大覚寺を本山とする。
⇒だいかく‐じ【大覚寺】
だい‐がくしゃ【大学者】
非常にすぐれた学者。
だいがく‐せい【大学生】
大学の学生。
⇒だい‐がく【大学】
だいかく‐せそん【大覚世尊】
(大覚と世尊との合成語)仏の敬称。大覚尊。
⇒だい‐かく【大覚】
だいがく‐せっち‐きじゅん【大学設置基準】
大学設置に必要な最低の基準を定めた文部科学省令。学校教育法に基づき、1956年制定。91年大幅に緩和された。
⇒だい‐がく【大学】
たいかく‐せん【対角線】
多角形の隣り合っていない二つの頂点を結ぶ直線。また多面体で、同一の面上にない二つの頂点を結ぶ直線。
⇒たい‐かく【対角】
だいがく‐とうこう【大学東校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1858年(安政5)設立の種痘所が、その後、西洋医学所・医学所と改称され、68年(明治1)医学校、69年大学東校。その後、71年東校、72年第一大学区医学校、74年東京医学校を経て77年東京大学の医学部となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐なんこう【大学南校】‥カウ
東京大学の前身の一つ。1869年(明治2)に開成学校(開成所)を大学南校と改称。その後、71年南校、73年開成学校、74年東京開成学校を経て77年東京大学となる。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ノート【大学ノート】
大判の筆記帳。通常B5判の大きさ。大学生が使うのでいう。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐かみ【大学頭】
大学寮の長官。また、江戸時代、林羅山の孫鳳岡が従五位に叙せられ大学頭と称してから、林氏が代々任ぜられ、幕府の学問所の一切を統轄した。国子祭酒。祭酒。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐じち【大学の自治】
大学が政治上・宗教上その他の権力または勢力の干渉を受けることなく、全構成員の意志に基づいて研究と教育の自由を行使すること。→学問の自由。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐の‐しゅう【大学の衆】
律令制の大学の学生がくしょう。篁物語「異腹の子の―にてありけり」
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐びょういん【大学病院】‥ビヤウヰン
大学の医学部または医科大学が設置・運営する病院。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくひょうか‐がくいじゅよ‐きこう【大学評価学位授与機構】‥ヒヤウ‥ヰ‥
独立行政法人の一つ。大学等の教育研究活動の評価と、大学以外で行われる高等教育の学生に対する学位の授与を行う。1991年学位授与機構として設立。2000年現機構に改組、04年法人化。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐ふんそう【大学紛争】‥サウ
大学のあり方に不満を抱く学生と、大学当局との間で起こる紛争。日本では、1960年代後半に頻発した。
大学紛争
提供:NHK
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐べっそう【大学別曹】‥サウ
(曹は曹司ぞうしの意)平安時代、貴族がその一族出身の大学寮学生のために設けた公認の寄宿施設。奨学院・勧学院・学館院など。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐よびもん【大学予備門】
①(→)予備校2に同じ。
②東京大学予備門。1877年設立。第一高等中学校(後の旧制第一高等学校)の前身。
⇒だい‐がく【大学】
だい‐かぐら【太神楽】
①伊勢神宮に奉納する神楽。だいだいかぐら。
②雑芸の一種。獅子舞のほか、品玉しなだま・皿回しなどの曲芸を演ずるもの。1から出た。大道神楽。代神楽。〈[季]新年〉。好色五人女1「曲太鼓きょくだいこ―の来り」
太神楽
 ③〔建〕(→)御神楽おかぐら2に同じ。
だいがく‐りょう【大学寮】‥レウ
律令制で、式部省に属する官吏養成機関。はじめ経学・算、のち紀伝・明経・明法・算道の四道を博士・助教らが五位以上の貴族の子弟ほかの学生に教授し、兼ねてこれに関する事務一切をつかさどった。文屋司ふみやづかさ。おおつかさ。大学。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐れい【大学令】
旧制の官立・公立・私立各大学について、その目的・組織および監督の規定を設けた勅令。1918年(大正7)公布。第二次大戦後、学校教育法などがこれに代わって施行。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくわくもん【大学或問】
経世書。熊沢蕃山著。2巻。清の日本侵攻が必至という危機感を根底に、幕府に政治のあり方を述べた上申書を、問答体に書き改めたもの。1687年(貞享4)頃成立。この書のために蕃山は幕府により下総古河に幽閉された。別名「経済弁」。
たいか‐けんちく【耐火建築】‥クワ‥
火災に耐えうる建築。耐火材料を用いた建築。火災の場合、類焼することなく、また、内部が焼失しても補修により使用できるもの。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かこ【大過去】‥クワ‥
(plus-que-parfait フランス)インド‐ヨーロッパ語などの時間表現の一つ。過去の一時点を基準にして、出来事や動作がその時点以前に終了し、その帰結が何らかの形でその時点まで及んでいることを表す。過去完了。
たいか‐こうぞう【耐火構造】‥クワ‥ザウ
建築物の部分について、所要の耐火性能を持つもの。鉄筋コンクリート構造など。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐がさ【台笠】
大名行列などのとき、袋に入れて棒をつけ、供の者に持たせた被笠かぶりがさ。→たてがさ
台笠
③〔建〕(→)御神楽おかぐら2に同じ。
だいがく‐りょう【大学寮】‥レウ
律令制で、式部省に属する官吏養成機関。はじめ経学・算、のち紀伝・明経・明法・算道の四道を博士・助教らが五位以上の貴族の子弟ほかの学生に教授し、兼ねてこれに関する事務一切をつかさどった。文屋司ふみやづかさ。おおつかさ。大学。
⇒だい‐がく【大学】
だいがく‐れい【大学令】
旧制の官立・公立・私立各大学について、その目的・組織および監督の規定を設けた勅令。1918年(大正7)公布。第二次大戦後、学校教育法などがこれに代わって施行。
⇒だい‐がく【大学】
だいがくわくもん【大学或問】
経世書。熊沢蕃山著。2巻。清の日本侵攻が必至という危機感を根底に、幕府に政治のあり方を述べた上申書を、問答体に書き改めたもの。1687年(貞享4)頃成立。この書のために蕃山は幕府により下総古河に幽閉された。別名「経済弁」。
たいか‐けんちく【耐火建築】‥クワ‥
火災に耐えうる建築。耐火材料を用いた建築。火災の場合、類焼することなく、また、内部が焼失しても補修により使用できるもの。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かこ【大過去】‥クワ‥
(plus-que-parfait フランス)インド‐ヨーロッパ語などの時間表現の一つ。過去の一時点を基準にして、出来事や動作がその時点以前に終了し、その帰結が何らかの形でその時点まで及んでいることを表す。過去完了。
たいか‐こうぞう【耐火構造】‥クワ‥ザウ
建築物の部分について、所要の耐火性能を持つもの。鉄筋コンクリート構造など。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐がさ【台笠】
大名行列などのとき、袋に入れて棒をつけ、供の者に持たせた被笠かぶりがさ。→たてがさ
台笠
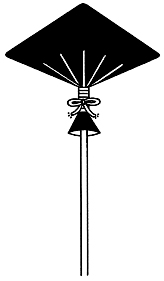 たいか‐ざいりょう【耐火材料】‥クワ‥レウ
火災による高温に耐えうる材料。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かし【代貸】
(ダイガシとも)貸元の代理。
だい‐かしょう【大和尚・大和上】‥クワシヤウ
⇒だいおしょう
たいが‐しょうせつ【大河小説】‥セウ‥
(roman-fleuve フランス)一群の人々の歴史を、数世代にわたって、社会的背景から書いた小説。20世紀前半に続出した。マルタン=デュ=ガールの「チボー家の人々」など。
⇒たい‐が【大河】
だい‐がしら【大頭】
幸若こうわか舞の一流派。名の由来に諸説があるが不確定。現存する福岡県みやま市瀬高町の幸若舞はこの末流という。→幸若舞
ダイカスト
(die-casting)鋳造ちゅうぞう法の一つ。アルミニウム合金・亜鉛合金などを溶融したものを、圧力によって特殊鋼の精密な金型(ダイス)に圧し込んで鋳物を得る方法。寸法が正確で仕上げがほとんど不要、かつ機械的性質が優秀で、大量生産に適する。ダイキャスト。
たいか‐ぜんだい【大化前代】‥クワ‥
古代の時期区分の一つ。氏姓制度の矛盾が激化し官司制度が進展した大和時代末期、6〜7世紀の頃を指す。
⇒たいか【大化】
だい‐かぞく【大家族】
①多人数の家族。
②一対の夫婦とその子供以外に、傍系血族とその配偶者までも含んでいる家父長制的家族。「―制」
たい‐がため【体固め】
レスリングの技の一つ。相手をいったんうつ伏せに抑え、腕と足を使って仰向けに返して固める。
だい‐かつ【大喝】
大声で叱りつけること。
⇒だいかつ‐いっせい【大喝一声】
だいかつ‐いっせい【大喝一声】
大きなひと声で叱りつけること。正岡子規、月の都「修行の妨すなと―」
⇒だい‐かつ【大喝】
だい‐がっく【大学区】‥ガク‥
①1872年(明治5)の学制に定められた大学校設置の区域。また同時に教育行政の単位区画。初めは全国を8大学区とし、後に7大学区に改めた。→学区。
②小さい地域の学区(小学区)に対して大きい地域の学区。
だい‐かっこ【大括弧】‥クワツ‥
角かく括弧。ブラケット。[ ] 数式で、小括弧・中括弧よりも大きなくくりを示す。
だい‐がっこう【大学校】‥ガクカウ
学校教育法(旧制では大学令)によらないで、省庁など行政機関が管轄している大学程度の学校。気象大学校・防衛大学校など。第二次大戦前では陸軍大学校・海軍大学校。
たいか‐ど【耐火度】‥クワ‥
耐火の程度を示す度合。その物質が軟化変形をおこす温度で表し、ふつうはゼーゲル錐すいの溶融する温度と比較する。
⇒たい‐か【耐火】
たいが‐どう【大雅堂】‥ダウ
①池大雅の号。
②池大雅の旧居。京都東山双林寺の境内にあった。
⇒たいが【大雅】
たいが‐ドラマ【大河ドラマ】
NHKのテレビ番組。1年間かけて放送する歴史ドラマの称。第1作は1963年の「花の生涯」。大河小説にちなんだ名称とも。
⇒たい‐が【大河】
たいか‐にじゅういっかじょう‐ようきゅう【対華二十一カ条要求】‥クワ‥ジフ‥デウエウキウ
(→)二十一カ条要求に同じ。
たいか‐ねんど【耐火粘土】‥クワ‥
高熱を加えても溶融しないため、耐火煉瓦・坩堝るつぼなどの製造に用いられる粘土。アルミナを多量に含む。木節きぶし粘土の類。
⇒たい‐か【耐火】
たいか‐の‐かいしん【大化改新】‥クワ‥
大化元年(645)夏、中大兄皇子(のちの天智天皇)を中心に、中臣(藤原)鎌足ら革新的な豪族が蘇我大臣家を滅ぼして開始した古代政治史上の大改革。孝徳天皇を立て都を難波に移し、翌春、私有地・私有民の廃止、国・郡・里制による地方行政権の中央集中、戸籍の作成や耕地の調査による班田収授法の実施、調・庸など税制の統一、の4綱目から成る改新の詔みことのりを公布、古代東アジア的な中央集権国家成立の出発点となった。しかし、律令国家の形成には、壬申の乱(672年)後の天武・持統朝の改革が必要であった。大化新政。大化革新。
→文献資料[改新の詔]
⇒たいか【大化】
たいか‐ざいりょう【耐火材料】‥クワ‥レウ
火災による高温に耐えうる材料。
⇒たい‐か【耐火】
だい‐かし【代貸】
(ダイガシとも)貸元の代理。
だい‐かしょう【大和尚・大和上】‥クワシヤウ
⇒だいおしょう
たいが‐しょうせつ【大河小説】‥セウ‥
(roman-fleuve フランス)一群の人々の歴史を、数世代にわたって、社会的背景から書いた小説。20世紀前半に続出した。マルタン=デュ=ガールの「チボー家の人々」など。
⇒たい‐が【大河】
だい‐がしら【大頭】
幸若こうわか舞の一流派。名の由来に諸説があるが不確定。現存する福岡県みやま市瀬高町の幸若舞はこの末流という。→幸若舞
ダイカスト
(die-casting)鋳造ちゅうぞう法の一つ。アルミニウム合金・亜鉛合金などを溶融したものを、圧力によって特殊鋼の精密な金型(ダイス)に圧し込んで鋳物を得る方法。寸法が正確で仕上げがほとんど不要、かつ機械的性質が優秀で、大量生産に適する。ダイキャスト。
たいか‐ぜんだい【大化前代】‥クワ‥
古代の時期区分の一つ。氏姓制度の矛盾が激化し官司制度が進展した大和時代末期、6〜7世紀の頃を指す。
⇒たいか【大化】
だい‐かぞく【大家族】
①多人数の家族。
②一対の夫婦とその子供以外に、傍系血族とその配偶者までも含んでいる家父長制的家族。「―制」
たい‐がため【体固め】
レスリングの技の一つ。相手をいったんうつ伏せに抑え、腕と足を使って仰向けに返して固める。
だい‐かつ【大喝】
大声で叱りつけること。
⇒だいかつ‐いっせい【大喝一声】
だいかつ‐いっせい【大喝一声】
大きなひと声で叱りつけること。正岡子規、月の都「修行の妨すなと―」
⇒だい‐かつ【大喝】
だい‐がっく【大学区】‥ガク‥
①1872年(明治5)の学制に定められた大学校設置の区域。また同時に教育行政の単位区画。初めは全国を8大学区とし、後に7大学区に改めた。→学区。
②小さい地域の学区(小学区)に対して大きい地域の学区。
だい‐かっこ【大括弧】‥クワツ‥
角かく括弧。ブラケット。[ ] 数式で、小括弧・中括弧よりも大きなくくりを示す。
だい‐がっこう【大学校】‥ガクカウ
学校教育法(旧制では大学令)によらないで、省庁など行政機関が管轄している大学程度の学校。気象大学校・防衛大学校など。第二次大戦前では陸軍大学校・海軍大学校。
たいか‐ど【耐火度】‥クワ‥
耐火の程度を示す度合。その物質が軟化変形をおこす温度で表し、ふつうはゼーゲル錐すいの溶融する温度と比較する。
⇒たい‐か【耐火】
たいが‐どう【大雅堂】‥ダウ
①池大雅の号。
②池大雅の旧居。京都東山双林寺の境内にあった。
⇒たいが【大雅】
たいが‐ドラマ【大河ドラマ】
NHKのテレビ番組。1年間かけて放送する歴史ドラマの称。第1作は1963年の「花の生涯」。大河小説にちなんだ名称とも。
⇒たい‐が【大河】
たいか‐にじゅういっかじょう‐ようきゅう【対華二十一カ条要求】‥クワ‥ジフ‥デウエウキウ
(→)二十一カ条要求に同じ。
たいか‐ねんど【耐火粘土】‥クワ‥
高熱を加えても溶融しないため、耐火煉瓦・坩堝るつぼなどの製造に用いられる粘土。アルミナを多量に含む。木節きぶし粘土の類。
⇒たい‐か【耐火】
たいか‐の‐かいしん【大化改新】‥クワ‥
大化元年(645)夏、中大兄皇子(のちの天智天皇)を中心に、中臣(藤原)鎌足ら革新的な豪族が蘇我大臣家を滅ぼして開始した古代政治史上の大改革。孝徳天皇を立て都を難波に移し、翌春、私有地・私有民の廃止、国・郡・里制による地方行政権の中央集中、戸籍の作成や耕地の調査による班田収授法の実施、調・庸など税制の統一、の4綱目から成る改新の詔みことのりを公布、古代東アジア的な中央集権国家成立の出発点となった。しかし、律令国家の形成には、壬申の乱(672年)後の天武・持統朝の改革が必要であった。大化新政。大化革新。
→文献資料[改新の詔]
⇒たいか【大化】
広辞苑に「大海」で始まるの検索結果 1-8。