複数辞典一括検索+![]()
![]()
さ【差】🔗⭐🔉
さ【差】
(呉音はシャ)
①性質・状態のへだたり。ちがい。「―をつける」「貧富の―」
②一つの数値と他の数値との間のひらき。さしひき。「―を求める」
さし【差し】🔗⭐🔉
さし【差し】
[一]〔名〕
①(「尺」とも書く)長短をはかる具。ものさし。
②二人ですること。
㋐さしむかい。人情本、縁結娯色糸えんむすびごしきのいと「併し―ぢや飲めねえね」。「―で話す」
㋑さしにない。「―でかつぐ」
③さしさわり。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「御新造の前では―であつた」
④さしとおすもの。
㋐(「釵子」とも書く)かんざし。
㋑(「刺」「指」とも書く)米刺こめさし。
㋒(「緡」とも書く)銭差ぜにさし。狂言、緡縄さしなわ「いや―がなうて。えつながなんだ」
⑤(普通「サシ」と書く)能の構成要素の一つ。拍子に合わせない謡で、ごく単純な節で言い流す一節。
⑥舞楽・能などで、手をさし出す類の動作。また、舞曲を数えるのに用いる語。「一―舞う」
⑦下級の女官。おさし。
[二]〔接頭〕
動詞に冠して語勢を強め、あるいは調える。万葉集11「雷神なるかみのしまし響とよもし―曇り」。「―招く」「―出す」「―迫る」
ざし【差し】🔗⭐🔉
ざし【差し】
〔接尾〕
ある語に添えて物の姿・状態を表す語。「枝―」「おも―」
さし‐あ・う【差し合う】‥アフ🔗⭐🔉
さし‐あ・う【差し合う】‥アフ
〔自五〕
①出合う。でくわす。一つになる。落窪物語1「小路切りに辻に―・ひぬ」
②かちあって不都合になる。さしつかえる。さしさわりがある。新古今和歌集雑「これかれ誘ひけるを―・ふ事ありて留まりて」
さし‐あお・ぐ【差し仰ぐ】‥アフグ🔗⭐🔉
さし‐あお・ぐ【差し仰ぐ】‥アフグ
〔自四〕
上を向く。あおぐ。竹取物語「えとどむまじければ、ただ―・ぎて泣きをり」
さし‐あが・る【差し上がる】🔗⭐🔉
さし‐あが・る【差し上がる】
〔自四〕
(日や月などが)あがる。のぼる。源氏物語藤袴「月くまなく―・りて、空のけしきも艶えんなるに」
さし‐あつま・る【差し集まる】🔗⭐🔉
さし‐あつま・る【差し集まる】
〔自四〕
「あつまる」を強めていう語。栄華物語鶴林「御堂御堂の僧など―・りて、かいひざをして」
さし‐あわ・す【差し合す】‥アハス🔗⭐🔉
さし‐あわ・す【差し合す】‥アハス
〔他下二〕
一つに合わせる。いっしょにする。源氏物語行幸「御心を―・せてのたまはむこと」
さし‐い・ず【射し出づ・差し出づ】‥イヅ🔗⭐🔉
さし‐い・ず【射し出づ・差し出づ】‥イヅ
〔自下二〕
①光が照り出す。万葉集11「山の端に―・づる月のはつはつに」
②立ちでる。外に出る。伊勢物語「―・でたる石あり」
③分を越えて進み出る。ですぎる。ですぎたことをする。枕草子28「―・でて、我ひとりさいまくる者」
さし‐いそ・ぐ【差し急ぐ】🔗⭐🔉
さし‐いそ・ぐ【差し急ぐ】
〔自五〕
「いそぐ」を強めていう語。
さし‐いだ・す【差し出す】🔗⭐🔉
さし‐いだ・す【差し出す】
〔他五〕
①「いだす」を強めていう語。さしだす。
②提出する。さしあげる。
③送り出す。発送する。
さし‐いらえ【差し応へ】‥イラヘ🔗⭐🔉
さし‐いらえ【差し応へ】‥イラヘ
①応答。返事。源氏物語夕顔「え―も聞えず」
②相手をすること。合奏などをすること。源氏物語宿木「ひとりごとはさうざうしきを、―し給へかし」
さし‐う・く【差し受く】🔗⭐🔉
さし‐う・く【差し受く】
〔他下二〕
「受く」を強めていう語。徒然草「酒を出したれば、―・け―・け、よよと飲みぬ」
さし‐おさ・える【差し押さえる】‥オサヘル🔗⭐🔉
さし‐おさ・える【差し押さえる】‥オサヘル
〔他下一〕[文]さしおさ・ふ(下二)
①「おさえる」を強めていう語。とどめる。
②差押えをする。「証拠物件を―・える」
さし‐か・う【差し交ふ】‥カフ🔗⭐🔉
さし‐か・う【差し交ふ】‥カフ
〔他下二〕
互いに交え合わせる。交差させる。万葉集8「真玉手の玉手―・へあまた夜も寝てしかも」
さし‐かえ・る【差し帰る】‥カヘル🔗⭐🔉
さし‐かえ・る【差し帰る】‥カヘル
〔自四〕
棹をさして帰る。源氏物語橋姫「―・る宇治の川をさ」
さし‐かか・る【差し掛かる】🔗⭐🔉
さし‐かか・る【差し掛かる】
〔自五〕
①その場に臨む。その時期になる。「峠に―・る」「雨期に―・る」
②まぎわになる。さしせまる。狂言、山立聟「―・つた事で御座れば、断りを云うて、後から送らせられい」
③上からおおいかぶさる。好色一代男1「世之介四阿屋あずまやの棟に―・り」
さし‐かく・す【差し隠す】🔗⭐🔉
さし‐かく・す【差し隠す】
〔他五〕
(扇・袖などを)かざしてかくす。源氏物語横笛「まろ、顔は隠さむ。なほなほとて、御袖して―・し給へば」
さし‐か・ける【差し掛ける】🔗⭐🔉
さし‐か・ける【差し掛ける】
〔他下一〕[文]さしか・く(下二)
①盃をさし向ける。蜻蛉日記下「土器かわらけ―・けられ」
②かさなどを上からかざす。狂言、末広がり「内へ入つて―・けい」
③寄りかからせる。
さし‐がさ【差し傘】🔗⭐🔉
さし‐がさ【差し傘】
かぶり笠に対して、手でさすからかさ。さしからかさ。
さし‐かた【差し肩】🔗⭐🔉
さし‐かた【差し肩】
高く張って水平になった肩。いかり肩。今昔物語集24「丈高くて―にて見苦しかりけるを」↔撫肩なでがた
さし‐かた・める【差し固める・鎖し固める】🔗⭐🔉
さし‐かた・める【差し固める・鎖し固める】
〔他下一〕[文]さしかた・む(下二)
①門・戸などを堅くとざす。固く警戒する。源氏物語横笛「こはなど、かく―・めたる」
②厳重に身ごしらえをする。平治物語「腹巻に小具足―・めて」
さし‐がね【差し金】🔗⭐🔉
さし‐がね【差し金】
①(「指矩」とも書く)(→)「まがりがね(曲尺)」に同じ。
②文楽の人形の左手に取り付けられ、手首や指を動かす棒と紐ひもの仕掛け。
③歌舞伎の小道具。蝶・鳥などを操る黒塗りの細い竹ざお。
④転じて、陰で人をそそのかしあやつること。「局長の―で動く」
⑤⇒さしきん
さし‐かまい【差し構い】‥カマヒ🔗⭐🔉
さし‐かまい【差し構い】‥カマヒ
(多く「―ない」の形で用いる)不都合だとしてさしとめたり、咎めたりすること。
さし‐かま・う【差し構ふ】‥カマフ🔗⭐🔉
さし‐かま・う【差し構ふ】‥カマフ
[一]〔他下二〕
待ちかまえる。準備する。日葡辞書「サシカマエタルニンジュ(人数)」
[二]〔他四〕
おさえとどめる。異議を申し立てる。浄瑠璃、曾我会稽山「畏つてお請け申すところ、榛谷の四郎―・ひ」
さし‐がみ【指し紙・差し紙】🔗⭐🔉
さし‐がみ【指し紙・差し紙】
①江戸時代、奉行所が人民を召喚するために発した出頭命令書。御召状。
②蔵米の落札人が米商に発行した切手。
③芸者・娼妓が、新しく出るひろめの時、半紙を縦に四つに切ったほどの細長い紙に名前や風体などを記して、茶屋・揚屋に配るもの。傾城禁短気「―僉議して見し内に」
さし‐からかさ【差し傘】🔗⭐🔉
さし‐からかさ【差し傘】
(→)「さしがさ」に同じ。
さし‐かわ・す【差し交わす】‥カハス🔗⭐🔉
さし‐かわ・す【差し交わす】‥カハス
〔他五〕
交差させる。互いにさし合う。「木々が枝を―・す」「盃を―・す」
さし‐くち【指し口・差し口】🔗⭐🔉
さし‐くち【指し口・差し口】
他の木の一端をとりつけるため横面にうがった枘穴ほぞあな。
さし‐ぐち【差し口】🔗⭐🔉
さし‐ぐち【差し口】
(サシクチとも)
①他から申し入れたことば。つげ口。密告。
②入口。狂言、筑紫の奥「うかうか往たれば、つい―にござつて叱られておりやる」
③冒頭。片言かたこと2「書物の―に、そもそもと書き出すはくるしからずとかや」
さし‐く・む【差し汲む】🔗⭐🔉
さし‐く・む【差し汲む】
〔他四〕
手を伸ばして汲み取る。蜻蛉日記中「雲ゐよりこちくの声を聞くなへに―・むばかり見ゆる月影」
さし‐ぐ・む【差し含む】🔗⭐🔉
さし‐ぐ・む【差し含む】
〔自五〕
なみだぐむ。後撰和歌集恋「いにしへの野中の清水見るからに―・むものは涙なりけり」
さし‐く・る【差し呉る】🔗⭐🔉
さし‐く・る【差し呉る】
〔他下二〕
馬に乗っていて手綱をゆるめる。曾我物語1「主も屈強の馬乗りにて、…―・れてこそ歩ませけれ」
さし‐く・る【差し繰る】🔗⭐🔉
さし‐く・る【差し繰る】
〔他五〕
さしつかえのないように都合をつける。くりあわせる。「時間を―・る」
さし‐くわ・える【差し加える】‥クハヘル🔗⭐🔉
さし‐くわ・える【差し加える】‥クハヘル
〔他下一〕[文]さしくは・ふ(下二)
「加える」を強めていう語。つけ加える。
さし‐こ・える【差し越える】🔗⭐🔉
さし‐こ・える【差し越える】
〔自下一〕[文]さしこ・ゆ(下二)
あるべき順序をふみこえて行う。特に、人をさしおいて先に出る。
さし‐こ・す【差し越す】🔗⭐🔉
さし‐こ・す【差し越す】
〔自五〕
①越えて前へ出る。
②他をさしおいて事を行う。一定の順序・手続をふまずに行う。
③(他動詞として)送って来る。よこす。
さし‐こなし【差しこなし】🔗⭐🔉
さし‐こなし【差しこなし】
刀などを腰にさした具合。さしぶり。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「大刀・刀の―」
さし‐こ・む【射し込む・差し込む】(自五)🔗⭐🔉
さし‐こ・む【射し込む・差し込む】
〔自五〕
光などが中へ入る。中まで照らす。さしいる。
さし‐こ・む【差し込む】(他五・自五)🔗⭐🔉
さし‐こ・む【差し込む】
[一]〔他五〕
①突き入れる。差し入れる。「鍵を―・む」
②わきから口を出す。入れ知恵をする。浄瑠璃、鎌倉三代記「病みほうけの頼家に―・まれては年来の大望が成就せぬ」
[二]〔自五〕
胸・腹などが物を突っ込んだように痛む。胃痙攣けいれんを起こす。癪しゃくを起こす。「横腹が―・む」
さし‐こ・ゆ【差し越ゆ】🔗⭐🔉
さし‐こ・ゆ【差し越ゆ】
〔自下二〕
①上を越えて通る。蜻蛉日記上「松山の―・えてしもあらじ世をわれによそへて騒ぐ波かな」
②さしでる。でしゃばる。枕草子28「今参りの―・えて、物知り顔に教へやうなる事いひうしろみたる」
さし‐こわら・す【差し強らす】‥コハラス🔗⭐🔉
さし‐こわら・す【差し強らす】‥コハラス
〔他四〕
刀を腰にさしていかめしく装う。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「大だら―・し」
さし‐さわ・る【差し障る】‥サハル🔗⭐🔉
さし‐さわ・る【差し障る】‥サハル
〔自五〕
じゃまになる。さわりとなる。さしつかえる。「―・ることがある」
さし‐じお【差し塩】‥ジホ🔗⭐🔉
さし‐じお【差し塩】‥ジホ
苦味のある劣等な塩。↔真塩ましお
さし‐すが・う【差し次ふ】‥スガフ🔗⭐🔉
さし‐すが・う【差し次ふ】‥スガフ
〔自四〕
すぐあとにつづく。匹敵する。栄華物語殿上花見「二の宮またいと美しうて、―・ひておはします」
さしすぎ‐びと【差し過ぎ人】🔗⭐🔉
さしすぎ‐びと【差し過ぎ人】
出過ぎたことをする人。さしでもの。でしゃばり。源氏物語夢浮橋「例の物めでの―、いと有難くをかしと思ふべし」
さし‐す・ぐ【差し過ぐ】🔗⭐🔉
さし‐す・ぐ【差し過ぐ】
〔自上二〕
①出過ぎる。さしでる。源氏物語空蝉「未だいと若きここちにさこそ―・ぎたるやうなれど」
②通り過ぎる。平家物語10「佐野の松原―・ぎて」
さし‐すぐ・す【差し過す】🔗⭐🔉
さし‐すぐ・す【差し過す】
〔自四〕
(→)「さしすぐ」1に同じ。
さし‐すて【差し捨て・指し捨て】🔗⭐🔉
さし‐すて【差し捨て・指し捨て】
①棹をさしたままにして止めておくこと。
②(サシズテとも)酒席で、相手に盃をさしたまま、かえしを受けないこと。
さし‐だ・す【差し出す】🔗⭐🔉
さし‐だ・す【差し出す】
〔他五〕
①前へ出す。「両手を―・す」
②提出する。さしあげる。「申請書を―・す」
③送り出す。発送する。「招待状を―・す」
さし‐ちがえ【差し違え】‥チガヘ🔗⭐🔉
さし‐ちがえ【差し違え】‥チガヘ
①入れ違えること。誤って他の方へ差すこと。
②たがいちがいにすること。
③相撲で、行司が勝負を見誤り、負けた方に軍配を差すこと。
さし‐ちが・える【差し違える】‥チガヘル🔗⭐🔉
さし‐ちが・える【差し違える】‥チガヘル
〔他下一〕[文]さしちが・ふ(下二)
①たがいちがいにする。枕草子278「三尺の御几帳一具ひとよろいを―・へて」
②誤って他の方へさし入れる。
③相撲で、行司が誤って負けた方へ軍配をあげる。
○差しつ抑えつさしつおさえつ🔗⭐🔉
○差しつ抑えつさしつおさえつ
盃をさしたり、他人のさしてくれるのをおさえたり。盛んに盃をとりかわして、の意。
⇒さ・す【差す・指す】
さし‐つかえ【差支え】‥ツカヘ
さしつかえること。都合の悪い事情。さわり。さまたげ。支障。「―があって行けない」
さし‐つか・える【差し支える】‥ツカヘル
〔自下一〕[文]さしつか・ふ(下二)
都合の悪いことが生ずる。障害が生ずる。さまたげとなる。さしあう。「夜更しは仕事に―・える」
さし‐つかわ・す【差し遣わす】‥ツカハス
〔他五〕
さしむけてつかわす。派遣する。
さし‐つぎ【刺継ぎ】
布地の弱った所を、同質・同色のやや細めの糸で刺縫いして丈夫にする継ぎ方。
さし‐つぎ【指し継ぎ】
将棋で、指しかけの対局を再開すること。
さし‐つぎ【差次・差継】
①次の位置。次位。つぎ。源氏物語末摘花「左衛門の乳母とて、大弐の―におぼいたるが娘」
②極臈ごくろうに次ぐ六位の蔵人。
③差引勘定。
さし‐つ・く【差し着く・差し付く】
[一]〔自四〕
さす棹で舟が岸に着く。源氏物語浮舟「かの岸に―・きて下り給ふに」
[二]〔他下二〕
①物におしあてる。
②棹をさして舟を岸に着ける。源氏物語澪標「岸に―・くるほど見れば」
③目の前に差し出す。つきつける。
④あてつける。あてこする。
さし‐つ・ぐ【差し次ぐ・差し継ぐ】
〔自四〕
次につづく。後につづく。源氏物語若菜下「この院・大殿に―・ぎ奉りては、人も参り仕うまつり」
さしつけ‐て【差付けて】
〔副〕
つきつけて。あからさまに。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―申出す折もござりませぬ」
さしつけ‐に【差付けに】
〔副〕
いきなり。うちつけに。
さしっ‐こ【刺子】
サシコの促音化。
さし‐つか・える【差し支える】‥ツカヘル🔗⭐🔉
さし‐つか・える【差し支える】‥ツカヘル
〔自下一〕[文]さしつか・ふ(下二)
都合の悪いことが生ずる。障害が生ずる。さまたげとなる。さしあう。「夜更しは仕事に―・える」
さし‐つかわ・す【差し遣わす】‥ツカハス🔗⭐🔉
さし‐つかわ・す【差し遣わす】‥ツカハス
〔他五〕
さしむけてつかわす。派遣する。
さし‐つ・ぐ【差し次ぐ・差し継ぐ】🔗⭐🔉
さし‐つ・ぐ【差し次ぐ・差し継ぐ】
〔自四〕
次につづく。後につづく。源氏物語若菜下「この院・大殿に―・ぎ奉りては、人も参り仕うまつり」
○差しつ差されつさしつさされつ🔗⭐🔉
○差しつ差されつさしつさされつ
互いに何度も酒を注つぎあうさま。「―一晩語り合う」
⇒さ・す【差す・指す】
さ‐しったり【然知ったり】
①かねて待ちかまえていた時に発する声。こころえた。おっと合点だ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「はつしと打つ。―と開く身に」
②心得ていたのに油断して失敗した時に発する声。ええしまった。浄瑠璃、日本振袖始「突けども斬れども手答へなし。―と取り直し」
さし‐づつ【指筒】
(→)受筒うけづつ1に同じ。
さし‐づと【差髱】
江戸中期、髱たぼを水平に丸く突き出すのに用いたかもじ。
さし‐つど・う【差し集う】‥ツドフ
〔自五〕
寄りあつまる。枕草子82「長押なげしのしもに火近く取りよせて、―・ひて」
さし‐づな【差綱】
(→)「さしなわ」に同じ。
さし‐つま・る【差し詰る】
〔自四〕
①つまる。窮する。浄瑠璃、曾我会稽山「この詞に兄弟―・つたる気を開き」
②その場にせまる。さしせまる。世間胸算用3「それぞれの家業外になり行き、―・りて迷惑する事なり」
さしつめ‐ひきつめ【差詰め引詰め】
(サシは矢を弦につがえる、ヒキは弓をひきしぼる意)多くの矢を次々に手早く弦につがえて射出すさま。さしとりひきつめ。さしとりひきとり。平家物語4「究竟くっきょうの弓の上手どもが矢先を揃へて―さんざんに射る」
さし‐つらぬ・く【刺し貫く】
〔他五〕
さしとおす。太平記20「罪人を鉄くろがねの串に―・き」
さし‐て【指し手】
①将棋で、駒を進める方法。
②将棋を指す人。
さし‐て【差し手】
相撲で、自分の手を相手の腋わきの下に差し入れること。また、その手。「―争い」
さし‐て
〔副〕
①(下に打消の語を伴って)これといって。さほど。たいして。格別に。源氏物語賢木「―思ふことなきだに」。「―苦労はない」
②特に。とりわけ。平家物語12「鎌倉殿に―申すべき大事ども候ふ」
⇒さしてもない
さし‐で【差し出】
①さしでること。
②差し出口。日葡辞書「サシデヲイウ」
③差出者。〈日葡辞書〉
⇒さしで‐ぐち【差し出口】
⇒さしで‐の‐いそ【差出の磯】
⇒さしで‐はんがく【差出半学】
⇒さしで‐もの【差し出者】
さしで‐がまし・い【差し出がましい】
〔形〕[文]さしでがま・し(シク)
でしゃばるようである。「―・いまねはよせ」
さしで‐ぐち【差し出口】
分を越えて口出しすること。さしいでぐち。
⇒さし‐で【差し出】
さし‐つど・う【差し集う】‥ツドフ🔗⭐🔉
さし‐つど・う【差し集う】‥ツドフ
〔自五〕
寄りあつまる。枕草子82「長押なげしのしもに火近く取りよせて、―・ひて」
さし‐つま・る【差し詰る】🔗⭐🔉
さし‐つま・る【差し詰る】
〔自四〕
①つまる。窮する。浄瑠璃、曾我会稽山「この詞に兄弟―・つたる気を開き」
②その場にせまる。さしせまる。世間胸算用3「それぞれの家業外になり行き、―・りて迷惑する事なり」
さし‐て【差し手】🔗⭐🔉
さし‐て【差し手】
相撲で、自分の手を相手の腋わきの下に差し入れること。また、その手。「―争い」
さし‐で【差し出】🔗⭐🔉
さし‐で【差し出】
①さしでること。
②差し出口。日葡辞書「サシデヲイウ」
③差出者。〈日葡辞書〉
⇒さしで‐ぐち【差し出口】
⇒さしで‐の‐いそ【差出の磯】
⇒さしで‐はんがく【差出半学】
⇒さしで‐もの【差し出者】
さしで‐がまし・い【差し出がましい】🔗⭐🔉
さしで‐がまし・い【差し出がましい】
〔形〕[文]さしでがま・し(シク)
でしゃばるようである。「―・いまねはよせ」
さしで‐ぐち【差し出口】🔗⭐🔉
さしで‐ぐち【差し出口】
分を越えて口出しすること。さしいでぐち。
⇒さし‐で【差し出】
○座して食らえば山も空しざしてくらえばやまもむなし
働かないで暮らしていれば、山のように豊富な財産もやがてはなくなってしまう。座食すれば山も空し。
⇒ざ・する【座する・坐する】
さしで‐もの【差し出者】🔗⭐🔉
さしで‐もの【差し出者】
さしでて言いまたは行動する者。ですぎもの。
⇒さし‐で【差し出】
さし・でる【差し出る】🔗⭐🔉
さし・でる【差し出る】
〔自下一〕
①前に出る。進み出る。
②分を越えて進み出る。でしゃばる。「―・でた振舞い」
さし‐とど・む【差し止む】🔗⭐🔉
さし‐とど・む【差し止む】
〔他下二〕
おさえとどめる。禁止する。さしとめる。
さし‐と・める【差し止める】🔗⭐🔉
さし‐と・める【差し止める】
〔他下一〕[文]さしと・む(下二)
ある動作をやめさせる。禁止する。「新聞の記事を―・める」「出入りを―・める」
さし‐とら・す【差し取らす】🔗⭐🔉
さし‐とら・す【差し取らす】
〔他下二〕
つきつけて受け取らせる。手渡しする。源氏物語浮舟「わたくしの人にや、艶えんなる文は―・する」
さし‐に【差し荷】🔗⭐🔉
さし‐に【差し荷】
さしにないの荷物。
さし‐の・べる【差し伸べる・差し延べる】🔗⭐🔉
さし‐の・べる【差し伸べる・差し延べる】
〔他下一〕[文]さしの・ぶ(下二)
(ある方向にのばすようにして)出す。さし出す。「救援の手を―・べる」
さし‐のぼ・る【差し上る・差し昇る】🔗⭐🔉
さし‐のぼ・る【差し上る・差し昇る】
〔自五〕
(日や月などが)のぼる。
さし‐ば【差し歯】🔗⭐🔉
さし‐ば【差し歯】
①足駄の台に歯を入れること。また、その歯。
②人工の歯をつぎたすこと。また、その歯。継ぎ歯。
さし‐はさ・む【挟む・差し挟む】🔗⭐🔉
さし‐はさ・む【挟む・差し挟む】
〔他五〕
①間に入れる。はさみこむ。さしこむ。源氏物語若菜下「(端書を)えよくも隠し給はで、御しとねの下に―・み給ひつ」。「口を―・む」
②転じて、ひそかに心にいだく。含む。多く、悪い思いをいだく意にいう。平家物語5「野心を―・んで朝威をほろぼさんとする輩」
さし‐はず・す【差し外す】‥ハヅス🔗⭐🔉
さし‐はず・す【差し外す】‥ハヅス
〔他四〕
(棹などを)はずす。また、さしそこなう。源氏物語浮舟「童、棹―・して落ち入り侍りにける」
さし‐び【差し火】🔗⭐🔉
さし‐び【差し火】
炭火をさらにつぎ足すこと。また、その火。
さし‐ひか・える【差し控える】‥ヒカヘル🔗⭐🔉
さし‐ひか・える【差し控える】‥ヒカヘル
〔他下一〕[文]さしひか・ふ(下二)
ひかえ目にする。遠慮する。ひかえる。「発言を―・える」
さし‐ひ・く【差し引く】🔗⭐🔉
さし‐ひ・く【差し引く】
[一]〔自五〕
(潮が)差したり引いたりする。増減する。日葡辞書「ネッキ(熱気)ガサシヒク」
[二]〔他五〕
ある数から一部を引き去る。へらす。「給料から税金を―・く」
さし‐ひびき【差し響き】🔗⭐🔉
さし‐ひびき【差し響き】
音などがひびくこと。転じて、関係が他に及ぶこと。影響。
さし‐ひび・く【差し響く】🔗⭐🔉
さし‐ひび・く【差し響く】
〔自五〕
(音などが他に響くことから転じて)他に関係を及ぼす。影響する。
さし‐ふだ【差し札】🔗⭐🔉
さし‐ふだ【差し札】
組香くみこうで、香を聞いた人が鑑定して差し入れる札。10客分あり、木・象牙などで製し、表に花模様・紋印、裏に一・二・三・ウなどと記す。香札。
さし‐ふる・す【差し旧す・挿し旧す】🔗⭐🔉
さし‐ふる・す【差し旧す・挿し旧す】
〔他四〕
櫛くし・刀などを古くなるまで長い間さす。
さし‐ほこらか・す【差し誇らかす】🔗⭐🔉
さし‐ほこらか・す【差し誇らかす】
〔他四〕
刀剣などを自慢らしくさす。源平盛衰記1「大きなる黒鞘巻を隠したる気けもなく―・したりけるが」
さし‐ほら・す【差し誇らす】🔗⭐🔉
さし‐ほら・す【差し誇らす】
〔他四〕
「さしほこらかす」に同じ。一説に、「差し惚ほらす」で、だらしなく差す意。浄瑠璃、傾城酒呑童子「例の大太刀前下りに―・し」
さし‐まね・く【差し招く・麾く】🔗⭐🔉
さし‐まね・く【差し招く・麾く】
〔他五〕
①人を手でまねく。呼ぶ。「秘書を―・く」
②指揮して向かう方面を指示する。指図する。三蔵法師伝承徳頃点「勝幡を麾サシマネキテ」
さし‐まわし【差し回し】‥マハシ🔗⭐🔉
さし‐まわし【差し回し】‥マハシ
さしまわすこと。
さし‐まわ・す【差し回す】‥マハス🔗⭐🔉
さし‐まわ・す【差し回す】‥マハス
〔他五〕
そちらへ行かせる。さし向ける。「車を―・す」
さし‐むか・う【差し向かう】‥ムカフ🔗⭐🔉
さし‐むか・う【差し向かう】‥ムカフ
〔自五〕
①その方へ向く。相対する。むかいあう。万葉集9「―・ふ鹿島の崎に」
②二人むかいあう。対座する。枕草子184「―・ひきこえたる心地うつつともおぼえず」
さし‐むき【差し向き】🔗⭐🔉
さし‐むき【差し向き】
〔副〕
さしあたり。とりあえず。目下。「―生活には困らない」
さし‐む・く【差し向く】🔗⭐🔉
さし‐む・く【差し向く】
[一]〔自四〕
その方へ向く。
[二]〔他下二〕
⇒さしむける(下一)
さし‐む・ける【差し向ける】🔗⭐🔉
さし‐む・ける【差し向ける】
〔他下一〕[文]さしむ・く(下二)
①その方へ向かせる。「光を―・ける」
②つかわす。派遣する。やる。平家物語7「既に討手を―・けらるる由聞えしかば」。「迎えの車を―・ける」
さし‐め【差し芽】🔗⭐🔉
さし‐め【差し芽】
植物の無性繁殖法の一つ。通常、わずかに枝・茎のついた芽を床とこにさし、発根させて新株を得る。
さし‐や・く【差し焼く】🔗⭐🔉
さし‐や・く【差し焼く】
〔他四〕
焼く。万葉集13「―・かむ小屋おやの醜屋しこやに」
さし‐や・る【差し遣る】🔗⭐🔉
さし‐や・る【差し遣る】
〔他四〕
押しやる。進める。やる。源氏物語紅葉賀「掻きあはせばかり弾きて、―・り給へれば」
さし‐ゆる・す【差し許す】🔗⭐🔉
さし‐ゆる・す【差し許す】
〔他五〕
「許す」をおもおもしくいう語。
さし‐よ・す【差し寄す】🔗⭐🔉
さし‐よ・す【差し寄す】
〔他下二〕
①そばへよせる。源氏物語若菜上「廊の外とに御車―・せたる人々も」
②短く縮める。三道「五段の内序急を―・せて」
さし‐よ・る【差し寄る】🔗⭐🔉
さし‐よ・る【差し寄る】
〔自四〕
近寄る。寄る。万葉集19「―・らむ磯の崎崎、漕ぎ泊はてむ泊とまり泊に」
[漢]差🔗⭐🔉
差 字形
 筆順
筆順
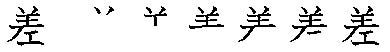 〔工部7画/10画/教育/2625・3A39〕
〔音〕サ(漢) シャ(呉) シ(呉)(漢)
〔訓〕さす
[意味]
①ふぞろい。ちがい。へだたり。「雲泥の差」「差異・差等・段差・参差しんし・千差万別」。一つの数値と他の数値との間のひらき。さしひき。「差額・誤差・時差」
②等級をつける。「差別さべつ・しゃべつ・差配」
③まじわる。さしちがう。「交差」
④使いをやる。つかわす。「差遣・欽差きんさ」
▷④の意味では、本来は漢音「サイ」。日本では、「つきさす」「さしこむ」「ものさし」などの「さす」「さし」にこの字を当てる。
[解字]
形声。「
〔工部7画/10画/教育/2625・3A39〕
〔音〕サ(漢) シャ(呉) シ(呉)(漢)
〔訓〕さす
[意味]
①ふぞろい。ちがい。へだたり。「雲泥の差」「差異・差等・段差・参差しんし・千差万別」。一つの数値と他の数値との間のひらき。さしひき。「差額・誤差・時差」
②等級をつける。「差別さべつ・しゃべつ・差配」
③まじわる。さしちがう。「交差」
④使いをやる。つかわす。「差遣・欽差きんさ」
▷④の意味では、本来は漢音「サイ」。日本では、「つきさす」「さしこむ」「ものさし」などの「さす」「さし」にこの字を当てる。
[解字]
形声。「 」(=穂がふぞろいにたれた形)+音符「左」。
[下ツキ
格差・過差・僅差・欽差・交差・公差・較差・誤差・視差・時差・収差・参差・千差万別・大差・段差・等差・偏差・落差
」(=穂がふぞろいにたれた形)+音符「左」。
[下ツキ
格差・過差・僅差・欽差・交差・公差・較差・誤差・視差・時差・収差・参差・千差万別・大差・段差・等差・偏差・落差
 筆順
筆順
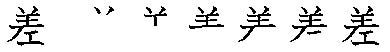 〔工部7画/10画/教育/2625・3A39〕
〔音〕サ(漢) シャ(呉) シ(呉)(漢)
〔訓〕さす
[意味]
①ふぞろい。ちがい。へだたり。「雲泥の差」「差異・差等・段差・参差しんし・千差万別」。一つの数値と他の数値との間のひらき。さしひき。「差額・誤差・時差」
②等級をつける。「差別さべつ・しゃべつ・差配」
③まじわる。さしちがう。「交差」
④使いをやる。つかわす。「差遣・欽差きんさ」
▷④の意味では、本来は漢音「サイ」。日本では、「つきさす」「さしこむ」「ものさし」などの「さす」「さし」にこの字を当てる。
[解字]
形声。「
〔工部7画/10画/教育/2625・3A39〕
〔音〕サ(漢) シャ(呉) シ(呉)(漢)
〔訓〕さす
[意味]
①ふぞろい。ちがい。へだたり。「雲泥の差」「差異・差等・段差・参差しんし・千差万別」。一つの数値と他の数値との間のひらき。さしひき。「差額・誤差・時差」
②等級をつける。「差別さべつ・しゃべつ・差配」
③まじわる。さしちがう。「交差」
④使いをやる。つかわす。「差遣・欽差きんさ」
▷④の意味では、本来は漢音「サイ」。日本では、「つきさす」「さしこむ」「ものさし」などの「さす」「さし」にこの字を当てる。
[解字]
形声。「 」(=穂がふぞろいにたれた形)+音符「左」。
[下ツキ
格差・過差・僅差・欽差・交差・公差・較差・誤差・視差・時差・収差・参差・千差万別・大差・段差・等差・偏差・落差
」(=穂がふぞろいにたれた形)+音符「左」。
[下ツキ
格差・過差・僅差・欽差・交差・公差・較差・誤差・視差・時差・収差・参差・千差万別・大差・段差・等差・偏差・落差
広辞苑に「差」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む
 )部4画〕
)部4画〕