複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (23)
そう‐じょう【双調】サウデウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【双調】サウデウ
①〔音〕日本の音名の一つ。十二律の下から6番目の音。中国の十二律の仲呂ちゅうりょに相当し、音高は、洋楽のト音(G音)に近い。→十二律(表)。
②雅楽の六調子の一つ。双調の音を宮きゅう(主音)とする呂旋りょせんの調子。呂旋音階。
そう‐じょう【宋襄】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【宋襄】‥ジヤウ
中国、春秋時代の宋の襄公。
⇒そうじょう‐の‐じん【宋襄の仁】
そう‐じょう【奏上】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【奏上】‥ジヤウ
天子に申し上げること。
そう‐じょう【奏杖】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【奏杖】‥ヂヤウ
文書を挟んで貴人に差し出す杖。文杖ふづえ・ぶんじょう。
奏杖
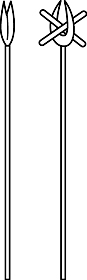
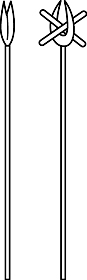
そう‐じょう【奏状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【奏状】‥ジヤウ
臣下の意見を奏上する文書。
そう‐じょう【相承】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐じょう【相承】サウ‥
⇒そうしょう
そう‐じょう【相乗】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐じょう【相乗】サウ‥
①2個以上の数を掛け合わせること。
②複数の要因が重なり、掛け合わせたほどの大きさになること。「―作用」
⇒そうじょう‐こうか【相乗効果】
⇒そうじょう‐せき【相乗積】
⇒そうじょう‐へいきん【相乗平均】
そう‐じょう【掃攘】サウジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【掃攘】サウジヤウ
はらいのぞくこと。特に、異国人を排斥すること。
そう‐じょう【葬場・喪場】サウヂヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【葬場・喪場】サウヂヤウ
葬儀を行う場所。葬儀場。
⇒そうじょう‐でん【喪場殿】
そう‐じょう【僧正】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【僧正】‥ジヤウ
僧官の最上級。のちに大僧正・僧正・権僧正に分けた。現在、各宗で僧階の一つ。
そうじょう【僧肇】‥デウ🔗⭐🔉
そうじょう【僧肇】‥デウ
中国、後秦の学僧。鳩摩羅什くまらじゅうの弟子。什門の四哲(僧肇・僧叡・道生・僧融)の一人。長安で師の訳経を助ける。(384〜414頃)→肇論じょうろん
そう‐じょう【層状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【層状】‥ジヤウ
層をなした形。かさなったさま。
そう‐じょう【層畳】‥デフ🔗⭐🔉
そう‐じょう【層畳】‥デフ
幾重にも重なること。
そう‐じょう【総状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【総状】‥ジヤウ
ふさのかたち。ふさの状態。
⇒そうじょう‐かじょ【総状花序】
そう‐じょう【騒擾】サウゼウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【騒擾】サウゼウ
さわぎみだれること。騒動。擾乱。「―事件」
⇒そうじょう‐ざい【騒擾罪】
そうじょう‐かじょ【総状花序】‥ジヤウクワ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐かじょ【総状花序】‥ジヤウクワ‥
①花序の一つ。長い花軸の上に柄のある花を総状に多数つける。フジ・アブラナの花序の類。
②広義には有限花序である集散花序と対をなす用語として、花が花房の下方あるいは外側から開花する無限花序をさす。総穂そうすい花序。
→花序(図)
⇒そう‐じょう【総状】
そうじょう‐が‐たに【僧正谷】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐が‐たに【僧正谷】‥ジヤウ‥
京都市左京区鞍馬山にある谷。源義経が兵法を学んだ所と伝えられる。
そうじょう‐こうか【相乗効果】サウ‥カウクワ🔗⭐🔉
そうじょう‐こうか【相乗効果】サウ‥カウクワ
複数の要因が重なって、それら個々がもたらす効果の和以上を生ずること。
⇒そう‐じょう【相乗】
そうじょう‐ざい【騒擾罪】サウゼウ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐ざい【騒擾罪】サウゼウ‥
騒乱罪のこと。1995年刑法改正前の呼称。
⇒そう‐じょう【騒擾】
そうじょう‐せき【相乗積】サウ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐せき【相乗積】サウ‥
2個以上の数を掛け合わせて得た積。
⇒そう‐じょう【相乗】
そうじょう‐でん【喪場殿】サウヂヤウ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐でん【喪場殿】サウヂヤウ‥
天皇崩御の時、葬儀場に設ける仮殿。そうばどの。
⇒そう‐じょう【葬場・喪場】
そうじょう‐の‐じん【宋襄の仁】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐の‐じん【宋襄の仁】‥ジヤウ‥
[左伝僖公22年](楚との戦いで、宋の公子目夷が楚の布陣しないうちに討ちたいと請うたが、襄公は、君子は人の困っている時に苦しめてはいけないといって討たず、かえって楚のために敗れたという故事)無益のなさけ。時宜を得ていない憐れみ。
⇒そう‐じょう【宋襄】
そうじょう‐へいきん【相乗平均】サウ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐へいきん【相乗平均】サウ‥
n個の数について、その相乗積のn乗根。幾何平均。
⇒そう‐じょう【相乗】
大辞林の検索結果 (30)
そう-じょう【双調】🔗⭐🔉
そう-じょう サウデウ [1][0] 【双調】
(1)日本音楽の音名。十二律の六番目の音。中国十二律の仲呂(チユウリヨ)に相当し,音高は洋楽のトにほぼ等しい。
(2)雅楽の六調子の一。{(1)}を主音とするもの。呂旋音階に属する。
そう-じょう【奏上】🔗⭐🔉
そう-じょう ―ジヤウ [0] 【奏上】 (名)スル
天皇に申し上げること。申奏。進奏。上奏。「総理大臣から事件の概要を―する」
そう-じょう【奏杖】🔗⭐🔉
そう-じょう ―ヂヤウ [0] 【奏杖】
高貴な人に文書を渡すとき挟んで差し出す杖(ツエ)。ふづえ。
そう-じょう【奏状】🔗⭐🔉
そう-じょう ―ジヤウ [0] 【奏状】
奏を記した文書。太政官(ダイジヨウカン)から奉るものには,事柄の大小に応じて,書式に論奏・奏事・便奏の三段階があった。
そう-じょう【相生】🔗⭐🔉
そう-じょう サウジヤウ [0] 【相生】
〔「そうしょう」とも〕
(1)五行説で,互いに他のものを生み出す関係。木が火を,火が土を,土が金を,金が水を,水が木を生むとする。
⇔相克(ソウコク)
(2)「相性」に同じ。また,相性がよいこと。「お俊は庄兵衛と相剋,彦右衛門と―なるべし/いさなとり(露伴)」
そう-じょう【相承】🔗⭐🔉
そう-じょう サウ― [0] 【相承】 (名)スル
⇒そうしょう(相承)
そう-じょう【相乗】🔗⭐🔉
そう-じょう サウ― [0] 【相乗】 (名)スル
(1)二つ以上の数を掛け合わせること。
(2)二つ以上の要素が相互に効果を強めあうこと。
そうじょう-こうか【相乗効果】🔗⭐🔉
そうじょう-こうか サウ―カウクワ [5] 【相乗効果】
複数の原因が重なって,個々に得られる結果以上になること。
そうじょう-さよう【相乗作用】🔗⭐🔉
そうじょう-さよう サウ― [5] 【相乗作用】
いくつかの要素が組み合わされると,互いに影響しあって個々に働くときよりも大きな力を発揮すること。
そうじょう-せき【相乗積】🔗⭐🔉
そうじょう-せき サウ― [3] 【相乗積】
二つ以上の数を掛け合わせて得た積。
そう-じょう【掃攘】🔗⭐🔉
そう-じょう サウジヤウ [0] 【掃攘】 (名)スル
はらいのぞくこと。特に幕末,外国を排撃すること。「天下の人民力を戮(アワ)せて夷狄を―せんと/近世紀聞(延房)」
そう-じょう【葬場・喪場】🔗⭐🔉
そう-じょう サウヂヤウ [0] 【葬場・喪場】
葬式を行う式場。葬儀場。斎場。
そうじょう-でん【葬場殿・喪場殿】🔗⭐🔉
そうじょう-でん サウヂヤウ― [3] 【葬場殿・喪場殿】
天皇の崩御の際,葬儀場に設ける仮殿。そうばどの。
そう-じょう【僧正】🔗⭐🔉
そう-じょう ―ジヤウ [1] 【僧正】
(1)僧綱(ソウゴウ)の最高位。僧都(ソウズ)・律師の上に位し,僧尼を統轄する。のち,大・正・権(ゴン)の三階級に分かれる。
(2)現在では,各宗の僧階の一。
そう-じょう【層状】🔗⭐🔉
そう-じょう ―ジヤウ [0] 【層状】
重なって層をなしている状態。
そうじょう-がんどうりゅうかてっこう-こうしょう【層状含銅硫化鉄鉱鉱床】🔗⭐🔉
そうじょう-がんどうりゅうかてっこう-こうしょう ―ジヤウガンドウリウクワテツクワウクワウシヤウ [16] 【層状含銅硫化鉄鉱鉱床】
緻密(チミツ)塊状の硫化物(黄鉄鉱・磁硫鉄鉱・黄銅鉱など)の集合体からなる層状の鉱床。海底火山活動に伴う噴気熱水による生成物と考えられ,広域変成作用を受けていることが多い。愛媛県別子(ベツシ)銅山は典型例。
→キースラーガー
そう-じょう【層畳】🔗⭐🔉
そう-じょう ―デフ [0] 【層畳】 (名)スル
何重にもかさなること。「市の―して高く聳ゆる状は/即興詩人(鴎外)」
そう-じょう【総状】🔗⭐🔉
そう-じょう ―ジヤウ [0] 【総状】
ふさのような状態。
そうじょう-かじょ【総状花序】🔗⭐🔉
そうじょう-かじょ ―ジヤウクワ― [5] 【総状花序】
無限花序の一。比較的節間の伸びた主軸に柄のある花を多数つけた花序。フジなど。
→花序
そう-じょう【騒擾】🔗⭐🔉
そう-じょう サウゼウ [0] 【騒擾】 (名)スル
事件などを起こして社会の秩序を乱すこと。「藩士の京師を―するもあり/日本開化小史(卯吉)」
そうじょう-ざい【騒擾罪】🔗⭐🔉
そうじょう-ざい サウゼウ― [3] 【騒擾罪】
⇒騒乱罪(ソウランザイ)
そう-じょう【宋襄】🔗⭐🔉
そう-じょう ―ジヤウ 【宋襄】
中国,春秋時代の宋の王,襄公。
そうじょう-の-じん【宋襄の仁】🔗⭐🔉
そうじょう-の-じん ―ジヤウ― 【宋襄の仁】
〔宋と楚(ソ)との戦いの際,宋の公子目夷が楚の布陣しないうちに攻撃しようと進言したが,襄公は君子は人の困っているときに苦しめてはいけないといって攻めず,楚に敗れたという「左氏伝(僖公二十二年)」の故事による〕
不必要な哀れみを施してひどい目にあうこと。無益の情け。事宜を得ない哀れみ。
そうじょう-が-たに【僧正谷】🔗⭐🔉
そうじょう-が-たに ソウジヤウ― 【僧正谷】
京都市左京区,鞍馬寺と貴船神社との間にある谷。牛若丸が武術を修業した所と伝える。
そう-じょうたい【躁状態】🔗⭐🔉
そう-じょうたい サウジヤウタイ [3] 【躁状態】
気分が高揚し意欲の亢進(コウシン)や思考の促進がみられる精神状態。爽快感があり,多弁で話の内容は誇大的,時に観念奔逸がある。活動性は高まるが行動に統一性がなく抑制がきかない。躁鬱(ソウウツ)病の典型的症状であるが,身体疾患やアルコール酩酊状態でもみられる。
そうじょう【相乗作用】(和英)🔗⭐🔉
そうじょう【相乗作用】
synergism (薬などの).
そうじょう【僧正】(和英)🔗⭐🔉
そうじょう【僧正】
a high priest;a bishop.→英和
そうじょう【層状の】(和英)🔗⭐🔉
そうじょう【層状の】
stratified;stratiform.
広辞苑+大辞林に「そうじょう」で始まるの検索結果。
 個の正の数について,これらの全部の積の
個の正の数について,これらの全部の積の  ,
,  ,
,  の相乗平均は
の相乗平均は