複数辞典一括検索+![]()
![]()
つかわ・す【遣わす】ツカハス🔗⭐🔉
つかわ・す【遣わす】ツカハス

 動五
動五



 他
他

 目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。
「皇帝が家臣を隣国に━」
「使者を━」
目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。
「皇帝が家臣を隣国に━」
「使者を━」
 目上の人が目下の人に物などを与える。
「ほうびを━」
目上の人が目下の人に物などを与える。
「ほうびを━」


 補動
補動
 《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。
「聞いて━」
「褒めて━」
「御所望なら呼んで━」
関連語
大分類‖与える‖あたえる
中分類‖与える‖あたえる
《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。
「聞いて━」
「褒めて━」
「御所望なら呼んで━」
関連語
大分類‖与える‖あたえる
中分類‖与える‖あたえる

 動五
動五



 他
他

 目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。
「皇帝が家臣を隣国に━」
「使者を━」
目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。
「皇帝が家臣を隣国に━」
「使者を━」
 目上の人が目下の人に物などを与える。
「ほうびを━」
目上の人が目下の人に物などを与える。
「ほうびを━」


 補動
補動
 《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。
「聞いて━」
「褒めて━」
「御所望なら呼んで━」
関連語
大分類‖与える‖あたえる
中分類‖与える‖あたえる
《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。
「聞いて━」
「褒めて━」
「御所望なら呼んで━」
関連語
大分類‖与える‖あたえる
中分類‖与える‖あたえる
つき【月】🔗⭐🔉
つき【月】

 名
名

 地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。
地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。
 古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。
古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。
 月の光。月光。
「━が差し込む」
月の光。月光。
「━が差し込む」
 暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。
「━に一度、会合を開く」
◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。
暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。
「━に一度、会合を開く」
◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。
 約一〇か月の妊娠期間。
「━が満ちて出産する」
約一〇か月の妊娠期間。
「━が満ちて出産する」
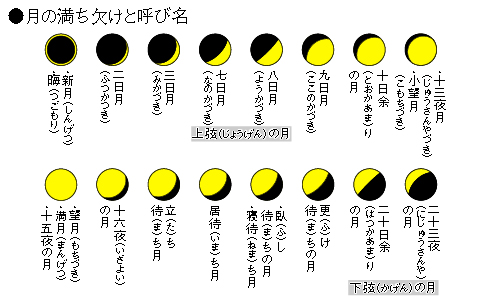

 名
名

 地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。
地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。
 古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。
古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。
 月の光。月光。
「━が差し込む」
月の光。月光。
「━が差し込む」
 暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。
「━に一度、会合を開く」
◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。
暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。
「━に一度、会合を開く」
◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。
 約一〇か月の妊娠期間。
「━が満ちて出産する」
約一〇か月の妊娠期間。
「━が満ちて出産する」
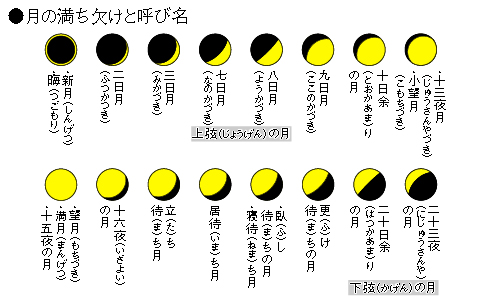
【月と鼈すっぽん】🔗⭐🔉
【月と鼈すっぽん】
二つのものの違いがはなはだしいことのたとえ。
◇どちらも丸い形をしているが、その価値の差は比較にならないほど大きいことから。
【月に叢雲むらくも花に風】🔗⭐🔉
【月に叢雲むらくも花に風】
好事にはとかく邪魔が入りやすく、よい状態は長続きしないことのたとえ。
つき【▼坏】🔗⭐🔉
つき【▼坏】

 名
名
 古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。
古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。

 名
名
 古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。
古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。
つき【▼槻】🔗⭐🔉
つき【▼槻】

 名
名
 〔古〕ケヤキ。
〔古〕ケヤキ。

 名
名
 〔古〕ケヤキ。
〔古〕ケヤキ。
つき【付き(▽附き)】🔗⭐🔉
つき【付き(▽附き)】


 名
名

 付くこと。付着すること。また、そのぐあい。
付くこと。付着すること。また、そのぐあい。
 火がつくこと。また、そのぐあい。
「━の悪いライター」
火がつくこと。また、そのぐあい。
「━の悪いライター」
 勝負事などで、好運。
「━が落ちる」
勝負事などで、好運。
「━が落ちる」
 つき従う人。つきそい。従者。
「お━の人」
つき従う人。つきそい。従者。
「お━の人」

 (造)
(造) 《名詞に付いて》
《名詞に付いて》
 その様子。
「顔━・手━・体━」
その様子。
「顔━・手━・体━」
 かな書きが多い。
かな書きが多い。
 そのものが付属していること。
「保証━」
「バス、トイレ━」
「骨━の肉」
そのものが付属していること。
「保証━」
「バス、トイレ━」
「骨━の肉」
 そのものに付き添ったり所属したりしていること。
「社長━の秘書」
「チーム━の医師」
◇
そのものに付き添ったり所属したりしていること。
「社長━の秘書」
「チーム━の医師」
◇ は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。
関連語
大分類‖付く‖つく
中分類‖付着‖ふちゃく
は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。
関連語
大分類‖付く‖つく
中分類‖付着‖ふちゃく


 名
名

 付くこと。付着すること。また、そのぐあい。
付くこと。付着すること。また、そのぐあい。
 火がつくこと。また、そのぐあい。
「━の悪いライター」
火がつくこと。また、そのぐあい。
「━の悪いライター」
 勝負事などで、好運。
「━が落ちる」
勝負事などで、好運。
「━が落ちる」
 つき従う人。つきそい。従者。
「お━の人」
つき従う人。つきそい。従者。
「お━の人」

 (造)
(造) 《名詞に付いて》
《名詞に付いて》
 その様子。
「顔━・手━・体━」
その様子。
「顔━・手━・体━」
 かな書きが多い。
かな書きが多い。
 そのものが付属していること。
「保証━」
「バス、トイレ━」
「骨━の肉」
そのものが付属していること。
「保証━」
「バス、トイレ━」
「骨━の肉」
 そのものに付き添ったり所属したりしていること。
「社長━の秘書」
「チーム━の医師」
◇
そのものに付き添ったり所属したりしていること。
「社長━の秘書」
「チーム━の医師」
◇ は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。
関連語
大分類‖付く‖つく
中分類‖付着‖ふちゃく
は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。
関連語
大分類‖付く‖つく
中分類‖付着‖ふちゃく
明鏡国語辞典 ページ 4032。