複数辞典一括検索+![]()
![]()
しょう【床】シャウ🔗⭐🔉
しょう【床】シャウ
 (造)
(造)
 ねどこ。寝台。
「起━・病━・臨━」
ねどこ。寝台。
「起━・病━・臨━」
 腰かけ。
「━几しょうぎ」
腰かけ。
「━几しょうぎ」
 花や苗を育てる所。苗どこ。
「温━」
花や苗を育てる所。苗どこ。
「温━」
 物を支える部分。底部。土台。
「花━・河━」
物を支える部分。底部。土台。
「花━・河━」
 (造)
(造)
 ねどこ。寝台。
「起━・病━・臨━」
ねどこ。寝台。
「起━・病━・臨━」
 腰かけ。
「━几しょうぎ」
腰かけ。
「━几しょうぎ」
 花や苗を育てる所。苗どこ。
「温━」
花や苗を育てる所。苗どこ。
「温━」
 物を支える部分。底部。土台。
「花━・河━」
物を支える部分。底部。土台。
「花━・河━」
しょう‐ぎ【床▼几・床机】シャウ━🔗⭐🔉
しょう‐ぎ【床▼几・床机】シャウ━

 名
名
 脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。
脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。

 名
名
 脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。
脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。
とこ【床】🔗⭐🔉
とこ【床】

 名
名

 寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。
「━をとる」
「━に就く」
「病の━に臥ふす」
寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。
「━をとる」
「━に就く」
「病の━に臥ふす」
 ゆか。
「━を張る」
ゆか。
「━を張る」
 苗を植えて育てるところ。苗床。
苗を植えて育てるところ。苗床。
 畳の芯しん。
畳の芯しん。
 川の底。川床。
川の底。川床。
 「床の間」の略。→床の間
「━柱」
「床の間」の略。→床の間
「━柱」

 名
名

 寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。
「━をとる」
「━に就く」
「病の━に臥ふす」
寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。
「━をとる」
「━に就く」
「病の━に臥ふす」
 ゆか。
「━を張る」
ゆか。
「━を張る」
 苗を植えて育てるところ。苗床。
苗を植えて育てるところ。苗床。
 畳の芯しん。
畳の芯しん。
 川の底。川床。
川の底。川床。
 「床の間」の略。→床の間
「━柱」
「床の間」の略。→床の間
「━柱」
とこ‐あげ【床上げ】🔗⭐🔉
とこ‐あげ【床上げ】

 名・自サ変
名・自サ変
 長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。
長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。

 名・自サ変
名・自サ変
 長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。
長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。
とこ‐いり【床入り】🔗⭐🔉
とこ‐いり【床入り】

 名・自サ変
名・自サ変
 寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。
寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。

 名・自サ変
名・自サ変
 寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。
寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。
とこ‐かざり【床飾り】🔗⭐🔉
とこ‐かざり【床飾り】

 名
名
 掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。
掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。

 名
名
 掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。
掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。
とこ‐さかずき【床杯】━サカヅキ🔗⭐🔉
とこ‐さかずき【床杯】━サカヅキ

 名
名
 婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。
婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。

 名
名
 婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。
婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。
とこ‐ずれ【床擦れ】🔗⭐🔉
とこ‐ずれ【床擦れ】

 名
名
 長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。
長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。

 名
名
 長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。
長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。
とこ‐だたみ【床畳】🔗⭐🔉
とこ‐だたみ【床畳】

 名
名
 床の間に敷く畳。
床の間に敷く畳。

 名
名
 床の間に敷く畳。
床の間に敷く畳。
とこ‐つち【床土】🔗⭐🔉
とこ‐つち【床土】

 名
名

 苗床用の土。
苗床用の土。
 床の間の壁などに使う土。
床の間の壁などに使う土。

 名
名

 苗床用の土。
苗床用の土。
 床の間の壁などに使う土。
床の間の壁などに使う土。
とこ‐の‐ま【床の間】🔗⭐🔉
とこ‐の‐ま【床の間】

 名
名
 日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。
日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。
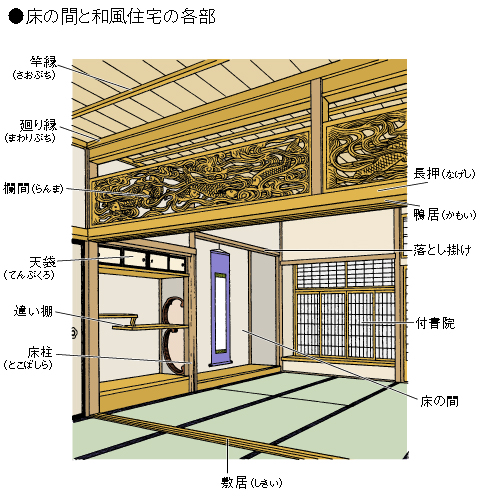

 名
名
 日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。
日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。
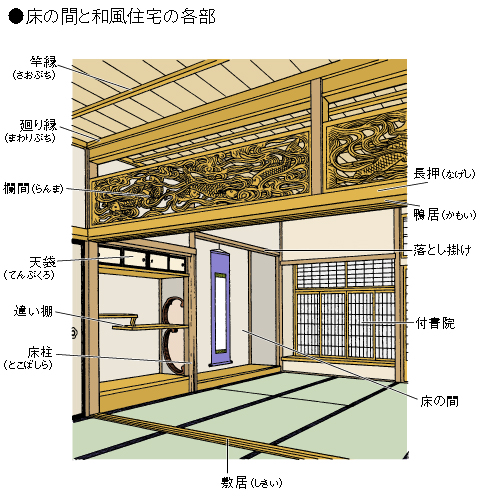
とこ‐ばしら【床柱】🔗⭐🔉
とこ‐ばなれ【床離れ】🔗⭐🔉
とこ‐ばなれ【床離れ】

 名・自サ変
名・自サ変

 朝、寝床から起き出ること。起床。
朝、寝床から起き出ること。起床。
 病気が治って病床から離れること。
病気が治って病床から離れること。

 名・自サ変
名・自サ変

 朝、寝床から起き出ること。起床。
朝、寝床から起き出ること。起床。
 病気が治って病床から離れること。
病気が治って病床から離れること。
とこ‐ばらい【床払い】━バラヒ🔗⭐🔉
とこ‐ばらい【床払い】━バラヒ

 名
名
 床上げ。
床上げ。

 名
名
 床上げ。
床上げ。
とこ‐や【床屋】🔗⭐🔉
とこ‐や【床屋】

 名
名
 理髪店。理容店。また、理髪師。
理髪店。理容店。また、理髪師。

 名
名
 理髪店。理容店。また、理髪師。
理髪店。理容店。また、理髪師。
とこ‐やま【床山】🔗⭐🔉
とこ‐やま【床山】

 名
名
 力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。
力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。

 名
名
 力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。
力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。
ゆか【床】🔗⭐🔉
ゆか【床】

 名
名

 建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。
「━が抜ける」
建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。
「━が抜ける」
 劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。
劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。
 料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。
料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。

 名
名

 建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。
「━が抜ける」
建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。
「━が抜ける」
 劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。
劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。
 料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。
料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。
ゆか‐いた【床板】🔗⭐🔉
ゆか‐いた【床板】

 名
名
 建物の床として張られた板。
建物の床として張られた板。

 名
名
 建物の床として張られた板。
建物の床として張られた板。
ゆか‐うえ【床上】━ウヘ🔗⭐🔉
ゆか‐うんどう【床運動】🔗⭐🔉
ゆか‐うんどう【床運動】

 名
名
 体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。
体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。

 名
名
 体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。
体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。
ゆかし・い【(床しい)】🔗⭐🔉
ゆかし・い【(床しい)】

 形
形

 気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。
「━人柄」
気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。
「━人柄」
 昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。
「古式━儀式」
昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。
「古式━儀式」
 ‐げ/‐さ/‐が・る
‐げ/‐さ/‐が・る

 形
形

 気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。
「━人柄」
気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。
「━人柄」
 昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。
「古式━儀式」
昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。
「古式━儀式」
 ‐げ/‐さ/‐が・る
‐げ/‐さ/‐が・る
ゆか‐だんぼう【床暖房】━ダンバウ🔗⭐🔉
ゆか‐だんぼう【床暖房】━ダンバウ

 名
名
 家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。
家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。

 名
名
 家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。
家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。
明鏡国語辞典に「床」で始まるの検索結果 1-23。