複数辞典一括検索+![]()
![]()
【恒】🔗⭐🔉
【恒】
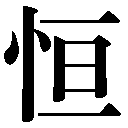 9画
9画  部 [常用漢字]
区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50
【恆】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50
【恆】旧字人名に使える旧字
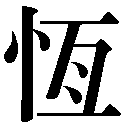 9画
9画  部
区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91
《常用音訓》コウ
《音読み》
部
区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91
《常用音訓》コウ
《音読み》  コウ
コウ /ゴウ
/ゴウ 〈h
〈h ng〉/
ng〉/ コウ
コウ
 《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに
《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる
《意味》
《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに
《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる
《意味》

 {名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕
{名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕
 {動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕
{動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕
 {動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」
{動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」
 {副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」
{副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。
{名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。
 {名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙
《単語家族》
克コク(張りきる)
{名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙
《単語家族》
克コク(張りきる) 極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。
《類義》
→常
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。
《類義》
→常
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
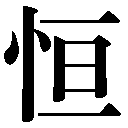 9画
9画  部 [常用漢字]
区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50
【恆】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50
【恆】旧字人名に使える旧字
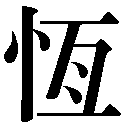 9画
9画  部
区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91
《常用音訓》コウ
《音読み》
部
区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91
《常用音訓》コウ
《音読み》  コウ
コウ /ゴウ
/ゴウ 〈h
〈h ng〉/
ng〉/ コウ
コウ
 《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに
《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる
《意味》
《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに
《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる
《意味》

 {名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕
{名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕
 {動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕
{動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕
 {動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」
{動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」
 {副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」
{副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。
{名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。
 {名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙
《単語家族》
克コク(張りきる)
{名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙
《単語家族》
克コク(張りきる) 極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。
《類義》
→常
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。
《類義》
→常
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源 ページ 1682 での【恒】単語。