複数辞典一括検索+![]()
![]()
【章】🔗⭐🔉
【章】
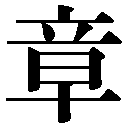 11画 立部 [三年]
区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(シヤウ)
11画 立部 [三年]
区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(シヤウ)
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)
《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき
《意味》
ng〉
《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)
《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき
《意味》
 {名}楽曲のひと区切り。「楽章」
{名}楽曲のひと区切り。「楽章」
 {名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」
{名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」
 {単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕
{単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕
 {名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕
{名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕
 {名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕
{名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕
 {形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕
{形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕
 {動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕
{動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕
 {名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」
{名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」
 {単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」
《解字》
{単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」
《解字》
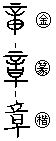 会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。
《単語家族》
昌ショウ(あきらか)
会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。
《単語家族》
昌ショウ(あきらか) 彰(あきらか)
彰(あきらか) 陽(明るく浮き出る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
陽(明るく浮き出る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
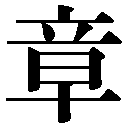 11画 立部 [三年]
区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(シヤウ)
11画 立部 [三年]
区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(シヤウ)
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)
《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき
《意味》
ng〉
《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)
《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき
《意味》
 {名}楽曲のひと区切り。「楽章」
{名}楽曲のひと区切り。「楽章」
 {名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」
{名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」
 {単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕
{単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕
 {名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕
{名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕
 {名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕
{名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕
 {形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕
{形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕
 {動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕
{動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕
 {名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」
{名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」
 {単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」
《解字》
{単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」
《解字》
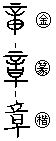 会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。
《単語家族》
昌ショウ(あきらか)
会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。
《単語家族》
昌ショウ(あきらか) 彰(あきらか)
彰(あきらか) 陽(明るく浮き出る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
陽(明るく浮き出る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
漢字源 ページ 3256 での【章】単語。