複数辞典一括検索+![]()
![]()
物 もの🔗⭐🔉
【物】
 8画 牛部 [三年]
区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8
《常用音訓》ブツ/モツ/もの
《音読み》 ブツ
8画 牛部 [三年]
区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8
《常用音訓》ブツ/モツ/もの
《音読み》 ブツ /モツ/モチ
/モツ/モチ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 もの
《名付け》 たね・もの
《意味》
〉
《訓読み》 もの
《名付け》 たね・もの
《意味》
 {名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕
{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕
 {名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕
{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕
 〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。
〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」
《解字》
会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。
〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」
《解字》
会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 8画 牛部 [三年]
区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8
《常用音訓》ブツ/モツ/もの
《音読み》 ブツ
8画 牛部 [三年]
区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8
《常用音訓》ブツ/モツ/もの
《音読み》 ブツ /モツ/モチ
/モツ/モチ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 もの
《名付け》 たね・もの
《意味》
〉
《訓読み》 もの
《名付け》 たね・もの
《意味》
 {名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕
{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕
 {名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕
{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕
 〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。
〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」
《解字》
会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。
〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」
《解字》
会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
者 もの🔗⭐🔉
【者】
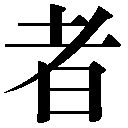 人名に使える旧字
人名に使える旧字
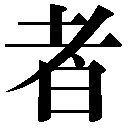 8画 老部 [三年]
区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2
《常用音訓》シャ/もの
《音読み》 シャ
8画 老部 [三年]
区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2
《常用音訓》シャ/もの
《音読み》 シャ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 もの/こと
《名付け》 ひさ・ひと
《意味》
〉
《訓読み》 もの/こと
《名付け》 ひさ・ひと
《意味》
 {名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕
{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕
 {助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕
{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕
 {助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」
{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」
 「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。
「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。
 {助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」
《解字》
{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」
《解字》
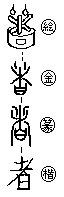 象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
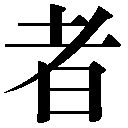 人名に使える旧字
人名に使える旧字
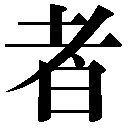 8画 老部 [三年]
区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2
《常用音訓》シャ/もの
《音読み》 シャ
8画 老部 [三年]
区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2
《常用音訓》シャ/もの
《音読み》 シャ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 もの/こと
《名付け》 ひさ・ひと
《意味》
〉
《訓読み》 もの/こと
《名付け》 ひさ・ひと
《意味》
 {名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕
{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕
 {助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕
{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕
 {助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」
{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」
 「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。
「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。
 {助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」
《解字》
{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」
《解字》
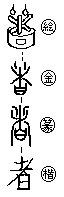 象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「もの」で完全一致するの検索結果 1-2。