複数辞典一括検索+![]()
![]()
【伺隙】🔗⭐🔉
【伺隙】
シゲキ・ゲキヲウカガウ うまく利用すべき機会をねらう。
【伺察】🔗⭐🔉
【伺察】
シサツ ようすをうかがい探る。ようすを探ること。また、その人。
【似】🔗⭐🔉
【似】
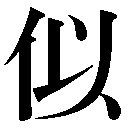 7画 人部 [五年]
区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97
《常用音訓》ジ/に…る
《音読み》 ジ
7画 人部 [五年]
区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97
《常用音訓》ジ/に…る
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈s
〈s ・sh
・sh 〉
《訓読み》 にる/にたり/ごとし
《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり
《意味》
〉
《訓読み》 にる/にたり/ごとし
《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり
《意味》
 {動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕
{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕
 {動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕
{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕
 {指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕
{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕
 {助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕
{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕
 {動}つぐ。▽嗣に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
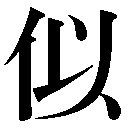 7画 人部 [五年]
区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97
《常用音訓》ジ/に…る
《音読み》 ジ
7画 人部 [五年]
区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97
《常用音訓》ジ/に…る
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈s
〈s ・sh
・sh 〉
《訓読み》 にる/にたり/ごとし
《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり
《意味》
〉
《訓読み》 にる/にたり/ごとし
《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり
《意味》
 {動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕
{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕
 {動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕
{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕
 {指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕
{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕
 {助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕
{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕
 {動}つぐ。▽嗣に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源 ページ 231。