複数辞典一括検索+![]()
![]()
【琲】🔗⭐🔉
【琲】
 12画 玉部
区点=6474 16進=606A シフトJIS=E0E8
《音読み》 ハイ
12画 玉部
区点=6474 16進=606A シフトJIS=E0E8
《音読み》 ハイ /バイ
/バイ 〈b
〈b i〉
《訓読み》 つらぬく
《意味》
i〉
《訓読み》 つらぬく
《意味》
 {名}たま飾り。多くの真珠にひもを通して、二列にたらした飾り。
{名}たま飾り。多くの真珠にひもを通して、二列にたらした飾り。
 {動}つらぬく。ひもを通してつらぬく。
〔国〕「珈琲コーヒー」とは、コーヒーのこと。▽オランダ語koffieの音訳。
《解字》
会意兼形声。「玉+音符非(二列にわかれる)」。
{動}つらぬく。ひもを通してつらぬく。
〔国〕「珈琲コーヒー」とは、コーヒーのこと。▽オランダ語koffieの音訳。
《解字》
会意兼形声。「玉+音符非(二列にわかれる)」。
 12画 玉部
区点=6474 16進=606A シフトJIS=E0E8
《音読み》 ハイ
12画 玉部
区点=6474 16進=606A シフトJIS=E0E8
《音読み》 ハイ /バイ
/バイ 〈b
〈b i〉
《訓読み》 つらぬく
《意味》
i〉
《訓読み》 つらぬく
《意味》
 {名}たま飾り。多くの真珠にひもを通して、二列にたらした飾り。
{名}たま飾り。多くの真珠にひもを通して、二列にたらした飾り。
 {動}つらぬく。ひもを通してつらぬく。
〔国〕「珈琲コーヒー」とは、コーヒーのこと。▽オランダ語koffieの音訳。
《解字》
会意兼形声。「玉+音符非(二列にわかれる)」。
{動}つらぬく。ひもを通してつらぬく。
〔国〕「珈琲コーヒー」とは、コーヒーのこと。▽オランダ語koffieの音訳。
《解字》
会意兼形声。「玉+音符非(二列にわかれる)」。
【琵】🔗⭐🔉
【琵】
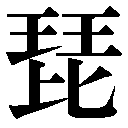 12画 玉部
区点=4092 16進=487C シフトJIS=94FA
《音読み》 ヒ
12画 玉部
区点=4092 16進=487C シフトJIS=94FA
《音読み》 ヒ /ビ
/ビ 〈p
〈p 〉
《意味》
〉
《意味》
 「琵琶ビワ」とは、(イ)果樹の名。びわの木。「枇杷」とも。(ロ)弦楽器の名。びわの実形の胴に棹サオがついており、四弦(イラン起源)または五弦(インド起源)の弦楽器。中国の阮咸ゲンカン(四弦)とともに奈良時代に日本に伝来した。
《解字》
形声。「ことの形+音符比」。上部は、玉ではない。
《熟語》
→熟語
「琵琶ビワ」とは、(イ)果樹の名。びわの木。「枇杷」とも。(ロ)弦楽器の名。びわの実形の胴に棹サオがついており、四弦(イラン起源)または五弦(インド起源)の弦楽器。中国の阮咸ゲンカン(四弦)とともに奈良時代に日本に伝来した。
《解字》
形声。「ことの形+音符比」。上部は、玉ではない。
《熟語》
→熟語
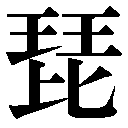 12画 玉部
区点=4092 16進=487C シフトJIS=94FA
《音読み》 ヒ
12画 玉部
区点=4092 16進=487C シフトJIS=94FA
《音読み》 ヒ /ビ
/ビ 〈p
〈p 〉
《意味》
〉
《意味》
 「琵琶ビワ」とは、(イ)果樹の名。びわの木。「枇杷」とも。(ロ)弦楽器の名。びわの実形の胴に棹サオがついており、四弦(イラン起源)または五弦(インド起源)の弦楽器。中国の阮咸ゲンカン(四弦)とともに奈良時代に日本に伝来した。
《解字》
形声。「ことの形+音符比」。上部は、玉ではない。
《熟語》
→熟語
「琵琶ビワ」とは、(イ)果樹の名。びわの木。「枇杷」とも。(ロ)弦楽器の名。びわの実形の胴に棹サオがついており、四弦(イラン起源)または五弦(インド起源)の弦楽器。中国の阮咸ゲンカン(四弦)とともに奈良時代に日本に伝来した。
《解字》
形声。「ことの形+音符比」。上部は、玉ではない。
《熟語》
→熟語
【琵琶行】🔗⭐🔉
【琵琶行】
ビワコウ 唐の白居易のつくった長編詩。白居易が江州に左遷されていたとき(八一六年)、潯陽江ジンヨウコウのほとりで、ある女性のひく琵琶の音を聞き、その女性の生涯に感じてつくった。
【琵琶記】🔗⭐🔉
【琵琶記】
ビワキ 元ゲン代末の高明がつくった戯曲。後漢時代にある新婚の男が、妻である趙チョウ氏の娘に父母をたのんで都に出た。やがて勅命で大臣のむことなる。趙氏の娘は夫の父母の死後、夫をたずね都でめぐりあう。大臣の娘は自分から譲って趙氏の娘を正妻とし、三人仲よく暮らしたという筋。初期南曲の傑作。
漢字源 ページ 2884。