複数辞典一括検索+![]()
![]()
【丐戸】🔗⭐🔉
【丐戸】
カイコ 江蘇コウソ省・浙江セッコウ省一帯に住んでいた賤民センミンの名。一般の人と結婚したり、官吏になったりすることを禁じられていた。
【丐取】🔗⭐🔉
【丐取】
カイシュ ねだって手に入れる。
【丐命】🔗⭐🔉
【丐命】
カイメイ 命の助かることを願う。助命を求めること。〈類義語〉乞命キツメイ。
【丑】🔗⭐🔉
【丑】
 4画 一部 [人名漢字]
区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E
《音読み》 チュウ(チウ)
4画 一部 [人名漢字]
区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E
《音読み》 チュウ(チウ)
 〈ch
〈ch u〉
《訓読み》 うし
《名付け》 うし・ひろ
《意味》
u〉
《訓読み》 うし
《名付け》 うし・ひろ
《意味》
 {名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。
{名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。
 {名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。
《解字》
{名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。
《解字》
 象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。
《単語家族》
手シュ
象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。
《単語家族》
手シュ 守シュ(とりこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
守シュ(とりこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 4画 一部 [人名漢字]
区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E
《音読み》 チュウ(チウ)
4画 一部 [人名漢字]
区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E
《音読み》 チュウ(チウ)
 〈ch
〈ch u〉
《訓読み》 うし
《名付け》 うし・ひろ
《意味》
u〉
《訓読み》 うし
《名付け》 うし・ひろ
《意味》
 {名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。
{名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。
 {名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。
《解字》
{名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。
《解字》
 象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。
《単語家族》
手シュ
象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。
《単語家族》
手シュ 守シュ(とりこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
守シュ(とりこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
【丑三】🔗⭐🔉
【丑三】
ウシミツ〔国〕 丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。
丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。 真夜中のこと。
真夜中のこと。
 丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。
丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。 真夜中のこと。
真夜中のこと。
【不】🔗⭐🔉
【不】
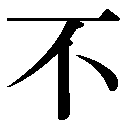 4画 一部 [四年]
区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573
《常用音訓》フ/ブ
《音読み》 フ
4画 一部 [四年]
区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573
《常用音訓》フ/ブ
《音読み》 フ /ブ
/ブ /フウ
/フウ /フツ
/フツ /ホチ
/ホチ 〈f
〈f u〉〈b
u〉〈b 〉
《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば
《名付け》 ず
《意味》
〉
《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば
《名付け》 ず
《意味》
 {副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」
{副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」
 {感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。
{感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。
 {助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕
{助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕
 {接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕
{接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕
 {形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕
《解字》
{形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕
《解字》
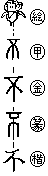 象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
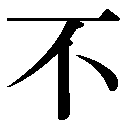 4画 一部 [四年]
区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573
《常用音訓》フ/ブ
《音読み》 フ
4画 一部 [四年]
区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573
《常用音訓》フ/ブ
《音読み》 フ /ブ
/ブ /フウ
/フウ /フツ
/フツ /ホチ
/ホチ 〈f
〈f u〉〈b
u〉〈b 〉
《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば
《名付け》 ず
《意味》
〉
《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば
《名付け》 ず
《意味》
 {副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」
{副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」
 {感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。
{感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。
 {助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕
{助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕
 {接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕
{接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕
 {形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕
《解字》
{形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕
《解字》
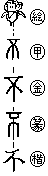 象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源 ページ 60。