複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (0)
大辞林の検索結果 (100)
はい-あつ【背圧】🔗⭐🔉
はい-あつ [0] 【背圧】
蒸気機関や内燃機関の排気の圧力。この圧力が高いと,機関の効率は悪くなる。バック-プレッシャー。
はい-あん【廃案】🔗⭐🔉
はい-あん [0] 【廃案】
議決・採用されず廃止となった議案・考案。国会で,審議未了となった案件。
はいい-すう【配位数】🔗⭐🔉
はいい-すう ― ― [3] 【配位数】
(1)錯体の中で,中心の原子に配位している配位子の数。
(2)結晶構造をつくる一つの原子の周囲に隣接する他の原子の数。
― [3] 【配位数】
(1)錯体の中で,中心の原子に配位している配位子の数。
(2)結晶構造をつくる一つの原子の周囲に隣接する他の原子の数。
 ― [3] 【配位数】
(1)錯体の中で,中心の原子に配位している配位子の数。
(2)結晶構造をつくる一つの原子の周囲に隣接する他の原子の数。
― [3] 【配位数】
(1)錯体の中で,中心の原子に配位している配位子の数。
(2)結晶構造をつくる一つの原子の周囲に隣接する他の原子の数。
はい-うら【灰占】🔗⭐🔉
はい-うら ハヒ― [0] 【灰占】
昔,埋み火や火桶(ヒオケ)などの灰を掻(カ)いて吉凶を占ったこと。
はい-えそ【肺壊疽】🔗⭐🔉
はい-えそ ― ソ [3] 【肺壊疽】
腐敗菌の混合感染により,肺組織が化膿・壊死(エシ)する病気。多く肺炎に続発。肺化膿症。
ソ [3] 【肺壊疽】
腐敗菌の混合感染により,肺組織が化膿・壊死(エシ)する病気。多く肺炎に続発。肺化膿症。
 ソ [3] 【肺壊疽】
腐敗菌の混合感染により,肺組織が化膿・壊死(エシ)する病気。多く肺炎に続発。肺化膿症。
ソ [3] 【肺壊疽】
腐敗菌の混合感染により,肺組織が化膿・壊死(エシ)する病気。多く肺炎に続発。肺化膿症。
はい-おさえ【灰押(さ)え】🔗⭐🔉
はい-おさえ ハヒオサヘ [3][0][5] 【灰押(さ)え】
「灰押し」に同じ。
はい-おし【灰押し】🔗⭐🔉
はい-おし ハヒ― [0][4] 【灰押し】
香炉・火鉢などの灰を掻きならし整える金具。灰押さえ。灰掻き。
はい-おとし【灰落(と)し】🔗⭐🔉
はい-おとし ハヒ― [3][0] 【灰落(と)し】
タバコの灰などを落とし入れる器具。灰皿。
はいかい-か【俳諧歌】🔗⭐🔉
はいかい-か [3] 【俳諧歌】
(1)和歌の一体。滑稽味を帯びた和歌。古今集巻一九に「誹諧歌」として多数が収録されて以来,勅撰集にしばしば取り上げられた。はいかいうた。
(2)狂歌の別名。
はいかい-し【俳諧師】🔗⭐🔉
はいかい-し [3] 【俳諧師】
俳諧を職業とする人。また,俳諧に巧みな人。俳諧宗匠。点者。業俳(ギヨウハイ)。
はいかい-しきもく【俳諧式目】🔗⭐🔉
はいかい-しきもく [6] 【俳諧式目】
俳諧興行の際の規則・作法。また,それらを記した書。「はなひ草」「毛吹草」など。
はいかい-み【俳諧味】🔗⭐🔉
はいかい-み [3][5][0] 【俳諧味】
俳諧的な味わい・趣。滑稽・軽妙・洒脱・脱俗的な味わいなど。俳味。
はいかいたいよう【俳諧大要】🔗⭐🔉
はいかいたいよう ―タイエウ 【俳諧大要】
俳論。正岡子規著。1895年(明治28)「日本」に連載。子規が自らの俳句理論を体系的に論述,写実を主張した。
はい-かき【灰掻き】🔗⭐🔉
はい-かき ハヒ― [3][4] 【灰掻き】
「灰押し」に同じ。
はいき-かん【排気管】🔗⭐🔉
はいき-かん ―クワン [0] 【排気管】
熱機関で,排気を出すための管。消音器を含めていうこともある。
はいき-き【排気機】🔗⭐🔉
はいき-き [3] 【排気機】
(1)エア-ポンプに同じ。
(2)蒸気機関で,復水器中の空気を排出する装置。
(3)鉱山・土木工事などで,ガス・空気の排出に用いる機械の総称。
はいき-こう【排気坑】🔗⭐🔉
はいき-こう ―カウ [0][3] 【排気坑】
鉱山やトンネルで,坑内の汚れた空気を地上に排出する坑道。
はいき-きかく【廃棄規格】🔗⭐🔉
はいき-きかく [4] 【廃棄規格】
製品が廃棄物になったときの処理の仕方(埋め立て不適,焼却不適,リサイクル可能など)についての規格を定めること。適正処理が困難な廃棄物を減らすのが目的。
はいき-の-かみ【波比岐神】🔗⭐🔉
はいき-の-かみ ハヒキ― 【波比岐神】
屋敷を守護するといわれる神。古事記神話では大年神(オオトシノカミ)の子。
はいくたいかん【俳句大観】🔗⭐🔉
はいくたいかん ―タイクワン 【俳句大観】
俳句集。佐々政一編。1916年(大正5)刊。明治以前の著名な発句を五十音順に配列,初句・中句・本句のどこからも検索でき,句ごとに作者と出典を記す。
はい-け【廃家】🔗⭐🔉
はい-け [1] 【廃家】 (名)スル
「はいか(廃家)」に同じ。
はいこう-せい【背光性】🔗⭐🔉
はいこう-せい ハイクワウ― [0] 【背光性】
植物器官が光の来る方向と反対方向に曲がる性質。負の屈光性。背日性。
→屈性
はい-こ・む【這い込む】🔗⭐🔉
はい-こ・む ハヒ― [3][0] 【這い込む】 (動マ五[四])
(1)はって中にはいりこむ。はい入る。「―・むすきもない」「石垣から,獺(カワウソ)が―・んで/歌行灯(鏡花)」
(2)夜這(ヨバ)いをする。「ラシヤメンの処へ―・んで/西洋道中膝栗毛(魯文)」
[可能] はいこめる
はい-さつ【拝察】🔗⭐🔉
はい-さつ [0] 【拝察】 (名)スル
推察することをへりくだっていう語。「御心労のほど―いたします」
はいしん-こうい【背信行為】🔗⭐🔉
はいしん-こうい ―カウ [5] 【背信行為】
(1)信義を裏切る行為。
(2)戦争において,味方の利益のため,休戦旗・赤十字旗を不当に使用するなどして,敵の信頼を裏切りその行動を誤らせる行為。戦時国際法上,違法とされる。
[5] 【背信行為】
(1)信義を裏切る行為。
(2)戦争において,味方の利益のため,休戦旗・赤十字旗を不当に使用するなどして,敵の信頼を裏切りその行動を誤らせる行為。戦時国際法上,違法とされる。
 [5] 【背信行為】
(1)信義を裏切る行為。
(2)戦争において,味方の利益のため,休戦旗・赤十字旗を不当に使用するなどして,敵の信頼を裏切りその行動を誤らせる行為。戦時国際法上,違法とされる。
[5] 【背信行為】
(1)信義を裏切る行為。
(2)戦争において,味方の利益のため,休戦旗・赤十字旗を不当に使用するなどして,敵の信頼を裏切りその行動を誤らせる行為。戦時国際法上,違法とされる。
はいすい-かん【配水管】🔗⭐🔉
はいすい-かん ―クワン [0] 【配水管】
上水を供給するための管。
はいすい-き【排水器】🔗⭐🔉
はいすい-き [3] 【排水器】
排水に用いる器械。排水ポンプなど。
はいすい-けん【排水権】🔗⭐🔉
はいすい-けん [3] 【排水権】
自然に流れてくる水を隣地に排出することができる権利。民法上,認められている。
はいすい-ろ【排水路】🔗⭐🔉
はいすい-ろ [3] 【排水路】
雨水・汚水などの排水のために設けた水路。
はい-すくい【灰掬い】🔗⭐🔉
はい-すくい ハヒスクヒ [3] 【灰掬い】
「灰匙(ハイサジ)」に同じ。
はいせい-しん【肺性心】🔗⭐🔉
はいせい-しん [3] 【肺性心】
肺気腫・肺結核などの肺疾患に伴って発症する心臓障害。右心室が機能不全に陥り,呼吸困難・心悸亢進が見られる。
はい-せいせい【裴世清】🔗⭐🔉
はい-せいせい 【裴世清】
中国,隋の官人。608年遣隋使小野妹子(オノノイモコ)らの帰国のとき,隋使として来日。朝廷に国書を提出。同年,再び遣隋使となった妹子らとともに隋に帰った。生没年未詳。
はいせき-いこう【配石遺構】🔗⭐🔉
はいせき-いこう ― コウ [5] 【配石遺構】
縄文時代につくられた,石を種々の形に配置した遺構。環状列石・方形・祭壇状・配石墓があり,祭祀・埋葬に関係している。
コウ [5] 【配石遺構】
縄文時代につくられた,石を種々の形に配置した遺構。環状列石・方形・祭壇状・配石墓があり,祭祀・埋葬に関係している。
 コウ [5] 【配石遺構】
縄文時代につくられた,石を種々の形に配置した遺構。環状列石・方形・祭壇状・配石墓があり,祭祀・埋葬に関係している。
コウ [5] 【配石遺構】
縄文時代につくられた,石を種々の形に配置した遺構。環状列石・方形・祭壇状・配石墓があり,祭祀・埋葬に関係している。
はい-せせり【灰 り】🔗⭐🔉
り】🔗⭐🔉
はい-せせり ハヒ― 【灰 り】
火箸(ヒバシ)などで灰をいじること。灰いじり。「火箸を取り―して/浮世草子・諸艶大鑑 3」
り】
火箸(ヒバシ)などで灰をいじること。灰いじり。「火箸を取り―して/浮世草子・諸艶大鑑 3」
 り】
火箸(ヒバシ)などで灰をいじること。灰いじり。「火箸を取り―して/浮世草子・諸艶大鑑 3」
り】
火箸(ヒバシ)などで灰をいじること。灰いじり。「火箸を取り―して/浮世草子・諸艶大鑑 3」
はいせつ-き【排泄器】🔗⭐🔉
はいせつ-き [4][3] 【排泄器】
「排出器」に同じ。
はい-そくせん【肺塞栓】🔗⭐🔉
はい-そくせん [3] 【肺塞栓】
手術・けが・伝染病などによって生じた血栓や気泡などが,血流によって運ばれて肺の血管をふさいだ状態。太い動脈に生じると激しい胸痛を訴え,ショック状態に陥る。
はいた-てき【排他的】🔗⭐🔉
はいた-てき [0] 【排他的】 (形動)
自分や仲間以外の者を排斥する傾向のあるさま。「―な言動」「―な集団」
はいた-てき-ろんりわ【排他的論理和】🔗⭐🔉
はいた-てき-ろんりわ [8] 【排他的論理和】
⇒エクスクルーシブ-オア
はい-たいし【廃太子】🔗⭐🔉
はい-たいし 【廃太子】
皇太子を退位させること。また,その皇太子。「早良(サワラ)の―をば崇道天皇と号し/平家 3」
はい-たか【鷂】🔗⭐🔉
はい-たか [0] 【鷂】
〔「はしたか(鷂)」の転〕
タカ目タカ科の鳥。全長35センチメートル内外。雄は上面は灰青色,下面には赤褐色の横斑がある。雌は上面は褐色,下面の横斑は灰黒色。ユーラシアに分布し,日本では全国の低山帯の林にすむ。雄は雌よりも小さく,羽色を異にするので,コノリとも呼ばれる。
はい-たたき【蠅叩き】🔗⭐🔉
はい-たたき ハヒ― [3] 【蠅叩き】
⇒はえたたき(蠅叩)
はいち-てんかん【配置転換】🔗⭐🔉
はいち-てんかん ―クワン [4] 【配置転換】 (名)スル
組織の中における人の職務地・職務内容をかえること。配転。
はいち-せい【背地性】🔗⭐🔉
はいち-せい [0] 【背地性】
植物の茎が重力にさからって,上方に向かって屈曲する性質。負の屈地性。
→屈性
はい-つう【背痛】🔗⭐🔉
はい-つう [0] 【背痛】
背中の痛み。
はいとう-おち【配当落ち】🔗⭐🔉
はいとう-おち ―タウ― [0] 【配当落ち】
決算期を過ぎて,株式にその期の配当金受け取りの権利がなくなった状態。一般に,証券市場ではその配当金に見合う分だけ安くなる。
はいとう-きん【配当金】🔗⭐🔉
はいとう-きん ―タウ― [0] 【配当金】
株主などに分配される利益金。株式配当金や保険配当金など。
はいとう-せいこう【配当性向】🔗⭐🔉
はいとう-せいこう ―タウ―カウ [5] 【配当性向】
税引き利益のうち配当金の支払いに向けられる比率。
はいとう-つき【配当付き】🔗⭐🔉
はいとう-つき ―タウ― [0] 【配当付き】
売買される株式に,その決算期の配当金を受け得る権利が付いていること。
はいとう-りつ【配当率】🔗⭐🔉
はいとう-りつ ―タウ― [3] 【配当率】
株式の額面金額に対する配当金の割合。
はいとう-れい【廃刀令】🔗⭐🔉
はいとう-れい ―タウ― 【廃刀令】
1876年(明治9),大礼服着用者・軍人・警官以外の帯刀を禁止した法令。これで特権を奪われた不平士族の中には,反乱を起こす者が現れた。
はいとう-たい【配糖体】🔗⭐🔉
はいとう-たい ハイタウ― [0] 【配糖体】
糖の水酸基が炭化水素やアルコールなどの非糖質化合物と結合(グリコシド結合)してできる化合物の総称。生体成分として広く存在し,植物の医薬効果,花の色などのもとになると考えられている。グリコシド。
はい-とうみつ【廃糖蜜】🔗⭐🔉
はい-とうみつ ―タウミツ [3] 【廃糖蜜】
サトウキビやテンサイの糖蜜から,繰り返し砂糖を結晶させたあとに残る液。アルコール工業や食品工業の原料として用いる。
はい-ならし【灰均し】🔗⭐🔉
はい-ならし ハヒ― [3][5] 【灰均し】
火鉢などの灰を平らにするのに用いる金属製の道具。灰かき。灰おさえ。
はい-ねこ【灰猫】🔗⭐🔉
はい-ねこ ハヒ― [0] 【灰猫】
(1)灰色の猫。
(2)火を落としたかまどの中に入って暖をとり,灰だらけになった猫。かまどねこ。「―のやうな柳もお花かな/おらが春」
はい-ねつ【廃熱・排熱】🔗⭐🔉
はい-ねつ [0] 【廃熱・排熱】
別のある目的で使った熱の残り。余熱。また,目的とするものを得る過程で発生する熱。「―を利用した温水プール」
はい-のうよう【肺膿瘍】🔗⭐🔉
はい-のうよう ―ノウヤウ [3] 【肺膿瘍】
化膿菌・アメーバ・真菌などにより,肺組織に化膿・壊死(エシ)性の腫瘤が形成された状態。肺化膿症。肺癰(ハイヨウ)。
はい-の-き【灰の木】🔗⭐🔉
はい-の-き ハヒ― [3] 【灰の木】
ハイノキ科の常緑小高木。西日本の山中に生える。葉は狭卵形で光沢がある。初夏,葉腋(ヨウエキ)に花冠が五深裂する白色の花を数個つける。枝葉を燃やした灰から灰汁(アク)をとり染色に用いる。
灰の木
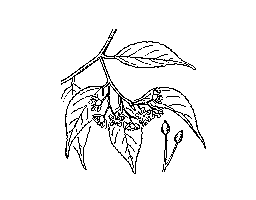 [図]
[図]
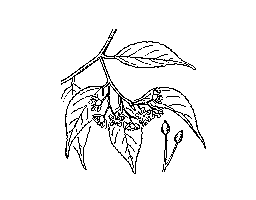 [図]
[図]
はい-はく【拝白】🔗⭐🔉
はい-はく [1][0] 【拝白】
つつしんで申し上げること。拝啓。
はいはん-ちけん【廃藩置県】🔗⭐🔉
はいはん-ちけん [5][6] 【廃藩置県】
1871年(明治4)7月,全国の藩を廃して府県を置いたこと。これにより中央集権的統一国家が確立された。当初,北海道を除き三府三〇二県(沖縄県の設置は79年),年末までに三府七二県となる。
はい-ふう【俳風・誹風】🔗⭐🔉
はい-ふう [0] 【俳風・誹風】
俳諧・俳句の作風・風体・流儀。
はいふうすえつむはな【誹風末摘花】🔗⭐🔉
はいふうすえつむはな ―ス ツムハナ 【誹風末摘花】
川柳集。四編四冊。似実軒酔茶(ジジツケンスイチヤ)編。1776〜1801年刊。川柳評万句合などから恋の句を集めたもの。
ツムハナ 【誹風末摘花】
川柳集。四編四冊。似実軒酔茶(ジジツケンスイチヤ)編。1776〜1801年刊。川柳評万句合などから恋の句を集めたもの。
 ツムハナ 【誹風末摘花】
川柳集。四編四冊。似実軒酔茶(ジジツケンスイチヤ)編。1776〜1801年刊。川柳評万句合などから恋の句を集めたもの。
ツムハナ 【誹風末摘花】
川柳集。四編四冊。似実軒酔茶(ジジツケンスイチヤ)編。1776〜1801年刊。川柳評万句合などから恋の句を集めたもの。
はい-ふき【灰吹き】🔗⭐🔉
はい-ふき ハヒ― [4][0] 【灰吹き】
タバコ盆に付属した竹筒で,タバコの灰・吸い殻などを落とし込むもの。吐月峰(トゲツポウ)。
はいふき-ほう【灰吹き法】🔗⭐🔉
はいふき-ほう ハヒ―ハフ [0] 【灰吹き法】
金・銀などを精錬する方法。炉(反射炉の一種)の下面にくぼみをつけて灰を詰め,その上に載せた金・銀と鉛との混合物を加熱して鉛を溶かし出して灰に吸収させ,金・銀を採取する。
はい-ふるい【灰篩い】🔗⭐🔉
はい-ふるい ハヒフルヒ [3] 【灰篩い】
灰をふるって,中にはいっている異物を取り除くための金網の張ってある道具。
はい-ほうろく【灰炮烙】🔗⭐🔉
はい-ほうろく ハヒハウロク [3] 【灰炮烙】
「灰器(ハイキ)」に同じ。
はいま【駅・駅馬】🔗⭐🔉
はいま 【駅・駅馬】
「はゆま(駅馬)」の転。「―に乗て馳せて奏せり/日本書紀(清寧訓)」
はい-まく【胚膜】🔗⭐🔉
はい-まく [0] 【胚膜】
哺乳類・鳥類・爬虫類の発生途上の胚を包む膜。胚組織の一部から形成されたもので,羊膜・漿膜・尿膜・卵黄嚢をさす。胚の保護・ガス交換・排出などの役割をする。胎膜。
はい-まくら【俳枕】🔗⭐🔉
はい-まくら [3] 【俳枕】
俳句に詠まれた各地の名所・旧跡。
はい-まつ【這松】🔗⭐🔉
はい-まつ ハヒ― [0][2] 【這松】
マツ科の常緑低木。本州中部以北の高山帯に生える。幹は地をはい,よく分枝して四方に広がる。葉は五個ずつ束生。雌雄同株で六月頃開花。松かさは長さ約4センチメートルの卵形。盆栽などにする。
はいまつ-たい【這松帯】🔗⭐🔉
はいまつ-たい ハヒ― [0] 【這松帯】
温帯の高山帯のこと。高木限界の上部でハイマツの低木林が発達するのでいう。
はい-まみれ【灰塗れ】🔗⭐🔉
はい-まみれ ハヒ― [3] 【灰塗れ】
灰だらけになること。はいまぶれ。「―になる」
はい-まわ・る【這い回る】🔗⭐🔉
はい-まわ・る ハヒマハル [4][3] 【這い回る】 (動ラ五[四])
あちこちはって歩く。「赤ん坊が座敷を―・る」
[可能] はいまわれる
はい-み【俳味】🔗⭐🔉
はい-み [3][1] 【俳味】
俳諧のもっている情趣。軽妙・洒脱な味わい。俳諧味。
はい-もう【廃忘・敗亡】🔗⭐🔉
はい-もう ―マウ 【廃忘・敗亡】 (名)スル
(1)忘れ去ること。「御尋ね有りけるに,折節―してのべ得ざりければ/盛衰記 4」
(2)驚きあわてること。うろたえること。「何れも―して,是れをとどむる人無し/浮世草子・武道伝来記 1」
はい-ゆ【廃油】🔗⭐🔉
はい-ゆ [0] 【廃油】
役に立たなくなった油。使用済みの潤滑油など。特に,船舶内で生じた不要な油。
はい-よ【敗余】🔗⭐🔉
はい-よ [1] 【敗余】
戦いに敗れたあと。
はい-よせ【灰寄せ】🔗⭐🔉
はい-よせ ハヒ― [0][4] 【灰寄せ】
火葬のあと,灰をかき寄せて遺骨を拾うこと。こつあげ。
はい-よ・る【這い寄る】🔗⭐🔉
はい-よ・る ハヒ― [0][3] 【這い寄る】 (動ラ五[四])
はうようにして近寄る。そっと忍び寄る。「敵陣に―・る」
はい-らい【拝礼】🔗⭐🔉
はい-らい [0] 【拝礼】
朝廷や院における元旦の拝賀。「正月一日院の―に殿ばらかずをつくして/和泉式部日記」
はいらん-ゆうはつ【排卵誘発】🔗⭐🔉
はいらん-ゆうはつ ―イウ― [5] 【排卵誘発】
正常に排卵が行われないために不妊である場合などに,薬剤により人工的に排卵をおこさせること。「―剤」
はいり-ほう【背理法】🔗⭐🔉
はいり-ほう ―ハフ [0] 【背理法】
⇒帰謬法(キビユウホウ)
は-いれ【歯入れ】🔗⭐🔉
は-いれ [3] 【歯入れ】
下駄の歯を入れかえること。
はい-れん【海菴】🔗⭐🔉
はい-れん [0] 【海菴】
カライワシ目の魚。全長は普通50センチメートル内外。体形は長く側扁し,背びれの後端が糸状にのびる。背側は青く腹側は銀白色。口は斜め上向きにつき,目とともに大きい。食用。太平洋・インド洋の温暖域に分布。淡水にもすめる。イセゴイ。
はい-ろう【肺労・肺癆】🔗⭐🔉
はい-ろう ―ラウ [0] 【肺労・肺癆】
肺結核の旧称。
はい-わ【俳話】🔗⭐🔉
はい-わ [0] 【俳話】
俳諧・俳句についての話。
はい-わた・る【這ひ渡る】🔗⭐🔉
はい-わた・る ハヒ― 【這ひ渡る】 (動ラ四)
(1)はうようにそっと行く。忍びやかに行く。「この主とおぼしきも,―・る時侍(ハベ)べかめる/源氏(夕顔)」
(2)牛車など用いずに歩いて行く。「明石の浦はただ―・る程なれば/源氏(須磨)」
(3)つるや草木の根などがはいのびる。「下にのみ―・りつる葦の根の/後撰(雑三)」
はうた-もの【端歌物】🔗⭐🔉
はうた-もの [0] 【端歌物】
地歌の一種。三味線組歌・長歌物の次に発生した,自由な曲風の歌。「雪」「黒髪」など。
は-うちわ【羽団扇】🔗⭐🔉
は-うちわ ―ウチハ [3][2] 【羽団扇】
鳥の羽根でつくったうちわ。「天狗の―」
はうちわ-まめ【羽団扇豆】🔗⭐🔉
はうちわ-まめ ―ウチハ― [4] 【羽団扇豆】
ルピナスの別名。
は-う・つ【羽搏つ・羽撃つ】🔗⭐🔉
は-う・つ [2] 【羽搏つ・羽撃つ】 (動タ五[四])
鳥がはばたく。「鳶(トビ)一羽…ぱた
 と―・つては駛(ハ)せ/自然と人生(蘆花)」
と―・つては駛(ハ)せ/自然と人生(蘆花)」

 と―・つては駛(ハ)せ/自然と人生(蘆花)」
と―・つては駛(ハ)せ/自然と人生(蘆花)」
はうつた-の【這ふ蔦の】🔗⭐🔉
はうつた-の ハフツタ― 【這ふ蔦の】 (枕詞)
蔦のつるがおのおの向きを異にしてはい分かれて行くところから,「おのがむきむき」「わかる」にかかる。「―各が向き向き天雲の別れし行けば/万葉 1804」「―別れし来れば/万葉 135」
はえ-うち【蠅打ち】🔗⭐🔉
はえ-うち ハヘ― [0][4] 【蠅打ち】
「蠅叩(ハエタタ)き」に同じ。[季]夏。
はえ-かわ・る【生え変(わ)る】🔗⭐🔉
はえ-かわ・る ―カハル [4][0] 【生え変(わ)る】 (動ラ五[四])
前にあったものがなくなったあとに,新しいものが生える。「歯が―・る」
はえ-たたき【蠅叩き】🔗⭐🔉
はえ-たたき ハヘ― [3] 【蠅叩き】
蠅を打ち殺すための,長い柄のついた道具。はいたたき。はえうち。[季]夏。《―とり彼一打我一打/虚子》
はえ-つ・く【蝕え尽く】🔗⭐🔉
はえ-つ・く 【蝕え尽く】 (動カ上二)
日食・月食で,皆既食となる。「日,―・きたること有り/日本書紀(推古訓)」
はえ-とり【蠅取り】🔗⭐🔉
はえ-とり ハヘ― [0][4][3] 【蠅取り】
(1)ハエをとるための道具。蠅取り器や蠅取り紙,蠅たたきなど。はいとり。
(2)「蠅取蜘蛛(グモ)」の略。
はえとり-そう【蠅取草】🔗⭐🔉
はえとり-そう ハヘ―サウ [0] 【蠅取草】
ハエジゴクの別名。
はえ-ぬ・く【生え抜く】🔗⭐🔉
はえ-ぬ・く 【生え抜く】 (動カ四)
(1)その土地で生まれそこで成長する。「吉原で―・いたやうに口を利くから/洒落本・南江駅話」
(2)はえて上に突き抜ける。「二王立ちに立たるは,金輪際より忽ちに―・いたるがごとく也/浄瑠璃・嫗山姥」
広辞苑+大辞林に「−は」で始まるの検索結果。もっと読み込む