複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (5)
じっ‐と🔗⭐🔉
じっ‐と
〔副〕
(「ぢっと」とも書いた)
①動かず何もしないさま。「―座って待つ」
②目を凝らすさま。「―見つめる」
③その事だけに神経を集中させているさま。「―こらえる」
④力をこめるさま。日葡辞書「テニジットニギル」
じっ‐とく【十徳】🔗⭐🔉
じっ‐とく【十徳】
①10種の徳。多くの徳。
②(僧服の「直綴じきとつ」の転という)衣服の名。素襖すおうに似て脇を縫いつけたもの。武士は葛布くずふで白または黒、胸紐あり、中間ちゅうげん・小者・輿舁こしかきなどは布を用い胸紐がなく、四幅袴よのばかまを用いる。鎌倉末期に始まり、室町時代には旅行服とした。江戸時代には儒者・医師・絵師などの外出に用い、絽・紗などで作り、黒色無文、共切れ平絎ひらぐけの短い紐をつけ、腰から下に襞ひだをつけて袴を略した。
十徳
 ⇒じっとく‐よのばかま【十徳四幅袴】
⇒じっとく‐よのばかま【十徳四幅袴】
 ⇒じっとく‐よのばかま【十徳四幅袴】
⇒じっとく‐よのばかま【十徳四幅袴】
じっとく【拾得】🔗⭐🔉
じっとく【拾得】
唐代の僧。天台山の近くに寒山とともに住み、奇行が多く、豊干ぶかんに師事したと伝える。その詩は「寒山詩」中に収載。普賢の化身と称せられ、画題にされる。生没年未詳。→寒山
じっとく‐よのばかま【十徳四幅袴】🔗⭐🔉
じっとく‐よのばかま【十徳四幅袴】
十徳を着て四幅袴をつけた服装。犬追物の矢取・犬牽、馬の口取、轅輿ながえこしを舁かく者などが用いた。
⇒じっ‐とく【十徳】
じっとり🔗⭐🔉
じっとり
かなりの量の汗や血がにじみ出てくるさま。ひどく湿っているさま。「肌が―する」「―と汗ばむ」
大辞林の検索結果 (6)
じっ-と🔗⭐🔉
じっ-と [0] (副)スル
(1)凝視するさま。つくづく。「―見まもる」
(2)我慢するさま。耐えるさま。「―痛さをこらえる」
(3)動かずにいるさま。「―立っている」
(4)力をこめるさま。ぎゅっと。「昆陽野(コヤノ)の宿の遊女が,袖を―控いて/狂言・茶ぐり(天正本)」
じっ-とく【十徳】🔗⭐🔉
じっ-とく [0][4] 【十徳】
(1)一〇種の徳。
(2)〔「直綴(ジキトツ)」の転か〕
男子の上着の一。丈は短く,羽織に似る。武家のものは素襖(スオウ)に似ていて胸紐(ヒモ)がある。鎌倉末期から用いられ,中間(チユウゲン)や小者は四幅袴(ヨノバカマ)の上に着た。江戸時代には医師・儒者・茶人などの礼服となった。
十徳(2)
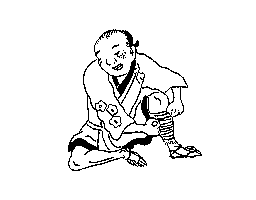 [図]
[図]
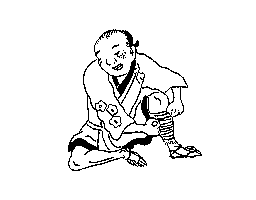 [図]
[図]
じっとく-よのばかま【十徳四幅袴】🔗⭐🔉
じっとく-よのばかま [7] 【十徳四幅袴】
十徳と四幅袴を着けたいでたち。武家の小者などの服装。十徳四布(シフ)袴。
じっとり🔗⭐🔉
じっとり [3] (副)スル
(1)しめりけを多く含んでいるさま。また,汗ばんださま。「ひたいに―(と)汗をかく」「―(と)するような暑さ」
(2)しとやかで落ち着いたさま。「あまりはすはでない―とした女子(オナゴ)があつたら,世話してくだんせ/滑稽本・浮世風呂 4」
広辞苑+大辞林に「じっと」で始まるの検索結果。