複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (5)
もず【百舌・鵙】🔗⭐🔉
もず‐かんじょう【百舌勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
もず‐かんじょう【百舌勘定】‥ヂヤウ
(モズ・ハト・シギが15文の買食いをし、勘定のとき、モズはハトに8文、シギに7文出させて、自分は何も出さなかったという昔話から)自分は多く出さずに、他人にばかり出させるようにすること。
もず‐こふんぐん【百舌鳥古墳群】🔗⭐🔉
もず‐こふんぐん【百舌鳥古墳群】
大阪府堺市にある大古墳群。墳長480メートル余で、日本最大の大仙陵古墳(仁徳天皇陵)を含む前方後円墳二十数基をはじめとする100基以上の古墳から成る。
○百舌の草潜もずのくさぐき🔗⭐🔉
○百舌の草潜もずのくさぐき
モズが春になると山に移り、平地に少なくなることを、草の中にもぐり込むものと見ていったもの。万葉集10「春されば―見えずとも」
⇒もず【百舌・鵙】
○百舌の速贄もずのはやにえ🔗⭐🔉
○百舌の速贄もずのはやにえ
(モズの捧げる初物の供物の意)モズが秋に虫などを捕らえて木の枝に貫いておくもの。翌春、他の鳥の餌に供されてしまうとしていう。〈[季]秋〉。散木奇歌集「垣根には―立ててけり」
⇒もず【百舌・鵙】
もずめ【物集】モヅメ
姓氏の一つ。
⇒もずめ‐たかみ【物集高見】
もずめ‐たかみ【物集高見】モヅメ‥
国語学者。豊後(大分県)生れ。東大教授。「広文庫」「群書索引」を編。(1847〜1928)
⇒もずめ【物集】
モスリン【muslin・毛斯綸】
(もとイラクのモスルから産出した薄地綿布の称)梳毛そもう織物の一つ。薄地の毛織物で、日本ではメリンスとも呼ぶ。綿製のものは綿モスリン。→メリノ→メリンス
モスル【Mosul イギリス・al-Mawṣil アラビア】
(モスール・モースルとも)イラク北部の都市。チグリス川中流にあり、古くから隊商路の重要拠点。また、近郊に油田が開発され、精油所がある。人口66万4千(1987)。
も・する【模する・摸する】
〔他サ変〕[文]模す(サ変)
①ある形をまねてつくる。似せる。
②ひきうつして書く。
モスレム【Moslem】
⇒ムスリム
も‐せい【茂生】
生え茂ること。
も‐ぞ
(係助詞のモとゾの複合したもの)
①「も」の意をさらに強める語。万葉集11「立ちて思ひ居て―思ふ」
②事態を予測してあやぶむ気持を表す。…と困るから。伊勢物語「思ひ―つくとてこの女をほかへ追ひやらむとす」
③転じて、事態に対するかすかな期待を表す。…しないかなあ。源平盛衰記40「もし浮かび―上がり給ふとて、しばし見けれども、三人ながら深く沈みて見えざりけり」
も‐ぞう【模造・摸造】‥ザウ
実物に似せて造ること。また、その物。「―品」
⇒もぞう‐し【模造紙】
も‐ぞう【模像】‥ザウ
模して作った像。
もぞう‐し【模造紙】‥ザウ‥
日本の局紙きょくしを、オーストリアで亜硫酸パルプを使って模造したものをさらに日本で模して造った洋紙。なめらかでつやがあり強靱。雑誌の表紙・事務用品・各種包装紙などに使用。
⇒も‐ぞう【模造・摸造】
も‐そっと
〔副〕
もう少し。もちっと。狂言、宝の槌「―上京へ参らう」
もそ‐もそ
①食べ物が乾いていたり、繊維が多かったりするさま。「―したパン」
②口をあまり開けずにものを言う声。また、そのさま。「耳元で―とささやく」
③小さく緩慢に身動きするさま。「―と起き出す」
もぞ‐もぞ
①虫がうごめくさま。また、そのような感じがするさま。「背中が―する」
②手足や体を緩慢に動かすさま。「―はい出す」
もそろ【醨・醪】
薄い酒。うすざけ。一説に、濁酒とも。〈倭名類聚鈔16〉
もそろ‐もそろ
そろりそろり。出雲風土記「河船の―に国来くにこ国来と引き来」
もだ【黙】
①だまっていること。ものを言わないこと。万葉集4「中々に―もあらましを」
②何もしないでぼんやりしているさま。万葉集10「―もあらむ時も鳴かなむひぐらしの」
⇒黙有り
大辞林の検索結果 (6)
もず【百舌・百舌鳥・鵙】🔗⭐🔉
もず [1] 【百舌・百舌鳥・鵙】
(1)スズメ目モズ科の鳥の総称。世界に約八〇種,日本にはモズ・アカモズ・チゴモズ・オオモズ・オオカラモズの五種がいる。
(2){(1)}の一種。全長20センチメートルほどで,尾が長い。雄は顔に太い黒帯があり,頭部は茶色,背面は灰褐色,腹面は淡褐色。脇は赤褐色で,翼に白斑がある。雌は全体が褐色。昆虫や小動物を捕食し,とった獲物を小枝などに突き刺しておく習性がある。[季]秋。《―啼くや一番高い木のさきに/正岡子規》
百舌(2)
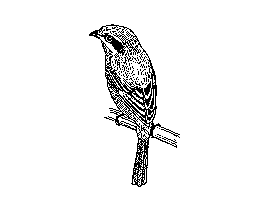 [図]
[図]
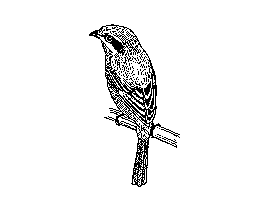 [図]
[図]
もず=の草潜(クサグキ)🔗⭐🔉
――の草潜(クサグキ)
モズが春になると人里近くに姿を見せなくなるのを,草の中にもぐり込むと思っていったもの。「春されば―見えずとも/古今六帖 6」
もず=の速贄(ハヤニエ)🔗⭐🔉
――の速贄(ハヤニエ)
モズが枝に突き刺しておく虫など。他の鳥の餌になるのを,供物と見立てた語。もずの磔(ハリツケ)。
もず-かんじょう【百舌勘定】🔗⭐🔉
もず-かんじょう ―カンヂヤウ [3] 【百舌勘定】
〔ハトとシギとモズが集まって一五文の買い食いをしたが,ハトに八文,シギに七文出させて,モズは一文も出さなかったという昔話から〕
自分はあまり金を出さず,他の人にばかり出させようとすること。
もず-こふんぐん【百舌鳥古墳群】🔗⭐🔉
もず-こふんぐん 【百舌鳥古墳群】
大阪府堺市の南部にある古墳時代中期に属する古墳群。仁徳陵・履仲陵をはじめ,十数基の大形前方後円墳と陪塚(バイチヨウ)とからなる。長持形石棺・鉄製武器武具類・馬具などが出土。
もず【百舌】(和英)🔗⭐🔉
もず【百舌】
《鳥》a shrike.→英和
広辞苑+大辞林に「百舌」で始まるの検索結果。
 モズ
提供:OPO
モズ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
→鳴声
提供:NHKサービスセンター