複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (10)
がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉
がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ
めがね。
め‐がね【眼鏡】🔗⭐🔉
め‐がね【眼鏡】
①遠視・近視・乱視・老眼などの視力を調整し、または光線が強く入るのを防ぐため目にかける凹または凸レンズ、あるいは単なる色ガラスの器具。〈日葡辞書〉
②遠眼鏡とおめがねのこと。
③物を見て、その善悪・可否を考え定めること。鑑識。めきき。日葡辞書「メガネノアルヒト」。甲陽軍鑑16「太刀にも刀にも、―と言ふこと専一に候」
④江戸時代、女の髪の結い方。眼鏡のように左右に輪を作る。
⇒めがね‐え【眼鏡絵】
⇒めがね‐ごし【眼鏡越し】
⇒めがね‐ざる【眼鏡猿】
⇒めがね‐ちがい【眼鏡違い】
⇒めがね‐ばし【眼鏡橋】
⇒めがね‐へび【眼鏡蛇】
⇒眼鏡が狂う
⇒眼鏡にかなう
めがね‐え【眼鏡絵】‥ヱ🔗⭐🔉
○眼鏡が狂うめがねがくるう🔗⭐🔉
○眼鏡が狂うめがねがくるう
人物などを見損なう。鑑定しそこなう。
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ごし【眼鏡越し】
眼鏡をかけたまま、上眼うわめを使って、眼鏡の上から見ること。
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ざる【眼鏡猿】
メガネザル科のサルの総称。3種がフィリピンからインドネシアに分布。毛色は淡い褐色。体形はサルらしくなく、顔、特に目が大きい。頭胴長10センチメートル余、尾長20センチメートルほど。森林にすみ、夜行性で、昆虫を捕食。
めがねざる
 メガネザル
撮影:小宮輝之
メガネザル
撮影:小宮輝之
 ⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ
人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。
⇒め‐がね【眼鏡】
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ
人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。
⇒め‐がね【眼鏡】
 メガネザル
撮影:小宮輝之
メガネザル
撮影:小宮輝之
 ⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ
人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。
⇒め‐がね【眼鏡】
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ
人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ごし【眼鏡越し】🔗⭐🔉
めがね‐ごし【眼鏡越し】
眼鏡をかけたまま、上眼うわめを使って、眼鏡の上から見ること。
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ざる【眼鏡猿】🔗⭐🔉
めがね‐ざる【眼鏡猿】
メガネザル科のサルの総称。3種がフィリピンからインドネシアに分布。毛色は淡い褐色。体形はサルらしくなく、顔、特に目が大きい。頭胴長10センチメートル余、尾長20センチメートルほど。森林にすみ、夜行性で、昆虫を捕食。
めがねざる
 メガネザル
撮影:小宮輝之
メガネザル
撮影:小宮輝之
 ⇒め‐がね【眼鏡】
⇒め‐がね【眼鏡】
 メガネザル
撮影:小宮輝之
メガネザル
撮影:小宮輝之
 ⇒め‐がね【眼鏡】
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐ばし【眼鏡橋】🔗⭐🔉
めがね‐ばし【眼鏡橋】
石造または煉瓦造の2連のアーチ橋の俗称。石造のものは1634年(寛永11)中国の僧如定が長崎に伝え、その後九州各地で建設。煉瓦造のものは明治時代に鉄道橋や水門などとして建設。
眼鏡橋(長崎)
撮影:山梨勝弘
 ⇒め‐がね【眼鏡】
⇒め‐がね【眼鏡】
 ⇒め‐がね【眼鏡】
⇒め‐がね【眼鏡】
めがね‐へび【眼鏡蛇】🔗⭐🔉
めがね‐へび【眼鏡蛇】
インドコブラの異称。
⇒め‐がね【眼鏡】
大辞林の検索結果 (11)
がん-きょう【眼鏡】🔗⭐🔉
がん-きょう ―キヤウ [0] 【眼鏡】
めがね。
め-がね【眼鏡】🔗⭐🔉
め-がね [1] 【眼鏡】
(1)不完全な視力を調整したり,強い光線を防ぐために,目につけるレンズや色ガラスなどを用いた器具。がんきょう。
(2)物を見て,善悪などを見分けること。また,その力。
→おめがね
(3)望遠鏡。とおめがね。
(4)江戸時代の女の髪形の一。髻(モトドリ)を二分して二つの輪をつくったもの。
めがね=が狂・う🔗⭐🔉
――が狂・う
良否を見分ける眼識が狂う。判断を誤る。
めがね=にかな・う🔗⭐🔉
――にかな・う
目上の人に認められる。お眼鏡にかなう。「社長の―・って抜擢(バツテキ)される」
めがね-え【眼鏡絵】🔗⭐🔉
めがね-え ― [3] 【眼鏡絵】
覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。
[3] 【眼鏡絵】
覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。
 [3] 【眼鏡絵】
覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。
[3] 【眼鏡絵】
覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。
めがね-ごし【眼鏡越し】🔗⭐🔉
めがね-ごし [0] 【眼鏡越し】
(1)上目(ウワメ)遣いに,眼鏡の上から見ること。「―に見つめる」
(2)眼鏡を通して見ること。
めがね-ざる【眼鏡猿】🔗⭐🔉
めがね-ざる [4] 【眼鏡猿】
霊長目メガネザル科に属する哺乳類の総称。原猿類の一種。小形で,頭胴長10〜15センチメートル。尾長約20センチメートル。体は淡黄色あるいは灰褐色から暗褐色。目は大きく,夜行性で樹上にすむ。昆虫・トカゲなどを食べる。フィリピン・スラウェシ・カリマンタン・スマトラなどに分布。三種に分かれる。
眼鏡猿
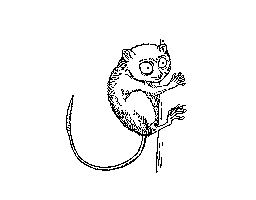 [図]
[図]
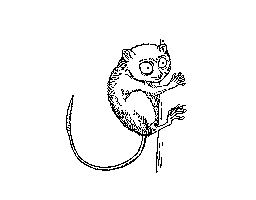 [図]
[図]
めがね-ちがい【眼鏡違い】🔗⭐🔉
めがね-ちがい ―チガヒ [4] 【眼鏡違い】
人物や物のよしあしの判断を誤ること。
めがね-ばし【眼鏡橋】🔗⭐🔉
めがね-ばし [3] 【眼鏡橋】
石造りのアーチ橋の通称。江戸時代に中国から伝えられ,長崎を中心に九州各地に造られた。
眼鏡橋
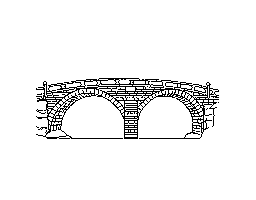 [図]
[図]
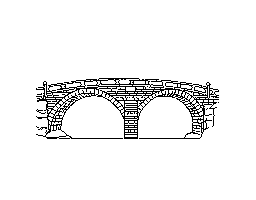 [図]
[図]
めがね-へび【眼鏡蛇】🔗⭐🔉
めがね-へび [4] 【眼鏡蛇】
コブラの代表種。有毒蛇。敵を威嚇するとき,前半身を立てて首近くの肋骨を広げ,体を大きく見せる。また,背の黄色の斑紋が大きな目のようになる。インドに分布。
めがね【眼鏡】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「眼鏡」で始まるの検索結果。