複数辞典一括検索+![]()
![]()
おどり-おび ヲドリ― [4] 【踊り帯】🔗⭐🔉
おどり-おび ヲドリ― [4] 【踊り帯】
錦(ニシキ)・金襴(キンラン)の通し柄で鏡仕立てに仕上げた,日本舞踊に使う女帯。
おどり-ぐい ヲドリグヒ [0] 【踊り食い】🔗⭐🔉
おどり-ぐい ヲドリグヒ [0] 【踊り食い】
白魚などの小魚やエビを生きたまま食うこと。また,その料理。
おどり-ぐし ヲドリ― [3] 【躍り串】🔗⭐🔉
おどり-ぐし ヲドリ― [3] 【躍り串】
海魚を姿焼きにするときの串の打ち方。魚が泳いでいるように見えることからいう。波打ち。
→上(ノボ)り串
おどり-くどき ヲドリ― 【踊り口説き】🔗⭐🔉
おどり-くどき ヲドリ― 【踊り口説き】
「盆踊り口説き」に同じ。
おどり-こ ヲドリ― [0] 【踊り子】🔗⭐🔉
おどり-こ ヲドリ― [0] 【踊り子】
(1)(盆踊りなどで「音頭取り」に対していう)踊りをおどる人。踊り手。[季]秋。《づか
 と来て―にさゝやける/高野素十》
(2)踊りを職業としている女性。「旅回りの―」
(3)「おどり{(7)}」に同じ。
(4)〔もと僧侶の隠語。生きたまま味噌汁に入れると,苦しがって踊るように見えることから〕
ドジョウの異名。「―汁」
と来て―にさゝやける/高野素十》
(2)踊りを職業としている女性。「旅回りの―」
(3)「おどり{(7)}」に同じ。
(4)〔もと僧侶の隠語。生きたまま味噌汁に入れると,苦しがって踊るように見えることから〕
ドジョウの異名。「―汁」

 と来て―にさゝやける/高野素十》
(2)踊りを職業としている女性。「旅回りの―」
(3)「おどり{(7)}」に同じ。
(4)〔もと僧侶の隠語。生きたまま味噌汁に入れると,苦しがって踊るように見えることから〕
ドジョウの異名。「―汁」
と来て―にさゝやける/高野素十》
(2)踊りを職業としている女性。「旅回りの―」
(3)「おどり{(7)}」に同じ。
(4)〔もと僧侶の隠語。生きたまま味噌汁に入れると,苦しがって踊るように見えることから〕
ドジョウの異名。「―汁」
おどり-こ-そう ヲドリ―サウ [0] 【踊子草】🔗⭐🔉
おどり-こ-そう ヲドリ―サウ [0] 【踊子草】
シソ科の多年草。原野に自生し,茎は四角で高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で対生し,粗い鋸歯がある。初夏,葉腋に白か淡紅色の唇形花を開く。和名は花冠の上唇を笠に,下唇を踊り子にみたてたもの。若芽を食用にする。野芝麻。踊り草。踊り花。[季]夏。
踊子草
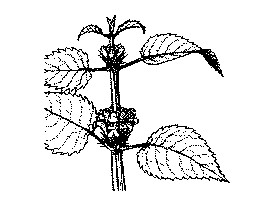 [図]
[図]
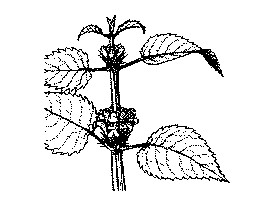 [図]
[図]
おどり-じ ヲドリヂ [0][3] 【踊り地】🔗⭐🔉
おどり-じ ヲドリヂ [0][3] 【踊り地】
(1)歌舞伎で,京阪の郭・揚屋・茶屋などの場で用いる太鼓・三味線などの囃子(ハヤシ)。
(2)歌舞伎舞踊で,華やかな手踊りの部分。
大辞林 ページ 140353。