複数辞典一括検索+![]()
![]()
はつ-みせ [0] 【初店・初見世】🔗⭐🔉
はつ-みせ [0] 【初店・初見世】
遊女が初めて店に出て客をとること。
はつ-みそら [4] 【初御空】🔗⭐🔉
はつ-みそら [4] 【初御空】
「初空(ハツゾラ)」に同じ。[季]新年。《―八咫の鴉は東へ/皿井旭川》
はつ-みみ [0] 【初耳】🔗⭐🔉
はつ-みみ [0] 【初耳】
初めて聞くこと。「その話は―だ」
はつ-む [1] 【撥無・撥撫】 (名)スル🔗⭐🔉
はつ-む [1] 【撥無・撥撫】 (名)スル
払いのけて信じないこと。否定すること。「丸で歴史を―した話だ/青年(鴎外)」
はつ-むかし [3] 【初昔】🔗⭐🔉
はつ-むかし [3] 【初昔】
(1)上等の抹茶の銘の一。白みを帯びた茶。徳川将軍家で後昔(アトムカシ)とともに愛飲された。後昔より古くから製せられていたことによる名という。後世,「昔」を「廿一日」の合字とし,旧暦三月二一日,あるいは八十八夜を含む前後二一日のうち,初昔は前一〇日に,後昔は後一〇日に摘んで製した茶などと付会された。
(2)元日に前年をさしていう語。旧年(フルトシ)。
は-つむり 【半頭・半首】🔗⭐🔉
は-つむり 【半頭・半首】
平安・鎌倉時代に用いられた,額から頬にかけての顔面を守る武具。下卒が兜(カブト)のかわりに用い,また,上級武士も兜と重ねて用いた。はつぶり。
半頭
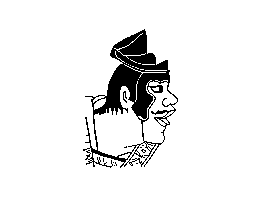 [図]
[図]
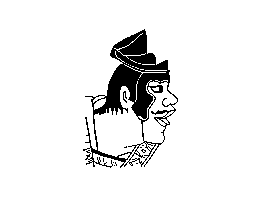 [図]
[図]
はつ-めい 【発明】🔗⭐🔉
はつ-めい 【発明】
■一■ [0] (名)スル
(1)それまで世になかった新しいものを,考え出したり作り出したりすること。「蓄音機を―する」「―者」「―家」
(2)物事の意味や道理を明らかにすること。明らかにさとること。「念仏を行じて,浄土に生じ,大事を―すべしといへり/沙石 4」
■二■ [2] (形動)[文]ナリ
賢いさま。利発なさま。「そこは―な潔さんのこと案じは致しませんが/もしや草紙(桜痴)」
はつめい-しゃ-けん [5] 【発明者権】🔗⭐🔉
はつめい-しゃ-けん [5] 【発明者権】
発明を行なった者の有する権利で,特許を受け,特許証に発明者として記載される権利。発明権。
はつ-めいげつ [3] 【初名月】🔗⭐🔉
はつ-めいげつ [3] 【初名月】
(「後(ノチ)の月」に対して)陰暦八月一五日の夜の月。芋名月。「―やいもあらひ/浄瑠璃・淀鯉(上)」
大辞林 ページ 152333。