複数辞典一括検索+![]()
![]()
いれ-あ・げる【入れ揚げる】🔗⭐🔉
いれ-あ・げる [4] 【入れ揚げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 いれあ・ぐ
愛人や道楽のために金銭を多く使う。つぎこむ。「競輪・競馬に―・げる」
いれ-あわ・す【入れ合はす】🔗⭐🔉
いれ-あわ・す ―アハス 【入れ合はす】 (動サ下二)
埋め合わせる。「おのれが損は―・せ今は金もいらぬ/浄瑠璃・五十年忌(中)」
いれ-あわせ【入れ合(わ)せ】🔗⭐🔉
いれ-あわせ ―アハセ [0] 【入れ合(わ)せ】
埋め合わせ。いりあわせ。
い-れい【威令】🔗⭐🔉
い-れい  ― [0] 【威令】
威力ある命令。「天下に―が行われる」
― [0] 【威令】
威力ある命令。「天下に―が行われる」
 ― [0] 【威令】
威力ある命令。「天下に―が行われる」
― [0] 【威令】
威力ある命令。「天下に―が行われる」
い-れい【威霊】🔗⭐🔉
い-れい  ― [0][1] 【威霊】
(1)威力ある神霊。
(2)天子の威光。
― [0][1] 【威霊】
(1)威力ある神霊。
(2)天子の威光。
 ― [0][1] 【威霊】
(1)威力ある神霊。
(2)天子の威光。
― [0][1] 【威霊】
(1)威力ある神霊。
(2)天子の威光。
い-れい【異例】🔗⭐🔉
い-れい [0] 【異例】 (名・形動)[文]ナリ
普通と違った例。前例のないこと。例のない,珍しいこと。「今夏は―の暑さだ」「―の措置」「―の抜擢(バツテキ)」
い-れい【違令】🔗⭐🔉
い-れい  ― [0] 【違令】
命令・法令に違反すること。
― [0] 【違令】
命令・法令に違反すること。
 ― [0] 【違令】
命令・法令に違反すること。
― [0] 【違令】
命令・法令に違反すること。
い-れい【違戻】🔗⭐🔉
い-れい  ― [0] 【違戻】 (名)スル
道理・命令にたがうこと。「敢て君命に―するを許すにあらず/明六雑誌 7」
― [0] 【違戻】 (名)スル
道理・命令にたがうこと。「敢て君命に―するを許すにあらず/明六雑誌 7」
 ― [0] 【違戻】 (名)スル
道理・命令にたがうこと。「敢て君命に―するを許すにあらず/明六雑誌 7」
― [0] 【違戻】 (名)スル
道理・命令にたがうこと。「敢て君命に―するを許すにあらず/明六雑誌 7」
い-れい【違例】🔗⭐🔉
い-れい  ― [0] 【違例】
(1)常と違うこと。
(2)病気その他でからだの具合がいつもと違うこと。病気。不例。「入道相国―の御心地とてとどまり給ひぬ/平家 6」
― [0] 【違例】
(1)常と違うこと。
(2)病気その他でからだの具合がいつもと違うこと。病気。不例。「入道相国―の御心地とてとどまり給ひぬ/平家 6」
 ― [0] 【違例】
(1)常と違うこと。
(2)病気その他でからだの具合がいつもと違うこと。病気。不例。「入道相国―の御心地とてとどまり給ひぬ/平家 6」
― [0] 【違例】
(1)常と違うこと。
(2)病気その他でからだの具合がいつもと違うこと。病気。不例。「入道相国―の御心地とてとどまり給ひぬ/平家 6」
い-れい【慰霊】🔗⭐🔉
い-れい  ― [0] 【慰霊】
死んだ人の霊魂をなぐさめること。「―碑」
― [0] 【慰霊】
死んだ人の霊魂をなぐさめること。「―碑」
 ― [0] 【慰霊】
死んだ人の霊魂をなぐさめること。「―碑」
― [0] 【慰霊】
死んだ人の霊魂をなぐさめること。「―碑」
いれい-さい【慰霊祭】🔗⭐🔉
いれい-さい  ― [2] 【慰霊祭】
死者の霊魂をなぐさめるために行う祭儀。
― [2] 【慰霊祭】
死者の霊魂をなぐさめるために行う祭儀。
 ― [2] 【慰霊祭】
死者の霊魂をなぐさめるために行う祭儀。
― [2] 【慰霊祭】
死者の霊魂をなぐさめるために行う祭儀。
い-れい【遺霊】🔗⭐🔉
い-れい  ― [0] 【遺霊】
死者の霊魂。
― [0] 【遺霊】
死者の霊魂。
 ― [0] 【遺霊】
死者の霊魂。
― [0] 【遺霊】
死者の霊魂。
イレウス ileus
ileus 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
いれ-かえ【入れ替え・入れ換え】🔗⭐🔉
いれ-かえ ―カヘ [0] 【入れ替え・入れ換え】 (名)スル
(1)いれかえること。「首脳陣の総―」
(2)埋め合わせ。「此―に思ひがけなき銀もらひ給ふべし/浮世草子・置土産 5」
いれかえ-もよう【入れ替え模様】🔗⭐🔉
いれかえ-もよう ―カヘ―ヤウ [5] 【入れ替え模様】
白と黒との互い違いになっている模様。市松(イチマツ)・亀甲(キツコウ)の模様など。
いれかえ-りょうがえ【入替両替】🔗⭐🔉
いれかえ-りょうがえ ―カヘリヤウガヘ [5] 【入替両替】
近世,商品や米切手などの証券類を担保に貸し付けをした,大坂の両替屋。
いれ-か・える【入れ替える・入れ換える】🔗⭐🔉
いれ-か・える ―カヘル [4][3] 【入れ替える・入れ換える】 (動ア下一)[文]ハ下二 いれか・ふ
中のものを出して,別のものを入れる。中身をとりかえる。「夏物と冬物を―・える」「心を―・える」
いれ-かけ【入れ掛け】🔗⭐🔉
いれ-かけ [0] 【入れ掛け】
雨や事故のため,その日の興行を中途でやめること。
いれ-がみ【入れ髪】🔗⭐🔉
いれ-がみ [0] 【入れ髪】
髪を結うとき,足し添えに入れる髪。かもじ。いれげ。そえがみ。
いれ-かわり【入れ替(わ)り・入れ代(わ)り】🔗⭐🔉
いれ-かわり ―カハリ [0] 【入れ替(わ)り・入れ代(わ)り】
(1)いれかわること。交代すること。「―に出て行く」
(2)江戸で,毎年11月に俳優が互いに出演劇場を交代したこと。また,その月の芝居。
いれかわり-たちかわり【入れ替(わ)り立ち替(わ)り】🔗⭐🔉
いれかわり-たちかわり ―カハリ―カハリ [0] 【入れ替(わ)り立ち替(わ)り】 (副)
次から次へと,ひっきりなしに。いりかわりたちかわり。「―客が来る」
いれ-かわ・る【入れ替(わ)る・入れ代(わ)る】🔗⭐🔉
いれ-かわ・る ―カハル [4] 【入れ替(わ)る・入れ代(わ)る】 (動ラ五[四])
とって代わる。交代する。いりかわる。「順序が―・る」
[可能] いれかわれる
イレギュラー-バウンド irregular bound
irregular bound 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
イレギュラー-バウンド [6]  irregular bound
irregular bound 野球・テニスなどで,ボールが地面にあたって思わぬ方向にはずむこと。イレギュラー。
野球・テニスなどで,ボールが地面にあたって思わぬ方向にはずむこと。イレギュラー。
 irregular bound
irregular bound 野球・テニスなどで,ボールが地面にあたって思わぬ方向にはずむこと。イレギュラー。
野球・テニスなどで,ボールが地面にあたって思わぬ方向にはずむこと。イレギュラー。
いれ-ぐい【入れ食い】🔗⭐🔉
いれ-ぐい ―グヒ [0] 【入れ食い】
釣りで,釣り針を水中に入れるとすぐに魚がかかること。
いれ-げ【入れ毛】🔗⭐🔉
いれ-げ [0] 【入れ毛】
「入れ髪(ガミ)」に同じ。
いれ-こ【入れ子・入れ籠】🔗⭐🔉
いれ-こ [0] 【入れ子・入れ籠】
(1)大きな箱や器の中に,それより一まわり小さくて同じ形のものを順々に入れていくこと。また,そのように細工された箱・器。
(2)自分の子が死んだあと,迎え入れた他人の子。養子。《入子》
(3)〔(1)の意から〕
内に隠されている事情。
(4)和船で,櫓臍(ロペソ)をはめるための櫓にある穴。
いれこ-いた【入れ子板】🔗⭐🔉
いれこ-いた [4] 【入れ子板】
唐戸(カラド)などの框(カマチ)や桟の間にはめ込んだ板。いりこいた。綿板(ワタイタ)。
いれこ-ことば【入れ子詞】🔗⭐🔉
いれこ-ことば [4] 【入れ子詞】
⇒入れ詞(コトバ)
いれこ-さかずき【入れ子杯・入れ子盃】🔗⭐🔉
いれこ-さかずき ―ヅキ [4] 【入れ子杯・入れ子盃】
大小数個を順次に重ねるようにした杯。
いれこ-ざけ【入れ子鮭・内子鮭】🔗⭐🔉
いれこ-ざけ [3] 【入れ子鮭・内子鮭】
腹に卵をもっている鮭。子籠(コゴモリ)鮭。
いれこ-じゅう【入れ子重】🔗⭐🔉
いれこ-じゅう ―ヂユウ [3] 【入れ子重】
大小が組み合わせになった重箱。
いれこ-ばち【入れ子鉢】🔗⭐🔉
いれこ-ばち [3] 【入れ子鉢】
大小が順にはいるように組み合わされた鉢。七つ一組が普通。
いれこ-びし【入れ子菱】🔗⭐🔉
いれこ-びし [3] 【入れ子菱】
織文様の一。菱の中に,二重三重に菱を入れた形。
入れ子菱
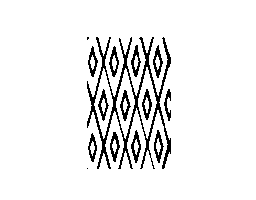 [図]
[図]
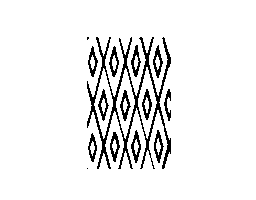 [図]
[図]
いれこ-ぶた【入れ子蓋】🔗⭐🔉
いれこ-ぶた [3] 【入れ子蓋】
ふたの厚みだけ容器の枠の内側がへこみ,ふたをしたとき,枠とふたとが平らになるようにしたもの。
いれこ-ぶち【入れ子縁】🔗⭐🔉
いれこ-ぶち [0][3] 【入れ子縁】
入れ子板の周囲,框(カマチ)や桟との間に装飾的に取り付けられる刳(ク)り形のある縁。いりこぶち。
いれこ-まくら【入れ子枕】🔗⭐🔉
いれこ-まくら [4] 【入れ子枕】
大小が順に入るようになった箱枕。夢想枕。無双枕。[嬉遊笑覧]
いれこ-ます【入れ子枡】🔗⭐🔉
いれこ-ます [3] 【入れ子枡】
大小の枡を組み合わせて一組としたもの。一合・三合・五合・一升の四個一組が普通。
いれ-ごと【入れ事】🔗⭐🔉
いれ-ごと [0] 【入れ事】
歌舞伎などで,原作にはない場面や演技などを挿入すること。
いれ-ことば【入れ詞】🔗⭐🔉
いれ-ことば 【入れ詞】
言葉の一音ごとに他の音をはさみ,特定の人だけに通じるようにした一種の隠語。「やきもち(焼餅)」を「やしきしもしちし」(「し」の音を挿入)という類。唐言もこの一。入れ子詞。
→挟み詞(コトバ)
いれ-こみ【入れ込み・入れ籠み】🔗⭐🔉
いれ-こみ [0] 【入れ込み・入れ籠み】
〔「いれごみ」とも〕
(1)多くの人を男女あるいは階級などの区別をしないでいっしょに入れること。また,その場所。
(2)劇場で,開場から開幕までの時間。
(3)男女混浴。いりこみ。
いれ-こ・む【入れ込む・入れ籠む】🔗⭐🔉
いれ-こ・む [3] 【入れ込む・入れ籠む】
■一■ (動マ五[四])
(1)中に押し込む。「余程財産もあるし,…乃公(オレ)も余程お豊を―・まうと骨折つて見た/不如帰(蘆花)」
(2)(資金を)つぎ込む。「商イニ金ヨホド―・ンダ/ヘボン」
(3)熱中する。「サッカーに―・む」
(4)馬が興奮した状態になる。はやり立つ。「スタートを前に―・む」
■二■ (動マ下二)
{■一■(1)}に同じ。「屏風の袋に―・めたる,所々に寄せかけ/源氏(東屋)」
いれ-さく【入れ作】🔗⭐🔉
いれ-さく 【入れ作】
江戸時代,地主から土地を借り,地代を払って耕作し,農業を営むこと。また,その人。小作。
いれ-じち【入れ質】🔗⭐🔉
いれ-じち [0] 【入れ質】
(1)質に入れること。
(2)中世,ある物を担保に入れて米や銭を借りること。
いれ-ずみ【入れ墨・刺青・文身】🔗⭐🔉
いれ-ずみ [0] 【入れ墨・刺青・文身】 (名)スル
(1)肌に針や刃物で傷をつけ,墨汁・朱・ベンガラ・緑青などの色素をすり込んで,文字・紋様・絵柄を描き出すこと。近世では,遊侠(ユウキヨウ)の徒の間で盛んに行われた。彫り物。
(2)昔の刑罰の一。顔や腕に束ねた針で墨を刺し入れて前科者のしるしとした。江戸時代には,江戸追放などの付加刑として行われた。黥(ゲイ)。
いれずみ-もの【入れ墨者】🔗⭐🔉
いれずみ-もの [0] 【入れ墨者】
江戸時代,入れ墨の刑に処せられた者。
いれ-た・つ【入れ立つ】🔗⭐🔉
いれ-た・つ 【入れ立つ】 (動タ下二)
(1)立ち入らせる。出入りさせる。「心わづらはしき北の方いで来て後は,内にも―・てず/枕草子 315」
(2)自分で費用を負担する。立て替える。[日葡]
いれ-たて【入れ立て】🔗⭐🔉
いれ-たて 【入れ立て】
(1)費用を自分で負担すること。自弁。「足駄・雪駄に至るまで,仕著せの外は身の―との定めなり/浄瑠璃・百日曾我」
(2)立てかえること。[日葡]
いれ-ぢえ【入れ知恵・入れ智慧】🔗⭐🔉
いれ-ぢえ ―ヂ [0] 【入れ知恵・入れ智慧】 (名)スル
他人に策を授けること。また,その知恵。多く悪い(よけいな)ことを教える場合にいう。「子供に―する」
[0] 【入れ知恵・入れ智慧】 (名)スル
他人に策を授けること。また,その知恵。多く悪い(よけいな)ことを教える場合にいう。「子供に―する」
 [0] 【入れ知恵・入れ智慧】 (名)スル
他人に策を授けること。また,その知恵。多く悪い(よけいな)ことを教える場合にいう。「子供に―する」
[0] 【入れ知恵・入れ智慧】 (名)スル
他人に策を授けること。また,その知恵。多く悪い(よけいな)ことを教える場合にいう。「子供に―する」
いれ-ちがい【入れ違い】🔗⭐🔉
いれ-ちがい ―チガヒ [0] 【入れ違い】
(1)順序が間違ってはいること。いれちがえ。
(2)一方が出るとかわりに他方がはいること。いれちがえ。「あいにくと―になる」
いれ-ちが・う【入れ違う】🔗⭐🔉
いれ-ちが・う ―チガフ [4][0] 【入れ違う】
■一■ (動ワ五[ハ四])
(1)順序や場などを間違えて入れる。「順番を―・う」
(2)一方が出たあとへ他方が入る。
■二■ (動ハ下二)
⇒いれちがえる
いれ-ちが・える【入れ違える】🔗⭐🔉
いれ-ちが・える ―チガヘル [5] 【入れ違える】 (動ア下一)[文]ハ下二 いれちが・ふ
(1)間違って入れる。「中身を―・える」
(2)互い違いになるように入れる。
〔中世後期にはヤ行にも活用した。「ニンジュヲイレチガユル/日葡」〕
い-れつ【威烈】🔗⭐🔉
い-れつ  ― [1] 【威烈】
勢いの激しいこと。激しい威力。
― [1] 【威烈】
勢いの激しいこと。激しい威力。
 ― [1] 【威烈】
勢いの激しいこと。激しい威力。
― [1] 【威烈】
勢いの激しいこと。激しい威力。
い-れつ【遺烈】🔗⭐🔉
い-れつ  ― [0][1] 【遺烈】
先人のなした立派な功績。
― [0][1] 【遺烈】
先人のなした立派な功績。
 ― [0][1] 【遺烈】
先人のなした立派な功績。
― [0][1] 【遺烈】
先人のなした立派な功績。
いれ-つち【入れ土】🔗⭐🔉
いれ-つち [0] 【入れ土】
農地の土壌の改善のために,性質の異なる土を入れること。また,その土。客土。
イレデンティズム irredentism
irredentism 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
イレデンティズム [5]  irredentism
irredentism 同一民族でありながら,その居住地域が自国に属していないとき,それを併合しようとする運動。民族統一主義。
同一民族でありながら,その居住地域が自国に属していないとき,それを併合しようとする運動。民族統一主義。
 irredentism
irredentism 同一民族でありながら,その居住地域が自国に属していないとき,それを併合しようとする運動。民族統一主義。
同一民族でありながら,その居住地域が自国に属していないとき,それを併合しようとする運動。民族統一主義。
いれ-にっき【入れ日記】🔗⭐🔉
いれ-にっき [3] 【入れ日記】
〔「いりにっき」とも〕
商品に同封して送る納品書。
いれ-ば【入れ歯】🔗⭐🔉
いれ-ば [0] 【入れ歯】
(1)抜けたり,抜いたりした歯を補うためにはめる,人工の歯。義歯。「総―」
(2)下駄の歯入れ。
いれ-ばな【入れ花・入れ端】🔗⭐🔉
いれ-ばな [0] 【入れ花・入れ端】
(1)入れたばかりの煎茶。出花。「―の茶びんご橋はこちこちと/浄瑠璃・今宮心中(上)」
(2)俳諧・狂歌で出句者が作品に添えて出す料金。選句や入選作を刷り物にする際の印刷代。点料。にゅうか。
いれ-ひも【入れ紐】🔗⭐🔉
いれ-ひも [0] 【入れ紐】
袍(ホウ)・直衣(ノウシ)・狩衣などの頸上(クビカミ)についている紐。先を玉結びにした雄紐と輪になった雌紐とからなる。雄紐の玉を雌紐の輪に入れてとめ,襟を合わせる。
いれ-ぶし【入れ節】🔗⭐🔉
いれ-ぶし [0] 【入れ節】
浄瑠璃などで,一部にほかの節をはさみ入れたもの。また,はさみ入れた節。
いれ-ふだ【入れ札】🔗⭐🔉
いれ-ふだ [0] 【入れ札】
(1)「にゅうさつ(入札)」に同じ。「今時は諸方の―,すこしの利潤を見掛けて/浮世草子・永代蔵 1」
(2)江戸時代,村役人などを選ぶとき,名前を書いて投票した用紙。また,投票すること。
いれ-ぶつじ【入れ仏事】🔗⭐🔉
いれ-ぶつじ 【入れ仏事】
(1)費用を提供して,万事寺に任せてする法事。「すぐに菩提寺に詣で―の供養/浮世草子・新色五巻書」
(2)出費が多くて利益のないこと。骨折り損。「判をおさせた百両の,金も養家へ―/人情本・梅児誉美(初)」
いれ-ふで【入れ筆】🔗⭐🔉
いれ-ふで 【入れ筆】
あとから書き入れること。加筆。「ちよつと―頼みます/浄瑠璃・卯月の潤色(中)」
イレブン eleven
eleven 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
イレブン [2]  eleven
eleven 〔一一人でプレーするところから〕
サッカーの一チームを構成し,競技に参加するメンバー。また,サッカー-チームのこと。
〔一一人でプレーするところから〕
サッカーの一チームを構成し,競技に参加するメンバー。また,サッカー-チームのこと。
 eleven
eleven 〔一一人でプレーするところから〕
サッカーの一チームを構成し,競技に参加するメンバー。また,サッカー-チームのこと。
〔一一人でプレーするところから〕
サッカーの一チームを構成し,競技に参加するメンバー。また,サッカー-チームのこと。
イレブン-ナイン🔗⭐🔉
イレブン-ナイン [5]
〔eleven nines〕
純度・精度が極めて高いこと。誤差が極めて小さいこと。純度・精度を表す数字に九が一一続くことから。
いれ-ぼくろ【入れ黒子】🔗⭐🔉
いれ-ぼくろ [3] 【入れ黒子】
(1)書いたり,はりつけたりする,化粧としてのほくろ。つけぼくろ。ビューティー-スポット。
(2)いれずみ。ほりもの。「墨をもて頭に竜蛇の形を―し候ふを/読本・弓張月(続)」
(3)遊女などが誠意を示すため,腕などに相手の名をいれずみしたもの。「たがひに彫つた―/人情本・辰巳園 3」
いれ-ま・ぜる【入れ混ぜる・入れ交ぜる】🔗⭐🔉
いれ-ま・ぜる [4] 【入れ混ぜる・入れ交ぜる】 (動ザ下一)[文]ザ下二 いれま・ず
種々のものを入りまじらせる。まぜいれる。「鉄銭銅銭―・ぜて/安愚楽鍋(魯文)」
いれ-め【入れ目】🔗⭐🔉
いれ-め [0] 【入れ目】
(1)人工の眼球。義眼。
(2)江戸時代,大坂の蔵屋敷で貢納米が払い下げられるとき,納札者の払う手数料。
いれ-もじ【入れ文字】🔗⭐🔉
いれ-もじ [0] 【入れ文字】
和歌の遊戯的技巧の一。歌の中にある語を内容とは関係ない文字続きとして詠み込むこと。また,詠み込まれた語。物の名の歌ともいい,「あしひきの山たちはなれ行く雲の」の中に「たちばな」の語が詠み込まれているようなもの。
いれ-もとゆい【入れ元結】🔗⭐🔉
いれ-もとゆい ―モトユヒ [3] 【入れ元結】
元結を締めた上に,飾りに結ぶ子供用の元結。金箔紙に松・竹・鶴・亀などを描き両端に芯(シン)を入れたもの。大元結。絵元結。化粧元結。
いれ-もの【入れ物・容れ物】🔗⭐🔉
いれ-もの [0] 【入れ物・容れ物】
(1)物を入れるうつわ。容器。
(2)棺の忌み詞。
い・れる【入れる】🔗⭐🔉
い・れる [0] 【入れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 い・る
 ある区画・容器の外側にあるものを,内側に移す。
(1)物を容器の中に移す。「カメラにフィルムを―・れる」「コップに水を―・れる」「受け取った金を銀行に―・れる(=預金スル)」
(2)ある物を,それがちょうどはまり込むようになっている所へはめ込む。「窓にガラスを―・れる」「入れ歯を―・れる」
(3)入ってこようとするのをさまたげずにおく。「窓をあけて風を―・れる」「だれも部屋には―・れない」
(4)(液体や粒状の物の中に)異質の物を加えて混ぜる。混ぜる。「コーヒーに砂糖を―・れる」「栗(クリ)を―・れた御飯」
ある区画・容器の外側にあるものを,内側に移す。
(1)物を容器の中に移す。「カメラにフィルムを―・れる」「コップに水を―・れる」「受け取った金を銀行に―・れる(=預金スル)」
(2)ある物を,それがちょうどはまり込むようになっている所へはめ込む。「窓にガラスを―・れる」「入れ歯を―・れる」
(3)入ってこようとするのをさまたげずにおく。「窓をあけて風を―・れる」「だれも部屋には―・れない」
(4)(液体や粒状の物の中に)異質の物を加えて混ぜる。混ぜる。「コーヒーに砂糖を―・れる」「栗(クリ)を―・れた御飯」
 人や物をある集団や施設に移す。
(1)その集団の中に加える。「うちの工場に若手を二,三人―・れることにした」「君たちを仲間に―・れる」
(2)別の組織や施設に移す。「病人を病院に―・れる」「子供が六歳になったら小学校に―・れなくてはいけない」
(3)新たに機械・道具などを導入する。「新しいコンピューターを―・れた」
(4)商人が商品を納入する。「うちで―・れた品はあとまで責任をもちます」
(5)商人が品物を仕入れる。「この食堂では酒類はすべてあの酒屋から―・れている」
(6)金銭を家計のために提供する。「自分の食費は,毎月家に―・れている」
(7)戸籍に帰属させる。「結婚式はあげたが,まだ籍を―・れてない」
(8)(「質に入れる」「担保に入れる」の形で)担保物件として相手にさし出す。「指輪を質に―・れて金(カネ)を作る」「家を担保に―・れて金を借りる」
人や物をある集団や施設に移す。
(1)その集団の中に加える。「うちの工場に若手を二,三人―・れることにした」「君たちを仲間に―・れる」
(2)別の組織や施設に移す。「病人を病院に―・れる」「子供が六歳になったら小学校に―・れなくてはいけない」
(3)新たに機械・道具などを導入する。「新しいコンピューターを―・れた」
(4)商人が商品を納入する。「うちで―・れた品はあとまで責任をもちます」
(5)商人が品物を仕入れる。「この食堂では酒類はすべてあの酒屋から―・れている」
(6)金銭を家計のために提供する。「自分の食費は,毎月家に―・れている」
(7)戸籍に帰属させる。「結婚式はあげたが,まだ籍を―・れてない」
(8)(「質に入れる」「担保に入れる」の形で)担保物件として相手にさし出す。「指輪を質に―・れて金(カネ)を作る」「家を担保に―・れて金を借りる」
 間や途中に何かを置く。はさむ。
(1)二つの物の間に別の物をはさむ。「外壁と内壁の間に断熱材を―・れる」
(2)物事を中断して他のことを割り込ませる。「文章の途中に写真を―・れる」「番組の途中にコマーシャルを―・れる」
(3)疑いなどをさしはさむ。「疑いを―・れる余地がない」
間や途中に何かを置く。はさむ。
(1)二つの物の間に別の物をはさむ。「外壁と内壁の間に断熱材を―・れる」
(2)物事を中断して他のことを割り込ませる。「文章の途中に写真を―・れる」「番組の途中にコマーシャルを―・れる」
(3)疑いなどをさしはさむ。「疑いを―・れる余地がない」
 (「…に力を入れる」の形で)
(1)…の筋肉を緊張させる。「両足に力を―・れてふんばる」
(2)…に努力を集中させる。努力する。「新製品の開発に力を―・れる」
(「…に力を入れる」の形で)
(1)…の筋肉を緊張させる。「両足に力を―・れてふんばる」
(2)…に努力を集中させる。努力する。「新製品の開発に力を―・れる」
 ある作用を外から加える。
(1)くぼみ・墨などによって線・図形・文字を記す。「三〇センチおきに切れ目を―・れる」「万年筆に名前を―・れてもらう」「透かしを―・れた紙」
(2)(「…を入れる」の形で,言葉による動作を表す語を受けて)他人に対し,言葉で働きかける。「先方に詫(ワ)びを―・れる」「そういうときはすぐに断り(=事情ノ説明)を―・れておかなくてはだめだ」
(3)横から口を出す。「ひとの話に茶々を―・れるな」「ひとの話にわきから口を―・れる」「横槍を―・れる」「半畳を―・れる」
(4)(「連絡を入れる」「電話を入れる」などの形で)…に連絡をする。「出張先から本社に連絡を―・れる」「会社に電話を―・れて指示を求める」
(5)修正や欠点指摘の作用を加える。「買った家に手を―・れる」「人の書いた文章に手を―・れる」「行政の腐敗にメスを―・れる」
(6)他人に対し,気力をふるいたたせるような作用を加える。「監督が選手に気合を―・れる」「活を―・れる」
(7)自分自身,気力や努力を注ぎ込む。「もっと身を―・れて勉強しなさい」「念を―・れて校正をする」「学術書の出版に本腰を―・れる」
ある作用を外から加える。
(1)くぼみ・墨などによって線・図形・文字を記す。「三〇センチおきに切れ目を―・れる」「万年筆に名前を―・れてもらう」「透かしを―・れた紙」
(2)(「…を入れる」の形で,言葉による動作を表す語を受けて)他人に対し,言葉で働きかける。「先方に詫(ワ)びを―・れる」「そういうときはすぐに断り(=事情ノ説明)を―・れておかなくてはだめだ」
(3)横から口を出す。「ひとの話に茶々を―・れるな」「ひとの話にわきから口を―・れる」「横槍を―・れる」「半畳を―・れる」
(4)(「連絡を入れる」「電話を入れる」などの形で)…に連絡をする。「出張先から本社に連絡を―・れる」「会社に電話を―・れて指示を求める」
(5)修正や欠点指摘の作用を加える。「買った家に手を―・れる」「人の書いた文章に手を―・れる」「行政の腐敗にメスを―・れる」
(6)他人に対し,気力をふるいたたせるような作用を加える。「監督が選手に気合を―・れる」「活を―・れる」
(7)自分自身,気力や努力を注ぎ込む。「もっと身を―・れて勉強しなさい」「念を―・れて校正をする」「学術書の出版に本腰を―・れる」
 ある範囲に含めて考える。
(1)数量を数える際,それをも含めて数える。「参加者は私を―・れると一〇名だ」「費用は交通費を―・れて五千円」
(2)分類をする際,あるグループの中に含める。「中学生は大人に―・れる」
(3)(「…を考えに入れる」などの形で)物事をする際,ある事を考慮の対象に含める。考えに含める。「こういう事情を考慮に―・れて処理して下さい」「乗り換え時間を計算に―・れてなかったので,遅れてしまいました」
(4)目・耳などの知覚や記憶に取り入れる。「ぜひお耳に―・れておきたいことがあります」「やがて見参に―・れたりけり/平家 2」
ある範囲に含めて考える。
(1)数量を数える際,それをも含めて数える。「参加者は私を―・れると一〇名だ」「費用は交通費を―・れて五千円」
(2)分類をする際,あるグループの中に含める。「中学生は大人に―・れる」
(3)(「…を考えに入れる」などの形で)物事をする際,ある事を考慮の対象に含める。考えに含める。「こういう事情を考慮に―・れて処理して下さい」「乗り換え時間を計算に―・れてなかったので,遅れてしまいました」
(4)目・耳などの知覚や記憶に取り入れる。「ぜひお耳に―・れておきたいことがあります」「やがて見参に―・れたりけり/平家 2」
 (「火を入れる」の形で)炉などに点火する。「熔鉱炉に火を―・れる」「ストーブに火を―・れる」
(「火を入れる」の形で)炉などに点火する。「熔鉱炉に火を―・れる」「ストーブに火を―・れる」
 機械・道具を操作して機能させる。「スイッチを―・れる」「一日中暖房を―・れている」
機械・道具を操作して機能させる。「スイッチを―・れる」「一日中暖房を―・れている」
 (「容れる」とも書く)他からの提案や要求を認めて採用・受諾する。うけいれる。「現場の人たちの提案を―・れて改革をはかる」「世に―・れられずにさびしく死んだ」
(「容れる」とも書く)他からの提案や要求を認めて採用・受諾する。うけいれる。「現場の人たちの提案を―・れて改革をはかる」「世に―・れられずにさびしく死んだ」
 (「淹れる」とも書く)湯を注いで飲み物をつくる。「お茶を―・れる」「コーヒーを―・れる」
(「淹れる」とも書く)湯を注いで飲み物をつくる。「お茶を―・れる」「コーヒーを―・れる」
 投票・入札などで,氏名・可否・値段などを記した紙片などを箱に入れて自分の意志を表す。「今度の選挙ではだれに―・れようか」
〔「入(イ)る」に対する他動詞〕
[慣用] 頭に―・息を―・一札(イツサツ)―・肩を―・活を―・勘定に―・気を―・気合を―・嘴(クチバシ)を―・腰を―・ご覧に―・探りを―・朱を―・朱筆を―・底を―・茶々を―・手に―・手を―・泣きを―・念を―・年季を―・鋏(ハサミ)を―・一息―・筆を―・本腰を―・身を―・耳に―・メスを―・焼きを―・詫びを―/間(カン)髪(ハツ)を入れず・世に入れられる
投票・入札などで,氏名・可否・値段などを記した紙片などを箱に入れて自分の意志を表す。「今度の選挙ではだれに―・れようか」
〔「入(イ)る」に対する他動詞〕
[慣用] 頭に―・息を―・一札(イツサツ)―・肩を―・活を―・勘定に―・気を―・気合を―・嘴(クチバシ)を―・腰を―・ご覧に―・探りを―・朱を―・朱筆を―・底を―・茶々を―・手に―・手を―・泣きを―・念を―・年季を―・鋏(ハサミ)を―・一息―・筆を―・本腰を―・身を―・耳に―・メスを―・焼きを―・詫びを―/間(カン)髪(ハツ)を入れず・世に入れられる
 ある区画・容器の外側にあるものを,内側に移す。
(1)物を容器の中に移す。「カメラにフィルムを―・れる」「コップに水を―・れる」「受け取った金を銀行に―・れる(=預金スル)」
(2)ある物を,それがちょうどはまり込むようになっている所へはめ込む。「窓にガラスを―・れる」「入れ歯を―・れる」
(3)入ってこようとするのをさまたげずにおく。「窓をあけて風を―・れる」「だれも部屋には―・れない」
(4)(液体や粒状の物の中に)異質の物を加えて混ぜる。混ぜる。「コーヒーに砂糖を―・れる」「栗(クリ)を―・れた御飯」
ある区画・容器の外側にあるものを,内側に移す。
(1)物を容器の中に移す。「カメラにフィルムを―・れる」「コップに水を―・れる」「受け取った金を銀行に―・れる(=預金スル)」
(2)ある物を,それがちょうどはまり込むようになっている所へはめ込む。「窓にガラスを―・れる」「入れ歯を―・れる」
(3)入ってこようとするのをさまたげずにおく。「窓をあけて風を―・れる」「だれも部屋には―・れない」
(4)(液体や粒状の物の中に)異質の物を加えて混ぜる。混ぜる。「コーヒーに砂糖を―・れる」「栗(クリ)を―・れた御飯」
 人や物をある集団や施設に移す。
(1)その集団の中に加える。「うちの工場に若手を二,三人―・れることにした」「君たちを仲間に―・れる」
(2)別の組織や施設に移す。「病人を病院に―・れる」「子供が六歳になったら小学校に―・れなくてはいけない」
(3)新たに機械・道具などを導入する。「新しいコンピューターを―・れた」
(4)商人が商品を納入する。「うちで―・れた品はあとまで責任をもちます」
(5)商人が品物を仕入れる。「この食堂では酒類はすべてあの酒屋から―・れている」
(6)金銭を家計のために提供する。「自分の食費は,毎月家に―・れている」
(7)戸籍に帰属させる。「結婚式はあげたが,まだ籍を―・れてない」
(8)(「質に入れる」「担保に入れる」の形で)担保物件として相手にさし出す。「指輪を質に―・れて金(カネ)を作る」「家を担保に―・れて金を借りる」
人や物をある集団や施設に移す。
(1)その集団の中に加える。「うちの工場に若手を二,三人―・れることにした」「君たちを仲間に―・れる」
(2)別の組織や施設に移す。「病人を病院に―・れる」「子供が六歳になったら小学校に―・れなくてはいけない」
(3)新たに機械・道具などを導入する。「新しいコンピューターを―・れた」
(4)商人が商品を納入する。「うちで―・れた品はあとまで責任をもちます」
(5)商人が品物を仕入れる。「この食堂では酒類はすべてあの酒屋から―・れている」
(6)金銭を家計のために提供する。「自分の食費は,毎月家に―・れている」
(7)戸籍に帰属させる。「結婚式はあげたが,まだ籍を―・れてない」
(8)(「質に入れる」「担保に入れる」の形で)担保物件として相手にさし出す。「指輪を質に―・れて金(カネ)を作る」「家を担保に―・れて金を借りる」
 間や途中に何かを置く。はさむ。
(1)二つの物の間に別の物をはさむ。「外壁と内壁の間に断熱材を―・れる」
(2)物事を中断して他のことを割り込ませる。「文章の途中に写真を―・れる」「番組の途中にコマーシャルを―・れる」
(3)疑いなどをさしはさむ。「疑いを―・れる余地がない」
間や途中に何かを置く。はさむ。
(1)二つの物の間に別の物をはさむ。「外壁と内壁の間に断熱材を―・れる」
(2)物事を中断して他のことを割り込ませる。「文章の途中に写真を―・れる」「番組の途中にコマーシャルを―・れる」
(3)疑いなどをさしはさむ。「疑いを―・れる余地がない」
 (「…に力を入れる」の形で)
(1)…の筋肉を緊張させる。「両足に力を―・れてふんばる」
(2)…に努力を集中させる。努力する。「新製品の開発に力を―・れる」
(「…に力を入れる」の形で)
(1)…の筋肉を緊張させる。「両足に力を―・れてふんばる」
(2)…に努力を集中させる。努力する。「新製品の開発に力を―・れる」
 ある作用を外から加える。
(1)くぼみ・墨などによって線・図形・文字を記す。「三〇センチおきに切れ目を―・れる」「万年筆に名前を―・れてもらう」「透かしを―・れた紙」
(2)(「…を入れる」の形で,言葉による動作を表す語を受けて)他人に対し,言葉で働きかける。「先方に詫(ワ)びを―・れる」「そういうときはすぐに断り(=事情ノ説明)を―・れておかなくてはだめだ」
(3)横から口を出す。「ひとの話に茶々を―・れるな」「ひとの話にわきから口を―・れる」「横槍を―・れる」「半畳を―・れる」
(4)(「連絡を入れる」「電話を入れる」などの形で)…に連絡をする。「出張先から本社に連絡を―・れる」「会社に電話を―・れて指示を求める」
(5)修正や欠点指摘の作用を加える。「買った家に手を―・れる」「人の書いた文章に手を―・れる」「行政の腐敗にメスを―・れる」
(6)他人に対し,気力をふるいたたせるような作用を加える。「監督が選手に気合を―・れる」「活を―・れる」
(7)自分自身,気力や努力を注ぎ込む。「もっと身を―・れて勉強しなさい」「念を―・れて校正をする」「学術書の出版に本腰を―・れる」
ある作用を外から加える。
(1)くぼみ・墨などによって線・図形・文字を記す。「三〇センチおきに切れ目を―・れる」「万年筆に名前を―・れてもらう」「透かしを―・れた紙」
(2)(「…を入れる」の形で,言葉による動作を表す語を受けて)他人に対し,言葉で働きかける。「先方に詫(ワ)びを―・れる」「そういうときはすぐに断り(=事情ノ説明)を―・れておかなくてはだめだ」
(3)横から口を出す。「ひとの話に茶々を―・れるな」「ひとの話にわきから口を―・れる」「横槍を―・れる」「半畳を―・れる」
(4)(「連絡を入れる」「電話を入れる」などの形で)…に連絡をする。「出張先から本社に連絡を―・れる」「会社に電話を―・れて指示を求める」
(5)修正や欠点指摘の作用を加える。「買った家に手を―・れる」「人の書いた文章に手を―・れる」「行政の腐敗にメスを―・れる」
(6)他人に対し,気力をふるいたたせるような作用を加える。「監督が選手に気合を―・れる」「活を―・れる」
(7)自分自身,気力や努力を注ぎ込む。「もっと身を―・れて勉強しなさい」「念を―・れて校正をする」「学術書の出版に本腰を―・れる」
 ある範囲に含めて考える。
(1)数量を数える際,それをも含めて数える。「参加者は私を―・れると一〇名だ」「費用は交通費を―・れて五千円」
(2)分類をする際,あるグループの中に含める。「中学生は大人に―・れる」
(3)(「…を考えに入れる」などの形で)物事をする際,ある事を考慮の対象に含める。考えに含める。「こういう事情を考慮に―・れて処理して下さい」「乗り換え時間を計算に―・れてなかったので,遅れてしまいました」
(4)目・耳などの知覚や記憶に取り入れる。「ぜひお耳に―・れておきたいことがあります」「やがて見参に―・れたりけり/平家 2」
ある範囲に含めて考える。
(1)数量を数える際,それをも含めて数える。「参加者は私を―・れると一〇名だ」「費用は交通費を―・れて五千円」
(2)分類をする際,あるグループの中に含める。「中学生は大人に―・れる」
(3)(「…を考えに入れる」などの形で)物事をする際,ある事を考慮の対象に含める。考えに含める。「こういう事情を考慮に―・れて処理して下さい」「乗り換え時間を計算に―・れてなかったので,遅れてしまいました」
(4)目・耳などの知覚や記憶に取り入れる。「ぜひお耳に―・れておきたいことがあります」「やがて見参に―・れたりけり/平家 2」
 (「火を入れる」の形で)炉などに点火する。「熔鉱炉に火を―・れる」「ストーブに火を―・れる」
(「火を入れる」の形で)炉などに点火する。「熔鉱炉に火を―・れる」「ストーブに火を―・れる」
 機械・道具を操作して機能させる。「スイッチを―・れる」「一日中暖房を―・れている」
機械・道具を操作して機能させる。「スイッチを―・れる」「一日中暖房を―・れている」
 (「容れる」とも書く)他からの提案や要求を認めて採用・受諾する。うけいれる。「現場の人たちの提案を―・れて改革をはかる」「世に―・れられずにさびしく死んだ」
(「容れる」とも書く)他からの提案や要求を認めて採用・受諾する。うけいれる。「現場の人たちの提案を―・れて改革をはかる」「世に―・れられずにさびしく死んだ」
 (「淹れる」とも書く)湯を注いで飲み物をつくる。「お茶を―・れる」「コーヒーを―・れる」
(「淹れる」とも書く)湯を注いで飲み物をつくる。「お茶を―・れる」「コーヒーを―・れる」
 投票・入札などで,氏名・可否・値段などを記した紙片などを箱に入れて自分の意志を表す。「今度の選挙ではだれに―・れようか」
〔「入(イ)る」に対する他動詞〕
[慣用] 頭に―・息を―・一札(イツサツ)―・肩を―・活を―・勘定に―・気を―・気合を―・嘴(クチバシ)を―・腰を―・ご覧に―・探りを―・朱を―・朱筆を―・底を―・茶々を―・手に―・手を―・泣きを―・念を―・年季を―・鋏(ハサミ)を―・一息―・筆を―・本腰を―・身を―・耳に―・メスを―・焼きを―・詫びを―/間(カン)髪(ハツ)を入れず・世に入れられる
投票・入札などで,氏名・可否・値段などを記した紙片などを箱に入れて自分の意志を表す。「今度の選挙ではだれに―・れようか」
〔「入(イ)る」に対する他動詞〕
[慣用] 頭に―・息を―・一札(イツサツ)―・肩を―・活を―・勘定に―・気を―・気合を―・嘴(クチバシ)を―・腰を―・ご覧に―・探りを―・朱を―・朱筆を―・底を―・茶々を―・手に―・手を―・泣きを―・念を―・年季を―・鋏(ハサミ)を―・一息―・筆を―・本腰を―・身を―・耳に―・メスを―・焼きを―・詫びを―/間(カン)髪(ハツ)を入れず・世に入れられる
い・れる【煎れる・炒れる】🔗⭐🔉
い・れる [2] 【煎れる・炒れる】 (動ラ下一)
(1)炒られた状態になる。「豆はもう―・れた」
(2)いらいらする。いらだつ。「ほんに
 肝の―・れた事よ/滑稽本・浮世風呂 2」
肝の―・れた事よ/滑稽本・浮世風呂 2」

 肝の―・れた事よ/滑稽本・浮世風呂 2」
肝の―・れた事よ/滑稽本・浮世風呂 2」
いれ-わた【入れ綿】🔗⭐🔉
いれ-わた [0] 【入れ綿】
布団などに綿を入れること。また,その綿。
いれあげる【入れ揚げる】(和英)🔗⭐🔉
いれあげる【入れ揚げる】
lavish money on.
いれい【異例】(和英)🔗⭐🔉
いれい【慰霊祭】(和英)🔗⭐🔉
いれい【慰霊祭】
a memorial service.慰霊塔 a cenotaph.→英和
いれげ【入れ毛】(和英)🔗⭐🔉
いれげ【入れ毛】
artificial[false]hair.
いれちがい【入れ違いになる】(和英)🔗⭐🔉
いれちがい【入れ違いになる】
pass a person in entering.
いれちがえ【入れ違える】(和英)🔗⭐🔉
いれちがえ【入れ違える】
misplace;→英和
put in a wrong place[position].
いれば【入れ歯】(和英)🔗⭐🔉
いれば【入れ歯】
an artificial tooth;dentures (総入れ歯).〜をする have a false tooth put in.
大辞林に「いれ」で始まるの検索結果 1-89。