複数辞典一括検索+![]()
![]()
お-ば【姥・御婆】🔗⭐🔉
お-ば 【姥・御婆】
年とった女。老婆。[名義抄]
お-ば【伯母・叔母】🔗⭐🔉
お-ば ヲ― [0] 【伯母・叔母】
〔「を(小)は(母)」から〕
父母の姉妹。(ア)父母の姉。また,伯父の妻をもいう。《伯母》(イ)父母の妹。また,叔父の妻をもいう。《叔母》
⇔おじ
お-ばあさん【お祖母さん】🔗⭐🔉
お-ばあさん [2] 【お祖母さん】
〔「おばばさま」の転〕
祖母を敬っていう語。
⇔おじいさん
「田舎の―」
お-ばあさん【お婆さん】🔗⭐🔉
お-ばあさん [2] 【お婆さん】
老年の女性を親しんでいう語。
⇔おじいさん
「隣の―」
おばがさけ【伯母が酒】🔗⭐🔉
おばがさけ ヲバ― 【伯母が酒】
狂言の一。酒屋の伯母のところへ甥(オイ)が鬼の面をかぶっていき,おどして酒を存分に飲むが,酔って寝こんだために正体を見破られる。
お-ばけ【御化け】🔗⭐🔉
お-ばけ [2] 【御化け】
(1)何物かが霊能によって姿を変えたもの。特に,異様・奇怪な形をしたものをいう。ばけもの。「から傘の―」「―が出た」
(2)死人が再びこの世に現れたときの,想像上の姿。幽霊。
(3)形や大きさが異様なもの。「―カボチャ」「―きのこ」
おばけ-がい【御化け貝】🔗⭐🔉
おばけ-がい ―ガヒ [3] 【御化け貝】
ヤドカリの異名。
おばけ-ごよみ【御化け暦】🔗⭐🔉
おばけ-ごよみ [4] 【御化け暦】
明治・大正時代,伊勢神宮司庁が発行した官製暦以外に,民間で禁を破って発行した私家製の暦の俗称。
おば-け【尾羽毛】🔗⭐🔉
おば-け ヲバ― [0] 【尾羽毛】
クジラの脂皮を縦に薄切りにしたもの。やや黄色みのある白色。食用。おばき。おばいけ。おばいき。
おばこ🔗⭐🔉
おばこ
(1)(東北地方で)跡取り娘以外の娘。また,未婚女性や妹をさす地方もある。
(2)秋田・山形地方に伝わる民謡。おばこ節。「秋田おばこ」「庄内おばこ」など。
おばこ-むすび【姨子結び】🔗⭐🔉
おばこ-むすび ヲバコ― [4] 【姨子結び】
江戸末期の婦人の髪形の一。髪先を根の周囲に渦巻き状に巻いて,根に笄(コウガイ)をさし,輪の上に出して留めるもの。町家の婦人の略装中では正しい風とされ,丸髷についで多く結われた。おばこ。
おば-さん【小母さん】🔗⭐🔉
おば-さん ヲバ― [0] 【小母さん】
他人である年配の女性を親しんでいう語。
⇔おじさん
「隣の―」
おば-さん【伯母さん・叔母さん】🔗⭐🔉
おば-さん ヲバ― [0] 【伯母さん・叔母さん】
「おば(伯母・叔母)」を敬って,また親しんでいう語。
⇔おじさん
お-はした【御半下・御端】🔗⭐🔉
お-はした 【御半下・御端】
「はしため」を丁寧にいう語。おすえ。「日のめもついに見給はぬ女郎達や―なり/浮世草子・一代男 4」
おばしま【欄】🔗⭐🔉
おばしま [0] 【欄】
欄干(ランカン)。てすり。
おば-じゃ-ひと【伯母者人・叔母者人】🔗⭐🔉
おば-じゃ-ひと ヲバヂヤ― 【伯母者人・叔母者人】
〔「おばである人」の意。「者」は当て字〕
おばである人。おばさん。おばじゃもの。「―,御ざりまするか/狂言・伯母が酒(虎寛本)」
お-ばしら【男柱・雄柱】🔗⭐🔉
お-ばしら ヲ― 【男柱・雄柱】
(1)「おとこばしら(男柱)」に同じ。
(2)櫛(クシ)の両端にある太い二本の歯。「みみづらに刺せるゆつつま櫛の―ひとつ取りかきて/古事記(上訓)」
おばすて【姨捨・伯母捨・姨棄】🔗⭐🔉
おばすて ヲバステ 【姨捨・伯母捨・姨棄】
能の一。三番目物。世阿弥作。中秋の名月の夜,信濃国姨捨山に老女が現れ,姨捨山の伝説を語り,舞を舞う。「関寺小町」「檜垣」とともに「三老女」といわれる。
おばすて-やま【姨捨山】🔗⭐🔉
おばすて-やま ヲバステ― 【姨捨山】
(1)長野盆地南部にある冠着(カムリキ)山の別名。海抜1252メートル。古来,田毎の月で知られた観月の名所。棄老伝説があり「大和物語」「今昔物語集」などに伝わる。うばすてやま。((歌枕))「わが心なぐさめかねつ更級や―に照る月をみて/古今(雑上)」
(2)昔話の一。年老いた親を山中に捨てなければならなくなることに端を発する話。捨てないで家で隠し養っていた親の知恵によって隣国からの難題を解き,以後棄老の掟をやめるという型と,捨てに行った子が道々での親の愛に感動して連れ帰る型とがある。
お-はせ【男茎】🔗⭐🔉
お-はせ ヲ― 【男茎】
陰茎。男根。おはし。「―形」
おばた【小俣】🔗⭐🔉
おばた ヲバタ 【小俣】
三重県中部,度会(ワタライ)郡の町。宮川の渡しで発展。伊勢たくあんの本場。離宮院跡がある。
おばた【小幡】🔗⭐🔉
おばた ヲバタ 【小幡】
姓氏の一。
おばた-えいのすけ【小幡英之助】🔗⭐🔉
おばた-えいのすけ ヲバタ― 【小幡英之助】
(1850-1909) 歯科医。豊前国中津殿町の生まれ。日本人として洋方歯科医の第一号。歯科医術における器械器具の考案につとめた。
おばた-かげのり【小幡景憲】🔗⭐🔉
おばた-かげのり ヲバタ― 【小幡景憲】
(1572-1663) 軍学者。甲州流軍学の祖。通称,勘兵衛。徳川秀忠に仕えた。門弟に北条氏長・山鹿素行ら多数がいる。「甲陽軍鑑」を増補集成。
おはち-いれ【御鉢入れ】🔗⭐🔉
おはち-いれ [3] 【御鉢入れ】
御鉢を入れて飯の冷えるのを防ぐ藁(ワラ)製の器。ふご。御櫃(オヒツ)入れ。[季]冬。
おはち-まわり【御鉢回り】🔗⭐🔉
おはち-まわり ―マハリ [4] 【御鉢回り】
火山の火口壁の周縁を歩くこと。富士山が代表的。おはちめぐり。[季]夏。
お-ばち【雄蜂】🔗⭐🔉
お-ばち ヲ― [1] 【雄蜂】
(1)雄のハチ。
(2)ミツバチの雄。体長約1.5センチメートルで,大きく発達した複眼をもつ。不受精卵から発生し,女王バチと交尾すると死ぬ。寿命約一か月。
おはつ-ほ【御初穂】🔗⭐🔉
おはつ-ほ [0] 【御初穂】
〔「おはつお」とも〕
(1)神仏や朝廷に奉る,その年に初めてとれた穀物。
(2)神仏に供える穀物やお供えもの。
お-ばな【尾花】🔗⭐🔉
お-ばな ヲ― [1] 【尾花】
(1)〔花の形が獣の尾に似ていることから〕
ススキの花穂。また,ススキのこと。[季]秋。《折れたるがほゝけて居りし―かな/加賀谷凡秋》
(2)襲(カサネ)の色目の名。表は白,裏は薄はなだ色。秋に用いる。
おばな-あしげ【尾花葦毛】🔗⭐🔉
おばな-あしげ ヲ― [4] 【尾花葦毛】
馬の毛色の名。たてがみと四肢が灰白色の葦毛の馬。
おばな-いろ【尾花色】🔗⭐🔉
おばな-いろ ヲ― [0] 【尾花色】
枯れたススキのように薄い黒を帯びた白色。
おばな-がゆ【尾花粥】🔗⭐🔉
おばな-がゆ ヲ― 【尾花粥】
昔,宮中で八朔の祝儀の際に用いた粥。疫病よけのまじないとして,ススキの花穂を黒焼きにして入れた。江戸時代には民間にも行われた。尾花の粥。
おばなざわ【尾花沢】🔗⭐🔉
おばなざわ ヲバナザハ 【尾花沢】
山形県北東部,最上川中流東岸の市。近世,羽州街道の宿場町。江戸前期には銀山により繁栄,のち銀山温泉となる。農業が盛ん。
お-はなし【御話】🔗⭐🔉
お-はなし [0] 【御話】
(1)話の尊敬語・丁寧語。「―は承りました」
(2)現実離れした話。架空の話。「―として聞いておく」
(3)江戸時代,一番富の当たり番号を刷った紙札。影富(カゲトミ)は禁止されていたので,「お話」と称して売った。
おはな-はんしち【お花半七】🔗⭐🔉
おはな-はんしち 【お花半七】
1698年に心中したという大坂の遊女お花と刀屋の手代半七の巷説。「長町女腹切(ナガマチオンナノハラキリ)」「京羽二重娘気質(キヨウハブタエムスメカタギ)」などに脚色。
お-はなり【小放り】🔗⭐🔉
お-はなり ヲ― 【小放り】
古代の少女の髪形。振り分け髪に結った髪。はなり。「葦屋(アシノヤ)の菟原処女(ウナイオトメ)の八歳子(ヤトセコ)の片生ひの時ゆ―に髪たくまでに/万葉 1809」
お-ばね【尾羽】🔗⭐🔉
お-ばね ヲ― [1] 【尾羽】
鳥類の尾の羽。扇状に生え,飛ぶ時の舵の役目をし,止まっている時には体のバランスをとる。
おばま【小浜】🔗⭐🔉
おばま ヲバマ 【小浜】
(1)福井県西部,小浜湾に面する市。旧城下町。若狭地方の中心地で,商業・漁業が盛ん。湾岸は景勝地,また文化財を有する社寺が多い。特産物に若狭塗がある。
(2)長崎県島原半島中西部,雲仙岳の西麓にある,温泉・観光の町。
おばま-せん【小浜線】🔗⭐🔉
おばま-せん ヲバマ― 【小浜線】
JR 西日本の鉄道線。福井県敦賀・小浜・京都府東舞鶴間,84.3キロメートル。主として若狭湾岸を走る。
お-はまり【御填り】🔗⭐🔉
お-はまり 【御填り】
(1)夢中になること。悪いことに溺(オボ)れること。「ふかい恋の淵をしりながら水心しらぬ人の―なり/浮世草子・椀久二世(下)」
(2)計略にかかってだまされること。また,思い違いをすること。「大抵の梅桜と同じ事に思するさうながそれは大きな―/浄瑠璃・日本西王母」
お-はむき【御歯向き】🔗⭐🔉
お-はむき 【御歯向き】
「はむき」を丁寧にいう語。おせじ。へつらい。「浮世に追従軽薄あれば,参会(デアイ)に座なり―あり/滑稽本・根無草後編」
おば-むこ【伯母婿・叔母婿】🔗⭐🔉
おば-むこ ヲバ― [3] 【伯母婿・叔母婿】
(1)父母の姉の夫。《伯母婿》
(2)父母の妹の夫。《叔母婿》
おはら-め【大原女】🔗⭐🔉
おはら-め [0] 【大原女】
(1)大原の辺りから市中に黒木などを売りに来る女。筒袖に帯を前で結び,脛巾(ハバキ)にわらじばきといういでたちで,荷を頭の上にのせて歩く。おおはらめ。
〔源平の争いののちに建礼門院が大原で出家したとき,おつきの阿波内侍が始めたのを見習ったという〕
(2)歌舞伎舞踊の一。長唄。変化物。本名題「奉掛色浮世図画(カケタテマツルイロノウキヨエ)」。二世瀬川如皐(ジヨコウ)作。1810年江戸中村座で三世中村歌右衛門初演。おかめの面をつけた小原女から引き抜きで毛槍を振る奴(ヤツコ)に変わる。
大原女(1)
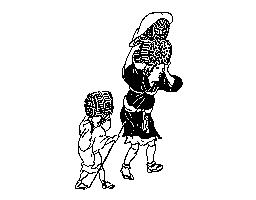 [図]
[図]
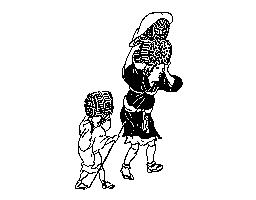 [図]
[図]
おはら-うんしん【小原雲心】🔗⭐🔉
おはら-うんしん ヲハラ― 【小原雲心】
(1861-1916) 生け花の家元。小原流の開祖。号,六合軒。島根県松江市の生まれ。彫刻から生け花に転じた。盛花・投入の創始者。1912年に小原式国風(コクフウ)盛花を掲げて,池坊から独立した。
おはら-ほううん【小原豊雲】🔗⭐🔉
おはら-ほううん ヲハラ― 【小原豊雲】
(1908-1995) 小原流の三世家元。大阪生まれ。生け花にオブジェをとりこみ,造形芸術へと展開させた。戦後の生け花界を主導した一人。
おばら【小原】🔗⭐🔉
おばら ヲバラ 【小原】
姓氏の一。
おばら-くによし【小原国芳】🔗⭐🔉
おばら-くによし ヲバラ― 【小原国芳】
(1887-1977) 教育家。鹿児島県生まれ。京大卒。全人教育論を唱え,自由教育運動を実践し,玉川学園を創設。
おはらい-もの【御払い物】🔗⭐🔉
おはらい-もの ―ハラヒ― [0] 【御払い物】
屑屋などに売り払うべき品物。不用な物。
おはらえ-たて【御祓立て】🔗⭐🔉
おはらえ-たて オハラヘ― [4] 【御祓立て】
兜(カブト)の眉庇(マビサシ)の中央の飾り物(前立物)を立てる所。伊勢の御幣(ゴヘイ)をさしたところからいう。はらいたて。
お-はり【御針】🔗⭐🔉
お-はり [0][2] 【御針】
(1)裁縫をすること。針仕事。
(2)「お針子」に同じ。
おはり-こ【御針子】🔗⭐🔉
おはり-こ [0] 【御針子】
雇われて針仕事をする女。お針。
お-はれ【御晴れ】🔗⭐🔉
お-はれ 【御晴れ】
(1)晴れ着。また,それを着た姿。晴れ姿。
(2)貴人の外出または到着。御成(オナリ)。
お-ばん【お晩】🔗⭐🔉
お-ばん [0] 【お晩】
(東北・信越地方で,「お晩です」「お晩でございます」などの形で)夜の挨拶(アイサツ)の言葉として用いる語。こんばんは。
お-ばんさい【御晩菜】🔗⭐🔉
お-ばんさい [0] 【御晩菜】
惣菜(ソウザイ)のこと。関西,特に京都でいう。
おば【伯[叔]母】(和英)🔗⭐🔉
おば【伯[叔]母】
an aunt.→英和
おばあさん【お婆さん】(和英)🔗⭐🔉
おばあさん【お婆さん】
(1) a grandmother[grandma,granny (小児語)].→英和
(2) an old woman[lady](老婆).
おばけ【お化け】(和英)🔗⭐🔉
おばち【雄蜂】(和英)🔗⭐🔉
おばち【雄蜂】
a drone.→英和
大辞林に「おば」で始まるの検索結果 1-63。