複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぼ🔗⭐🔉
ぼ
「ほ」の濁音の仮名。両唇破裂音の有声子音と後舌の半狭母音とから成る音節。
ぼ【戊】🔗⭐🔉
ぼ [1] 【戊】
十干の第五。つちのえ。
ボア boa
boa 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボア [1]  boa
boa (1)有鱗目ボア科のヘビの総称。大半は中・小形のヘビだが,アナコンダは体長10メートル,コモンボアは6メートルに達する大形種。ほとんどが卵胎生。オーストラリアを除く熱帯・亜熱帯に分布。
(2)毛皮や羽毛の,長い筒状の襟巻。
(3)毛足の長い,アクリルなどのニット地。
(1)有鱗目ボア科のヘビの総称。大半は中・小形のヘビだが,アナコンダは体長10メートル,コモンボアは6メートルに達する大形種。ほとんどが卵胎生。オーストラリアを除く熱帯・亜熱帯に分布。
(2)毛皮や羽毛の,長い筒状の襟巻。
(3)毛足の長い,アクリルなどのニット地。
 boa
boa (1)有鱗目ボア科のヘビの総称。大半は中・小形のヘビだが,アナコンダは体長10メートル,コモンボアは6メートルに達する大形種。ほとんどが卵胎生。オーストラリアを除く熱帯・亜熱帯に分布。
(2)毛皮や羽毛の,長い筒状の襟巻。
(3)毛足の長い,アクリルなどのニット地。
(1)有鱗目ボア科のヘビの総称。大半は中・小形のヘビだが,アナコンダは体長10メートル,コモンボアは6メートルに達する大形種。ほとんどが卵胎生。オーストラリアを除く熱帯・亜熱帯に分布。
(2)毛皮や羽毛の,長い筒状の襟巻。
(3)毛足の長い,アクリルなどのニット地。
ボア bore
bore 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ぼ-あい【暮靄】🔗⭐🔉
ぼ-あい [0] 【暮靄】
もや。晩靄。「遠く比叡愛宕の山々が―に霞んで/朱雀日記(潤一郎)」
ほ-あかり【火明(か)り・灯明(か)り】🔗⭐🔉
ほ-あかり [2] 【火明(か)り・灯明(か)り】
たいまつや灯火などのあかり。
ほあかり-の-みこと【火明命】🔗⭐🔉
ほあかり-の-みこと 【火明命】
(1)日本書紀に見える神。瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の子。尾張連(オワリノムラジ)などの祖先。火照命(ホデリノミコト)。
(2)「播磨国風土記」に見える神。大己貴神(オオアナムチノカミ)の子。あまりの気性の激しさに,この神のもとを逃げ出そうとした大己貴神の船を破壊した。
ボアズ Franz Boas
Franz Boas 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボアズ  Franz Boas
Franz Boas (1858-1942) ドイツ生まれのアメリカの人類学者。カナダのイヌイットや北アメリカ北西海岸のインディアンを調査。心理的・歴史的要因を重んじ,その民族の内側から文化を記述する研究態度に徹した。
(1858-1942) ドイツ生まれのアメリカの人類学者。カナダのイヌイットや北アメリカ北西海岸のインディアンを調査。心理的・歴史的要因を重んじ,その民族の内側から文化を記述する研究態度に徹した。
 Franz Boas
Franz Boas (1858-1942) ドイツ生まれのアメリカの人類学者。カナダのイヌイットや北アメリカ北西海岸のインディアンを調査。心理的・歴史的要因を重んじ,その民族の内側から文化を記述する研究態度に徹した。
(1858-1942) ドイツ生まれのアメリカの人類学者。カナダのイヌイットや北アメリカ北西海岸のインディアンを調査。心理的・歴史的要因を重んじ,その民族の内側から文化を記述する研究態度に徹した。
ボアソナード Gustave
Gustave  mile Boissonade
mile Boissonade 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボアソナード  Gustave
Gustave  mile Boissonade
mile Boissonade (1825-1910) フランスの法学者。1873年(明治6)日本政府の招きにより来日。法学教育に携わり多数の法律家を養成。最初の刑法・治罪法・民法の法典を起草し,日本の近代法整備に貢献。95年帰国。
(1825-1910) フランスの法学者。1873年(明治6)日本政府の招きにより来日。法学教育に携わり多数の法律家を養成。最初の刑法・治罪法・民法の法典を起草し,日本の近代法整備に貢献。95年帰国。
 Gustave
Gustave  mile Boissonade
mile Boissonade (1825-1910) フランスの法学者。1873年(明治6)日本政府の招きにより来日。法学教育に携わり多数の法律家を養成。最初の刑法・治罪法・民法の法典を起草し,日本の近代法整備に貢献。95年帰国。
(1825-1910) フランスの法学者。1873年(明治6)日本政府の招きにより来日。法学教育に携わり多数の法律家を養成。最初の刑法・治罪法・民法の法典を起草し,日本の近代法整備に貢献。95年帰国。
ほあん-かん【保安官】🔗⭐🔉
ほあん-かん ―クワン [2] 【保安官】
アメリカで,郡などの治安維持の任に当たる官吏。住民の選挙によって選ばれる。シェリフ。
ほあん-けいさつ【保安警察】🔗⭐🔉
ほあん-けいさつ [4] 【保安警察】
社会秩序の維持を目的とする警察。治安警察。
ほあん-たい【保安隊】🔗⭐🔉
ほあん-たい [0] 【保安隊】
1952年(昭和27)警察予備隊を改組して発足した陸上部隊。54年自衛隊へと発展。
ほあん-よういん【保安要員】🔗⭐🔉
ほあん-よういん ―エウ ン [4] 【保安要員】
鉱山などで,作業員・施設などの保安業務にたずさわる人。
ン [4] 【保安要員】
鉱山などで,作業員・施設などの保安業務にたずさわる人。
 ン [4] 【保安要員】
鉱山などで,作業員・施設などの保安業務にたずさわる人。
ン [4] 【保安要員】
鉱山などで,作業員・施設などの保安業務にたずさわる人。
ほあん-りん【保安林】🔗⭐🔉
ほあん-りん [2] 【保安林】
森林法に基づき,一定の公益目的のために農林水産大臣が指定する森林。水源の涵養(カンヨウ),土砂流出の防備,風水害の防備,魚付き,風致保存などの目的による。
ボイアルド Matteo Maria Boiardo
Matteo Maria Boiardo 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイアルド  Matteo Maria Boiardo
Matteo Maria Boiardo (1441-1494) イタリアの詩人。騎士道物語詩の傑作「恋するオルランド」(未完)の作者として知られる。
(1441-1494) イタリアの詩人。騎士道物語詩の傑作「恋するオルランド」(未完)の作者として知られる。
 Matteo Maria Boiardo
Matteo Maria Boiardo (1441-1494) イタリアの詩人。騎士道物語詩の傑作「恋するオルランド」(未完)の作者として知られる。
(1441-1494) イタリアの詩人。騎士道物語詩の傑作「恋するオルランド」(未完)の作者として知られる。
ボイオチア Boi
Boi tia
tia 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイオチア  Boi
Boi tia
tia ギリシャの中部地方。紀元前447年,テーベを中心にボイオチア同盟を結成。
ギリシャの中部地方。紀元前447年,テーベを中心にボイオチア同盟を結成。
 Boi
Boi tia
tia ギリシャの中部地方。紀元前447年,テーベを中心にボイオチア同盟を結成。
ギリシャの中部地方。紀元前447年,テーベを中心にボイオチア同盟を結成。
ぼ-いき【墓域】🔗⭐🔉
ぼ-いき ― キ [1][0] 【墓域】
墓地として区切られた地域。墓場。
キ [1][0] 【墓域】
墓地として区切られた地域。墓場。
 キ [1][0] 【墓域】
墓地として区切られた地域。墓場。
キ [1][0] 【墓域】
墓地として区切られた地域。墓場。
ほいく-えん【保育園】🔗⭐🔉
ほいく-えん ― ン [3] 【保育園】
保育所の通称。
ン [3] 【保育園】
保育所の通称。
 ン [3] 【保育園】
保育所の通称。
ン [3] 【保育園】
保育所の通称。
ほいく-き【保育器】🔗⭐🔉
ほいく-き [3] 【保育器】
未熟児を入れて保育する装置。内部の温度・湿度・酸素供給量は適宜調整でき,外部からも観察できる。
ボイコット boycott
boycott 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイコット [3]  boycott
boycott (名)スル
〔1880年,アイルランドで小作人から排斥された農場の差配人ボイコット大尉の名に由来〕
(1)組織的もしくは集団的にある商品を買わなかったり,原料供給を断ったりして,取引を拒絶すること。不買同盟。
(2)一定の目的により,特定の人物を共同で排斥したり,集まりなどへの参加を共同で拒否すること。「授業を―する」
(名)スル
〔1880年,アイルランドで小作人から排斥された農場の差配人ボイコット大尉の名に由来〕
(1)組織的もしくは集団的にある商品を買わなかったり,原料供給を断ったりして,取引を拒絶すること。不買同盟。
(2)一定の目的により,特定の人物を共同で排斥したり,集まりなどへの参加を共同で拒否すること。「授業を―する」
 boycott
boycott (名)スル
〔1880年,アイルランドで小作人から排斥された農場の差配人ボイコット大尉の名に由来〕
(1)組織的もしくは集団的にある商品を買わなかったり,原料供給を断ったりして,取引を拒絶すること。不買同盟。
(2)一定の目的により,特定の人物を共同で排斥したり,集まりなどへの参加を共同で拒否すること。「授業を―する」
(名)スル
〔1880年,アイルランドで小作人から排斥された農場の差配人ボイコット大尉の名に由来〕
(1)組織的もしくは集団的にある商品を買わなかったり,原料供給を断ったりして,取引を拒絶すること。不買同盟。
(2)一定の目的により,特定の人物を共同で排斥したり,集まりなどへの参加を共同で拒否すること。「授業を―する」
ボイジャー Voyager
Voyager 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイジャー  Voyager
Voyager アメリカの無人惑星探査機。1977年打ち上げ。一号は木星と土星,二号は木星・土星・天王星・海王星を観測し,多くの有用な情報をもたらした。
アメリカの無人惑星探査機。1977年打ち上げ。一号は木星と土星,二号は木星・土星・天王星・海王星を観測し,多くの有用な情報をもたらした。
 Voyager
Voyager アメリカの無人惑星探査機。1977年打ち上げ。一号は木星と土星,二号は木星・土星・天王星・海王星を観測し,多くの有用な情報をもたらした。
アメリカの無人惑星探査機。1977年打ち上げ。一号は木星と土星,二号は木星・土星・天王星・海王星を観測し,多くの有用な情報をもたらした。
ボイス voice
voice 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイス [1]  voice
voice (1)声。
(2)「態{(2)(ア)}」に同じ。
(1)声。
(2)「態{(2)(ア)}」に同じ。
 voice
voice (1)声。
(2)「態{(2)(ア)}」に同じ。
(1)声。
(2)「態{(2)(ア)}」に同じ。
ボイス-メール voice mail
voice mail 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイス-メール [4]  voice mail
voice mail 音声による電子メール-システム。特定の相手に対するメッセージをセンターに登録,本人だけがメッセージを聞き,返事を登録できる仕組み。音声メール。
音声による電子メール-システム。特定の相手に対するメッセージをセンターに登録,本人だけがメッセージを聞き,返事を登録できる仕組み。音声メール。
 voice mail
voice mail 音声による電子メール-システム。特定の相手に対するメッセージをセンターに登録,本人だけがメッセージを聞き,返事を登録できる仕組み。音声メール。
音声による電子メール-システム。特定の相手に対するメッセージをセンターに登録,本人だけがメッセージを聞き,返事を登録できる仕組み。音声メール。
ボイス-レコーダー🔗⭐🔉
ボイス-レコーダー [5]
〔cockpit voice recorder〕
飛行機の操縦室内の音声を自動的に録音する機械。飛行機の墜落にも耐えられるように堅牢な箱に納められている。
ボイス Joseph Beuys
Joseph Beuys 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイス  Joseph Beuys
Joseph Beuys (1921-1986) ドイツの芸術家。あらゆる領域における創造的活動を喚起することを目標として,美術教育や社会的実践活動,さらにイベントやパフォーマンスを展開した。エコロジー運動にも参加。
(1921-1986) ドイツの芸術家。あらゆる領域における創造的活動を喚起することを目標として,美術教育や社会的実践活動,さらにイベントやパフォーマンスを展開した。エコロジー運動にも参加。
 Joseph Beuys
Joseph Beuys (1921-1986) ドイツの芸術家。あらゆる領域における創造的活動を喚起することを目標として,美術教育や社会的実践活動,さらにイベントやパフォーマンスを展開した。エコロジー運動にも参加。
(1921-1986) ドイツの芸術家。あらゆる領域における創造的活動を喚起することを目標として,美術教育や社会的実践活動,さらにイベントやパフォーマンスを展開した。エコロジー運動にも参加。
ボイス-バロット-の-ほうそく【―の法則】🔗⭐🔉
ボイス-バロット-の-ほうそく ―ハフソク 【―の法則】
風向と低・高気圧の中心の関係を示す法則。1857年オランダ人ボイス=バロット(Buys Ballot 1817-1890)が航海用の指針として発表したもの。すなわち,北半球においては風を背にして立つと低気圧の中心は左手のやや前方にあり,高気圧の中心は右手のやや後方にあるという法則。
ボイセン-イェンセン Peter Boysen-Jensen
Peter Boysen-Jensen 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイセン-イェンセン  Peter Boysen-Jensen
Peter Boysen-Jensen (1883-1959) デンマークの植物生理学・生態学者。光合成産物の呼吸による消費や生長への配分などを解析し,生態学の定量的研究の基礎を築く。また,屈光性の研究から生長ホルモンの存在を解明。
(1883-1959) デンマークの植物生理学・生態学者。光合成産物の呼吸による消費や生長への配分などを解析し,生態学の定量的研究の基礎を築く。また,屈光性の研究から生長ホルモンの存在を解明。
 Peter Boysen-Jensen
Peter Boysen-Jensen (1883-1959) デンマークの植物生理学・生態学者。光合成産物の呼吸による消費や生長への配分などを解析し,生態学の定量的研究の基礎を築く。また,屈光性の研究から生長ホルモンの存在を解明。
(1883-1959) デンマークの植物生理学・生態学者。光合成産物の呼吸による消費や生長への配分などを解析し,生態学の定量的研究の基礎を築く。また,屈光性の研究から生長ホルモンの存在を解明。
ほ-いつ【捕逸】🔗⭐🔉
ほ-いつ [0] 【捕逸】 (名)スル
「捕手逸球」の略。パス-ボール。
ほい-とう【陪堂】🔗⭐🔉
ほい-とう ―タウ [0] 【陪堂】
〔「ほい」は唐音〕
(1)(ア)禅宗で,僧堂以外の場所でもてなし(陪食(バイシヨク))を受けること。「相伴邏斎の僧,―,外僧堂の輩/庭訓往来」(イ)禅宗で,僧の食事の世話をすること。また,その僧や飯米。
(2)他人に食事を施すこと。また,その食事や飯米。「今夜一夜の―たべやつとよばはつて/幸若・烏帽子折」
(3)金品をもらって回ること。ものもらい。こじき。ほいと。「さて此処彼処,―しけれども,呉れざりければ/仮名草子・仁勢物語」
ほい-な・い【本意無い】🔗⭐🔉
ほい-な・い [3] 【本意無い】 (形)[文]ク ほいな・し
(1)期待はずれだ。飽き足りない。「お糸さんは…顔も見せない。私は何となく―・かつた/平凡(四迷)」
(2)本来の意向に反する。不本意である。「かへすがへす―・くこそ覚え侍れ/竹取」
ぼい-ぼい🔗⭐🔉
ぼい-ぼい (副)
不平不満などをつぶやくさま。ぶつぶつ。「悪態ばかり―ぼやきくさつて/滑稽本・浮世床(初)」
ボイボジナ Vojvodina
Vojvodina 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイボジナ  Vojvodina
Vojvodina ユーゴスラビア,セルビア共和国の北部を占める自治州。もとハンガリー領であったが第一次大戦後ユーゴスラビアに編入された。住民はセルビア人とハンガリー人。州都ノビザード。
ユーゴスラビア,セルビア共和国の北部を占める自治州。もとハンガリー領であったが第一次大戦後ユーゴスラビアに編入された。住民はセルビア人とハンガリー人。州都ノビザード。
 Vojvodina
Vojvodina ユーゴスラビア,セルビア共和国の北部を占める自治州。もとハンガリー領であったが第一次大戦後ユーゴスラビアに編入された。住民はセルビア人とハンガリー人。州都ノビザード。
ユーゴスラビア,セルビア共和国の北部を占める自治州。もとハンガリー領であったが第一次大戦後ユーゴスラビアに編入された。住民はセルビア人とハンガリー人。州都ノビザード。
ぼい-やま【ぼい山】🔗⭐🔉
ぼい-やま [0] 【ぼい山】
北陸地方の多雪地域に広く分布する二次林。雪圧による匍匐(ホフク)性の落葉低木林で,燃料用の「ぼい(=粗朶(ソダ))」を採取する。
ほいやり🔗⭐🔉
ほいやり (副)
やさしく,あるいはうれしそうにほほえむさま。にっこりと。「母―と笑顔して/浄瑠璃・宵庚申(下)」
ボイラー boiler
boiler 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイラー [1]  boiler
boiler (1)給湯用の湯沸かし釜。
(2)水を加熱して蒸気を発生させる装置。工業用に広く用いられるほか,炊事・暖房用など各種のものがある。汽缶。
(1)給湯用の湯沸かし釜。
(2)水を加熱して蒸気を発生させる装置。工業用に広く用いられるほか,炊事・暖房用など各種のものがある。汽缶。
 boiler
boiler (1)給湯用の湯沸かし釜。
(2)水を加熱して蒸気を発生させる装置。工業用に広く用いられるほか,炊事・暖房用など各種のものがある。汽缶。
(1)給湯用の湯沸かし釜。
(2)水を加熱して蒸気を発生させる装置。工業用に広く用いられるほか,炊事・暖房用など各種のものがある。汽缶。
ボイラー-ぎし【―技士】🔗⭐🔉
ボイラー-ぎし [5] 【―技士】
ボイラーを取り扱う資格を有する者。
ボイル boil
boil 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイル [1]  boil
boil (名)スル
ゆでること。また,湯などをわかすこと。「玉子を―する」
(名)スル
ゆでること。また,湯などをわかすこと。「玉子を―する」
 boil
boil (名)スル
ゆでること。また,湯などをわかすこと。「玉子を―する」
(名)スル
ゆでること。また,湯などをわかすこと。「玉子を―する」
ボイル-ゆ【―油】🔗⭐🔉
ボイル-ゆ [3] 【―油】
亜麻仁油のような乾性油に,マンガンやコバルトの酸化物を加え煮沸して製した油。乾燥性が強く,ペンキや油絵の具の溶剤に使われる。
ボイル voile
voile 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイル [1]  voile
voile 強撚糸(キヨウネンシ)で粗く織った薄地の布。夏服やシャツに使用。
強撚糸(キヨウネンシ)で粗く織った薄地の布。夏服やシャツに使用。
 voile
voile 強撚糸(キヨウネンシ)で粗く織った薄地の布。夏服やシャツに使用。
強撚糸(キヨウネンシ)で粗く織った薄地の布。夏服やシャツに使用。
ボイル Robert Boyle
Robert Boyle 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイル  Robert Boyle
Robert Boyle (1627-1691) イギリスの物理学者・化学者。フックとともに空気ポンプを製作し,気体の体積と圧力に関するボイルの法則を発見。粒子論による元素概念を提起し,近代化学の基礎を築いた。
(1627-1691) イギリスの物理学者・化学者。フックとともに空気ポンプを製作し,気体の体積と圧力に関するボイルの法則を発見。粒子論による元素概念を提起し,近代化学の基礎を築いた。
 Robert Boyle
Robert Boyle (1627-1691) イギリスの物理学者・化学者。フックとともに空気ポンプを製作し,気体の体積と圧力に関するボイルの法則を発見。粒子論による元素概念を提起し,近代化学の基礎を築いた。
(1627-1691) イギリスの物理学者・化学者。フックとともに空気ポンプを製作し,気体の体積と圧力に関するボイルの法則を発見。粒子論による元素概念を提起し,近代化学の基礎を築いた。
ボイル-シャルル-の-ほうそく【―の法則】🔗⭐🔉
ボイル-シャルル-の-ほうそく ―ハフソク 【―の法則】
ボイルの法則とシャルルの法則から得られる法則で,気体の体積は圧力に反比例し絶対温度に比例するという法則。ただし実在の気体はわずかながらこの法則からずれた性質を示し,厳密にこの法則に従う仮想的な気体を理想気体という。
ボイル-の-ほうそく【―の法則】🔗⭐🔉
ボイル-の-ほうそく ―ハフソク 【―の法則】
一定温度において,気体の体積は圧力に反比例するという法則。
ボイルド boiled
boiled 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ボイルド [1]  boiled
boiled 「ゆでた」「煮た」の意で,多く他の語に付いて複合語を作る。「―-エッグ」
「ゆでた」「煮た」の意で,多く他の語に付いて複合語を作る。「―-エッグ」
 boiled
boiled 「ゆでた」「煮た」の意で,多く他の語に付いて複合語を作る。「―-エッグ」
「ゆでた」「煮た」の意で,多く他の語に付いて複合語を作る。「―-エッグ」
ほい-ろ【焙炉】🔗⭐🔉
ほい-ろ [1] 【焙炉】
木枠の底に和紙を張り,火鉢などにかざして海苔・茶などを乾燥させる道具。特に,製茶用のものをいう。[季]春。
焙炉
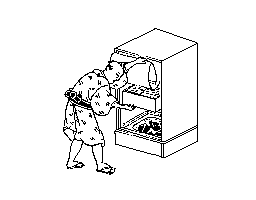 [図]
[図]
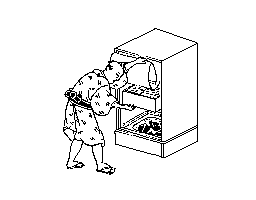 [図]
[図]
ぼ-いん【戊寅】🔗⭐🔉
ぼ-いん [0] 【戊寅】
干支(エト)の一。つちのえとら。
ぼ-いん【母音】🔗⭐🔉
ぼ-いん [0] 【母音】
言語音の分類の一。声帯の振動で生じた有声の呼気が,咽頭や口腔内の通路で閉鎖や狭めをうけずに響きよく発せられる音。現代日本語の共通語ではア・イ・ウ・エ・オの五つに区分する。ぼおん。母韻。
⇔子音
ぼいん-こうたい【母音交替】🔗⭐🔉
ぼいん-こうたい ―カウ― [4] 【母音交替】
一つの語根中の母音が,文法機能や品詞の変化に応じて,音色や長さの違う別の母音と交替すること。インド-ヨーロッパ諸語に特徴的で,英語の tooth(「歯」の単数形)―teeth(複数形),sing(「歌う」の現在形)―sang(同過去形)―sung(同過去分詞形)などがその例。また,日本語の,フネ―フナ(舟),シロ―シラ(白),カルシ―カロシ(軽)などについてもいう。アプラウト。
ぼいん-さんかくけい【母音三角形】🔗⭐🔉
ぼいん-さんかくけい [6] 【母音三角形】
母音を,発音するときの舌の位置の前後,口の開きの広狭など調音上の違いによって分類し,逆三角形の頂点や各辺上に位置づけて図示したもの。
母音三角形
 [図]
[図]
 [図]
[図]
ぼいん-ちょうわ【母音調和】🔗⭐🔉
ぼいん-ちょうわ ―テウ― [4] 【母音調和】
語幹あるいは語幹と接辞の結合など一定の言語単位内部で,共存可能な母音の組み合わせに制限が認められる現象。ある言語の母音が,前舌・後舌,円唇・非円唇,広い・狭いなどの基準によってグループに分かれ,同一グループの母音どうしでのみ共存が許される。アルタイ諸語,フィン-ウゴル諸語のほか,アフリカやアメリカ-インディアンの言語などにもみられる。
ぼいん🔗⭐🔉
ぼいん [2]
■一■ (副)
(多く「と」を伴って)勢いよくけったりなぐったりするさま。「―となぐる」
■二■ (名)
女性の大きな乳房を俗にいう語。
ぼう【亡】🔗⭐🔉
ぼう バウ [1] 【亡】
死ぬこと。没。「二月八日―」
ぼう【坊】🔗⭐🔉
ぼう バウ [1] 【坊】
■一■ (名)
(1)僧侶の居所。転じて,僧侶。房。「僧―」「お―さん」
(2)男の幼児を親しんで呼ぶ称。江戸時代には女児についてもいった。「―や」「―はどこの子だい」
(3)(ア)唐の都城制に倣った条坊制の一区画。四周を大路で囲まれた区域をさし,これがさらに小路によって一六の町(坪)に分かれる。(イ)条坊制で,左京・右京おのおのの各条を四坊に分かつ大路。南北に通じ,東西に通じる「条」に対する。
(4)皇太子の居所「東宮坊」から転じて,皇太子をいう。「―にもようせずは,この御子のゐ給べきなめり/源氏(桐壺)」
■二■ (代)
一人称。男の幼児が自分をさし示していう語。「それは―のだよ」
■三■ (接尾)
(1)人の名に付けて,親しみや軽いあざけりの意を表す。「お春―」「けん―」
(2)人の様態を表す語に付いて,そういう人であることを表す。上にくる語によって「ぼ」「んぼ」「んぼう」の形にもなる。「朝寝―」「赤ん―」「赤んぼ」「暴れん―」「けちん―」「けちんぼ」
(3)僧侶の通称や坊号などの下に添えて用いる。「武蔵―弁慶」「法界―」
ぼう【芒】🔗⭐🔉
ぼう バウ [1] 【芒】
のぎ。
ぼう【房】🔗⭐🔉
ぼう バウ [1] 【房】
(1)小部屋。つぼね。「草の御蓆も此の―にこそまうけ侍るべけれ/源氏(若紫)」
(2)僧の住んでいる所。また,僧。「或る―には経典を読誦する比丘有り/今昔 4」「すぐれたる御―ぞかし/大鏡(昔物語)」
(3)二十八宿の一。東方の星宿。蠍座(サソリザ)の前半部に当たる。房宿。そいぼし。
ぼう【昴】🔗⭐🔉
ぼう バウ [1] 【昴】
二十八宿の一。西方の星宿。昴宿。すばる。
ぼう【某】🔗⭐🔉
ぼう [1] 【某】
■一■ (名)
ある人や場所・月日などが不明な場合,また意図的にそれとはっきり指し示していわない場合に用いる語。「中村―」「―政治家」「―年―月」
■二■ (代)
一人称。男性が自らをへりくだっていう語。それがし。やつがれ。「―稽首敬白/明衡往来」
ぼう【帽】🔗⭐🔉
ぼう [1] 【帽】
頭にかぶるもの。帽子。「ベレー―」「長押(ナゲシ)から中折れの―を取つて被る/青年(鴎外)」
ぼう【棒】🔗⭐🔉
ぼう バウ [0] 【棒】
(1)手に持てるくらいの細長い木・金属・竹など。「短い―」「マッチ―」
(2)六尺(約1.8メートル)くらいの木を武具としたもの。また,それを用いる武術。棒術。
(3)まっすぐに引いた線。棒線。「横に―を引く」
(4)疲労などのために足の筋肉がつっぱってしまうこと。「足が―になる」
(5)一直線であること。単調で変化のないこと。また,連続すること。「台詞(セリフ)を―に読む」「―暗記」
(6)〔仏〕 禅宗で,師が指導のために用いる棒。一棒。
ぼう【暴】🔗⭐🔉
ぼう [1] 【暴】 (名・形動)[文]ナリ
(1)荒々しいこと。乱暴であること。また,そのさま。「日方が言葉に募つて―な事でも仕はせぬかと/天うつ浪(露伴)」
(2)道理にはずれていること。不法であること。また,そのさま。「はや乱酔の友達らの,―なコップの悪強(ワルジイ)酒/当世書生気質(逍遥)」
ぼ-う【暮雨】🔗⭐🔉
ぼ-う [1] 【暮雨】
夕暮れに降る雨。
ぼ・う【追ふ】🔗⭐🔉
ぼ・う ボフ 【追ふ】 (動ハ四)
〔「おふ」の転〕
おう。追いかける。「往なずば早う―・ひ往なせ/浄瑠璃・夏祭」
ぼう【茫】🔗⭐🔉
ぼう バウ [1] 【茫】 (ト|タル)[文]形動タリ
(1)広々としているさま。「高原に出ると…見わたす先は―としてゐる/日本北アルプス縦断記(烏水)」
(2)ぼんやりとしているさま。「―とした湯気の中に/田舎教師(花袋)」
ぼいん【母音】(和英)🔗⭐🔉
ぼいん【母音】
a vowel.→英和
ぼいん【拇印】(和英)🔗⭐🔉
ぼいん【拇印】
a thumb impression.〜を押す seal with the thumb.→英和
ぼう【某】(和英)🔗⭐🔉
ぼう【某】
a (ある);a (certain) person (ある人).‖某氏 a certain person;Mr.So-and-so.某所 a certain place;somewhere.
大辞林に「ぼ」で始まるの検索結果 1-72。もっと読み込む