複数辞典一括検索+![]()
![]()
ふり【振り・風】🔗⭐🔉
ふり 【振り・風】
■一■ [0][2] (名)
(1)振ること。振り方。「バットの―が鈍い」
(2)動作の仕方。様子。また,姿・容姿。「知らない―をする」「腰附,肩附,歩く―/歌行灯(鏡花)」「天性―よく見事に生(ソダチ)たる松のごとし/耳塵集」
(3)踊りのしぐさ。また,歌舞伎などで,俳優の所作。「―を付ける」
(4)料理屋・遊女屋などで,紹介や予約のないこと。「―の客」
(5)女物の和服の袖の,袖付け止まりから袖下までの縫い合わせてない部分。
(6)方位や角度をずらすこと。また,ずれていること。振れ。「建ては建てたが,ちつくり笠に―がある/浄瑠璃・一谷嫩軍記」
(7)下帯・猿股などをつけてないこと。「帯ひろ前の―になつて居るやうな/志都能石屋」
(8)分担・負担させること。「そんならなほしてそつちが―だぞ/洒落本・三人酩酊」
(9)「振り売り」に同じ。「荻織る笠を市に―する(羽笠)/冬の日」
(10)「振袖」に同じ。「片町の―を内へ呼び入/浄瑠璃・夕霧阿波鳴渡(中)」
(11)「振り回し」に同じ。「借銀かさみ,次第に―につまり/浮世草子・永代蔵 6」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)振る動作の回数を表すのに用いる。「バットを一―二―してからバッター-ボックスに立つ」
(2)刀剣を数えるのに用いる。「太刀一―を贈る」
ぶり【振り・風】🔗⭐🔉
ぶり 【振り・風】
名詞またはそれに準ずる語の下に付いて複合語をつくる。
(1)状態・動作の仕方・あり方を表す。「枝―」「勉強―」
〔「歩きっぷり」「男っぷり」「飲みっぷり」のように「っぷり」となることがある〕
(2)数量を表す語に付いて,分量がそれだけに相当することを表す。「大―」「五軒―もある家/鹿狩(独歩)」
(3)時間を表す語に付いて,それだけの時間を経過して,再び同じ状態になることを表す。「五年―の帰郷」「三日―の晴天」
(4)歌・和歌の曲調・調子を表す。「万葉―」
(5)古代歌謡,特に雅楽寮に伝わる歌曲の曲名を表す。多く,歌詞の冒頭の語に付ける。「天田(アマダ)―/古事記(下訓)」
ふり-あい【振(り)合い】🔗⭐🔉
ふり-あい ―アヒ [0] 【振(り)合い】
(1)他とのつりあい。バランス。「―が悪い」
(2)その場の状況。都合。
ふり-あ・う【振(り)合う・触(り)合う】🔗⭐🔉
ふり-あ・う ―アフ [3] 【振(り)合う・触(り)合う】 (動ワ五[ハ四])
互いに触れる。触れ合う。「袖―・うも多生の縁」
ふり-あお・ぐ【振(り)仰ぐ】🔗⭐🔉
ふり-あお・ぐ ―アフグ [4] 【振(り)仰ぐ】 (動ガ五[四])
顔を上に向ける。顔をあげて高い所を見る。「頂上を―・ぐ」
ふり-あ・げる【振(り)上げる】🔗⭐🔉
ふり-あ・げる [4] 【振(り)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 ふりあ・ぐ
(1)手や手に持っている物を勢いよく上げる。「鍬(クワ)を―・げる」「手を―・げる」
(2)振りながら次第に高くする。「白山中宮の神輿(シンヨ)を賁(カザ)り奉り,比叡山へ―・げ奉る/平家 1」
ふり-あて【振(り)当て】🔗⭐🔉
ふり-あて [0] 【振(り)当て】
ふりあてること。わりあて。
ふり-あ・てる【振(り)当てる】🔗⭐🔉
ふり-あ・てる [4] 【振(り)当てる】 (動タ下一)[文]タ下二 ふりあ・つ
担当・分担をきめる。わりふる。「広報係を―・てる」
ふり-あらい【振(り)洗い】🔗⭐🔉
ふり-あらい ―アラヒ [3] 【振(り)洗い】 (名)スル
洗剤溶液の中で,布を振り動かして洗うこと。
ふり-い・ず【振り出づ】🔗⭐🔉
ふり-い・ず ―イヅ 【振り出づ】 (動ダ下二)
(1)振り切って出て行く。「―・でて行かむ事もあはれにて/源氏(末摘花)」
(2)声を高く張り上げる。「鈴虫の―・でたるほど/源氏(鈴虫)」
(3)紅(クレナイ)を水にふり出して染める。「紅の―・でつつなく涙には/古今(恋二)」
ふり-うり【振(り)売り】🔗⭐🔉
ふり-うり [0] 【振(り)売り】 (名)スル
(1)持ち歩いている商品の名を大声で呼びながら売り歩くこと。また,その人。触れ売り。振り。「町中を―し/浄瑠璃・宵庚申(下)」
(2)中世,座に属さないで,自由に行なった商売。また,その人。
ふり-おこ・す【振り起(こ)す】🔗⭐🔉
ふり-おこ・す [4] 【振り起(こ)す】 (動サ五[四])
(1)心を奮い立たせる。「勇気を―・して物を言つて見やう/平凡(四迷)」
(2)勢いよく立てる。「梓弓末―・し/万葉 4164」
ふり-おろ・す【振り下ろす】🔗⭐🔉
ふり-おろ・す [4] 【振り下ろす】 (動サ五[四])
振り上げたものを勢いよく下ろす。「斧(オノ)を―・す」
[可能] ふりおろせる
ふり-かえ【振(り)替え・振替】🔗⭐🔉
ふり-かえ ―カヘ [0] 【振(り)替え・振替】
(1)振り替えること。入れ替えること。流用すること。「―の休日」
(2)「郵便振替」の略。
(3)実際に金銭を出し入れせず,帳簿上で,ある勘定を他の勘定へ移すこと。振替勘定。
ふりかえ-きゅうじつ【振(り)替え休日】🔗⭐🔉
ふりかえ-きゅうじつ ―カヘキウ― [5] 【振(り)替え休日】
(1)祝祭日が日曜日と重なった場合,その翌日を祝祭日に振り替えて休日とすること。また,その日。
(2)休日に出勤や登校などをした場合,他の日を代わりに休日とすること。また,その日。
ふり-かえ・る【振(り)返る】🔗⭐🔉
ふり-かえ・る ―カヘル [3] 【振(り)返る】 (動ラ五[四])
(1)体をねじるようにして後ろを見る。「別れを惜しんで―・る」
(2)過去の事を考える。また,回顧する。「学生時代を―・る」
ふり-か・える【振(り)替える】🔗⭐🔉
ふり-か・える ―カヘル [4][3] 【振(り)替える】 (動ア下一)[文]ハ下二 ふりか・ふ
(1)臨時に,ある物を他の用途に用いる。一時的にとりかえる。「電車の不通区間をバスに―・える」「休日を月曜に―・える」
(2)簿記で,振り替え{(3)}にする。「営業費に―・える」
ふり-かけ【振(り)掛け】🔗⭐🔉
ふり-かけ [0] 【振(り)掛け】
(1)飯に振りかけて食べる粉状の食品。魚粉などに海苔(ノリ)・胡麻(ゴマ)・鰹節(カツオブシ)・香辛料を加えたもの。
(2)絵筆を金網の上からこすりつけ,絵の具を網目から煙のように出してかく方法。調子を弱めたり,雲霧・湯気などの感じを出すときに用いる。ふき。
ふり-か・ける【振(り)掛ける・振り懸ける】🔗⭐🔉
ふり-か・ける [4] 【振(り)掛ける・振り懸ける】 (動カ下一)[文]カ下二 ふりか・く
(1)粉末状・液状のものを少量,上から散らすようにしてかける。「赤飯にゴマを―・ける」
(2)顔に髪を垂らしてかける。髪で顔を隠す。「―・くべき髪のおぼえさへあやしからむと思ふに/枕草子 184」
ふり-かた【振(り)方】🔗⭐🔉
ふり-かた [0] 【振(り)方】
(1)ふり動かす方法。「バットの―」
(2)処置の仕方。扱い方。「身の―に困る」
ふり-がな【振(り)仮名】🔗⭐🔉
ふり-がな [0][3] 【振(り)仮名】
漢字の傍らに,その読み方を示すために書きそえる仮名。ルビ。
ふり-かぶ・る【振りかぶる】🔗⭐🔉
ふり-かぶ・る [4] 【振りかぶる】 (動ラ五[四])
手に持った物を勢いよく頭の上にふりあげる。「大刀を―・る」「―・って第一球を投げる」
[可能] ふりかぶれる
ふり-かわり【振り替(わ)り】🔗⭐🔉
ふり-かわり ―カハリ [0] 【振り替(わ)り】
囲碁で,二か所の争いのときに,一方をあきらめて他方を確実に取ること。
ふり-き・る【振(り)切る】🔗⭐🔉
ふり-き・る [3] 【振(り)切る】 (動ラ五[四])
(1)手などを強く振って,しがみついているものを離す。振り離す。「手を―・って逃げる」
(2)他人の頼みや,懇願をことわる。「頼みを―・って戻る」
(3)追い着こうとするのを引き離す。「ゴール寸前で―・る」
(4)完全に振る。十分に振る。「バットを―・る」
[可能] ふりきれる
ふり-き・れる【振り切れる】🔗⭐🔉
ふり-き・れる [4] 【振り切れる】 (動ラ下一)
メーターの針が回り過ぎて目盛りの外へ出る。
ふり-こ【振(り)子】🔗⭐🔉
ふり-こ [0] 【振(り)子】
固定された点または軸のまわりに周期的な振動を行うもの。単振り子・実体振り子・ねじれ振り子などがある。しんし。
ふりこ-どけい【振(り)子時計】🔗⭐🔉
ふりこ-どけい [4] 【振(り)子時計】
振り子の振動の等時性を利用して歯車の動きを調節し,針が一定の速さで動くようにした時計。
ふりこ-のこぎり【振(り)子鋸】🔗⭐🔉
ふりこ-のこぎり [4] 【振(り)子鋸】
丸鋸(マルノコ)の一種。高所からつり下げて,木材を横切りする。
ふり-こ・す【振り越す】🔗⭐🔉
ふり-こ・す 【振り越す】 (動サ四)
後ろに垂れた髪を分けて,肩から前に垂らす。「朝寝がみ誰が手枕にたばつけてけさは形見に―・してみる/金葉(恋上)」
ふり-ごと【振(り)事】🔗⭐🔉
ふり-ごと [0] 【振(り)事】
⇒所作事(シヨサゴト)
ふり-ごま【振り駒】🔗⭐🔉
ふり-ごま [0] 【振り駒】
将棋で,先手を決めるために三枚あるいは五枚の歩(フ)を盤上に投げること。歩が多ければ振った者が,と金が多ければ相手が先手。振り歩。
ふり-こみ【振(り)込み】🔗⭐🔉
ふり-こみ [0] 【振(り)込み】
(1)振替口座・預金口座などに金銭を払い込むこと。
(2)麻雀で,他の者の上がり牌(パイ)を捨てること。放銃。
(3)突然押しかけて来ること。「そんなやすいては―の未至客(ハンカキヤク)のする事で/洒落本・白狐通」
ふり-こ・む【振(り)込む】🔗⭐🔉
ふり-こ・む [3] 【振(り)込む】 (動マ五[四])
(1)振って中に入れる。荒っぽく持ち込む。「万灯を―・んで見りやあ唯も帰れない/たけくらべ(一葉)」
(2)振替口座・預金口座などに金銭を払い込む。「代金を口座に―・む」
(3)麻雀で,他の者の上がり牌(パイ)を捨てる。「役満を―・む」
(4)強引に入り込む。押しかける。「追ひ出した女房…―・んで来たるならんか/滑稽本・膝栗毛(発端)」
[可能] ふりこめる
ふり-さ・く【振り放く】🔗⭐🔉
ふり-さ・く 【振り放く】 (動カ下二)
はるか遠くを見る。振りあおぐ。「―・けて三日月見れば/万葉 994」
ふりさけ・みる【振り放け見る】🔗⭐🔉
ふりさけ・みる 【振り放け見る】 (動マ上一)
ふり仰いで,はるか遠くを見る。「天の原―・みれば春日なるみかさの山に出でし月かも/古今(羇旅)」
ふり-さしがみ【振り差し紙】🔗⭐🔉
ふり-さしがみ 【振り差し紙】
江戸時代,両替店相互の間のみに通用する手形。
ふり-しお【振(り)塩】🔗⭐🔉
ふり-しお ―シホ [0] 【振(り)塩】
〔「ふりじお」とも〕
料理で,材料の上にまんべんなく塩をふること。また,その塩。
ふり-しぼ・る【振(り)絞る】🔗⭐🔉
ふり-しぼ・る [4] 【振(り)絞る】 (動ラ五[四])
ありったけの声や力を出す。「声を―・って応援する」「力を―・って走り抜く」
[可能] ふりしぼれる
ふり-す・てる【振(り)捨てる】🔗⭐🔉
ふり-す・てる [4] 【振(り)捨てる】 (動タ下一)[文]タ下二 ふりす・つ
(1)思い切って捨てる。捨てて顧みない。「未練を―・てる」「自分を―・てた女の名/明暗(漱石)」
(2)神輿(ミコシ)などをかつぎ出し置き去りにする。「神輿をば陣頭に―・て奉り/平家 1」
ふり-だし【振(り)出し・振出】🔗⭐🔉
ふり-だし [0] 【振(り)出し・振出】
(1)振って出すこと。また,振って小さな穴から中身を出すようにした容器。
(2)双六(スゴロク)の出発点。転じて,物事の初め。「交渉が―に戻る」
(3)一連の遍歴の最初。始まり。「牛乳配達を―に転々と職を変えた」
(4)手形・小切手などを発行すること。
(5)「振り出し薬」の略。
(6)口細の小形の容器。茶の湯では,小粒の菓子や香煎(コウセン)を入れる。陶磁器が多い。
ふりだし-ぐすり【振(り)出し薬】🔗⭐🔉
ふりだし-ぐすり [5] 【振(り)出し薬】
生薬を入れた布袋を湯の中で振り動かし,成分をとかし出して飲むもの。煎剤(センザイ)。湯剤。ふりだし。
ふり-だ・す【振(り)出す】🔗⭐🔉
ふり-だ・す [3][0] 【振(り)出す】 (動サ五[四])
(1)容器を振って中にある物を出す。「おみくじを―・す」
(2)振りはじめる。「鈴を―・す」
(3)為替・手形・小切手を発行する。「手形を―・す」
(4)水の中で振って成分などを出す。また,水の中で振って汚れを落とす。「あんまりよごれてゐるから,ざつと―・してもらつて/歌舞伎・四谷怪談」
[可能] ふりだせる
ふり-つけ【振(り)付け・振付】🔗⭐🔉
ふり-つけ [0] 【振(り)付け・振付】
舞踊の所作を考案して演者に教えること。「バレエの―をする」
ふり-つ・ける【振(り)付ける】🔗⭐🔉
ふり-つ・ける [4] 【振(り)付ける】 (動カ下一)[文]カ下二 ふりつ・く
(1)振り付けをする。振りを付ける。「新曲に―・ける」
(2)嫌ってはねつける。ふる。「大きに―・けてやりんした/洒落本・遊子方言」
ふり-つるべ【振り釣瓶】🔗⭐🔉
ふり-つるべ [3] 【振り釣瓶】
桶に縄や竿(サオ)を付け,手で下ろして汲むようにしたもの。
ふり-テン【振り聴】🔗⭐🔉
ふり-テン [0] 【振り聴】
麻雀で聴牌(テンパイ)したとき,上がれるはずの牌をすでに自分で捨ててしまっている状態。
ふり-とば・す【振(り)飛ばす】🔗⭐🔉
ふり-とば・す [4] 【振(り)飛ばす】 (動サ五[四])
振って飛ばす。飛ばす。「水滴を―・す」
[可能] ふりとばせる
ふり-なわ【振(り)縄】🔗⭐🔉
ふり-なわ ―ナハ [0] 【振(り)縄】
巻網・引き網の副漁具。多数の木片をひもで取り付けたロープ。この木が揺れて魚は網に追い込まれる。桂縄(カツラナワ)。
ふり-にげ【振(り)逃げ】🔗⭐🔉
ふり-にげ [0] 【振(り)逃げ】 (名)スル
野球で,一塁に走者がいない,または二死のとき,空振り三振した球を捕手が捕りそこね,打者が一塁に走りこんでセーフになること。
ふり-ぬ・く【振(り)抜く】🔗⭐🔉
ふり-ぬ・く [3] 【振(り)抜く】 (動カ五[四])
バットなどを十分に振る。ふりきる。
[可能] ふりぬける
ふり-ば【振(り)歯】🔗⭐🔉
ふり-ば [0] 【振(り)歯】
⇒あさり(歯振)
ふり-は・う【振り延ふ】🔗⭐🔉
ふり-は・う ―ハフ 【振り延ふ】 (動ハ下二)
(1)わざわざ…する。ことさら…する。「かく―・へ給へるにいかで隠れむとて/宇津保(俊蔭)」「―・エテ行ク/日葡」
→振り延え
(2)のばして振る。「しろたへの袖―・へて人のゆくらむ/古今(春上)」
ふり-はえ【振り延へ】🔗⭐🔉
ふり-はえ ―ハヘ 【振り延へ】 (副)
〔動詞「ふりはう」の連用形から〕
わざわざ。ことさら。「久しう訪れ給はざりけるをおぼし出でて―つかはしたりければ/源氏(若紫)」
ふり-はな・す【振(り)放す】🔗⭐🔉
ふり-はな・す [4] 【振(り)放す】 (動サ五[四])
(1)しがみ付いている物を,体を振って離れさせる。「すがりつく手を―・す」
(2)追いついてくる者を追いつかせずに引き離す。「二位を―・してゴール-インする」
[可能] ふりはなせる
ふり-はな・つ【振(り)放つ】🔗⭐🔉
ふり-はな・つ [4] 【振(り)放つ】 (動タ五[四])
「振り放す」に同じ。「母親の止めるのを―・つて/田舎教師(花袋)」
ふり-はば【振(り)幅】🔗⭐🔉
ふり-はば [0][4] 【振(り)幅】
振動している物体の振動の幅。
→振幅(シンプク)
ふり-はら・う【振(り)払う】🔗⭐🔉
ふり-はら・う ―ハラフ [4] 【振(り)払う】 (動ワ五[ハ四])
手や体を振って,払いのける。「差し出した手を―・う」
[可能] ふりはらえる
ふり-びしゃ【振(り)飛車】🔗⭐🔉
ふり-びしゃ [0] 【振(り)飛車】
将棋で,飛車を横に動かして駒組みをする戦法。移した位置によって中(ナカ)飛車・三間飛車・向かい飛車などという。
⇔居(イ)飛車
ふり-ふ【振(り)歩】🔗⭐🔉
ふり-ふ [0] 【振(り)歩】
「振り駒(ゴマ)」に同じ。
ぶり-ぶり【振り振り】🔗⭐🔉
ぶり-ぶり 【振り振り】
■一■ [0] (名)
(1)近世の玩具の一。木製の,槌(ツチ)の形をしたもの。毬(マリ)を打つとも,両側に車をつけて引いて遊んだともいう。のちには正月の飾り物となった。玉ぶりぶり。「正月遊びの―の玉を投げて/浮世草子・風流曲三味線」
(2)直径約10センチメートルの円形の的。二筋の綱で串(クシ)につける。
(3)太刀の柄の下げ緒のおもりの金物。
■二■ [1] (副)スル
小刻みに揺れるさま。また,震動する音を表す語。「先陣越された宇治川に膝―の流れ武者/浄瑠璃・鑓の権三(上)」
振り振り■一■(1)
 [図]
[図]
 [図]
[図]
ぶりぶり-ぎっちょう【振り振り毬杖】🔗⭐🔉
ぶりぶり-ぎっちょう ―チヤウ [5] 【振り振り毬杖】
「ぶりぶり{■一■(1)}」に同じ。
ふり-ほど・く【振り解く】🔗⭐🔉
ふり-ほど・く [4] 【振り解く】 (動カ五[四])
もつれたりからんだりしているものを,振ってほどく。「綱を―・く」
[可能] ふりほどける
ふり-ま・く【振り撒く】🔗⭐🔉
ふり-ま・く [3] 【振り撒く】 (動カ五[四])
(1)あたり一面にまきちらす。「水を―・く」
(2)惜しまずに与える。「愛敬を―・く」
[可能] ふりまける
ふり-まわし【振り回し】🔗⭐🔉
ふり-まわし ―マハシ [0] 【振り回し】
(1)振り回すこと。「太刀の―」
(2)やり繰り。繰り回し。「心易き妾をかくまへ置けるといふ,それは手前も―もなる人の事/浮世草子・胸算用 4」
ふり-まわ・す【振(り)回す】🔗⭐🔉
ふり-まわ・す ―マハス [4][3] 【振(り)回す】 (動サ五[四])
(1)手や,手に持った物を大きく振り動かす。また,乱暴に振り動かす。「棒を―・して暴れる」
(2)得意げに持ち出す。ひけらかす。「生半可な知識を―・す」「肩書を―・す」「威光を―・す」
(3)人を思うままに動かす。「子供に―・される」「にせ情報に―・される」
[可能] ふりまわせる
ふり-みせ【振(り)見せ】🔗⭐🔉
ふり-みせ [0] 【振(り)見せ】
舞踏などで,振付師が自分で工夫した振り付けを演じて見せ,関係者の意見を聞くこと。
ふり-む・く【振(り)向く】🔗⭐🔉
ふり-む・く [3] 【振(り)向く】
■一■ (動カ五[四])
顔や上体を回して後ろを見る。通り過ぎたものなどを,関心を持ってよく見る。振りかえる。「物音に―・く」「思わず―・くような美人」
[可能] ふりむける
■二■ (動カ下二)
⇒ふりむける
ふりむ・ける【振(り)向ける】🔗⭐🔉
ふりむ・ける [4] 【振(り)向ける】 (動カ下一)[文]カ下二 ふりむ・く
(1)動かして,ある方向に向かせる。「頭を右に―・ける」
(2)別の目的・用途に変える。「車を一台送迎用に―・ける」
ふり-わけ【振(り)分け】🔗⭐🔉
ふり-わけ [0] 【振(り)分け】
(1)ふりわけること。また,ふりわけたもの。
(2)二つの荷物を紐(ヒモ)でつなぎ,前後に分けて肩にかけること。また,その荷物。「―にしてかつぐ」
(3)中間の地点。「―の所なれば,中の町といへるよし/滑稽本・膝栗毛 3」
(4)「振り分け髪」に同じ。「みぐし―にて/宇津保(蔵開上)」
(5)近世,若い男の髪形の一。前髪を左右に分け,末端を髻(モトドリ)の背に出す。[守貞漫稿]
振り分け(2)
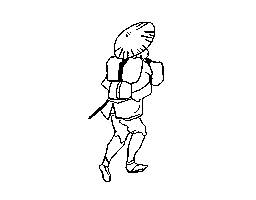 [図]
[図]
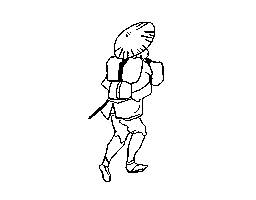 [図]
[図]
ふりわけ-がみ【振(り)分け髪】🔗⭐🔉
ふりわけ-がみ [4] 【振(り)分け髪】
二,三歳から八歳頃の男女の髪形の一。肩のあたりで切りそろえ,左右に分けて垂らした髪。
振り分け髪
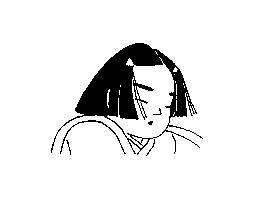 [図]
[図]
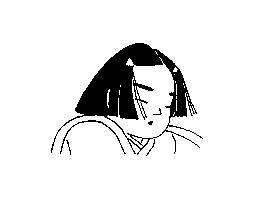 [図]
[図]
ふりわけ-にもつ【振(り)分け荷物】🔗⭐🔉
ふりわけ-にもつ [5] 【振(り)分け荷物】
振り分けにした荷物。
ふり-わ・ける【振(り)分ける】🔗⭐🔉
ふり-わ・ける [4] 【振(り)分ける】 (動カ下一)[文]カ下二 ふりわ・く
(1)二つに分ける。二方向に分ける。「荷物を前後に―・ける」
(2)いくつかに分ける。「三人に仕事を―・ける」
ふりあげる【振り上げる】(和英)🔗⭐🔉
ふりあげる【振り上げる】
raise.→英和
ふりかえる【振り返る】(和英)🔗⭐🔉
ふりかえる【振り返る】
look back;turn one's head.
ふりかける【振り掛ける】(和英)🔗⭐🔉
ふりかける【振り掛ける】
sprinkle.→英和
ふりかた【振り方】(和英)🔗⭐🔉
ふりかた【振り方】
[身の](a plan for) one's future;how to dispose of oneself.
ふりがな【振り仮名をつける】(和英)🔗⭐🔉
ふりがな【振り仮名をつける】
give[print]kana (along with Chinese characters).
ふりかぶる【振りかぶる】(和英)🔗⭐🔉
ふりかぶる【振りかぶる】
holdhigh;raise.→英和
ふりきる【振り切る】(和英)🔗⭐🔉
ふりきる【振り切る】
⇒振り放す.
ふりこむ【振り込む】(和英)🔗⭐🔉
ふりこむ【振り込む】
transfer<100,000 yen>to.
ふりはなす【振り放す】(和英)🔗⭐🔉
ふりはなす【振り放す】
shake off.
ふりはらう【振り払う】(和英)🔗⭐🔉
ふりはらう【振り払う】
⇒振り放す.
ふりむく【振り向く】(和英)🔗⭐🔉
ふりむく【振り向く】
turn;→英和
look back.
大辞林に「振り」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む