複数辞典一括検索+![]()
![]()
え【枝】🔗⭐🔉
え [0] 【枝】
えだ。「梅が―」
えだ【枝】🔗⭐🔉
えだ 【枝】
■一■ [0] (名)
(1)植物の主幹から分かれた茎。側芽や不定芽の発達したもの。「―が茂る」
(2)ものの本体・本筋から分かれ出たもの。「本筋からはずれた―の話」
(3)からだの手や足。四肢。「―を引き闕(カ)きて/古事記(中訓)」
(4)一族。子孫。「北家のすゑ,いまに―ひろごり給へり/大鏡(道長)」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)木の枝を数えるのに用いる。「一―の梅」
(2)細長い物を数えるのに用いる。「長持三十―/平家 10」
(3)〔昔,贈り物を木の枝に添えて差し出したことから〕
贈り物を数えるのに用いる。「雉一―奉らせ給ふ/源氏(行幸)」
えだ=の雪🔗⭐🔉
――の雪
〔晋の孫康が,枝に積もった雪を灯火の代わりにして書を読んだという「蒙求」の故事から〕
苦学すること。「窓の蛍を睦び,―を馴らし給ふ心ざし/源氏(乙女)」
えだ=を連(ツラ)・ぬ🔗⭐🔉
――を連(ツラ)・ぬ
〔「連枝」の訓読みから〕
兄弟の仲が親密であること。また,仲がよいことのたとえ。「頼朝も,ついには靡く,青柳の―・ぬる御契り/謡曲・船弁慶」
えだ=を鳴らさ ず🔗⭐🔉
ず🔗⭐🔉
――を鳴らさ ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「―
ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「― ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
 ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「―
ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「― ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
えだ-うち【枝打ち】🔗⭐🔉
えだ-うち [0] 【枝打ち】 (名)スル
発育を促したり,節のないよい材を得るために樹木の下枝を切りはらうこと。枝下ろし。「庭木を―する」
えだ-うつり【枝移り】🔗⭐🔉
えだ-うつり [0] 【枝移り】 (名)スル
鳥などが枝から枝へと移ること。
えだ-おとり【枝劣り】🔗⭐🔉
えだ-おとり 【枝劣り】
〔幹より枝の方が劣っていることから〕
父祖より子孫の劣っていること。「もと見れば高き桂も今日よりや―すと人のいふらむ/宇津保(祭の使)」
えだ-おろし【枝下ろし】🔗⭐🔉
えだ-おろし [3] 【枝下ろし】 (名)スル
「枝打(エダウ)ち」に同じ。
えだ-がみ【枝神・裔神】🔗⭐🔉
えだ-がみ 【枝神・裔神】
末社に祀(マツ)られている神。
えだ-がわ【枝川】🔗⭐🔉
えだ-がわ ―ガハ [0] 【枝川】
(本流に対して)支流。
えだ-がわり【枝変(わ)り】🔗⭐🔉
えだ-がわり ―ガハリ [3] 【枝変(わ)り】
植物体の一部の枝のみが他と異なる遺伝形質を示す現象。芽の始原細胞における体細胞遺伝子の突然変異によって起こる。長十郎ナシから二十世紀ナシを得たのがこの例である。芽条変異。
えだ-ぎ【枝木】🔗⭐🔉
えだ-ぎ [0] 【枝木】
木の枝。
えだきり-ばさみ【枝切り鋏】🔗⭐🔉
えだきり-ばさみ [5] 【枝切り鋏】
樹木の剪定(センテイ)に用いる鋏。
えだ-ぐり【枝栗】🔗⭐🔉
えだ-ぐり [0] 【枝栗】
枝のついたまま折り取った栗の実。
えだ-げ【枝毛】🔗⭐🔉
えだ-げ [0] 【枝毛】
毛髪の先が枝のように裂けたもの。
えだ-ざし【枝差し】🔗⭐🔉
えだ-ざし 【枝差し】
枝振り。「竜胆(リンドウ)は,―などもむつかしけれど/枕草子 67」
えだ-ざし【枝挿し】🔗⭐🔉
えだ-ざし [0] 【枝挿し】
挿し木の一。枝を挿し穂として用いるもの。
えだ-さんご【枝珊瑚】🔗⭐🔉
えだ-さんご [3] 【枝珊瑚】
枝の形をしたサンゴ。
えだ-した【枝下】🔗⭐🔉
えだ-した [0] 【枝下】
地面から力枝までの幹の部分。
えだ-しゃく【枝尺】🔗⭐🔉
えだ-しゃく [0] 【枝尺】
シャクガ科エダシャク亜科のガの総称。後ろばねの第五脈を欠くことが特徴。幼虫はシャクトリムシで,広葉樹の葉を食う。エダシャクトリ。エダシャクガ。
えだ-じろ【枝城】🔗⭐🔉
えだ-じろ [0] 【枝城】
(本城を根城と呼ぶのに対して)出城(デジロ)。支城。
えだ-ずみ【枝炭】🔗⭐🔉
えだ-ずみ [0] 【枝炭】
ツツジなどの細い木の枝を焼いてつくった炭。火のおこりを早くするために茶道で用いる。上に胡粉(ゴフン)を塗った白炭(シロズミ)と,塗らない山色(ヤマイロ)の二種がある。
えだ-ちょうし【枝調子】🔗⭐🔉
えだ-ちょうし ―テウシ [3] 【枝調子】
雅楽で,基本の六調子に対して,主音は同じで音階の違う調子。壱越(イチコツ)調に対しての沙陀(サダ)調,黄鐘(オウシキ)調に対する水調など五種がある。
えだ-づか【枝束】🔗⭐🔉
えだ-づか [2][0] 【枝束】
小屋組で,真束(シンヅカ)と陸梁(ロクバリ)の接点から斜めに出て,合掌を支えている方杖(ホウヅエ)。小屋方杖。
えだ-つき【枝付き】🔗⭐🔉
えだ-つき [0] 【枝付き】
枝のつき具合。枝ぶり。
えだ-つぎ【枝接ぎ】🔗⭐🔉
えだ-ながれ【枝流れ】🔗⭐🔉
えだ-ながれ [3] 【枝流れ】
支流。分流。枝川。
えだ-にく【枝肉】🔗⭐🔉
えだ-にく [0] 【枝肉】
家畜を屠殺(トサツ)後,放血して皮をはぎ,頭部・内臓と四肢の先端を取り除いた骨付きの肉。普通,脊柱に添って左右に二分したものをいう。
えだ-の-しゅじつ【枝の主日】🔗⭐🔉
えだ-の-しゅじつ 【枝の主日】
⇒棕櫚(シユロ)の主日(シユジツ)
えだ-は【枝葉】🔗⭐🔉
えだ-は [0] 【枝葉】
(1)枝と葉。
(2)物事の本質的でない,ささいな部分。枝葉末節。「―にこだわる」
(3)本家から分かれた者。また,家来・従者。「―の者は追つての御沙汰/人情本・梅児誉美(後)」
えだ-はらい【枝払い】🔗⭐🔉
えだ-はらい ―ハラヒ [3] 【枝払い】
伐採した木の枝を幹から切り離すこと。
→枝打ち
えだ-はり【枝張(り)】🔗⭐🔉
えだ-はり [0] 【枝張(り)】
樹木の枝の広がり具合。
えだ-ばり【枝針】🔗⭐🔉
えだ-ばり [0] 【枝針】
釣りで,胴突き仕掛けなどのように幹糸の途中から出してある針。
えだ-ばん【枝番】🔗⭐🔉
えだ-ばん [0] 【枝番】
〔「枝番号」の略〕
分類や順番を示す番号を,さらに細かく分けるときに付ける番号。
えだ-ぶり【枝振り】🔗⭐🔉
えだ-ぶり [0] 【枝振り】
枝の伸びたありさま。枝のかっこう。えださし。「―のいい松」
えだ-まめ【枝豆】🔗⭐🔉
えだ-まめ [0] 【枝豆】
まだ熟していない青い大豆を枝ごととったもの。さやのままゆでて食べる。[季]秋。
えだ-みち【枝道・岐路】🔗⭐🔉
えだ-みち [0] 【枝道・岐路】
(1)本道から分かれた道。横道。
(2)物事の本筋からはずれたところ。「話が―にそれる」
えだ-みや【枝宮】🔗⭐🔉
えだ-みや [0] 【枝宮】
「末社(マツシヤ)」に同じ。
えだ-むら【枝村】🔗⭐🔉
えだ-むら [0] 【枝村】
江戸時代,開拓などによって本村から分立した村。元の村は親村・親郷という。
えだ-わかれ【枝分かれ】🔗⭐🔉
えだ-わかれ [3] 【枝分かれ】 (名)スル
(1)木の枝が分かれること。分枝。
(2)一本の物が途中から何本かに分かれること。「何本もの支線が―する」
し【枝】🔗⭐🔉
し 【枝】 (接尾)
助数詞。細長い物を数えるのに用いる。「長刀一―」
し-いん【子院・支院・枝院】🔗⭐🔉
し-いん ― ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
 ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
しおり【栞・枝折(り)】🔗⭐🔉
しおり シヲリ [0] 【栞・枝折(り)】
〔動詞「枝折る」の連用形から〕
(1)本の読みかけのところに挟んでしるしとする,細幅の紙片やひも。
(2)案内書。手引き。「旅の―」「英文学研究の―」
(3)山道などで,木の枝を折っておいて道しるべとすること。また,その道しるべ。「―を尋ねつつも登り給ひなまし/今昔 28」
(4)くるわ。城郭。「三の丸―ぎはまで追入りしかども/太閤記」
(5)「枝折り戸」の略。
しおり-がき【枝折(り)垣】🔗⭐🔉
しおり-がき シヲリ― [3] 【枝折(り)垣】
竹または木の枝を折ったもので作った粗末な垣。茶室の庭などに用いる。
しおり-ど【枝折(り)戸】🔗⭐🔉
しおり-ど シヲリ― [3] 【枝折(り)戸】
(1)竹や木の枝を折って作った簡素な開き戸。
(2)露地の小門の一。丸竹の枠に割り竹を両面から菱目(ヒシメ)に組み付けたもの。菱目の交差部分は蕨縄(ワラビナワ)で結い,門柱には丸太を用いる。
枝折り戸(2)
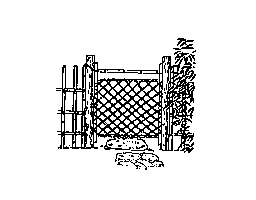 [図]
[図]
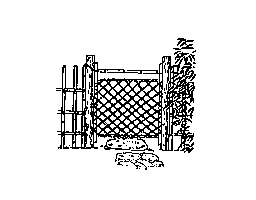 [図]
[図]
し-お・る【枝折る】🔗⭐🔉
し-お・る ―ヲル 【枝折る】 (動ラ四)
〔「撓(シオ)る」と同源。「枝折る」は当て字か〕
道しるべのため,木の枝などを折る。「世の憂さに―・らで入りし奥山に/浜松中納言 1」
しがい-だるき【枝外垂木】🔗⭐🔉
しがい-だるき シグワイ― [4] 【枝外垂木】
屋根の妻の壁面に用いる,棟木から丸桁にかけて打たれている急勾配の化粧垂木。追っ立て垂木。
し-かん【枝幹】🔗⭐🔉
し-かん [0] 【枝幹】
(1)枝と幹。
(2)末と本(モト)。
し-じょう【枝条】🔗⭐🔉
し-じょう ―デウ [0] 【枝条】
木の枝。
し-ぞく【支族・枝族】🔗⭐🔉
し-ぞく [1] 【支族・枝族】
分かれ出た血族。分家。別家。
しだれ【枝垂れ・垂れ】🔗⭐🔉
しだれ [3] 【枝垂れ・垂れ】
〔下二段動詞「垂(シダ)る」の連用形から〕
たれ下がること。しだり。
しだれ-うめ【枝垂れ梅】🔗⭐🔉
しだれ-うめ [3] 【枝垂れ梅】
ウメの一品種。枝のたれ下がる梅。
しだれ-ざくら【枝垂れ桜】🔗⭐🔉
しだれ-ざくら [4] 【枝垂れ桜】
バラ科の落葉高木。エドヒガンの一変種で,枝のたれ下がるもの。花は普通,淡紅白色五弁。糸桜。[季]春。
しだれ-ひがん【枝垂れ彼岸】🔗⭐🔉
しだれ-ひがん [4] 【枝垂れ彼岸】
シダレザクラの異名。
しだれ-もも【枝垂れ桃】🔗⭐🔉
しだれ-もも [3] 【枝垂れ桃】
モモの園芸品種。枝のたれ下がるもので,主として観賞用。シダリモモ。
しだれ-やなぎ【枝垂れ柳】🔗⭐🔉
しだれ-やなぎ [4] 【枝垂れ柳】
ヤナギ科の落葉高木。中国原産。街路樹・庭園樹として広く植えられる。枝は細長く下垂し,広線形の葉を互生。雌雄異株。早春,黄緑色の花穂を葉腋につける。種子には白い綿毛がある。普通ヤナギというと本種をさす。糸柳。シダリヤナギ。
し-とう【枝頭】🔗⭐🔉
し-とう [0] 【枝頭】
枝の先端。
し-よう【枝葉】🔗⭐🔉
し-よう ―エフ [0][1] 【枝葉】
(1)木の枝と葉。えだは。
(2)本筋からはずれた部分。物事の主要でない部分。
(3)家系・流派などで主流から分かれ出た一派。
しよう-まっせつ【枝葉末節】🔗⭐🔉
しよう-まっせつ ―エフ― [1][0] 【枝葉末節】
主要でない部分。細かい部分。「―にこだわる」
し-りん【支輪・枝輪】🔗⭐🔉
し-りん [0] 【支輪・枝輪】
社寺建築で,折り上げ天井を支える湾曲した竪木(タテギ)。
支輪
 [図]
[図]
 [図]
[図]
よ【枝】🔗⭐🔉
よ 【枝】
えだ。一説に,花びらの意ともいう。「この花の一―のうちは百種の/万葉 1457」
えだぶり【枝ぶりのよい松】(和英)🔗⭐🔉
えだぶり【枝ぶりのよい松】
a shapely pine tree.
えだまめ【枝豆】(和英)🔗⭐🔉
えだまめ【枝豆】
green soybeans.
しおりど【枝折戸】(和英)🔗⭐🔉
しおりど【枝折戸】
a wicket made of branches and twigs.
しだれ【枝垂柳】(和英)🔗⭐🔉
しだれ【枝垂柳】
a weeping willow.枝垂桜 a drooping cherry tree.
しだれる【枝垂れる】(和英)🔗⭐🔉
しだれる【枝垂れる】
droop;→英和
hang down.
しよう【枝葉の】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「枝」で始まるの検索結果 1-71。