複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (64)
え【枝】🔗⭐🔉
え【枝】
えだ。万葉集17「神さびて立てる栂つがの木幹もとも―も」
えだ【枝】🔗⭐🔉
えだ‐うち【枝打ち】🔗⭐🔉
えだ‐うち【枝打ち】
樹木の枯枝・下枝などを切り落とすこと。主に、節のない材を得るために行う。枝下ろし。打ち枝。
えだ‐うつり【枝移り】🔗⭐🔉
えだ‐うつり【枝移り】
鳥が枝から枝へと飛び移ること。
えだ‐えだ【枝枝】🔗⭐🔉
えだ‐えだ【枝枝】
①多くの枝。
②兄弟・親族・子孫など一族の人々。栄華物語紫野「―栄え出でさせ給ふを」
えだ‐おうぎ【枝扇】‥アフギ🔗⭐🔉
えだ‐おうぎ【枝扇】‥アフギ
葉のついたままの枝を扇に代用したもの。枕草子12「なしの木…もとより打ち切りて定澄僧都の―にせばや」
えだ‐おとり【枝劣り】🔗⭐🔉
えだ‐おとり【枝劣り】
(幹から出た枝が幹よりは劣っていることから)父祖より子孫の劣っていること。宇津保物語祭使「今日よりや―すと人のいふらむ」
えだ‐おろし【枝下ろし】🔗⭐🔉
えだ‐おろし【枝下ろし】
(→)「枝打ち」に同じ。
えだ‐かき【枝掻き】🔗⭐🔉
えだ‐かき【枝掻き】
ウルシの枝木から漆を採取すること。
えだ‐がき【枝柿】🔗⭐🔉
えだ‐がき【枝柿】
①枝のついたままの柿の実。好色五人女2「唐瓜―かざる事のをかし」
②つるし柿。誹風柳多留15「―の種を出すのに目がすわり」
えだ‐がみ【枝神・裔神】🔗⭐🔉
えだ‐がみ【枝神・裔神】
末社の神。
えだ‐かもじ【枝髢】🔗⭐🔉
えだ‐かもじ【枝髢】
髪を長く見せるためにつぎ足す髢。
えだ‐がわ【枝川】‥ガハ🔗⭐🔉
えだ‐がわ【枝川】‥ガハ
本流に対して、支流。えだながれ。
えだ‐がわり【枝変り】‥ガハリ🔗⭐🔉
えだ‐がわり【枝変り】‥ガハリ
枝など植物体の一部分が母体と変わった形質になること。花の色変り、葉の斑入りと同様、体細胞突然変異の一種。その部分の種子または接穂はその変異形質を遺伝する。これを利用して果樹などの品種改良を行う。温州蜜柑から早生温州の生じたのは、その例。芽条変異。
えだ‐ぐり【枝栗】🔗⭐🔉
えだ‐ぐり【枝栗】
枝のついた栗の実。
えだ‐げ【枝毛】🔗⭐🔉
えだ‐げ【枝毛】
毛髪の先が枝のように分岐したもの。
えだ‐ごう【枝郷】‥ガウ🔗⭐🔉
えだ‐ごう【枝郷】‥ガウ
中世・近世、開発により新しくできた村の称。元の村である本郷(元郷)に対していう。枝村。
えだ‐さし【枝差】🔗⭐🔉
えだ‐さし【枝差】
草木の枝のさし出たようす。えだぶり。宇津保物語楼上下「―をかしう、めづらかなる木ども」
えだ‐ざし【枝挿し】🔗⭐🔉
えだ‐ざし【枝挿し】
枝を取って挿木とするもの。
えだ‐さんご【枝珊瑚】🔗⭐🔉
えだ‐さんご【枝珊瑚】
木の枝の形をした珊瑚。
えだ‐した【枝下】🔗⭐🔉
えだ‐した【枝下】
樹木の最も下の枝から地表までの長さ。
えだ‐しゃくとり【枝尺蠖】🔗⭐🔉
えだ‐しゃくとり【枝尺蠖】
(→)「しゃくとりむし」に同じ。
えだ‐じろ【枝城】🔗⭐🔉
えだ‐じろ【枝城】
根城ねじろの外に築いた城。出城。
えだ‐ずみ【枝炭】🔗⭐🔉
えだ‐ずみ【枝炭】
茶道で火を起こすのに用いる炭。ツツジ・クヌギなどの小枝を焼いてつくり、上に石灰や胡粉を塗ったものを白炭しろずみ、塗らないものを山色やまいろという。よこやまずみ。
えだ‐ぞり【枝橇】🔗⭐🔉
えだ‐ぞり【枝橇】
薪炭や人を乗せて山上から下ろす、数本の樹枝を結び合わせたそり。ずま。
えだ‐ちょうし【枝調子】‥テウ‥🔗⭐🔉
えだ‐ちょうし【枝調子】‥テウ‥
雅楽で、主要な調子(主おも調子)から派生した副次的な調子。主音は同じで、音階が違うもの。黄鐘おうしき調の枝調子は水調すいじょう、壱越いちこつ調の枝調子は沙陀さだ調。
えだ‐づか【枝束】🔗⭐🔉
えだ‐づか【枝束】
〔建〕小屋組における斜めの束。陸梁ろくばりと合掌との間をつなぐ部材。方杖ほうづえ。
えだ‐つぎ【枝接ぎ】🔗⭐🔉
えだ‐ながれ【枝流れ】🔗⭐🔉
えだ‐ながれ【枝流れ】
支流。分流。えだがわ。
えだ‐にく【枝肉】🔗⭐🔉
えだ‐にく【枝肉】
出荷用に処理された食肉の形態。皮をはぎ、内臓・頭・尾・肢端をとり去った、骨つきの肉。通常、正中線にそって左右に二等分する。
えだ‐の‐ゆき【枝の雪】🔗⭐🔉
えだ‐の‐ゆき【枝の雪】
(晋の孫康の故事から)苦学すること。学問にいそしむこと。窓の雪。源氏物語少女「窓の蛍をむつび、―を馴らし給ふ心ざし」→蛍雪けいせつ
えだ‐は【枝葉】🔗⭐🔉
えだ‐は【枝葉】
①枝と葉。
②物事の本筋でないこと。主要でない部分。「―の問題にかかずらう」
えだ‐はらい【枝払い】‥ハラヒ🔗⭐🔉
えだ‐はらい【枝払い】‥ハラヒ
鉈なたなどで枝のつけ根で切り離すこと。枝打ち。
えだ‐ばん【枝番】🔗⭐🔉
えだ‐ばん【枝番】
(枝番号の略)番号を付けて順番・分類を定めた後に、中間に挿入したり、下位を更に分類したりする場合に付ける番号。
えだ‐ひげむし【枝髭虫】🔗⭐🔉
えだ‐ひげむし【枝髭虫】
エダヒゲムシ綱の節足動物の総称。多足類の一群。体は頭部・胴節・尾節から成り、6個の背板と9対の歩脚を持つ。体長0.5ミリメートル、触角が枝分れしている。湿った落葉の下や土の中に生息し、菌類や腐った動植物を食う。世界中に分布し、日本には約100種。少脚類。ヤスデモドキ。
えだ‐ふね【枝船】🔗⭐🔉
えだ‐ふね【枝船】
本船もとぶねにつき従う小船。供船。
えだ‐ぶり【枝振り】🔗⭐🔉
えだ‐ぶり【枝振り】
枝の出ぐあい、かっこう。えださし。「―の良い松」
えだ‐ぼね【枝骨・肢骨】🔗⭐🔉
えだ‐ぼね【枝骨・肢骨】
手足の骨。また、手足。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―もいでくれうと立ち上がれば」
えだ‐まめ【枝豆】🔗⭐🔉
えだ‐まめ【枝豆】
大豆の未熟なうちに茎ごと切り取ったもの。さやのままゆでて食用とする。旧暦九月十三夜の月に供える。〈[季]秋〉
枝豆
撮影:関戸 勇


えだ‐みち【枝道・岐路】🔗⭐🔉
えだ‐みち【枝道・岐路】
①本道から分かれ出た道。よこみち。
②本筋からはずれたところ。えだは。「話が―に入る」
えだ‐もの【枝物】🔗⭐🔉
えだ‐もの【枝物】
華道で、草本そうほんのものに対して木本もくほんの材料の総称。木物きもの。
えだ‐わかれ【枝分れ】🔗⭐🔉
○枝を交わすえだをかわす🔗⭐🔉
○枝を交わすえだをかわす
(「連理の枝」から)二つの枝が一つになって木目が通る。男女の契りの深いことのたとえ。「枝を連ぬ」とも。源氏物語桐壺「羽を並べ枝を交はさむと契らせ給ひしに」
⇒えだ【枝】
○枝を鳴らさずえだをならさず🔗⭐🔉
○枝を鳴らさずえだをならさず
[論衡「風条えだを鳴らさず、雨塊つちくれを破らず」]太平の世には樹の枝を鳴らすほどの風も吹かない。天下太平なさまをいう。謡曲、高砂「枝を鳴らさぬ御代なれや」
⇒えだ【枝】
エタン【Äthan ドイツ・ethane イギリス】
分子式C2H6 パラフィン炭化水素の一つ。天然ガス・石炭ガス・石油分解ガスなどの中に含まれる無色の気体。性状はメタンに似る。
えだん‐にりゅう【恵檀二流】ヱ‥リウ
〔仏〕日本天台宗の恵心流と檀那流の二流派。良源門下の恵心院源信と檀那院覚運が派祖で、いずれも師から弟子に秘密に伝えられる口伝法門を重んずる。
エチェガライ【José Echegaray】
スペインの劇作家。代表作「恐ろしき媒なかだち」。ノーベル賞。(1832〜1916)
エチェガライ
提供:ullstein bild/APL
 エチオピア【Ethiopia】
アフリカ北東部の連邦民主共和国。「シバの女王の国」と称して世界最古の王国とされ、4世紀頃からキリスト教国となる。1936年イタリアに征服されたが、41年独立を回復。75年帝政を廃止。面積110万4000平方キロメートル。人口7107万(2004)。首都アジス‐アベバ。旧称アビシニア。→アフリカ(図)。
⇒エチオピア‐く【エチオピア区】
⇒エチオピア‐ご【エチオピア語】
⇒エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】
エチオピア‐く【エチオピア区】
動物地理学上の区分の一つ。アフリカ大陸のサハラ砂漠より南の地域。キリン・カバ・ハゲワシなどが固有種で、爬虫類の多いことが特徴。東洋区と共通・近縁種も多いことから、現在では両者を合わせて旧熱帯区とし、それぞれを亜区としている。→動物地理区(図)。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐ご【エチオピア語】
(Ethiopian)
①古代エチオピア語。ゲーズ語とも呼ばれ、4世紀頃の碑文のほか、キリスト教関係の翻訳など多くの文献をもつ。セム語派中の南西セム語群に属する。
②エチオピアで話されている80以上の言語の総称。公用語のアムハラ語のほか、ティグリニャ語が主要な言語。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】‥カウ‥
(Ethiopian Plateau)アフリカ北東部、エチオピアの主要部を占める高原。平均標高約2300メートルで、畑作が行われ都市が発達。別称、アビシニア高原。
エチオピア高原
撮影:小松義夫
エチオピア【Ethiopia】
アフリカ北東部の連邦民主共和国。「シバの女王の国」と称して世界最古の王国とされ、4世紀頃からキリスト教国となる。1936年イタリアに征服されたが、41年独立を回復。75年帝政を廃止。面積110万4000平方キロメートル。人口7107万(2004)。首都アジス‐アベバ。旧称アビシニア。→アフリカ(図)。
⇒エチオピア‐く【エチオピア区】
⇒エチオピア‐ご【エチオピア語】
⇒エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】
エチオピア‐く【エチオピア区】
動物地理学上の区分の一つ。アフリカ大陸のサハラ砂漠より南の地域。キリン・カバ・ハゲワシなどが固有種で、爬虫類の多いことが特徴。東洋区と共通・近縁種も多いことから、現在では両者を合わせて旧熱帯区とし、それぞれを亜区としている。→動物地理区(図)。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐ご【エチオピア語】
(Ethiopian)
①古代エチオピア語。ゲーズ語とも呼ばれ、4世紀頃の碑文のほか、キリスト教関係の翻訳など多くの文献をもつ。セム語派中の南西セム語群に属する。
②エチオピアで話されている80以上の言語の総称。公用語のアムハラ語のほか、ティグリニャ語が主要な言語。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】‥カウ‥
(Ethiopian Plateau)アフリカ北東部、エチオピアの主要部を占める高原。平均標高約2300メートルで、畑作が行われ都市が発達。別称、アビシニア高原。
エチオピア高原
撮影:小松義夫
 ⇒エチオピア【Ethiopia】
エチカ【Ethica】
(「倫理学」の意)スピノザの主著。1675年頃完成。77年刊行。幾何学の秩序にしたがって論証するという仕方で、形而上学、精神と認識、感情、倫理学、人間の自由と至福などの広い領域を体系的に論じている。
えちかわ‐や【越川屋】ヱチカハ‥
江戸上野池之端仲町にあった袋物屋。
エチケット【etiquette】
①礼儀。作法。礼法。ベルツ、ベルツの日記「日本では西洋人の間で…礼式エチケットがあまり厳格に守られておらず」。「食卓での―」「―に反する」
②ワインの瓶のラベル。
えち‐ご【越期】ヱチ‥
ある時期を越えて長く続くこと。手遅れになること。おつご。狂歌咄「さまざま薬を用ゆれども落ちず。後には―になり」
えちご【越後】ヱチ‥
旧国名。今の新潟県の大部分。古名、こしのみちのしり。
⇒えちご‐かたびら【越後帷子】
⇒えちご‐さらし【越後晒】
⇒えちご‐じし【越後獅子】
⇒えちご‐じょうふ【越後上布】
⇒えちご‐ちぢみ【越後縮】
⇒えちご‐ぬの【越後布】
⇒えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】
⇒えちご‐ふで【越後筆】
⇒えちご‐へいや【越後平野】
⇒えちご‐や【越後屋】
⇒えちご‐ゆざわ【越後湯沢】
⇒えちご‐りゅう【越後流】
えちご‐かたびら【越後帷子】ヱチ‥
越後国小千谷おぢやから産出する上布じょうふまたは縮ちぢみのかたびら。→越後上布→越後縮ちぢみ。
⇒えちご【越後】
えちご‐さらし【越後晒】ヱチ‥
(→)越後上布に同じ。好色一代男3「二布は―、赤染にして」
⇒えちご【越後】
えちご‐じし【越後獅子】ヱチ‥
①越後国西蒲原郡の神社の里神楽の獅子舞。
②越後国西蒲原郡月潟地方から出る獅子舞。子供が小さい獅子頭をかぶり、身をそらせ、逆立ちで歩くなどの芸をしながら、銭を乞いあるく。蒲原獅子。角兵衛獅子。
③地歌。2を題材とする。天明(1781〜1789)頃、峰崎勾当作曲。箏の手付には市浦検校作曲と八重崎検校作曲の2曲がある。
④歌舞伎舞踊。長唄。七変化舞踊「遅桜手爾葉七字おそざくらてにはのななもじ」の一部。篠田金次作詞、9世杵屋六左衛門作曲。1811年(文化8)初演。地歌を取り入れたもので、越後の角兵衛獅子が浜唄・おけさ踊り・布晒ぬのざらしなどの諸芸を見せる。
⇒えちご【越後】
えちご‐じょうふ【越後上布】ヱチ‥ジヤウ‥
江戸時代、越後国小千谷おぢや付近から苧からむしの繊維を用いて織り出した上質な麻織物の総称。雪晒さらしに特徴がある。越後晒。
⇒えちご【越後】
えちご‐ちぢみ【越後縮】ヱチ‥
越後国小千谷おぢや地方から出す縮。苧からむしで織った夏着尺きじゃく。おぢやちぢみ。越後布。
⇒えちご【越後】
えちご‐ぬの【越後布】ヱチ‥
(→)越後縮ちぢみに同じ。
⇒えちご【越後】
えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】ヱチ‥
越後地方に伝承された七つの不思議な現象。臭水くそうず(石油。柄目木がらめきの火など)・鎌鼬かまいたち・波の題目・逆さ竹・八房梅やつぶさうめ・赤坊主八滝・弘智法師遺骸ほか諸説ある。
⇒えちご【越後】
えちご‐ふで【越後筆】ヱチ‥
越後村松藩内などで製作した筆。のち見附市に移る。
⇒えちご【越後】
えちご‐へいや【越後平野】ヱチ‥
新潟平野の別称。
⇒えちご【越後】
えちご‐や【越後屋】ヱチ‥
(祖先が越後守高次といったことからの名という)伊勢商人三井高利が経営した呉服店。本店は京都。江戸・大坂に店を置く。江戸店は1673年(延宝1)江戸本町に開店、83年(天和3)日本橋駿河町に移転。今の三越の前身。
⇒えちご【越後】
えちご‐ゆざわ【越後湯沢】ヱチ‥ザハ
「湯沢2」参照。
⇒えちご【越後】
えちご‐りゅう【越後流】ヱチ‥リウ
上杉謙信の采配を規範とする軍学の一派。謙信の将、宇佐美駿河守定行を祖とする宇佐美流・神徳流、越後の沢崎主水もんどを祖とする要門流などに分流。謙信流。
⇒えちご【越後】
え‐ちず【絵地図】ヱ‥ヅ
記号を用いず、絵をかいて表した地図。
えちぜん【越前】ヱチ‥
①旧国名。今の福井県の東部。古名、こしのみちのくち。
②福井県中部の市。刃物・和紙などの伝統産業のほか、電子・機械・繊維工業も立地。人口8万8千。
⇒えちぜん‐がに【越前蟹】
⇒えちぜん‐がみ【越前紙】
⇒えちぜん‐くらげ【越前水母】
えちぜん‐がに【越前蟹】ヱチ‥
ズワイガニの、越前一帯で水揚げするものの称。
⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐がみ【越前紙】ヱチ‥
上古以来、現今に至るまで福井県越前市今立を中心として越前各地で産出してきた和紙。奉書紙は特に優秀。
越前美術紙
撮影:関戸 勇
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチカ【Ethica】
(「倫理学」の意)スピノザの主著。1675年頃完成。77年刊行。幾何学の秩序にしたがって論証するという仕方で、形而上学、精神と認識、感情、倫理学、人間の自由と至福などの広い領域を体系的に論じている。
えちかわ‐や【越川屋】ヱチカハ‥
江戸上野池之端仲町にあった袋物屋。
エチケット【etiquette】
①礼儀。作法。礼法。ベルツ、ベルツの日記「日本では西洋人の間で…礼式エチケットがあまり厳格に守られておらず」。「食卓での―」「―に反する」
②ワインの瓶のラベル。
えち‐ご【越期】ヱチ‥
ある時期を越えて長く続くこと。手遅れになること。おつご。狂歌咄「さまざま薬を用ゆれども落ちず。後には―になり」
えちご【越後】ヱチ‥
旧国名。今の新潟県の大部分。古名、こしのみちのしり。
⇒えちご‐かたびら【越後帷子】
⇒えちご‐さらし【越後晒】
⇒えちご‐じし【越後獅子】
⇒えちご‐じょうふ【越後上布】
⇒えちご‐ちぢみ【越後縮】
⇒えちご‐ぬの【越後布】
⇒えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】
⇒えちご‐ふで【越後筆】
⇒えちご‐へいや【越後平野】
⇒えちご‐や【越後屋】
⇒えちご‐ゆざわ【越後湯沢】
⇒えちご‐りゅう【越後流】
えちご‐かたびら【越後帷子】ヱチ‥
越後国小千谷おぢやから産出する上布じょうふまたは縮ちぢみのかたびら。→越後上布→越後縮ちぢみ。
⇒えちご【越後】
えちご‐さらし【越後晒】ヱチ‥
(→)越後上布に同じ。好色一代男3「二布は―、赤染にして」
⇒えちご【越後】
えちご‐じし【越後獅子】ヱチ‥
①越後国西蒲原郡の神社の里神楽の獅子舞。
②越後国西蒲原郡月潟地方から出る獅子舞。子供が小さい獅子頭をかぶり、身をそらせ、逆立ちで歩くなどの芸をしながら、銭を乞いあるく。蒲原獅子。角兵衛獅子。
③地歌。2を題材とする。天明(1781〜1789)頃、峰崎勾当作曲。箏の手付には市浦検校作曲と八重崎検校作曲の2曲がある。
④歌舞伎舞踊。長唄。七変化舞踊「遅桜手爾葉七字おそざくらてにはのななもじ」の一部。篠田金次作詞、9世杵屋六左衛門作曲。1811年(文化8)初演。地歌を取り入れたもので、越後の角兵衛獅子が浜唄・おけさ踊り・布晒ぬのざらしなどの諸芸を見せる。
⇒えちご【越後】
えちご‐じょうふ【越後上布】ヱチ‥ジヤウ‥
江戸時代、越後国小千谷おぢや付近から苧からむしの繊維を用いて織り出した上質な麻織物の総称。雪晒さらしに特徴がある。越後晒。
⇒えちご【越後】
えちご‐ちぢみ【越後縮】ヱチ‥
越後国小千谷おぢや地方から出す縮。苧からむしで織った夏着尺きじゃく。おぢやちぢみ。越後布。
⇒えちご【越後】
えちご‐ぬの【越後布】ヱチ‥
(→)越後縮ちぢみに同じ。
⇒えちご【越後】
えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】ヱチ‥
越後地方に伝承された七つの不思議な現象。臭水くそうず(石油。柄目木がらめきの火など)・鎌鼬かまいたち・波の題目・逆さ竹・八房梅やつぶさうめ・赤坊主八滝・弘智法師遺骸ほか諸説ある。
⇒えちご【越後】
えちご‐ふで【越後筆】ヱチ‥
越後村松藩内などで製作した筆。のち見附市に移る。
⇒えちご【越後】
えちご‐へいや【越後平野】ヱチ‥
新潟平野の別称。
⇒えちご【越後】
えちご‐や【越後屋】ヱチ‥
(祖先が越後守高次といったことからの名という)伊勢商人三井高利が経営した呉服店。本店は京都。江戸・大坂に店を置く。江戸店は1673年(延宝1)江戸本町に開店、83年(天和3)日本橋駿河町に移転。今の三越の前身。
⇒えちご【越後】
えちご‐ゆざわ【越後湯沢】ヱチ‥ザハ
「湯沢2」参照。
⇒えちご【越後】
えちご‐りゅう【越後流】ヱチ‥リウ
上杉謙信の采配を規範とする軍学の一派。謙信の将、宇佐美駿河守定行を祖とする宇佐美流・神徳流、越後の沢崎主水もんどを祖とする要門流などに分流。謙信流。
⇒えちご【越後】
え‐ちず【絵地図】ヱ‥ヅ
記号を用いず、絵をかいて表した地図。
えちぜん【越前】ヱチ‥
①旧国名。今の福井県の東部。古名、こしのみちのくち。
②福井県中部の市。刃物・和紙などの伝統産業のほか、電子・機械・繊維工業も立地。人口8万8千。
⇒えちぜん‐がに【越前蟹】
⇒えちぜん‐がみ【越前紙】
⇒えちぜん‐くらげ【越前水母】
えちぜん‐がに【越前蟹】ヱチ‥
ズワイガニの、越前一帯で水揚げするものの称。
⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐がみ【越前紙】ヱチ‥
上古以来、現今に至るまで福井県越前市今立を中心として越前各地で産出してきた和紙。奉書紙は特に優秀。
越前美術紙
撮影:関戸 勇
 ⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐くらげ【越前水母】ヱチ‥
ビゼンクラゲ目の鉢虫類。傘部は厚い寒天質で、下面に口を囲んで8本の口腕がある。直径1メートル、重さ150キログラムに達する。淡褐色。東シナ海から日本海に流入し、越前では古くから知られる。食用。
⇒えちぜん【越前】
えち‐もの
姿ばかりを飾って役に立たない柔弱な者。甲陽軍鑑13「―と申すは、小袖諸道具をもいつくしくばかり思案して、女の好むやうに仕り、微若なる奴を―とて、何の役にもたたぬ臆病者にて」
エチモロジー【etymology】
①語の起源・歴史。語源。
②語源の研究。語源学。
エチュード【étude フランス】
①〔音〕楽器の練習のために作られた楽曲。芸術的なものもある。練習曲。
→エチュード 「黒鍵」Op.10-5
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②〔美〕習作。↔タブロー
え‐ぢょうちん【絵提灯】ヱヂヤウ‥
吉野紙などの薄紙を張って絵を描いた提灯。夏の夜、軒先などに吊して点火する。岐阜提灯が有名。
エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
〔化〕アルキル基の一つ。化学式‐C2H5
⇒エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
⇒エチル‐エーテル【ethyl ether】
エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
アルコール類の一つ。分子式C2H5OH 無色透明、特有の香りと味を持つ液体。揮発しやすく燃えやすい。糖類のアルコール発酵により生成し、酒類の成分となる。工業的にはエチレンを原料として合成し、溶剤、燃料、種々の化学薬品の合成原料となる。単にアルコールともいう。酒精。エタノール。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチル‐エーテル【ethyl ether】
分子式(C2H5)2O エーテル類の一つ。アルコールに濃硫酸を加え蒸留して製する無色の液体。特異な香気をもち、揮発しやすく燃えやすい。麻酔性がある。溶剤としての用途が広く、医薬にも用いる。ジエチル‐エーテルまたは単にエーテルともいう。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
分子式H2C=CH2 炭化水素の一つ。無色可燃性の気体。アルコールと濃硫酸とを熱すると生じる。工業的にはエタンの脱水素またはナフサの熱分解によって製する。石油化学工業の重要な基礎原料。また、植物中に生成し、植物ホルモンの一つとして果実の成熟、落葉・落果の促進などの生理作用を示す。生油気せいゆき。エテン。
⇒エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
⇒エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
⇒エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】
⇒エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
⇒エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
⇒エチレン‐プロピレン‐ゴム
エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
環状エーテルの一つ。分子式C2H4O 芳香のある無色の気体。反応性に富み爆発性をもつ。エチレンを触媒の存在下で酸化して合成する。石油化学工業における重要な中間体で、エチレン‐グリコールや界面活性剤(ポリエチレン‐オキシド)の製造に用いる。酸化エチレン。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
分子式HOCH2CH2OH 最も簡単な2価アルコール。無色粘稠ねんちゅう性の甘味ある液体。吸湿性が強い。主としてエチレン‐オキシドと水との反応により製する。エンジン冷却水の不凍液に用いるほか、合成繊維(ポリエステル)の原料。単にグリコールともいう。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】‥クワ‥
(→)オレフィンに同じ。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
アンモニアのような臭気をもつ無色の液体。水とは任意の割合で混ざる。強塩基性。分子式H2NCH2CH2NH2 2座配位子として金属原子に配位して錯体をつくりやすい。配位子としてはenと略記。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
(ethylenediaminetetraacetic acid)EDTAと略記。エチレン‐ジアミンとクロロ酢酸との反応によってつくられる四塩基酸。無色の結晶性粉末。化学式(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 水に溶け、アルカリ土類金属イオンを含む多くの金属イオンと安定な水溶性の錯体(キレート)を形成。金属イオンの分析、有毒金属の除去などに用いる。エデト酸。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐プロピレン‐ゴム
(ethylene-propyrene rubber)エチレンとプロピレンとを共重合させて得られる合成ゴム。耐熱性・耐寒性・耐水性・電気的性質に優れる。車両部品・建材・電線被覆などに利用。EPR
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
えっ
〔感〕
①呼びかける声。えい。
②意外のことに驚いて発する声。
えつ【斉魚】
カタクチイワシ科の海産の硬骨魚。食用。有明海および周辺の河川の特産。
えつ【悦】
喜ぶこと。嬉しがること。機嫌のよいこと。
⇒悦に入る
えつ【粤】ヱツ
①(「越」とも書く)中国南部に広く分布した南方系の少数民族およびその国名。百粤・於越・甌おう越・閩びん越などがある。
②広東省の別称。
えつ【越】ヱツ
①春秋戦国時代、列国の一つ。はじめ中国東南の少数民族から出たと考えられる。隣国呉と抗争、前473年、勾践こうせんは呉王夫差を破り、会稽に都し、浙江・江蘇・山東に覇を唱えたが、楚の威王に滅ぼされた。( 〜前257頃)
②浙江省の別称。
③越南の略。ベトナムのこと。「中―国境」
④越国こしのくにの略。「―中」
えつ【鉞】ヱツ
まさかり。古代中国では、青銅製の大型の斧。罪人の首や腰を斬った。「斧ふ―を加える」
えつ【謁】
貴人または目上の人に面会すること。まみえること。おめみえ。「―を賜う」
えつ【閲】
一々目を通してしらべること。「―を乞う」
え‐つう【会通】ヱ‥
〔仏〕一見矛盾対立するように見える説を合わせて互いに意味が通ずるようにさせること。調和的解釈を施すこと。会釈。
えっ‐か【液化】エキクワ
⇒えきか
エッカーマン【Johann Peter Eckermann】
ゲーテ晩年の秘書。作「ゲーテとの対話」で文豪の日常と言動を伝えた。(1792〜1854)
えっ‐かい【越階】ヱツ‥
⇒おっかい
えつ‐かいかん【粤海関】‥クワン
清代、1685年広州に設置された海関。海禁解除に伴って設立され、交易は公行という特許商人が担い、関税の徴収も引き受けた。
えっ‐き【悦喜】
喜ぶこと。好色一代女1「―鼻の先にあらはなり」
え‐つき【役調・課役】
えだちとみつぎ。古代の夫役と貢物。万葉集16「里長さとおさが―徴はたらば」
え‐づき【餌付】ヱ‥
えづくこと。
えっ‐きょう【越境】ヱツキヤウ
境界線や国境などを越えること。おっきょう。
⇒えっきょう‐にゅうがく【越境入学】
えっきょう‐にゅうがく【越境入学】ヱツキヤウニフ‥
定められた学区の境界を越えて、他の学区の学校に入学すること。
⇒えっ‐きょう【越境】
エッグ【egg】
卵。鶏卵。「スクランブル‐―」
⇒エッグ‐ノッグ【eggnog】
え‐づ・く【餌付く】ヱ‥
〔自五〕
小鳥や家畜などが、馴れてえさを食べるようになる。
え‐づくし【絵尽し】ヱ‥
江戸時代の歌舞伎・浄瑠璃の舞台面を絵画化し、文字を散らした小冊子。歌舞伎絵尽・浄瑠璃絵尽がある。江戸歌舞伎のものは絵本番付ともいう。
エックス【X・x】
①アルファベットの24番目の文字。
②数学で未知数の符号。転じて、未知の物事。
③ローマ数字の10。
エックス‐エム‐エル【XML】
(Extensible Markup Language)構造化された文書やデータを記述するための書式表現言語の一つ。SGMLの文法を簡素化し欠点を解消したもので、独自の書式を定義する機能をもつ。コンピューターのデータ送受信のほか、文書の意味の表現などにも利用。
エックスオー‐ジャン【XO醤】
(中国語)中国料理の調味料の一つ。赤唐辛子・にんにく・エシャロット・干しえび・干し貝柱などを炒め合わせたもの。
エックス‐きゃく【X脚】
直立すると下肢かしが膝のところで外側に開きX字型を示す状態。両側の外反膝。↔O脚
エックス‐せん【X線】
(X-rays)電磁波の一種。ふつう波長が0.01〜10ナノメートルの間。1895年レントゲンが発見、未知の線という意味でX線と命名。物質透過能力・電離作用・写真感光作用・化学作用・生理作用などが強く、干渉・回折などの現象を生じるので、結晶構造の研究、スペクトル分析、医療などに応用。レントゲン線。→電磁波(図)。
⇒エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】
⇒エックスせん‐かん【X線管】
⇒エックスせん‐しゃしん【X線写真】
⇒エックスせん‐てんたい【X線天体】
⇒エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
⇒エックスせん‐バースト【X線バースト】
エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】‥クワイ‥ハフ
X線を結晶で回折させ、これを解析して結晶構造を解明する方法。非晶質・液体・生物・DNAの構造解析にも利用。X線回折。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐かん【X線管】‥クワン
X線を発生させるための真空管。陰極から放出される電子を高電圧で加速し、これをタングステン・銅などの陽極(対陰極)に衝突させて、そこから発生させる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐しゃしん【X線写真】
X線を用いて撮影した写真。レントゲン写真。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐せんしょくたい【X染色体】
性染色体の一つ。Y染色体に対立する。接合子でX染色体同士が対となったとき一方の性を決定し、XYが対となったときには他方の性を決定する。普通、ホモ接合体が雌性となる場合にいい、雄性となる場合にはZ染色体とも呼ぶ。→Y染色体
エックスせん‐てんたい【X線天体】
X線を放射する天体。中性子星・ブラック‐ホール・超新星残骸・クエーサーなど。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
X線天体を観測・研究する天文学の一分野。人工衛星・気球などに搭載したX線検出器により観測する。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐バースト【X線バースト】
(X-ray burst)天体から短時間に爆発的にX線が放出される現象。連星系中の中性子星やブラック‐ホールが起こすと考えられる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐デー
(和製語X day)いつかは定かでないが近い将来重大な出来事が実際に起こるとされる日。また、計画を実行する予定の日。
エックスバー‐りろん【エックスバー理論】
〔言〕(X-bar theory)生成文法の用語。言語では、どの種類の句の構造も階層的な構造をなしており、その構成がよく類似している。そうした類似性を変項Xと横棒(バー)を用いて表記することにより捉えようとする理論。
エッグ‐ノッグ【eggnog】
卵・牛乳・砂糖を攪拌した飲み物。また、それにブランデーやラムを加えたカクテル。温・冷2種類がある。
⇒エッグ【egg】
エックハルト【Johannes Eckhart】
(通称Meister E.)ドイツの神学者。ドミニコ会に属する神秘主義者。新プラトン主義的な思想の流れの中で、魂の根底において神に触れることを介しての、神の子キリストとの神秘的合一を説いた。(1260頃〜1328頃)
え‐つけ【絵付】ヱ‥
陶磁器の表面に絵具で彩飾を施すこと。釉うわぐすりの下に焼きつけるのを下絵付、上に焼きつけるのを上絵付という。
え‐づけ【餌付け】ヱ‥
人に馴れにくい野生の動物を、人から餌をもらうまでに馴れさせること。
えつ‐げき【越劇】ヱツ‥
中国、浙江省紹興地方より起こった演劇。上海に進出して女優劇となる。
エッケ‐ホモ【ecce homo ラテン】
(「見よ、この人を」の意)新約聖書(ウルガタ訳)で、ピラトがイエスをユダヤ民衆の前に引き出した時の言葉。
エッケルト【Franz Eckert】
ドイツの音楽家。1879年(明治12)来日、海軍軍務局・宮内省雅楽所に勤務、また文部省音楽取調掛に出向。軍楽隊を養成。(1852〜1916)
えっ‐けん【越権】ヱツ‥
権限をこえて事を行うこと。おっけん。「―行為」
⇒えっけん‐だいり【越権代理】
えっ‐けん【謁見】
貴人または目上の人に面会すること。「大統領に―する」「―を賜る」
えっけん‐だいり【越権代理】ヱツ‥
〔法〕代理人の権限の範囲を越える代理行為。相手方がそれを権限内の行為と信じたことに正当な理由があると、その効果は本人に及ぶ。
⇒えっ‐けん【越権】
えつ‐ごく【越獄】ヱツ‥
⇒おつごく
えっさ
〔感〕
重い物を動かす時などの掛け声。また、調子をつけるはやし声。
えっ‐さい【悦哉・雀
⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐くらげ【越前水母】ヱチ‥
ビゼンクラゲ目の鉢虫類。傘部は厚い寒天質で、下面に口を囲んで8本の口腕がある。直径1メートル、重さ150キログラムに達する。淡褐色。東シナ海から日本海に流入し、越前では古くから知られる。食用。
⇒えちぜん【越前】
えち‐もの
姿ばかりを飾って役に立たない柔弱な者。甲陽軍鑑13「―と申すは、小袖諸道具をもいつくしくばかり思案して、女の好むやうに仕り、微若なる奴を―とて、何の役にもたたぬ臆病者にて」
エチモロジー【etymology】
①語の起源・歴史。語源。
②語源の研究。語源学。
エチュード【étude フランス】
①〔音〕楽器の練習のために作られた楽曲。芸術的なものもある。練習曲。
→エチュード 「黒鍵」Op.10-5
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②〔美〕習作。↔タブロー
え‐ぢょうちん【絵提灯】ヱヂヤウ‥
吉野紙などの薄紙を張って絵を描いた提灯。夏の夜、軒先などに吊して点火する。岐阜提灯が有名。
エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
〔化〕アルキル基の一つ。化学式‐C2H5
⇒エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
⇒エチル‐エーテル【ethyl ether】
エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
アルコール類の一つ。分子式C2H5OH 無色透明、特有の香りと味を持つ液体。揮発しやすく燃えやすい。糖類のアルコール発酵により生成し、酒類の成分となる。工業的にはエチレンを原料として合成し、溶剤、燃料、種々の化学薬品の合成原料となる。単にアルコールともいう。酒精。エタノール。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチル‐エーテル【ethyl ether】
分子式(C2H5)2O エーテル類の一つ。アルコールに濃硫酸を加え蒸留して製する無色の液体。特異な香気をもち、揮発しやすく燃えやすい。麻酔性がある。溶剤としての用途が広く、医薬にも用いる。ジエチル‐エーテルまたは単にエーテルともいう。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
分子式H2C=CH2 炭化水素の一つ。無色可燃性の気体。アルコールと濃硫酸とを熱すると生じる。工業的にはエタンの脱水素またはナフサの熱分解によって製する。石油化学工業の重要な基礎原料。また、植物中に生成し、植物ホルモンの一つとして果実の成熟、落葉・落果の促進などの生理作用を示す。生油気せいゆき。エテン。
⇒エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
⇒エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
⇒エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】
⇒エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
⇒エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
⇒エチレン‐プロピレン‐ゴム
エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
環状エーテルの一つ。分子式C2H4O 芳香のある無色の気体。反応性に富み爆発性をもつ。エチレンを触媒の存在下で酸化して合成する。石油化学工業における重要な中間体で、エチレン‐グリコールや界面活性剤(ポリエチレン‐オキシド)の製造に用いる。酸化エチレン。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
分子式HOCH2CH2OH 最も簡単な2価アルコール。無色粘稠ねんちゅう性の甘味ある液体。吸湿性が強い。主としてエチレン‐オキシドと水との反応により製する。エンジン冷却水の不凍液に用いるほか、合成繊維(ポリエステル)の原料。単にグリコールともいう。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】‥クワ‥
(→)オレフィンに同じ。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
アンモニアのような臭気をもつ無色の液体。水とは任意の割合で混ざる。強塩基性。分子式H2NCH2CH2NH2 2座配位子として金属原子に配位して錯体をつくりやすい。配位子としてはenと略記。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
(ethylenediaminetetraacetic acid)EDTAと略記。エチレン‐ジアミンとクロロ酢酸との反応によってつくられる四塩基酸。無色の結晶性粉末。化学式(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 水に溶け、アルカリ土類金属イオンを含む多くの金属イオンと安定な水溶性の錯体(キレート)を形成。金属イオンの分析、有毒金属の除去などに用いる。エデト酸。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐プロピレン‐ゴム
(ethylene-propyrene rubber)エチレンとプロピレンとを共重合させて得られる合成ゴム。耐熱性・耐寒性・耐水性・電気的性質に優れる。車両部品・建材・電線被覆などに利用。EPR
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
えっ
〔感〕
①呼びかける声。えい。
②意外のことに驚いて発する声。
えつ【斉魚】
カタクチイワシ科の海産の硬骨魚。食用。有明海および周辺の河川の特産。
えつ【悦】
喜ぶこと。嬉しがること。機嫌のよいこと。
⇒悦に入る
えつ【粤】ヱツ
①(「越」とも書く)中国南部に広く分布した南方系の少数民族およびその国名。百粤・於越・甌おう越・閩びん越などがある。
②広東省の別称。
えつ【越】ヱツ
①春秋戦国時代、列国の一つ。はじめ中国東南の少数民族から出たと考えられる。隣国呉と抗争、前473年、勾践こうせんは呉王夫差を破り、会稽に都し、浙江・江蘇・山東に覇を唱えたが、楚の威王に滅ぼされた。( 〜前257頃)
②浙江省の別称。
③越南の略。ベトナムのこと。「中―国境」
④越国こしのくにの略。「―中」
えつ【鉞】ヱツ
まさかり。古代中国では、青銅製の大型の斧。罪人の首や腰を斬った。「斧ふ―を加える」
えつ【謁】
貴人または目上の人に面会すること。まみえること。おめみえ。「―を賜う」
えつ【閲】
一々目を通してしらべること。「―を乞う」
え‐つう【会通】ヱ‥
〔仏〕一見矛盾対立するように見える説を合わせて互いに意味が通ずるようにさせること。調和的解釈を施すこと。会釈。
えっ‐か【液化】エキクワ
⇒えきか
エッカーマン【Johann Peter Eckermann】
ゲーテ晩年の秘書。作「ゲーテとの対話」で文豪の日常と言動を伝えた。(1792〜1854)
えっ‐かい【越階】ヱツ‥
⇒おっかい
えつ‐かいかん【粤海関】‥クワン
清代、1685年広州に設置された海関。海禁解除に伴って設立され、交易は公行という特許商人が担い、関税の徴収も引き受けた。
えっ‐き【悦喜】
喜ぶこと。好色一代女1「―鼻の先にあらはなり」
え‐つき【役調・課役】
えだちとみつぎ。古代の夫役と貢物。万葉集16「里長さとおさが―徴はたらば」
え‐づき【餌付】ヱ‥
えづくこと。
えっ‐きょう【越境】ヱツキヤウ
境界線や国境などを越えること。おっきょう。
⇒えっきょう‐にゅうがく【越境入学】
えっきょう‐にゅうがく【越境入学】ヱツキヤウニフ‥
定められた学区の境界を越えて、他の学区の学校に入学すること。
⇒えっ‐きょう【越境】
エッグ【egg】
卵。鶏卵。「スクランブル‐―」
⇒エッグ‐ノッグ【eggnog】
え‐づ・く【餌付く】ヱ‥
〔自五〕
小鳥や家畜などが、馴れてえさを食べるようになる。
え‐づくし【絵尽し】ヱ‥
江戸時代の歌舞伎・浄瑠璃の舞台面を絵画化し、文字を散らした小冊子。歌舞伎絵尽・浄瑠璃絵尽がある。江戸歌舞伎のものは絵本番付ともいう。
エックス【X・x】
①アルファベットの24番目の文字。
②数学で未知数の符号。転じて、未知の物事。
③ローマ数字の10。
エックス‐エム‐エル【XML】
(Extensible Markup Language)構造化された文書やデータを記述するための書式表現言語の一つ。SGMLの文法を簡素化し欠点を解消したもので、独自の書式を定義する機能をもつ。コンピューターのデータ送受信のほか、文書の意味の表現などにも利用。
エックスオー‐ジャン【XO醤】
(中国語)中国料理の調味料の一つ。赤唐辛子・にんにく・エシャロット・干しえび・干し貝柱などを炒め合わせたもの。
エックス‐きゃく【X脚】
直立すると下肢かしが膝のところで外側に開きX字型を示す状態。両側の外反膝。↔O脚
エックス‐せん【X線】
(X-rays)電磁波の一種。ふつう波長が0.01〜10ナノメートルの間。1895年レントゲンが発見、未知の線という意味でX線と命名。物質透過能力・電離作用・写真感光作用・化学作用・生理作用などが強く、干渉・回折などの現象を生じるので、結晶構造の研究、スペクトル分析、医療などに応用。レントゲン線。→電磁波(図)。
⇒エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】
⇒エックスせん‐かん【X線管】
⇒エックスせん‐しゃしん【X線写真】
⇒エックスせん‐てんたい【X線天体】
⇒エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
⇒エックスせん‐バースト【X線バースト】
エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】‥クワイ‥ハフ
X線を結晶で回折させ、これを解析して結晶構造を解明する方法。非晶質・液体・生物・DNAの構造解析にも利用。X線回折。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐かん【X線管】‥クワン
X線を発生させるための真空管。陰極から放出される電子を高電圧で加速し、これをタングステン・銅などの陽極(対陰極)に衝突させて、そこから発生させる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐しゃしん【X線写真】
X線を用いて撮影した写真。レントゲン写真。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐せんしょくたい【X染色体】
性染色体の一つ。Y染色体に対立する。接合子でX染色体同士が対となったとき一方の性を決定し、XYが対となったときには他方の性を決定する。普通、ホモ接合体が雌性となる場合にいい、雄性となる場合にはZ染色体とも呼ぶ。→Y染色体
エックスせん‐てんたい【X線天体】
X線を放射する天体。中性子星・ブラック‐ホール・超新星残骸・クエーサーなど。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
X線天体を観測・研究する天文学の一分野。人工衛星・気球などに搭載したX線検出器により観測する。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐バースト【X線バースト】
(X-ray burst)天体から短時間に爆発的にX線が放出される現象。連星系中の中性子星やブラック‐ホールが起こすと考えられる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐デー
(和製語X day)いつかは定かでないが近い将来重大な出来事が実際に起こるとされる日。また、計画を実行する予定の日。
エックスバー‐りろん【エックスバー理論】
〔言〕(X-bar theory)生成文法の用語。言語では、どの種類の句の構造も階層的な構造をなしており、その構成がよく類似している。そうした類似性を変項Xと横棒(バー)を用いて表記することにより捉えようとする理論。
エッグ‐ノッグ【eggnog】
卵・牛乳・砂糖を攪拌した飲み物。また、それにブランデーやラムを加えたカクテル。温・冷2種類がある。
⇒エッグ【egg】
エックハルト【Johannes Eckhart】
(通称Meister E.)ドイツの神学者。ドミニコ会に属する神秘主義者。新プラトン主義的な思想の流れの中で、魂の根底において神に触れることを介しての、神の子キリストとの神秘的合一を説いた。(1260頃〜1328頃)
え‐つけ【絵付】ヱ‥
陶磁器の表面に絵具で彩飾を施すこと。釉うわぐすりの下に焼きつけるのを下絵付、上に焼きつけるのを上絵付という。
え‐づけ【餌付け】ヱ‥
人に馴れにくい野生の動物を、人から餌をもらうまでに馴れさせること。
えつ‐げき【越劇】ヱツ‥
中国、浙江省紹興地方より起こった演劇。上海に進出して女優劇となる。
エッケ‐ホモ【ecce homo ラテン】
(「見よ、この人を」の意)新約聖書(ウルガタ訳)で、ピラトがイエスをユダヤ民衆の前に引き出した時の言葉。
エッケルト【Franz Eckert】
ドイツの音楽家。1879年(明治12)来日、海軍軍務局・宮内省雅楽所に勤務、また文部省音楽取調掛に出向。軍楽隊を養成。(1852〜1916)
えっ‐けん【越権】ヱツ‥
権限をこえて事を行うこと。おっけん。「―行為」
⇒えっけん‐だいり【越権代理】
えっ‐けん【謁見】
貴人または目上の人に面会すること。「大統領に―する」「―を賜る」
えっけん‐だいり【越権代理】ヱツ‥
〔法〕代理人の権限の範囲を越える代理行為。相手方がそれを権限内の行為と信じたことに正当な理由があると、その効果は本人に及ぶ。
⇒えっ‐けん【越権】
えつ‐ごく【越獄】ヱツ‥
⇒おつごく
えっさ
〔感〕
重い物を動かす時などの掛け声。また、調子をつけるはやし声。
えっ‐さい【悦哉・雀 】
〔動〕小形のタカの一種「つみ」の雄の俗称。
えっさっさ
〔感〕
物をかついで走る時の掛け声。また、そうした気持を表すはやしことば。
⇒えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
安政(1854〜1860)の頃、大坂で流行した一種の俗謡。また、岐阜県下呂市小坂町の盆踊り歌。
⇒えっさっさ
えっさら‐おっさら
大儀そうに歩いて行くさまにいう語。御苦労にも。わざわざ。えっちらおっちら。浮世風呂2「お弁当がおそいと宿まで取りに参りますわな。さうして―お師匠様へ持つてつてたべます」
エッジ【edge】
①端はし。ふち。へり。
②スキーの滑走面の両側の角。多く金属などで補強する。また、スケート靴の氷に接する面の両角。
⇒エッジ‐ボール【edge ball】
エッジ‐ボール【edge ball】
卓球で、ボールが相手側コートの縁に当たること。
⇒エッジ【edge】
えっ‐しゃ【謁者】
客の取次をする者。
エッシャー【Maurice Cornelis Escher】
オランダの版画家。独特の幾何学的方法論を駆使して、錯視的で幻想的な小宇宙を生み出す。(1898〜1972)
えっ‐しゅう【越州】ヱツシウ
越前・越中・越後の総称。
えっしゅう‐よう【越州窯】ヱツシウエウ
中国浙江省北部(古くは越)を中心とした、後漢代から宋代にかけての青磁窯。特に晩唐・五代の頃の青磁は秘色ひそくと称され著名。
えつじん【越人】ヱツ‥
⇒おちえつじん(越智越人)
えっ・する【謁する】
〔自サ変〕[文]謁す(サ変)
貴人・目上の人に面会する。お目にかかる。「竜顔に―・する」
えっ・する【閲する】
〔他サ変〕[文]閲す(サ変)
①しらべ見る。
②目をとおす。「草案を―・する」
③時間が経過する。「はや5年を―・し」
エッセイスト【essayist】
随筆家。
エッセー【essai フランス・essay イギリス】
①随筆。自由な形式で書かれた、思索性をもつ散文。
②試論。小論。
エッセネ‐は【エッセネ派】
(Essenes)イエス時代のユダヤ教三大教派の一つ。一切の財産を共有し、厳格な律法遵守の生活を営み、終末を待望した。死海写本中のクムラン文書を生み出した教団と同一視される。→サドカイ派→ファリサイ派
エッセン【essen ドイツ】
(旧制高校の学生語)食事すること。また、食べ物。
エッセン【Essen】
ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州、ルール工業地帯の中心都市。重工業が発達。クルップ財閥の根拠地。人口60万(1999)。
エッセンシャル【essential】
本質的。必須の。
⇒エッセンシャル‐オイル【essential oil】
エッセンシャル‐オイル【essential oil】
精油。
⇒エッセンシャル【essential】
エッセンス【essence】
①物事の本質。精髄。
②植物体から抽出した芳香性の精油。また、そのアルコール溶液。香油。「バニラ‐―」
えっ‐そ【越俎】ヱツ‥
[荘子逍遥遊](料理人が料理を怠っても、神主は酒樽や俎まないたを越うばって代りをするものではない意の原文から)自分の職分を越えて他人の権限内に立ち入ること。越権。「―の罪」
えっ‐そ【越訴】ヱツ‥
⇒おっそ
えつぞうちしん【閲蔵知津】‥ザウ‥
〔仏〕中国、明末の学僧智旭(1599〜1655)が、自ら閲覧した経論や注釈書・目録など1773部について解説した書。48巻。仏書の総合解説書。
えったヱツタ
「えた」の訛。〈日葡辞書〉
エッダ【Edda】
9〜13世紀に古アイスランド語で書かれたゲルマン神話や英雄伝説の集成。1643年にアイスランドで発見された。天地創造、神と巨人族との闘争を主な内容とする。韻文の古エッダとスノッリ=スツルルソン(Snorri Sturluson1178〜1241)が編纂した散文の新エッダ(「詩学の書」)とがある。
エッチ【H・h】
①アルファベットの8番目の文字。エイチ。
②〔化〕水素の元素記号。
③(hard)鉛筆の芯の硬さを表す符号。「2H」
④インダクタンスの単位ヘンリーの略号(H)。
⑤単位の接頭語ヘクト(hecto,102)の略号(h)。
⑥時間を表す単位、時(hour)の略号(h)。
⑦プランクの定数(h)。
⑧(「変態」のローマ字書きhentaiの略)
㋐性に関する言動が露骨でいやらしいさま。
㋑俗に、性交。
エッチ‐アール‐ず【HR図】‥ヅ
〔天〕(→)ヘルツシュプルング‐ラッセル図の略。
エッチ‐アイアン‐ほう【Hアイアン法】‥ハフ
(H-iron process)直接製鉄法の一つ。粉状の鉄鉱石を、流動炉で低温高圧水素中に浮遊懸濁させ、直接還元する。鉄分98パーセント以上のものが得られ、粉末冶金・溶接用鉄粉として使用。
エッチ‐アイ‐ブイ【HIV】
(human immunodeficiency virus)ヒト免疫不全ウイルス。レトロ‐ウイルス科レンチ‐ウイルス亜科に属するRNAウイルスで、エイズの病原。
エッチ‐エス‐ケー【HSK】
(「漢語水平考試」の拼音ピンイン表記Hanyu Shuiping Kaoshiの略)中国教育部(文部科学省に相当)認定の中国語(漢語)検定試験。中国語を母語としない人を対象とする。
エッチ‐エム‐ディー【HMD】
(head mounted display)立体映像装置の一種。頭に被ってバーチャル‐リアリティーを体験するための装置で、両眼の位置に小型のディスプレーを設置してある。
エッチ‐エル‐エー‐こうげん【HLA抗原】‥カウ‥
(human leukocyte antigen)ヒト白血球抗原。ヒトの個体を免疫学的に特徴づける抗原で、臓器や組織の移植の際、拒絶反応を起こすか否かの組織適合性に関与する(主要組織適合抗原)。クラスⅠ、Ⅱに大別。それらの機能と構造を決定する遺伝子複合体は第6染色体のHLA領域に存在。→組織適合抗原
エッチがた‐こう【H形鋼】‥カウ
形鋼の一種。断面がH形で、建物の梁や地下構造物の基礎工事用などに使われる。
エッチがた‐コンベヤー【H形コンベヤー】
切羽きりは運搬機の一種。断面がH形で床面に接して設置でき、また各種の採炭機をのせて動かせるので、カッペとともに切羽の完全機械化への道を開いた。パンツァ‐コンベヤー。
エッチ‐ツー‐ブロッカー【H2 blocker】
ヒスタミンのH2受容体への結合を阻害して胃酸分泌を抑制する薬。胃・十二指腸潰瘍などの治療に用いられる。
エッチ‐ティー‐エム‐エル【HTML】
(Hyper Text Markup Language)データ記述用言語の一つ。ウェブでハイパー‐テキスト文書、すなわちホームページの文書を作製・整形するためのもの。文字のほか音声・画像の扱いが可能で、ハイパー‐リンク機能を持つ。
エッチ‐ティー‐ティー‐ピー【HTTP】
(hypertext transfer protocol)プロトコル3の一種。ウェブ‐サーバーとウェブ‐ブラウザーの間などで、ハイパー‐テキストを通信するために用いられる。これにSSL暗号機能を付加したHTTPSは、ウェブを通じた個人情報の通信に使われる。
エッチ‐に‐エー‐ロケット【H‐ⅡAロケット】
日本製のロケット。日本が独自の技術で開発したH‐Ⅱロケットの改良型。
エッチ‐ビー【HB】
鉛筆の芯の硬さと濃さとを表す符号で、硬すぎず濃すぎない標準的なもの。
エッチ‐ビー‐プロセス【H. B. process】
多色平版の製版法。すりガラス上に色分解ポジを作り、修整ののち網ネガを作成し、感光液を塗布した亜鉛板に焼きつけて版とする。発明者のアメリカ人ヒューブナー(W. Huebner1886〜1966)と協力者ブライシュタイン(Breistein)の頭文字からの命名。
エッチ‐ブイ‐ばん【HV判】
写真感光材料の大きさの一つ。8.9センチメートル×15.8センチメートルの大きさに対する慣用名。HVは縦横の比率がハイビジョンと同じ9対16であることからいう。
えっちゅう【越中】ヱツ‥
①旧国名。今の富山県。こしのみちのなか。
②越中褌ふんどしの略。
⇒えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】
⇒えっちゅう‐じま【越中島】
⇒えっちゅう‐じま【越中縞】
⇒えっちゅう‐ふんどし【越中褌】
えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】ヱツ‥
(→)「おわら節」に同じ。
→文献資料[越中おわら節]
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中島】ヱツ‥
東京都江東区南西部の地区。江戸初期、榊原越中守の別邸所在地。隅田川河口東岸に位置し、1875年(明治8)日本最初の商船学校(現、東京海洋大学)が設置された。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中縞】ヱツ‥
越中福野・富山地方に産する縞木綿。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐ふんどし【越中褌】ヱツ‥
(細川越中守忠興の始めたものという)長さ1メートル程の小幅の布に紐をつけたふんどし。夏目漱石、坊つちやん「丸裸の―一つになつて」
⇒えっちゅう【越中】
えっ‐ちょう【越鳥】ヱツテウ
①中国、越の国の鳥。
②クジャクの異称。
⇒越鳥南枝に巣くう
】
〔動〕小形のタカの一種「つみ」の雄の俗称。
えっさっさ
〔感〕
物をかついで走る時の掛け声。また、そうした気持を表すはやしことば。
⇒えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
安政(1854〜1860)の頃、大坂で流行した一種の俗謡。また、岐阜県下呂市小坂町の盆踊り歌。
⇒えっさっさ
えっさら‐おっさら
大儀そうに歩いて行くさまにいう語。御苦労にも。わざわざ。えっちらおっちら。浮世風呂2「お弁当がおそいと宿まで取りに参りますわな。さうして―お師匠様へ持つてつてたべます」
エッジ【edge】
①端はし。ふち。へり。
②スキーの滑走面の両側の角。多く金属などで補強する。また、スケート靴の氷に接する面の両角。
⇒エッジ‐ボール【edge ball】
エッジ‐ボール【edge ball】
卓球で、ボールが相手側コートの縁に当たること。
⇒エッジ【edge】
えっ‐しゃ【謁者】
客の取次をする者。
エッシャー【Maurice Cornelis Escher】
オランダの版画家。独特の幾何学的方法論を駆使して、錯視的で幻想的な小宇宙を生み出す。(1898〜1972)
えっ‐しゅう【越州】ヱツシウ
越前・越中・越後の総称。
えっしゅう‐よう【越州窯】ヱツシウエウ
中国浙江省北部(古くは越)を中心とした、後漢代から宋代にかけての青磁窯。特に晩唐・五代の頃の青磁は秘色ひそくと称され著名。
えつじん【越人】ヱツ‥
⇒おちえつじん(越智越人)
えっ・する【謁する】
〔自サ変〕[文]謁す(サ変)
貴人・目上の人に面会する。お目にかかる。「竜顔に―・する」
えっ・する【閲する】
〔他サ変〕[文]閲す(サ変)
①しらべ見る。
②目をとおす。「草案を―・する」
③時間が経過する。「はや5年を―・し」
エッセイスト【essayist】
随筆家。
エッセー【essai フランス・essay イギリス】
①随筆。自由な形式で書かれた、思索性をもつ散文。
②試論。小論。
エッセネ‐は【エッセネ派】
(Essenes)イエス時代のユダヤ教三大教派の一つ。一切の財産を共有し、厳格な律法遵守の生活を営み、終末を待望した。死海写本中のクムラン文書を生み出した教団と同一視される。→サドカイ派→ファリサイ派
エッセン【essen ドイツ】
(旧制高校の学生語)食事すること。また、食べ物。
エッセン【Essen】
ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州、ルール工業地帯の中心都市。重工業が発達。クルップ財閥の根拠地。人口60万(1999)。
エッセンシャル【essential】
本質的。必須の。
⇒エッセンシャル‐オイル【essential oil】
エッセンシャル‐オイル【essential oil】
精油。
⇒エッセンシャル【essential】
エッセンス【essence】
①物事の本質。精髄。
②植物体から抽出した芳香性の精油。また、そのアルコール溶液。香油。「バニラ‐―」
えっ‐そ【越俎】ヱツ‥
[荘子逍遥遊](料理人が料理を怠っても、神主は酒樽や俎まないたを越うばって代りをするものではない意の原文から)自分の職分を越えて他人の権限内に立ち入ること。越権。「―の罪」
えっ‐そ【越訴】ヱツ‥
⇒おっそ
えつぞうちしん【閲蔵知津】‥ザウ‥
〔仏〕中国、明末の学僧智旭(1599〜1655)が、自ら閲覧した経論や注釈書・目録など1773部について解説した書。48巻。仏書の総合解説書。
えったヱツタ
「えた」の訛。〈日葡辞書〉
エッダ【Edda】
9〜13世紀に古アイスランド語で書かれたゲルマン神話や英雄伝説の集成。1643年にアイスランドで発見された。天地創造、神と巨人族との闘争を主な内容とする。韻文の古エッダとスノッリ=スツルルソン(Snorri Sturluson1178〜1241)が編纂した散文の新エッダ(「詩学の書」)とがある。
エッチ【H・h】
①アルファベットの8番目の文字。エイチ。
②〔化〕水素の元素記号。
③(hard)鉛筆の芯の硬さを表す符号。「2H」
④インダクタンスの単位ヘンリーの略号(H)。
⑤単位の接頭語ヘクト(hecto,102)の略号(h)。
⑥時間を表す単位、時(hour)の略号(h)。
⑦プランクの定数(h)。
⑧(「変態」のローマ字書きhentaiの略)
㋐性に関する言動が露骨でいやらしいさま。
㋑俗に、性交。
エッチ‐アール‐ず【HR図】‥ヅ
〔天〕(→)ヘルツシュプルング‐ラッセル図の略。
エッチ‐アイアン‐ほう【Hアイアン法】‥ハフ
(H-iron process)直接製鉄法の一つ。粉状の鉄鉱石を、流動炉で低温高圧水素中に浮遊懸濁させ、直接還元する。鉄分98パーセント以上のものが得られ、粉末冶金・溶接用鉄粉として使用。
エッチ‐アイ‐ブイ【HIV】
(human immunodeficiency virus)ヒト免疫不全ウイルス。レトロ‐ウイルス科レンチ‐ウイルス亜科に属するRNAウイルスで、エイズの病原。
エッチ‐エス‐ケー【HSK】
(「漢語水平考試」の拼音ピンイン表記Hanyu Shuiping Kaoshiの略)中国教育部(文部科学省に相当)認定の中国語(漢語)検定試験。中国語を母語としない人を対象とする。
エッチ‐エム‐ディー【HMD】
(head mounted display)立体映像装置の一種。頭に被ってバーチャル‐リアリティーを体験するための装置で、両眼の位置に小型のディスプレーを設置してある。
エッチ‐エル‐エー‐こうげん【HLA抗原】‥カウ‥
(human leukocyte antigen)ヒト白血球抗原。ヒトの個体を免疫学的に特徴づける抗原で、臓器や組織の移植の際、拒絶反応を起こすか否かの組織適合性に関与する(主要組織適合抗原)。クラスⅠ、Ⅱに大別。それらの機能と構造を決定する遺伝子複合体は第6染色体のHLA領域に存在。→組織適合抗原
エッチがた‐こう【H形鋼】‥カウ
形鋼の一種。断面がH形で、建物の梁や地下構造物の基礎工事用などに使われる。
エッチがた‐コンベヤー【H形コンベヤー】
切羽きりは運搬機の一種。断面がH形で床面に接して設置でき、また各種の採炭機をのせて動かせるので、カッペとともに切羽の完全機械化への道を開いた。パンツァ‐コンベヤー。
エッチ‐ツー‐ブロッカー【H2 blocker】
ヒスタミンのH2受容体への結合を阻害して胃酸分泌を抑制する薬。胃・十二指腸潰瘍などの治療に用いられる。
エッチ‐ティー‐エム‐エル【HTML】
(Hyper Text Markup Language)データ記述用言語の一つ。ウェブでハイパー‐テキスト文書、すなわちホームページの文書を作製・整形するためのもの。文字のほか音声・画像の扱いが可能で、ハイパー‐リンク機能を持つ。
エッチ‐ティー‐ティー‐ピー【HTTP】
(hypertext transfer protocol)プロトコル3の一種。ウェブ‐サーバーとウェブ‐ブラウザーの間などで、ハイパー‐テキストを通信するために用いられる。これにSSL暗号機能を付加したHTTPSは、ウェブを通じた個人情報の通信に使われる。
エッチ‐に‐エー‐ロケット【H‐ⅡAロケット】
日本製のロケット。日本が独自の技術で開発したH‐Ⅱロケットの改良型。
エッチ‐ビー【HB】
鉛筆の芯の硬さと濃さとを表す符号で、硬すぎず濃すぎない標準的なもの。
エッチ‐ビー‐プロセス【H. B. process】
多色平版の製版法。すりガラス上に色分解ポジを作り、修整ののち網ネガを作成し、感光液を塗布した亜鉛板に焼きつけて版とする。発明者のアメリカ人ヒューブナー(W. Huebner1886〜1966)と協力者ブライシュタイン(Breistein)の頭文字からの命名。
エッチ‐ブイ‐ばん【HV判】
写真感光材料の大きさの一つ。8.9センチメートル×15.8センチメートルの大きさに対する慣用名。HVは縦横の比率がハイビジョンと同じ9対16であることからいう。
えっちゅう【越中】ヱツ‥
①旧国名。今の富山県。こしのみちのなか。
②越中褌ふんどしの略。
⇒えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】
⇒えっちゅう‐じま【越中島】
⇒えっちゅう‐じま【越中縞】
⇒えっちゅう‐ふんどし【越中褌】
えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】ヱツ‥
(→)「おわら節」に同じ。
→文献資料[越中おわら節]
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中島】ヱツ‥
東京都江東区南西部の地区。江戸初期、榊原越中守の別邸所在地。隅田川河口東岸に位置し、1875年(明治8)日本最初の商船学校(現、東京海洋大学)が設置された。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中縞】ヱツ‥
越中福野・富山地方に産する縞木綿。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐ふんどし【越中褌】ヱツ‥
(細川越中守忠興の始めたものという)長さ1メートル程の小幅の布に紐をつけたふんどし。夏目漱石、坊つちやん「丸裸の―一つになつて」
⇒えっちゅう【越中】
えっ‐ちょう【越鳥】ヱツテウ
①中国、越の国の鳥。
②クジャクの異称。
⇒越鳥南枝に巣くう
 エチオピア【Ethiopia】
アフリカ北東部の連邦民主共和国。「シバの女王の国」と称して世界最古の王国とされ、4世紀頃からキリスト教国となる。1936年イタリアに征服されたが、41年独立を回復。75年帝政を廃止。面積110万4000平方キロメートル。人口7107万(2004)。首都アジス‐アベバ。旧称アビシニア。→アフリカ(図)。
⇒エチオピア‐く【エチオピア区】
⇒エチオピア‐ご【エチオピア語】
⇒エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】
エチオピア‐く【エチオピア区】
動物地理学上の区分の一つ。アフリカ大陸のサハラ砂漠より南の地域。キリン・カバ・ハゲワシなどが固有種で、爬虫類の多いことが特徴。東洋区と共通・近縁種も多いことから、現在では両者を合わせて旧熱帯区とし、それぞれを亜区としている。→動物地理区(図)。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐ご【エチオピア語】
(Ethiopian)
①古代エチオピア語。ゲーズ語とも呼ばれ、4世紀頃の碑文のほか、キリスト教関係の翻訳など多くの文献をもつ。セム語派中の南西セム語群に属する。
②エチオピアで話されている80以上の言語の総称。公用語のアムハラ語のほか、ティグリニャ語が主要な言語。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】‥カウ‥
(Ethiopian Plateau)アフリカ北東部、エチオピアの主要部を占める高原。平均標高約2300メートルで、畑作が行われ都市が発達。別称、アビシニア高原。
エチオピア高原
撮影:小松義夫
エチオピア【Ethiopia】
アフリカ北東部の連邦民主共和国。「シバの女王の国」と称して世界最古の王国とされ、4世紀頃からキリスト教国となる。1936年イタリアに征服されたが、41年独立を回復。75年帝政を廃止。面積110万4000平方キロメートル。人口7107万(2004)。首都アジス‐アベバ。旧称アビシニア。→アフリカ(図)。
⇒エチオピア‐く【エチオピア区】
⇒エチオピア‐ご【エチオピア語】
⇒エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】
エチオピア‐く【エチオピア区】
動物地理学上の区分の一つ。アフリカ大陸のサハラ砂漠より南の地域。キリン・カバ・ハゲワシなどが固有種で、爬虫類の多いことが特徴。東洋区と共通・近縁種も多いことから、現在では両者を合わせて旧熱帯区とし、それぞれを亜区としている。→動物地理区(図)。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐ご【エチオピア語】
(Ethiopian)
①古代エチオピア語。ゲーズ語とも呼ばれ、4世紀頃の碑文のほか、キリスト教関係の翻訳など多くの文献をもつ。セム語派中の南西セム語群に属する。
②エチオピアで話されている80以上の言語の総称。公用語のアムハラ語のほか、ティグリニャ語が主要な言語。
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチオピア‐こうげん【エチオピア高原】‥カウ‥
(Ethiopian Plateau)アフリカ北東部、エチオピアの主要部を占める高原。平均標高約2300メートルで、畑作が行われ都市が発達。別称、アビシニア高原。
エチオピア高原
撮影:小松義夫
 ⇒エチオピア【Ethiopia】
エチカ【Ethica】
(「倫理学」の意)スピノザの主著。1675年頃完成。77年刊行。幾何学の秩序にしたがって論証するという仕方で、形而上学、精神と認識、感情、倫理学、人間の自由と至福などの広い領域を体系的に論じている。
えちかわ‐や【越川屋】ヱチカハ‥
江戸上野池之端仲町にあった袋物屋。
エチケット【etiquette】
①礼儀。作法。礼法。ベルツ、ベルツの日記「日本では西洋人の間で…礼式エチケットがあまり厳格に守られておらず」。「食卓での―」「―に反する」
②ワインの瓶のラベル。
えち‐ご【越期】ヱチ‥
ある時期を越えて長く続くこと。手遅れになること。おつご。狂歌咄「さまざま薬を用ゆれども落ちず。後には―になり」
えちご【越後】ヱチ‥
旧国名。今の新潟県の大部分。古名、こしのみちのしり。
⇒えちご‐かたびら【越後帷子】
⇒えちご‐さらし【越後晒】
⇒えちご‐じし【越後獅子】
⇒えちご‐じょうふ【越後上布】
⇒えちご‐ちぢみ【越後縮】
⇒えちご‐ぬの【越後布】
⇒えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】
⇒えちご‐ふで【越後筆】
⇒えちご‐へいや【越後平野】
⇒えちご‐や【越後屋】
⇒えちご‐ゆざわ【越後湯沢】
⇒えちご‐りゅう【越後流】
えちご‐かたびら【越後帷子】ヱチ‥
越後国小千谷おぢやから産出する上布じょうふまたは縮ちぢみのかたびら。→越後上布→越後縮ちぢみ。
⇒えちご【越後】
えちご‐さらし【越後晒】ヱチ‥
(→)越後上布に同じ。好色一代男3「二布は―、赤染にして」
⇒えちご【越後】
えちご‐じし【越後獅子】ヱチ‥
①越後国西蒲原郡の神社の里神楽の獅子舞。
②越後国西蒲原郡月潟地方から出る獅子舞。子供が小さい獅子頭をかぶり、身をそらせ、逆立ちで歩くなどの芸をしながら、銭を乞いあるく。蒲原獅子。角兵衛獅子。
③地歌。2を題材とする。天明(1781〜1789)頃、峰崎勾当作曲。箏の手付には市浦検校作曲と八重崎検校作曲の2曲がある。
④歌舞伎舞踊。長唄。七変化舞踊「遅桜手爾葉七字おそざくらてにはのななもじ」の一部。篠田金次作詞、9世杵屋六左衛門作曲。1811年(文化8)初演。地歌を取り入れたもので、越後の角兵衛獅子が浜唄・おけさ踊り・布晒ぬのざらしなどの諸芸を見せる。
⇒えちご【越後】
えちご‐じょうふ【越後上布】ヱチ‥ジヤウ‥
江戸時代、越後国小千谷おぢや付近から苧からむしの繊維を用いて織り出した上質な麻織物の総称。雪晒さらしに特徴がある。越後晒。
⇒えちご【越後】
えちご‐ちぢみ【越後縮】ヱチ‥
越後国小千谷おぢや地方から出す縮。苧からむしで織った夏着尺きじゃく。おぢやちぢみ。越後布。
⇒えちご【越後】
えちご‐ぬの【越後布】ヱチ‥
(→)越後縮ちぢみに同じ。
⇒えちご【越後】
えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】ヱチ‥
越後地方に伝承された七つの不思議な現象。臭水くそうず(石油。柄目木がらめきの火など)・鎌鼬かまいたち・波の題目・逆さ竹・八房梅やつぶさうめ・赤坊主八滝・弘智法師遺骸ほか諸説ある。
⇒えちご【越後】
えちご‐ふで【越後筆】ヱチ‥
越後村松藩内などで製作した筆。のち見附市に移る。
⇒えちご【越後】
えちご‐へいや【越後平野】ヱチ‥
新潟平野の別称。
⇒えちご【越後】
えちご‐や【越後屋】ヱチ‥
(祖先が越後守高次といったことからの名という)伊勢商人三井高利が経営した呉服店。本店は京都。江戸・大坂に店を置く。江戸店は1673年(延宝1)江戸本町に開店、83年(天和3)日本橋駿河町に移転。今の三越の前身。
⇒えちご【越後】
えちご‐ゆざわ【越後湯沢】ヱチ‥ザハ
「湯沢2」参照。
⇒えちご【越後】
えちご‐りゅう【越後流】ヱチ‥リウ
上杉謙信の采配を規範とする軍学の一派。謙信の将、宇佐美駿河守定行を祖とする宇佐美流・神徳流、越後の沢崎主水もんどを祖とする要門流などに分流。謙信流。
⇒えちご【越後】
え‐ちず【絵地図】ヱ‥ヅ
記号を用いず、絵をかいて表した地図。
えちぜん【越前】ヱチ‥
①旧国名。今の福井県の東部。古名、こしのみちのくち。
②福井県中部の市。刃物・和紙などの伝統産業のほか、電子・機械・繊維工業も立地。人口8万8千。
⇒えちぜん‐がに【越前蟹】
⇒えちぜん‐がみ【越前紙】
⇒えちぜん‐くらげ【越前水母】
えちぜん‐がに【越前蟹】ヱチ‥
ズワイガニの、越前一帯で水揚げするものの称。
⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐がみ【越前紙】ヱチ‥
上古以来、現今に至るまで福井県越前市今立を中心として越前各地で産出してきた和紙。奉書紙は特に優秀。
越前美術紙
撮影:関戸 勇
⇒エチオピア【Ethiopia】
エチカ【Ethica】
(「倫理学」の意)スピノザの主著。1675年頃完成。77年刊行。幾何学の秩序にしたがって論証するという仕方で、形而上学、精神と認識、感情、倫理学、人間の自由と至福などの広い領域を体系的に論じている。
えちかわ‐や【越川屋】ヱチカハ‥
江戸上野池之端仲町にあった袋物屋。
エチケット【etiquette】
①礼儀。作法。礼法。ベルツ、ベルツの日記「日本では西洋人の間で…礼式エチケットがあまり厳格に守られておらず」。「食卓での―」「―に反する」
②ワインの瓶のラベル。
えち‐ご【越期】ヱチ‥
ある時期を越えて長く続くこと。手遅れになること。おつご。狂歌咄「さまざま薬を用ゆれども落ちず。後には―になり」
えちご【越後】ヱチ‥
旧国名。今の新潟県の大部分。古名、こしのみちのしり。
⇒えちご‐かたびら【越後帷子】
⇒えちご‐さらし【越後晒】
⇒えちご‐じし【越後獅子】
⇒えちご‐じょうふ【越後上布】
⇒えちご‐ちぢみ【越後縮】
⇒えちご‐ぬの【越後布】
⇒えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】
⇒えちご‐ふで【越後筆】
⇒えちご‐へいや【越後平野】
⇒えちご‐や【越後屋】
⇒えちご‐ゆざわ【越後湯沢】
⇒えちご‐りゅう【越後流】
えちご‐かたびら【越後帷子】ヱチ‥
越後国小千谷おぢやから産出する上布じょうふまたは縮ちぢみのかたびら。→越後上布→越後縮ちぢみ。
⇒えちご【越後】
えちご‐さらし【越後晒】ヱチ‥
(→)越後上布に同じ。好色一代男3「二布は―、赤染にして」
⇒えちご【越後】
えちご‐じし【越後獅子】ヱチ‥
①越後国西蒲原郡の神社の里神楽の獅子舞。
②越後国西蒲原郡月潟地方から出る獅子舞。子供が小さい獅子頭をかぶり、身をそらせ、逆立ちで歩くなどの芸をしながら、銭を乞いあるく。蒲原獅子。角兵衛獅子。
③地歌。2を題材とする。天明(1781〜1789)頃、峰崎勾当作曲。箏の手付には市浦検校作曲と八重崎検校作曲の2曲がある。
④歌舞伎舞踊。長唄。七変化舞踊「遅桜手爾葉七字おそざくらてにはのななもじ」の一部。篠田金次作詞、9世杵屋六左衛門作曲。1811年(文化8)初演。地歌を取り入れたもので、越後の角兵衛獅子が浜唄・おけさ踊り・布晒ぬのざらしなどの諸芸を見せる。
⇒えちご【越後】
えちご‐じょうふ【越後上布】ヱチ‥ジヤウ‥
江戸時代、越後国小千谷おぢや付近から苧からむしの繊維を用いて織り出した上質な麻織物の総称。雪晒さらしに特徴がある。越後晒。
⇒えちご【越後】
えちご‐ちぢみ【越後縮】ヱチ‥
越後国小千谷おぢや地方から出す縮。苧からむしで織った夏着尺きじゃく。おぢやちぢみ。越後布。
⇒えちご【越後】
えちご‐ぬの【越後布】ヱチ‥
(→)越後縮ちぢみに同じ。
⇒えちご【越後】
えちご‐の‐ななふしぎ【越後の七不思議】ヱチ‥
越後地方に伝承された七つの不思議な現象。臭水くそうず(石油。柄目木がらめきの火など)・鎌鼬かまいたち・波の題目・逆さ竹・八房梅やつぶさうめ・赤坊主八滝・弘智法師遺骸ほか諸説ある。
⇒えちご【越後】
えちご‐ふで【越後筆】ヱチ‥
越後村松藩内などで製作した筆。のち見附市に移る。
⇒えちご【越後】
えちご‐へいや【越後平野】ヱチ‥
新潟平野の別称。
⇒えちご【越後】
えちご‐や【越後屋】ヱチ‥
(祖先が越後守高次といったことからの名という)伊勢商人三井高利が経営した呉服店。本店は京都。江戸・大坂に店を置く。江戸店は1673年(延宝1)江戸本町に開店、83年(天和3)日本橋駿河町に移転。今の三越の前身。
⇒えちご【越後】
えちご‐ゆざわ【越後湯沢】ヱチ‥ザハ
「湯沢2」参照。
⇒えちご【越後】
えちご‐りゅう【越後流】ヱチ‥リウ
上杉謙信の采配を規範とする軍学の一派。謙信の将、宇佐美駿河守定行を祖とする宇佐美流・神徳流、越後の沢崎主水もんどを祖とする要門流などに分流。謙信流。
⇒えちご【越後】
え‐ちず【絵地図】ヱ‥ヅ
記号を用いず、絵をかいて表した地図。
えちぜん【越前】ヱチ‥
①旧国名。今の福井県の東部。古名、こしのみちのくち。
②福井県中部の市。刃物・和紙などの伝統産業のほか、電子・機械・繊維工業も立地。人口8万8千。
⇒えちぜん‐がに【越前蟹】
⇒えちぜん‐がみ【越前紙】
⇒えちぜん‐くらげ【越前水母】
えちぜん‐がに【越前蟹】ヱチ‥
ズワイガニの、越前一帯で水揚げするものの称。
⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐がみ【越前紙】ヱチ‥
上古以来、現今に至るまで福井県越前市今立を中心として越前各地で産出してきた和紙。奉書紙は特に優秀。
越前美術紙
撮影:関戸 勇
 ⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐くらげ【越前水母】ヱチ‥
ビゼンクラゲ目の鉢虫類。傘部は厚い寒天質で、下面に口を囲んで8本の口腕がある。直径1メートル、重さ150キログラムに達する。淡褐色。東シナ海から日本海に流入し、越前では古くから知られる。食用。
⇒えちぜん【越前】
えち‐もの
姿ばかりを飾って役に立たない柔弱な者。甲陽軍鑑13「―と申すは、小袖諸道具をもいつくしくばかり思案して、女の好むやうに仕り、微若なる奴を―とて、何の役にもたたぬ臆病者にて」
エチモロジー【etymology】
①語の起源・歴史。語源。
②語源の研究。語源学。
エチュード【étude フランス】
①〔音〕楽器の練習のために作られた楽曲。芸術的なものもある。練習曲。
→エチュード 「黒鍵」Op.10-5
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②〔美〕習作。↔タブロー
え‐ぢょうちん【絵提灯】ヱヂヤウ‥
吉野紙などの薄紙を張って絵を描いた提灯。夏の夜、軒先などに吊して点火する。岐阜提灯が有名。
エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
〔化〕アルキル基の一つ。化学式‐C2H5
⇒エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
⇒エチル‐エーテル【ethyl ether】
エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
アルコール類の一つ。分子式C2H5OH 無色透明、特有の香りと味を持つ液体。揮発しやすく燃えやすい。糖類のアルコール発酵により生成し、酒類の成分となる。工業的にはエチレンを原料として合成し、溶剤、燃料、種々の化学薬品の合成原料となる。単にアルコールともいう。酒精。エタノール。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチル‐エーテル【ethyl ether】
分子式(C2H5)2O エーテル類の一つ。アルコールに濃硫酸を加え蒸留して製する無色の液体。特異な香気をもち、揮発しやすく燃えやすい。麻酔性がある。溶剤としての用途が広く、医薬にも用いる。ジエチル‐エーテルまたは単にエーテルともいう。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
分子式H2C=CH2 炭化水素の一つ。無色可燃性の気体。アルコールと濃硫酸とを熱すると生じる。工業的にはエタンの脱水素またはナフサの熱分解によって製する。石油化学工業の重要な基礎原料。また、植物中に生成し、植物ホルモンの一つとして果実の成熟、落葉・落果の促進などの生理作用を示す。生油気せいゆき。エテン。
⇒エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
⇒エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
⇒エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】
⇒エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
⇒エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
⇒エチレン‐プロピレン‐ゴム
エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
環状エーテルの一つ。分子式C2H4O 芳香のある無色の気体。反応性に富み爆発性をもつ。エチレンを触媒の存在下で酸化して合成する。石油化学工業における重要な中間体で、エチレン‐グリコールや界面活性剤(ポリエチレン‐オキシド)の製造に用いる。酸化エチレン。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
分子式HOCH2CH2OH 最も簡単な2価アルコール。無色粘稠ねんちゅう性の甘味ある液体。吸湿性が強い。主としてエチレン‐オキシドと水との反応により製する。エンジン冷却水の不凍液に用いるほか、合成繊維(ポリエステル)の原料。単にグリコールともいう。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】‥クワ‥
(→)オレフィンに同じ。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
アンモニアのような臭気をもつ無色の液体。水とは任意の割合で混ざる。強塩基性。分子式H2NCH2CH2NH2 2座配位子として金属原子に配位して錯体をつくりやすい。配位子としてはenと略記。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
(ethylenediaminetetraacetic acid)EDTAと略記。エチレン‐ジアミンとクロロ酢酸との反応によってつくられる四塩基酸。無色の結晶性粉末。化学式(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 水に溶け、アルカリ土類金属イオンを含む多くの金属イオンと安定な水溶性の錯体(キレート)を形成。金属イオンの分析、有毒金属の除去などに用いる。エデト酸。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐プロピレン‐ゴム
(ethylene-propyrene rubber)エチレンとプロピレンとを共重合させて得られる合成ゴム。耐熱性・耐寒性・耐水性・電気的性質に優れる。車両部品・建材・電線被覆などに利用。EPR
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
えっ
〔感〕
①呼びかける声。えい。
②意外のことに驚いて発する声。
えつ【斉魚】
カタクチイワシ科の海産の硬骨魚。食用。有明海および周辺の河川の特産。
えつ【悦】
喜ぶこと。嬉しがること。機嫌のよいこと。
⇒悦に入る
えつ【粤】ヱツ
①(「越」とも書く)中国南部に広く分布した南方系の少数民族およびその国名。百粤・於越・甌おう越・閩びん越などがある。
②広東省の別称。
えつ【越】ヱツ
①春秋戦国時代、列国の一つ。はじめ中国東南の少数民族から出たと考えられる。隣国呉と抗争、前473年、勾践こうせんは呉王夫差を破り、会稽に都し、浙江・江蘇・山東に覇を唱えたが、楚の威王に滅ぼされた。( 〜前257頃)
②浙江省の別称。
③越南の略。ベトナムのこと。「中―国境」
④越国こしのくにの略。「―中」
えつ【鉞】ヱツ
まさかり。古代中国では、青銅製の大型の斧。罪人の首や腰を斬った。「斧ふ―を加える」
えつ【謁】
貴人または目上の人に面会すること。まみえること。おめみえ。「―を賜う」
えつ【閲】
一々目を通してしらべること。「―を乞う」
え‐つう【会通】ヱ‥
〔仏〕一見矛盾対立するように見える説を合わせて互いに意味が通ずるようにさせること。調和的解釈を施すこと。会釈。
えっ‐か【液化】エキクワ
⇒えきか
エッカーマン【Johann Peter Eckermann】
ゲーテ晩年の秘書。作「ゲーテとの対話」で文豪の日常と言動を伝えた。(1792〜1854)
えっ‐かい【越階】ヱツ‥
⇒おっかい
えつ‐かいかん【粤海関】‥クワン
清代、1685年広州に設置された海関。海禁解除に伴って設立され、交易は公行という特許商人が担い、関税の徴収も引き受けた。
えっ‐き【悦喜】
喜ぶこと。好色一代女1「―鼻の先にあらはなり」
え‐つき【役調・課役】
えだちとみつぎ。古代の夫役と貢物。万葉集16「里長さとおさが―徴はたらば」
え‐づき【餌付】ヱ‥
えづくこと。
えっ‐きょう【越境】ヱツキヤウ
境界線や国境などを越えること。おっきょう。
⇒えっきょう‐にゅうがく【越境入学】
えっきょう‐にゅうがく【越境入学】ヱツキヤウニフ‥
定められた学区の境界を越えて、他の学区の学校に入学すること。
⇒えっ‐きょう【越境】
エッグ【egg】
卵。鶏卵。「スクランブル‐―」
⇒エッグ‐ノッグ【eggnog】
え‐づ・く【餌付く】ヱ‥
〔自五〕
小鳥や家畜などが、馴れてえさを食べるようになる。
え‐づくし【絵尽し】ヱ‥
江戸時代の歌舞伎・浄瑠璃の舞台面を絵画化し、文字を散らした小冊子。歌舞伎絵尽・浄瑠璃絵尽がある。江戸歌舞伎のものは絵本番付ともいう。
エックス【X・x】
①アルファベットの24番目の文字。
②数学で未知数の符号。転じて、未知の物事。
③ローマ数字の10。
エックス‐エム‐エル【XML】
(Extensible Markup Language)構造化された文書やデータを記述するための書式表現言語の一つ。SGMLの文法を簡素化し欠点を解消したもので、独自の書式を定義する機能をもつ。コンピューターのデータ送受信のほか、文書の意味の表現などにも利用。
エックスオー‐ジャン【XO醤】
(中国語)中国料理の調味料の一つ。赤唐辛子・にんにく・エシャロット・干しえび・干し貝柱などを炒め合わせたもの。
エックス‐きゃく【X脚】
直立すると下肢かしが膝のところで外側に開きX字型を示す状態。両側の外反膝。↔O脚
エックス‐せん【X線】
(X-rays)電磁波の一種。ふつう波長が0.01〜10ナノメートルの間。1895年レントゲンが発見、未知の線という意味でX線と命名。物質透過能力・電離作用・写真感光作用・化学作用・生理作用などが強く、干渉・回折などの現象を生じるので、結晶構造の研究、スペクトル分析、医療などに応用。レントゲン線。→電磁波(図)。
⇒エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】
⇒エックスせん‐かん【X線管】
⇒エックスせん‐しゃしん【X線写真】
⇒エックスせん‐てんたい【X線天体】
⇒エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
⇒エックスせん‐バースト【X線バースト】
エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】‥クワイ‥ハフ
X線を結晶で回折させ、これを解析して結晶構造を解明する方法。非晶質・液体・生物・DNAの構造解析にも利用。X線回折。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐かん【X線管】‥クワン
X線を発生させるための真空管。陰極から放出される電子を高電圧で加速し、これをタングステン・銅などの陽極(対陰極)に衝突させて、そこから発生させる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐しゃしん【X線写真】
X線を用いて撮影した写真。レントゲン写真。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐せんしょくたい【X染色体】
性染色体の一つ。Y染色体に対立する。接合子でX染色体同士が対となったとき一方の性を決定し、XYが対となったときには他方の性を決定する。普通、ホモ接合体が雌性となる場合にいい、雄性となる場合にはZ染色体とも呼ぶ。→Y染色体
エックスせん‐てんたい【X線天体】
X線を放射する天体。中性子星・ブラック‐ホール・超新星残骸・クエーサーなど。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
X線天体を観測・研究する天文学の一分野。人工衛星・気球などに搭載したX線検出器により観測する。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐バースト【X線バースト】
(X-ray burst)天体から短時間に爆発的にX線が放出される現象。連星系中の中性子星やブラック‐ホールが起こすと考えられる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐デー
(和製語X day)いつかは定かでないが近い将来重大な出来事が実際に起こるとされる日。また、計画を実行する予定の日。
エックスバー‐りろん【エックスバー理論】
〔言〕(X-bar theory)生成文法の用語。言語では、どの種類の句の構造も階層的な構造をなしており、その構成がよく類似している。そうした類似性を変項Xと横棒(バー)を用いて表記することにより捉えようとする理論。
エッグ‐ノッグ【eggnog】
卵・牛乳・砂糖を攪拌した飲み物。また、それにブランデーやラムを加えたカクテル。温・冷2種類がある。
⇒エッグ【egg】
エックハルト【Johannes Eckhart】
(通称Meister E.)ドイツの神学者。ドミニコ会に属する神秘主義者。新プラトン主義的な思想の流れの中で、魂の根底において神に触れることを介しての、神の子キリストとの神秘的合一を説いた。(1260頃〜1328頃)
え‐つけ【絵付】ヱ‥
陶磁器の表面に絵具で彩飾を施すこと。釉うわぐすりの下に焼きつけるのを下絵付、上に焼きつけるのを上絵付という。
え‐づけ【餌付け】ヱ‥
人に馴れにくい野生の動物を、人から餌をもらうまでに馴れさせること。
えつ‐げき【越劇】ヱツ‥
中国、浙江省紹興地方より起こった演劇。上海に進出して女優劇となる。
エッケ‐ホモ【ecce homo ラテン】
(「見よ、この人を」の意)新約聖書(ウルガタ訳)で、ピラトがイエスをユダヤ民衆の前に引き出した時の言葉。
エッケルト【Franz Eckert】
ドイツの音楽家。1879年(明治12)来日、海軍軍務局・宮内省雅楽所に勤務、また文部省音楽取調掛に出向。軍楽隊を養成。(1852〜1916)
えっ‐けん【越権】ヱツ‥
権限をこえて事を行うこと。おっけん。「―行為」
⇒えっけん‐だいり【越権代理】
えっ‐けん【謁見】
貴人または目上の人に面会すること。「大統領に―する」「―を賜る」
えっけん‐だいり【越権代理】ヱツ‥
〔法〕代理人の権限の範囲を越える代理行為。相手方がそれを権限内の行為と信じたことに正当な理由があると、その効果は本人に及ぶ。
⇒えっ‐けん【越権】
えつ‐ごく【越獄】ヱツ‥
⇒おつごく
えっさ
〔感〕
重い物を動かす時などの掛け声。また、調子をつけるはやし声。
えっ‐さい【悦哉・雀
⇒えちぜん【越前】
えちぜん‐くらげ【越前水母】ヱチ‥
ビゼンクラゲ目の鉢虫類。傘部は厚い寒天質で、下面に口を囲んで8本の口腕がある。直径1メートル、重さ150キログラムに達する。淡褐色。東シナ海から日本海に流入し、越前では古くから知られる。食用。
⇒えちぜん【越前】
えち‐もの
姿ばかりを飾って役に立たない柔弱な者。甲陽軍鑑13「―と申すは、小袖諸道具をもいつくしくばかり思案して、女の好むやうに仕り、微若なる奴を―とて、何の役にもたたぬ臆病者にて」
エチモロジー【etymology】
①語の起源・歴史。語源。
②語源の研究。語源学。
エチュード【étude フランス】
①〔音〕楽器の練習のために作られた楽曲。芸術的なものもある。練習曲。
→エチュード 「黒鍵」Op.10-5
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②〔美〕習作。↔タブロー
え‐ぢょうちん【絵提灯】ヱヂヤウ‥
吉野紙などの薄紙を張って絵を描いた提灯。夏の夜、軒先などに吊して点火する。岐阜提灯が有名。
エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
〔化〕アルキル基の一つ。化学式‐C2H5
⇒エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
⇒エチル‐エーテル【ethyl ether】
エチル‐アルコール【ethyl alcohol】
アルコール類の一つ。分子式C2H5OH 無色透明、特有の香りと味を持つ液体。揮発しやすく燃えやすい。糖類のアルコール発酵により生成し、酒類の成分となる。工業的にはエチレンを原料として合成し、溶剤、燃料、種々の化学薬品の合成原料となる。単にアルコールともいう。酒精。エタノール。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチル‐エーテル【ethyl ether】
分子式(C2H5)2O エーテル類の一つ。アルコールに濃硫酸を加え蒸留して製する無色の液体。特異な香気をもち、揮発しやすく燃えやすい。麻酔性がある。溶剤としての用途が広く、医薬にも用いる。ジエチル‐エーテルまたは単にエーテルともいう。
⇒エチル【Äthyl ドイツ・ethyl イギリス】
エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
分子式H2C=CH2 炭化水素の一つ。無色可燃性の気体。アルコールと濃硫酸とを熱すると生じる。工業的にはエタンの脱水素またはナフサの熱分解によって製する。石油化学工業の重要な基礎原料。また、植物中に生成し、植物ホルモンの一つとして果実の成熟、落葉・落果の促進などの生理作用を示す。生油気せいゆき。エテン。
⇒エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
⇒エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
⇒エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】
⇒エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
⇒エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
⇒エチレン‐プロピレン‐ゴム
エチレン‐オキシド【ethylene oxide】
環状エーテルの一つ。分子式C2H4O 芳香のある無色の気体。反応性に富み爆発性をもつ。エチレンを触媒の存在下で酸化して合成する。石油化学工業における重要な中間体で、エチレン‐グリコールや界面活性剤(ポリエチレン‐オキシド)の製造に用いる。酸化エチレン。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐グリコール【ethylene glycol】
分子式HOCH2CH2OH 最も簡単な2価アルコール。無色粘稠ねんちゅう性の甘味ある液体。吸湿性が強い。主としてエチレン‐オキシドと水との反応により製する。エンジン冷却水の不凍液に用いるほか、合成繊維(ポリエステル)の原料。単にグリコールともいう。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレンけい‐たんかすいそ【エチレン系炭化水素】‥クワ‥
(→)オレフィンに同じ。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン【ethylenediamine】
アンモニアのような臭気をもつ無色の液体。水とは任意の割合で混ざる。強塩基性。分子式H2NCH2CH2NH2 2座配位子として金属原子に配位して錯体をつくりやすい。配位子としてはenと略記。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐ジアミン‐しさくさん【エチレンジアミン四酢酸】
(ethylenediaminetetraacetic acid)EDTAと略記。エチレン‐ジアミンとクロロ酢酸との反応によってつくられる四塩基酸。無色の結晶性粉末。化学式(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 水に溶け、アルカリ土類金属イオンを含む多くの金属イオンと安定な水溶性の錯体(キレート)を形成。金属イオンの分析、有毒金属の除去などに用いる。エデト酸。
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
エチレン‐プロピレン‐ゴム
(ethylene-propyrene rubber)エチレンとプロピレンとを共重合させて得られる合成ゴム。耐熱性・耐寒性・耐水性・電気的性質に優れる。車両部品・建材・電線被覆などに利用。EPR
⇒エチレン【Äthylen ドイツ・ethylene イギリス】
えっ
〔感〕
①呼びかける声。えい。
②意外のことに驚いて発する声。
えつ【斉魚】
カタクチイワシ科の海産の硬骨魚。食用。有明海および周辺の河川の特産。
えつ【悦】
喜ぶこと。嬉しがること。機嫌のよいこと。
⇒悦に入る
えつ【粤】ヱツ
①(「越」とも書く)中国南部に広く分布した南方系の少数民族およびその国名。百粤・於越・甌おう越・閩びん越などがある。
②広東省の別称。
えつ【越】ヱツ
①春秋戦国時代、列国の一つ。はじめ中国東南の少数民族から出たと考えられる。隣国呉と抗争、前473年、勾践こうせんは呉王夫差を破り、会稽に都し、浙江・江蘇・山東に覇を唱えたが、楚の威王に滅ぼされた。( 〜前257頃)
②浙江省の別称。
③越南の略。ベトナムのこと。「中―国境」
④越国こしのくにの略。「―中」
えつ【鉞】ヱツ
まさかり。古代中国では、青銅製の大型の斧。罪人の首や腰を斬った。「斧ふ―を加える」
えつ【謁】
貴人または目上の人に面会すること。まみえること。おめみえ。「―を賜う」
えつ【閲】
一々目を通してしらべること。「―を乞う」
え‐つう【会通】ヱ‥
〔仏〕一見矛盾対立するように見える説を合わせて互いに意味が通ずるようにさせること。調和的解釈を施すこと。会釈。
えっ‐か【液化】エキクワ
⇒えきか
エッカーマン【Johann Peter Eckermann】
ゲーテ晩年の秘書。作「ゲーテとの対話」で文豪の日常と言動を伝えた。(1792〜1854)
えっ‐かい【越階】ヱツ‥
⇒おっかい
えつ‐かいかん【粤海関】‥クワン
清代、1685年広州に設置された海関。海禁解除に伴って設立され、交易は公行という特許商人が担い、関税の徴収も引き受けた。
えっ‐き【悦喜】
喜ぶこと。好色一代女1「―鼻の先にあらはなり」
え‐つき【役調・課役】
えだちとみつぎ。古代の夫役と貢物。万葉集16「里長さとおさが―徴はたらば」
え‐づき【餌付】ヱ‥
えづくこと。
えっ‐きょう【越境】ヱツキヤウ
境界線や国境などを越えること。おっきょう。
⇒えっきょう‐にゅうがく【越境入学】
えっきょう‐にゅうがく【越境入学】ヱツキヤウニフ‥
定められた学区の境界を越えて、他の学区の学校に入学すること。
⇒えっ‐きょう【越境】
エッグ【egg】
卵。鶏卵。「スクランブル‐―」
⇒エッグ‐ノッグ【eggnog】
え‐づ・く【餌付く】ヱ‥
〔自五〕
小鳥や家畜などが、馴れてえさを食べるようになる。
え‐づくし【絵尽し】ヱ‥
江戸時代の歌舞伎・浄瑠璃の舞台面を絵画化し、文字を散らした小冊子。歌舞伎絵尽・浄瑠璃絵尽がある。江戸歌舞伎のものは絵本番付ともいう。
エックス【X・x】
①アルファベットの24番目の文字。
②数学で未知数の符号。転じて、未知の物事。
③ローマ数字の10。
エックス‐エム‐エル【XML】
(Extensible Markup Language)構造化された文書やデータを記述するための書式表現言語の一つ。SGMLの文法を簡素化し欠点を解消したもので、独自の書式を定義する機能をもつ。コンピューターのデータ送受信のほか、文書の意味の表現などにも利用。
エックスオー‐ジャン【XO醤】
(中国語)中国料理の調味料の一つ。赤唐辛子・にんにく・エシャロット・干しえび・干し貝柱などを炒め合わせたもの。
エックス‐きゃく【X脚】
直立すると下肢かしが膝のところで外側に開きX字型を示す状態。両側の外反膝。↔O脚
エックス‐せん【X線】
(X-rays)電磁波の一種。ふつう波長が0.01〜10ナノメートルの間。1895年レントゲンが発見、未知の線という意味でX線と命名。物質透過能力・電離作用・写真感光作用・化学作用・生理作用などが強く、干渉・回折などの現象を生じるので、結晶構造の研究、スペクトル分析、医療などに応用。レントゲン線。→電磁波(図)。
⇒エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】
⇒エックスせん‐かん【X線管】
⇒エックスせん‐しゃしん【X線写真】
⇒エックスせん‐てんたい【X線天体】
⇒エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
⇒エックスせん‐バースト【X線バースト】
エックスせん‐かいせつほう【X線回折法】‥クワイ‥ハフ
X線を結晶で回折させ、これを解析して結晶構造を解明する方法。非晶質・液体・生物・DNAの構造解析にも利用。X線回折。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐かん【X線管】‥クワン
X線を発生させるための真空管。陰極から放出される電子を高電圧で加速し、これをタングステン・銅などの陽極(対陰極)に衝突させて、そこから発生させる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐しゃしん【X線写真】
X線を用いて撮影した写真。レントゲン写真。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐せんしょくたい【X染色体】
性染色体の一つ。Y染色体に対立する。接合子でX染色体同士が対となったとき一方の性を決定し、XYが対となったときには他方の性を決定する。普通、ホモ接合体が雌性となる場合にいい、雄性となる場合にはZ染色体とも呼ぶ。→Y染色体
エックスせん‐てんたい【X線天体】
X線を放射する天体。中性子星・ブラック‐ホール・超新星残骸・クエーサーなど。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐てんもんがく【X線天文学】
X線天体を観測・研究する天文学の一分野。人工衛星・気球などに搭載したX線検出器により観測する。
⇒エックス‐せん【X線】
エックスせん‐バースト【X線バースト】
(X-ray burst)天体から短時間に爆発的にX線が放出される現象。連星系中の中性子星やブラック‐ホールが起こすと考えられる。
⇒エックス‐せん【X線】
エックス‐デー
(和製語X day)いつかは定かでないが近い将来重大な出来事が実際に起こるとされる日。また、計画を実行する予定の日。
エックスバー‐りろん【エックスバー理論】
〔言〕(X-bar theory)生成文法の用語。言語では、どの種類の句の構造も階層的な構造をなしており、その構成がよく類似している。そうした類似性を変項Xと横棒(バー)を用いて表記することにより捉えようとする理論。
エッグ‐ノッグ【eggnog】
卵・牛乳・砂糖を攪拌した飲み物。また、それにブランデーやラムを加えたカクテル。温・冷2種類がある。
⇒エッグ【egg】
エックハルト【Johannes Eckhart】
(通称Meister E.)ドイツの神学者。ドミニコ会に属する神秘主義者。新プラトン主義的な思想の流れの中で、魂の根底において神に触れることを介しての、神の子キリストとの神秘的合一を説いた。(1260頃〜1328頃)
え‐つけ【絵付】ヱ‥
陶磁器の表面に絵具で彩飾を施すこと。釉うわぐすりの下に焼きつけるのを下絵付、上に焼きつけるのを上絵付という。
え‐づけ【餌付け】ヱ‥
人に馴れにくい野生の動物を、人から餌をもらうまでに馴れさせること。
えつ‐げき【越劇】ヱツ‥
中国、浙江省紹興地方より起こった演劇。上海に進出して女優劇となる。
エッケ‐ホモ【ecce homo ラテン】
(「見よ、この人を」の意)新約聖書(ウルガタ訳)で、ピラトがイエスをユダヤ民衆の前に引き出した時の言葉。
エッケルト【Franz Eckert】
ドイツの音楽家。1879年(明治12)来日、海軍軍務局・宮内省雅楽所に勤務、また文部省音楽取調掛に出向。軍楽隊を養成。(1852〜1916)
えっ‐けん【越権】ヱツ‥
権限をこえて事を行うこと。おっけん。「―行為」
⇒えっけん‐だいり【越権代理】
えっ‐けん【謁見】
貴人または目上の人に面会すること。「大統領に―する」「―を賜る」
えっけん‐だいり【越権代理】ヱツ‥
〔法〕代理人の権限の範囲を越える代理行為。相手方がそれを権限内の行為と信じたことに正当な理由があると、その効果は本人に及ぶ。
⇒えっ‐けん【越権】
えつ‐ごく【越獄】ヱツ‥
⇒おつごく
えっさ
〔感〕
重い物を動かす時などの掛け声。また、調子をつけるはやし声。
えっ‐さい【悦哉・雀 】
〔動〕小形のタカの一種「つみ」の雄の俗称。
えっさっさ
〔感〕
物をかついで走る時の掛け声。また、そうした気持を表すはやしことば。
⇒えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
安政(1854〜1860)の頃、大坂で流行した一種の俗謡。また、岐阜県下呂市小坂町の盆踊り歌。
⇒えっさっさ
えっさら‐おっさら
大儀そうに歩いて行くさまにいう語。御苦労にも。わざわざ。えっちらおっちら。浮世風呂2「お弁当がおそいと宿まで取りに参りますわな。さうして―お師匠様へ持つてつてたべます」
エッジ【edge】
①端はし。ふち。へり。
②スキーの滑走面の両側の角。多く金属などで補強する。また、スケート靴の氷に接する面の両角。
⇒エッジ‐ボール【edge ball】
エッジ‐ボール【edge ball】
卓球で、ボールが相手側コートの縁に当たること。
⇒エッジ【edge】
えっ‐しゃ【謁者】
客の取次をする者。
エッシャー【Maurice Cornelis Escher】
オランダの版画家。独特の幾何学的方法論を駆使して、錯視的で幻想的な小宇宙を生み出す。(1898〜1972)
えっ‐しゅう【越州】ヱツシウ
越前・越中・越後の総称。
えっしゅう‐よう【越州窯】ヱツシウエウ
中国浙江省北部(古くは越)を中心とした、後漢代から宋代にかけての青磁窯。特に晩唐・五代の頃の青磁は秘色ひそくと称され著名。
えつじん【越人】ヱツ‥
⇒おちえつじん(越智越人)
えっ・する【謁する】
〔自サ変〕[文]謁す(サ変)
貴人・目上の人に面会する。お目にかかる。「竜顔に―・する」
えっ・する【閲する】
〔他サ変〕[文]閲す(サ変)
①しらべ見る。
②目をとおす。「草案を―・する」
③時間が経過する。「はや5年を―・し」
エッセイスト【essayist】
随筆家。
エッセー【essai フランス・essay イギリス】
①随筆。自由な形式で書かれた、思索性をもつ散文。
②試論。小論。
エッセネ‐は【エッセネ派】
(Essenes)イエス時代のユダヤ教三大教派の一つ。一切の財産を共有し、厳格な律法遵守の生活を営み、終末を待望した。死海写本中のクムラン文書を生み出した教団と同一視される。→サドカイ派→ファリサイ派
エッセン【essen ドイツ】
(旧制高校の学生語)食事すること。また、食べ物。
エッセン【Essen】
ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州、ルール工業地帯の中心都市。重工業が発達。クルップ財閥の根拠地。人口60万(1999)。
エッセンシャル【essential】
本質的。必須の。
⇒エッセンシャル‐オイル【essential oil】
エッセンシャル‐オイル【essential oil】
精油。
⇒エッセンシャル【essential】
エッセンス【essence】
①物事の本質。精髄。
②植物体から抽出した芳香性の精油。また、そのアルコール溶液。香油。「バニラ‐―」
えっ‐そ【越俎】ヱツ‥
[荘子逍遥遊](料理人が料理を怠っても、神主は酒樽や俎まないたを越うばって代りをするものではない意の原文から)自分の職分を越えて他人の権限内に立ち入ること。越権。「―の罪」
えっ‐そ【越訴】ヱツ‥
⇒おっそ
えつぞうちしん【閲蔵知津】‥ザウ‥
〔仏〕中国、明末の学僧智旭(1599〜1655)が、自ら閲覧した経論や注釈書・目録など1773部について解説した書。48巻。仏書の総合解説書。
えったヱツタ
「えた」の訛。〈日葡辞書〉
エッダ【Edda】
9〜13世紀に古アイスランド語で書かれたゲルマン神話や英雄伝説の集成。1643年にアイスランドで発見された。天地創造、神と巨人族との闘争を主な内容とする。韻文の古エッダとスノッリ=スツルルソン(Snorri Sturluson1178〜1241)が編纂した散文の新エッダ(「詩学の書」)とがある。
エッチ【H・h】
①アルファベットの8番目の文字。エイチ。
②〔化〕水素の元素記号。
③(hard)鉛筆の芯の硬さを表す符号。「2H」
④インダクタンスの単位ヘンリーの略号(H)。
⑤単位の接頭語ヘクト(hecto,102)の略号(h)。
⑥時間を表す単位、時(hour)の略号(h)。
⑦プランクの定数(h)。
⑧(「変態」のローマ字書きhentaiの略)
㋐性に関する言動が露骨でいやらしいさま。
㋑俗に、性交。
エッチ‐アール‐ず【HR図】‥ヅ
〔天〕(→)ヘルツシュプルング‐ラッセル図の略。
エッチ‐アイアン‐ほう【Hアイアン法】‥ハフ
(H-iron process)直接製鉄法の一つ。粉状の鉄鉱石を、流動炉で低温高圧水素中に浮遊懸濁させ、直接還元する。鉄分98パーセント以上のものが得られ、粉末冶金・溶接用鉄粉として使用。
エッチ‐アイ‐ブイ【HIV】
(human immunodeficiency virus)ヒト免疫不全ウイルス。レトロ‐ウイルス科レンチ‐ウイルス亜科に属するRNAウイルスで、エイズの病原。
エッチ‐エス‐ケー【HSK】
(「漢語水平考試」の拼音ピンイン表記Hanyu Shuiping Kaoshiの略)中国教育部(文部科学省に相当)認定の中国語(漢語)検定試験。中国語を母語としない人を対象とする。
エッチ‐エム‐ディー【HMD】
(head mounted display)立体映像装置の一種。頭に被ってバーチャル‐リアリティーを体験するための装置で、両眼の位置に小型のディスプレーを設置してある。
エッチ‐エル‐エー‐こうげん【HLA抗原】‥カウ‥
(human leukocyte antigen)ヒト白血球抗原。ヒトの個体を免疫学的に特徴づける抗原で、臓器や組織の移植の際、拒絶反応を起こすか否かの組織適合性に関与する(主要組織適合抗原)。クラスⅠ、Ⅱに大別。それらの機能と構造を決定する遺伝子複合体は第6染色体のHLA領域に存在。→組織適合抗原
エッチがた‐こう【H形鋼】‥カウ
形鋼の一種。断面がH形で、建物の梁や地下構造物の基礎工事用などに使われる。
エッチがた‐コンベヤー【H形コンベヤー】
切羽きりは運搬機の一種。断面がH形で床面に接して設置でき、また各種の採炭機をのせて動かせるので、カッペとともに切羽の完全機械化への道を開いた。パンツァ‐コンベヤー。
エッチ‐ツー‐ブロッカー【H2 blocker】
ヒスタミンのH2受容体への結合を阻害して胃酸分泌を抑制する薬。胃・十二指腸潰瘍などの治療に用いられる。
エッチ‐ティー‐エム‐エル【HTML】
(Hyper Text Markup Language)データ記述用言語の一つ。ウェブでハイパー‐テキスト文書、すなわちホームページの文書を作製・整形するためのもの。文字のほか音声・画像の扱いが可能で、ハイパー‐リンク機能を持つ。
エッチ‐ティー‐ティー‐ピー【HTTP】
(hypertext transfer protocol)プロトコル3の一種。ウェブ‐サーバーとウェブ‐ブラウザーの間などで、ハイパー‐テキストを通信するために用いられる。これにSSL暗号機能を付加したHTTPSは、ウェブを通じた個人情報の通信に使われる。
エッチ‐に‐エー‐ロケット【H‐ⅡAロケット】
日本製のロケット。日本が独自の技術で開発したH‐Ⅱロケットの改良型。
エッチ‐ビー【HB】
鉛筆の芯の硬さと濃さとを表す符号で、硬すぎず濃すぎない標準的なもの。
エッチ‐ビー‐プロセス【H. B. process】
多色平版の製版法。すりガラス上に色分解ポジを作り、修整ののち網ネガを作成し、感光液を塗布した亜鉛板に焼きつけて版とする。発明者のアメリカ人ヒューブナー(W. Huebner1886〜1966)と協力者ブライシュタイン(Breistein)の頭文字からの命名。
エッチ‐ブイ‐ばん【HV判】
写真感光材料の大きさの一つ。8.9センチメートル×15.8センチメートルの大きさに対する慣用名。HVは縦横の比率がハイビジョンと同じ9対16であることからいう。
えっちゅう【越中】ヱツ‥
①旧国名。今の富山県。こしのみちのなか。
②越中褌ふんどしの略。
⇒えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】
⇒えっちゅう‐じま【越中島】
⇒えっちゅう‐じま【越中縞】
⇒えっちゅう‐ふんどし【越中褌】
えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】ヱツ‥
(→)「おわら節」に同じ。
→文献資料[越中おわら節]
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中島】ヱツ‥
東京都江東区南西部の地区。江戸初期、榊原越中守の別邸所在地。隅田川河口東岸に位置し、1875年(明治8)日本最初の商船学校(現、東京海洋大学)が設置された。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中縞】ヱツ‥
越中福野・富山地方に産する縞木綿。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐ふんどし【越中褌】ヱツ‥
(細川越中守忠興の始めたものという)長さ1メートル程の小幅の布に紐をつけたふんどし。夏目漱石、坊つちやん「丸裸の―一つになつて」
⇒えっちゅう【越中】
えっ‐ちょう【越鳥】ヱツテウ
①中国、越の国の鳥。
②クジャクの異称。
⇒越鳥南枝に巣くう
】
〔動〕小形のタカの一種「つみ」の雄の俗称。
えっさっさ
〔感〕
物をかついで走る時の掛け声。また、そうした気持を表すはやしことば。
⇒えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
えっさっさ‐ぶし【えっさっさ節】
安政(1854〜1860)の頃、大坂で流行した一種の俗謡。また、岐阜県下呂市小坂町の盆踊り歌。
⇒えっさっさ
えっさら‐おっさら
大儀そうに歩いて行くさまにいう語。御苦労にも。わざわざ。えっちらおっちら。浮世風呂2「お弁当がおそいと宿まで取りに参りますわな。さうして―お師匠様へ持つてつてたべます」
エッジ【edge】
①端はし。ふち。へり。
②スキーの滑走面の両側の角。多く金属などで補強する。また、スケート靴の氷に接する面の両角。
⇒エッジ‐ボール【edge ball】
エッジ‐ボール【edge ball】
卓球で、ボールが相手側コートの縁に当たること。
⇒エッジ【edge】
えっ‐しゃ【謁者】
客の取次をする者。
エッシャー【Maurice Cornelis Escher】
オランダの版画家。独特の幾何学的方法論を駆使して、錯視的で幻想的な小宇宙を生み出す。(1898〜1972)
えっ‐しゅう【越州】ヱツシウ
越前・越中・越後の総称。
えっしゅう‐よう【越州窯】ヱツシウエウ
中国浙江省北部(古くは越)を中心とした、後漢代から宋代にかけての青磁窯。特に晩唐・五代の頃の青磁は秘色ひそくと称され著名。
えつじん【越人】ヱツ‥
⇒おちえつじん(越智越人)
えっ・する【謁する】
〔自サ変〕[文]謁す(サ変)
貴人・目上の人に面会する。お目にかかる。「竜顔に―・する」
えっ・する【閲する】
〔他サ変〕[文]閲す(サ変)
①しらべ見る。
②目をとおす。「草案を―・する」
③時間が経過する。「はや5年を―・し」
エッセイスト【essayist】
随筆家。
エッセー【essai フランス・essay イギリス】
①随筆。自由な形式で書かれた、思索性をもつ散文。
②試論。小論。
エッセネ‐は【エッセネ派】
(Essenes)イエス時代のユダヤ教三大教派の一つ。一切の財産を共有し、厳格な律法遵守の生活を営み、終末を待望した。死海写本中のクムラン文書を生み出した教団と同一視される。→サドカイ派→ファリサイ派
エッセン【essen ドイツ】
(旧制高校の学生語)食事すること。また、食べ物。
エッセン【Essen】
ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州、ルール工業地帯の中心都市。重工業が発達。クルップ財閥の根拠地。人口60万(1999)。
エッセンシャル【essential】
本質的。必須の。
⇒エッセンシャル‐オイル【essential oil】
エッセンシャル‐オイル【essential oil】
精油。
⇒エッセンシャル【essential】
エッセンス【essence】
①物事の本質。精髄。
②植物体から抽出した芳香性の精油。また、そのアルコール溶液。香油。「バニラ‐―」
えっ‐そ【越俎】ヱツ‥
[荘子逍遥遊](料理人が料理を怠っても、神主は酒樽や俎まないたを越うばって代りをするものではない意の原文から)自分の職分を越えて他人の権限内に立ち入ること。越権。「―の罪」
えっ‐そ【越訴】ヱツ‥
⇒おっそ
えつぞうちしん【閲蔵知津】‥ザウ‥
〔仏〕中国、明末の学僧智旭(1599〜1655)が、自ら閲覧した経論や注釈書・目録など1773部について解説した書。48巻。仏書の総合解説書。
えったヱツタ
「えた」の訛。〈日葡辞書〉
エッダ【Edda】
9〜13世紀に古アイスランド語で書かれたゲルマン神話や英雄伝説の集成。1643年にアイスランドで発見された。天地創造、神と巨人族との闘争を主な内容とする。韻文の古エッダとスノッリ=スツルルソン(Snorri Sturluson1178〜1241)が編纂した散文の新エッダ(「詩学の書」)とがある。
エッチ【H・h】
①アルファベットの8番目の文字。エイチ。
②〔化〕水素の元素記号。
③(hard)鉛筆の芯の硬さを表す符号。「2H」
④インダクタンスの単位ヘンリーの略号(H)。
⑤単位の接頭語ヘクト(hecto,102)の略号(h)。
⑥時間を表す単位、時(hour)の略号(h)。
⑦プランクの定数(h)。
⑧(「変態」のローマ字書きhentaiの略)
㋐性に関する言動が露骨でいやらしいさま。
㋑俗に、性交。
エッチ‐アール‐ず【HR図】‥ヅ
〔天〕(→)ヘルツシュプルング‐ラッセル図の略。
エッチ‐アイアン‐ほう【Hアイアン法】‥ハフ
(H-iron process)直接製鉄法の一つ。粉状の鉄鉱石を、流動炉で低温高圧水素中に浮遊懸濁させ、直接還元する。鉄分98パーセント以上のものが得られ、粉末冶金・溶接用鉄粉として使用。
エッチ‐アイ‐ブイ【HIV】
(human immunodeficiency virus)ヒト免疫不全ウイルス。レトロ‐ウイルス科レンチ‐ウイルス亜科に属するRNAウイルスで、エイズの病原。
エッチ‐エス‐ケー【HSK】
(「漢語水平考試」の拼音ピンイン表記Hanyu Shuiping Kaoshiの略)中国教育部(文部科学省に相当)認定の中国語(漢語)検定試験。中国語を母語としない人を対象とする。
エッチ‐エム‐ディー【HMD】
(head mounted display)立体映像装置の一種。頭に被ってバーチャル‐リアリティーを体験するための装置で、両眼の位置に小型のディスプレーを設置してある。
エッチ‐エル‐エー‐こうげん【HLA抗原】‥カウ‥
(human leukocyte antigen)ヒト白血球抗原。ヒトの個体を免疫学的に特徴づける抗原で、臓器や組織の移植の際、拒絶反応を起こすか否かの組織適合性に関与する(主要組織適合抗原)。クラスⅠ、Ⅱに大別。それらの機能と構造を決定する遺伝子複合体は第6染色体のHLA領域に存在。→組織適合抗原
エッチがた‐こう【H形鋼】‥カウ
形鋼の一種。断面がH形で、建物の梁や地下構造物の基礎工事用などに使われる。
エッチがた‐コンベヤー【H形コンベヤー】
切羽きりは運搬機の一種。断面がH形で床面に接して設置でき、また各種の採炭機をのせて動かせるので、カッペとともに切羽の完全機械化への道を開いた。パンツァ‐コンベヤー。
エッチ‐ツー‐ブロッカー【H2 blocker】
ヒスタミンのH2受容体への結合を阻害して胃酸分泌を抑制する薬。胃・十二指腸潰瘍などの治療に用いられる。
エッチ‐ティー‐エム‐エル【HTML】
(Hyper Text Markup Language)データ記述用言語の一つ。ウェブでハイパー‐テキスト文書、すなわちホームページの文書を作製・整形するためのもの。文字のほか音声・画像の扱いが可能で、ハイパー‐リンク機能を持つ。
エッチ‐ティー‐ティー‐ピー【HTTP】
(hypertext transfer protocol)プロトコル3の一種。ウェブ‐サーバーとウェブ‐ブラウザーの間などで、ハイパー‐テキストを通信するために用いられる。これにSSL暗号機能を付加したHTTPSは、ウェブを通じた個人情報の通信に使われる。
エッチ‐に‐エー‐ロケット【H‐ⅡAロケット】
日本製のロケット。日本が独自の技術で開発したH‐Ⅱロケットの改良型。
エッチ‐ビー【HB】
鉛筆の芯の硬さと濃さとを表す符号で、硬すぎず濃すぎない標準的なもの。
エッチ‐ビー‐プロセス【H. B. process】
多色平版の製版法。すりガラス上に色分解ポジを作り、修整ののち網ネガを作成し、感光液を塗布した亜鉛板に焼きつけて版とする。発明者のアメリカ人ヒューブナー(W. Huebner1886〜1966)と協力者ブライシュタイン(Breistein)の頭文字からの命名。
エッチ‐ブイ‐ばん【HV判】
写真感光材料の大きさの一つ。8.9センチメートル×15.8センチメートルの大きさに対する慣用名。HVは縦横の比率がハイビジョンと同じ9対16であることからいう。
えっちゅう【越中】ヱツ‥
①旧国名。今の富山県。こしのみちのなか。
②越中褌ふんどしの略。
⇒えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】
⇒えっちゅう‐じま【越中島】
⇒えっちゅう‐じま【越中縞】
⇒えっちゅう‐ふんどし【越中褌】
えっちゅう‐おわらぶし【越中おわら節】ヱツ‥
(→)「おわら節」に同じ。
→文献資料[越中おわら節]
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中島】ヱツ‥
東京都江東区南西部の地区。江戸初期、榊原越中守の別邸所在地。隅田川河口東岸に位置し、1875年(明治8)日本最初の商船学校(現、東京海洋大学)が設置された。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐じま【越中縞】ヱツ‥
越中福野・富山地方に産する縞木綿。
⇒えっちゅう【越中】
えっちゅう‐ふんどし【越中褌】ヱツ‥
(細川越中守忠興の始めたものという)長さ1メートル程の小幅の布に紐をつけたふんどし。夏目漱石、坊つちやん「丸裸の―一つになつて」
⇒えっちゅう【越中】
えっ‐ちょう【越鳥】ヱツテウ
①中国、越の国の鳥。
②クジャクの異称。
⇒越鳥南枝に巣くう
し【枝】🔗⭐🔉
し【枝】
①えだ。
②細長い物を数えるのに用いる語。「長刀1―」
し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン🔗⭐🔉
し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン
①(→)塔頭たっちゅう2に同じ。
②末寺。本寺に属する寺院をいう。
し‐おり【枝折】‥ヲリ🔗⭐🔉
し‐おり【枝折】‥ヲリ
①山道などで、木の枝を折りかけて帰りの道しるべとすること。新古今和歌集春「吉野山去年こぞの―の道変へて」
②枝折垣の略。
③枝折戸の略。
④城郭の異称。太閤記12「三の丸―ぎはまで追ひ入りしかども」
⇒しおり‐がき【枝折垣】
⇒しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】
しおり‐がき【枝折垣】‥ヲリ‥🔗⭐🔉
しおり‐がき【枝折垣】‥ヲリ‥
竹または木の枝を折りかけてつくった垣。
⇒し‐おり【枝折】
しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】‥ヲリ‥🔗⭐🔉
しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】‥ヲリ‥
竹または木の枝を折りかけてつくった、簡単な押し開き戸。
⇒し‐おり【枝折】
し‐お・る【枝折る・栞る】‥ヲル🔗⭐🔉
し‐お・る【枝折る・栞る】‥ヲル
〔他四〕
木の枝を折って道しるべとする。転じて、道案内をする。浜松中納言物語1「世のうさに―・らで入りし奥山に」
し‐かん【枝幹】🔗⭐🔉
し‐かん【枝幹】
①えだとみき。
②末と本。
し‐けい【枝茎】🔗⭐🔉
し‐けい【枝茎】
えだとくき。
し‐ご【枝梧】🔗⭐🔉
し‐ご【枝梧】
さしつかえ。また、くいちがい。郵便報知「―なく取計ふべし」
し‐じょう【枝条】‥デウ🔗⭐🔉
し‐じょう【枝条】‥デウ
えだ。
し‐ぞく【支族・枝族】🔗⭐🔉
し‐ぞく【支族・枝族】
本家から分かれ出た血族。分家。
し‐たい【支隊・枝隊】🔗⭐🔉
し‐たい【支隊・枝隊】
本隊から分かれた部隊。
しだれ【垂れ・枝垂れ】🔗⭐🔉
しだれ【垂れ・枝垂れ】
(シダル(下二)の連用形から)下に垂れること。しだり。
⇒しだれ‐いと【垂れ糸】
⇒しだれ‐いとすぎ【垂れ糸杉】
⇒しだれ‐うめ【垂れ梅】
⇒しだれ‐ざくら【垂れ桜】
⇒しだれ‐とりげ【垂れ鳥毛】
⇒しだれ‐は【垂れ葉】
⇒しだれ‐ひがん【垂れ彼岸】
⇒しだれ‐もも【垂れ桃】
⇒しだれ‐やなぎ【垂れ柳】
し‐とう【枝頭】🔗⭐🔉
し‐とう【枝頭】
枝の先端。〈日葡辞書〉
し‐よう【枝葉】‥エフ🔗⭐🔉
し‐よう【枝葉】‥エフ
①枝と葉。えだは。
②転じて、主要でない部分。「―にこだわる」
⇒しよう‐まっせつ【枝葉末節】
しよう‐まっせつ【枝葉末節】‥エフ‥🔗⭐🔉
しよう‐まっせつ【枝葉末節】‥エフ‥
物事の本質からはずれた、ささいな部分。「―の問題」
⇒し‐よう【枝葉】
し‐りん【支輪・枝輪】🔗⭐🔉
し‐りん【支輪・枝輪】
社寺建築の軒裏や折上おりあげ天井の斜めに立ち上がる部分。湾曲した竪木を並べ、裏に板を張る。しゅり。すり。
支輪


よ【枝】🔗⭐🔉
よ【枝】
(エの転)えだ。一説に花びら。万葉集8「この花のひと―のうちは百種の言こと持ちかねて折らえけらずや」
[漢]枝🔗⭐🔉
枝 字形
 筆順
筆順
 〔木部4画/8画/教育/2762・3B5E〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕えだ (名)え
[意味]
①木のえだ。「枝葉・剪枝せんし・桂林一枝」
②えだわかれ。(同)支。「枝流・枝隊」
▷(対)幹。
[解字]
形声。「木」+音符「支」(=分かれる)。幹から分かれ出た木のえだの意。
[下ツキ
幹枝・金枝玉葉・樹枝・楊枝・茘枝・連枝
〔木部4画/8画/教育/2762・3B5E〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕えだ (名)え
[意味]
①木のえだ。「枝葉・剪枝せんし・桂林一枝」
②えだわかれ。(同)支。「枝流・枝隊」
▷(対)幹。
[解字]
形声。「木」+音符「支」(=分かれる)。幹から分かれ出た木のえだの意。
[下ツキ
幹枝・金枝玉葉・樹枝・楊枝・茘枝・連枝
 筆順
筆順
 〔木部4画/8画/教育/2762・3B5E〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕えだ (名)え
[意味]
①木のえだ。「枝葉・剪枝せんし・桂林一枝」
②えだわかれ。(同)支。「枝流・枝隊」
▷(対)幹。
[解字]
形声。「木」+音符「支」(=分かれる)。幹から分かれ出た木のえだの意。
[下ツキ
幹枝・金枝玉葉・樹枝・楊枝・茘枝・連枝
〔木部4画/8画/教育/2762・3B5E〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕えだ (名)え
[意味]
①木のえだ。「枝葉・剪枝せんし・桂林一枝」
②えだわかれ。(同)支。「枝流・枝隊」
▷(対)幹。
[解字]
形声。「木」+音符「支」(=分かれる)。幹から分かれ出た木のえだの意。
[下ツキ
幹枝・金枝玉葉・樹枝・楊枝・茘枝・連枝
大辞林の検索結果 (71)
え【枝】🔗⭐🔉
え [0] 【枝】
えだ。「梅が―」
えだ【枝】🔗⭐🔉
えだ 【枝】
■一■ [0] (名)
(1)植物の主幹から分かれた茎。側芽や不定芽の発達したもの。「―が茂る」
(2)ものの本体・本筋から分かれ出たもの。「本筋からはずれた―の話」
(3)からだの手や足。四肢。「―を引き闕(カ)きて/古事記(中訓)」
(4)一族。子孫。「北家のすゑ,いまに―ひろごり給へり/大鏡(道長)」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)木の枝を数えるのに用いる。「一―の梅」
(2)細長い物を数えるのに用いる。「長持三十―/平家 10」
(3)〔昔,贈り物を木の枝に添えて差し出したことから〕
贈り物を数えるのに用いる。「雉一―奉らせ給ふ/源氏(行幸)」
えだ=の雪🔗⭐🔉
――の雪
〔晋の孫康が,枝に積もった雪を灯火の代わりにして書を読んだという「蒙求」の故事から〕
苦学すること。「窓の蛍を睦び,―を馴らし給ふ心ざし/源氏(乙女)」
えだ=を連(ツラ)・ぬ🔗⭐🔉
――を連(ツラ)・ぬ
〔「連枝」の訓読みから〕
兄弟の仲が親密であること。また,仲がよいことのたとえ。「頼朝も,ついには靡く,青柳の―・ぬる御契り/謡曲・船弁慶」
えだ=を鳴らさ ず🔗⭐🔉
ず🔗⭐🔉
――を鳴らさ ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「―
ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「― ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
 ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「―
ず
〔論衡(是応)〕
天下泰平のさま。世の中の平穏無事なさま。「― ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
ぬ御世なれや/謡曲・高砂」
えだ-うち【枝打ち】🔗⭐🔉
えだ-うち [0] 【枝打ち】 (名)スル
発育を促したり,節のないよい材を得るために樹木の下枝を切りはらうこと。枝下ろし。「庭木を―する」
えだ-うつり【枝移り】🔗⭐🔉
えだ-うつり [0] 【枝移り】 (名)スル
鳥などが枝から枝へと移ること。
えだ-おとり【枝劣り】🔗⭐🔉
えだ-おとり 【枝劣り】
〔幹より枝の方が劣っていることから〕
父祖より子孫の劣っていること。「もと見れば高き桂も今日よりや―すと人のいふらむ/宇津保(祭の使)」
えだ-おろし【枝下ろし】🔗⭐🔉
えだ-おろし [3] 【枝下ろし】 (名)スル
「枝打(エダウ)ち」に同じ。
えだ-がみ【枝神・裔神】🔗⭐🔉
えだ-がみ 【枝神・裔神】
末社に祀(マツ)られている神。
えだ-がわ【枝川】🔗⭐🔉
えだ-がわ ―ガハ [0] 【枝川】
(本流に対して)支流。
えだ-がわり【枝変(わ)り】🔗⭐🔉
えだ-がわり ―ガハリ [3] 【枝変(わ)り】
植物体の一部の枝のみが他と異なる遺伝形質を示す現象。芽の始原細胞における体細胞遺伝子の突然変異によって起こる。長十郎ナシから二十世紀ナシを得たのがこの例である。芽条変異。
えだ-ぎ【枝木】🔗⭐🔉
えだ-ぎ [0] 【枝木】
木の枝。
えだきり-ばさみ【枝切り鋏】🔗⭐🔉
えだきり-ばさみ [5] 【枝切り鋏】
樹木の剪定(センテイ)に用いる鋏。
えだ-ぐり【枝栗】🔗⭐🔉
えだ-ぐり [0] 【枝栗】
枝のついたまま折り取った栗の実。
えだ-げ【枝毛】🔗⭐🔉
えだ-げ [0] 【枝毛】
毛髪の先が枝のように裂けたもの。
えだ-ざし【枝差し】🔗⭐🔉
えだ-ざし 【枝差し】
枝振り。「竜胆(リンドウ)は,―などもむつかしけれど/枕草子 67」
えだ-ざし【枝挿し】🔗⭐🔉
えだ-ざし [0] 【枝挿し】
挿し木の一。枝を挿し穂として用いるもの。
えだ-さんご【枝珊瑚】🔗⭐🔉
えだ-さんご [3] 【枝珊瑚】
枝の形をしたサンゴ。
えだ-した【枝下】🔗⭐🔉
えだ-した [0] 【枝下】
地面から力枝までの幹の部分。
えだ-しゃく【枝尺】🔗⭐🔉
えだ-しゃく [0] 【枝尺】
シャクガ科エダシャク亜科のガの総称。後ろばねの第五脈を欠くことが特徴。幼虫はシャクトリムシで,広葉樹の葉を食う。エダシャクトリ。エダシャクガ。
えだ-じろ【枝城】🔗⭐🔉
えだ-じろ [0] 【枝城】
(本城を根城と呼ぶのに対して)出城(デジロ)。支城。
えだ-ずみ【枝炭】🔗⭐🔉
えだ-ずみ [0] 【枝炭】
ツツジなどの細い木の枝を焼いてつくった炭。火のおこりを早くするために茶道で用いる。上に胡粉(ゴフン)を塗った白炭(シロズミ)と,塗らない山色(ヤマイロ)の二種がある。
えだ-ちょうし【枝調子】🔗⭐🔉
えだ-ちょうし ―テウシ [3] 【枝調子】
雅楽で,基本の六調子に対して,主音は同じで音階の違う調子。壱越(イチコツ)調に対しての沙陀(サダ)調,黄鐘(オウシキ)調に対する水調など五種がある。
えだ-づか【枝束】🔗⭐🔉
えだ-づか [2][0] 【枝束】
小屋組で,真束(シンヅカ)と陸梁(ロクバリ)の接点から斜めに出て,合掌を支えている方杖(ホウヅエ)。小屋方杖。
えだ-つき【枝付き】🔗⭐🔉
えだ-つき [0] 【枝付き】
枝のつき具合。枝ぶり。
えだ-つぎ【枝接ぎ】🔗⭐🔉
えだ-ながれ【枝流れ】🔗⭐🔉
えだ-ながれ [3] 【枝流れ】
支流。分流。枝川。
えだ-にく【枝肉】🔗⭐🔉
えだ-にく [0] 【枝肉】
家畜を屠殺(トサツ)後,放血して皮をはぎ,頭部・内臓と四肢の先端を取り除いた骨付きの肉。普通,脊柱に添って左右に二分したものをいう。
えだ-の-しゅじつ【枝の主日】🔗⭐🔉
えだ-の-しゅじつ 【枝の主日】
⇒棕櫚(シユロ)の主日(シユジツ)
えだ-は【枝葉】🔗⭐🔉
えだ-は [0] 【枝葉】
(1)枝と葉。
(2)物事の本質的でない,ささいな部分。枝葉末節。「―にこだわる」
(3)本家から分かれた者。また,家来・従者。「―の者は追つての御沙汰/人情本・梅児誉美(後)」
えだ-はらい【枝払い】🔗⭐🔉
えだ-はらい ―ハラヒ [3] 【枝払い】
伐採した木の枝を幹から切り離すこと。
→枝打ち
えだ-はり【枝張(り)】🔗⭐🔉
えだ-はり [0] 【枝張(り)】
樹木の枝の広がり具合。
えだ-ばり【枝針】🔗⭐🔉
えだ-ばり [0] 【枝針】
釣りで,胴突き仕掛けなどのように幹糸の途中から出してある針。
えだ-ばん【枝番】🔗⭐🔉
えだ-ばん [0] 【枝番】
〔「枝番号」の略〕
分類や順番を示す番号を,さらに細かく分けるときに付ける番号。
えだ-ぶり【枝振り】🔗⭐🔉
えだ-ぶり [0] 【枝振り】
枝の伸びたありさま。枝のかっこう。えださし。「―のいい松」
えだ-まめ【枝豆】🔗⭐🔉
えだ-まめ [0] 【枝豆】
まだ熟していない青い大豆を枝ごととったもの。さやのままゆでて食べる。[季]秋。
えだ-みち【枝道・岐路】🔗⭐🔉
えだ-みち [0] 【枝道・岐路】
(1)本道から分かれた道。横道。
(2)物事の本筋からはずれたところ。「話が―にそれる」
えだ-みや【枝宮】🔗⭐🔉
えだ-みや [0] 【枝宮】
「末社(マツシヤ)」に同じ。
えだ-むら【枝村】🔗⭐🔉
えだ-むら [0] 【枝村】
江戸時代,開拓などによって本村から分立した村。元の村は親村・親郷という。
えだ-わかれ【枝分かれ】🔗⭐🔉
えだ-わかれ [3] 【枝分かれ】 (名)スル
(1)木の枝が分かれること。分枝。
(2)一本の物が途中から何本かに分かれること。「何本もの支線が―する」
し【枝】🔗⭐🔉
し 【枝】 (接尾)
助数詞。細長い物を数えるのに用いる。「長刀一―」
し-いん【子院・支院・枝院】🔗⭐🔉
し-いん ― ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
 ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
しおり【栞・枝折(り)】🔗⭐🔉
しおり シヲリ [0] 【栞・枝折(り)】
〔動詞「枝折る」の連用形から〕
(1)本の読みかけのところに挟んでしるしとする,細幅の紙片やひも。
(2)案内書。手引き。「旅の―」「英文学研究の―」
(3)山道などで,木の枝を折っておいて道しるべとすること。また,その道しるべ。「―を尋ねつつも登り給ひなまし/今昔 28」
(4)くるわ。城郭。「三の丸―ぎはまで追入りしかども/太閤記」
(5)「枝折り戸」の略。
しおり-がき【枝折(り)垣】🔗⭐🔉
しおり-がき シヲリ― [3] 【枝折(り)垣】
竹または木の枝を折ったもので作った粗末な垣。茶室の庭などに用いる。
しおり-ど【枝折(り)戸】🔗⭐🔉
しおり-ど シヲリ― [3] 【枝折(り)戸】
(1)竹や木の枝を折って作った簡素な開き戸。
(2)露地の小門の一。丸竹の枠に割り竹を両面から菱目(ヒシメ)に組み付けたもの。菱目の交差部分は蕨縄(ワラビナワ)で結い,門柱には丸太を用いる。
枝折り戸(2)
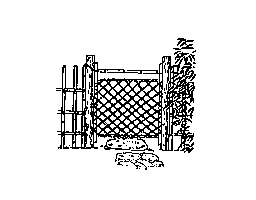 [図]
[図]
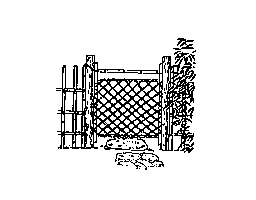 [図]
[図]
し-お・る【枝折る】🔗⭐🔉
し-お・る ―ヲル 【枝折る】 (動ラ四)
〔「撓(シオ)る」と同源。「枝折る」は当て字か〕
道しるべのため,木の枝などを折る。「世の憂さに―・らで入りし奥山に/浜松中納言 1」
しがい-だるき【枝外垂木】🔗⭐🔉
しがい-だるき シグワイ― [4] 【枝外垂木】
屋根の妻の壁面に用いる,棟木から丸桁にかけて打たれている急勾配の化粧垂木。追っ立て垂木。
し-かん【枝幹】🔗⭐🔉
し-かん [0] 【枝幹】
(1)枝と幹。
(2)末と本(モト)。
し-じょう【枝条】🔗⭐🔉
し-じょう ―デウ [0] 【枝条】
木の枝。
し-ぞく【支族・枝族】🔗⭐🔉
し-ぞく [1] 【支族・枝族】
分かれ出た血族。分家。別家。
しだれ【枝垂れ・垂れ】🔗⭐🔉
しだれ [3] 【枝垂れ・垂れ】
〔下二段動詞「垂(シダ)る」の連用形から〕
たれ下がること。しだり。
しだれ-うめ【枝垂れ梅】🔗⭐🔉
しだれ-うめ [3] 【枝垂れ梅】
ウメの一品種。枝のたれ下がる梅。
しだれ-ざくら【枝垂れ桜】🔗⭐🔉
しだれ-ざくら [4] 【枝垂れ桜】
バラ科の落葉高木。エドヒガンの一変種で,枝のたれ下がるもの。花は普通,淡紅白色五弁。糸桜。[季]春。
しだれ-ひがん【枝垂れ彼岸】🔗⭐🔉
しだれ-ひがん [4] 【枝垂れ彼岸】
シダレザクラの異名。
しだれ-もも【枝垂れ桃】🔗⭐🔉
しだれ-もも [3] 【枝垂れ桃】
モモの園芸品種。枝のたれ下がるもので,主として観賞用。シダリモモ。
しだれ-やなぎ【枝垂れ柳】🔗⭐🔉
しだれ-やなぎ [4] 【枝垂れ柳】
ヤナギ科の落葉高木。中国原産。街路樹・庭園樹として広く植えられる。枝は細長く下垂し,広線形の葉を互生。雌雄異株。早春,黄緑色の花穂を葉腋につける。種子には白い綿毛がある。普通ヤナギというと本種をさす。糸柳。シダリヤナギ。
し-とう【枝頭】🔗⭐🔉
し-とう [0] 【枝頭】
枝の先端。
し-よう【枝葉】🔗⭐🔉
し-よう ―エフ [0][1] 【枝葉】
(1)木の枝と葉。えだは。
(2)本筋からはずれた部分。物事の主要でない部分。
(3)家系・流派などで主流から分かれ出た一派。
しよう-まっせつ【枝葉末節】🔗⭐🔉
しよう-まっせつ ―エフ― [1][0] 【枝葉末節】
主要でない部分。細かい部分。「―にこだわる」
し-りん【支輪・枝輪】🔗⭐🔉
し-りん [0] 【支輪・枝輪】
社寺建築で,折り上げ天井を支える湾曲した竪木(タテギ)。
支輪
 [図]
[図]
 [図]
[図]
よ【枝】🔗⭐🔉
よ 【枝】
えだ。一説に,花びらの意ともいう。「この花の一―のうちは百種の/万葉 1457」
えだぶり【枝ぶりのよい松】(和英)🔗⭐🔉
えだぶり【枝ぶりのよい松】
a shapely pine tree.
えだまめ【枝豆】(和英)🔗⭐🔉
えだまめ【枝豆】
green soybeans.
しおりど【枝折戸】(和英)🔗⭐🔉
しおりど【枝折戸】
a wicket made of branches and twigs.
しだれ【枝垂柳】(和英)🔗⭐🔉
しだれ【枝垂柳】
a weeping willow.枝垂桜 a drooping cherry tree.
しだれる【枝垂れる】(和英)🔗⭐🔉
しだれる【枝垂れる】
droop;→英和
hang down.
しよう【枝葉の】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「枝」で始まるの検索結果。