複数辞典一括検索+![]()
![]()
かい【貝】🔗⭐🔉
かい カヒ [1] 【貝】
(1)かたい貝殻(カイガラ)をもった軟体動物の総称。二枚貝・巻貝(マキガイ)・角貝(ツノガイ)などを含む。多くは水中にすむ。
(2)貝殻。「―細工」
(3)ほらがい。「―をにはかに吹き出でたるこそ/枕草子 120」
(4)「貝合わせ」の略。「―の御勝負/御湯殿上(文明一九)」
かい=を作・る🔗⭐🔉
――を作・る
〔口の形が「へ」の字になり,蛤(ハマグリ)の形に似るところから〕
べそをかく。泣き顔になる。「―・るもいとほしながら/源氏(明石)」
かい-あわせ【貝合(わ)せ】🔗⭐🔉
かい-あわせ カヒアハセ [3] 【貝合(わ)せ】
(1)平安時代の物合わせの一種。左右二組に分かれ,それぞれ貝を出して合わせ,その形・色・大きさ・珍しさなどの優劣を争う遊戯。「この姫君と上との御方の姫君と―せさせ給はむとて/堤中納言(貝あはせ)」
(2)平安末期から起こった遊戯。三六○個の蛤(ハマグリ)の貝殻を両片に分かち,一片を地貝(ジガイ),一片を出貝(ダシガイ)といい,地貝はすべて甲を上にして伏せ,これに出貝を一個ずつ出して合わせ,対になる貝を多く合わせ取った者を勝ちとした遊戯。後世,合わせる便宜上,貝の裏に絵や歌を書いた。かいおおい。
かい-いし【貝石】🔗⭐🔉
かい-いし カヒ― [1][2] 【貝石】
(1)貝殻の化石となったもの。
(2)貝殻の付着した石。
かい-いしばい【貝石灰】🔗⭐🔉
かい-いしばい カヒイシバヒ [4] 【貝石灰】
牡蠣(カキ)の殻を焼いてつくった灰。石炭の代わりに用いる。かきがらばい。かきばい。
かい-おおい【貝覆い】🔗⭐🔉
かい-おおい カヒオホヒ [3] 【貝覆い】
「貝合(カイア)わせ{(2)}」に同じ。「方をわかちて,絵づくの―ありけり/著聞 11」
かいおおい【貝おほひ】🔗⭐🔉
かいおおい カヒオホヒ 【貝おほひ】
俳諧発句合(ホツクアワセ)。一巻。松尾芭蕉撰。1672年刊。六〇の発句および芭蕉の判詞を当時の流行語や小唄の一節などによって仕立てた集。芭蕉の処女撰集。三十番俳諧合。
かい-おけ【貝桶】🔗⭐🔉
かい-おけ カヒヲケ [3] 【貝桶】
貝合わせの貝を入れる六角形の桶。二個で一組となる。近世には,嫁入り道具の第一の調度とされた。
貝桶
 [図]
[図]
 [図]
[図]
かいかけ-おんせん【貝掛温泉】🔗⭐🔉
かいかけ-おんせん カヒカケヲンセン 【貝掛温泉】
新潟県南部,苗場山の北東中腹の渓谷にある食塩泉。古くからの湯治場。
かい-がね【貝鐘・貝鉦】🔗⭐🔉
かい-がね カヒ― 【貝鐘・貝鉦】
法螺貝(ホラガイ)と鉦(カネ)・鐘など金属打楽器の類。寺院の行事や戦場での合図のために鳴らすもの。「那智新宮大衆,軍に勝て―を鳴し/盛衰記 13」
かい-かむり【貝被】🔗⭐🔉
かい-かむり カヒ― [3] 【貝被】
原始的なカニの一種。甲の背はよくふくらみ,半球状。甲の長さ約7センチメートル。体表は硬い短毛で覆われる。後ろの二対の歩脚は短く,背側にあって先端が鉤爪状になっており,これで海綿・貝殻などを背負っている。北海道南端以南に広く分布。カイカブリ。
かい-がら【貝殻】🔗⭐🔉
かい-がら カヒ― [3][0] 【貝殻】
貝の外側を覆っている殻。外套膜から分泌される石灰質から成り,貝の身を保護している。貝。介殻。「―細工(ザイク)」
かいがら-ついほう【貝殻追放】🔗⭐🔉
かいがら-ついほう カヒ―ハウ [5] 【貝殻追放】
オストラシズムの誤訳。
かいがら-ぶし【貝殻節】🔗⭐🔉
かいがら-ぶし カヒ― 【貝殻節】
鳥取県の民謡で,帆立て貝漁の櫓漕(ロコ)ぎ唄。鳥取市賀露神社の祭礼で演じられる「ホーエンヤ舟」の舟漕ぎの掛け声をもとにして生まれた。
かいがら-ぼね【貝殻骨】🔗⭐🔉
かいがら-ぼね カヒ― [0] 【貝殻骨】
肩胛骨(ケンコウコツ)の俗称。かいがね。
かいがら-むし【貝殻虫】🔗⭐🔉
かいがら-むし カヒ― [4] 【貝殻虫】
半翅目カイガラムシ上科の昆虫の総称。体長数ミリメートル。二齢以後の幼虫は植物に固着し,多量の分泌物に覆われ,貝殻のように見えるものもある。成虫の雄ははねがあり飛ぶが,雌ははねが,多くは脚もなく寄生植物に固着し分泌物で覆われる。害虫となるものが多いが,その分泌物や体成分が利用されるものもある。
かいがら-じま【貝殻島】🔗⭐🔉
かいがら-じま カヒガラ― 【貝殻島】
北海道東部,歯舞諸島の島。根室半島とは珸瑶瑁(ゴヨウマイ)水道を隔てる。第二次大戦後はソ連(現ロシア連邦)の占領下にある。
かい-ぐら【貝鞍】🔗⭐🔉
かい-ぐら カヒ― [0] 【貝鞍】
鞍の表面の漆地に青貝で模様をちりばめ,みがき出したもの。
かい-こう【貝香・甲香】🔗⭐🔉
かい-こう カヒカウ 【貝香・甲香】
巻貝アカニシのふた。粉末を保香剤として練り香に用いる。へなたり。こうこう。
かい-ざいく【貝細工】🔗⭐🔉
かい-ざいく カヒ― [3] 【貝細工】
(1)貝殻で作った器具・細工物。
(2)キク科の多年草。オーストラリア原産。高さ約1メートル。夏から秋に茎頂に径2センチメートル内外の頭花をつける。舌状花が,乾燥した感じがするのを貝細工にみたてる。ドライフラワー・切り花などにする。
かい-じゃくし【貝杓子】🔗⭐🔉
かい-じゃくし カヒ― [3] 【貝杓子】
板屋貝や帆立貝などの貝殻に,竹または木の柄をつけた杓子。
かい-すり【貝磨り・貝摺り】🔗⭐🔉
かい-すり カヒ― 【貝磨り・貝摺り】
青貝などをすって細工すること。また,その細工物。「沈(ヂン)・紫檀の―/栄花(歌合)」
かい-だこ【貝蛸】🔗⭐🔉
かい-だこ カヒ― [3] 【貝蛸】
タコの一種。雌は体長24センチメートルほどで,黒く縁どられた純白の美しい薄い貝殻(アオイガイ)をつくる。雄はきわめて小さく貝殻はなく,昔は雌についた寄生虫と思われた。温・熱帯の海に広く分布。
かいたに【貝谷】🔗⭐🔉
かいたに カヒタニ 【貝谷】
姓氏の一。
かいたに-やおこ【貝谷八百子】🔗⭐🔉
かいたに-やおこ カヒタニヤホコ 【貝谷八百子】
(1921-1991) 舞踊家。本名,スミ子。福岡県生まれ。数多くの古典バレエを日本に紹介。「マクベス」「獅子‐石橋(シヤツキヨウ)」などの創作バレエを発表。
かい-づか【貝塚】🔗⭐🔉
かい-づか カヒ― [0][1] 【貝塚】
古代人が食べた貝の殻などが堆積(タイセキ)したもの。ヨーロッパでは中石器時代以後,日本では縄文時代から弥生時代中期までのものが見られる。土器・石器・人骨・獣骨などがまじって発掘される。
かいづか-いぶき【貝塚伊吹】🔗⭐🔉
かいづか-いぶき カヒ― [5] 【貝塚伊吹】
イブキの園芸品種。幹は直立して枝は太く,側枝はねじれ,円錐形の樹形をなす。生け垣・庭木などとする。
かいづか【貝塚】🔗⭐🔉
かいづか カヒヅカ 【貝塚】
大阪府南西部,大阪湾に面する市。願泉寺(貝塚御坊)の寺内町として発達。紡績業が盛ん。
かいづか【貝塚】🔗⭐🔉
かいづか カヒヅカ 【貝塚】
姓氏の一。
かいづか-しげき【貝塚茂樹】🔗⭐🔉
かいづか-しげき カヒヅカ― 【貝塚茂樹】
(1904-1987) 中国史学者。東京生まれ。京大卒。小川琢治の次男。京大人文科学研究所で中国古代の甲骨文字や金石文の研究を行う。「京都大学人文科学研究所蔵甲骨文字」三大冊は,世界の学界で反響を呼んだ。
かい-づくし【貝尽(く)し】🔗⭐🔉
かい-づくし カヒ― [3] 【貝尽(く)し】
模様・絵・文などが,種々の貝ばかりを題材として作られていること。
かい-づめ【貝爪】🔗⭐🔉
かい-づめ カヒ― [1] 【貝爪】
短くて横にひらたい感じのつめ。
かい-なり【貝状】🔗⭐🔉
かい-なり カヒ― [0] 【貝状】
「貝状形(カイナリガタ)」の略。
かいなり-がた【貝状形】🔗⭐🔉
かいなり-がた カヒ― [0] 【貝状形】
貝のような形。特に,その形をした笄(コウガイ)。
かい-の-くち【貝の口】🔗⭐🔉
かい-の-くち カヒ― [3] 【貝の口】
帯の結び方の一。一端を折り返し,二つ折りにした他端と真結びに結ぶもの。男の角帯や少女の帯を結ぶ。
貝の口
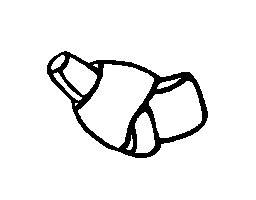 [図]
[図]
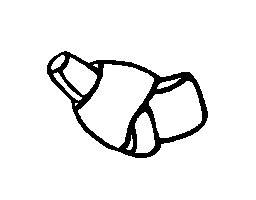 [図]
[図]
かい-の-たま【貝の珠】🔗⭐🔉
かい-の-たま カヒ― 【貝の珠】
真珠。[日葡]
かい-ばい【貝灰】🔗⭐🔉
かい-ばい カヒバヒ [1] 【貝灰】
牡蠣(カキ)・蛤(ハマグリ)・姥貝(ウバガイ)などの貝殻を焼き,消和して得る消石灰。漆喰(シツクイ)の材料。
かい-ばしら【貝柱】🔗⭐🔉
かい-ばしら カヒ― [3] 【貝柱】
(1)二枚貝の両方の貝殻をつなぎ,閉じさせる筋肉。閉殻筋。肉柱。
(2)ホタテガイ・イタヤガイなどの肉柱を加工した食品。はしら。
かいばら【貝原】🔗⭐🔉
かいばら カヒバラ 【貝原】
姓氏の一。
かいばら-えきけん【貝原益軒】🔗⭐🔉
かいばら-えきけん カヒバラ― 【貝原益軒】
(1630-1714) 江戸前期の儒学者・本草家・教育思想家。筑前生まれ。名は篤信。初め損軒と号した。福岡藩儒。朱陸兼学から朱子学に帰し,本草などにも目を向け,博物学的実証主義に立って窮理の道を重視。著「大疑録」「大和本草」,医書の「養生訓」,子女の教育を説いた「和俗童子訓」など多数。
かい-びょうぶ【貝屏風】🔗⭐🔉
かい-びょうぶ カヒビヤウブ [3] 【貝屏風】
金紙に貝細工で種々の模様をつけたおもちゃの小屏風。
かい-ふき【貝吹き】🔗⭐🔉
かい-ふき カヒ― [3][4][0] 【貝吹き】
戦陣などで,法螺(ホラ)貝を吹いて号令や合図をすること。また,その役目の人。
かい-へん【貝偏】🔗⭐🔉
かい-へん カヒ― [0] 【貝偏】
漢字の偏の一。「財」「賊」「賦」などの「貝」の部分。貨幣・財産に関する文字を作る。大貝(オオガイ)に対して小貝(コガイ)ともいう。
かい-むらさき【貝紫】🔗⭐🔉
かい-むらさき カヒ― [4] 【貝紫】
地中海産のアッキガイ科の貝の分泌液からとった紫色の染料。非常に高価なため,ローマ時代には皇帝と元老院議員のみの衣服に使用した。帝王紫。ティリアン=パープル。
かい-やき【貝焼(き)】🔗⭐🔉
かい-やき カヒ― [0] 【貝焼(き)】
(1)貝類を貝殻のまま焼いた料理。
(2)鮑(アワビ)・帆立貝などの大きな貝殻を,鍋の代わりにして煮ること。また,その料理。
かい-やぐら【貝櫓・蜃楼】🔗⭐🔉
かい-やぐら カヒ― [3] 【貝櫓・蜃楼】
〔「蜃楼」を訓読みした語〕
蜃気楼(シンキロウ)のこと。
かい-よせ【貝寄せ】🔗⭐🔉
かい-よせ カヒ― [0] 【貝寄せ】
〔貝を浜辺に吹き寄せる風の意〕
大阪四天王寺の聖霊会(シヨウリヨウエ)(もと陰暦二月二〇日)前後に吹く西風。[季]春。《―に乗りて帰郷の船疾し/中村草田男》
〔聖霊会に供える造花の材料の貝を竜神が難波の浜に捧げるものと言い伝える〕
かい-ろう【貝楼】🔗⭐🔉
かい-ろう カヒ― [0] 【貝楼】
蜃気楼(シンキロウ)のこと。貝やぐら。
かい-わ【貝輪】🔗⭐🔉
かい-わ カヒ― [0] 【貝輪】
貝殻製の腕輪。大形の二枚貝の殻に穴を開けて環状にしたり,巻貝を輪切りにしたもの。縄文時代から古墳時代にかけて用いられた。貝釧(カイクシロ)。
かい-わり【貝割(り)・卵割(り)・穎割(り)】🔗⭐🔉
かい-わり カヒ― [0] 【貝割(り)・卵割(り)・穎割(り)】
(1)二枚貝が開いたような形。また,卵が二つに割れたような形。
(2)「かいわれ」に同じ。
(3)端を{(1)}のように結ぶ帯の結び方。
(4)広袖の袖口を真ん中でくくったもの。十六ささげ。
(5)スズキ目の海魚。全長30センチメートルほど。アジ類の一種。体は卵円形で,著しく側扁する。体色は青みを帯びた銀白色。食用にして美味。本州中部以南に広く分布。ヒラアジ。
かいわり-な【貝割(り)菜】🔗⭐🔉
かいわり-な カヒ― [4] 【貝割(り)菜】
芽が出たばかりの,貝割り形をした二葉を食べる野菜。摘まみ菜など。かいわり。かいわれ。[季]秋。
かい-われ【貝割れ・穎割れ】🔗⭐🔉
かい-われ カヒ― [0] 【貝割れ・穎割れ】
(1)芽を出したばかりの頃,貝殻を開いたように二枚の子葉を開いている幼い植物。かいわり。
(2)貝割り菜のこと。
かいわれ-な【貝割れ菜】🔗⭐🔉
かいわれ-な カヒ― [4] 【貝割れ菜】
⇒貝割り菜
ばい【貝・ ・海
・海 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
ばい [1] 【貝・ ・海
・海 】
(1)海産の巻貝。貝殻は長卵形で殻高7センチメートル内外。表面は黄褐色の殻皮でおおわれる。殻は乳白色で栗色の斑紋がある。肉は食用。貝殻は貝細工の材料。昔は貝殻を使ってばいごま(べいごま)を作った。浅海の砂底にすむ。北海道南部以南に分布。
(2)「貝独楽(バイゴマ)」の略。「―ヲ回ス/日葡」
】
(1)海産の巻貝。貝殻は長卵形で殻高7センチメートル内外。表面は黄褐色の殻皮でおおわれる。殻は乳白色で栗色の斑紋がある。肉は食用。貝殻は貝細工の材料。昔は貝殻を使ってばいごま(べいごま)を作った。浅海の砂底にすむ。北海道南部以南に分布。
(2)「貝独楽(バイゴマ)」の略。「―ヲ回ス/日葡」
 ・海
・海 】
(1)海産の巻貝。貝殻は長卵形で殻高7センチメートル内外。表面は黄褐色の殻皮でおおわれる。殻は乳白色で栗色の斑紋がある。肉は食用。貝殻は貝細工の材料。昔は貝殻を使ってばいごま(べいごま)を作った。浅海の砂底にすむ。北海道南部以南に分布。
(2)「貝独楽(バイゴマ)」の略。「―ヲ回ス/日葡」
】
(1)海産の巻貝。貝殻は長卵形で殻高7センチメートル内外。表面は黄褐色の殻皮でおおわれる。殻は乳白色で栗色の斑紋がある。肉は食用。貝殻は貝細工の材料。昔は貝殻を使ってばいごま(べいごま)を作った。浅海の砂底にすむ。北海道南部以南に分布。
(2)「貝独楽(バイゴマ)」の略。「―ヲ回ス/日葡」
ばい-うち【貝打ち・海 打ち】🔗⭐🔉
打ち】🔗⭐🔉
ばい-うち [0][1] 【貝打ち・海 打ち】
「貝(バイ)回し」に同じ。[季]秋。《負け海
打ち】
「貝(バイ)回し」に同じ。[季]秋。《負け海 やたましひ抜けの遠ころげ/山口誓子》
やたましひ抜けの遠ころげ/山口誓子》
 打ち】
「貝(バイ)回し」に同じ。[季]秋。《負け海
打ち】
「貝(バイ)回し」に同じ。[季]秋。《負け海 やたましひ抜けの遠ころげ/山口誓子》
やたましひ抜けの遠ころげ/山口誓子》
ばい-か【貝貨】🔗⭐🔉
ばい-か ―クワ [0][1] 【貝貨】
タカラガイなどの貝殻製の貴重品。古代中国やアジア・アフリカ・北アメリカ・オセアニアなどの諸民族の間で,結婚やイニシエーションにおける贈与交換の際に用いられた。
ばい-き【貝器】🔗⭐🔉
ばい-き [1] 【貝器】
貝殻で作った道具類。縄文時代の貝匙(カイサジ)・貝杓子(カイジヤクシ),弥生時代の貝包丁など。
ばい-ごま【貝独楽】🔗⭐🔉
ばい-ごま [0] 【貝独楽】
巻貝バイの殻の中に溶かした鉛や蝋(ロウ)を注ぎ込んで作ったこま。また,鉄などでそれを模して作ったこま。べいごま。[季]秋。
→ばい回し
ばい-しょ【貝書】🔗⭐🔉
ばい-しょ [1] 【貝書】
⇒貝多羅葉(バイタラヨウ)
ばいたら【貝多羅】🔗⭐🔉
ばいたら [0] 【貝多羅】
〔仏〕
〔梵 pattra 木の葉の意〕
多羅樹の葉。古代インドで文字を記すのに用いたもの。転じて,書物・記録の意。また,仏教経典の意。貝葉。貝多葉。多羅葉。
ばいたら-よう【貝多羅葉】🔗⭐🔉
ばいたら-よう ―エフ [4] 【貝多羅葉】
貝多羅のこと。貝葉。貝書。
ばい-まげ【貝髷】🔗⭐🔉
ばい-まげ 【貝髷】
江戸時代の女の髷。簪(カンザシ)を中央に立て,それに髪を巻き込むもの。髷の形が巻貝に似るところからの名。
貝髷
 [図]
[図]
 [図]
[図]
ばい-まわし【貝回し・海 回し】🔗⭐🔉
回し】🔗⭐🔉
ばい-まわし ―マハシ [3] 【貝回し・海 回し】
ばいごまを回し,ぶつけ合う遊び。古く,重陽(チヨウヨウ)の節句の遊びであった。ばい打ち。[季]秋。
貝回し
回し】
ばいごまを回し,ぶつけ合う遊び。古く,重陽(チヨウヨウ)の節句の遊びであった。ばい打ち。[季]秋。
貝回し
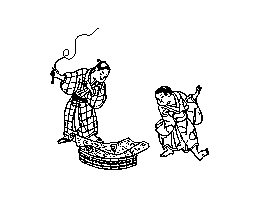 [図]
[図]
 回し】
ばいごまを回し,ぶつけ合う遊び。古く,重陽(チヨウヨウ)の節句の遊びであった。ばい打ち。[季]秋。
貝回し
回し】
ばいごまを回し,ぶつけ合う遊び。古く,重陽(チヨウヨウ)の節句の遊びであった。ばい打ち。[季]秋。
貝回し
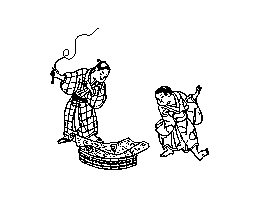 [図]
[図]
ばい-も【貝母】🔗⭐🔉
ばい-も [0][1] 【貝母】
(1)アミガサユリの漢名。
(2)生薬の一。アミガサユリの鱗茎(リンケイ)で,生石灰粉をつけて乾かしたもの。鎮咳(チンガイ)・去痰(キヨタン)薬に用いる。
ばい-よう【貝葉】🔗⭐🔉
ばい-よう ―エフ [0] 【貝葉】
⇒貝多羅葉(バイタラヨウ)
べい-ごま【貝独楽】🔗⭐🔉
べい-ごま [0] 【貝独楽】
「ばいごま」の転。
かいがら【貝殻】(和英)🔗⭐🔉
かいがら【貝殻】
a shell.→英和
かいざいく【貝細工】(和英)🔗⭐🔉
かいざいく【貝細工】
shellwork.→英和
かいづか【貝塚】(和英)🔗⭐🔉
かいづか【貝塚】
a kitchen midden;a shell mound[heap].
かいばしら【貝柱】(和英)🔗⭐🔉
かいばしら【貝柱】
a (shell) ligament.
大辞林に「貝」で始まるの検索結果 1-71。