複数辞典一括検索+![]()
![]()
しし【肉・宍】🔗⭐🔉
しし 【肉・宍】
にく。人体の肉。「我が―はみ膾(ナマス)はやし/万葉 3885」[和名抄]
しし【尿】🔗⭐🔉
しし 【尿】
〔幼児語〕
小便。おしっこ。
しし【獣・鹿・猪】🔗⭐🔉
しし [1] 【獣・鹿・猪】
〔「しし(肉)」と同源〕
(1)猪(イノシシ)や鹿(シカ)など,その肉を食用にする獣の総称。「み吉野のをむろが嶽に―伏すと/古事記(下)」
(2)特に猪のこと。[季]秋。
し-し【士師】🔗⭐🔉
し-し [1] 【士師】
(1)中国周代に,刑をつかさどった役人。
(2)〔Judges〕
旧約聖書士師記に記されている王国成立以前のイスラエルにおけるカリスマ的指導者・救護者。大士師と小士師がいた。その多くは部族の長。裁(サバ)き司(ヅカサ)。
し-し【支子】🔗⭐🔉
し-し [1] 【支子】
嫡子以外の子。
し-し【史詩】🔗⭐🔉
し-し [1] 【史詩】
歴史上の出来事を扱った詩。
し-し【四四】🔗⭐🔉
し-し [1] 【四四】
連珠で,四目が同時に二か所にできること。先手側の禁手とされる。
し-し【四至】🔗⭐🔉
し-し [1] 【四至】
〔「しじ」とも〕
「しいし(四至)」に同じ。
し-し【四始】🔗⭐🔉
し-し [1] 【四始】
〔歳・月・日・時の初めの意〕
正月元日。
し-し【四肢】🔗⭐🔉
し-し [1] 【四肢】
両手と両足。手足。また,動物の四本の足。
し-し【四詩】🔗⭐🔉
し-し [1] 【四詩】
(1)詩経の四種の詩体。国風・大雅・小雅・頌(シヨウ)の総称。
(2)前漢に行われた四種の詩経。すなわち魯(ロ)の申培の伝えた魯詩,斉の轅固生(エンコセイ)の伝えた斉詩,燕の韓嬰の伝えた韓詩,魯の毛亨(モウコウ)の伝えた毛詩の四種。毛詩だけが現存している。
し-し【市史】🔗⭐🔉
し-し [1] 【市史】
市の歴史。また,それを記録した書物。
し-し【死屍】🔗⭐🔉
し-し [1] 【死屍】
死体。なきがら。しかばね。「―累々」
し-し【志士】🔗⭐🔉
し-し [1] 【志士】
身を犠牲にして国や社会のために尽くそうという,高い志をもっている人。「勤王の―」
し-し【私史】🔗⭐🔉
し-し [1] 【私史】
「野史(ヤシ){(1)}」に同じ。
し-し【私資】🔗⭐🔉
し-し [1] 【私資】
個人の財産。私財。私産。
し-し【刺史】🔗⭐🔉
し-し [1] 【刺史】
(1)中国の地方官。漢代では地方監察官,隋・唐代では州の長官。宋以後廃止。
(2)国守(コクシユ)の唐名。
し-し【師資】🔗⭐🔉
し-し [1] 【師資】
〔老子(二七章)「善人,不善人之師,不善人,善人之資」〕
(1)師匠。先生。
(2)師匠と弟子。師弟関係。「朕上人と―の契浅からず/太平記 26」
し-し【紙誌】🔗⭐🔉
し-し [1] 【紙誌】
新聞と雑誌。
し-し【紫史】🔗⭐🔉
し-し [1] 【紫史】
〔紫式部の書いたふみの意〕
源氏物語の異名。紫文。
し-し【嗣子】🔗⭐🔉
し-し [1] 【嗣子】
家のあとを継ぐ子。あとつぎ。
し-し【獅子・師子】🔗⭐🔉
し-し [1] 【獅子・師子】
(1)ライオン。古来,百獣の王とされ,権威・王権などの象徴ともされた。獅子王。
(2){(1)}を基に想像された獣。仏教では文殊(モンジユ)菩薩の乗物とする。
(3)神社の社頭などに置いて魔よけとする。{(1)}に似た獣の像。古くは器物の重しともした。
(4)「獅子舞」「獅子頭(シシガシラ){(1)}」の略。
(5)〔仏〕(人の王であるところから)仏。「―の座」
し-し【詩史】🔗⭐🔉
し-し [1] 【詩史】
(1)詩の歴史。
(2)詩文で記した歴史。
し-し【詩思】🔗⭐🔉
し-し [1] 【詩思】
詩を作ろうとする気持ち。詩情。詩興。「―を生ぜしめ給ふを/即興詩人(鴎外)」
しし【子思】🔗⭐🔉
しし 【子思】
(前492?-前431?) 中国,春秋時代の魯(ロ)の学者。名は (キユウ),子思は字(アザナ)。孔子の孫。孔子の高弟,曾子(ソウシ)に師事。「中庸」の著者といわれる。
(キユウ),子思は字(アザナ)。孔子の孫。孔子の高弟,曾子(ソウシ)に師事。「中庸」の著者といわれる。
 (キユウ),子思は字(アザナ)。孔子の孫。孔子の高弟,曾子(ソウシ)に師事。「中庸」の著者といわれる。
(キユウ),子思は字(アザナ)。孔子の孫。孔子の高弟,曾子(ソウシ)に師事。「中庸」の著者といわれる。
しし【尸子】🔗⭐🔉
しし 【尸子】
中国の雑家の書。戦国時代の思想家尸佼の著作。上巻一三篇,下巻佚文数十則が伝わる。儒家思想を主とし,ときに道家・名家の観点をまじえる。また歴史故事や民間伝説を引いて例証としている。
し-し【孜孜】🔗⭐🔉
し-し [1] 【孜孜】
■一■ (ト|タル)[文]形動タリ
熱心に励むさま。孳孳(ジジ)。「君子は己を修むるに―たり/欺かざるの記(独歩)」
■二■ (副)
{■一■}に同じ。「―勉強して能く身を立て/福翁百話(諭吉)」
し-し🔗⭐🔉
し-し (副)
すすり泣くさま。しくしく。「―と泣く/蜻蛉(中)」
しし-あい【肉合(い)】🔗⭐🔉
しし-あい ―アヒ [0] 【肉合(い)】
肉のつき具合。ししおき。
ししあい-ぼり【肉合い彫(り)】🔗⭐🔉
ししあい-ぼり ―アヒ― [0] 【肉合い彫(り)】
主に彫金で,模様の周囲を彫り沈めて,浮き彫りの効果を出す技法。模様の面は地の面より高くならない。日本では杉浦乗意(1701-1761)が始めたとされる。
ししあい-まきえ【肉合い蒔絵】🔗⭐🔉
ししあい-まきえ ―アヒ― [5][6] 【肉合い蒔絵】
蒔絵技法の一。高蒔絵と研ぎ出し蒔絵とが併用された立体的な感じを与えるもの。肉合い研ぎ出し蒔絵。
[5][6] 【肉合い蒔絵】
蒔絵技法の一。高蒔絵と研ぎ出し蒔絵とが併用された立体的な感じを与えるもの。肉合い研ぎ出し蒔絵。
 [5][6] 【肉合い蒔絵】
蒔絵技法の一。高蒔絵と研ぎ出し蒔絵とが併用された立体的な感じを与えるもの。肉合い研ぎ出し蒔絵。
[5][6] 【肉合い蒔絵】
蒔絵技法の一。高蒔絵と研ぎ出し蒔絵とが併用された立体的な感じを与えるもの。肉合い研ぎ出し蒔絵。
ししい-でん【紫宸殿】🔗⭐🔉
ししい-でん 【紫宸殿】
⇒ししんでん(紫宸殿)
しし-うど【猪独活】🔗⭐🔉
しし-うど [3] 【猪独活】
セリ科の大形多年草。山地の草原に自生。根葉は羽状複葉。茎は中空で,高さ1.5メートル内外。夏,白色の小花を複散形花序につける。ウドに似るが食用にならない。根を風邪などの薬とする。イヌウド。
しし-おう【獅子王】🔗⭐🔉
しし-おう ―ワウ [3] 【獅子王】
(1)百獣の王として獅子をたたえていう語。
(2)名剣の名。源頼政が (ヌエ)を射たとき二条天皇から賞賜されたもの。豊後(ブンゴ)定秀または高平の作という。
(ヌエ)を射たとき二条天皇から賞賜されたもの。豊後(ブンゴ)定秀または高平の作という。
 (ヌエ)を射たとき二条天皇から賞賜されたもの。豊後(ブンゴ)定秀または高平の作という。
(ヌエ)を射たとき二条天皇から賞賜されたもの。豊後(ブンゴ)定秀または高平の作という。
しし-おき【肉置き】🔗⭐🔉
しし-おき [0] 【肉置き】
肉のつき具合。ししあい。「―豊かに,目なざし燃ゆる如くなれば/即興詩人(鴎外)」
しし-おどし【鹿威し】🔗⭐🔉
しし-おどし [3] 【鹿威し】
(1)「添水(ソウズ)」に同じ。
(2)田畑に来る鳥獣を追い払うための装置。添水・鳴子など。
しし-おどり【鹿踊り】🔗⭐🔉
しし-おどり ―ヲドリ [3] 【鹿踊り】
岩手・宮城両県で盆や祭礼に行われる芸能。鹿の頭をかぶり,胸に太鼓をつけた者が組になって踊り,寺社や家々をめぐり歩く。
しし-おどり【獅子踊り】🔗⭐🔉
しし-おどり ―ヲドリ [3] 【獅子踊り】
東日本に広く行われる一人立ちの風流(フリユウ)獅子舞。四隅に花笠をかぶり簓(ササラ)を摺(ス)る者が立つ中で,胸に太鼓をつけ,獅子頭(シシガシラ)をかぶった者三人が踊る。
→獅子舞
しし-がき【鹿垣】🔗⭐🔉
しし-がき [2] 【鹿垣】
(1)枝のついた木や竹で作った垣。田畑に鹿(シカ)や猪(イノシシ)などの侵入するのを防ぐもの。[季]秋。
(2)砦(トリデ)の周りに設けて防御用にした垣。鹿砦(ロクサイ)。
しし-かぐら【獅子神楽】🔗⭐🔉
しし-かぐら [3] 【獅子神楽】
獅子頭(シシガシラ)に神を勧請(カンジヨウ)し,家々を清めて回る神楽。伊勢の太神楽(ダイカグラ)や東北地方の権現(ゴンゲン)舞など。
しし-がしら【獅子頭】🔗⭐🔉
しし-がしら [3] 【獅子頭】
(1)獅子の頭の形に似せて作った木製の仮面。獅子舞に使う。しし。
(2)金魚の一品種。頭部に多くのいぼがあり,冠をかぶったように見える。背びれはない。
(3)ウラボシ科の常緑性シダ植物。葉は倒披針形の羽状葉で獅子のたてがみ状に多数根生。胞子葉は栄養葉より細長い。百足草(ムカデグサ)。鰯骨(イワシボネ)。オサバ。
獅子頭(3)
 [図]
[図]
 [図]
[図]
ししがしら-の-かぶと【獅子頭の兜】🔗⭐🔉
ししがしら-の-かぶと 【獅子頭の兜】
獅子頭{(1)}を前立(マエダテ)として付けた兜。
ししがたに【鹿ヶ谷】🔗⭐🔉
ししがたに 【鹿ヶ谷】
京都市左京区,大文字山西麓の地名。
ししがたに-じけん【鹿ヶ谷事件】🔗⭐🔉
ししがたに-じけん 【鹿ヶ谷事件】
1177年,俊寛・藤原成親(ナリチカ)・藤原師光(モロミツ)(西光)ら後白河法皇の近臣が,鹿ヶ谷の俊寛の山荘で平家討伐を謀議した事件。多田行綱の密告によって発覚,師光は死罪,成親・俊寛らは流罪。
シシカバブ (トルコ)
(トルコ)  i
i kebab
kebab 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
シシカバブ [3]  (トルコ)
(トルコ)  i
i kebab
kebab トルコ料理の一。羊肉を串(クシ)に刺して焼いたもの。シャシリック。
トルコ料理の一。羊肉を串(クシ)に刺して焼いたもの。シャシリック。
 (トルコ)
(トルコ)  i
i kebab
kebab トルコ料理の一。羊肉を串(クシ)に刺して焼いたもの。シャシリック。
トルコ料理の一。羊肉を串(クシ)に刺して焼いたもの。シャシリック。
しし-がり【猪狩(り)・鹿狩(り)】🔗⭐🔉
しし-がり [0][2][3] 【猪狩(り)・鹿狩(り)】
山野にはいって猪(イノシシ)・鹿(シカ)などの獣を捕らえること。しし。
し-しき【司式】🔗⭐🔉
し-しき [0] 【司式】
式を執り行うこと。特に,キリスト教で,洗礼・聖餐や結婚・葬儀などの式をつかさどること。
し-しき【四職】🔗⭐🔉
し-しき [1] 【四職】
(1)律令制で,左京職・右京職・大膳職・修理(シユリ)職の総称。
(2)室町時代,侍所の長官(所司)に任ぜられた,山名・一色・京極・赤松の四家。四殿衆。四職衆。
し-しき【歯式】🔗⭐🔉
し-しき [0] 【歯式】
動物の歯の種類と数とを表す式。上下顎の片側の門歯・犬歯・前臼歯・後臼歯の数を左から右へ分数式で示す。哺乳類では分類の重要な基準になる。
しし-きゅう【獅子宮】🔗⭐🔉
しし-きゅう [2] 【獅子宮】
黄道十二宮の第五宮。獅子座に相当していたが,現在は歳差のためずれている。
し-しきゅう【四死球】🔗⭐🔉
し-しきゅう ―シキウ [2] 【四死球】
野球で,四球(フォア-ボール)と死球(デッド-ボール)をいう。
しし-きゅうきゅう【孜孜汲汲】🔗⭐🔉
しし-きゅうきゅう ―キフキフ [1] 【孜孜汲汲】 (ト|タル)[文]形動タリ
飽きることなく努力を重ねるさま。「―として其功を奏せし者も/世路日記(香水)」
しし-く【獅子吼】🔗⭐🔉
しし-く [2] 【獅子吼】 (名)スル
(1)獅子がほえること。
(2)釈迦の説法・教説。獅子がほえて,百獣を恐れさせる威力にたとえていう。
(3)熱弁をふるって真理・正義を説くこと。
しし-くしろ【肉串ろ】🔗⭐🔉
しし-くしろ 【肉串ろ】 (枕詞)
串に刺して焼いた獣肉がうまいことから,「熟睡(ウマイ)」に,また良味(ヨミ)と同音の「黄泉(ヨミ)」にかかる。「―熟睡寝し間(ト)に/日本書紀(継体)」「―黄泉に待たむと/万葉 1809」
しし-ぐち【獅子口】🔗⭐🔉
しし-ぐち [2] 【獅子口】
(1)屋根の棟飾りの一。棟の両端に用いる箱形の瓦で,頂上に経の巻という丸瓦を三〜五個のせる。社寺・宮殿建築に多く用いる。
(2)能面の一。口を大きく開き,牙(キバ)をむき出した凶暴な面相のもの。石橋(シヤツキヨウ)の獅子などに用いる。
(3)竹筒の花入れの一。一重切りの窓が横に大きく切られたもの。鰐口(ワニグチ)。
獅子口(1)
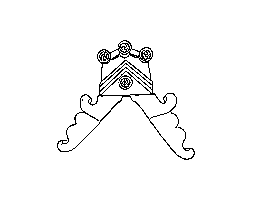 [図]
獅子口(2)
[図]
獅子口(2)
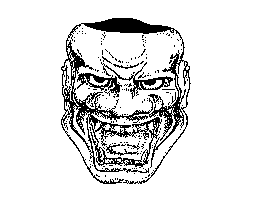 [図]
[図]
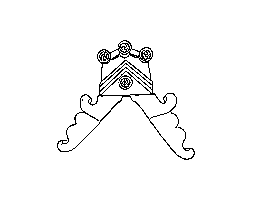 [図]
獅子口(2)
[図]
獅子口(2)
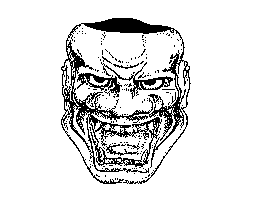 [図]
[図]
しし-こく【獅子国】🔗⭐🔉
しし-こく 【獅子国】
セイロン(現スリランカ)の古名。
しし-こつ【四肢骨】🔗⭐🔉
しし-こつ [2] 【四肢骨】
上肢および下肢の骨の総称。
ししこらか・す🔗⭐🔉
ししこらか・す (動サ四)
病気などを治しそこなう。こじらす。「―・しつる時は,うたて侍るを/源氏(若紫)」
しし-ざ【獅子座】🔗⭐🔉
しし-ざ [0] 【獅子座】
(1)仏の座る座。また,高僧の座る所。猊座(ゲイザ)。獅子の座。
(2)〔(ラテン) Leo〕
四月下旬の宵に南中する星座。黄道十二宮の獅子宮に相当した。ギリシャ神話ではネメアの谷間に住み人畜を害した獅子で,ヘラクレスに退治されたものという。
ししざ-りゅうせいぐん【獅子座流星群】🔗⭐🔉
ししざ-りゅうせいぐん ―リウセイ― [6] 【獅子座流星群】
毎年11月一六,七日頃に現れる流星群。獅子座ガンマ星の近くに放射点がある。約33年ごとに大出現し,1799年.1833年には大流星雨をもたらした。
しし-ざる【獅子猿】🔗⭐🔉
しし-ざる [3] 【獅子猿】
ライオン-タマリンの別名。
ししし【子思子】🔗⭐🔉
ししし 【子思子】
孔子の孫,子思の撰による儒書。宋代に散逸して現存しないが,「礼記」中の「中庸」はその一部であるという。
しし-じもの【猪じもの・鹿じもの】🔗⭐🔉
しし-じもの 【猪じもの・鹿じもの】
〔「じもの」は接尾語〕
鹿(シカ)や猪(イノシシ)のように。副詞的に用いる。「―い這(ハ)ひ伏しつつ/万葉 199」
しし-そうしょう【師資相承】🔗⭐🔉
しし-そうしょう ―サウシヨウ [1] 【師資相承】 (名)スル
師から弟子へと道を次第に伝えていくこと。
しし-そんそん【子子孫孫】🔗⭐🔉
しし-そんそん [1] 【子子孫孫】
子孫を強めていう語。子孫の続く限りの意。代々。「―に至るまで語り伝える」
しし-たけ【猪茸】🔗⭐🔉
しし-たけ [2] 【猪茸】
担子菌類ヒダナシタケ目のきのこ。傘の径は20〜30センチメートル。あくが強く,苦味がある。近縁種のコウタケと同種とする説もある。
ししち-ほん【四七品】🔗⭐🔉
ししち-ほん [3][0] 【四七品】
「妙法蓮華経」の異名。二八品から成るのでいう。
し-しつ【死失】🔗⭐🔉
し-しつ [0] 【死失】
死ぬこと。「今若し一朝病苦の為めに此処にて―せなば/経国美談(竜渓)」
し-しつ【私室】🔗⭐🔉
し-しつ [0] 【私室】
公共の建物の中で,個人が私的に使う部屋。
し-しつ【屍室】🔗⭐🔉
し-しつ [0] 【屍室】
病院などの霊安室のこと。
し-しつ【紙質】🔗⭐🔉
し-しつ [0] 【紙質】
紙の品質。かみしつ。
し-しつ【脂質】🔗⭐🔉
し-しつ [1] 【脂質】
生物体内に存在して,水に不溶,有機溶媒に可溶の有機化合物の総称。脂肪酸と各種アルコールとのエステルである単純脂質(中性脂肪あるいは油脂,蝋(ロウ)),脂肪酸・アルコール・リン酸・糖などから成る複合脂質(リン脂質・糖脂質など),および以上二者の加水分解生成物で水に不溶の物質(脂肪酸・高級アルコール・ステロールなど)やテルペン・脂溶性ビタミンなどの誘導脂質に分類される。リピド。
し-しつ【歯質】🔗⭐🔉
し-しつ [0] 【歯質】
⇒象牙質(ゾウゲシツ)
し-しつ【資質】🔗⭐🔉
し-しつ [0] 【資質】
生まれつきの性質や才能。「優秀な―」
しし-つき【肉付き】🔗⭐🔉
しし-つき [0] 【肉付き】
肉づき。ししおき。
し-しつだん【四悉檀】🔗⭐🔉
し-しつだん [2] 【四悉檀】
〔仏〕
〔悉檀は 梵 siddh nta の音訳で,教説の立て方の意〕
仏が人々を教え導く四種の方法。世界悉檀(人々の心に合わせて説く),各々為人悉檀(各人の宗教的能力を考えて説く),対治悉檀(煩悩(ボンノウ)を打ち砕く),第一義悉檀(真理に直接導こうとする)の四つ。
nta の音訳で,教説の立て方の意〕
仏が人々を教え導く四種の方法。世界悉檀(人々の心に合わせて説く),各々為人悉檀(各人の宗教的能力を考えて説く),対治悉檀(煩悩(ボンノウ)を打ち砕く),第一義悉檀(真理に直接導こうとする)の四つ。
 nta の音訳で,教説の立て方の意〕
仏が人々を教え導く四種の方法。世界悉檀(人々の心に合わせて説く),各々為人悉檀(各人の宗教的能力を考えて説く),対治悉檀(煩悩(ボンノウ)を打ち砕く),第一義悉檀(真理に直接導こうとする)の四つ。
nta の音訳で,教説の立て方の意〕
仏が人々を教え導く四種の方法。世界悉檀(人々の心に合わせて説く),各々為人悉檀(各人の宗教的能力を考えて説く),対治悉檀(煩悩(ボンノウ)を打ち砕く),第一義悉檀(真理に直接導こうとする)の四つ。
ししっ-ぱな【獅子っ鼻】🔗⭐🔉
ししっ-ぱな [0][2] 【獅子っ鼻】
「ししばな(獅子鼻)」に同じ。
しし-とう【獅子唐】🔗⭐🔉
しし-とう ―タウ [0] 【獅子唐】
「ししとうがらし」の略。
しし-とうがらし【獅子唐芥子】🔗⭐🔉
しし-とうがらし ―タウガラシ [5] 【獅子唐芥子】
トウガラシの栽培変種。いわゆるピーマンのうち,在来品種で,果実が小さく細長いもの。シシトウ。青唐芥子。
しし-なべ【猪鍋】🔗⭐🔉
しし-なべ [0] 【猪鍋】
薄切りにした猪(イノシシ)の肉を野菜類とともに味噌仕立てにした鍋料理。割り下で煮ることもある。いのしし鍋。ぼたん鍋。[季]冬。
しし-の-ざ【獅子の座】🔗⭐🔉
しし-の-ざ 【獅子の座】
⇒ししざ(獅子座)(1)
しし-ばな【獅子鼻】🔗⭐🔉
しし-ばな [0] 【獅子鼻】
(1)(獅子頭{(1)}の鼻に似て)低く小鼻の広がった鼻。ししっぱな。
(2)獅子の頭部に似せて彫刻した木鼻(キバナ)。
しし-ばば【尿糞】🔗⭐🔉
しし-ばば 【尿糞】
小便と大便。「立居もひとりで出来ねえから,―もおまるでとる/滑稽本・浮世風呂 2」
しし-びしお【肉醤・醢】🔗⭐🔉
しし-びしお ―ビシホ 【肉醤・醢】
肉を用いた,塩辛のような食品。にくしょう。[和名抄]
しし-ぶえ【鹿笛】🔗⭐🔉
しし-ぶえ [2][3] 【鹿笛】
「しかぶえ(鹿笛)」に同じ。
しし-ふしゅせつ【止止不須説】🔗⭐🔉
しし-ふしゅせつ [4] 【止止不須説】
〔仏〕
〔法華経(方便品)〕
舎利弗(シヤリホツ)が最高の教えを求めたのに対し,釈迦が三度断ったときの言葉。「止みなん,止みなん,説くべからず」と訓読する。なおも教えを請う舎利弗の求めに応じ,法華経の教説が語られる。
しし-ふせぎ【猪防ぎ・鹿防ぎ】🔗⭐🔉
しし-ふせぎ [3] 【猪防ぎ・鹿防ぎ】
猪(イノシシ)や鹿(シカ)などが田畑を荒らすのを防ぐための設備。
しし【嗣子】(和英)🔗⭐🔉
しし【獅子】(和英)🔗⭐🔉
しし【四肢】(和英)🔗⭐🔉
しし【四肢】
the limbs;the legs and arms.
しし【志士】(和英)🔗⭐🔉
しし【志士】
a patriot.→英和
ししそんそん【子々孫々に伝える】(和英)🔗⭐🔉
ししそんそん【子々孫々に伝える】
hand down to posterity.〜に至るまで even to one's remotest descendants.
ししつ【資質】(和英)🔗⭐🔉
ししつ【紙質】(和英)🔗⭐🔉
ししつ【紙質】
the quality of paper.
ししつ【私室】(和英)🔗⭐🔉
ししつ【私室】
a private room.
大辞林に「しし」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む
 足(ダクアシ)
足(ダクアシ)