複数辞典一括検索+![]()
![]()
えび‐ね【海=老根・×蝦根】🔗⭐🔉
えび‐ね【海=老根・×蝦根】

 ラン科エビネ属の多年草。山林や竹林に生え、高さ三〇〜四〇センチ。根茎は太くて節が多く、横にはい、エビに似る。葉は長楕円形で縦ひだがある。春、紫褐色で中央が白または紅紫色の花を一〇個ほど開く。エビネ属にはキエビネ・ニオイエビネなども含まれ、観賞用に栽培され、園芸品種が多い。《季 春》
ラン科エビネ属の多年草。山林や竹林に生え、高さ三〇〜四〇センチ。根茎は太くて節が多く、横にはい、エビに似る。葉は長楕円形で縦ひだがある。春、紫褐色で中央が白または紅紫色の花を一〇個ほど開く。エビネ属にはキエビネ・ニオイエビネなども含まれ、観賞用に栽培され、園芸品種が多い。《季 春》

 ラン科エビネ属の多年草。山林や竹林に生え、高さ三〇〜四〇センチ。根茎は太くて節が多く、横にはい、エビに似る。葉は長楕円形で縦ひだがある。春、紫褐色で中央が白または紅紫色の花を一〇個ほど開く。エビネ属にはキエビネ・ニオイエビネなども含まれ、観賞用に栽培され、園芸品種が多い。《季 春》
ラン科エビネ属の多年草。山林や竹林に生え、高さ三〇〜四〇センチ。根茎は太くて節が多く、横にはい、エビに似る。葉は長楕円形で縦ひだがある。春、紫褐色で中央が白または紅紫色の花を一〇個ほど開く。エビネ属にはキエビネ・ニオイエビネなども含まれ、観賞用に栽培され、園芸品種が多い。《季 春》
エピネフリン【epinephrine】🔗⭐🔉
エピネフリン【epinephrine】
 アドレナリン
アドレナリン
 アドレナリン
アドレナリン
えびの🔗⭐🔉
えびの
宮崎県南西部の市。米作や畜産が盛ん。南部に、えびの高原がある。人口二・七万。
えびの‐こうげん【えびの高原】‐カウゲン🔗⭐🔉
えびの‐こうげん【えびの高原】‐カウゲン
宮崎県南西部にある高原。標高約一二〇〇メートル。韓国(からくに)岳・白鳥(しらとり)山・甑(こしき)岳に囲まれ、六観音池などの火口湖や温泉がある。中央にある硫黄山の噴気で、秋にススキがえび色に染まる。
えび‐の‐しっぽ【海=老の×尻△尾】🔗⭐🔉
えび‐の‐しっぽ【海=老の×尻△尾】

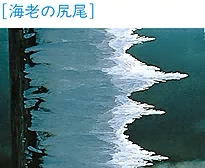 霧氷の一。高山などで、セ氏零度以下に過冷却した霧や雲の粒が岩石・樹木などに吹きつけられて着氷したもの。風上側に伸び、エビの尾状になる。
霧氷の一。高山などで、セ氏零度以下に過冷却した霧や雲の粒が岩石・樹木などに吹きつけられて着氷したもの。風上側に伸び、エビの尾状になる。

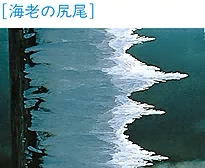 霧氷の一。高山などで、セ氏零度以下に過冷却した霧や雲の粒が岩石・樹木などに吹きつけられて着氷したもの。風上側に伸び、エビの尾状になる。
霧氷の一。高山などで、セ氏零度以下に過冷却した霧や雲の粒が岩石・樹木などに吹きつけられて着氷したもの。風上側に伸び、エビの尾状になる。
えび‐の‐はたふね【×蝦の×鰭△槽】🔗⭐🔉
えび‐の‐はたふね【×蝦の×鰭△槽】
大嘗祭(だいじようさい)や新嘗祭(しんじようさい)で、天皇が手を洗う器。土器で、両端にエビの尾に似た取っ手がついている。えびはたふね。
えびはら‐きのすけ【海老原喜之助】🔗⭐🔉
えびはら‐きのすけ【海老原喜之助】
[一九〇四〜一九七〇]洋画家。鹿児島の生まれ。川端画学校で学んだのち、渡仏して藤田嗣治に師事。帰国後、独立美術協会展に出品した「曲馬」などが代表作。骨太い造形性を備えた斬新な作風で、国際的に活躍した。
え‐ひめ【△兄姫】🔗⭐🔉
え‐ひめ【△兄姫】
姉妹のうち年長のほうのむすめ。「名は―、弟比売(おとひめ)、この二柱の女王(ひめみこ)、浄き公民(たみ)なり」〈記・中〉 弟姫(おとひめ)。
弟姫(おとひめ)。
 弟姫(おとひめ)。
弟姫(おとひめ)。
えひめ【愛媛】🔗⭐🔉
えひめ【愛媛】
四国地方北西部の県。もとの伊予(いよ)国にあたる。県庁所在地は松山市。名は、古事記に「伊予国は愛比売(えひめ)と謂(い)ひ」とあるところによる。
大辞泉 ページ 1735。