複数辞典一括検索+![]()
![]()
○吾が仏尊しあがほとけとうとし🔗⭐🔉
○吾が仏尊しあがほとけとうとし
自分のありがたく思っているものだけが尊いと考えて、世間一般のことをかえりみない偏狭な心をいう。我が家の仏尊し。
⇒あ‐が‐ほとけ【吾が仏】
あか‐ほや【赤ほや】
火山灰土壌の一種。黄橙色でおがくず状軽鬆けいそうのガラス質。南九州に分布。いもご。あかおんじ。
あかぼり【赤堀】
姓氏の一つ。
⇒あかぼり‐しろう【赤堀四郎】
あかぼり‐しろう【赤堀四郎】‥ラウ
有機化学者。静岡県生れ。阪大教授、同学長。阪大蛋白質研究所初代所長。酵素タカアミラーゼの結晶化に成功。また蛋白質のアミノ酸を決定する赤堀法を開発、蛋白質の構造解明に貢献。文化勲章。(1900〜1992)
⇒あかぼり【赤堀】
あか‐ほん【赤本】
①江戸中期に刊行された草双紙くさぞうしの一種。遅くとも宝永(1704〜1711)には存し、享保(1716〜1736)頃盛行。形は半紙半截はんせつ、1冊5丁。赤色の表紙を用いた。桃太郎・猿蟹さるかに合戦などのお伽噺とぎばなしを題材とし、絵を主とした子供向きのもの。初期のものには、やや小型で「赤小本」といわれるものがあり、また、ままごと遊びや雛祭用のためにこれをさらに小さくした「ひいな本」もある。→黒本。
②草双紙の総称。
③赤色を主とした極彩色の表紙の少年向き講談本。
④俗受けをねらった低級な安い本。
あかま【赤間】
地名の一つ。
⇒あかま‐いし【赤間石】
⇒あかま‐が‐せき【赤間関・赤馬関】
⇒あかま‐じんぐう【赤間神宮】
あか‐ま【淦間】
和船のあかのたまる所で、多くはなかほどの低い所。
あかま‐いし【赤間石】
山口県山陽小野田市から産出する赤褐色・紫色・紫青色の凝灰質泥岩。硯材とする。あかま。
⇒あかま【赤間】
あがま・う【崇まふ】アガマフ
〔他下二〕
(アガムに接尾語フの付いた語)「あがめる」に同じ。狂言、富士松「猿は山王の使者でござる。まづ―・へて御ざる」
あか‐まえだれ【赤前垂れ】‥マヘ‥
赤い色の前垂。近世、料理屋・茶屋などの接客の女が用いた。また、それを着用した女。
あかま‐が‐せき【赤間関・赤馬関】
下関しものせきの古称。太平記39「門司・―を経て」
⇒あかま【赤間】
あかま‐じんぐう【赤間神宮】
下関市にある元官幣大社。祭神は安徳天皇。もと阿弥陀寺・赤間宮といった。
⇒あかま【赤間】
あかまた
ヘビの一種。全長1〜1.5メートル。無毒。性質はかなり荒く、鼠・鳥・トカゲ・蛇・蛙などを食う。奄美諸島と沖縄諸島にすみ、奄美では「まったぶ」という。
あかまた‐くろまた【赤また黒また】
沖縄の八重山諸島に残る民俗行事。旧暦6月の豊年祭に、海上の楽土「にらいかない」から訪れる仮面姿の二神を迎える行事。
あか‐まつ【赤松】
マツ科の常緑高木。樹皮は亀甲状にはげやすく、芽の色と共に赤褐色。山地に多い。クロマツより葉が柔らかい。材は建築用皮付丸太、薪炭用、パルプの原料。雌松めまつ。
アカマツ
撮影:関戸 勇
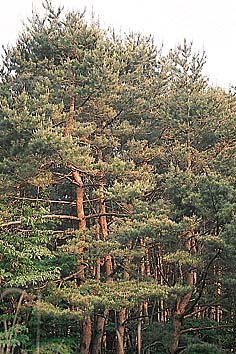 あかまつ【赤松】
姓氏の一つ。播磨の豪族。鎌倉時代佐用荘を本拠として興り、南北朝時代以降同国守護。室町幕府四職ししきの一家。
⇒あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
⇒あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】
⇒あかまつ‐のりむら【赤松則村】
⇒あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
⇒あかまつ‐よしのり【赤松義則】
あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
社会運動家。山口県生れ。東大在学中、新人会を結成。日本労働総同盟・日本共産党で活動、のち社会民衆党書記長。満州事変後は国家社会主義に転じ、さらに日本主義を唱え、大政翼賛会などに参加。主著「日本社会運動史」。(1894〜1955)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】‥イウ
(名はノリスケとも)南北朝時代の武将。則村の子。はじめ出家。後醍醐天皇の倒幕挙兵に加わり、のち足利尊氏に従って、播磨・備前の守護。(1311〜1371)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐のりむら【赤松則村】
南北朝初期の武将。播磨の守護。法名、円心。元弘の乱に六波羅を攻めたが、のち足利尊氏に従い、白旗城に拠って新田義貞の追撃を阻止。(1277〜1350)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
室町中期の武将。播磨・備前・美作の守護。足利義教を自邸に招いて殺し播磨に走ったが、山名持豊(宗全)らに攻められて自刃。(1373〜1441一説に1381〜1441)→嘉吉かきつの乱。
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐よしのり【赤松義則】
南北朝・室町初期の武将。則祐の子。明徳の乱に功あり、播磨・備前・美作守護、幕府の侍所所司。(1358〜1427)
⇒あかまつ【赤松】
あ‐が‐まま【吾が儘】
自分の思い通り。わがまま。大鏡兼家「一天下を―にして」
あか‐まんま【赤飯】
イヌタデの別称。あかのまんま。
あか‐み【赤み】
赤い程度。赤さ。「頬に―がさす」
⇒あかみ‐じょうご【赤み上戸】
⇒あかみ‐ばし・る【赤み走る】
あか‐み【赤身】
①動物の赤い肉。特に魚類についていう。↔白身しろみ。
②木材の中心の生活機能を失った帯紅色の部分。心材。↔白太しらた
あ‐が‐み【吾が身】
①自分。わがみ。
②(代名詞的に)相手を呼ぶ語。そなた。わがみ。物類称呼「他ひとをさして云ふ詞に、畿内にて―と云ふ」
あかみ‐じょうご【赤み上戸】‥ジヤウ‥
飲めば、すぐに顔の赤くなる酒飲み。色上戸。色み上戸。狂言、酒講式「かくしても、かくしかひなき、―は笑止の者なり」↔青み上戸。
⇒あか‐み【赤み】
あか‐みず【赤水】‥ミヅ
寒流。親潮おやしお。
あか‐みず【閼伽水】‥ミヅ
仏に供える水。散木奇歌集「花の―むすぶ手の」
あか‐みそ【赤味噌】
赤褐色に仕上げた味噌。辛口と甘口とがある。田舎味噌・仙台味噌・江戸味噌の類。
あかみ‐ばし・る【赤み走る】
〔自四〕
赤みがさす。赤くなる。好色一代女6「上髭うわひげありて―・り、天窓あたまはきんかなる人」
⇒あか‐み【赤み】
あかみみ‐がめ【赤耳亀】
カメの一種。北アメリカ原産。側頭部に赤い斑紋があるのでこの名がある。子ガメはミドリガメと呼ばれ、ペットとして輸入。その逃げ出したものが成長し、全国の川や池に定着。
アカミミガメ
撮影:関戸 勇
あかまつ【赤松】
姓氏の一つ。播磨の豪族。鎌倉時代佐用荘を本拠として興り、南北朝時代以降同国守護。室町幕府四職ししきの一家。
⇒あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
⇒あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】
⇒あかまつ‐のりむら【赤松則村】
⇒あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
⇒あかまつ‐よしのり【赤松義則】
あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
社会運動家。山口県生れ。東大在学中、新人会を結成。日本労働総同盟・日本共産党で活動、のち社会民衆党書記長。満州事変後は国家社会主義に転じ、さらに日本主義を唱え、大政翼賛会などに参加。主著「日本社会運動史」。(1894〜1955)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】‥イウ
(名はノリスケとも)南北朝時代の武将。則村の子。はじめ出家。後醍醐天皇の倒幕挙兵に加わり、のち足利尊氏に従って、播磨・備前の守護。(1311〜1371)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐のりむら【赤松則村】
南北朝初期の武将。播磨の守護。法名、円心。元弘の乱に六波羅を攻めたが、のち足利尊氏に従い、白旗城に拠って新田義貞の追撃を阻止。(1277〜1350)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
室町中期の武将。播磨・備前・美作の守護。足利義教を自邸に招いて殺し播磨に走ったが、山名持豊(宗全)らに攻められて自刃。(1373〜1441一説に1381〜1441)→嘉吉かきつの乱。
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐よしのり【赤松義則】
南北朝・室町初期の武将。則祐の子。明徳の乱に功あり、播磨・備前・美作守護、幕府の侍所所司。(1358〜1427)
⇒あかまつ【赤松】
あ‐が‐まま【吾が儘】
自分の思い通り。わがまま。大鏡兼家「一天下を―にして」
あか‐まんま【赤飯】
イヌタデの別称。あかのまんま。
あか‐み【赤み】
赤い程度。赤さ。「頬に―がさす」
⇒あかみ‐じょうご【赤み上戸】
⇒あかみ‐ばし・る【赤み走る】
あか‐み【赤身】
①動物の赤い肉。特に魚類についていう。↔白身しろみ。
②木材の中心の生活機能を失った帯紅色の部分。心材。↔白太しらた
あ‐が‐み【吾が身】
①自分。わがみ。
②(代名詞的に)相手を呼ぶ語。そなた。わがみ。物類称呼「他ひとをさして云ふ詞に、畿内にて―と云ふ」
あかみ‐じょうご【赤み上戸】‥ジヤウ‥
飲めば、すぐに顔の赤くなる酒飲み。色上戸。色み上戸。狂言、酒講式「かくしても、かくしかひなき、―は笑止の者なり」↔青み上戸。
⇒あか‐み【赤み】
あか‐みず【赤水】‥ミヅ
寒流。親潮おやしお。
あか‐みず【閼伽水】‥ミヅ
仏に供える水。散木奇歌集「花の―むすぶ手の」
あか‐みそ【赤味噌】
赤褐色に仕上げた味噌。辛口と甘口とがある。田舎味噌・仙台味噌・江戸味噌の類。
あかみ‐ばし・る【赤み走る】
〔自四〕
赤みがさす。赤くなる。好色一代女6「上髭うわひげありて―・り、天窓あたまはきんかなる人」
⇒あか‐み【赤み】
あかみみ‐がめ【赤耳亀】
カメの一種。北アメリカ原産。側頭部に赤い斑紋があるのでこの名がある。子ガメはミドリガメと呼ばれ、ペットとして輸入。その逃げ出したものが成長し、全国の川や池に定着。
アカミミガメ
撮影:関戸 勇
 あか・む【赤む】
[一]〔自四〕
赤くなる。赤みがつく。枕草子3「顔少し―・みてゐたるこそをかしけれ」
[二]〔他下二〕
⇒あかめる(下一)
あが・む【崇む】
〔他下二〕
⇒あがめる(下一)
あか‐むけ【赤剥け】
皮膚が赤くすりむけること。また、その赤はだ。
あか‐むし【赤虫】
①ビクイソメ科の大形の多毛類。体長0.6〜1メートル。環節数は600〜800に達し、濃い橙紅色。本州南部沿岸の砂泥中にすみ、マダイの釣餌に好適。
②ツツガムシの別称。
③「あかぼうふら」の別称。
あか‐むつ【赤鯥】
①スズキ科の海産の硬骨魚。暖海の深部にすむ。食用。のどぐろ。
アカムツ
提供:東京動物園協会
あか・む【赤む】
[一]〔自四〕
赤くなる。赤みがつく。枕草子3「顔少し―・みてゐたるこそをかしけれ」
[二]〔他下二〕
⇒あかめる(下一)
あが・む【崇む】
〔他下二〕
⇒あがめる(下一)
あか‐むけ【赤剥け】
皮膚が赤くすりむけること。また、その赤はだ。
あか‐むし【赤虫】
①ビクイソメ科の大形の多毛類。体長0.6〜1メートル。環節数は600〜800に達し、濃い橙紅色。本州南部沿岸の砂泥中にすみ、マダイの釣餌に好適。
②ツツガムシの別称。
③「あかぼうふら」の別称。
あか‐むつ【赤鯥】
①スズキ科の海産の硬骨魚。暖海の深部にすむ。食用。のどぐろ。
アカムツ
提供:東京動物園協会
 ②コイ科の淡水魚カワムツの生殖期の雄。
あか‐むらさき【赤紫】
赤みをおびた紫色。源氏物語絵合「―の表紙、紫檀の軸」
Munsell color system: 5RP4.5/12
あか‐め【赤女】
赤い色の鯛。神代紀下「―は赤鯛なり」
あか‐め【赤目】
①疲れ・病気や緊張などのため、眼の結膜が充血して赤く見えるもの。また、興奮して血筋の張った目。
②白子しろこなどの眼。虹彩が赤いもの。虹彩や眼底の色素の欠乏により、眼底の血管が透けて見えるのによる。
③⇒あかんべ。
④〔動〕
㋐アカメ科の汽水魚。四国南部と九州東南部の大河に遡ることもある。瞳孔が赤く見える場合が多い。
㋑ヒガイ(鰉)の方言。
㋒メナダ(赤目魚)の方言。
⇒あかめ‐げんしょう【赤目現象】
⇒あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
あかめ【赤目】
三重県西部、名張なばり市南西部の地区。赤目四十八滝と称する大小多数の滝で有名。
赤目四十八滝
撮影:的場 啓
②コイ科の淡水魚カワムツの生殖期の雄。
あか‐むらさき【赤紫】
赤みをおびた紫色。源氏物語絵合「―の表紙、紫檀の軸」
Munsell color system: 5RP4.5/12
あか‐め【赤女】
赤い色の鯛。神代紀下「―は赤鯛なり」
あか‐め【赤目】
①疲れ・病気や緊張などのため、眼の結膜が充血して赤く見えるもの。また、興奮して血筋の張った目。
②白子しろこなどの眼。虹彩が赤いもの。虹彩や眼底の色素の欠乏により、眼底の血管が透けて見えるのによる。
③⇒あかんべ。
④〔動〕
㋐アカメ科の汽水魚。四国南部と九州東南部の大河に遡ることもある。瞳孔が赤く見える場合が多い。
㋑ヒガイ(鰉)の方言。
㋒メナダ(赤目魚)の方言。
⇒あかめ‐げんしょう【赤目現象】
⇒あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
あかめ【赤目】
三重県西部、名張なばり市南西部の地区。赤目四十八滝と称する大小多数の滝で有名。
赤目四十八滝
撮影:的場 啓
 あか‐め【赤芽】
植物の赤みを帯びた新芽。また、新芽の美しいアカメガシワ・カナメモチなどの園芸上の通称。
⇒あかめ‐がしわ【赤芽柏】
⇒あかめ‐もち【赤芽黐】
あかめ‐がしわ【赤芽柏】‥ガシハ
(若葉が鮮紅色だからいう)トウダイグサ科の落葉高木。日本・中国大陸に自生、日本では二次林に多い。高さ10メートルに達する。雌雄異株。夏、白色の花を穂状につける。材は軟らかく、床柱・下駄・薪炭などに用いる。果実の毛を集めて駆虫剤(主にサナダムシ)とする。
あかめがしわ
あか‐め【赤芽】
植物の赤みを帯びた新芽。また、新芽の美しいアカメガシワ・カナメモチなどの園芸上の通称。
⇒あかめ‐がしわ【赤芽柏】
⇒あかめ‐もち【赤芽黐】
あかめ‐がしわ【赤芽柏】‥ガシハ
(若葉が鮮紅色だからいう)トウダイグサ科の落葉高木。日本・中国大陸に自生、日本では二次林に多い。高さ10メートルに達する。雌雄異株。夏、白色の花を穂状につける。材は軟らかく、床柱・下駄・薪炭などに用いる。果実の毛を集めて駆虫剤(主にサナダムシ)とする。
あかめがしわ
 ⇒あか‐め【赤芽】
あかめ‐げんしょう【赤目現象】‥シヤウ
(写真用語)フラッシュを用いて顔を撮影した時、瞳が兎の眼のように赤く写る現象。強い光が網膜の毛細血管で反射するために起こる。
⇒あか‐め【赤目】
あか‐めばる【赤眼張】
①体色が赤みを帯びるメバル属の魚の俗称。
②ハタ科の海魚。アカハタ。(鹿児島方言)
あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
フグ科の海魚。全長約30センチメートル。帯赤褐色。本州中部以南の内湾に多い。身と精巣以外は毒性が強い。
⇒あか‐め【赤目】
アガメムノン【Agamemnōn】
ギリシア神話のミュケナイ(ミケネ)王。トロイア戦争におけるギリシア軍の総帥。オレステス・イフィゲネイア・エレクトラの父。凱旋後、妃クリュタイムネストラとその情夫アイギストスとに暗殺された。
あかめ‐もち【赤芽黐】
〔植〕カナメモチの別称。アカメ。
⇒あか‐め【赤芽】
あか・める【赤める】
〔他下一〕[文]あか・む(下二)
赤くする。赤らめる。源氏物語帚木「顔うち―・めてゐたり」
あが・める【崇める】
〔他下一〕[文]あが・む(下二)
①尊いものとして扱う。神代紀下「益ますます―・め敬いやまふ」。「祖先を―・める」
②寵愛する。源氏物語帚木「親など立ち副ひもて―・めて」
あか‐もがさ【赤疱瘡・赤斑瘡】
麻疹はしかの古称。栄華物語嶺月「―といふものいできて」
あか‐もく【赤藻屑】
褐藻類ホンダワラ科の海藻。高さ数メートルに達する。葉は約3センチメートル、有柄の線形で欠刻がある。茶褐色。枯れはじめると赤みを帯びる。浅海の岩礁の多い所に生育。流れ藻の構成種。肥料やヨードの原料。
あか‐もの【赤物】
①色の赤いもの。特に、タイ・ホウボウなど、外皮の赤い魚。
②ツツジ科の常緑小低木。高山帯に生え、高さ10〜30センチメートル。葉は厚く卵形でとがる。茎には赤い毛がある。夏、葉腋に鐘形の小白花をつけ、実は円くて紅熟。イワハゼ。
③赤く彩色した人形・玩具。赤色が病魔を退散させるという俗信から、江戸時代疱瘡ほうそう除けのまじないとして流行。
あが‐もの【贖物】
①祓はらえの時、身の災いをあがない祓うもの。人形ひとかたに災いを負わせて水に流しやる類。形代かたしろ。
②罪のつぐないとして出す財物。
あか‐もん【赤門】
①朱塗りの門。→御守殿ごしゅでん門。
②東京大学の南西隅の朱塗りの門。もと加賀前田家上屋敷の御守殿門で、1827年(文政10)将軍家斉の女むすめ溶姫が前田斉泰に嫁した際に建造したもの。転じて、東京大学の異称。「―出で」
あか‐やがら【赤矢柄】
魚類のヤガラの一種。体色が赤みを帯びる。→やがら3
あか‐ゆうたい【赤郵袋】‥イウ‥
紅色の布製の郵便郵袋。速達としない書留・現金書留郵便物を入れて、一局から他局へ送る袋。
あか‐ゆき【赤雪】
⇒せきせつ
あか‐ゆみ【赤弓】
丹や朱または赤漆で塗った弓。
あか‐ら【赤ら】
①赤みを帯びているさま。
②(飲めば顔が赤くなるからいう)酒の異称。本朝二十不孝「先祖より酒の家に生れ、―呑めといはれて此の方」
⇒あから‐おぶね【赤ら小舟】
⇒あから‐か【赤らか】
⇒あから‐がお【赤ら顔】
⇒あから‐がしわ【赤ら柏】
あから‐おぶね【赤ら小舟】‥ヲ‥
赤く塗った舟。特に、官船。(古代、官船は赤く塗ったから)万葉集16「沖行くや―に裹つとやらば」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐か【赤らか】
赤みを帯びて美しいさま。源氏物語常夏「紅といふものいと―にかいつけて」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がお【赤ら顔】‥ガホ
赤みをおびた顔。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がしわ【赤ら柏】‥ガシハ
①葉に赤みのある柏。供物を盛る具とした。万葉集20「印南野の―は時はあれど」
②京都北野天満宮の11月1日の祭。供物を赤ら柏に盛るからいう。6月の青柏祭に対する。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐さま
(「偸閑」「白地」とも当てる)
①たちまち。急。皇極紀「―に斬るべし」
②一時的であるさま。ちょっと。しばらく。宇津保物語忠乞「暇許させ給はぬをしひて申して―にまかでぬ」
③(「―にも」の形で、否定の語を伴って)かりそめにも。古今著聞集20「―にも、あどなきことをばすまじきことなり」
④かくさず、ありのまま。あらわ。はっきり。好色一代女4「女は妖淫うつくしき肌を―になし」。「―に言う」「―な軽蔑」
あから・し
〔形シク〕
痛切である。ひどい。一説に、悲しい。欽明紀「何ぞ悲しきことの―・しき」。蜻蛉日記下「などか来ぬ、とはぬ、にくし、―・しとて」
あからし・ぶ
〔自四〕
痛切に感ずる。心から嘆く。〈日本霊異記上訓釈〉
あからしま‐かぜ【あからしま風】
(アカラシマはアカラサマ(俄かの意)の転)暴風。はやて。あかしまかぜ。あらしまかぜ。神武紀「海の中にして卒にわかに―に遇ひぬ」
あからひき‐の‐いと【赤ら引の糸】
(→)「あかひきのいと」に同じ。持統紀「―参拾伍斤」
あから‐ひく【赤ら引く】
〔枕〕
(明るく光る、あるいは、赤みを帯びる意)「日」「月」「子」「君」「朝」「膚」「敷妙」にかかる。
あから・ぶ【赤らぶ】
〔自上二〕
赤みがさす。赤くなる。赤らむ。祝詞、神賀詞「赤玉のみ―・びまし」
あから・ぶ【明らぶ】
〔他下二〕
明らかにする。心をはらす。続日本紀31「誰とともにかも見そなはし―・べたまはむと」
あから・む【赤らむ】
[一]〔自五〕
赤くなる。赤みがさす。「―・んだ顔」
[二]〔他下二〕
⇒あからめる(下一)
あから・む【明らむ】
〔自五〕
夜が明けてきて、空が明るくなる。「東の空が―・む」
あから‐め【あから目】
(アカラはアカル(散)と同根)
①ふと目をほかへ移すこと。わきみ。よそみ。徒然草「花の本には、ねぢ寄り立ち寄り、―もせずまもりて」
②心をほかへ移すこと。うわき。宇津保物語俊蔭「いみじき色好みを、かく―もせさせたてまつらぬこと」
⇒あからめ‐さ・す【あから目さす】
あからめ‐さ・す【あから目さす】
〔他四〕
ふと目をそらす間に、急に見えなくなる。続日本紀36「―・す事のごとく」
⇒あから‐め【あから目】
あから・める【赤らめる】
〔他下一〕[文]あから・む(下二)
赤くする。赤める。「顔を―・める」
あか‐ランプ【赤ランプ】
赤い灯火。危険を知らせる信号。「計画の実行に―がつく」
あかり【明かり】
①物を明らかにする光。光線。「一筋の―がさす」「ネオンの―」
②灯火。あかし。「―をつける」「―をともす」
③明るい所。おもてだったところ。あかるみ。〈日葡辞書〉
④疑いをはらす証拠。証あかし。浄瑠璃、新版歌祭文「久松様の―もたちまち、打ってかはった勘六殿」。「―を立てる」
⑤諒闇りょうあんなど暗い気分の期間が終わること。あけ。
⇒あかり‐さき【明り先】
⇒あかり‐しょいん【明書院】
⇒あかり‐しょうじ【明り障子】
⇒あかり‐そうじ【明り障子】
⇒あかり‐どこ【明り床】
⇒あかり‐とり【明り取り】
⇒あかり‐まど【明り窓】
⇒明かりが立つ
⇒明かりを走る
あがり【上がり・揚り】
①位置・地位・価値・程度・値段・能力などが高い方に向かうこと。はねあがること。
②風呂などから出ること。日葡辞書「フロアガリ」。浮世風呂前「ヤア、義遊さん、モウお―かナ」
③地方から京都へ来ること。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「―の衆ならば、土産みやげ召せ召せ」
④終わること。だめになること。(雨が)やむこと。(魚・虫が)死ぬこと。また、用ずみになること。〈日葡辞書〉。「膳の―」
⑤できあがること。また、そのできぐあい。仕上がり。浮世風呂3「伊予染に黒裏さ。とんだいい―だつた」。「蚕の―(上蔟)」「ホラ、一丁―だ」
⑥双六すごろくで、駒が最終の場所へ進むこと。また、その場所。また、トランプなどで勝負がつくこと。
⑦収入。収穫。売上げ。「今日の―は少なかった」
⑧(沖縄で)東。
⑨(「上がり花」の略)お茶。
⑩(接尾語的に)前にその職業・身分・状態だった者。「役人―」「病気―」
⇒あがり‐うま【騰り馬】
⇒あがり‐おり【上がり下り】
⇒あがり‐かぶと【上り兜・揚り甲】
⇒あがり‐かまち【上がり框】
⇒あがり‐くち【上がり口】
⇒あがり‐さがり【上がり下がり】
⇒あがり‐ざしき【揚座敷】
⇒あがり‐ぜん【上がり膳】
⇒あがり‐だか【上がり高】
⇒あがり‐だん【上がり段】
⇒あがり‐ち【上地・上知】
⇒あがり‐でんじ【上がり田地】
⇒あがり‐なまず【上がり鯰】
⇒あがり‐ば【上がり場】
⇒あがり‐はな【上がり端】
⇒あがり‐ばな【上がり花】
⇒あがり‐ふじ【上り藤】
⇒あがり‐ま【揚り間】
⇒あがり‐まち【上がりまち】
⇒あがり‐まゆ【揚り繭】
⇒あがり‐め【上がり目】
⇒あがり‐もの【上がり物】
⇒あがり‐もの【上がり者】
⇒あがり‐や【揚屋】
⇒あがり‐やしき【上り屋敷】
⇒あがり‐ゆ【上がり湯】
⇒あがり‐ゆぐち【上がり湯口】
⇒上がりを請く
あがり【殯】
(→)「あらき(荒城)」に同じ。〈仲哀紀訓注〉
⇒あがり‐の‐みや【殯宮】
あがり‐うま【騰り馬】
躍りはねるくせのある馬。はねうま。駻馬かんば。古今著聞集16「六むつのあしげといふ―有りけり」
⇒あがり【上がり・揚り】
あがり‐おり【上がり下り】
上がることと下りること。あがりさがり。
⇒あがり【上がり・揚り】
⇒あか‐め【赤芽】
あかめ‐げんしょう【赤目現象】‥シヤウ
(写真用語)フラッシュを用いて顔を撮影した時、瞳が兎の眼のように赤く写る現象。強い光が網膜の毛細血管で反射するために起こる。
⇒あか‐め【赤目】
あか‐めばる【赤眼張】
①体色が赤みを帯びるメバル属の魚の俗称。
②ハタ科の海魚。アカハタ。(鹿児島方言)
あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
フグ科の海魚。全長約30センチメートル。帯赤褐色。本州中部以南の内湾に多い。身と精巣以外は毒性が強い。
⇒あか‐め【赤目】
アガメムノン【Agamemnōn】
ギリシア神話のミュケナイ(ミケネ)王。トロイア戦争におけるギリシア軍の総帥。オレステス・イフィゲネイア・エレクトラの父。凱旋後、妃クリュタイムネストラとその情夫アイギストスとに暗殺された。
あかめ‐もち【赤芽黐】
〔植〕カナメモチの別称。アカメ。
⇒あか‐め【赤芽】
あか・める【赤める】
〔他下一〕[文]あか・む(下二)
赤くする。赤らめる。源氏物語帚木「顔うち―・めてゐたり」
あが・める【崇める】
〔他下一〕[文]あが・む(下二)
①尊いものとして扱う。神代紀下「益ますます―・め敬いやまふ」。「祖先を―・める」
②寵愛する。源氏物語帚木「親など立ち副ひもて―・めて」
あか‐もがさ【赤疱瘡・赤斑瘡】
麻疹はしかの古称。栄華物語嶺月「―といふものいできて」
あか‐もく【赤藻屑】
褐藻類ホンダワラ科の海藻。高さ数メートルに達する。葉は約3センチメートル、有柄の線形で欠刻がある。茶褐色。枯れはじめると赤みを帯びる。浅海の岩礁の多い所に生育。流れ藻の構成種。肥料やヨードの原料。
あか‐もの【赤物】
①色の赤いもの。特に、タイ・ホウボウなど、外皮の赤い魚。
②ツツジ科の常緑小低木。高山帯に生え、高さ10〜30センチメートル。葉は厚く卵形でとがる。茎には赤い毛がある。夏、葉腋に鐘形の小白花をつけ、実は円くて紅熟。イワハゼ。
③赤く彩色した人形・玩具。赤色が病魔を退散させるという俗信から、江戸時代疱瘡ほうそう除けのまじないとして流行。
あが‐もの【贖物】
①祓はらえの時、身の災いをあがない祓うもの。人形ひとかたに災いを負わせて水に流しやる類。形代かたしろ。
②罪のつぐないとして出す財物。
あか‐もん【赤門】
①朱塗りの門。→御守殿ごしゅでん門。
②東京大学の南西隅の朱塗りの門。もと加賀前田家上屋敷の御守殿門で、1827年(文政10)将軍家斉の女むすめ溶姫が前田斉泰に嫁した際に建造したもの。転じて、東京大学の異称。「―出で」
あか‐やがら【赤矢柄】
魚類のヤガラの一種。体色が赤みを帯びる。→やがら3
あか‐ゆうたい【赤郵袋】‥イウ‥
紅色の布製の郵便郵袋。速達としない書留・現金書留郵便物を入れて、一局から他局へ送る袋。
あか‐ゆき【赤雪】
⇒せきせつ
あか‐ゆみ【赤弓】
丹や朱または赤漆で塗った弓。
あか‐ら【赤ら】
①赤みを帯びているさま。
②(飲めば顔が赤くなるからいう)酒の異称。本朝二十不孝「先祖より酒の家に生れ、―呑めといはれて此の方」
⇒あから‐おぶね【赤ら小舟】
⇒あから‐か【赤らか】
⇒あから‐がお【赤ら顔】
⇒あから‐がしわ【赤ら柏】
あから‐おぶね【赤ら小舟】‥ヲ‥
赤く塗った舟。特に、官船。(古代、官船は赤く塗ったから)万葉集16「沖行くや―に裹つとやらば」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐か【赤らか】
赤みを帯びて美しいさま。源氏物語常夏「紅といふものいと―にかいつけて」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がお【赤ら顔】‥ガホ
赤みをおびた顔。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がしわ【赤ら柏】‥ガシハ
①葉に赤みのある柏。供物を盛る具とした。万葉集20「印南野の―は時はあれど」
②京都北野天満宮の11月1日の祭。供物を赤ら柏に盛るからいう。6月の青柏祭に対する。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐さま
(「偸閑」「白地」とも当てる)
①たちまち。急。皇極紀「―に斬るべし」
②一時的であるさま。ちょっと。しばらく。宇津保物語忠乞「暇許させ給はぬをしひて申して―にまかでぬ」
③(「―にも」の形で、否定の語を伴って)かりそめにも。古今著聞集20「―にも、あどなきことをばすまじきことなり」
④かくさず、ありのまま。あらわ。はっきり。好色一代女4「女は妖淫うつくしき肌を―になし」。「―に言う」「―な軽蔑」
あから・し
〔形シク〕
痛切である。ひどい。一説に、悲しい。欽明紀「何ぞ悲しきことの―・しき」。蜻蛉日記下「などか来ぬ、とはぬ、にくし、―・しとて」
あからし・ぶ
〔自四〕
痛切に感ずる。心から嘆く。〈日本霊異記上訓釈〉
あからしま‐かぜ【あからしま風】
(アカラシマはアカラサマ(俄かの意)の転)暴風。はやて。あかしまかぜ。あらしまかぜ。神武紀「海の中にして卒にわかに―に遇ひぬ」
あからひき‐の‐いと【赤ら引の糸】
(→)「あかひきのいと」に同じ。持統紀「―参拾伍斤」
あから‐ひく【赤ら引く】
〔枕〕
(明るく光る、あるいは、赤みを帯びる意)「日」「月」「子」「君」「朝」「膚」「敷妙」にかかる。
あから・ぶ【赤らぶ】
〔自上二〕
赤みがさす。赤くなる。赤らむ。祝詞、神賀詞「赤玉のみ―・びまし」
あから・ぶ【明らぶ】
〔他下二〕
明らかにする。心をはらす。続日本紀31「誰とともにかも見そなはし―・べたまはむと」
あから・む【赤らむ】
[一]〔自五〕
赤くなる。赤みがさす。「―・んだ顔」
[二]〔他下二〕
⇒あからめる(下一)
あから・む【明らむ】
〔自五〕
夜が明けてきて、空が明るくなる。「東の空が―・む」
あから‐め【あから目】
(アカラはアカル(散)と同根)
①ふと目をほかへ移すこと。わきみ。よそみ。徒然草「花の本には、ねぢ寄り立ち寄り、―もせずまもりて」
②心をほかへ移すこと。うわき。宇津保物語俊蔭「いみじき色好みを、かく―もせさせたてまつらぬこと」
⇒あからめ‐さ・す【あから目さす】
あからめ‐さ・す【あから目さす】
〔他四〕
ふと目をそらす間に、急に見えなくなる。続日本紀36「―・す事のごとく」
⇒あから‐め【あから目】
あから・める【赤らめる】
〔他下一〕[文]あから・む(下二)
赤くする。赤める。「顔を―・める」
あか‐ランプ【赤ランプ】
赤い灯火。危険を知らせる信号。「計画の実行に―がつく」
あかり【明かり】
①物を明らかにする光。光線。「一筋の―がさす」「ネオンの―」
②灯火。あかし。「―をつける」「―をともす」
③明るい所。おもてだったところ。あかるみ。〈日葡辞書〉
④疑いをはらす証拠。証あかし。浄瑠璃、新版歌祭文「久松様の―もたちまち、打ってかはった勘六殿」。「―を立てる」
⑤諒闇りょうあんなど暗い気分の期間が終わること。あけ。
⇒あかり‐さき【明り先】
⇒あかり‐しょいん【明書院】
⇒あかり‐しょうじ【明り障子】
⇒あかり‐そうじ【明り障子】
⇒あかり‐どこ【明り床】
⇒あかり‐とり【明り取り】
⇒あかり‐まど【明り窓】
⇒明かりが立つ
⇒明かりを走る
あがり【上がり・揚り】
①位置・地位・価値・程度・値段・能力などが高い方に向かうこと。はねあがること。
②風呂などから出ること。日葡辞書「フロアガリ」。浮世風呂前「ヤア、義遊さん、モウお―かナ」
③地方から京都へ来ること。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「―の衆ならば、土産みやげ召せ召せ」
④終わること。だめになること。(雨が)やむこと。(魚・虫が)死ぬこと。また、用ずみになること。〈日葡辞書〉。「膳の―」
⑤できあがること。また、そのできぐあい。仕上がり。浮世風呂3「伊予染に黒裏さ。とんだいい―だつた」。「蚕の―(上蔟)」「ホラ、一丁―だ」
⑥双六すごろくで、駒が最終の場所へ進むこと。また、その場所。また、トランプなどで勝負がつくこと。
⑦収入。収穫。売上げ。「今日の―は少なかった」
⑧(沖縄で)東。
⑨(「上がり花」の略)お茶。
⑩(接尾語的に)前にその職業・身分・状態だった者。「役人―」「病気―」
⇒あがり‐うま【騰り馬】
⇒あがり‐おり【上がり下り】
⇒あがり‐かぶと【上り兜・揚り甲】
⇒あがり‐かまち【上がり框】
⇒あがり‐くち【上がり口】
⇒あがり‐さがり【上がり下がり】
⇒あがり‐ざしき【揚座敷】
⇒あがり‐ぜん【上がり膳】
⇒あがり‐だか【上がり高】
⇒あがり‐だん【上がり段】
⇒あがり‐ち【上地・上知】
⇒あがり‐でんじ【上がり田地】
⇒あがり‐なまず【上がり鯰】
⇒あがり‐ば【上がり場】
⇒あがり‐はな【上がり端】
⇒あがり‐ばな【上がり花】
⇒あがり‐ふじ【上り藤】
⇒あがり‐ま【揚り間】
⇒あがり‐まち【上がりまち】
⇒あがり‐まゆ【揚り繭】
⇒あがり‐め【上がり目】
⇒あがり‐もの【上がり物】
⇒あがり‐もの【上がり者】
⇒あがり‐や【揚屋】
⇒あがり‐やしき【上り屋敷】
⇒あがり‐ゆ【上がり湯】
⇒あがり‐ゆぐち【上がり湯口】
⇒上がりを請く
あがり【殯】
(→)「あらき(荒城)」に同じ。〈仲哀紀訓注〉
⇒あがり‐の‐みや【殯宮】
あがり‐うま【騰り馬】
躍りはねるくせのある馬。はねうま。駻馬かんば。古今著聞集16「六むつのあしげといふ―有りけり」
⇒あがり【上がり・揚り】
あがり‐おり【上がり下り】
上がることと下りること。あがりさがり。
⇒あがり【上がり・揚り】
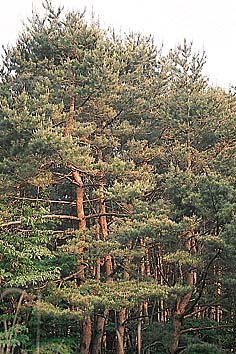 あかまつ【赤松】
姓氏の一つ。播磨の豪族。鎌倉時代佐用荘を本拠として興り、南北朝時代以降同国守護。室町幕府四職ししきの一家。
⇒あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
⇒あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】
⇒あかまつ‐のりむら【赤松則村】
⇒あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
⇒あかまつ‐よしのり【赤松義則】
あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
社会運動家。山口県生れ。東大在学中、新人会を結成。日本労働総同盟・日本共産党で活動、のち社会民衆党書記長。満州事変後は国家社会主義に転じ、さらに日本主義を唱え、大政翼賛会などに参加。主著「日本社会運動史」。(1894〜1955)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】‥イウ
(名はノリスケとも)南北朝時代の武将。則村の子。はじめ出家。後醍醐天皇の倒幕挙兵に加わり、のち足利尊氏に従って、播磨・備前の守護。(1311〜1371)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐のりむら【赤松則村】
南北朝初期の武将。播磨の守護。法名、円心。元弘の乱に六波羅を攻めたが、のち足利尊氏に従い、白旗城に拠って新田義貞の追撃を阻止。(1277〜1350)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
室町中期の武将。播磨・備前・美作の守護。足利義教を自邸に招いて殺し播磨に走ったが、山名持豊(宗全)らに攻められて自刃。(1373〜1441一説に1381〜1441)→嘉吉かきつの乱。
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐よしのり【赤松義則】
南北朝・室町初期の武将。則祐の子。明徳の乱に功あり、播磨・備前・美作守護、幕府の侍所所司。(1358〜1427)
⇒あかまつ【赤松】
あ‐が‐まま【吾が儘】
自分の思い通り。わがまま。大鏡兼家「一天下を―にして」
あか‐まんま【赤飯】
イヌタデの別称。あかのまんま。
あか‐み【赤み】
赤い程度。赤さ。「頬に―がさす」
⇒あかみ‐じょうご【赤み上戸】
⇒あかみ‐ばし・る【赤み走る】
あか‐み【赤身】
①動物の赤い肉。特に魚類についていう。↔白身しろみ。
②木材の中心の生活機能を失った帯紅色の部分。心材。↔白太しらた
あ‐が‐み【吾が身】
①自分。わがみ。
②(代名詞的に)相手を呼ぶ語。そなた。わがみ。物類称呼「他ひとをさして云ふ詞に、畿内にて―と云ふ」
あかみ‐じょうご【赤み上戸】‥ジヤウ‥
飲めば、すぐに顔の赤くなる酒飲み。色上戸。色み上戸。狂言、酒講式「かくしても、かくしかひなき、―は笑止の者なり」↔青み上戸。
⇒あか‐み【赤み】
あか‐みず【赤水】‥ミヅ
寒流。親潮おやしお。
あか‐みず【閼伽水】‥ミヅ
仏に供える水。散木奇歌集「花の―むすぶ手の」
あか‐みそ【赤味噌】
赤褐色に仕上げた味噌。辛口と甘口とがある。田舎味噌・仙台味噌・江戸味噌の類。
あかみ‐ばし・る【赤み走る】
〔自四〕
赤みがさす。赤くなる。好色一代女6「上髭うわひげありて―・り、天窓あたまはきんかなる人」
⇒あか‐み【赤み】
あかみみ‐がめ【赤耳亀】
カメの一種。北アメリカ原産。側頭部に赤い斑紋があるのでこの名がある。子ガメはミドリガメと呼ばれ、ペットとして輸入。その逃げ出したものが成長し、全国の川や池に定着。
アカミミガメ
撮影:関戸 勇
あかまつ【赤松】
姓氏の一つ。播磨の豪族。鎌倉時代佐用荘を本拠として興り、南北朝時代以降同国守護。室町幕府四職ししきの一家。
⇒あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
⇒あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】
⇒あかまつ‐のりむら【赤松則村】
⇒あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
⇒あかまつ‐よしのり【赤松義則】
あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
社会運動家。山口県生れ。東大在学中、新人会を結成。日本労働総同盟・日本共産党で活動、のち社会民衆党書記長。満州事変後は国家社会主義に転じ、さらに日本主義を唱え、大政翼賛会などに参加。主著「日本社会運動史」。(1894〜1955)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】‥イウ
(名はノリスケとも)南北朝時代の武将。則村の子。はじめ出家。後醍醐天皇の倒幕挙兵に加わり、のち足利尊氏に従って、播磨・備前の守護。(1311〜1371)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐のりむら【赤松則村】
南北朝初期の武将。播磨の守護。法名、円心。元弘の乱に六波羅を攻めたが、のち足利尊氏に従い、白旗城に拠って新田義貞の追撃を阻止。(1277〜1350)
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
室町中期の武将。播磨・備前・美作の守護。足利義教を自邸に招いて殺し播磨に走ったが、山名持豊(宗全)らに攻められて自刃。(1373〜1441一説に1381〜1441)→嘉吉かきつの乱。
⇒あかまつ【赤松】
あかまつ‐よしのり【赤松義則】
南北朝・室町初期の武将。則祐の子。明徳の乱に功あり、播磨・備前・美作守護、幕府の侍所所司。(1358〜1427)
⇒あかまつ【赤松】
あ‐が‐まま【吾が儘】
自分の思い通り。わがまま。大鏡兼家「一天下を―にして」
あか‐まんま【赤飯】
イヌタデの別称。あかのまんま。
あか‐み【赤み】
赤い程度。赤さ。「頬に―がさす」
⇒あかみ‐じょうご【赤み上戸】
⇒あかみ‐ばし・る【赤み走る】
あか‐み【赤身】
①動物の赤い肉。特に魚類についていう。↔白身しろみ。
②木材の中心の生活機能を失った帯紅色の部分。心材。↔白太しらた
あ‐が‐み【吾が身】
①自分。わがみ。
②(代名詞的に)相手を呼ぶ語。そなた。わがみ。物類称呼「他ひとをさして云ふ詞に、畿内にて―と云ふ」
あかみ‐じょうご【赤み上戸】‥ジヤウ‥
飲めば、すぐに顔の赤くなる酒飲み。色上戸。色み上戸。狂言、酒講式「かくしても、かくしかひなき、―は笑止の者なり」↔青み上戸。
⇒あか‐み【赤み】
あか‐みず【赤水】‥ミヅ
寒流。親潮おやしお。
あか‐みず【閼伽水】‥ミヅ
仏に供える水。散木奇歌集「花の―むすぶ手の」
あか‐みそ【赤味噌】
赤褐色に仕上げた味噌。辛口と甘口とがある。田舎味噌・仙台味噌・江戸味噌の類。
あかみ‐ばし・る【赤み走る】
〔自四〕
赤みがさす。赤くなる。好色一代女6「上髭うわひげありて―・り、天窓あたまはきんかなる人」
⇒あか‐み【赤み】
あかみみ‐がめ【赤耳亀】
カメの一種。北アメリカ原産。側頭部に赤い斑紋があるのでこの名がある。子ガメはミドリガメと呼ばれ、ペットとして輸入。その逃げ出したものが成長し、全国の川や池に定着。
アカミミガメ
撮影:関戸 勇
 あか・む【赤む】
[一]〔自四〕
赤くなる。赤みがつく。枕草子3「顔少し―・みてゐたるこそをかしけれ」
[二]〔他下二〕
⇒あかめる(下一)
あが・む【崇む】
〔他下二〕
⇒あがめる(下一)
あか‐むけ【赤剥け】
皮膚が赤くすりむけること。また、その赤はだ。
あか‐むし【赤虫】
①ビクイソメ科の大形の多毛類。体長0.6〜1メートル。環節数は600〜800に達し、濃い橙紅色。本州南部沿岸の砂泥中にすみ、マダイの釣餌に好適。
②ツツガムシの別称。
③「あかぼうふら」の別称。
あか‐むつ【赤鯥】
①スズキ科の海産の硬骨魚。暖海の深部にすむ。食用。のどぐろ。
アカムツ
提供:東京動物園協会
あか・む【赤む】
[一]〔自四〕
赤くなる。赤みがつく。枕草子3「顔少し―・みてゐたるこそをかしけれ」
[二]〔他下二〕
⇒あかめる(下一)
あが・む【崇む】
〔他下二〕
⇒あがめる(下一)
あか‐むけ【赤剥け】
皮膚が赤くすりむけること。また、その赤はだ。
あか‐むし【赤虫】
①ビクイソメ科の大形の多毛類。体長0.6〜1メートル。環節数は600〜800に達し、濃い橙紅色。本州南部沿岸の砂泥中にすみ、マダイの釣餌に好適。
②ツツガムシの別称。
③「あかぼうふら」の別称。
あか‐むつ【赤鯥】
①スズキ科の海産の硬骨魚。暖海の深部にすむ。食用。のどぐろ。
アカムツ
提供:東京動物園協会
 ②コイ科の淡水魚カワムツの生殖期の雄。
あか‐むらさき【赤紫】
赤みをおびた紫色。源氏物語絵合「―の表紙、紫檀の軸」
Munsell color system: 5RP4.5/12
あか‐め【赤女】
赤い色の鯛。神代紀下「―は赤鯛なり」
あか‐め【赤目】
①疲れ・病気や緊張などのため、眼の結膜が充血して赤く見えるもの。また、興奮して血筋の張った目。
②白子しろこなどの眼。虹彩が赤いもの。虹彩や眼底の色素の欠乏により、眼底の血管が透けて見えるのによる。
③⇒あかんべ。
④〔動〕
㋐アカメ科の汽水魚。四国南部と九州東南部の大河に遡ることもある。瞳孔が赤く見える場合が多い。
㋑ヒガイ(鰉)の方言。
㋒メナダ(赤目魚)の方言。
⇒あかめ‐げんしょう【赤目現象】
⇒あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
あかめ【赤目】
三重県西部、名張なばり市南西部の地区。赤目四十八滝と称する大小多数の滝で有名。
赤目四十八滝
撮影:的場 啓
②コイ科の淡水魚カワムツの生殖期の雄。
あか‐むらさき【赤紫】
赤みをおびた紫色。源氏物語絵合「―の表紙、紫檀の軸」
Munsell color system: 5RP4.5/12
あか‐め【赤女】
赤い色の鯛。神代紀下「―は赤鯛なり」
あか‐め【赤目】
①疲れ・病気や緊張などのため、眼の結膜が充血して赤く見えるもの。また、興奮して血筋の張った目。
②白子しろこなどの眼。虹彩が赤いもの。虹彩や眼底の色素の欠乏により、眼底の血管が透けて見えるのによる。
③⇒あかんべ。
④〔動〕
㋐アカメ科の汽水魚。四国南部と九州東南部の大河に遡ることもある。瞳孔が赤く見える場合が多い。
㋑ヒガイ(鰉)の方言。
㋒メナダ(赤目魚)の方言。
⇒あかめ‐げんしょう【赤目現象】
⇒あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
あかめ【赤目】
三重県西部、名張なばり市南西部の地区。赤目四十八滝と称する大小多数の滝で有名。
赤目四十八滝
撮影:的場 啓
 あか‐め【赤芽】
植物の赤みを帯びた新芽。また、新芽の美しいアカメガシワ・カナメモチなどの園芸上の通称。
⇒あかめ‐がしわ【赤芽柏】
⇒あかめ‐もち【赤芽黐】
あかめ‐がしわ【赤芽柏】‥ガシハ
(若葉が鮮紅色だからいう)トウダイグサ科の落葉高木。日本・中国大陸に自生、日本では二次林に多い。高さ10メートルに達する。雌雄異株。夏、白色の花を穂状につける。材は軟らかく、床柱・下駄・薪炭などに用いる。果実の毛を集めて駆虫剤(主にサナダムシ)とする。
あかめがしわ
あか‐め【赤芽】
植物の赤みを帯びた新芽。また、新芽の美しいアカメガシワ・カナメモチなどの園芸上の通称。
⇒あかめ‐がしわ【赤芽柏】
⇒あかめ‐もち【赤芽黐】
あかめ‐がしわ【赤芽柏】‥ガシハ
(若葉が鮮紅色だからいう)トウダイグサ科の落葉高木。日本・中国大陸に自生、日本では二次林に多い。高さ10メートルに達する。雌雄異株。夏、白色の花を穂状につける。材は軟らかく、床柱・下駄・薪炭などに用いる。果実の毛を集めて駆虫剤(主にサナダムシ)とする。
あかめがしわ
 ⇒あか‐め【赤芽】
あかめ‐げんしょう【赤目現象】‥シヤウ
(写真用語)フラッシュを用いて顔を撮影した時、瞳が兎の眼のように赤く写る現象。強い光が網膜の毛細血管で反射するために起こる。
⇒あか‐め【赤目】
あか‐めばる【赤眼張】
①体色が赤みを帯びるメバル属の魚の俗称。
②ハタ科の海魚。アカハタ。(鹿児島方言)
あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
フグ科の海魚。全長約30センチメートル。帯赤褐色。本州中部以南の内湾に多い。身と精巣以外は毒性が強い。
⇒あか‐め【赤目】
アガメムノン【Agamemnōn】
ギリシア神話のミュケナイ(ミケネ)王。トロイア戦争におけるギリシア軍の総帥。オレステス・イフィゲネイア・エレクトラの父。凱旋後、妃クリュタイムネストラとその情夫アイギストスとに暗殺された。
あかめ‐もち【赤芽黐】
〔植〕カナメモチの別称。アカメ。
⇒あか‐め【赤芽】
あか・める【赤める】
〔他下一〕[文]あか・む(下二)
赤くする。赤らめる。源氏物語帚木「顔うち―・めてゐたり」
あが・める【崇める】
〔他下一〕[文]あが・む(下二)
①尊いものとして扱う。神代紀下「益ますます―・め敬いやまふ」。「祖先を―・める」
②寵愛する。源氏物語帚木「親など立ち副ひもて―・めて」
あか‐もがさ【赤疱瘡・赤斑瘡】
麻疹はしかの古称。栄華物語嶺月「―といふものいできて」
あか‐もく【赤藻屑】
褐藻類ホンダワラ科の海藻。高さ数メートルに達する。葉は約3センチメートル、有柄の線形で欠刻がある。茶褐色。枯れはじめると赤みを帯びる。浅海の岩礁の多い所に生育。流れ藻の構成種。肥料やヨードの原料。
あか‐もの【赤物】
①色の赤いもの。特に、タイ・ホウボウなど、外皮の赤い魚。
②ツツジ科の常緑小低木。高山帯に生え、高さ10〜30センチメートル。葉は厚く卵形でとがる。茎には赤い毛がある。夏、葉腋に鐘形の小白花をつけ、実は円くて紅熟。イワハゼ。
③赤く彩色した人形・玩具。赤色が病魔を退散させるという俗信から、江戸時代疱瘡ほうそう除けのまじないとして流行。
あが‐もの【贖物】
①祓はらえの時、身の災いをあがない祓うもの。人形ひとかたに災いを負わせて水に流しやる類。形代かたしろ。
②罪のつぐないとして出す財物。
あか‐もん【赤門】
①朱塗りの門。→御守殿ごしゅでん門。
②東京大学の南西隅の朱塗りの門。もと加賀前田家上屋敷の御守殿門で、1827年(文政10)将軍家斉の女むすめ溶姫が前田斉泰に嫁した際に建造したもの。転じて、東京大学の異称。「―出で」
あか‐やがら【赤矢柄】
魚類のヤガラの一種。体色が赤みを帯びる。→やがら3
あか‐ゆうたい【赤郵袋】‥イウ‥
紅色の布製の郵便郵袋。速達としない書留・現金書留郵便物を入れて、一局から他局へ送る袋。
あか‐ゆき【赤雪】
⇒せきせつ
あか‐ゆみ【赤弓】
丹や朱または赤漆で塗った弓。
あか‐ら【赤ら】
①赤みを帯びているさま。
②(飲めば顔が赤くなるからいう)酒の異称。本朝二十不孝「先祖より酒の家に生れ、―呑めといはれて此の方」
⇒あから‐おぶね【赤ら小舟】
⇒あから‐か【赤らか】
⇒あから‐がお【赤ら顔】
⇒あから‐がしわ【赤ら柏】
あから‐おぶね【赤ら小舟】‥ヲ‥
赤く塗った舟。特に、官船。(古代、官船は赤く塗ったから)万葉集16「沖行くや―に裹つとやらば」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐か【赤らか】
赤みを帯びて美しいさま。源氏物語常夏「紅といふものいと―にかいつけて」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がお【赤ら顔】‥ガホ
赤みをおびた顔。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がしわ【赤ら柏】‥ガシハ
①葉に赤みのある柏。供物を盛る具とした。万葉集20「印南野の―は時はあれど」
②京都北野天満宮の11月1日の祭。供物を赤ら柏に盛るからいう。6月の青柏祭に対する。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐さま
(「偸閑」「白地」とも当てる)
①たちまち。急。皇極紀「―に斬るべし」
②一時的であるさま。ちょっと。しばらく。宇津保物語忠乞「暇許させ給はぬをしひて申して―にまかでぬ」
③(「―にも」の形で、否定の語を伴って)かりそめにも。古今著聞集20「―にも、あどなきことをばすまじきことなり」
④かくさず、ありのまま。あらわ。はっきり。好色一代女4「女は妖淫うつくしき肌を―になし」。「―に言う」「―な軽蔑」
あから・し
〔形シク〕
痛切である。ひどい。一説に、悲しい。欽明紀「何ぞ悲しきことの―・しき」。蜻蛉日記下「などか来ぬ、とはぬ、にくし、―・しとて」
あからし・ぶ
〔自四〕
痛切に感ずる。心から嘆く。〈日本霊異記上訓釈〉
あからしま‐かぜ【あからしま風】
(アカラシマはアカラサマ(俄かの意)の転)暴風。はやて。あかしまかぜ。あらしまかぜ。神武紀「海の中にして卒にわかに―に遇ひぬ」
あからひき‐の‐いと【赤ら引の糸】
(→)「あかひきのいと」に同じ。持統紀「―参拾伍斤」
あから‐ひく【赤ら引く】
〔枕〕
(明るく光る、あるいは、赤みを帯びる意)「日」「月」「子」「君」「朝」「膚」「敷妙」にかかる。
あから・ぶ【赤らぶ】
〔自上二〕
赤みがさす。赤くなる。赤らむ。祝詞、神賀詞「赤玉のみ―・びまし」
あから・ぶ【明らぶ】
〔他下二〕
明らかにする。心をはらす。続日本紀31「誰とともにかも見そなはし―・べたまはむと」
あから・む【赤らむ】
[一]〔自五〕
赤くなる。赤みがさす。「―・んだ顔」
[二]〔他下二〕
⇒あからめる(下一)
あから・む【明らむ】
〔自五〕
夜が明けてきて、空が明るくなる。「東の空が―・む」
あから‐め【あから目】
(アカラはアカル(散)と同根)
①ふと目をほかへ移すこと。わきみ。よそみ。徒然草「花の本には、ねぢ寄り立ち寄り、―もせずまもりて」
②心をほかへ移すこと。うわき。宇津保物語俊蔭「いみじき色好みを、かく―もせさせたてまつらぬこと」
⇒あからめ‐さ・す【あから目さす】
あからめ‐さ・す【あから目さす】
〔他四〕
ふと目をそらす間に、急に見えなくなる。続日本紀36「―・す事のごとく」
⇒あから‐め【あから目】
あから・める【赤らめる】
〔他下一〕[文]あから・む(下二)
赤くする。赤める。「顔を―・める」
あか‐ランプ【赤ランプ】
赤い灯火。危険を知らせる信号。「計画の実行に―がつく」
あかり【明かり】
①物を明らかにする光。光線。「一筋の―がさす」「ネオンの―」
②灯火。あかし。「―をつける」「―をともす」
③明るい所。おもてだったところ。あかるみ。〈日葡辞書〉
④疑いをはらす証拠。証あかし。浄瑠璃、新版歌祭文「久松様の―もたちまち、打ってかはった勘六殿」。「―を立てる」
⑤諒闇りょうあんなど暗い気分の期間が終わること。あけ。
⇒あかり‐さき【明り先】
⇒あかり‐しょいん【明書院】
⇒あかり‐しょうじ【明り障子】
⇒あかり‐そうじ【明り障子】
⇒あかり‐どこ【明り床】
⇒あかり‐とり【明り取り】
⇒あかり‐まど【明り窓】
⇒明かりが立つ
⇒明かりを走る
あがり【上がり・揚り】
①位置・地位・価値・程度・値段・能力などが高い方に向かうこと。はねあがること。
②風呂などから出ること。日葡辞書「フロアガリ」。浮世風呂前「ヤア、義遊さん、モウお―かナ」
③地方から京都へ来ること。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「―の衆ならば、土産みやげ召せ召せ」
④終わること。だめになること。(雨が)やむこと。(魚・虫が)死ぬこと。また、用ずみになること。〈日葡辞書〉。「膳の―」
⑤できあがること。また、そのできぐあい。仕上がり。浮世風呂3「伊予染に黒裏さ。とんだいい―だつた」。「蚕の―(上蔟)」「ホラ、一丁―だ」
⑥双六すごろくで、駒が最終の場所へ進むこと。また、その場所。また、トランプなどで勝負がつくこと。
⑦収入。収穫。売上げ。「今日の―は少なかった」
⑧(沖縄で)東。
⑨(「上がり花」の略)お茶。
⑩(接尾語的に)前にその職業・身分・状態だった者。「役人―」「病気―」
⇒あがり‐うま【騰り馬】
⇒あがり‐おり【上がり下り】
⇒あがり‐かぶと【上り兜・揚り甲】
⇒あがり‐かまち【上がり框】
⇒あがり‐くち【上がり口】
⇒あがり‐さがり【上がり下がり】
⇒あがり‐ざしき【揚座敷】
⇒あがり‐ぜん【上がり膳】
⇒あがり‐だか【上がり高】
⇒あがり‐だん【上がり段】
⇒あがり‐ち【上地・上知】
⇒あがり‐でんじ【上がり田地】
⇒あがり‐なまず【上がり鯰】
⇒あがり‐ば【上がり場】
⇒あがり‐はな【上がり端】
⇒あがり‐ばな【上がり花】
⇒あがり‐ふじ【上り藤】
⇒あがり‐ま【揚り間】
⇒あがり‐まち【上がりまち】
⇒あがり‐まゆ【揚り繭】
⇒あがり‐め【上がり目】
⇒あがり‐もの【上がり物】
⇒あがり‐もの【上がり者】
⇒あがり‐や【揚屋】
⇒あがり‐やしき【上り屋敷】
⇒あがり‐ゆ【上がり湯】
⇒あがり‐ゆぐち【上がり湯口】
⇒上がりを請く
あがり【殯】
(→)「あらき(荒城)」に同じ。〈仲哀紀訓注〉
⇒あがり‐の‐みや【殯宮】
あがり‐うま【騰り馬】
躍りはねるくせのある馬。はねうま。駻馬かんば。古今著聞集16「六むつのあしげといふ―有りけり」
⇒あがり【上がり・揚り】
あがり‐おり【上がり下り】
上がることと下りること。あがりさがり。
⇒あがり【上がり・揚り】
⇒あか‐め【赤芽】
あかめ‐げんしょう【赤目現象】‥シヤウ
(写真用語)フラッシュを用いて顔を撮影した時、瞳が兎の眼のように赤く写る現象。強い光が網膜の毛細血管で反射するために起こる。
⇒あか‐め【赤目】
あか‐めばる【赤眼張】
①体色が赤みを帯びるメバル属の魚の俗称。
②ハタ科の海魚。アカハタ。(鹿児島方言)
あかめ‐ふぐ【赤目河豚】
フグ科の海魚。全長約30センチメートル。帯赤褐色。本州中部以南の内湾に多い。身と精巣以外は毒性が強い。
⇒あか‐め【赤目】
アガメムノン【Agamemnōn】
ギリシア神話のミュケナイ(ミケネ)王。トロイア戦争におけるギリシア軍の総帥。オレステス・イフィゲネイア・エレクトラの父。凱旋後、妃クリュタイムネストラとその情夫アイギストスとに暗殺された。
あかめ‐もち【赤芽黐】
〔植〕カナメモチの別称。アカメ。
⇒あか‐め【赤芽】
あか・める【赤める】
〔他下一〕[文]あか・む(下二)
赤くする。赤らめる。源氏物語帚木「顔うち―・めてゐたり」
あが・める【崇める】
〔他下一〕[文]あが・む(下二)
①尊いものとして扱う。神代紀下「益ますます―・め敬いやまふ」。「祖先を―・める」
②寵愛する。源氏物語帚木「親など立ち副ひもて―・めて」
あか‐もがさ【赤疱瘡・赤斑瘡】
麻疹はしかの古称。栄華物語嶺月「―といふものいできて」
あか‐もく【赤藻屑】
褐藻類ホンダワラ科の海藻。高さ数メートルに達する。葉は約3センチメートル、有柄の線形で欠刻がある。茶褐色。枯れはじめると赤みを帯びる。浅海の岩礁の多い所に生育。流れ藻の構成種。肥料やヨードの原料。
あか‐もの【赤物】
①色の赤いもの。特に、タイ・ホウボウなど、外皮の赤い魚。
②ツツジ科の常緑小低木。高山帯に生え、高さ10〜30センチメートル。葉は厚く卵形でとがる。茎には赤い毛がある。夏、葉腋に鐘形の小白花をつけ、実は円くて紅熟。イワハゼ。
③赤く彩色した人形・玩具。赤色が病魔を退散させるという俗信から、江戸時代疱瘡ほうそう除けのまじないとして流行。
あが‐もの【贖物】
①祓はらえの時、身の災いをあがない祓うもの。人形ひとかたに災いを負わせて水に流しやる類。形代かたしろ。
②罪のつぐないとして出す財物。
あか‐もん【赤門】
①朱塗りの門。→御守殿ごしゅでん門。
②東京大学の南西隅の朱塗りの門。もと加賀前田家上屋敷の御守殿門で、1827年(文政10)将軍家斉の女むすめ溶姫が前田斉泰に嫁した際に建造したもの。転じて、東京大学の異称。「―出で」
あか‐やがら【赤矢柄】
魚類のヤガラの一種。体色が赤みを帯びる。→やがら3
あか‐ゆうたい【赤郵袋】‥イウ‥
紅色の布製の郵便郵袋。速達としない書留・現金書留郵便物を入れて、一局から他局へ送る袋。
あか‐ゆき【赤雪】
⇒せきせつ
あか‐ゆみ【赤弓】
丹や朱または赤漆で塗った弓。
あか‐ら【赤ら】
①赤みを帯びているさま。
②(飲めば顔が赤くなるからいう)酒の異称。本朝二十不孝「先祖より酒の家に生れ、―呑めといはれて此の方」
⇒あから‐おぶね【赤ら小舟】
⇒あから‐か【赤らか】
⇒あから‐がお【赤ら顔】
⇒あから‐がしわ【赤ら柏】
あから‐おぶね【赤ら小舟】‥ヲ‥
赤く塗った舟。特に、官船。(古代、官船は赤く塗ったから)万葉集16「沖行くや―に裹つとやらば」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐か【赤らか】
赤みを帯びて美しいさま。源氏物語常夏「紅といふものいと―にかいつけて」
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がお【赤ら顔】‥ガホ
赤みをおびた顔。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐がしわ【赤ら柏】‥ガシハ
①葉に赤みのある柏。供物を盛る具とした。万葉集20「印南野の―は時はあれど」
②京都北野天満宮の11月1日の祭。供物を赤ら柏に盛るからいう。6月の青柏祭に対する。
⇒あか‐ら【赤ら】
あから‐さま
(「偸閑」「白地」とも当てる)
①たちまち。急。皇極紀「―に斬るべし」
②一時的であるさま。ちょっと。しばらく。宇津保物語忠乞「暇許させ給はぬをしひて申して―にまかでぬ」
③(「―にも」の形で、否定の語を伴って)かりそめにも。古今著聞集20「―にも、あどなきことをばすまじきことなり」
④かくさず、ありのまま。あらわ。はっきり。好色一代女4「女は妖淫うつくしき肌を―になし」。「―に言う」「―な軽蔑」
あから・し
〔形シク〕
痛切である。ひどい。一説に、悲しい。欽明紀「何ぞ悲しきことの―・しき」。蜻蛉日記下「などか来ぬ、とはぬ、にくし、―・しとて」
あからし・ぶ
〔自四〕
痛切に感ずる。心から嘆く。〈日本霊異記上訓釈〉
あからしま‐かぜ【あからしま風】
(アカラシマはアカラサマ(俄かの意)の転)暴風。はやて。あかしまかぜ。あらしまかぜ。神武紀「海の中にして卒にわかに―に遇ひぬ」
あからひき‐の‐いと【赤ら引の糸】
(→)「あかひきのいと」に同じ。持統紀「―参拾伍斤」
あから‐ひく【赤ら引く】
〔枕〕
(明るく光る、あるいは、赤みを帯びる意)「日」「月」「子」「君」「朝」「膚」「敷妙」にかかる。
あから・ぶ【赤らぶ】
〔自上二〕
赤みがさす。赤くなる。赤らむ。祝詞、神賀詞「赤玉のみ―・びまし」
あから・ぶ【明らぶ】
〔他下二〕
明らかにする。心をはらす。続日本紀31「誰とともにかも見そなはし―・べたまはむと」
あから・む【赤らむ】
[一]〔自五〕
赤くなる。赤みがさす。「―・んだ顔」
[二]〔他下二〕
⇒あからめる(下一)
あから・む【明らむ】
〔自五〕
夜が明けてきて、空が明るくなる。「東の空が―・む」
あから‐め【あから目】
(アカラはアカル(散)と同根)
①ふと目をほかへ移すこと。わきみ。よそみ。徒然草「花の本には、ねぢ寄り立ち寄り、―もせずまもりて」
②心をほかへ移すこと。うわき。宇津保物語俊蔭「いみじき色好みを、かく―もせさせたてまつらぬこと」
⇒あからめ‐さ・す【あから目さす】
あからめ‐さ・す【あから目さす】
〔他四〕
ふと目をそらす間に、急に見えなくなる。続日本紀36「―・す事のごとく」
⇒あから‐め【あから目】
あから・める【赤らめる】
〔他下一〕[文]あから・む(下二)
赤くする。赤める。「顔を―・める」
あか‐ランプ【赤ランプ】
赤い灯火。危険を知らせる信号。「計画の実行に―がつく」
あかり【明かり】
①物を明らかにする光。光線。「一筋の―がさす」「ネオンの―」
②灯火。あかし。「―をつける」「―をともす」
③明るい所。おもてだったところ。あかるみ。〈日葡辞書〉
④疑いをはらす証拠。証あかし。浄瑠璃、新版歌祭文「久松様の―もたちまち、打ってかはった勘六殿」。「―を立てる」
⑤諒闇りょうあんなど暗い気分の期間が終わること。あけ。
⇒あかり‐さき【明り先】
⇒あかり‐しょいん【明書院】
⇒あかり‐しょうじ【明り障子】
⇒あかり‐そうじ【明り障子】
⇒あかり‐どこ【明り床】
⇒あかり‐とり【明り取り】
⇒あかり‐まど【明り窓】
⇒明かりが立つ
⇒明かりを走る
あがり【上がり・揚り】
①位置・地位・価値・程度・値段・能力などが高い方に向かうこと。はねあがること。
②風呂などから出ること。日葡辞書「フロアガリ」。浮世風呂前「ヤア、義遊さん、モウお―かナ」
③地方から京都へ来ること。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「―の衆ならば、土産みやげ召せ召せ」
④終わること。だめになること。(雨が)やむこと。(魚・虫が)死ぬこと。また、用ずみになること。〈日葡辞書〉。「膳の―」
⑤できあがること。また、そのできぐあい。仕上がり。浮世風呂3「伊予染に黒裏さ。とんだいい―だつた」。「蚕の―(上蔟)」「ホラ、一丁―だ」
⑥双六すごろくで、駒が最終の場所へ進むこと。また、その場所。また、トランプなどで勝負がつくこと。
⑦収入。収穫。売上げ。「今日の―は少なかった」
⑧(沖縄で)東。
⑨(「上がり花」の略)お茶。
⑩(接尾語的に)前にその職業・身分・状態だった者。「役人―」「病気―」
⇒あがり‐うま【騰り馬】
⇒あがり‐おり【上がり下り】
⇒あがり‐かぶと【上り兜・揚り甲】
⇒あがり‐かまち【上がり框】
⇒あがり‐くち【上がり口】
⇒あがり‐さがり【上がり下がり】
⇒あがり‐ざしき【揚座敷】
⇒あがり‐ぜん【上がり膳】
⇒あがり‐だか【上がり高】
⇒あがり‐だん【上がり段】
⇒あがり‐ち【上地・上知】
⇒あがり‐でんじ【上がり田地】
⇒あがり‐なまず【上がり鯰】
⇒あがり‐ば【上がり場】
⇒あがり‐はな【上がり端】
⇒あがり‐ばな【上がり花】
⇒あがり‐ふじ【上り藤】
⇒あがり‐ま【揚り間】
⇒あがり‐まち【上がりまち】
⇒あがり‐まゆ【揚り繭】
⇒あがり‐め【上がり目】
⇒あがり‐もの【上がり物】
⇒あがり‐もの【上がり者】
⇒あがり‐や【揚屋】
⇒あがり‐やしき【上り屋敷】
⇒あがり‐ゆ【上がり湯】
⇒あがり‐ゆぐち【上がり湯口】
⇒上がりを請く
あがり【殯】
(→)「あらき(荒城)」に同じ。〈仲哀紀訓注〉
⇒あがり‐の‐みや【殯宮】
あがり‐うま【騰り馬】
躍りはねるくせのある馬。はねうま。駻馬かんば。古今著聞集16「六むつのあしげといふ―有りけり」
⇒あがり【上がり・揚り】
あがり‐おり【上がり下り】
上がることと下りること。あがりさがり。
⇒あがり【上がり・揚り】
広辞苑 ページ 162 での【○吾が仏尊し】単語。