複数辞典一括検索+![]()
![]()
○顰みに倣うひそみにならう🔗⭐🔉
○顰みに倣うひそみにならう
「西施せいしの顰みに倣う」に同じ。→西施(成句)
⇒ひそみ【顰み・嚬み】
ひそみ‐ね【潜み音】
ひそんだ声。しのびね。
ひそ・む【潜む】
[一]〔自五〕
①ひそかに隠れている。しのんでいる。「物かげに―・む」
②まだ外からはそれと分からず内部に存在する。潜伏する。「病原菌が―・んでいる」「民衆に―・んでいる力」
[二]〔他下二〕
⇒ひそめる(下一)
ひそ・む【顰む・嚬む】
[一]〔自四〕
①顔つきがゆがむ。→くちひそむ。
②べそをかく。泣き顔になる。源氏物語東屋「いと悲しと見奉るにただ―・みに―・む」
[二]〔他下二〕
⇒ひそめる(下一)
ひ‐ぞめ【緋染め】
①緋色に染めること。また、そのもの。
②血赤色の土で、水にとかして赤色液とする染料。
ひそ‐め・く【密めく】
〔自四〕
①ひそかにする。しのんでする。平家物語(延慶本)「その夜、兵衛佐のもとに―・く事ありと聞きて」
②ひそひそと語る。私語する。ささやく。義経記3「はるかに夜更けて、内陣に―・きたり」
ひそ・める【潜める】
〔他下一〕[文]ひそ・む(下二)
①かくす。しのばせる。古今著聞集16「日暮るれば家にくだといふ小竹のよを多く散らしおきて、つとめてはとり―・めけり」。奥の細道「岩窟に身を―・め入て」
②静かにする。ひっそりとする。源氏物語玉鬘「いたうかい―・めて、かたみに心づかひしたり」
③控え目にする。源氏物語浮舟「正身こそ何事もおいらかに思さめ、よからぬ中となりぬるあたりは、煩はしきこともありぬべし。かい―・めて、さる心し給へ」。「声を―・める」
④平静にする。冷静にする。日葡辞書「サンコヲヒソメテキク」
⑤内に蔵している。「底力を―・めている」
ひそ・める【顰める・嚬める】
〔他下一〕[文]ひそ・む(下二)
(不快な気持で)眉のあたりに皺しわをよせる。徒然草「いとたへがたげに眉を―・め」
ひそ‐やか【密やか】
①ひそかにするさま。しのびやか。こっそり。「老夫婦だけの―な暮し」
②転じて、物の乏しいさま。浄瑠璃、近頃河原達引「そのやうに―な身代ぢやと」
ひ‐ぞり【乾反り・干反り】
①乾いてそりかえること。また、そのもの。浄瑠璃、今宮の心中「―仕直し上下を盤にかけて打ちけるが」
②すねて怒ること。意地悪を言うこと。浄瑠璃、新版歌祭文「お前がいやであらうといふ、―の文ぶんぢや」
③ひどい貧乏。
⇒ひぞり‐ごと【乾反り言】
⇒ひぞり‐ごま【乾反り独楽】
⇒ひぞり‐だいじん【乾反り大尽】
ひぞり‐ごと【乾反り言】
すねて無理を言いかけること。また、その言葉。
⇒ひ‐ぞり【乾反り・干反り】
ひぞり‐ごま【乾反り独楽】
くねりまわるこま。
⇒ひ‐ぞり【乾反り・干反り】
ひぞり‐だいじん【乾反り大尽】
わがままでやぼな金持の遊客。
⇒ひ‐ぞり【乾反り・干反り】
ひ‐ぞ・る【乾反る・干反る】
〔自五〕
(ヒソルとも)
①かわいてそりかえる。「板が―・る」
②すねる。意地悪くする。洒落本、聖遊廓「―・りかけたらつめつておかしやれ」
③当たった矢などがささらずにすべりおちる。〈日葡辞書〉
ひ‐そん【干損】
田畑が乾いて収穫が減ること。旱損。
ひ‐そんざい【非存在】
(me on ギリシア)ギリシア哲学で用いられた概念。非存在は存在の否定として無と考えられ、存在の不変不動と運動変化の全面的否定を帰結したが(パルメニデス)、デモクリトスがこれを空虚と解釈して運動の可能性と自然学の成立を確保した。プラトンは非存在を他性として解釈することにより、非存在を語ることとしての虚偽の可能性を存在論的に基礎づけた。
ひた【日田】
大分県北西部の市。筑後川の上流日田盆地の中心。水郷日田として知られ、耶馬日田英彦山国定公園の一部。近世、代官所が置かれ、また咸宜園かんぎえんは広瀬淡窓の私塾として名高い。日田杉も著名。人口7万4千。
ひ‐た【引板】
(ヒキタの音便ヒイタの約)鳴子なるこ。〈[季]秋〉。源氏物語夕霧「鹿は…山田の―にも驚かず」
ひた【直】
〔接頭〕
(一説に「ひと(一)」と同源)「いちず」「ただち」「まったく」などの意を表す。万葉集18「橘の成れるその実は―照りに」。「―かくし」「―面」
ひだ【襞】
①袴・衣服類に細く折り畳んである細長い折目。ひだめ。また、そのように見えるもの。「山の―」
②キノコの傘の裏面にあるしわの部分。菌褶。
ひだ【飛騨】
①旧国名。今の岐阜県の北部。飛州。
②岐阜県北端の市。飛騨山脈・飛騨高地に囲まれた山間に位置する。野菜・果樹栽培と畜産が盛ん。人口2万9千。
びた【鐚】
鐚銭びたせんの略。〈日葡辞書〉
ピタ【pita】
中近東の平たい円形のパン。切り開いて内部の空洞に詰め物をする。ピタ‐パン。ポケット‐パン。
ビター【bitter】
①苦いさま。「―‐チョコレート」
②ホップの利いた苦味の強いビール。
ひた‐あお【直青】‥アヲ
一面に青いこと。今昔物語集28「皆―なる装束をして」
ビターズ【bitters】
アルコールに薬草・香草などを漬けてつくった苦味の強いリキュール。また苦味をつけるための薬剤。
ひた‐あやまり【直謝り】
いちずに罪を謝すること。ひらあやまり。
ひたい【額】ヒタヒ
①顔の上部の、眉と髪の生えぎわとの間。前額。おでこ。〈類聚名義抄〉
②冠・烏帽子えぼしなどの額にあたる部分。→立烏帽子(図)。
③(「蔽髪」と書く)女官が正装の時に頭髪の前につけた、玉石類をちりばめた飾り。近世は、金銅の円板に剣形つるぎがたを加えた。平額ひらびたい。
額
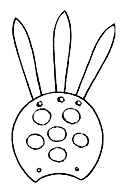 ④物の差し出たところ。枕草子66「あやふぐさは岸の―におふらむ」
⑤童舞わらわまいの冠の称。源氏物語藤裏葉「例のみづらに―ばかりのけしきを見せて」
⑥額付ひたいつきの略。
⇒ひたい‐あて【額当】
⇒ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】
⇒ひたい‐えぼし【額烏帽子】
⇒ひたい‐かくし【額隠し】
⇒ひたい‐がね【額金】
⇒ひたい‐がみ【額紙】
⇒ひたい‐がみ【額髪】
⇒ひたい‐ぎわ【額際】
⇒ひたい‐ぐし【額櫛】
⇒ひたい‐ぐち【額口】
⇒ひたい‐じろ【額白・戴白】
⇒ひたい‐つき【額月・額突】
⇒ひたい‐つき【額付き】
⇒ひたい‐なおし【額直し】
⇒ひたい‐の‐なみ【額の波】
⇒ひたい‐わた【額綿】
⇒額垂る
⇒額に汗する
⇒額に毛抜きを当てる
⇒額に角を入れる
⇒額には箭は立つとも背に箭は立たず
⇒額を集める
⇒額を合わせる
ひ‐だい【干鯛】‥ダヒ
薄塩をかけて干した鯛。鯛の干物。礼式の贈物に鮮魚の代りに用いる。
ひだい【比田井】‥ヰ
姓氏の一つ。
⇒ひだい‐てんらい【比田井天来】
ひ‐だい【肥大】
①こえて大きいこと。こえふとること。「―する官僚組織」
②〔生〕生体の器官や組織の容積が正常以上に大きくなること。「心臓―」
⇒ひだい‐せいちょう【肥大成長】
び‐たい【眉黛】
まゆずみ。
び‐たい【媚態】
男にこびるなまめかしい女の態度。また、人にこびへつらい、とり入ろうとする態度。「―をつくる」
び‐だい【尾大】
尾の方が首の方よりも大きいこと。
⇒尾大掉わず
び‐だい【尾題】
書物の巻末に記してある題名。→外題げだい→内題
び‐だい【美大】
美術大学の略。主に美術を教育・研究する大学。
ひたい‐あて【額当】ヒタヒ‥
(→)額金ひたいがねに同じ。
⇒ひたい【額】
ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】ヒタヒアハセ‥
(→)「さしわたしのいとこ」に同じ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐えぼし【額烏帽子】ヒタヒ‥
黒色の絹または紙を三角にして額に当てる小さい烏帽子。主に少年が用いる。
額烏帽子
④物の差し出たところ。枕草子66「あやふぐさは岸の―におふらむ」
⑤童舞わらわまいの冠の称。源氏物語藤裏葉「例のみづらに―ばかりのけしきを見せて」
⑥額付ひたいつきの略。
⇒ひたい‐あて【額当】
⇒ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】
⇒ひたい‐えぼし【額烏帽子】
⇒ひたい‐かくし【額隠し】
⇒ひたい‐がね【額金】
⇒ひたい‐がみ【額紙】
⇒ひたい‐がみ【額髪】
⇒ひたい‐ぎわ【額際】
⇒ひたい‐ぐし【額櫛】
⇒ひたい‐ぐち【額口】
⇒ひたい‐じろ【額白・戴白】
⇒ひたい‐つき【額月・額突】
⇒ひたい‐つき【額付き】
⇒ひたい‐なおし【額直し】
⇒ひたい‐の‐なみ【額の波】
⇒ひたい‐わた【額綿】
⇒額垂る
⇒額に汗する
⇒額に毛抜きを当てる
⇒額に角を入れる
⇒額には箭は立つとも背に箭は立たず
⇒額を集める
⇒額を合わせる
ひ‐だい【干鯛】‥ダヒ
薄塩をかけて干した鯛。鯛の干物。礼式の贈物に鮮魚の代りに用いる。
ひだい【比田井】‥ヰ
姓氏の一つ。
⇒ひだい‐てんらい【比田井天来】
ひ‐だい【肥大】
①こえて大きいこと。こえふとること。「―する官僚組織」
②〔生〕生体の器官や組織の容積が正常以上に大きくなること。「心臓―」
⇒ひだい‐せいちょう【肥大成長】
び‐たい【眉黛】
まゆずみ。
び‐たい【媚態】
男にこびるなまめかしい女の態度。また、人にこびへつらい、とり入ろうとする態度。「―をつくる」
び‐だい【尾大】
尾の方が首の方よりも大きいこと。
⇒尾大掉わず
び‐だい【尾題】
書物の巻末に記してある題名。→外題げだい→内題
び‐だい【美大】
美術大学の略。主に美術を教育・研究する大学。
ひたい‐あて【額当】ヒタヒ‥
(→)額金ひたいがねに同じ。
⇒ひたい【額】
ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】ヒタヒアハセ‥
(→)「さしわたしのいとこ」に同じ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐えぼし【額烏帽子】ヒタヒ‥
黒色の絹または紙を三角にして額に当てる小さい烏帽子。主に少年が用いる。
額烏帽子
 ⇒ひたい【額】
ひたい‐かくし【額隠し】ヒタヒ‥
(→)帽額もこう1の別称。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がね【額金】ヒタヒ‥
軍用の鉢巻の額の部分に入れた薄い鉄の板。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額紙】ヒタヒ‥
(→)紙烏帽子かみえぼし2のこと。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額髪】ヒタヒ‥
①ひたいの上の髪。まえがみ。ぬかがみ。
②前髪で二つに分けて左右の頬の辺に垂らし、肩の辺りで切りそろえたもの。源氏物語総角「顔に―をひきかけつつ」
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぎわ【額際】ヒタヒギハ
額の髪の生えぎわ。こうぎわ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐし【額櫛】ヒタヒ‥
女房装束を着用し髪上げの際に挿す櫛。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐち【額口】ヒタヒ‥
ひたいのさき。
⇒ひたい【額】
ひ‐たいじゅう【比体重】‥ヂユウ
身長に対する体重の割合。
ひたい‐じろ【額白・戴白】ヒタヒ‥
(→)月白つきじろに同じ。
⇒ひたい【額】
ひだい‐せいちょう【肥大成長】‥チヤウ
植物の茎や根が、軸と直角の方向に広がる成長。形成層の分裂による。
⇒ひ‐だい【肥大】
⇒ひたい【額】
ひたい‐かくし【額隠し】ヒタヒ‥
(→)帽額もこう1の別称。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がね【額金】ヒタヒ‥
軍用の鉢巻の額の部分に入れた薄い鉄の板。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額紙】ヒタヒ‥
(→)紙烏帽子かみえぼし2のこと。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額髪】ヒタヒ‥
①ひたいの上の髪。まえがみ。ぬかがみ。
②前髪で二つに分けて左右の頬の辺に垂らし、肩の辺りで切りそろえたもの。源氏物語総角「顔に―をひきかけつつ」
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぎわ【額際】ヒタヒギハ
額の髪の生えぎわ。こうぎわ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐし【額櫛】ヒタヒ‥
女房装束を着用し髪上げの際に挿す櫛。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐち【額口】ヒタヒ‥
ひたいのさき。
⇒ひたい【額】
ひ‐たいじゅう【比体重】‥ヂユウ
身長に対する体重の割合。
ひたい‐じろ【額白・戴白】ヒタヒ‥
(→)月白つきじろに同じ。
⇒ひたい【額】
ひだい‐せいちょう【肥大成長】‥チヤウ
植物の茎や根が、軸と直角の方向に広がる成長。形成層の分裂による。
⇒ひ‐だい【肥大】
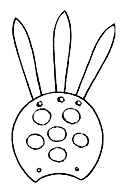 ④物の差し出たところ。枕草子66「あやふぐさは岸の―におふらむ」
⑤童舞わらわまいの冠の称。源氏物語藤裏葉「例のみづらに―ばかりのけしきを見せて」
⑥額付ひたいつきの略。
⇒ひたい‐あて【額当】
⇒ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】
⇒ひたい‐えぼし【額烏帽子】
⇒ひたい‐かくし【額隠し】
⇒ひたい‐がね【額金】
⇒ひたい‐がみ【額紙】
⇒ひたい‐がみ【額髪】
⇒ひたい‐ぎわ【額際】
⇒ひたい‐ぐし【額櫛】
⇒ひたい‐ぐち【額口】
⇒ひたい‐じろ【額白・戴白】
⇒ひたい‐つき【額月・額突】
⇒ひたい‐つき【額付き】
⇒ひたい‐なおし【額直し】
⇒ひたい‐の‐なみ【額の波】
⇒ひたい‐わた【額綿】
⇒額垂る
⇒額に汗する
⇒額に毛抜きを当てる
⇒額に角を入れる
⇒額には箭は立つとも背に箭は立たず
⇒額を集める
⇒額を合わせる
ひ‐だい【干鯛】‥ダヒ
薄塩をかけて干した鯛。鯛の干物。礼式の贈物に鮮魚の代りに用いる。
ひだい【比田井】‥ヰ
姓氏の一つ。
⇒ひだい‐てんらい【比田井天来】
ひ‐だい【肥大】
①こえて大きいこと。こえふとること。「―する官僚組織」
②〔生〕生体の器官や組織の容積が正常以上に大きくなること。「心臓―」
⇒ひだい‐せいちょう【肥大成長】
び‐たい【眉黛】
まゆずみ。
び‐たい【媚態】
男にこびるなまめかしい女の態度。また、人にこびへつらい、とり入ろうとする態度。「―をつくる」
び‐だい【尾大】
尾の方が首の方よりも大きいこと。
⇒尾大掉わず
び‐だい【尾題】
書物の巻末に記してある題名。→外題げだい→内題
び‐だい【美大】
美術大学の略。主に美術を教育・研究する大学。
ひたい‐あて【額当】ヒタヒ‥
(→)額金ひたいがねに同じ。
⇒ひたい【額】
ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】ヒタヒアハセ‥
(→)「さしわたしのいとこ」に同じ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐えぼし【額烏帽子】ヒタヒ‥
黒色の絹または紙を三角にして額に当てる小さい烏帽子。主に少年が用いる。
額烏帽子
④物の差し出たところ。枕草子66「あやふぐさは岸の―におふらむ」
⑤童舞わらわまいの冠の称。源氏物語藤裏葉「例のみづらに―ばかりのけしきを見せて」
⑥額付ひたいつきの略。
⇒ひたい‐あて【額当】
⇒ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】
⇒ひたい‐えぼし【額烏帽子】
⇒ひたい‐かくし【額隠し】
⇒ひたい‐がね【額金】
⇒ひたい‐がみ【額紙】
⇒ひたい‐がみ【額髪】
⇒ひたい‐ぎわ【額際】
⇒ひたい‐ぐし【額櫛】
⇒ひたい‐ぐち【額口】
⇒ひたい‐じろ【額白・戴白】
⇒ひたい‐つき【額月・額突】
⇒ひたい‐つき【額付き】
⇒ひたい‐なおし【額直し】
⇒ひたい‐の‐なみ【額の波】
⇒ひたい‐わた【額綿】
⇒額垂る
⇒額に汗する
⇒額に毛抜きを当てる
⇒額に角を入れる
⇒額には箭は立つとも背に箭は立たず
⇒額を集める
⇒額を合わせる
ひ‐だい【干鯛】‥ダヒ
薄塩をかけて干した鯛。鯛の干物。礼式の贈物に鮮魚の代りに用いる。
ひだい【比田井】‥ヰ
姓氏の一つ。
⇒ひだい‐てんらい【比田井天来】
ひ‐だい【肥大】
①こえて大きいこと。こえふとること。「―する官僚組織」
②〔生〕生体の器官や組織の容積が正常以上に大きくなること。「心臓―」
⇒ひだい‐せいちょう【肥大成長】
び‐たい【眉黛】
まゆずみ。
び‐たい【媚態】
男にこびるなまめかしい女の態度。また、人にこびへつらい、とり入ろうとする態度。「―をつくる」
び‐だい【尾大】
尾の方が首の方よりも大きいこと。
⇒尾大掉わず
び‐だい【尾題】
書物の巻末に記してある題名。→外題げだい→内題
び‐だい【美大】
美術大学の略。主に美術を教育・研究する大学。
ひたい‐あて【額当】ヒタヒ‥
(→)額金ひたいがねに同じ。
⇒ひたい【額】
ひたいあわせ‐の‐いとこ【額合せの従兄弟】ヒタヒアハセ‥
(→)「さしわたしのいとこ」に同じ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐えぼし【額烏帽子】ヒタヒ‥
黒色の絹または紙を三角にして額に当てる小さい烏帽子。主に少年が用いる。
額烏帽子
 ⇒ひたい【額】
ひたい‐かくし【額隠し】ヒタヒ‥
(→)帽額もこう1の別称。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がね【額金】ヒタヒ‥
軍用の鉢巻の額の部分に入れた薄い鉄の板。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額紙】ヒタヒ‥
(→)紙烏帽子かみえぼし2のこと。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額髪】ヒタヒ‥
①ひたいの上の髪。まえがみ。ぬかがみ。
②前髪で二つに分けて左右の頬の辺に垂らし、肩の辺りで切りそろえたもの。源氏物語総角「顔に―をひきかけつつ」
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぎわ【額際】ヒタヒギハ
額の髪の生えぎわ。こうぎわ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐし【額櫛】ヒタヒ‥
女房装束を着用し髪上げの際に挿す櫛。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐち【額口】ヒタヒ‥
ひたいのさき。
⇒ひたい【額】
ひ‐たいじゅう【比体重】‥ヂユウ
身長に対する体重の割合。
ひたい‐じろ【額白・戴白】ヒタヒ‥
(→)月白つきじろに同じ。
⇒ひたい【額】
ひだい‐せいちょう【肥大成長】‥チヤウ
植物の茎や根が、軸と直角の方向に広がる成長。形成層の分裂による。
⇒ひ‐だい【肥大】
⇒ひたい【額】
ひたい‐かくし【額隠し】ヒタヒ‥
(→)帽額もこう1の別称。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がね【額金】ヒタヒ‥
軍用の鉢巻の額の部分に入れた薄い鉄の板。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額紙】ヒタヒ‥
(→)紙烏帽子かみえぼし2のこと。
⇒ひたい【額】
ひたい‐がみ【額髪】ヒタヒ‥
①ひたいの上の髪。まえがみ。ぬかがみ。
②前髪で二つに分けて左右の頬の辺に垂らし、肩の辺りで切りそろえたもの。源氏物語総角「顔に―をひきかけつつ」
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぎわ【額際】ヒタヒギハ
額の髪の生えぎわ。こうぎわ。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐし【額櫛】ヒタヒ‥
女房装束を着用し髪上げの際に挿す櫛。
⇒ひたい【額】
ひたい‐ぐち【額口】ヒタヒ‥
ひたいのさき。
⇒ひたい【額】
ひ‐たいじゅう【比体重】‥ヂユウ
身長に対する体重の割合。
ひたい‐じろ【額白・戴白】ヒタヒ‥
(→)月白つきじろに同じ。
⇒ひたい【額】
ひだい‐せいちょう【肥大成長】‥チヤウ
植物の茎や根が、軸と直角の方向に広がる成長。形成層の分裂による。
⇒ひ‐だい【肥大】
広辞苑 ページ 16513 での【○顰みに倣う】単語。