複数辞典一括検索+![]()
![]()
○日向に氷ひなたにこおり🔗⭐🔉
○日向に氷ひなたにこおり
次第に消えていくことのたとえ。世間胸算用5「商ひ事なくて、いよいよ―の如し」
⇒ひ‐なた【日向】
ひなた‐ぼこ【日向ぼこ】
「ひなたぼこり」の略。〈[季]冬〉
⇒ひ‐なた【日向】
ひなた‐ぼこう【日向ぼこう】
ヒナタボコの転。
⇒ひ‐なた【日向】
ひなた‐ぼこり【日向ぼこり】
(→)「ひなたぼっこ」に同じ。〈[季]冬〉。今昔物語集19「春の節ときになりて、日うららかにて、―もせむ、若菜も摘みなむと思ひて」
⇒ひ‐なた【日向】
ひなた‐ぼっこ【日向ぼっこ】
(ヒナタボコの転)日向に出て暖まること。ひなたぼこり。天道てんとうぼこり。〈[季]冬〉
⇒ひ‐なた【日向】
ひなた‐みず【日向水】‥ミヅ
①日向にあって暖かくなった水。〈[季]夏〉
②なまぬるい水。
⇒ひ‐なた【日向】
ひな‐だん【雛壇・雛段】
①雛祭の時、人形や調度を飾り並べる、階段式の段。〈[季]春〉
②歌舞伎舞踊劇で、浄瑠璃・長唄などの演奏者がすわる二重になった台。長唄では上段に唄い手と三味線、下段に笛・大鼓・小鼓・太鼓と、2段に座を占める。→やまだい。
③(雛祭の壇のように赤毛氈もうせんをかけ、一段ずつ高くなっているから)歌舞伎劇場の1階見物席で、東西両桟敷とその前の高土間・新高土間などの称。
④俗に、国会の本会議場で、大臣席。また、会場・式場で一段高くしつらえた席。
ひなつ【日夏】
姓氏の一つ。
⇒ひなつ‐こうのすけ【日夏耿之介】
ひなつ‐こうのすけ【日夏耿之介】‥カウ‥
詩人・英文学者。本名、樋口国登。長野県生れ。早大卒。森厳な漢語趣味を駆使した神秘主義的象徴詩に異色。詩集「転身の頌」「黒衣聖母」、著「明治大正詩史」など。(1890〜1971)
日夏耿之介
撮影:田沼武能
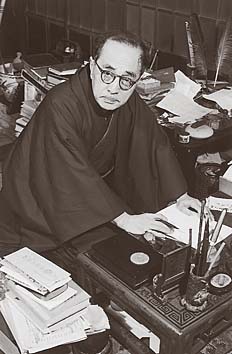 ⇒ひなつ【日夏】
ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】
火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」
ひな‐つ‐め【鄙つ女】
いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」
ひな‐づる【雛鶴】
鶴の雛。鶴の子。
ひな‐どり【雛鳥】
(→)「ひな(雛)」1に同じ。
ひな‐ながし【雛流し】
3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛
ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ
雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2
ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ
ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。
ひな‐の‐せっく【雛の節句】
3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉
ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ
3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉
ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
諸国の国府の称。とおのみかど。
⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】
ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ
諸国の国府に通ずる路。
⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】
都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」
ひな‐びと【鄙人】
田舎いなかの人。里人。
ひな・びる【鄙びる】
〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)
①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。
②言葉が訛なまる。
ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】
火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」
ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】
①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」
②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」
③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」
ひな‐べ【鄙辺】
鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」
ひな‐まつり【雛祭】
3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉
ひな‐まめほん【雛豆本】
雛道具用に作られた、特に小形の豆本。
ひ‐なみ【日並・日次】
①日記などに記す日の次第。日々の記録。
②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」
③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」
⇒ひなみ‐き【日次記】
ひなみ‐き【日次記】
日記。
⇒ひ‐なみ【日並・日次】
ひな‐もり【夷守】
辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」
ひな‐や【雛屋】
(→)「ひいなや」に同じ。
ひ‐なら‐ず【日ならず】
いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」
ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】
〔自下二〕
日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」
ひ‐ならべ‐て【日並べて】
毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」
ひ‐なわ【火縄】‥ナハ
①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。
②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」
⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】
⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】
ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥
銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。
火縄銃
⇒ひなつ【日夏】
ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】
火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」
ひな‐つ‐め【鄙つ女】
いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」
ひな‐づる【雛鶴】
鶴の雛。鶴の子。
ひな‐どり【雛鳥】
(→)「ひな(雛)」1に同じ。
ひな‐ながし【雛流し】
3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛
ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ
雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2
ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ
ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。
ひな‐の‐せっく【雛の節句】
3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉
ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ
3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉
ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
諸国の国府の称。とおのみかど。
⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】
ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ
諸国の国府に通ずる路。
⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】
都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」
ひな‐びと【鄙人】
田舎いなかの人。里人。
ひな・びる【鄙びる】
〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)
①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。
②言葉が訛なまる。
ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】
火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」
ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】
①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」
②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」
③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」
ひな‐べ【鄙辺】
鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」
ひな‐まつり【雛祭】
3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉
ひな‐まめほん【雛豆本】
雛道具用に作られた、特に小形の豆本。
ひ‐なみ【日並・日次】
①日記などに記す日の次第。日々の記録。
②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」
③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」
⇒ひなみ‐き【日次記】
ひなみ‐き【日次記】
日記。
⇒ひ‐なみ【日並・日次】
ひな‐もり【夷守】
辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」
ひな‐や【雛屋】
(→)「ひいなや」に同じ。
ひ‐なら‐ず【日ならず】
いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」
ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】
〔自下二〕
日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」
ひ‐ならべ‐て【日並べて】
毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」
ひ‐なわ【火縄】‥ナハ
①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。
②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」
⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】
⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】
ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥
銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。
火縄銃
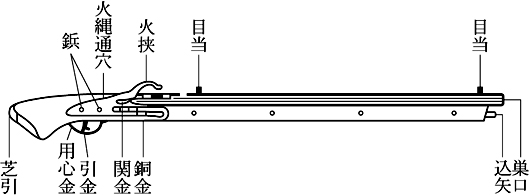 火縄銃
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
火縄銃
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒ひ‐なわ【火縄】
ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥
(→)火縄銃に同じ。
⇒ひ‐なわ【火縄】
ひ‐なん【非難・批難】
欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」
ひ‐なん【避難】
災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」
⇒ひなん‐かいだん【避難階段】
⇒ひなん‐こう【避難港】
⇒ひなん‐ひろば【避難広場】
⇒ひなん‐みん【避難民】
び‐なん【美男】
①容姿の美しい男。美男子。「―美女」
②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。
美男
⇒ひ‐なわ【火縄】
ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥
(→)火縄銃に同じ。
⇒ひ‐なわ【火縄】
ひ‐なん【非難・批難】
欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」
ひ‐なん【避難】
災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」
⇒ひなん‐かいだん【避難階段】
⇒ひなん‐こう【避難港】
⇒ひなん‐ひろば【避難広場】
⇒ひなん‐みん【避難民】
び‐なん【美男】
①容姿の美しい男。美男子。「―美女」
②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。
美男
 ⇒びなん‐かずら【美男葛】
⇒びなん‐せき【美男石】
⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】
ひなん‐かいだん【避難階段】
災害時の避難の用に供する階段。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ
①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。
②(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐こう【避難港】‥カウ
悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。
⇒ひ‐なん【避難】
び‐なんし【美男子】
(→)美男びなん1に同じ。びだんし。
びなん‐せき【美男石】
(→)美男葛かずら1に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐ひろば【避難広場】
災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐ぼうし【美男帽子】
(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐みん【避難民】
天災地変・戦争などで避難した人々。
⇒ひ‐なん【避難】
⇒びなん‐かずら【美男葛】
⇒びなん‐せき【美男石】
⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】
ひなん‐かいだん【避難階段】
災害時の避難の用に供する階段。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ
①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。
②(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐こう【避難港】‥カウ
悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。
⇒ひ‐なん【避難】
び‐なんし【美男子】
(→)美男びなん1に同じ。びだんし。
びなん‐せき【美男石】
(→)美男葛かずら1に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐ひろば【避難広場】
災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐ぼうし【美男帽子】
(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐みん【避難民】
天災地変・戦争などで避難した人々。
⇒ひ‐なん【避難】
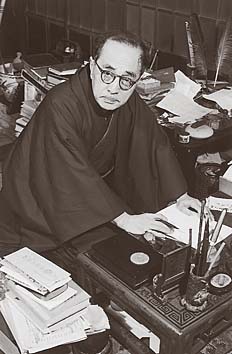 ⇒ひなつ【日夏】
ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】
火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」
ひな‐つ‐め【鄙つ女】
いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」
ひな‐づる【雛鶴】
鶴の雛。鶴の子。
ひな‐どり【雛鳥】
(→)「ひな(雛)」1に同じ。
ひな‐ながし【雛流し】
3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛
ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ
雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2
ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ
ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。
ひな‐の‐せっく【雛の節句】
3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉
ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ
3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉
ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
諸国の国府の称。とおのみかど。
⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】
ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ
諸国の国府に通ずる路。
⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】
都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」
ひな‐びと【鄙人】
田舎いなかの人。里人。
ひな・びる【鄙びる】
〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)
①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。
②言葉が訛なまる。
ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】
火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」
ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】
①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」
②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」
③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」
ひな‐べ【鄙辺】
鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」
ひな‐まつり【雛祭】
3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉
ひな‐まめほん【雛豆本】
雛道具用に作られた、特に小形の豆本。
ひ‐なみ【日並・日次】
①日記などに記す日の次第。日々の記録。
②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」
③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」
⇒ひなみ‐き【日次記】
ひなみ‐き【日次記】
日記。
⇒ひ‐なみ【日並・日次】
ひな‐もり【夷守】
辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」
ひな‐や【雛屋】
(→)「ひいなや」に同じ。
ひ‐なら‐ず【日ならず】
いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」
ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】
〔自下二〕
日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」
ひ‐ならべ‐て【日並べて】
毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」
ひ‐なわ【火縄】‥ナハ
①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。
②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」
⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】
⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】
ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥
銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。
火縄銃
⇒ひなつ【日夏】
ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】
火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」
ひな‐つ‐め【鄙つ女】
いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」
ひな‐づる【雛鶴】
鶴の雛。鶴の子。
ひな‐どり【雛鳥】
(→)「ひな(雛)」1に同じ。
ひな‐ながし【雛流し】
3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛
ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ
雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2
ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ
ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。
ひな‐の‐せっく【雛の節句】
3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉
ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ
3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉
ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
諸国の国府の称。とおのみかど。
⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】
ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ
諸国の国府に通ずる路。
⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】
ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】
都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」
ひな‐びと【鄙人】
田舎いなかの人。里人。
ひな・びる【鄙びる】
〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)
①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。
②言葉が訛なまる。
ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】
火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」
ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】
①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」
②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」
③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」
ひな‐べ【鄙辺】
鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」
ひな‐まつり【雛祭】
3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉
ひな‐まめほん【雛豆本】
雛道具用に作られた、特に小形の豆本。
ひ‐なみ【日並・日次】
①日記などに記す日の次第。日々の記録。
②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」
③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」
⇒ひなみ‐き【日次記】
ひなみ‐き【日次記】
日記。
⇒ひ‐なみ【日並・日次】
ひな‐もり【夷守】
辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」
ひな‐や【雛屋】
(→)「ひいなや」に同じ。
ひ‐なら‐ず【日ならず】
いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」
ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】
〔自下二〕
日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」
ひ‐ならべ‐て【日並べて】
毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」
ひ‐なわ【火縄】‥ナハ
①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。
②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」
⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】
⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】
ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥
銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。
火縄銃
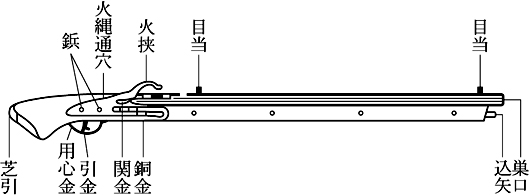 火縄銃
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
火縄銃
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒ひ‐なわ【火縄】
ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥
(→)火縄銃に同じ。
⇒ひ‐なわ【火縄】
ひ‐なん【非難・批難】
欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」
ひ‐なん【避難】
災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」
⇒ひなん‐かいだん【避難階段】
⇒ひなん‐こう【避難港】
⇒ひなん‐ひろば【避難広場】
⇒ひなん‐みん【避難民】
び‐なん【美男】
①容姿の美しい男。美男子。「―美女」
②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。
美男
⇒ひ‐なわ【火縄】
ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥
(→)火縄銃に同じ。
⇒ひ‐なわ【火縄】
ひ‐なん【非難・批難】
欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」
ひ‐なん【避難】
災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」
⇒ひなん‐かいだん【避難階段】
⇒ひなん‐こう【避難港】
⇒ひなん‐ひろば【避難広場】
⇒ひなん‐みん【避難民】
び‐なん【美男】
①容姿の美しい男。美男子。「―美女」
②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。
美男
 ⇒びなん‐かずら【美男葛】
⇒びなん‐せき【美男石】
⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】
ひなん‐かいだん【避難階段】
災害時の避難の用に供する階段。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ
①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。
②(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐こう【避難港】‥カウ
悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。
⇒ひ‐なん【避難】
び‐なんし【美男子】
(→)美男びなん1に同じ。びだんし。
びなん‐せき【美男石】
(→)美男葛かずら1に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐ひろば【避難広場】
災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐ぼうし【美男帽子】
(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐みん【避難民】
天災地変・戦争などで避難した人々。
⇒ひ‐なん【避難】
⇒びなん‐かずら【美男葛】
⇒びなん‐せき【美男石】
⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】
ひなん‐かいだん【避難階段】
災害時の避難の用に供する階段。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ
①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。
②(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐こう【避難港】‥カウ
悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。
⇒ひ‐なん【避難】
び‐なんし【美男子】
(→)美男びなん1に同じ。びだんし。
びなん‐せき【美男石】
(→)美男葛かずら1に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐ひろば【避難広場】
災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。
⇒ひ‐なん【避難】
びなん‐ぼうし【美男帽子】
(→)美男2に同じ。
⇒び‐なん【美男】
ひなん‐みん【避難民】
天災地変・戦争などで避難した人々。
⇒ひ‐なん【避難】
広辞苑 ページ 16649 での【○日向に氷】単語。