複数辞典一括検索+![]()
![]()
○臼から杵うすからきね🔗⭐🔉
○臼から杵うすからきね
(臼は女、杵は男を象徴する。女から男に働きかけるのは逆であるの意で)事が逆であるさまにいう。
⇒うす【臼・舂・碓】
うす‐かわ【薄皮】‥カハ
①物の表面を覆う薄い膜。
②薄皮饅頭まんじゅうの略。
③皮の薄いミカンの一種。
④女などの、色が白くて、きめの細かい皮膚。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「生れついたる―の」
⇒うすかわ‐まゆ【薄皮繭】
⇒うすかわ‐まんじゅう【薄皮饅頭】
うすかわ‐まゆ【薄皮繭】‥カハ‥
繭の層の薄いもの。
⇒うす‐かわ【薄皮】
うすかわ‐まんじゅう【薄皮饅頭】‥カハ‥ヂユウ
皮が薄く餡あんの多いまんじゅう。うすかわ。
⇒うす‐かわ【薄皮】
うすき【臼杵】
大分県東部の市。豊後水道の臼杵湾に臨み、永禄(1558〜1570)年間、大友氏の城下町として繁栄し、ポルトガル船が来航交易した。慶長以後、稲葉氏5万石の城下町。臼杵石仏がある。人口4万3千。
⇒うすき‐せきぶつ【臼杵石仏】
うす‐ぎ【薄着】
着物をたくさん重ねて着ないこと。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「―するな、毒喰ふな」。「伊達だての―」↔厚着
うずき【疼き】ウヅキ
うずくこと。いたみ。「胸の―」
うすき‐せきぶつ【臼杵石仏】
臼杵市深田・中尾・前田にまたがる石仏群。大日如来や釈迦三尊像・地蔵十王像など75体余りの諸像が現存し、平安後期から鎌倉期の作とされる。
臼杵石仏
撮影:新海良夫
 ⇒うすき【臼杵】
うす‐ぎたな・い【薄穢い・薄汚い】
〔形〕
なんとなくきたない。「―・い下着」「―・いやり方」
うす‐ぎぬ【薄衣】
地の薄いきもの。薄ごろも。
うす‐ぎぬ【薄帛・薄絹】
地の薄い絹織物。紗しゃ・絽ろなど。
うす‐きね【臼杵】
子供の遊戯の一つ。枕木の上に長い板を横たえ、板の両端に一人ずつ向かい合って立ち、交互に両端を踏んで上下するもの。互いに臼をつく杵のようになるからいう。シーソー。
うす‐きみわる・い【薄気味悪い】
〔形〕
なんとなく気味がわるい。「暗くて―・い部屋だ」
うす‐ぎり【薄切り】
食品を薄く切ること。薄く切ったもの。「ハムの―」
うす‐ぎり【薄霧】
薄くかかった霧。
うす‐きりふ【薄切斑】
斑ふの色の薄い切斑の矢羽。→切斑
うす‐ぎ・る【薄霧る】
〔自四〕
薄く霧が立ちこめる。風雅和歌集冬「あさけの山は―・りて」
うず・く【疼く】ウヅク
〔自五〕
ずきずき痛む。発心集「切り焼くがごとく―・きひびらき」。「傷が―・く」「胸が―・く」
うす‐くち【薄口】
①吸物や煮物などの料理の味付けが薄めのもの。「―に煮る」
②薄口醤油の略。↔濃口こいくち。
③陶器などで、薄手に仕上げてあるもの。「―の茶碗」
⇒うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】
うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】‥シヤウ‥
色が薄い醤油。味・香りともにあっさりしているが、塩分は多く含む。関西で多く使用。↔濃口醤油
⇒うす‐くち【薄口】
うずくまる【蹲】ウヅクマル
(人のうずくまったような形から)掛花入れの一種。信楽しがらきなどの小壺で、元来は室町時代から農家の豆入・茶壺として造られた。
うずくま・る【蹲る・踞る】
〔自五〕
(室町時代以後、仮名表記はウヅクマル)
①体を丸くして膝を折り腰を落とす。しゃがむ。〈日本霊異記下訓釈〉。「道端に―・る」
②獣などが前肢を折って地面に腹をつけてすわる。
うすくも【薄雲】
平家重代の鎧よろいの一つ。
うす‐ぐも【薄雲】
①薄くかかった雲。
薄雲
撮影:高橋健司
⇒うすき【臼杵】
うす‐ぎたな・い【薄穢い・薄汚い】
〔形〕
なんとなくきたない。「―・い下着」「―・いやり方」
うす‐ぎぬ【薄衣】
地の薄いきもの。薄ごろも。
うす‐ぎぬ【薄帛・薄絹】
地の薄い絹織物。紗しゃ・絽ろなど。
うす‐きね【臼杵】
子供の遊戯の一つ。枕木の上に長い板を横たえ、板の両端に一人ずつ向かい合って立ち、交互に両端を踏んで上下するもの。互いに臼をつく杵のようになるからいう。シーソー。
うす‐きみわる・い【薄気味悪い】
〔形〕
なんとなく気味がわるい。「暗くて―・い部屋だ」
うす‐ぎり【薄切り】
食品を薄く切ること。薄く切ったもの。「ハムの―」
うす‐ぎり【薄霧】
薄くかかった霧。
うす‐きりふ【薄切斑】
斑ふの色の薄い切斑の矢羽。→切斑
うす‐ぎ・る【薄霧る】
〔自四〕
薄く霧が立ちこめる。風雅和歌集冬「あさけの山は―・りて」
うず・く【疼く】ウヅク
〔自五〕
ずきずき痛む。発心集「切り焼くがごとく―・きひびらき」。「傷が―・く」「胸が―・く」
うす‐くち【薄口】
①吸物や煮物などの料理の味付けが薄めのもの。「―に煮る」
②薄口醤油の略。↔濃口こいくち。
③陶器などで、薄手に仕上げてあるもの。「―の茶碗」
⇒うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】
うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】‥シヤウ‥
色が薄い醤油。味・香りともにあっさりしているが、塩分は多く含む。関西で多く使用。↔濃口醤油
⇒うす‐くち【薄口】
うずくまる【蹲】ウヅクマル
(人のうずくまったような形から)掛花入れの一種。信楽しがらきなどの小壺で、元来は室町時代から農家の豆入・茶壺として造られた。
うずくま・る【蹲る・踞る】
〔自五〕
(室町時代以後、仮名表記はウヅクマル)
①体を丸くして膝を折り腰を落とす。しゃがむ。〈日本霊異記下訓釈〉。「道端に―・る」
②獣などが前肢を折って地面に腹をつけてすわる。
うすくも【薄雲】
平家重代の鎧よろいの一つ。
うす‐ぐも【薄雲】
①薄くかかった雲。
薄雲
撮影:高橋健司
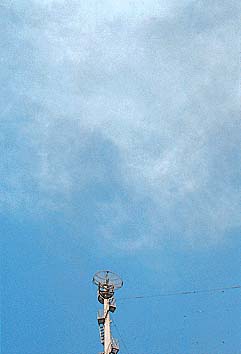 ②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】‥ヰン
源氏物語中の女性藤壺のこと。「薄雲」の巻にその崩御のことを記すからいう。
⇒うす‐ぐも【薄雲】
うす‐ぐもり【薄曇】
うっすらと曇ること。上層雲の多い曇り。
うず‐くら【雲珠鞍】
雲珠の飾りをつけた鞍。唐鞍からくら。
うす‐ぐら・い【薄暗い】
〔形〕[文]うすぐら・し(ク)
光が薄くて、まっくらではないが、暗い。ほのぐらい。「―・い部屋」
うす‐くらがり【薄暗がり】
少し暗いこと。また、その場所。「植込みの―に隠れる」
うす‐くりげ【薄栗毛】
馬の毛色の、黄色を帯びた栗毛で、たてがみの黒いもの。
うす‐ぐれ【薄暮れ】
夕方。うす暗くなるころ。〈日葡辞書〉
うす‐くれない【薄紅】‥クレナヰ
薄いくれない色。淡紅。
うす‐ぐろ・い【薄黒い】
〔形〕
少しばかり黒い。黒ずんでいる。
うす‐げしょう【薄化粧】‥シヤウ
あっさりと化粧すること。「―して外出する」「雪で―した山」↔厚化粧
うす‐けわい【薄粧】‥ケハヒ
うすげしょう。
うす‐こうばい【薄紅梅】
①紅梅の花の色の薄いもの。
②紅梅色の薄いもの。枕草子50「馬は…―の毛にて」
Munsell color system: 5RP7/8
③襲かさねの色目。紅梅襲の表裏とも薄いもの。
うす‐ごおり【薄氷】‥ゴホリ
①薄く張った氷。うすらひ。〈[季]春〉
②氷のひびのはいったさまに擬した模様。
うす‐こお・る【薄氷る】‥コホル
〔自四〕
薄く氷る。千載和歌集冬「岩間の水の―・るらむ」
うす‐こはく【薄琥珀】
絹織物の一つ。琥珀織の薄地のもの。タフタ。浜琥珀。
うす‐ざいしき【薄彩色】
薄く施した彩色。墨絵の上に藍・代赭たいしゃなどで薄く着色したもの。〈日葡辞書〉
うす‐ざくら【薄桜】
①桜の花の色のうすいもの。
②襲かさねの色目。表は白、裏は紅で、一重梅ひとえうめと異名同色。(蛙抄)
⇒うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
うず‐ざくら【雲珠桜】
①(「雲珠」は馬具。地名「鞍馬」との縁で)京都の鞍馬山に咲く桜の総称。
②いわゆるサトザクラの一種。花は紅色で重弁。
うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
襲かさねの色目。山科流では、表は薄青、裏も同じ、または薄紅。また、表は青、裏は蘇芳すおうとも。
⇒うす‐ざくら【薄桜】
うすさま‐みょうおう【烏枢沙摩明王】‥ミヤウワウ
(ウスシャマミョウオウとも。梵語Ucchuṣma 不浄潔・除穢と訳す)不浄を避けず衆生しゅじょうを救う徳を有するという明王。寺院の手洗いなどにまつられる。二臂・四臂・六臂のものがあり、忿怒ふんぬの相で、火焔に覆われる。烏芻沙摩明王。穢迹金剛えしゃくこんごう。火頭かず金剛。
うす‐さむ・い【薄寒い】
〔形〕[文]うすさむ・し(ク)
(主として明治期に用いた語)なんとなく寒い。少し寒く感じられる。うそさむい。
うす‐ざん【有珠山】
北海道南西部、洞爺とうや湖の南にある二重式活火山。標高733メートル。2000年に大規模な水蒸気爆発を観測。
有珠山と洞爺湖
撮影:新海良夫
②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】‥ヰン
源氏物語中の女性藤壺のこと。「薄雲」の巻にその崩御のことを記すからいう。
⇒うす‐ぐも【薄雲】
うす‐ぐもり【薄曇】
うっすらと曇ること。上層雲の多い曇り。
うず‐くら【雲珠鞍】
雲珠の飾りをつけた鞍。唐鞍からくら。
うす‐ぐら・い【薄暗い】
〔形〕[文]うすぐら・し(ク)
光が薄くて、まっくらではないが、暗い。ほのぐらい。「―・い部屋」
うす‐くらがり【薄暗がり】
少し暗いこと。また、その場所。「植込みの―に隠れる」
うす‐くりげ【薄栗毛】
馬の毛色の、黄色を帯びた栗毛で、たてがみの黒いもの。
うす‐ぐれ【薄暮れ】
夕方。うす暗くなるころ。〈日葡辞書〉
うす‐くれない【薄紅】‥クレナヰ
薄いくれない色。淡紅。
うす‐ぐろ・い【薄黒い】
〔形〕
少しばかり黒い。黒ずんでいる。
うす‐げしょう【薄化粧】‥シヤウ
あっさりと化粧すること。「―して外出する」「雪で―した山」↔厚化粧
うす‐けわい【薄粧】‥ケハヒ
うすげしょう。
うす‐こうばい【薄紅梅】
①紅梅の花の色の薄いもの。
②紅梅色の薄いもの。枕草子50「馬は…―の毛にて」
Munsell color system: 5RP7/8
③襲かさねの色目。紅梅襲の表裏とも薄いもの。
うす‐ごおり【薄氷】‥ゴホリ
①薄く張った氷。うすらひ。〈[季]春〉
②氷のひびのはいったさまに擬した模様。
うす‐こお・る【薄氷る】‥コホル
〔自四〕
薄く氷る。千載和歌集冬「岩間の水の―・るらむ」
うす‐こはく【薄琥珀】
絹織物の一つ。琥珀織の薄地のもの。タフタ。浜琥珀。
うす‐ざいしき【薄彩色】
薄く施した彩色。墨絵の上に藍・代赭たいしゃなどで薄く着色したもの。〈日葡辞書〉
うす‐ざくら【薄桜】
①桜の花の色のうすいもの。
②襲かさねの色目。表は白、裏は紅で、一重梅ひとえうめと異名同色。(蛙抄)
⇒うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
うず‐ざくら【雲珠桜】
①(「雲珠」は馬具。地名「鞍馬」との縁で)京都の鞍馬山に咲く桜の総称。
②いわゆるサトザクラの一種。花は紅色で重弁。
うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
襲かさねの色目。山科流では、表は薄青、裏も同じ、または薄紅。また、表は青、裏は蘇芳すおうとも。
⇒うす‐ざくら【薄桜】
うすさま‐みょうおう【烏枢沙摩明王】‥ミヤウワウ
(ウスシャマミョウオウとも。梵語Ucchuṣma 不浄潔・除穢と訳す)不浄を避けず衆生しゅじょうを救う徳を有するという明王。寺院の手洗いなどにまつられる。二臂・四臂・六臂のものがあり、忿怒ふんぬの相で、火焔に覆われる。烏芻沙摩明王。穢迹金剛えしゃくこんごう。火頭かず金剛。
うす‐さむ・い【薄寒い】
〔形〕[文]うすさむ・し(ク)
(主として明治期に用いた語)なんとなく寒い。少し寒く感じられる。うそさむい。
うす‐ざん【有珠山】
北海道南西部、洞爺とうや湖の南にある二重式活火山。標高733メートル。2000年に大規模な水蒸気爆発を観測。
有珠山と洞爺湖
撮影:新海良夫
 うす・し【薄し・淡し】
〔形ク〕
⇒うすい
うす‐じ【薄地】‥ヂ
織地や金属などの薄いもの。
うす‐じお【薄塩】‥ジホ
塩加減の薄いこと。また、薄い塩加減に調理してあること。甘塩。日葡辞書「ウスジヲノウヲ」
うず‐しお【渦潮】ウヅシホ
渦巻く潮流。万葉集15「名に負ふ鳴門の―に」
うす‐じき【薄敷】
取引所規定よりも少額の証拠金。もぐりの仲買人が、この証拠金を取って、取引所の相場を標準に一種の賭博行為をなすことをいう。薄張り。
うす‐したじ【薄下地】‥ヂ
塩加減を薄くした醤油。上方料理に用いる。浮世風呂2「―で吸物ぢやさかい」
うす‐じも【薄霜】
薄く降りた霜。
うずじょう‐ぎんが【渦状銀河】ウヅジヤウ‥
(→)渦巻うずまき銀河に同じ。
うす‐じり【薄知り】
うすうす事情を知っていること。狂言、花子「例の山の神が、―に知つて」
うす‐じろ【薄白】
和紙の名。室町時代に美濃で産した薄くて白い楮紙こうぞがみ。
うす‐じろ・い【薄白い】
〔形〕[文]うすじろ・し(ク)
(色がさめて)白っぽい。讃岐典侍日記「尾花の―・くなりて招きたちて見ゆるが」
うすす・く
〔自四〕
心がおちつかない。あわてる。驚き騒ぐ。源氏物語槿「御門守…―・き出で来てとみにもえ開けやらず」→いすすく
うず‐すま・る
〔自四〕
うずくまり集まる。古事記下「大宮人は…庭すずめ―・りゐて」
うす‐ずみ【薄墨】
①墨の色の薄いもの。源氏物語少女「まぎらはし書いたる濃墨こずみ・―、草がちにうちまぜ乱れたるも」
②薄墨紙の略。後拾遺和歌集春「―にかく玉づさと見ゆるかな」
③(女房詞)そばのかゆ。そばがき。
⇒うすずみ‐いろ【薄墨色】
⇒うすずみ‐がみ【薄墨紙】
⇒うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
⇒うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
⇒うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
うすずみ‐いろ【薄墨色】
墨色の薄いもの。ねずみ色。
Munsell color system: N6.1
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐がみ【薄墨紙】
反故ほごの墨色が十分に脱けずに残った、薄いねずみ色のすきがえし紙。平安末期から京都紙屋院かみやいんで作り、鎌倉時代からは綸旨りんじを書くのにも用いた。宿紙しゅくし。→紙屋紙かみやがみ。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
薄墨色に染めた衣。喪服用。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
①サトザクラの一品種。芽は緑色、花は白く一重咲きで直径4〜5センチメートル。
②(「淡墨桜」と書く)岐阜県本巣市根尾にあるエドヒガンの巨木。天然記念物。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
薄墨紙を用いた綸旨。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うす‐ず・む【薄ずむ】
〔自四〕
薄く黒ずんで見える。薄くかすんで見える。夫木和歌抄13「朝霧のそことしるしはなけれども―・み渡る三輪の杉むら」
うす‐ずり【薄摺】
薄い色に摺って染めること。
うす‐ぞめ【薄染】
色を薄く染めること。
⇒うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
薄い色に染めた衣服。万葉集12「くれなゐの―浅らかに」
⇒うす‐ぞめ【薄染】
ウスター‐ソース
(Worcestershire sauce)西洋料理の調味料で、日本で普通ソースと呼んでいるもの。各種の野菜・果実・香辛料・調味料を原料とする。イングランド中部のウスターで最初に作られ、19世紀末頃渡来。
うす‐だいこ【臼太鼓】
宮崎・大分・熊本などで行われる太鼓踊の一種。幟のぼりを負い音頭の唄につれ、鉦かね・笛を交える青年の勇壮な民俗舞踊。臼太鼓踊。
うず‐たか・い【堆い】ウヅタカイ
〔形〕[文]うづたか・し(ク)
(古くは清音。ウズダカシとも)もりあがって高い。積もって高い。平家物語8「飯はん―・くよそひ」。「書類を―・く積む」
うす‐たけ【臼茸】
担子菌類のきのこ。夏から秋に針葉樹林下に生じ、高さ約10センチメートル。漏斗状で中央は深い穴となり、黄褐色。外側は淡色で柄と傘との区別が明らかでない。〈易林本節用集〉
うす‐だたみ【薄畳】
昔、春・夏に用いた薄い畳。うすべり。
うすたび‐が【薄手火蛾・薄足袋蛾】
ヤママユガ科のガ。体も翅も橙褐色ないし黄褐色で、前後翅に各1個の円い半透明な紋がある。開張は約10センチメートル。幼虫はクリ・クヌギ・ケヤキ・サクラ・カエデなどを食い、成虫は秋に出現。繭は山叺やまかますなどと俗称。
ウスタビガ
撮影:海野和男
うす・し【薄し・淡し】
〔形ク〕
⇒うすい
うす‐じ【薄地】‥ヂ
織地や金属などの薄いもの。
うす‐じお【薄塩】‥ジホ
塩加減の薄いこと。また、薄い塩加減に調理してあること。甘塩。日葡辞書「ウスジヲノウヲ」
うず‐しお【渦潮】ウヅシホ
渦巻く潮流。万葉集15「名に負ふ鳴門の―に」
うす‐じき【薄敷】
取引所規定よりも少額の証拠金。もぐりの仲買人が、この証拠金を取って、取引所の相場を標準に一種の賭博行為をなすことをいう。薄張り。
うす‐したじ【薄下地】‥ヂ
塩加減を薄くした醤油。上方料理に用いる。浮世風呂2「―で吸物ぢやさかい」
うす‐じも【薄霜】
薄く降りた霜。
うずじょう‐ぎんが【渦状銀河】ウヅジヤウ‥
(→)渦巻うずまき銀河に同じ。
うす‐じり【薄知り】
うすうす事情を知っていること。狂言、花子「例の山の神が、―に知つて」
うす‐じろ【薄白】
和紙の名。室町時代に美濃で産した薄くて白い楮紙こうぞがみ。
うす‐じろ・い【薄白い】
〔形〕[文]うすじろ・し(ク)
(色がさめて)白っぽい。讃岐典侍日記「尾花の―・くなりて招きたちて見ゆるが」
うすす・く
〔自四〕
心がおちつかない。あわてる。驚き騒ぐ。源氏物語槿「御門守…―・き出で来てとみにもえ開けやらず」→いすすく
うず‐すま・る
〔自四〕
うずくまり集まる。古事記下「大宮人は…庭すずめ―・りゐて」
うす‐ずみ【薄墨】
①墨の色の薄いもの。源氏物語少女「まぎらはし書いたる濃墨こずみ・―、草がちにうちまぜ乱れたるも」
②薄墨紙の略。後拾遺和歌集春「―にかく玉づさと見ゆるかな」
③(女房詞)そばのかゆ。そばがき。
⇒うすずみ‐いろ【薄墨色】
⇒うすずみ‐がみ【薄墨紙】
⇒うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
⇒うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
⇒うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
うすずみ‐いろ【薄墨色】
墨色の薄いもの。ねずみ色。
Munsell color system: N6.1
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐がみ【薄墨紙】
反故ほごの墨色が十分に脱けずに残った、薄いねずみ色のすきがえし紙。平安末期から京都紙屋院かみやいんで作り、鎌倉時代からは綸旨りんじを書くのにも用いた。宿紙しゅくし。→紙屋紙かみやがみ。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
薄墨色に染めた衣。喪服用。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
①サトザクラの一品種。芽は緑色、花は白く一重咲きで直径4〜5センチメートル。
②(「淡墨桜」と書く)岐阜県本巣市根尾にあるエドヒガンの巨木。天然記念物。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
薄墨紙を用いた綸旨。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うす‐ず・む【薄ずむ】
〔自四〕
薄く黒ずんで見える。薄くかすんで見える。夫木和歌抄13「朝霧のそことしるしはなけれども―・み渡る三輪の杉むら」
うす‐ずり【薄摺】
薄い色に摺って染めること。
うす‐ぞめ【薄染】
色を薄く染めること。
⇒うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
薄い色に染めた衣服。万葉集12「くれなゐの―浅らかに」
⇒うす‐ぞめ【薄染】
ウスター‐ソース
(Worcestershire sauce)西洋料理の調味料で、日本で普通ソースと呼んでいるもの。各種の野菜・果実・香辛料・調味料を原料とする。イングランド中部のウスターで最初に作られ、19世紀末頃渡来。
うす‐だいこ【臼太鼓】
宮崎・大分・熊本などで行われる太鼓踊の一種。幟のぼりを負い音頭の唄につれ、鉦かね・笛を交える青年の勇壮な民俗舞踊。臼太鼓踊。
うず‐たか・い【堆い】ウヅタカイ
〔形〕[文]うづたか・し(ク)
(古くは清音。ウズダカシとも)もりあがって高い。積もって高い。平家物語8「飯はん―・くよそひ」。「書類を―・く積む」
うす‐たけ【臼茸】
担子菌類のきのこ。夏から秋に針葉樹林下に生じ、高さ約10センチメートル。漏斗状で中央は深い穴となり、黄褐色。外側は淡色で柄と傘との区別が明らかでない。〈易林本節用集〉
うす‐だたみ【薄畳】
昔、春・夏に用いた薄い畳。うすべり。
うすたび‐が【薄手火蛾・薄足袋蛾】
ヤママユガ科のガ。体も翅も橙褐色ないし黄褐色で、前後翅に各1個の円い半透明な紋がある。開張は約10センチメートル。幼虫はクリ・クヌギ・ケヤキ・サクラ・カエデなどを食い、成虫は秋に出現。繭は山叺やまかますなどと俗称。
ウスタビガ
撮影:海野和男
 うす‐だま【臼玉】
古墳時代の遺物の一種。管玉くだたまを短く切ったような臼形の祭祀・装身用の玉。滑石かっせき製が普通。
うす‐だみ【薄彩み】
薄くいろどること。日葡辞書「ウスダミノエ」
うす‐だ・む【薄彩む】
〔他四〕
薄くいろどる。正治百首「―・みわたる夕霞かな」
うす‐だん【薄緂】
白地に薄紫にいろどった緂だん。源氏物語若菜上「御手書かせ給へる唐の綾の―に」
うす‐ちゃ【薄茶】
①点茶の時、抹茶の分量を少なくしてたてるもの。おうす。↔濃茶こいちゃ。
②薄茶色の略。茶色のうすいもの。
⇒うすちゃ‐き【薄茶器】
⇒うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】
うすちゃ‐き【薄茶器】
茶道具の一種。薄茶をたてるとき、抹茶を入れておく容器。主に漆塗りの棗なつめなど。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】‥マヘ
薄茶をたてる作法。漆器の棗なつめ・茶碗・茶杓・茶筅ちゃせん・建水けんすい・柄杓ひしゃくなどを用い、一人ずつにたてる。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うす‐ちり【薄塵】
蒔絵まきえに金粉を薄く散らしたもの。
うす‐つき【臼搗き】
臼に物を入れて杵きねでつくこと。
⇒うすつき‐うた【臼搗き唄】
⇒うすつき‐うち【臼搗き打ち】
うすつき‐うた【臼搗き唄】
臼を杵でつきながら唄う労働唄。
⇒うす‐つき【臼搗き】
うすつき‐うち【臼搗き打ち】
杵で臼をつくように、ふりあげてうちおろすこと。浄瑠璃、日本振袖始「―に打つ鋤が、余つて向うへ越す処が」
⇒うす‐つき【臼搗き】
うす‐づきよ【薄月夜】
月の光のほのかにさす夜。おぼろづきよ。
うす‐づ・く【臼づく・舂く】
〔自四〕
①臼に物を入れて杵きねでつく。
②夕日が山に入ろうとする。父の終焉日記「かく日も壁際に―・き、飯時にもならんとするころ」
うず‐つ・くウヅツク
〔自四〕
ぐずぐずする。ぐずつく。浮世草子、世間手代気質「一生秀でずに―・いて居ようとは」
うす‐づくり【薄造り・薄作り】
刺身で、ごく薄くそぎ切りにしたもの。フグ・ヒラメなどに適する。
うすっ‐ぺら【薄っぺら】
薄くぺらぺらしていること。転じて、物の見方や人柄が奥深くないこと。浅薄。「―な用紙」「―な人間」
うす‐で【薄手】
①紙・織物・陶器などの地の薄いこと。「―の茶碗」↔厚手あつで。
②安っぽいこと。浅薄なこと。「―な内容の本」
③軽いきず。浅手。「―を負う」↔深手
うず‐ていこう【渦抵抗】ウヅ‥カウ
物体が流体中を進むとき、物体の形状が完全な流線型でない部分に生じる渦によって発生する抵抗。
うず‐でんりゅう【渦電流】ウヅ‥リウ
変化している磁場中の導体内に、電磁誘導によって流れる渦巻状の電流。渦動かどう電流。フーコー電流。
うす‐だま【臼玉】
古墳時代の遺物の一種。管玉くだたまを短く切ったような臼形の祭祀・装身用の玉。滑石かっせき製が普通。
うす‐だみ【薄彩み】
薄くいろどること。日葡辞書「ウスダミノエ」
うす‐だ・む【薄彩む】
〔他四〕
薄くいろどる。正治百首「―・みわたる夕霞かな」
うす‐だん【薄緂】
白地に薄紫にいろどった緂だん。源氏物語若菜上「御手書かせ給へる唐の綾の―に」
うす‐ちゃ【薄茶】
①点茶の時、抹茶の分量を少なくしてたてるもの。おうす。↔濃茶こいちゃ。
②薄茶色の略。茶色のうすいもの。
⇒うすちゃ‐き【薄茶器】
⇒うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】
うすちゃ‐き【薄茶器】
茶道具の一種。薄茶をたてるとき、抹茶を入れておく容器。主に漆塗りの棗なつめなど。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】‥マヘ
薄茶をたてる作法。漆器の棗なつめ・茶碗・茶杓・茶筅ちゃせん・建水けんすい・柄杓ひしゃくなどを用い、一人ずつにたてる。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うす‐ちり【薄塵】
蒔絵まきえに金粉を薄く散らしたもの。
うす‐つき【臼搗き】
臼に物を入れて杵きねでつくこと。
⇒うすつき‐うた【臼搗き唄】
⇒うすつき‐うち【臼搗き打ち】
うすつき‐うた【臼搗き唄】
臼を杵でつきながら唄う労働唄。
⇒うす‐つき【臼搗き】
うすつき‐うち【臼搗き打ち】
杵で臼をつくように、ふりあげてうちおろすこと。浄瑠璃、日本振袖始「―に打つ鋤が、余つて向うへ越す処が」
⇒うす‐つき【臼搗き】
うす‐づきよ【薄月夜】
月の光のほのかにさす夜。おぼろづきよ。
うす‐づ・く【臼づく・舂く】
〔自四〕
①臼に物を入れて杵きねでつく。
②夕日が山に入ろうとする。父の終焉日記「かく日も壁際に―・き、飯時にもならんとするころ」
うず‐つ・くウヅツク
〔自四〕
ぐずぐずする。ぐずつく。浮世草子、世間手代気質「一生秀でずに―・いて居ようとは」
うす‐づくり【薄造り・薄作り】
刺身で、ごく薄くそぎ切りにしたもの。フグ・ヒラメなどに適する。
うすっ‐ぺら【薄っぺら】
薄くぺらぺらしていること。転じて、物の見方や人柄が奥深くないこと。浅薄。「―な用紙」「―な人間」
うす‐で【薄手】
①紙・織物・陶器などの地の薄いこと。「―の茶碗」↔厚手あつで。
②安っぽいこと。浅薄なこと。「―な内容の本」
③軽いきず。浅手。「―を負う」↔深手
うず‐ていこう【渦抵抗】ウヅ‥カウ
物体が流体中を進むとき、物体の形状が完全な流線型でない部分に生じる渦によって発生する抵抗。
うず‐でんりゅう【渦電流】ウヅ‥リウ
変化している磁場中の導体内に、電磁誘導によって流れる渦巻状の電流。渦動かどう電流。フーコー電流。
 ⇒うすき【臼杵】
うす‐ぎたな・い【薄穢い・薄汚い】
〔形〕
なんとなくきたない。「―・い下着」「―・いやり方」
うす‐ぎぬ【薄衣】
地の薄いきもの。薄ごろも。
うす‐ぎぬ【薄帛・薄絹】
地の薄い絹織物。紗しゃ・絽ろなど。
うす‐きね【臼杵】
子供の遊戯の一つ。枕木の上に長い板を横たえ、板の両端に一人ずつ向かい合って立ち、交互に両端を踏んで上下するもの。互いに臼をつく杵のようになるからいう。シーソー。
うす‐きみわる・い【薄気味悪い】
〔形〕
なんとなく気味がわるい。「暗くて―・い部屋だ」
うす‐ぎり【薄切り】
食品を薄く切ること。薄く切ったもの。「ハムの―」
うす‐ぎり【薄霧】
薄くかかった霧。
うす‐きりふ【薄切斑】
斑ふの色の薄い切斑の矢羽。→切斑
うす‐ぎ・る【薄霧る】
〔自四〕
薄く霧が立ちこめる。風雅和歌集冬「あさけの山は―・りて」
うず・く【疼く】ウヅク
〔自五〕
ずきずき痛む。発心集「切り焼くがごとく―・きひびらき」。「傷が―・く」「胸が―・く」
うす‐くち【薄口】
①吸物や煮物などの料理の味付けが薄めのもの。「―に煮る」
②薄口醤油の略。↔濃口こいくち。
③陶器などで、薄手に仕上げてあるもの。「―の茶碗」
⇒うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】
うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】‥シヤウ‥
色が薄い醤油。味・香りともにあっさりしているが、塩分は多く含む。関西で多く使用。↔濃口醤油
⇒うす‐くち【薄口】
うずくまる【蹲】ウヅクマル
(人のうずくまったような形から)掛花入れの一種。信楽しがらきなどの小壺で、元来は室町時代から農家の豆入・茶壺として造られた。
うずくま・る【蹲る・踞る】
〔自五〕
(室町時代以後、仮名表記はウヅクマル)
①体を丸くして膝を折り腰を落とす。しゃがむ。〈日本霊異記下訓釈〉。「道端に―・る」
②獣などが前肢を折って地面に腹をつけてすわる。
うすくも【薄雲】
平家重代の鎧よろいの一つ。
うす‐ぐも【薄雲】
①薄くかかった雲。
薄雲
撮影:高橋健司
⇒うすき【臼杵】
うす‐ぎたな・い【薄穢い・薄汚い】
〔形〕
なんとなくきたない。「―・い下着」「―・いやり方」
うす‐ぎぬ【薄衣】
地の薄いきもの。薄ごろも。
うす‐ぎぬ【薄帛・薄絹】
地の薄い絹織物。紗しゃ・絽ろなど。
うす‐きね【臼杵】
子供の遊戯の一つ。枕木の上に長い板を横たえ、板の両端に一人ずつ向かい合って立ち、交互に両端を踏んで上下するもの。互いに臼をつく杵のようになるからいう。シーソー。
うす‐きみわる・い【薄気味悪い】
〔形〕
なんとなく気味がわるい。「暗くて―・い部屋だ」
うす‐ぎり【薄切り】
食品を薄く切ること。薄く切ったもの。「ハムの―」
うす‐ぎり【薄霧】
薄くかかった霧。
うす‐きりふ【薄切斑】
斑ふの色の薄い切斑の矢羽。→切斑
うす‐ぎ・る【薄霧る】
〔自四〕
薄く霧が立ちこめる。風雅和歌集冬「あさけの山は―・りて」
うず・く【疼く】ウヅク
〔自五〕
ずきずき痛む。発心集「切り焼くがごとく―・きひびらき」。「傷が―・く」「胸が―・く」
うす‐くち【薄口】
①吸物や煮物などの料理の味付けが薄めのもの。「―に煮る」
②薄口醤油の略。↔濃口こいくち。
③陶器などで、薄手に仕上げてあるもの。「―の茶碗」
⇒うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】
うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】‥シヤウ‥
色が薄い醤油。味・香りともにあっさりしているが、塩分は多く含む。関西で多く使用。↔濃口醤油
⇒うす‐くち【薄口】
うずくまる【蹲】ウヅクマル
(人のうずくまったような形から)掛花入れの一種。信楽しがらきなどの小壺で、元来は室町時代から農家の豆入・茶壺として造られた。
うずくま・る【蹲る・踞る】
〔自五〕
(室町時代以後、仮名表記はウヅクマル)
①体を丸くして膝を折り腰を落とす。しゃがむ。〈日本霊異記下訓釈〉。「道端に―・る」
②獣などが前肢を折って地面に腹をつけてすわる。
うすくも【薄雲】
平家重代の鎧よろいの一つ。
うす‐ぐも【薄雲】
①薄くかかった雲。
薄雲
撮影:高橋健司
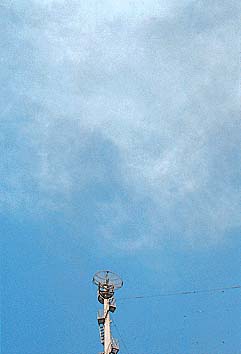 ②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】‥ヰン
源氏物語中の女性藤壺のこと。「薄雲」の巻にその崩御のことを記すからいう。
⇒うす‐ぐも【薄雲】
うす‐ぐもり【薄曇】
うっすらと曇ること。上層雲の多い曇り。
うず‐くら【雲珠鞍】
雲珠の飾りをつけた鞍。唐鞍からくら。
うす‐ぐら・い【薄暗い】
〔形〕[文]うすぐら・し(ク)
光が薄くて、まっくらではないが、暗い。ほのぐらい。「―・い部屋」
うす‐くらがり【薄暗がり】
少し暗いこと。また、その場所。「植込みの―に隠れる」
うす‐くりげ【薄栗毛】
馬の毛色の、黄色を帯びた栗毛で、たてがみの黒いもの。
うす‐ぐれ【薄暮れ】
夕方。うす暗くなるころ。〈日葡辞書〉
うす‐くれない【薄紅】‥クレナヰ
薄いくれない色。淡紅。
うす‐ぐろ・い【薄黒い】
〔形〕
少しばかり黒い。黒ずんでいる。
うす‐げしょう【薄化粧】‥シヤウ
あっさりと化粧すること。「―して外出する」「雪で―した山」↔厚化粧
うす‐けわい【薄粧】‥ケハヒ
うすげしょう。
うす‐こうばい【薄紅梅】
①紅梅の花の色の薄いもの。
②紅梅色の薄いもの。枕草子50「馬は…―の毛にて」
Munsell color system: 5RP7/8
③襲かさねの色目。紅梅襲の表裏とも薄いもの。
うす‐ごおり【薄氷】‥ゴホリ
①薄く張った氷。うすらひ。〈[季]春〉
②氷のひびのはいったさまに擬した模様。
うす‐こお・る【薄氷る】‥コホル
〔自四〕
薄く氷る。千載和歌集冬「岩間の水の―・るらむ」
うす‐こはく【薄琥珀】
絹織物の一つ。琥珀織の薄地のもの。タフタ。浜琥珀。
うす‐ざいしき【薄彩色】
薄く施した彩色。墨絵の上に藍・代赭たいしゃなどで薄く着色したもの。〈日葡辞書〉
うす‐ざくら【薄桜】
①桜の花の色のうすいもの。
②襲かさねの色目。表は白、裏は紅で、一重梅ひとえうめと異名同色。(蛙抄)
⇒うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
うず‐ざくら【雲珠桜】
①(「雲珠」は馬具。地名「鞍馬」との縁で)京都の鞍馬山に咲く桜の総称。
②いわゆるサトザクラの一種。花は紅色で重弁。
うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
襲かさねの色目。山科流では、表は薄青、裏も同じ、または薄紅。また、表は青、裏は蘇芳すおうとも。
⇒うす‐ざくら【薄桜】
うすさま‐みょうおう【烏枢沙摩明王】‥ミヤウワウ
(ウスシャマミョウオウとも。梵語Ucchuṣma 不浄潔・除穢と訳す)不浄を避けず衆生しゅじょうを救う徳を有するという明王。寺院の手洗いなどにまつられる。二臂・四臂・六臂のものがあり、忿怒ふんぬの相で、火焔に覆われる。烏芻沙摩明王。穢迹金剛えしゃくこんごう。火頭かず金剛。
うす‐さむ・い【薄寒い】
〔形〕[文]うすさむ・し(ク)
(主として明治期に用いた語)なんとなく寒い。少し寒く感じられる。うそさむい。
うす‐ざん【有珠山】
北海道南西部、洞爺とうや湖の南にある二重式活火山。標高733メートル。2000年に大規模な水蒸気爆発を観測。
有珠山と洞爺湖
撮影:新海良夫
②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】‥ヰン
源氏物語中の女性藤壺のこと。「薄雲」の巻にその崩御のことを記すからいう。
⇒うす‐ぐも【薄雲】
うす‐ぐもり【薄曇】
うっすらと曇ること。上層雲の多い曇り。
うず‐くら【雲珠鞍】
雲珠の飾りをつけた鞍。唐鞍からくら。
うす‐ぐら・い【薄暗い】
〔形〕[文]うすぐら・し(ク)
光が薄くて、まっくらではないが、暗い。ほのぐらい。「―・い部屋」
うす‐くらがり【薄暗がり】
少し暗いこと。また、その場所。「植込みの―に隠れる」
うす‐くりげ【薄栗毛】
馬の毛色の、黄色を帯びた栗毛で、たてがみの黒いもの。
うす‐ぐれ【薄暮れ】
夕方。うす暗くなるころ。〈日葡辞書〉
うす‐くれない【薄紅】‥クレナヰ
薄いくれない色。淡紅。
うす‐ぐろ・い【薄黒い】
〔形〕
少しばかり黒い。黒ずんでいる。
うす‐げしょう【薄化粧】‥シヤウ
あっさりと化粧すること。「―して外出する」「雪で―した山」↔厚化粧
うす‐けわい【薄粧】‥ケハヒ
うすげしょう。
うす‐こうばい【薄紅梅】
①紅梅の花の色の薄いもの。
②紅梅色の薄いもの。枕草子50「馬は…―の毛にて」
Munsell color system: 5RP7/8
③襲かさねの色目。紅梅襲の表裏とも薄いもの。
うす‐ごおり【薄氷】‥ゴホリ
①薄く張った氷。うすらひ。〈[季]春〉
②氷のひびのはいったさまに擬した模様。
うす‐こお・る【薄氷る】‥コホル
〔自四〕
薄く氷る。千載和歌集冬「岩間の水の―・るらむ」
うす‐こはく【薄琥珀】
絹織物の一つ。琥珀織の薄地のもの。タフタ。浜琥珀。
うす‐ざいしき【薄彩色】
薄く施した彩色。墨絵の上に藍・代赭たいしゃなどで薄く着色したもの。〈日葡辞書〉
うす‐ざくら【薄桜】
①桜の花の色のうすいもの。
②襲かさねの色目。表は白、裏は紅で、一重梅ひとえうめと異名同色。(蛙抄)
⇒うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
うず‐ざくら【雲珠桜】
①(「雲珠」は馬具。地名「鞍馬」との縁で)京都の鞍馬山に咲く桜の総称。
②いわゆるサトザクラの一種。花は紅色で重弁。
うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
襲かさねの色目。山科流では、表は薄青、裏も同じ、または薄紅。また、表は青、裏は蘇芳すおうとも。
⇒うす‐ざくら【薄桜】
うすさま‐みょうおう【烏枢沙摩明王】‥ミヤウワウ
(ウスシャマミョウオウとも。梵語Ucchuṣma 不浄潔・除穢と訳す)不浄を避けず衆生しゅじょうを救う徳を有するという明王。寺院の手洗いなどにまつられる。二臂・四臂・六臂のものがあり、忿怒ふんぬの相で、火焔に覆われる。烏芻沙摩明王。穢迹金剛えしゃくこんごう。火頭かず金剛。
うす‐さむ・い【薄寒い】
〔形〕[文]うすさむ・し(ク)
(主として明治期に用いた語)なんとなく寒い。少し寒く感じられる。うそさむい。
うす‐ざん【有珠山】
北海道南西部、洞爺とうや湖の南にある二重式活火山。標高733メートル。2000年に大規模な水蒸気爆発を観測。
有珠山と洞爺湖
撮影:新海良夫
 うす・し【薄し・淡し】
〔形ク〕
⇒うすい
うす‐じ【薄地】‥ヂ
織地や金属などの薄いもの。
うす‐じお【薄塩】‥ジホ
塩加減の薄いこと。また、薄い塩加減に調理してあること。甘塩。日葡辞書「ウスジヲノウヲ」
うず‐しお【渦潮】ウヅシホ
渦巻く潮流。万葉集15「名に負ふ鳴門の―に」
うす‐じき【薄敷】
取引所規定よりも少額の証拠金。もぐりの仲買人が、この証拠金を取って、取引所の相場を標準に一種の賭博行為をなすことをいう。薄張り。
うす‐したじ【薄下地】‥ヂ
塩加減を薄くした醤油。上方料理に用いる。浮世風呂2「―で吸物ぢやさかい」
うす‐じも【薄霜】
薄く降りた霜。
うずじょう‐ぎんが【渦状銀河】ウヅジヤウ‥
(→)渦巻うずまき銀河に同じ。
うす‐じり【薄知り】
うすうす事情を知っていること。狂言、花子「例の山の神が、―に知つて」
うす‐じろ【薄白】
和紙の名。室町時代に美濃で産した薄くて白い楮紙こうぞがみ。
うす‐じろ・い【薄白い】
〔形〕[文]うすじろ・し(ク)
(色がさめて)白っぽい。讃岐典侍日記「尾花の―・くなりて招きたちて見ゆるが」
うすす・く
〔自四〕
心がおちつかない。あわてる。驚き騒ぐ。源氏物語槿「御門守…―・き出で来てとみにもえ開けやらず」→いすすく
うず‐すま・る
〔自四〕
うずくまり集まる。古事記下「大宮人は…庭すずめ―・りゐて」
うす‐ずみ【薄墨】
①墨の色の薄いもの。源氏物語少女「まぎらはし書いたる濃墨こずみ・―、草がちにうちまぜ乱れたるも」
②薄墨紙の略。後拾遺和歌集春「―にかく玉づさと見ゆるかな」
③(女房詞)そばのかゆ。そばがき。
⇒うすずみ‐いろ【薄墨色】
⇒うすずみ‐がみ【薄墨紙】
⇒うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
⇒うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
⇒うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
うすずみ‐いろ【薄墨色】
墨色の薄いもの。ねずみ色。
Munsell color system: N6.1
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐がみ【薄墨紙】
反故ほごの墨色が十分に脱けずに残った、薄いねずみ色のすきがえし紙。平安末期から京都紙屋院かみやいんで作り、鎌倉時代からは綸旨りんじを書くのにも用いた。宿紙しゅくし。→紙屋紙かみやがみ。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
薄墨色に染めた衣。喪服用。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
①サトザクラの一品種。芽は緑色、花は白く一重咲きで直径4〜5センチメートル。
②(「淡墨桜」と書く)岐阜県本巣市根尾にあるエドヒガンの巨木。天然記念物。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
薄墨紙を用いた綸旨。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うす‐ず・む【薄ずむ】
〔自四〕
薄く黒ずんで見える。薄くかすんで見える。夫木和歌抄13「朝霧のそことしるしはなけれども―・み渡る三輪の杉むら」
うす‐ずり【薄摺】
薄い色に摺って染めること。
うす‐ぞめ【薄染】
色を薄く染めること。
⇒うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
薄い色に染めた衣服。万葉集12「くれなゐの―浅らかに」
⇒うす‐ぞめ【薄染】
ウスター‐ソース
(Worcestershire sauce)西洋料理の調味料で、日本で普通ソースと呼んでいるもの。各種の野菜・果実・香辛料・調味料を原料とする。イングランド中部のウスターで最初に作られ、19世紀末頃渡来。
うす‐だいこ【臼太鼓】
宮崎・大分・熊本などで行われる太鼓踊の一種。幟のぼりを負い音頭の唄につれ、鉦かね・笛を交える青年の勇壮な民俗舞踊。臼太鼓踊。
うず‐たか・い【堆い】ウヅタカイ
〔形〕[文]うづたか・し(ク)
(古くは清音。ウズダカシとも)もりあがって高い。積もって高い。平家物語8「飯はん―・くよそひ」。「書類を―・く積む」
うす‐たけ【臼茸】
担子菌類のきのこ。夏から秋に針葉樹林下に生じ、高さ約10センチメートル。漏斗状で中央は深い穴となり、黄褐色。外側は淡色で柄と傘との区別が明らかでない。〈易林本節用集〉
うす‐だたみ【薄畳】
昔、春・夏に用いた薄い畳。うすべり。
うすたび‐が【薄手火蛾・薄足袋蛾】
ヤママユガ科のガ。体も翅も橙褐色ないし黄褐色で、前後翅に各1個の円い半透明な紋がある。開張は約10センチメートル。幼虫はクリ・クヌギ・ケヤキ・サクラ・カエデなどを食い、成虫は秋に出現。繭は山叺やまかますなどと俗称。
ウスタビガ
撮影:海野和男
うす・し【薄し・淡し】
〔形ク〕
⇒うすい
うす‐じ【薄地】‥ヂ
織地や金属などの薄いもの。
うす‐じお【薄塩】‥ジホ
塩加減の薄いこと。また、薄い塩加減に調理してあること。甘塩。日葡辞書「ウスジヲノウヲ」
うず‐しお【渦潮】ウヅシホ
渦巻く潮流。万葉集15「名に負ふ鳴門の―に」
うす‐じき【薄敷】
取引所規定よりも少額の証拠金。もぐりの仲買人が、この証拠金を取って、取引所の相場を標準に一種の賭博行為をなすことをいう。薄張り。
うす‐したじ【薄下地】‥ヂ
塩加減を薄くした醤油。上方料理に用いる。浮世風呂2「―で吸物ぢやさかい」
うす‐じも【薄霜】
薄く降りた霜。
うずじょう‐ぎんが【渦状銀河】ウヅジヤウ‥
(→)渦巻うずまき銀河に同じ。
うす‐じり【薄知り】
うすうす事情を知っていること。狂言、花子「例の山の神が、―に知つて」
うす‐じろ【薄白】
和紙の名。室町時代に美濃で産した薄くて白い楮紙こうぞがみ。
うす‐じろ・い【薄白い】
〔形〕[文]うすじろ・し(ク)
(色がさめて)白っぽい。讃岐典侍日記「尾花の―・くなりて招きたちて見ゆるが」
うすす・く
〔自四〕
心がおちつかない。あわてる。驚き騒ぐ。源氏物語槿「御門守…―・き出で来てとみにもえ開けやらず」→いすすく
うず‐すま・る
〔自四〕
うずくまり集まる。古事記下「大宮人は…庭すずめ―・りゐて」
うす‐ずみ【薄墨】
①墨の色の薄いもの。源氏物語少女「まぎらはし書いたる濃墨こずみ・―、草がちにうちまぜ乱れたるも」
②薄墨紙の略。後拾遺和歌集春「―にかく玉づさと見ゆるかな」
③(女房詞)そばのかゆ。そばがき。
⇒うすずみ‐いろ【薄墨色】
⇒うすずみ‐がみ【薄墨紙】
⇒うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
⇒うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
⇒うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
うすずみ‐いろ【薄墨色】
墨色の薄いもの。ねずみ色。
Munsell color system: N6.1
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐がみ【薄墨紙】
反故ほごの墨色が十分に脱けずに残った、薄いねずみ色のすきがえし紙。平安末期から京都紙屋院かみやいんで作り、鎌倉時代からは綸旨りんじを書くのにも用いた。宿紙しゅくし。→紙屋紙かみやがみ。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ごろも【薄墨衣】
薄墨色に染めた衣。喪服用。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐ざくら【薄墨桜】
①サトザクラの一品種。芽は緑色、花は白く一重咲きで直径4〜5センチメートル。
②(「淡墨桜」と書く)岐阜県本巣市根尾にあるエドヒガンの巨木。天然記念物。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うすずみ‐の‐りんじ【薄墨の綸旨】
薄墨紙を用いた綸旨。
⇒うす‐ずみ【薄墨】
うす‐ず・む【薄ずむ】
〔自四〕
薄く黒ずんで見える。薄くかすんで見える。夫木和歌抄13「朝霧のそことしるしはなけれども―・み渡る三輪の杉むら」
うす‐ずり【薄摺】
薄い色に摺って染めること。
うす‐ぞめ【薄染】
色を薄く染めること。
⇒うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
うすぞめ‐ごろも【薄染衣】
薄い色に染めた衣服。万葉集12「くれなゐの―浅らかに」
⇒うす‐ぞめ【薄染】
ウスター‐ソース
(Worcestershire sauce)西洋料理の調味料で、日本で普通ソースと呼んでいるもの。各種の野菜・果実・香辛料・調味料を原料とする。イングランド中部のウスターで最初に作られ、19世紀末頃渡来。
うす‐だいこ【臼太鼓】
宮崎・大分・熊本などで行われる太鼓踊の一種。幟のぼりを負い音頭の唄につれ、鉦かね・笛を交える青年の勇壮な民俗舞踊。臼太鼓踊。
うず‐たか・い【堆い】ウヅタカイ
〔形〕[文]うづたか・し(ク)
(古くは清音。ウズダカシとも)もりあがって高い。積もって高い。平家物語8「飯はん―・くよそひ」。「書類を―・く積む」
うす‐たけ【臼茸】
担子菌類のきのこ。夏から秋に針葉樹林下に生じ、高さ約10センチメートル。漏斗状で中央は深い穴となり、黄褐色。外側は淡色で柄と傘との区別が明らかでない。〈易林本節用集〉
うす‐だたみ【薄畳】
昔、春・夏に用いた薄い畳。うすべり。
うすたび‐が【薄手火蛾・薄足袋蛾】
ヤママユガ科のガ。体も翅も橙褐色ないし黄褐色で、前後翅に各1個の円い半透明な紋がある。開張は約10センチメートル。幼虫はクリ・クヌギ・ケヤキ・サクラ・カエデなどを食い、成虫は秋に出現。繭は山叺やまかますなどと俗称。
ウスタビガ
撮影:海野和男
 うす‐だま【臼玉】
古墳時代の遺物の一種。管玉くだたまを短く切ったような臼形の祭祀・装身用の玉。滑石かっせき製が普通。
うす‐だみ【薄彩み】
薄くいろどること。日葡辞書「ウスダミノエ」
うす‐だ・む【薄彩む】
〔他四〕
薄くいろどる。正治百首「―・みわたる夕霞かな」
うす‐だん【薄緂】
白地に薄紫にいろどった緂だん。源氏物語若菜上「御手書かせ給へる唐の綾の―に」
うす‐ちゃ【薄茶】
①点茶の時、抹茶の分量を少なくしてたてるもの。おうす。↔濃茶こいちゃ。
②薄茶色の略。茶色のうすいもの。
⇒うすちゃ‐き【薄茶器】
⇒うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】
うすちゃ‐き【薄茶器】
茶道具の一種。薄茶をたてるとき、抹茶を入れておく容器。主に漆塗りの棗なつめなど。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】‥マヘ
薄茶をたてる作法。漆器の棗なつめ・茶碗・茶杓・茶筅ちゃせん・建水けんすい・柄杓ひしゃくなどを用い、一人ずつにたてる。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うす‐ちり【薄塵】
蒔絵まきえに金粉を薄く散らしたもの。
うす‐つき【臼搗き】
臼に物を入れて杵きねでつくこと。
⇒うすつき‐うた【臼搗き唄】
⇒うすつき‐うち【臼搗き打ち】
うすつき‐うた【臼搗き唄】
臼を杵でつきながら唄う労働唄。
⇒うす‐つき【臼搗き】
うすつき‐うち【臼搗き打ち】
杵で臼をつくように、ふりあげてうちおろすこと。浄瑠璃、日本振袖始「―に打つ鋤が、余つて向うへ越す処が」
⇒うす‐つき【臼搗き】
うす‐づきよ【薄月夜】
月の光のほのかにさす夜。おぼろづきよ。
うす‐づ・く【臼づく・舂く】
〔自四〕
①臼に物を入れて杵きねでつく。
②夕日が山に入ろうとする。父の終焉日記「かく日も壁際に―・き、飯時にもならんとするころ」
うず‐つ・くウヅツク
〔自四〕
ぐずぐずする。ぐずつく。浮世草子、世間手代気質「一生秀でずに―・いて居ようとは」
うす‐づくり【薄造り・薄作り】
刺身で、ごく薄くそぎ切りにしたもの。フグ・ヒラメなどに適する。
うすっ‐ぺら【薄っぺら】
薄くぺらぺらしていること。転じて、物の見方や人柄が奥深くないこと。浅薄。「―な用紙」「―な人間」
うす‐で【薄手】
①紙・織物・陶器などの地の薄いこと。「―の茶碗」↔厚手あつで。
②安っぽいこと。浅薄なこと。「―な内容の本」
③軽いきず。浅手。「―を負う」↔深手
うず‐ていこう【渦抵抗】ウヅ‥カウ
物体が流体中を進むとき、物体の形状が完全な流線型でない部分に生じる渦によって発生する抵抗。
うず‐でんりゅう【渦電流】ウヅ‥リウ
変化している磁場中の導体内に、電磁誘導によって流れる渦巻状の電流。渦動かどう電流。フーコー電流。
うす‐だま【臼玉】
古墳時代の遺物の一種。管玉くだたまを短く切ったような臼形の祭祀・装身用の玉。滑石かっせき製が普通。
うす‐だみ【薄彩み】
薄くいろどること。日葡辞書「ウスダミノエ」
うす‐だ・む【薄彩む】
〔他四〕
薄くいろどる。正治百首「―・みわたる夕霞かな」
うす‐だん【薄緂】
白地に薄紫にいろどった緂だん。源氏物語若菜上「御手書かせ給へる唐の綾の―に」
うす‐ちゃ【薄茶】
①点茶の時、抹茶の分量を少なくしてたてるもの。おうす。↔濃茶こいちゃ。
②薄茶色の略。茶色のうすいもの。
⇒うすちゃ‐き【薄茶器】
⇒うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】
うすちゃ‐き【薄茶器】
茶道具の一種。薄茶をたてるとき、抹茶を入れておく容器。主に漆塗りの棗なつめなど。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うすちゃ‐てまえ【薄茶手前】‥マヘ
薄茶をたてる作法。漆器の棗なつめ・茶碗・茶杓・茶筅ちゃせん・建水けんすい・柄杓ひしゃくなどを用い、一人ずつにたてる。
⇒うす‐ちゃ【薄茶】
うす‐ちり【薄塵】
蒔絵まきえに金粉を薄く散らしたもの。
うす‐つき【臼搗き】
臼に物を入れて杵きねでつくこと。
⇒うすつき‐うた【臼搗き唄】
⇒うすつき‐うち【臼搗き打ち】
うすつき‐うた【臼搗き唄】
臼を杵でつきながら唄う労働唄。
⇒うす‐つき【臼搗き】
うすつき‐うち【臼搗き打ち】
杵で臼をつくように、ふりあげてうちおろすこと。浄瑠璃、日本振袖始「―に打つ鋤が、余つて向うへ越す処が」
⇒うす‐つき【臼搗き】
うす‐づきよ【薄月夜】
月の光のほのかにさす夜。おぼろづきよ。
うす‐づ・く【臼づく・舂く】
〔自四〕
①臼に物を入れて杵きねでつく。
②夕日が山に入ろうとする。父の終焉日記「かく日も壁際に―・き、飯時にもならんとするころ」
うず‐つ・くウヅツク
〔自四〕
ぐずぐずする。ぐずつく。浮世草子、世間手代気質「一生秀でずに―・いて居ようとは」
うす‐づくり【薄造り・薄作り】
刺身で、ごく薄くそぎ切りにしたもの。フグ・ヒラメなどに適する。
うすっ‐ぺら【薄っぺら】
薄くぺらぺらしていること。転じて、物の見方や人柄が奥深くないこと。浅薄。「―な用紙」「―な人間」
うす‐で【薄手】
①紙・織物・陶器などの地の薄いこと。「―の茶碗」↔厚手あつで。
②安っぽいこと。浅薄なこと。「―な内容の本」
③軽いきず。浅手。「―を負う」↔深手
うず‐ていこう【渦抵抗】ウヅ‥カウ
物体が流体中を進むとき、物体の形状が完全な流線型でない部分に生じる渦によって発生する抵抗。
うず‐でんりゅう【渦電流】ウヅ‥リウ
変化している磁場中の導体内に、電磁誘導によって流れる渦巻状の電流。渦動かどう電流。フーコー電流。
広辞苑 ページ 1771 での【○臼から杵】単語。