複数辞典一括検索+![]()
![]()
○世と共よととも🔗⭐🔉
○世と共よととも
つね日ごろ。つねづね。源氏物語匂宮「かたはらいたき筋なれば―の心にかけて」
⇒よ【世・代】
よど‐ぬい【淀縫】‥ヌヒ
(山城の淀で作り出したからいう)革の裁ち余りの小片に模様などの縫取りをしたもの。タバコ入れ・巾着きんちゃくなどに用いる。
よ‐どの【夜殿】
夜、寝る殿舎。寝所。寝室。ねや。後撰和歌集恋「君が―に夜離がれせましや」
よどのかわせ【淀の川瀬】‥カハ‥
端唄・うた沢。伏見と大坂とを結ぶ三十石船と沿岸の水車をうたう。上方舞の地じにも用いる。
よど‐の‐くもん【四度の公文】
⇒しどのくもん
よど‐の‐つかい【四度使】‥ツカヒ
⇒しどのつかい
よど‐の‐へい【四度幣】
⇒しどのかんぺい(四度官幣)
よどばし【淀橋】
①もと東京都新宿区の一地区。東は新宿の繁華街に接し、青梅街道が東西に貫通。浄水場の跡地に都庁が移転。この地区を中心に新宿新都心と俗に呼ばれる超高層ビル群を形成。
淀橋浄水場(1952年撮影)
提供:東京都
 ②もと東京市35区の一つ。
よど‐ぶね【淀舟】
淀川を通う舟。
よ‐どまり【夜泊り】
夜、外泊すること。〈日葡辞書〉
よどみ【淀・澱】
①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」
②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」
③液体の下方に沈んでたまったもの。
よど・む【淀む・澱む】
〔自五〕
①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」
②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」
③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」
④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」
⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」
よどや【淀屋】
江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。
⇒よどや‐がわ【淀屋革】
⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】
よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ
(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。
⇒よどや【淀屋】
よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ
江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)
⇒よどや【淀屋】
よ‐とり【世取】
あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」
よど・る
〔自四〕
(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」
よど・る
〔他四〕
あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」
よ‐ど・る【夜取る】
〔自四〕
騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」
よな
火山灰のこと。
よな【米】
「よね」の古形。「―ぐら」
ヨナ【Jonah】
旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。
よ‐な
〔助詞〕
(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」
よない【米内】
姓氏の一つ。
⇒よない‐みつまさ【米内光政】
よ‐ない【余内・余荷】
江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。
よない‐みつまさ【米内光政】
軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)
米内光政
提供:毎日新聞社
②もと東京市35区の一つ。
よど‐ぶね【淀舟】
淀川を通う舟。
よ‐どまり【夜泊り】
夜、外泊すること。〈日葡辞書〉
よどみ【淀・澱】
①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」
②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」
③液体の下方に沈んでたまったもの。
よど・む【淀む・澱む】
〔自五〕
①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」
②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」
③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」
④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」
⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」
よどや【淀屋】
江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。
⇒よどや‐がわ【淀屋革】
⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】
よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ
(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。
⇒よどや【淀屋】
よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ
江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)
⇒よどや【淀屋】
よ‐とり【世取】
あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」
よど・る
〔自四〕
(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」
よど・る
〔他四〕
あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」
よ‐ど・る【夜取る】
〔自四〕
騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」
よな
火山灰のこと。
よな【米】
「よね」の古形。「―ぐら」
ヨナ【Jonah】
旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。
よ‐な
〔助詞〕
(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」
よない【米内】
姓氏の一つ。
⇒よない‐みつまさ【米内光政】
よ‐ない【余内・余荷】
江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。
よない‐みつまさ【米内光政】
軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)
米内光政
提供:毎日新聞社
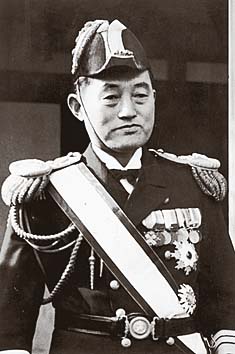 ⇒よない【米内】
よ‐なおし【世直し】‥ナホシ
①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」
②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」
③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。
⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】
よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥
幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか
⇒よ‐なおし【世直し】
よ‐なか【夜中】
夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。
よ‐なが【夜長】
①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」
②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。
よ‐ながり【夜ながり】
夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」
よ‐なき【夜泣き】
乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。
⇒よなき‐いし【夜泣石】
よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
鳥などが夜鳴くこと。
⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】
⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
よ‐なぎ【夜凪】
夜、風がやんで波が穏やかになること。
よなき‐いし【夜泣石】
夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。
⇒よ‐なき【夜泣き】
よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス
ナイチンゲールの異称。
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よな・ぐ【淘ぐ】
〔他下二〕
⇒よなげる(下一)
よなぐに‐さん【与那国蚕】
チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。
よなぐにさん
⇒よない【米内】
よ‐なおし【世直し】‥ナホシ
①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」
②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」
③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。
⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】
よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥
幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか
⇒よ‐なおし【世直し】
よ‐なか【夜中】
夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。
よ‐なが【夜長】
①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」
②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。
よ‐ながり【夜ながり】
夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」
よ‐なき【夜泣き】
乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。
⇒よなき‐いし【夜泣石】
よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
鳥などが夜鳴くこと。
⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】
⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
よ‐なぎ【夜凪】
夜、風がやんで波が穏やかになること。
よなき‐いし【夜泣石】
夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。
⇒よ‐なき【夜泣き】
よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス
ナイチンゲールの異称。
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よな・ぐ【淘ぐ】
〔他下二〕
⇒よなげる(下一)
よなぐに‐さん【与那国蚕】
チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。
よなぐにさん
 ヨナグニサン
撮影:湊 和雄
ヨナグニサン
撮影:湊 和雄
 よなぐに‐じま【与那国島】
沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。
よな‐ぐら【米蔵】
(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉
よなげ‐や【淘屋】
川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。
よな・げる【淘げる】
〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)
①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。
②細かい物などを水に入れて淘り分ける。
③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。
よなご【米子】
鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。
よなどり
(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。
よ‐なべ【夜鍋】
(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」
よ‐なみ【世並】
①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」
②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」
よな‐むし【米虫】
コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉
よな‐よな【夜な夜な】
〔副〕
夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」
よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ
世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」
よ‐ならべ‐て【夜並べて】
毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」
よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】
〔自下一〕[文]よな・る(下二)
①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」
②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」
よ‐なん【余難】
そのほかの災難。また、後に残る難儀。
よ‐に【世に】
〔副〕
①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」
②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13
よなぐに‐じま【与那国島】
沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。
よな‐ぐら【米蔵】
(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉
よなげ‐や【淘屋】
川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。
よな・げる【淘げる】
〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)
①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。
②細かい物などを水に入れて淘り分ける。
③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。
よなご【米子】
鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。
よなどり
(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。
よ‐なべ【夜鍋】
(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」
よ‐なみ【世並】
①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」
②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」
よな‐むし【米虫】
コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉
よな‐よな【夜な夜な】
〔副〕
夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」
よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ
世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」
よ‐ならべ‐て【夜並べて】
毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」
よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】
〔自下一〕[文]よな・る(下二)
①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」
②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」
よ‐なん【余難】
そのほかの災難。また、後に残る難儀。
よ‐に【世に】
〔副〕
①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」
②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13
 ②もと東京市35区の一つ。
よど‐ぶね【淀舟】
淀川を通う舟。
よ‐どまり【夜泊り】
夜、外泊すること。〈日葡辞書〉
よどみ【淀・澱】
①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」
②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」
③液体の下方に沈んでたまったもの。
よど・む【淀む・澱む】
〔自五〕
①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」
②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」
③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」
④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」
⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」
よどや【淀屋】
江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。
⇒よどや‐がわ【淀屋革】
⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】
よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ
(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。
⇒よどや【淀屋】
よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ
江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)
⇒よどや【淀屋】
よ‐とり【世取】
あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」
よど・る
〔自四〕
(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」
よど・る
〔他四〕
あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」
よ‐ど・る【夜取る】
〔自四〕
騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」
よな
火山灰のこと。
よな【米】
「よね」の古形。「―ぐら」
ヨナ【Jonah】
旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。
よ‐な
〔助詞〕
(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」
よない【米内】
姓氏の一つ。
⇒よない‐みつまさ【米内光政】
よ‐ない【余内・余荷】
江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。
よない‐みつまさ【米内光政】
軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)
米内光政
提供:毎日新聞社
②もと東京市35区の一つ。
よど‐ぶね【淀舟】
淀川を通う舟。
よ‐どまり【夜泊り】
夜、外泊すること。〈日葡辞書〉
よどみ【淀・澱】
①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」
②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」
③液体の下方に沈んでたまったもの。
よど・む【淀む・澱む】
〔自五〕
①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」
②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」
③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」
④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」
⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」
よどや【淀屋】
江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。
⇒よどや‐がわ【淀屋革】
⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】
よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ
(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。
⇒よどや【淀屋】
よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ
江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)
⇒よどや【淀屋】
よ‐とり【世取】
あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」
よど・る
〔自四〕
(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」
よど・る
〔他四〕
あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」
よ‐ど・る【夜取る】
〔自四〕
騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」
よな
火山灰のこと。
よな【米】
「よね」の古形。「―ぐら」
ヨナ【Jonah】
旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。
よ‐な
〔助詞〕
(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」
よない【米内】
姓氏の一つ。
⇒よない‐みつまさ【米内光政】
よ‐ない【余内・余荷】
江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。
よない‐みつまさ【米内光政】
軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)
米内光政
提供:毎日新聞社
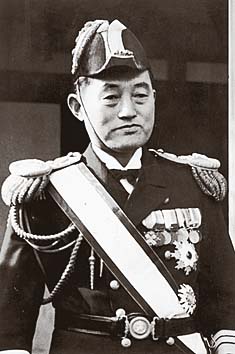 ⇒よない【米内】
よ‐なおし【世直し】‥ナホシ
①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」
②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」
③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。
⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】
よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥
幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか
⇒よ‐なおし【世直し】
よ‐なか【夜中】
夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。
よ‐なが【夜長】
①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」
②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。
よ‐ながり【夜ながり】
夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」
よ‐なき【夜泣き】
乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。
⇒よなき‐いし【夜泣石】
よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
鳥などが夜鳴くこと。
⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】
⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
よ‐なぎ【夜凪】
夜、風がやんで波が穏やかになること。
よなき‐いし【夜泣石】
夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。
⇒よ‐なき【夜泣き】
よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス
ナイチンゲールの異称。
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よな・ぐ【淘ぐ】
〔他下二〕
⇒よなげる(下一)
よなぐに‐さん【与那国蚕】
チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。
よなぐにさん
⇒よない【米内】
よ‐なおし【世直し】‥ナホシ
①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」
②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」
③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。
⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】
よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥
幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか
⇒よ‐なおし【世直し】
よ‐なか【夜中】
夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。
よ‐なが【夜長】
①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」
②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。
よ‐ながり【夜ながり】
夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」
よ‐なき【夜泣き】
乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。
⇒よなき‐いし【夜泣石】
よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
鳥などが夜鳴くこと。
⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】
⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
よ‐なぎ【夜凪】
夜、風がやんで波が穏やかになること。
よなき‐いし【夜泣石】
夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。
⇒よ‐なき【夜泣き】
よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス
ナイチンゲールの異称。
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐うどん【夜鳴饂飩】
夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よなき‐そば【夜鳴蕎麦】
(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】
よな・ぐ【淘ぐ】
〔他下二〕
⇒よなげる(下一)
よなぐに‐さん【与那国蚕】
チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。
よなぐにさん
 ヨナグニサン
撮影:湊 和雄
ヨナグニサン
撮影:湊 和雄
 よなぐに‐じま【与那国島】
沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。
よな‐ぐら【米蔵】
(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉
よなげ‐や【淘屋】
川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。
よな・げる【淘げる】
〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)
①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。
②細かい物などを水に入れて淘り分ける。
③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。
よなご【米子】
鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。
よなどり
(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。
よ‐なべ【夜鍋】
(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」
よ‐なみ【世並】
①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」
②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」
よな‐むし【米虫】
コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉
よな‐よな【夜な夜な】
〔副〕
夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」
よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ
世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」
よ‐ならべ‐て【夜並べて】
毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」
よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】
〔自下一〕[文]よな・る(下二)
①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」
②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」
よ‐なん【余難】
そのほかの災難。また、後に残る難儀。
よ‐に【世に】
〔副〕
①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」
②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13
よなぐに‐じま【与那国島】
沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。
よな‐ぐら【米蔵】
(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉
よなげ‐や【淘屋】
川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。
よな・げる【淘げる】
〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)
①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。
②細かい物などを水に入れて淘り分ける。
③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。
よなご【米子】
鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。
よなどり
(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。
よ‐なべ【夜鍋】
(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」
よ‐なみ【世並】
①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」
②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」
よな‐むし【米虫】
コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉
よな‐よな【夜な夜な】
〔副〕
夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」
よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ
世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」
よ‐ならべ‐て【夜並べて】
毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」
よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】
〔自下一〕[文]よな・る(下二)
①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」
②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」
よ‐なん【余難】
そのほかの災難。また、後に残る難儀。
よ‐に【世に】
〔副〕
①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」
②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13
広辞苑 ページ 20327 での【○世と共】単語。