複数辞典一括検索+![]()
![]()
○和を以て貴しと為すわをもってとうとしとなす🔗⭐🔉
○和を以て貴しと為すわをもってとうとしとなす
(聖徳太子の憲法十七条第1条として有名)他人との調和が大事であるということ。
⇒わ【和】
わん
犬の吠える声。
わん【椀】
①汁・飯などを盛る木製の食器。多く漆塗で蓋がある。→わん(碗・埦)。
②「椀盛り」の略。
③椀に盛った飲食物を数える語。
わん【湾】
海水や湖水が陸地に大きく入り込んだところ。入江。いりうみ。
わん【碗・埦】
(漆器の「椀」と区別して用いる字)飯・汁などを盛る陶磁器の食器。
ワン【one】
1。ひとつ。
ワン【WAN】
(wide area network)LAN(ラン)よりも広域にわたるコンピューター‐ネットワーク。
ワン‐ウェー【one-way】
①一方通行。片道。「―‐チケット」
②メーカーが回収しない容器や包装。また、そのような容器の使用方法。使い捨て。
わん‐かぐ【椀家具】
①椀・膳・折敷おしき・重箱など、漆塗の食器の総称。日本永代蔵2「―の部屋を預り」
②特に、椀。好色五人女2「―・壺・平ひら・るす・ちやつまで取りさばき」
わん‐がけ【椀がけ】
砂などから鉱物を選別する方法。砂と水を入れた椀を揺り、中央部に比重の大きい目的物を残す。砂金採取で行われる。→パンニング
わんかし‐でんせつ【椀貸伝説】
塚や池・淵、または山陰の洞穴ほらあななどで、頼めば膳や椀を貸してくれたが、ある時借りた人の不心得で貸してくれなくなったという伝説。九州から東北地方まで広く分布。→膳椀淵ぜんわんぶち
わん‐がん【湾岸】
湾の沿岸。「―道路」
⇒わんがん‐しょこく【湾岸諸国】
⇒わんがん‐せんそう【湾岸戦争】
わんがん‐しょこく【湾岸諸国】
(Gulf States)ペルシア湾湾岸の諸国。イラン・イラク・サウジ‐アラビア・アラブ首長国連邦・オマーン・カタール・バーレーン・クウェートの8カ国。
⇒わん‐がん【湾岸】
わんがん‐せんそう【湾岸戦争】‥サウ
1990年8月のイラクのクウェート侵攻に端を発し、翌年1月から約40日間、イラク軍と米軍中心の多国籍軍との間で行われた戦争。イラクの敗北で停戦。
⇒わん‐がん【湾岸】
わん‐きゅう【椀久】‥キウ
大坂御堂前の豪商椀屋久右衛門の略称。新町の遊女松山となじんで豪遊したため、座敷牢に入れられ、発狂して、一説に1677年(延宝5)没したという。西鶴の浮世草子に描かれ、また浄瑠璃・長唄・常磐津・清元などでは椀屋久兵衛としても脚色。
⇒わんきゅう‐すえのまつやま【椀久末松山】
わんきゅう‐すえのまつやま【椀久末松山】‥キウスヱ‥
①浄瑠璃。紀海音作の世話物。1710年(宝永7)頃初演。椀久の実話を脚色。
②歌舞伎脚本。渡辺霞亭作。1906年(明治39)初演。
⇒わん‐きゅう【椀久】
わん‐きょく【湾曲・彎曲】
弓形にまがること。
ワン‐ぎり【ワン切り】
電話をかけて、呼出し音を1回鳴らして切ること。
わん‐きん【腕巾】
汗ふき。汗ぬぐい。
わん‐くつ【湾屈・彎屈】
まがりかがまること。
ワン‐クッション
(和製語one cushion)影響力やショックをやわらげるための一段階。「―置く」
わんぐり
口を大きく開くさま。口を大きくあけてかみつくさま。あんぐり。浮世床2「あんまりひもじいにナ、―と食つたが因果」
ワングル
(朝鮮語wanggol)カヤツリグサ科の多年草。朝鮮半島各地に広く栽培。東京上野の不忍池に自生化。高さ1メートル前後で葉は線形。夏、褐色の大きな穂を出す。茎の繊維を綱とし、葉で簾すだれ・縄・草履を、皮で筵むしろ・帽子などを作る。カンエンガヤツリ。莞草かんそう。
わん‐けい【湾渓】
湾曲した渓谷。入り込んだ谷川。太平記39「―のせせらぎを渉れば路羊腸を遶めぐつて」
わん‐げつ【彎月】
①弓張月。弦月。
②陣立ての名。弦月の形に隊伍を列ねるもの。
ワンゲル
ワンダーフォーゲルの略。
わん‐こう【湾口】
湾の外海への出入り口。
わんこ‐そば【椀子蕎麦】
岩手県の郷土料理。給仕人が椀に盛ったそばを客の椀に次々に投げ入れ、満腹になるまでもてなすもの。
わん‐こつ【腕骨】
(→)手根骨に同じ。
わんさ
①がやがやと大勢が押しかけるさま。「申込者が―と来た」
②たくさんあるさま。「金は―とある」
③「わんさガール」の略。
⇒わんさ‐ガール【わんさガール】
⇒わんさ‐わんさ
ワンサイド‐ゲーム【one-sided game】
一方が終始圧倒的優位を続け、勝利に終わる試合。
わんさ‐ガール【わんさガール】
下っ端の映画女優や踊り子。大部屋女優。
⇒わんさ
わんざ‐くれ
ワザクレの撥音化。
わんさ‐わんさ
大勢の人が1カ所に押しかけるさま。大勢が混雑してやかましく押し寄せるさま。
⇒わんさ
わん‐ざん【和讒】
(ワザンの撥音化)
①讒言。中傷。告げ口。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「うらやましうての―ならば此の首御辺におまするぞ」
②無理。難題。歌舞伎、傾城壬生大念仏「是は―なる事を仰せられます」
ワン‐シーター【one-seater】
航空機・自動車などの一人乗り用のもの。単座式。
わん‐しゃ【腕車】
人力車の別称。内藤湖南、政治家「外出には二人引の―に乗り、節太のステツキ一本備ふべし」
わん‐しょう【腕章】‥シヤウ
儀式や行事のとき、目印にするために、洋服などの腕部にとりつける布や徽章。「―を巻く」
ワン‐ショルダー【one shoulder】
片方の肩をあらわにした洋服のスタイル。女性用の夏服や水着・イブニング‐ドレスなどに見られる。
ワンズ【万子】
(中国語)マージャン牌パイの一つ。「萬」字の彫ってあるもの。
ワン‐ステップ
①(one step)1歩。一段階。
②(one-step)4分の2拍子の現代社交ダンス。毎歩同じ速度で踊る足取りからできているのでいう。
ワンス‐モア【once more】
もう一度。
わん‐せき【惋惜】
驚き嘆いておしみいたむこと。
ワン‐セグ
(セグはセグメントの略)地上デジタル放送のサービスの一つ。携帯端末でも安定して受信ができる。放送電波の一部(13等分したうちの1セグメント)を用いることからの称。
ワン‐セット【one set】
(組になったものの)一揃い。一式。
わんそく‐るい【腕足類】
腕足動物門の海産動物の総称。2枚の殻をもち、二枚貝が体の左右に殻があるのに対して、殻が体の前後に位置する。シャミセンガイ・ホオズキガイなど。かつて触手動物の一綱に分類された。
ワンダーフォーゲル【Wandervogel ドイツ】
(渡り鳥の意)青年・学生のグループによる山野徒歩旅行の運動。20世紀初頭、ドイツに始まる。ワンゲル。
ワンダーランド【wonderland】
不思議の国。おとぎの国。
ワン‐タッチ
(和製語one touch)
①1回触れること。「ボールに―あり」
②一つの操作。また、機器などの操作が極度に簡単であること。
わん‐だね【椀種】
吸物の実の中で中心的なもの。主に魚介・豆腐・卵などを用いる。
ワンダフル【wonderful】
驚くべきさま。不思議なさま。すばらしいさま。素敵。
ワンタン【餛飩・雲呑】
(中国語)中国料理。小麦粉で作った薄皮に、葱ねぎ・胡椒・塩などをまぜて調味した挽肉ひきにくを包み、茹ゆでてスープをかけたもの。
⇒ワンタン‐メン【雲呑麺】
ワンタン‐メン【雲呑麺】
(中国語)中国料理。中華そばとワンタンにスープを加えたもの。
⇒ワンタン【餛飩・雲呑】
ワンデルング【Wanderung ドイツ】
自由に山野を歩きまわること。
わん‐ど【湾処】
入江。
わん‐とう【湾頭】
湾のほとり。
わん‐とう【彎刀・湾刀】‥タウ
湾曲した刀。刀身に反そりのある刀。↔直刀
わん‐ない【湾内】
湾の内。湾中。
わん‐にゅう【湾入・彎入】‥ニフ
水が陸地に弓形に入り込むこと。
わん‐ぱ【忘八・王八】
①中国で、鼈すっぽんの称。
②人をののしっていう語。
③遊女屋の主人。くつわ。
わん‐ぱく【腕白】
(古くはワンバク。「腕白」は当て字)子供がいたずらで言うことをきかないこと。活発に動き回ったり、わるさをしたりすること。また、その子供。浄瑠璃、生写朝顔話「育ても下種げすの―ども」。「―盛り」
ワン‐パターン
(和製語one pattern)言動などが常に一つの型にはまっていて変化がないこと。
ワン‐ピース【one-piece】
(ワンピース‐ドレスの略)婦人・子供用の服で、身頃とスカートとが一続きになったもの。→ツーピース→スリーピース
わん‐びき【椀挽き】
挽物細工で椀を作ること。また、それを業とする人。
ワンフーチン【王府井】
(Wangfujing)中国北京市最大の繁華街。故宮の東に南北に伸びる。
わん‐ぼ【縕袍】
(→)「わんぼう」に同じ。
ワン‐ポイント【one point】
①点数の1点。「―の差」
②片方の胸など、1カ所だけに刺繍ししゅうやプリントを施したデザイン。
③重要な1カ所。一つの要点。「―‐レッスン」
⇒ワンポイント‐リリーフ
ワンポイント‐リリーフ
(和製語one point relief)野球で、打者一人だけをアウトにするための救援。また、その投手。
⇒ワン‐ポイント【one point】
わん‐ぼう【縕袍】‥バウ
(オンポウの訛)
①布子ぬのこの綿入れ。どてら。わんぼ。誹風柳多留3「―は遣ると物見の松でいひ」
②転じて、粗末な着物。また、他人の衣服をけなしていう語。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「古―も其の風呂敷包みもきりきりこつちへおこせ」
ワンポーツ【黄包車】
(中国語)人力車のこと。
ワンボックス‐カー
(和製語one box car)箱型で、車体の前部から後部まで区切りのない乗用車。
ワン‐マン【one-man】
①「ひとりの」「ひとりで」の意。「―‐バス」
②(日本での用法)他人の意見や世評を顧みず、自分の思うままに振る舞う人。「―社長」
⇒ワンマン‐カー
⇒ワンマン‐コントロール【one-man control】
⇒ワンマン‐ショー【one-man show】
ワンマン‐カー
(和製語one-man car)一人の乗務員だけで運行される鉄道車両やバス。
⇒ワン‐マン【one-man】
ワンマン‐コントロール【one-man control】
①オートメーション化された設備で、1カ所に集めた制御機構を通じて設備全体を操作すること。
②一人の意思で全機構を動かすこと。
⇒ワン‐マン【one-man】
ワンマン‐ショー【one-man show】
舞台やテレビ番組などで、一人が中心になって演ずるショー。転じて、大勢の中の一人が、まるですべてを一人でしているかのように目立つこと。
⇒ワン‐マン【one-man】
ワン‐メーター
(和製語one meter)タクシーの利用が初乗り料金の範囲内であること。
わん‐もり【椀盛り】
野菜・鶏肉・魚介などを適宜に取り合わせ、大形の椀に盛った汁物あるいは煮物。わん。
ワンラ【完了】
(中国語)おしまいだ。終了。
わん‐りき【腕力】
⇒わんりょく。吉利支丹教義「唯万事叶ひ給ふ御―を以て」
わん‐りゅう【湾流】‥リウ
(Gulf Stream)北大西洋の暖流の一つ。メキシコ湾から北東に流れ、アメリカ合衆国東岸のハッテラス岬沖で東に向かい、北大西洋の亜熱帯環流の一部を形成する。ハッテラス岬以南の部分はフロリダ海流ともいう。黒潮と並ぶ大規模な海流。メキシコ湾流。
わん‐りょく【腕力】
①うでの力。うでぢから。
②うでに限らず、肉体的な力。「―に訴える」
⇒わんりょく‐ざた【腕力沙汰】
わんりょく‐ざた【腕力沙汰】
腕力で事の決着をつけること。
⇒わん‐りょく【腕力】
ワンルーム‐マンション
(和製語one-room mansion)浴室・便所以外は、居間・台所・寝室を兼ねた一つの部屋だけから成る集合住宅の住戸。また、その住宅棟。
わん‐れい【還礼】
(ワンは唐音)禅家で礼をしかえすこと。答拝。回礼ういれい。〈黒本本節用集〉
ワン‐レングス
(one-length cut)女性の髪形の一つ。やや長めの同じ長さに切りそろえてたらしたもの。ワンレン。
わん‐わん
①犬の吠える声。
②(幼児語)犬。
③やかましくわめくさま。大きな音や声が響くさま。狂言、鬼清水「一口にとつてかまう。―と申す程に」。「大の男が―と泣く」「歓声が―と響く」
ゐ
①五十音図ワ行の第2音。平安中期までは「う」に近い半母音〔w〕と母音〔i〕との結合した音節で〔wi〕と発音したが、現代はア行・ヤ行の「い」〔i〕の発音と同一。
②平仮名「ゐ」は「為」の草体。片仮名「ヰ」は「井」の略体。
ゑ
①五十音図ワ行の第4音。平安中期までは「う」に近い半母音〔w〕と母音〔e〕との結合した音節で〔we〕と発音し、ア行・ヤ行の「え」と区別があったが、以後混同し、現代の発音は「え」〔e〕と同じ。
②平仮名「ゑ」は「恵」の草体。片仮名「ヱ」は「恵」の草体の終りの部分。
を
①五十音図ワ行の第5音。平安中期までは「う」に近い半母音〔w〕に母音〔o〕を添えた〔wo〕だったが、現代は「お」〔o〕と同じに発音する。
②平仮名「を」は「遠」の草体。片仮名「ヲ」は「乎」の初めの3画。
を
〔助詞〕
➊(間投助詞)種々の語を受け、その語を確かに肯定し、承認する意を示す。主に奈良・平安時代に行われた。
①自己の願望・意志、他への希求・命令などを表現する文中で、連用修飾語に付いて強調する。古事記下「迎へ―ゆかむ待つには待たじ」。万葉集3「この世なる間は楽しく―あらな」。万葉集9「漁あさりする人と―見ませ草枕旅行く人にわが名は告らじ」。古今和歌集恋「恋しくは下したに―思へ紫のねずりの衣色にいづなゆめ」。古今和歌集秋「立ちとまり見て―渡らむもみぢばは雨と降るとも水はまさらじ」
②文末で文の内容を確認する。多く、強い詠嘆の余情が含まれる。「ものを」の形が多い。古事記上「あなにやしえをとこ―」。万葉集1「草枕旅ゆく君と知らませば岸の埴生ににほはさまし―」。万葉集12「あしひきの山より出づる月待つと人には言ひて妹待つ我―」。万葉集17「かからむとかねて知りせば越こしの海の荒磯ありその波も見せましもの―」。閑吟集「人買舟は沖を漕ぐ、とても売らるる身―、ただ静かに漕げよ船頭殿」。「そんなに欲しかったならあげたもの―」
③文中で下の「…み」という表現と呼応して、「…が…ので」の意を表す。万葉集1「山―繁み入りても取らず」。古今和歌集雑「笹の葉に降り積む雪のうれ―重み」
➋(格助詞)体言またはそれに準ずるものを受ける。
①対象を示す。現代語では、他動的意味の動詞と対応して目的格的な働きをするが、奈良・平安時代には、自動的意味の動詞や形容詞の前でも使われた。心情・可能の対象を示す「を」は、古くは「が」が一般的であったが、現代語では「人を好き」「故郷を恋しい」「字を書ける」など、「を」も広く使われる。万葉集1「紫の匂へる妹―にくくあらば人妻故に我恋ひめやも」。古今和歌集序「花―めで、鳥―うらやみ、霞―あはれび、露―かなしぶ」。古今和歌集秋「女郎花多かる野辺に宿りせばあやなくあだの名―や立ちなむ」。源氏物語玉鬘「うるさきたはぶれごと言ひかかり給ふ―煩はしきに」。栄華物語月宴「碁・双六うたせ、偏―つがせ」
②そこから離れる所・人を示す。万葉集15「はしけやし家―離れて」。万葉集20「たらちねの母―別れて」
③動作の移動する場所、持続する時間を示す。万葉集5「霞立つ長き春日―かざせれどいやなつかしき梅の花かも」。土佐日記「宇多の松原―行き過ぐ」。「空―飛ぶ」「道―急ぐ」「一日―歩き続ける」
④動詞と同じ意味を表す体言に付き、全体で一種の慣用句をつくる。土佐日記「まして女は船底に頭をつき当ててね―のみぞ泣く」。源氏物語明石「昼は一日寝い―のみ寝くらし」。「夢―夢見る」
➌(接続助詞)多く、活用する語の連体形を受け、次に続く動作・感情の原因・理由などを示す。順接・逆接を決める機能はなく、そのいずれにも用いる。
①下の句に対する順接条件を表す。…のだから。…ので。源氏物語桐壺「若宮のいと覚束なく露けき中に過し給ふも心苦しう思さるる―とく参り給へ」。徒然草「藁一束ありける―夕には是にふし、朝にはをさめけり」
②逆接関係を表す。…のに。口語では多く「ものを」「ところを」などの形をとる。古今和歌集夏「夏の夜はまだ宵ながらあけぬる―雲のいづこに月やどるらむ」。古今和歌集秋「白露の色は一つ―いかにして秋の木の葉を千々ちぢに染むらむ」。発心集「僧ありけり。本は清かりける―、年半たけて後、妻めをなんまうけたりける」。「折角でき上がったもの―、こわされてしまった」「お忙しいところ―おいでいただき恐縮です」
を‐こと‐てん【乎古止点】
(「乎古止」はヲコトの万葉仮名)漢文訓読で漢字の読みを示すため、字の隅などに付けた点や線の符号。例えば、多く行われた博士家点はかせけてんでは、「引」の左下の隅に点があれば「引きて」と読み、左上の隅に点があれば「引くに」と読む類で、その右上の2点が「ヲ」「コト」であることからいい、普通「ヲコト点」と書く。平安初期から室町時代頃まで行われ、仏家・儒家、また流派によって種々の形式があった。
乎古止点
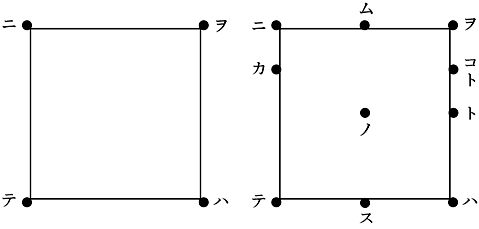 を‐ば
(格助詞「を」に係助詞「は」が付き濁音化したもの)動作・作用の対象を強く指し示す語。「失礼―致しました」
を‐や
(助詞のヲとヤとの連語)
➊格助詞ヲに係助詞ヤの付いたもの。…を…であろうか。玉葉集秋「秋の夜の長き程―たのむらむ出でていそがぬ山の端はの月」
➋間投助詞ヲに間投助詞ヤが付いて、意味を強めるもの。…ものを。…であるのになあ。源氏物語帚木「かの介はいとよしありてけしきばめる―」
➌間投助詞ヲに係助詞ヤの付いて熟したもの。程度の軽いものをあげたのを受け、程度の重いものをあげて反語の意を表す。漢文訓読からきた表現で、「いわんや…(…において)をや」の形をとるのが普通である。まして…当然であろう。平家物語4「王権猶かくの如し。何ぞ況や謀反八逆の輩に於て―」
ん
①五十音図および「いろは歌」に出ない仮名。昔は「はね仮名」「はね字」などといった。前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音。ただし、後続音の有無・種類により〔n〕〔ŋ〕〔m〕などとなる。
②平仮名「ん」は「无」の草体。片仮名「ン」は撥音記号「
を‐ば
(格助詞「を」に係助詞「は」が付き濁音化したもの)動作・作用の対象を強く指し示す語。「失礼―致しました」
を‐や
(助詞のヲとヤとの連語)
➊格助詞ヲに係助詞ヤの付いたもの。…を…であろうか。玉葉集秋「秋の夜の長き程―たのむらむ出でていそがぬ山の端はの月」
➋間投助詞ヲに間投助詞ヤが付いて、意味を強めるもの。…ものを。…であるのになあ。源氏物語帚木「かの介はいとよしありてけしきばめる―」
➌間投助詞ヲに係助詞ヤの付いて熟したもの。程度の軽いものをあげたのを受け、程度の重いものをあげて反語の意を表す。漢文訓読からきた表現で、「いわんや…(…において)をや」の形をとるのが普通である。まして…当然であろう。平家物語4「王権猶かくの如し。何ぞ況や謀反八逆の輩に於て―」
ん
①五十音図および「いろは歌」に出ない仮名。昔は「はね仮名」「はね字」などといった。前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音。ただし、後続音の有無・種類により〔n〕〔ŋ〕〔m〕などとなる。
②平仮名「ん」は「无」の草体。片仮名「ン」は撥音記号「 」の転形。また、「爾」の略体「尓」の上部あるいは「二」の転形とも。
ん
〔助動〕
①⇒む。
②打消の助動詞ヌの転。「出来ん」
ん
〔助詞〕
ノの転。くだけた場での会話に用いる。「ある―だ」「君―ち」
ん
〔感〕
⇒うん
ンジャメナ【N'djamena】
⇒ウンジャメナ
んす
〔助動〕
(近世の遊女語)
①尊敬の助動詞シャンスの転。浄瑠璃、生玉心中「もし心中などして死なんしたら」
②丁寧の助動詞マスの転。浄瑠璃、女殺油地獄「遣手にお問ひなさりんせ」
んず
〔助動〕
⇒むず
ん‐と‐す
⇒むとす。「終わりな―」
」の転形。また、「爾」の略体「尓」の上部あるいは「二」の転形とも。
ん
〔助動〕
①⇒む。
②打消の助動詞ヌの転。「出来ん」
ん
〔助詞〕
ノの転。くだけた場での会話に用いる。「ある―だ」「君―ち」
ん
〔感〕
⇒うん
ンジャメナ【N'djamena】
⇒ウンジャメナ
んす
〔助動〕
(近世の遊女語)
①尊敬の助動詞シャンスの転。浄瑠璃、生玉心中「もし心中などして死なんしたら」
②丁寧の助動詞マスの転。浄瑠璃、女殺油地獄「遣手にお問ひなさりんせ」
んず
〔助動〕
⇒むず
ん‐と‐す
⇒むとす。「終わりな―」
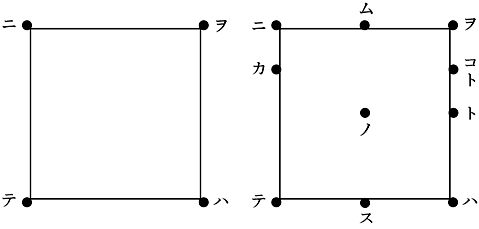 を‐ば
(格助詞「を」に係助詞「は」が付き濁音化したもの)動作・作用の対象を強く指し示す語。「失礼―致しました」
を‐や
(助詞のヲとヤとの連語)
➊格助詞ヲに係助詞ヤの付いたもの。…を…であろうか。玉葉集秋「秋の夜の長き程―たのむらむ出でていそがぬ山の端はの月」
➋間投助詞ヲに間投助詞ヤが付いて、意味を強めるもの。…ものを。…であるのになあ。源氏物語帚木「かの介はいとよしありてけしきばめる―」
➌間投助詞ヲに係助詞ヤの付いて熟したもの。程度の軽いものをあげたのを受け、程度の重いものをあげて反語の意を表す。漢文訓読からきた表現で、「いわんや…(…において)をや」の形をとるのが普通である。まして…当然であろう。平家物語4「王権猶かくの如し。何ぞ況や謀反八逆の輩に於て―」
ん
①五十音図および「いろは歌」に出ない仮名。昔は「はね仮名」「はね字」などといった。前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音。ただし、後続音の有無・種類により〔n〕〔ŋ〕〔m〕などとなる。
②平仮名「ん」は「无」の草体。片仮名「ン」は撥音記号「
を‐ば
(格助詞「を」に係助詞「は」が付き濁音化したもの)動作・作用の対象を強く指し示す語。「失礼―致しました」
を‐や
(助詞のヲとヤとの連語)
➊格助詞ヲに係助詞ヤの付いたもの。…を…であろうか。玉葉集秋「秋の夜の長き程―たのむらむ出でていそがぬ山の端はの月」
➋間投助詞ヲに間投助詞ヤが付いて、意味を強めるもの。…ものを。…であるのになあ。源氏物語帚木「かの介はいとよしありてけしきばめる―」
➌間投助詞ヲに係助詞ヤの付いて熟したもの。程度の軽いものをあげたのを受け、程度の重いものをあげて反語の意を表す。漢文訓読からきた表現で、「いわんや…(…において)をや」の形をとるのが普通である。まして…当然であろう。平家物語4「王権猶かくの如し。何ぞ況や謀反八逆の輩に於て―」
ん
①五十音図および「いろは歌」に出ない仮名。昔は「はね仮名」「はね字」などといった。前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音。ただし、後続音の有無・種類により〔n〕〔ŋ〕〔m〕などとなる。
②平仮名「ん」は「无」の草体。片仮名「ン」は撥音記号「 」の転形。また、「爾」の略体「尓」の上部あるいは「二」の転形とも。
ん
〔助動〕
①⇒む。
②打消の助動詞ヌの転。「出来ん」
ん
〔助詞〕
ノの転。くだけた場での会話に用いる。「ある―だ」「君―ち」
ん
〔感〕
⇒うん
ンジャメナ【N'djamena】
⇒ウンジャメナ
んす
〔助動〕
(近世の遊女語)
①尊敬の助動詞シャンスの転。浄瑠璃、生玉心中「もし心中などして死なんしたら」
②丁寧の助動詞マスの転。浄瑠璃、女殺油地獄「遣手にお問ひなさりんせ」
んず
〔助動〕
⇒むず
ん‐と‐す
⇒むとす。「終わりな―」
」の転形。また、「爾」の略体「尓」の上部あるいは「二」の転形とも。
ん
〔助動〕
①⇒む。
②打消の助動詞ヌの転。「出来ん」
ん
〔助詞〕
ノの転。くだけた場での会話に用いる。「ある―だ」「君―ち」
ん
〔感〕
⇒うん
ンジャメナ【N'djamena】
⇒ウンジャメナ
んす
〔助動〕
(近世の遊女語)
①尊敬の助動詞シャンスの転。浄瑠璃、生玉心中「もし心中などして死なんしたら」
②丁寧の助動詞マスの転。浄瑠璃、女殺油地獄「遣手にお問ひなさりんせ」
んず
〔助動〕
⇒むず
ん‐と‐す
⇒むとす。「終わりな―」
広辞苑 ページ 21258 での【○和を以て貴しと為す】単語。