複数辞典一括検索+![]()
![]()
○綺羅を磨くきらをみがく🔗⭐🔉
○綺羅を磨くきらをみがく
華美をこらす。
⇒き‐ら【綺羅】
き‐らん【貴覧】
他人の見ることの尊敬語。御覧。高覧。
きらん‐そう【金瘡小草】‥サウ
シソ科の小形の多年草。路傍に生え、茎は地表に拡がって這はう。茎葉には毛がある。葉は対生、しばしば紫色を帯びる。春、葉の付け根に濃紫色の美しい唇形小花を開く。ジゴクノカマノフタ。
キランソウ
撮影:関戸 勇
 ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥
末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。
きり【切り・限】
[一]〔名〕
①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」
②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」
③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」
④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」
⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。
⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。
⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」
⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」
[二]〔助詞〕
(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)
①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」
②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」
きり【桐】
①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」
キリ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥
末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。
きり【切り・限】
[一]〔名〕
①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」
②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」
③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」
④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」
⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。
⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。
⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」
⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」
[二]〔助詞〕
(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)
①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」
②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」
きり【桐】
①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」
キリ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。
桐
②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。
桐
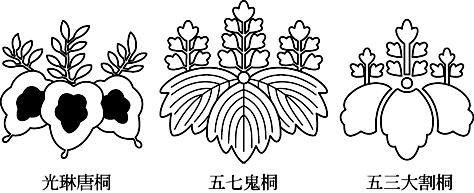 ③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」
④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」
きり【錐】
①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。
②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。
③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。
⇒錐の嚢中に処るがごとし
⇒錐は嚢を通す
⇒錐を立つべき地
きり【霧】
①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」
②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」
③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」
⇒霧不断の香を焚く
き‐り【肌理】
①皮膚のきめ。
②もくめ。
き‐り【奇利】
思いがけない利益。
き‐り【棋理】
囲碁・将棋の理論。
キリ
クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン
ぎ‐り【義理】
①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」
②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」
③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。
④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」
⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」
⇒義理ある仲
⇒義理一遍
⇒義理と褌欠かされぬ
⇒義理にも
⇒義理を立てる
⇒義理を張る
きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ
①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。
②割勘わりかん。切合勘定。
ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ
義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。
きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ
〔自五〕
①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」
②二つの物が十文字に交わる。
きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ
〔自四〕
霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」
きり‐あえ【切和え】‥アヘ
フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。
きり‐あげ【切上げ】
①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」
②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。
③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ
きり‐あげ【切揚げ】
サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。
きり‐あ・ける【切り明ける】
〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)
切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」
きり‐あ・げる【切り上げる】
〔他下一〕
①下から上へ向けて切る。
②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」
③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。
④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる
きり‐あさ【桐麻】
〔植〕イチビの別称。
きり‐あな【切穴】
劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。
きり‐あな【錐穴】
①錐であけた穴。
②楊弓で、的まとの中央にある穴。
きり‐あぶら【桐油】
(→)桐油とうゆ1に同じ。
きり‐あめ【霧雨】
⇒きりさめ
③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」
④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」
きり【錐】
①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。
②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。
③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。
⇒錐の嚢中に処るがごとし
⇒錐は嚢を通す
⇒錐を立つべき地
きり【霧】
①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」
②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」
③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」
⇒霧不断の香を焚く
き‐り【肌理】
①皮膚のきめ。
②もくめ。
き‐り【奇利】
思いがけない利益。
き‐り【棋理】
囲碁・将棋の理論。
キリ
クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン
ぎ‐り【義理】
①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」
②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」
③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。
④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」
⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」
⇒義理ある仲
⇒義理一遍
⇒義理と褌欠かされぬ
⇒義理にも
⇒義理を立てる
⇒義理を張る
きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ
①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。
②割勘わりかん。切合勘定。
ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ
義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。
きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ
〔自五〕
①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」
②二つの物が十文字に交わる。
きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ
〔自四〕
霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」
きり‐あえ【切和え】‥アヘ
フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。
きり‐あげ【切上げ】
①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」
②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。
③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ
きり‐あげ【切揚げ】
サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。
きり‐あ・ける【切り明ける】
〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)
切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」
きり‐あ・げる【切り上げる】
〔他下一〕
①下から上へ向けて切る。
②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」
③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。
④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる
きり‐あさ【桐麻】
〔植〕イチビの別称。
きり‐あな【切穴】
劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。
きり‐あな【錐穴】
①錐であけた穴。
②楊弓で、的まとの中央にある穴。
きり‐あぶら【桐油】
(→)桐油とうゆ1に同じ。
きり‐あめ【霧雨】
⇒きりさめ
 ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥
末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。
きり【切り・限】
[一]〔名〕
①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」
②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」
③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」
④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」
⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。
⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。
⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」
⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」
[二]〔助詞〕
(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)
①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」
②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」
きり【桐】
①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」
キリ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥
末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。
きり【切り・限】
[一]〔名〕
①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」
②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」
③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」
④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」
⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。
⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。
⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」
⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」
[二]〔助詞〕
(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)
①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」
②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」
きり【桐】
①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」
キリ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。
桐
②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。
桐
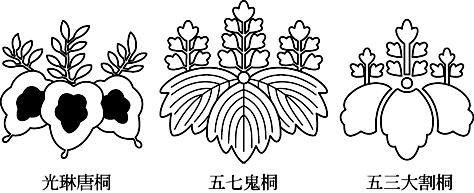 ③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」
④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」
きり【錐】
①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。
②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。
③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。
⇒錐の嚢中に処るがごとし
⇒錐は嚢を通す
⇒錐を立つべき地
きり【霧】
①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」
②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」
③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」
⇒霧不断の香を焚く
き‐り【肌理】
①皮膚のきめ。
②もくめ。
き‐り【奇利】
思いがけない利益。
き‐り【棋理】
囲碁・将棋の理論。
キリ
クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン
ぎ‐り【義理】
①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」
②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」
③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。
④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」
⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」
⇒義理ある仲
⇒義理一遍
⇒義理と褌欠かされぬ
⇒義理にも
⇒義理を立てる
⇒義理を張る
きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ
①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。
②割勘わりかん。切合勘定。
ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ
義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。
きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ
〔自五〕
①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」
②二つの物が十文字に交わる。
きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ
〔自四〕
霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」
きり‐あえ【切和え】‥アヘ
フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。
きり‐あげ【切上げ】
①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」
②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。
③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ
きり‐あげ【切揚げ】
サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。
きり‐あ・ける【切り明ける】
〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)
切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」
きり‐あ・げる【切り上げる】
〔他下一〕
①下から上へ向けて切る。
②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」
③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。
④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる
きり‐あさ【桐麻】
〔植〕イチビの別称。
きり‐あな【切穴】
劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。
きり‐あな【錐穴】
①錐であけた穴。
②楊弓で、的まとの中央にある穴。
きり‐あぶら【桐油】
(→)桐油とうゆ1に同じ。
きり‐あめ【霧雨】
⇒きりさめ
③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」
④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」
きり【錐】
①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。
②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。
③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。
⇒錐の嚢中に処るがごとし
⇒錐は嚢を通す
⇒錐を立つべき地
きり【霧】
①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」
②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」
③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」
⇒霧不断の香を焚く
き‐り【肌理】
①皮膚のきめ。
②もくめ。
き‐り【奇利】
思いがけない利益。
き‐り【棋理】
囲碁・将棋の理論。
キリ
クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン
ぎ‐り【義理】
①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」
②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」
③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。
④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」
⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」
⇒義理ある仲
⇒義理一遍
⇒義理と褌欠かされぬ
⇒義理にも
⇒義理を立てる
⇒義理を張る
きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ
①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。
②割勘わりかん。切合勘定。
ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ
義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。
きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ
〔自五〕
①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」
②二つの物が十文字に交わる。
きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ
〔自四〕
霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」
きり‐あえ【切和え】‥アヘ
フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。
きり‐あげ【切上げ】
①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」
②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。
③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ
きり‐あげ【切揚げ】
サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。
きり‐あ・ける【切り明ける】
〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)
切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」
きり‐あ・げる【切り上げる】
〔他下一〕
①下から上へ向けて切る。
②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」
③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。
④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる
きり‐あさ【桐麻】
〔植〕イチビの別称。
きり‐あな【切穴】
劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。
きり‐あな【錐穴】
①錐であけた穴。
②楊弓で、的まとの中央にある穴。
きり‐あぶら【桐油】
(→)桐油とうゆ1に同じ。
きり‐あめ【霧雨】
⇒きりさめ
広辞苑 ページ 5308 での【○綺羅を磨く】単語。