複数辞典一括検索+![]()
![]()
○気も無いけもない🔗⭐🔉
○気も無いけもない
①そのような様子が全くない。気配もない。宇津保物語祭使「けもなく青みやせて」。「心配の―」
②思いもよらない。とんでもない。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―こと言はしや島絽が十五箱」
⇒け【気】
け‐も‐ない【気も無い】
⇒け(気)(句)
け‐もの【獣】
(毛物の意)全身に毛のある四足の動物。畜類。けだもの。法華義疏長保点「一角の狩ケモノ出づるときは」
⇒けもの‐たおし【畜仆し】
⇒けもの‐へん【獣偏】
⇒けもの‐みち【獣道】
けもの‐たおし【畜仆し】‥タフシ
家畜を殺すこと。呪術によるという。国つ罪の一つ。祝詞、大祓詞「高つ鳥の災わざわい、―、蠱物まじものする罪」
⇒け‐もの【獣】
けもの‐へん【獣偏】
漢字の偏の一つ。「狩」「猫」などの偏の「犭」の称。「犭」は「犬」の字の変形。
⇒け‐もの【獣】
けもの‐みち【獣道】
鹿・猪などの通行で自然につけられた道。
⇒け‐もの【獣】
け‐もも【毛桃】
桃の一類。果実の皮に毛があるのでいう。万葉集7「はしきやし吾家わぎえの―本しげみ花のみ咲きて成らざらめやも」
け‐もん【仮門】
〔仏〕
①方便の教え。権門ごんもん。↔真門。
②浄土真宗で、自力で往生しようとすること。
け‐もん【暇文・假文】
⇒いとまぶみ
げ‐もん【解文】
①(→)解げ1に同じ。
②推薦状。栄華物語疑「阿闍梨の―を放たせ給ふ」
けもん‐さ【顕紋紗】
(→)「けんもんしゃ」に同じ。
けもん‐りょう【花文綾】
唐花からはなの模様のある綾あや。宇津保物語俊蔭「赤朽葉に―のこうちぎ」
けや
きわだって他と異なっているさま。けざやか。けやか。万葉集16「寒水しみずの心も―に思ほゆる」
げ‐や【下屋】
母屋もやにさしかけてつくった小屋根。また、その下の部分。
げ‐や【下野】
官職を辞して民間に下ること。また、政権を失って野党になることにもいう。「責任をとって―する」
けやか
きわだって他と異なっているさま。きわやか。雄略紀「玉縵たまかずらは大はなはだ貴けやかにして」
けやき【欅・槻】
(ケヤはケヤケシと同源。木理に基づく名か。キは木の意)ニレ科の落葉高木。山地に多いが、人家の防風林にも使われてきた。高さ20メートルに近く、周囲約3メートルに達する。花は早春新葉と共に生じ、淡黄緑色、雌雄同株。果実は3ミリメートルくらいの不定形で、複数個つけた先端の小枝ごと散布される。材は黄ばんで堅く、磨けば光沢を生じ、くるいが少ない。建築用装飾材または器具材として賞用。古名ツキノキ(槻の木)。伊京集「樫、ケヤキ」
けやき
 ケヤキ
提供:ネイチャー・プロダクション
ケヤキ
提供:ネイチャー・プロダクション
 け‐やき【毛焼き】
①鳥の羽をむしったあと肌に残る細かい毛を火で焼くこと。〈日葡辞書〉
②(→)「けばやき」に同じ。
け‐やく
(「契約」から。青森・秋田県で)友だち。仲良し。
げ‐やく【下薬】
(→)下剤げざいに同じ。
げ‐やく【解薬】
解毒用の薬。解毒剤。毒消し。
けやけ・し
〔形ク〕
①きわだっている。普通とはちがっている。源氏物語藤裏葉「いと―・うもつかうまつるかな」。大鏡道長「末代には―・き寿もちて侍る翁なりかし」
②感情が害されるさまである。こしゃくである。源氏物語胡蝶「めざましかるべき際は、―・うなども覚えけれ」
③きわだってすぐれている。すばらしい。大鏡道長「貫之召し出でて歌つかうまつらしめ給へり。…それをだに―・きことに思ひ給へしに」
け‐やす・し【消易し】
〔形ク〕
消えやすい。はかない。万葉集5「朝露の―・き我が身」
け‐やっこ【毛奴】
奴をののしっていう語。浄瑠璃、双生隅田川「嘘つき奴の糟奴、黴の生へた―と笑ふて」
け‐やぶ・る【蹴破る】
〔他五〕
①蹴ってやぶる。
②蹴散らす。「敵軍を―・る」
③つまずいて足を傷つける。醒睡笑「あやまちに足を―・り」
けやむら‐ろくすけ【毛谷村六助】
①安土桃山時代の剣客。もと豊前国彦山の麓に住む百姓。浄瑠璃「彦山権現誓助剣ひこさんごんげんちかいのすけだち」の主人公。吉岡一味斎の娘を助けて父の仇を討たせたという。歌舞伎でも行われ、黄表紙・合巻・読本などにも脚色。
②「彦山権現誓助剣」の通称。
け‐やり【毛槍】
鞘を鳥毛で包んだ槍。大名行列の先頭などで振り歩く。
⇒けやり‐あたま【毛槍頭】
⇒けやり‐むし【毛槍虫】
けやり‐あたま【毛槍頭】
毛槍の先のような髪形をした頭。
⇒け‐やり【毛槍】
けやり‐むし【毛槍虫】
ケヤリ科の多毛類。体長約20センチメートル、環節約170個。体の前部は太く、後端は細くなる。多数の長い赤褐色の鰓糸さいしをもつ一対の鰓冠が頭端にある。太い棲管せいかんの先から鰓冠を房のように広げて呼吸・摂食する姿が毛槍を思わせる。中部日本以南に広く分布。ケヤリ。
けやりむし
け‐やき【毛焼き】
①鳥の羽をむしったあと肌に残る細かい毛を火で焼くこと。〈日葡辞書〉
②(→)「けばやき」に同じ。
け‐やく
(「契約」から。青森・秋田県で)友だち。仲良し。
げ‐やく【下薬】
(→)下剤げざいに同じ。
げ‐やく【解薬】
解毒用の薬。解毒剤。毒消し。
けやけ・し
〔形ク〕
①きわだっている。普通とはちがっている。源氏物語藤裏葉「いと―・うもつかうまつるかな」。大鏡道長「末代には―・き寿もちて侍る翁なりかし」
②感情が害されるさまである。こしゃくである。源氏物語胡蝶「めざましかるべき際は、―・うなども覚えけれ」
③きわだってすぐれている。すばらしい。大鏡道長「貫之召し出でて歌つかうまつらしめ給へり。…それをだに―・きことに思ひ給へしに」
け‐やす・し【消易し】
〔形ク〕
消えやすい。はかない。万葉集5「朝露の―・き我が身」
け‐やっこ【毛奴】
奴をののしっていう語。浄瑠璃、双生隅田川「嘘つき奴の糟奴、黴の生へた―と笑ふて」
け‐やぶ・る【蹴破る】
〔他五〕
①蹴ってやぶる。
②蹴散らす。「敵軍を―・る」
③つまずいて足を傷つける。醒睡笑「あやまちに足を―・り」
けやむら‐ろくすけ【毛谷村六助】
①安土桃山時代の剣客。もと豊前国彦山の麓に住む百姓。浄瑠璃「彦山権現誓助剣ひこさんごんげんちかいのすけだち」の主人公。吉岡一味斎の娘を助けて父の仇を討たせたという。歌舞伎でも行われ、黄表紙・合巻・読本などにも脚色。
②「彦山権現誓助剣」の通称。
け‐やり【毛槍】
鞘を鳥毛で包んだ槍。大名行列の先頭などで振り歩く。
⇒けやり‐あたま【毛槍頭】
⇒けやり‐むし【毛槍虫】
けやり‐あたま【毛槍頭】
毛槍の先のような髪形をした頭。
⇒け‐やり【毛槍】
けやり‐むし【毛槍虫】
ケヤリ科の多毛類。体長約20センチメートル、環節約170個。体の前部は太く、後端は細くなる。多数の長い赤褐色の鰓糸さいしをもつ一対の鰓冠が頭端にある。太い棲管せいかんの先から鰓冠を房のように広げて呼吸・摂食する姿が毛槍を思わせる。中部日本以南に広く分布。ケヤリ。
けやりむし
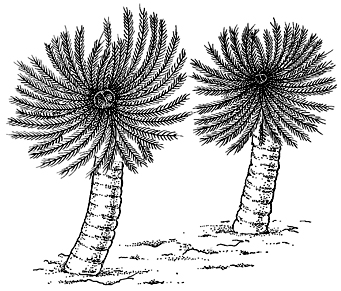 ケヤリムシ
提供:東京動物園協会
ケヤリムシ
提供:東京動物園協会
 ⇒け‐やり【毛槍】
げ‐ゆ【解由】
(解くる由よしの意)奈良・平安時代、国司などの任期が果てて交替する時、後任者から前任者に渡す、事務を滞りなく引き継いだ旨の文書。解由状。土佐日記「例の事ども皆しをへて―など取りて」
げ‐ゆう【外用】
〔仏〕外に現れる作用。さとりに基づいて外に現れた利他のはたらき。
げゆ‐じょう【解由状】‥ジヤウ
(→)解由に同じ。
げ‐よう【下用】
下層の人の食用とした、十分に搗つかない飯米。
⇒げよう‐びつ【下用櫃】
げよう‐びつ【下用櫃】
米櫃。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―には虚空蔵菩薩、米がないとせがまれ」
⇒げ‐よう【下用】
け‐よそい【褻装い】‥ヨソヒ
ふだんの服装。平服。久安百首「逢ふことは我が―のきぬなれや」
けら【鉧】
日本古来の製鋼法(けら押し、または、たたら吹き)による粗製品で、各種品質の鋼とスラグとの集合体。
けら【螻蛄・螻】
バッタ目ケラ科の昆虫。コオロギに似て、体長約3センチメートル。前肢は大きく、モグラのように土を掘るのに適する。夜行性で、よく灯火に来る。農作物を食害。土中で「じいい」と鳴く。これを俗に「みみずが鳴く」という。おけら。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉
けら
⇒け‐やり【毛槍】
げ‐ゆ【解由】
(解くる由よしの意)奈良・平安時代、国司などの任期が果てて交替する時、後任者から前任者に渡す、事務を滞りなく引き継いだ旨の文書。解由状。土佐日記「例の事ども皆しをへて―など取りて」
げ‐ゆう【外用】
〔仏〕外に現れる作用。さとりに基づいて外に現れた利他のはたらき。
げゆ‐じょう【解由状】‥ジヤウ
(→)解由に同じ。
げ‐よう【下用】
下層の人の食用とした、十分に搗つかない飯米。
⇒げよう‐びつ【下用櫃】
げよう‐びつ【下用櫃】
米櫃。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―には虚空蔵菩薩、米がないとせがまれ」
⇒げ‐よう【下用】
け‐よそい【褻装い】‥ヨソヒ
ふだんの服装。平服。久安百首「逢ふことは我が―のきぬなれや」
けら【鉧】
日本古来の製鋼法(けら押し、または、たたら吹き)による粗製品で、各種品質の鋼とスラグとの集合体。
けら【螻蛄・螻】
バッタ目ケラ科の昆虫。コオロギに似て、体長約3センチメートル。前肢は大きく、モグラのように土を掘るのに適する。夜行性で、よく灯火に来る。農作物を食害。土中で「じいい」と鳴く。これを俗に「みみずが鳴く」という。おけら。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉
けら
 ケラ
提供:ネイチャー・プロダクション
ケラ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒螻蛄の五能
⇒螻蛄の水渡り
⇒螻蛄腹立つれば鶫喜ぶ
けら【啄木鳥】
キツツキの別称。
ゲラ
(galleyの訛)
①組み上げた活字版を収める長方形の盤。2方または3方に縁がある。ゲラ箱。
②ゲラ刷ずりの略。
げ‐ら【下等】
〔代〕
(一人称)おれ。狂言、吃り「則ち―が事なり」
ケラー【Gottfried Keller】
スイスのドイツ系作家。写実主義の小説「緑のハインリヒ」、「ゼルトヴィーラの人々」「七つの伝説」「チューリヒ小説集」など。(1819〜1890)
ケラー【Helen Adams Keller】
アメリカの教育家・社会福祉事業家。2歳の時盲聾唖もうろうあとなったが力行りっこうして大学を卒業。身体障害者の援助に尽くす。3度来日。著「私の生涯」など。ヘレン=ケラー。(1880〜1968)
ヘレン‐ケラー
提供:毎日新聞社
⇒螻蛄の五能
⇒螻蛄の水渡り
⇒螻蛄腹立つれば鶫喜ぶ
けら【啄木鳥】
キツツキの別称。
ゲラ
(galleyの訛)
①組み上げた活字版を収める長方形の盤。2方または3方に縁がある。ゲラ箱。
②ゲラ刷ずりの略。
げ‐ら【下等】
〔代〕
(一人称)おれ。狂言、吃り「則ち―が事なり」
ケラー【Gottfried Keller】
スイスのドイツ系作家。写実主義の小説「緑のハインリヒ」、「ゼルトヴィーラの人々」「七つの伝説」「チューリヒ小説集」など。(1819〜1890)
ケラー【Helen Adams Keller】
アメリカの教育家・社会福祉事業家。2歳の時盲聾唖もうろうあとなったが力行りっこうして大学を卒業。身体障害者の援助に尽くす。3度来日。著「私の生涯」など。ヘレン=ケラー。(1880〜1968)
ヘレン‐ケラー
提供:毎日新聞社
 け‐らい【家来・家礼】
(中世以前では「家礼」「家頼」、近世は「家来」と書かれた。もと、子が父を敬い礼すること)
①貴人に礼を致すこと。今昔物語集22「―のためにかく参りたるに」
②朝廷の公事くじ・故実の作法を習うために摂家などに奉仕する者。太平記40「公家―の人々には」
③(主従の関係に転じて)武家に仕える者。家臣。転じて、従う者。部下。
④家に召し使う者。従者ずさ。従臣。家人けにん。
⇒けらい‐かまど【家来竈】
⇒けらい‐ぶん【家来分】
けらい‐かまど【家来竈】
(東北地方で)下男が主家から分家させてもらった家。→親竈おやかまど。
⇒け‐らい【家来・家礼】
けらい‐ぶん【家来分】
家来としての身分。家来なみの身分。
⇒け‐らい【家来・家礼】
け‐らく【快楽】
⇒かいらく。栄華物語本雫「忉利天女とうりてんにょの―を受けて」
⇒けらく‐ふたい【快楽不退】
けらく
(助動詞ケリのク語法)…したこと。万葉集18「神代より言ひ継ぎ―」
げ‐らく【下洛】
①比叡山などから京都の町へ下りること。平家物語1「山門の大衆夥しう―すと聞えしかば」
②都から地方へ下ること。↔上洛
げ‐らく【下落】
①物価・相場などが下がること。「株価が―する」↔騰貴。
②価値・等級などが下がること。↔上昇
けらく‐てん【化楽天】
〔仏〕六欲天の第5。ここに生まれたものは、自ら楽しい境遇を作り楽しみ、八千歳の寿命を保つという。楽変化天。化自楽天。化自在天。
けら‐くび【螻蛄首・螻首】
①槍の穂の刃と中茎なかごとの間の部分。塩首。→槍(図)。
②木材の継ぎ手の男木おぎの首がくびれた形をしたもの。→鎌継(図)。
③柄杓ひしゃくの部分名。柄裏の合ごうに指し込んだ際きわ。三つ角。→柄杓(図)
けらく‐ふたい【快楽不退】
快楽が永く続いて衰えないこと。
⇒け‐らく【快楽】
けら‐げい【螻蛄芸】
(→)「けらざい(螻蛄才)」に同じ。
けら‐けら
軽々しい感じの甲高い笑い声。
げら‐げら
無遠慮に大声で笑う声。
けら‐ざい【螻蛄才】
種々の芸を持っているが、一つも巧みなもののないこと。螻蛄芸。→螻蛄の五能
けらし
〔助動〕
(過去の助動詞ケリの連体形ケルに推量の助動詞ラシの付いたケルラシの約。ケリの形容詞化とも)
①過去の推定。…したらしい。万葉集6「諾うべしこそ見る人ごとに語りつぎ偲ひけらしき」
②「けり」の意を婉曲に述べ、詠嘆の意をこめる。…たのだなあ。…たことよ。鹿島紀行「まことに愛すべき山のすがたなりけらし」
ゲラ‐ずり【ゲラ刷】
組み上げた活字版をゲラに入れたまま校正用に試し刷りしたもの。校正刷。ゲラ。
ゲラダ‐ひひ【ゲラダ狒狒】
(gelada baboon)(ゲラダは現地語で狒狒の意)霊長目オナガザル科の猿。頭胴長は雄で約70センチメートル、雌で約55センチメートル。手足が黒いほかは全身褐色の毛で覆われ、雄の肩には長い毛が垂れる。標高2500〜4000メートルのエチオピア高原に分布、夜は断崖にかたまって眠る。ヒヒに似るが別属。ジェラダひひ。
ゲラダヒヒ
提供:東京動物園協会
け‐らい【家来・家礼】
(中世以前では「家礼」「家頼」、近世は「家来」と書かれた。もと、子が父を敬い礼すること)
①貴人に礼を致すこと。今昔物語集22「―のためにかく参りたるに」
②朝廷の公事くじ・故実の作法を習うために摂家などに奉仕する者。太平記40「公家―の人々には」
③(主従の関係に転じて)武家に仕える者。家臣。転じて、従う者。部下。
④家に召し使う者。従者ずさ。従臣。家人けにん。
⇒けらい‐かまど【家来竈】
⇒けらい‐ぶん【家来分】
けらい‐かまど【家来竈】
(東北地方で)下男が主家から分家させてもらった家。→親竈おやかまど。
⇒け‐らい【家来・家礼】
けらい‐ぶん【家来分】
家来としての身分。家来なみの身分。
⇒け‐らい【家来・家礼】
け‐らく【快楽】
⇒かいらく。栄華物語本雫「忉利天女とうりてんにょの―を受けて」
⇒けらく‐ふたい【快楽不退】
けらく
(助動詞ケリのク語法)…したこと。万葉集18「神代より言ひ継ぎ―」
げ‐らく【下洛】
①比叡山などから京都の町へ下りること。平家物語1「山門の大衆夥しう―すと聞えしかば」
②都から地方へ下ること。↔上洛
げ‐らく【下落】
①物価・相場などが下がること。「株価が―する」↔騰貴。
②価値・等級などが下がること。↔上昇
けらく‐てん【化楽天】
〔仏〕六欲天の第5。ここに生まれたものは、自ら楽しい境遇を作り楽しみ、八千歳の寿命を保つという。楽変化天。化自楽天。化自在天。
けら‐くび【螻蛄首・螻首】
①槍の穂の刃と中茎なかごとの間の部分。塩首。→槍(図)。
②木材の継ぎ手の男木おぎの首がくびれた形をしたもの。→鎌継(図)。
③柄杓ひしゃくの部分名。柄裏の合ごうに指し込んだ際きわ。三つ角。→柄杓(図)
けらく‐ふたい【快楽不退】
快楽が永く続いて衰えないこと。
⇒け‐らく【快楽】
けら‐げい【螻蛄芸】
(→)「けらざい(螻蛄才)」に同じ。
けら‐けら
軽々しい感じの甲高い笑い声。
げら‐げら
無遠慮に大声で笑う声。
けら‐ざい【螻蛄才】
種々の芸を持っているが、一つも巧みなもののないこと。螻蛄芸。→螻蛄の五能
けらし
〔助動〕
(過去の助動詞ケリの連体形ケルに推量の助動詞ラシの付いたケルラシの約。ケリの形容詞化とも)
①過去の推定。…したらしい。万葉集6「諾うべしこそ見る人ごとに語りつぎ偲ひけらしき」
②「けり」の意を婉曲に述べ、詠嘆の意をこめる。…たのだなあ。…たことよ。鹿島紀行「まことに愛すべき山のすがたなりけらし」
ゲラ‐ずり【ゲラ刷】
組み上げた活字版をゲラに入れたまま校正用に試し刷りしたもの。校正刷。ゲラ。
ゲラダ‐ひひ【ゲラダ狒狒】
(gelada baboon)(ゲラダは現地語で狒狒の意)霊長目オナガザル科の猿。頭胴長は雄で約70センチメートル、雌で約55センチメートル。手足が黒いほかは全身褐色の毛で覆われ、雄の肩には長い毛が垂れる。標高2500〜4000メートルのエチオピア高原に分布、夜は断崖にかたまって眠る。ヒヒに似るが別属。ジェラダひひ。
ゲラダヒヒ
提供:東京動物園協会
 ケラチン【Keratin ドイツ】
硬蛋白質の一つ。一般に化学試薬に対する抵抗力大。羽毛・爪・角・蹄ひづめ・毛髪などの主成分。脊椎動物の表皮、魚類・爬虫類の鱗うろこにも存在する。
けら‐つつき【啄木鳥】
キツツキの別称。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉
ゲラニオール【geraniol】
〔化〕分子式C10H18O バラの香りのある無色ないし淡黄色の液体。そのままで、またはエステルとして各種精油の主成分として存在する。工業的にはシトラールの還元で合成する。
ケラチン【Keratin ドイツ】
硬蛋白質の一つ。一般に化学試薬に対する抵抗力大。羽毛・爪・角・蹄ひづめ・毛髪などの主成分。脊椎動物の表皮、魚類・爬虫類の鱗うろこにも存在する。
けら‐つつき【啄木鳥】
キツツキの別称。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉
ゲラニオール【geraniol】
〔化〕分子式C10H18O バラの香りのある無色ないし淡黄色の液体。そのままで、またはエステルとして各種精油の主成分として存在する。工業的にはシトラールの還元で合成する。
 ケヤキ
提供:ネイチャー・プロダクション
ケヤキ
提供:ネイチャー・プロダクション
 け‐やき【毛焼き】
①鳥の羽をむしったあと肌に残る細かい毛を火で焼くこと。〈日葡辞書〉
②(→)「けばやき」に同じ。
け‐やく
(「契約」から。青森・秋田県で)友だち。仲良し。
げ‐やく【下薬】
(→)下剤げざいに同じ。
げ‐やく【解薬】
解毒用の薬。解毒剤。毒消し。
けやけ・し
〔形ク〕
①きわだっている。普通とはちがっている。源氏物語藤裏葉「いと―・うもつかうまつるかな」。大鏡道長「末代には―・き寿もちて侍る翁なりかし」
②感情が害されるさまである。こしゃくである。源氏物語胡蝶「めざましかるべき際は、―・うなども覚えけれ」
③きわだってすぐれている。すばらしい。大鏡道長「貫之召し出でて歌つかうまつらしめ給へり。…それをだに―・きことに思ひ給へしに」
け‐やす・し【消易し】
〔形ク〕
消えやすい。はかない。万葉集5「朝露の―・き我が身」
け‐やっこ【毛奴】
奴をののしっていう語。浄瑠璃、双生隅田川「嘘つき奴の糟奴、黴の生へた―と笑ふて」
け‐やぶ・る【蹴破る】
〔他五〕
①蹴ってやぶる。
②蹴散らす。「敵軍を―・る」
③つまずいて足を傷つける。醒睡笑「あやまちに足を―・り」
けやむら‐ろくすけ【毛谷村六助】
①安土桃山時代の剣客。もと豊前国彦山の麓に住む百姓。浄瑠璃「彦山権現誓助剣ひこさんごんげんちかいのすけだち」の主人公。吉岡一味斎の娘を助けて父の仇を討たせたという。歌舞伎でも行われ、黄表紙・合巻・読本などにも脚色。
②「彦山権現誓助剣」の通称。
け‐やり【毛槍】
鞘を鳥毛で包んだ槍。大名行列の先頭などで振り歩く。
⇒けやり‐あたま【毛槍頭】
⇒けやり‐むし【毛槍虫】
けやり‐あたま【毛槍頭】
毛槍の先のような髪形をした頭。
⇒け‐やり【毛槍】
けやり‐むし【毛槍虫】
ケヤリ科の多毛類。体長約20センチメートル、環節約170個。体の前部は太く、後端は細くなる。多数の長い赤褐色の鰓糸さいしをもつ一対の鰓冠が頭端にある。太い棲管せいかんの先から鰓冠を房のように広げて呼吸・摂食する姿が毛槍を思わせる。中部日本以南に広く分布。ケヤリ。
けやりむし
け‐やき【毛焼き】
①鳥の羽をむしったあと肌に残る細かい毛を火で焼くこと。〈日葡辞書〉
②(→)「けばやき」に同じ。
け‐やく
(「契約」から。青森・秋田県で)友だち。仲良し。
げ‐やく【下薬】
(→)下剤げざいに同じ。
げ‐やく【解薬】
解毒用の薬。解毒剤。毒消し。
けやけ・し
〔形ク〕
①きわだっている。普通とはちがっている。源氏物語藤裏葉「いと―・うもつかうまつるかな」。大鏡道長「末代には―・き寿もちて侍る翁なりかし」
②感情が害されるさまである。こしゃくである。源氏物語胡蝶「めざましかるべき際は、―・うなども覚えけれ」
③きわだってすぐれている。すばらしい。大鏡道長「貫之召し出でて歌つかうまつらしめ給へり。…それをだに―・きことに思ひ給へしに」
け‐やす・し【消易し】
〔形ク〕
消えやすい。はかない。万葉集5「朝露の―・き我が身」
け‐やっこ【毛奴】
奴をののしっていう語。浄瑠璃、双生隅田川「嘘つき奴の糟奴、黴の生へた―と笑ふて」
け‐やぶ・る【蹴破る】
〔他五〕
①蹴ってやぶる。
②蹴散らす。「敵軍を―・る」
③つまずいて足を傷つける。醒睡笑「あやまちに足を―・り」
けやむら‐ろくすけ【毛谷村六助】
①安土桃山時代の剣客。もと豊前国彦山の麓に住む百姓。浄瑠璃「彦山権現誓助剣ひこさんごんげんちかいのすけだち」の主人公。吉岡一味斎の娘を助けて父の仇を討たせたという。歌舞伎でも行われ、黄表紙・合巻・読本などにも脚色。
②「彦山権現誓助剣」の通称。
け‐やり【毛槍】
鞘を鳥毛で包んだ槍。大名行列の先頭などで振り歩く。
⇒けやり‐あたま【毛槍頭】
⇒けやり‐むし【毛槍虫】
けやり‐あたま【毛槍頭】
毛槍の先のような髪形をした頭。
⇒け‐やり【毛槍】
けやり‐むし【毛槍虫】
ケヤリ科の多毛類。体長約20センチメートル、環節約170個。体の前部は太く、後端は細くなる。多数の長い赤褐色の鰓糸さいしをもつ一対の鰓冠が頭端にある。太い棲管せいかんの先から鰓冠を房のように広げて呼吸・摂食する姿が毛槍を思わせる。中部日本以南に広く分布。ケヤリ。
けやりむし
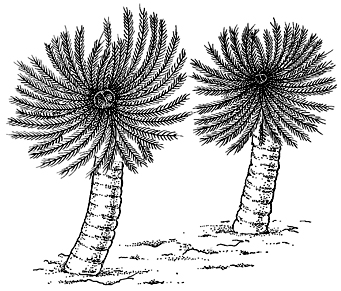 ケヤリムシ
提供:東京動物園協会
ケヤリムシ
提供:東京動物園協会
 ⇒け‐やり【毛槍】
げ‐ゆ【解由】
(解くる由よしの意)奈良・平安時代、国司などの任期が果てて交替する時、後任者から前任者に渡す、事務を滞りなく引き継いだ旨の文書。解由状。土佐日記「例の事ども皆しをへて―など取りて」
げ‐ゆう【外用】
〔仏〕外に現れる作用。さとりに基づいて外に現れた利他のはたらき。
げゆ‐じょう【解由状】‥ジヤウ
(→)解由に同じ。
げ‐よう【下用】
下層の人の食用とした、十分に搗つかない飯米。
⇒げよう‐びつ【下用櫃】
げよう‐びつ【下用櫃】
米櫃。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―には虚空蔵菩薩、米がないとせがまれ」
⇒げ‐よう【下用】
け‐よそい【褻装い】‥ヨソヒ
ふだんの服装。平服。久安百首「逢ふことは我が―のきぬなれや」
けら【鉧】
日本古来の製鋼法(けら押し、または、たたら吹き)による粗製品で、各種品質の鋼とスラグとの集合体。
けら【螻蛄・螻】
バッタ目ケラ科の昆虫。コオロギに似て、体長約3センチメートル。前肢は大きく、モグラのように土を掘るのに適する。夜行性で、よく灯火に来る。農作物を食害。土中で「じいい」と鳴く。これを俗に「みみずが鳴く」という。おけら。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉
けら
⇒け‐やり【毛槍】
げ‐ゆ【解由】
(解くる由よしの意)奈良・平安時代、国司などの任期が果てて交替する時、後任者から前任者に渡す、事務を滞りなく引き継いだ旨の文書。解由状。土佐日記「例の事ども皆しをへて―など取りて」
げ‐ゆう【外用】
〔仏〕外に現れる作用。さとりに基づいて外に現れた利他のはたらき。
げゆ‐じょう【解由状】‥ジヤウ
(→)解由に同じ。
げ‐よう【下用】
下層の人の食用とした、十分に搗つかない飯米。
⇒げよう‐びつ【下用櫃】
げよう‐びつ【下用櫃】
米櫃。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―には虚空蔵菩薩、米がないとせがまれ」
⇒げ‐よう【下用】
け‐よそい【褻装い】‥ヨソヒ
ふだんの服装。平服。久安百首「逢ふことは我が―のきぬなれや」
けら【鉧】
日本古来の製鋼法(けら押し、または、たたら吹き)による粗製品で、各種品質の鋼とスラグとの集合体。
けら【螻蛄・螻】
バッタ目ケラ科の昆虫。コオロギに似て、体長約3センチメートル。前肢は大きく、モグラのように土を掘るのに適する。夜行性で、よく灯火に来る。農作物を食害。土中で「じいい」と鳴く。これを俗に「みみずが鳴く」という。おけら。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉
けら
 ケラ
提供:ネイチャー・プロダクション
ケラ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒螻蛄の五能
⇒螻蛄の水渡り
⇒螻蛄腹立つれば鶫喜ぶ
けら【啄木鳥】
キツツキの別称。
ゲラ
(galleyの訛)
①組み上げた活字版を収める長方形の盤。2方または3方に縁がある。ゲラ箱。
②ゲラ刷ずりの略。
げ‐ら【下等】
〔代〕
(一人称)おれ。狂言、吃り「則ち―が事なり」
ケラー【Gottfried Keller】
スイスのドイツ系作家。写実主義の小説「緑のハインリヒ」、「ゼルトヴィーラの人々」「七つの伝説」「チューリヒ小説集」など。(1819〜1890)
ケラー【Helen Adams Keller】
アメリカの教育家・社会福祉事業家。2歳の時盲聾唖もうろうあとなったが力行りっこうして大学を卒業。身体障害者の援助に尽くす。3度来日。著「私の生涯」など。ヘレン=ケラー。(1880〜1968)
ヘレン‐ケラー
提供:毎日新聞社
⇒螻蛄の五能
⇒螻蛄の水渡り
⇒螻蛄腹立つれば鶫喜ぶ
けら【啄木鳥】
キツツキの別称。
ゲラ
(galleyの訛)
①組み上げた活字版を収める長方形の盤。2方または3方に縁がある。ゲラ箱。
②ゲラ刷ずりの略。
げ‐ら【下等】
〔代〕
(一人称)おれ。狂言、吃り「則ち―が事なり」
ケラー【Gottfried Keller】
スイスのドイツ系作家。写実主義の小説「緑のハインリヒ」、「ゼルトヴィーラの人々」「七つの伝説」「チューリヒ小説集」など。(1819〜1890)
ケラー【Helen Adams Keller】
アメリカの教育家・社会福祉事業家。2歳の時盲聾唖もうろうあとなったが力行りっこうして大学を卒業。身体障害者の援助に尽くす。3度来日。著「私の生涯」など。ヘレン=ケラー。(1880〜1968)
ヘレン‐ケラー
提供:毎日新聞社
 け‐らい【家来・家礼】
(中世以前では「家礼」「家頼」、近世は「家来」と書かれた。もと、子が父を敬い礼すること)
①貴人に礼を致すこと。今昔物語集22「―のためにかく参りたるに」
②朝廷の公事くじ・故実の作法を習うために摂家などに奉仕する者。太平記40「公家―の人々には」
③(主従の関係に転じて)武家に仕える者。家臣。転じて、従う者。部下。
④家に召し使う者。従者ずさ。従臣。家人けにん。
⇒けらい‐かまど【家来竈】
⇒けらい‐ぶん【家来分】
けらい‐かまど【家来竈】
(東北地方で)下男が主家から分家させてもらった家。→親竈おやかまど。
⇒け‐らい【家来・家礼】
けらい‐ぶん【家来分】
家来としての身分。家来なみの身分。
⇒け‐らい【家来・家礼】
け‐らく【快楽】
⇒かいらく。栄華物語本雫「忉利天女とうりてんにょの―を受けて」
⇒けらく‐ふたい【快楽不退】
けらく
(助動詞ケリのク語法)…したこと。万葉集18「神代より言ひ継ぎ―」
げ‐らく【下洛】
①比叡山などから京都の町へ下りること。平家物語1「山門の大衆夥しう―すと聞えしかば」
②都から地方へ下ること。↔上洛
げ‐らく【下落】
①物価・相場などが下がること。「株価が―する」↔騰貴。
②価値・等級などが下がること。↔上昇
けらく‐てん【化楽天】
〔仏〕六欲天の第5。ここに生まれたものは、自ら楽しい境遇を作り楽しみ、八千歳の寿命を保つという。楽変化天。化自楽天。化自在天。
けら‐くび【螻蛄首・螻首】
①槍の穂の刃と中茎なかごとの間の部分。塩首。→槍(図)。
②木材の継ぎ手の男木おぎの首がくびれた形をしたもの。→鎌継(図)。
③柄杓ひしゃくの部分名。柄裏の合ごうに指し込んだ際きわ。三つ角。→柄杓(図)
けらく‐ふたい【快楽不退】
快楽が永く続いて衰えないこと。
⇒け‐らく【快楽】
けら‐げい【螻蛄芸】
(→)「けらざい(螻蛄才)」に同じ。
けら‐けら
軽々しい感じの甲高い笑い声。
げら‐げら
無遠慮に大声で笑う声。
けら‐ざい【螻蛄才】
種々の芸を持っているが、一つも巧みなもののないこと。螻蛄芸。→螻蛄の五能
けらし
〔助動〕
(過去の助動詞ケリの連体形ケルに推量の助動詞ラシの付いたケルラシの約。ケリの形容詞化とも)
①過去の推定。…したらしい。万葉集6「諾うべしこそ見る人ごとに語りつぎ偲ひけらしき」
②「けり」の意を婉曲に述べ、詠嘆の意をこめる。…たのだなあ。…たことよ。鹿島紀行「まことに愛すべき山のすがたなりけらし」
ゲラ‐ずり【ゲラ刷】
組み上げた活字版をゲラに入れたまま校正用に試し刷りしたもの。校正刷。ゲラ。
ゲラダ‐ひひ【ゲラダ狒狒】
(gelada baboon)(ゲラダは現地語で狒狒の意)霊長目オナガザル科の猿。頭胴長は雄で約70センチメートル、雌で約55センチメートル。手足が黒いほかは全身褐色の毛で覆われ、雄の肩には長い毛が垂れる。標高2500〜4000メートルのエチオピア高原に分布、夜は断崖にかたまって眠る。ヒヒに似るが別属。ジェラダひひ。
ゲラダヒヒ
提供:東京動物園協会
け‐らい【家来・家礼】
(中世以前では「家礼」「家頼」、近世は「家来」と書かれた。もと、子が父を敬い礼すること)
①貴人に礼を致すこと。今昔物語集22「―のためにかく参りたるに」
②朝廷の公事くじ・故実の作法を習うために摂家などに奉仕する者。太平記40「公家―の人々には」
③(主従の関係に転じて)武家に仕える者。家臣。転じて、従う者。部下。
④家に召し使う者。従者ずさ。従臣。家人けにん。
⇒けらい‐かまど【家来竈】
⇒けらい‐ぶん【家来分】
けらい‐かまど【家来竈】
(東北地方で)下男が主家から分家させてもらった家。→親竈おやかまど。
⇒け‐らい【家来・家礼】
けらい‐ぶん【家来分】
家来としての身分。家来なみの身分。
⇒け‐らい【家来・家礼】
け‐らく【快楽】
⇒かいらく。栄華物語本雫「忉利天女とうりてんにょの―を受けて」
⇒けらく‐ふたい【快楽不退】
けらく
(助動詞ケリのク語法)…したこと。万葉集18「神代より言ひ継ぎ―」
げ‐らく【下洛】
①比叡山などから京都の町へ下りること。平家物語1「山門の大衆夥しう―すと聞えしかば」
②都から地方へ下ること。↔上洛
げ‐らく【下落】
①物価・相場などが下がること。「株価が―する」↔騰貴。
②価値・等級などが下がること。↔上昇
けらく‐てん【化楽天】
〔仏〕六欲天の第5。ここに生まれたものは、自ら楽しい境遇を作り楽しみ、八千歳の寿命を保つという。楽変化天。化自楽天。化自在天。
けら‐くび【螻蛄首・螻首】
①槍の穂の刃と中茎なかごとの間の部分。塩首。→槍(図)。
②木材の継ぎ手の男木おぎの首がくびれた形をしたもの。→鎌継(図)。
③柄杓ひしゃくの部分名。柄裏の合ごうに指し込んだ際きわ。三つ角。→柄杓(図)
けらく‐ふたい【快楽不退】
快楽が永く続いて衰えないこと。
⇒け‐らく【快楽】
けら‐げい【螻蛄芸】
(→)「けらざい(螻蛄才)」に同じ。
けら‐けら
軽々しい感じの甲高い笑い声。
げら‐げら
無遠慮に大声で笑う声。
けら‐ざい【螻蛄才】
種々の芸を持っているが、一つも巧みなもののないこと。螻蛄芸。→螻蛄の五能
けらし
〔助動〕
(過去の助動詞ケリの連体形ケルに推量の助動詞ラシの付いたケルラシの約。ケリの形容詞化とも)
①過去の推定。…したらしい。万葉集6「諾うべしこそ見る人ごとに語りつぎ偲ひけらしき」
②「けり」の意を婉曲に述べ、詠嘆の意をこめる。…たのだなあ。…たことよ。鹿島紀行「まことに愛すべき山のすがたなりけらし」
ゲラ‐ずり【ゲラ刷】
組み上げた活字版をゲラに入れたまま校正用に試し刷りしたもの。校正刷。ゲラ。
ゲラダ‐ひひ【ゲラダ狒狒】
(gelada baboon)(ゲラダは現地語で狒狒の意)霊長目オナガザル科の猿。頭胴長は雄で約70センチメートル、雌で約55センチメートル。手足が黒いほかは全身褐色の毛で覆われ、雄の肩には長い毛が垂れる。標高2500〜4000メートルのエチオピア高原に分布、夜は断崖にかたまって眠る。ヒヒに似るが別属。ジェラダひひ。
ゲラダヒヒ
提供:東京動物園協会
 ケラチン【Keratin ドイツ】
硬蛋白質の一つ。一般に化学試薬に対する抵抗力大。羽毛・爪・角・蹄ひづめ・毛髪などの主成分。脊椎動物の表皮、魚類・爬虫類の鱗うろこにも存在する。
けら‐つつき【啄木鳥】
キツツキの別称。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉
ゲラニオール【geraniol】
〔化〕分子式C10H18O バラの香りのある無色ないし淡黄色の液体。そのままで、またはエステルとして各種精油の主成分として存在する。工業的にはシトラールの還元で合成する。
ケラチン【Keratin ドイツ】
硬蛋白質の一つ。一般に化学試薬に対する抵抗力大。羽毛・爪・角・蹄ひづめ・毛髪などの主成分。脊椎動物の表皮、魚類・爬虫類の鱗うろこにも存在する。
けら‐つつき【啄木鳥】
キツツキの別称。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉
ゲラニオール【geraniol】
〔化〕分子式C10H18O バラの香りのある無色ないし淡黄色の液体。そのままで、またはエステルとして各種精油の主成分として存在する。工業的にはシトラールの還元で合成する。
広辞苑 ページ 6268 での【○気も無い】単語。