複数辞典一括検索+![]()
![]()
○孔席暖まらず、墨突黔まずこうせきあたたまらずぼくとつくろまず🔗⭐🔉
○孔席暖まらず、墨突黔まずこうせきあたたまらずぼくとつくろまず
[班固、賓の戯たわむれしに答う]孔子・墨子の二人は忙しく天下を歩きまわり、家に落ちついていなかったため、孔子の座席は暖まることなく、また、墨子の家の煙突は炊煙で黒くなることがなかった。道を伝えるために東奔西走すること。
⇒こう‐せき【孔席】
こうせき‐うん【高積雲】カウ‥
十種雲級の一つ。中層雲に属し、白色または灰色で、大きい丸みのある雲団。水滴から成る。高さは中緯度帯では2〜7キロメートル。羊雲。むら雲。記号Ac →雲級(表)
高積雲
撮影:高橋健司
 こうせき‐おとし【鉱石落し】クワウ‥
採鉱場から下位の坑道に鉱石を落とし、鉱車に積み入れるための設備。シュート。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐けんぱき【鉱石検波器】クワウ‥
鉱物と金属針との接触面の整流作用を利用した検波器。初期のラジオ受信に用いた。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐こう【黄石公】クワウ‥
秦末の隠士。漢の張良に兵書を授けたという老人。圯上老人いじょうろうじん。
こうせき‐こうぶつ【鉱石鉱物】クワウ‥クワウ‥
鉱石を構成する鉱物。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせきしき‐じゅしんき【鉱石式受信機】クワウ‥
鉱石検波器を用いた簡単なラジオ受信機。鉱石ラジオ。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐せい【洪積世】
(→)更新世に同じ。氷期に広域をおおった氷床の堆積物を大洪水の堆積物と誤認したところからの名。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐そう【洪積層】
①洪積世に形成された地層。
②中部ヨーロッパにおいて、台地を作って広く分布する砂礫層。かつて大洪水の堆積物と考えられた。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐だいち【洪積台地】
洪積層の構成する台地。洪積世(更新世)に形成された扇状地・三角洲などが隆起してやや浸食されたもの。武蔵野台地・下総台地など。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐とう【洪積統】
(→)洪積層1に同じ。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐どじょう【洪積土壌】‥ジヤウ
洪積層の上に発達した土壌。高師ヶ原や三方ヶ原など洪積段丘上の土壌で、東海地方から西南日本では黄褐色・赤褐色を呈するものが多い。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐ほう【鉱石法】クワウ‥ハフ
平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄より銑鉄の割合を多くし(60〜70パーセント)、酸化剤として多量の鉄鉱石を用いて操業する方法。鉱石中の酸化鉄が炭素・酸化炭素によって還元され鉄となり、炭素を吸収する。↔屑鉄法
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐りだつ【皇籍離脱】クワウ‥
皇族がその身分を離れて一般の国民となること。皇太子・皇太孫を除く皇族は皇室会議の議を経ればそれができる。旧制の臣籍降下に当たる。
⇒こう‐せき【皇籍】
こう‐ぜち【講説】カウ‥
(ゼチは呉音)講師こうじの説法。源氏物語鈴虫「―の折は、大方の鳴りをしづめて」
こう‐せつ【公設】
国家または公共団体が設立すること。↔私設。
⇒こうせつ‐いちば【公設市場】
⇒こうせつ‐しちや【公設質屋】
こう‐せつ【巧拙】カウ‥
巧みなこととまずいこと。上手と下手へた。「―を論じる」
こう‐せつ【交接】カウ‥
①まじわり近づくこと。交際。
②性交。交尾。
こう‐せつ【狎褻】カフ‥
なれてみだらになること。
こう‐せつ【巷説】カウ‥
ちまたのうわさ。世間のとりざた。風説。「―にまどわされる」
こう‐せつ【紅雪】
(→)赤雪せきせつに同じ。
こう‐せつ【荒説】クワウ‥
でたらめな説。取りとめのない風説。
こう‐せつ【降雪】カウ‥
雪のふること。また、ふった雪。
⇒こうせつ‐りょう【降雪量】
こう‐せつ【高節】カウ‥
けだかい節操。すぐれたみさお。
こう‐せつ【高説】カウ‥
①すぐれた説。
②他人の説の尊敬語。「御―を拝聴する」
こう‐せつ【膠接】カウ‥
ねばりつくこと。
こう‐せつ【講説】カウ‥
(コウゼツとも)講義して説明すること。また、その講義。日葡辞書「キャウヲカウゼッスル」
こう‐ぜつ【口舌】
①くちとした。
②ものいい。くちさき。弁舌。
⇒こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】
⇒こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
⇒こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
こう‐ぜつ【黄舌】クワウ‥
音声のまだ若くてととのわないこと。黄口こうこうの舌。謡曲、歌占「―の囀り」
こう‐ぜつ【喉舌】
のどとした。すなわち、ことばを発する大切なところ。
⇒こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】
ごう‐せつ【豪雪】ガウ‥
大量の降雪。大雪おおゆき。「―地帯」
こうせつ‐いちば【公設市場】
生活必需品を公正な価格で需要者に供給するため公設された市場。
⇒こう‐せつ【公設】
こうせつ‐おんしょう【高設温床】カウ‥ヲンシヤウ
発熱部が地上にある温床。排水不良の土地などで用いる。
こう‐せっけん【硬石鹸】カウセキ‥
(→)ソーダ石鹸に同じ。
こう‐せっこう【硬石膏】カウセキカウ
硫酸カルシウムの鉱物。斜方晶系で、白色または淡青色。
こうせつ‐しちや【公設質屋】
(→)公益質屋に同じ。
⇒こう‐せつ【公設】
ごう‐せっ‐とう【強窃盗】ガウ‥タウ
強盗と窃盗。
こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】‥アラソヒ
言いあらそい。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】‥クワン
[詩経大雅、烝民](君主の言葉を下へ伝える者の意)宰相。日本で、大納言の異称。
⇒こう‐ぜつ【喉舌】
こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
弁舌だけにすぐれて、実行力のない者。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
弁舌の巧みな人。口達者くちだっしゃ。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうせつ‐りょう【降雪量】カウ‥リヤウ
地上に降った雪の量。融かして液体の水にしたときの深さをミリメートルの単位で測ることが多い。その値を10倍すると積雪深に近くなる。→降水量
⇒こう‐せつ【降雪】
こう‐せん【口占】
①くちずさむこと。
②口づてに人に伝えること。
こう‐せん【口宣】
口で述べること。
こう‐せん【口銭・貢銭】
売買の仲介をした手数料。問屋口銭。コミッション。「五分の―を取る」→くちせん
こう‐せん【工専】
旧制の工業専門学校の略称。
こう‐せん【工船】
加工設備を船内に有し、漁獲物をただちに擂すり身・冷凍魚・魚粉などに加工する船。擂り身工船・冷凍工船の類。
こう‐せん【工銭】
工事の手間賃。工賃。
こう‐せん【公船】
①私法上、公用に供する船舶。多くは官公署の所有に属する。軍艦・測量船・練習船の類。
②国際法上、国家の公権を行使する船舶。軍艦、警察用・税関用の船舶の類。
こう‐せん【公賤】
(→)官賤に同じ。
こう‐せん【公選】
①公正な手段で選ぶこと。
②公共の職務に就く者を広く一般国民の投票によって選挙すること。「知事―」↔官選
こうせん【勾践・句践】
春秋時代の越の王。父王の頃から呉と争い、父の没後、呉王闔閭こうりょを敗死させたが、前494年闔閭の子夫差に囚われ、ようやく赦されて帰り、のち范蠡はんれいと謀って前477年遂に呉を討滅。( 〜前465)→臥薪嘗胆がしんしょうたん→会稽かいけいの恥
こう‐せん【功銭】
①奈良・平安時代、雇われた者に対する工賃で、銭貨で支払われるもの。布帛ふはくで支払われるものを功布、稲穀で支払われるものを功稲こうとうという。
②鎌倉時代、幕府の家人けにんなどが官に就く時の官への献金。
こう‐せん【広宣】クワウ‥
〔仏〕広く仏法を宣布すること。「―流布るふ」
こう‐せん【交戦】カウ‥
戦いを交えること。相戦うこと。互いに兵力を以て戦闘行為をなすこと。
⇒こうせん‐くいき【交戦区域】
⇒こうせん‐けん【交戦権】
⇒こうせん‐こく【交戦国】
⇒こうせん‐だんたい【交戦団体】
⇒こうせん‐ほうき【交戦法規】
こう‐せん【交線】カウ‥
平面と平面とが交わってできる線。特に、2平面の交わりをいう。
こう‐せん【光線】クワウ‥
①ひかり。光のさすすじ。
②光が空間を伝播する様子を光のエネルギーの流れる経路で表す線。
⇒こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】
こう‐せん【好戦】カウ‥
戦いを好むこと。すぐ武力に訴えようとすること。
⇒こうせん‐てき【好戦的】
こう‐せん【抗戦】カウ‥
抵抗してたたかうこと。「徹底―」
こう‐せん【攻戦】
攻め戦うこと。
こう‐せん【後先】
あとさき。先後。前後。
こう‐せん【香煎】カウ‥
①麦・米などを炒いって挽いた粉。砂糖を混ぜてそのまま、あるいは水や湯で練って食べる。また、菓子の材料に用いる。はったい。いりむぎ。麦こがし。
②山椒や薬草の粉などを調合したもの。湯をそそいで飲む。香煎湯。
こう‐せん【香饌】カウ‥
(→)施物せもつに同じ。
こう‐せん【高専】カウ‥
①高等専門学校の略称。
②旧制の高等学校・専門学校を総称する略称。
こう‐せん【黄泉】クワウ‥
(中国で、地の色を黄に配するからいう)
①地下の泉。
②死者の行く所。よみ。よみじ。冥土。九泉きゅうせん。平家物語6「―中有ちゅううの旅の空に」
こう‐せん【黄筌】クワウ‥
五代(蜀)の画家。字は要叔。四川成都の人。花鳥画にすぐれ、明確な輪郭線と濃厚な着色とによる精密な画風は黄氏体と呼ばれて、徐
こうせき‐おとし【鉱石落し】クワウ‥
採鉱場から下位の坑道に鉱石を落とし、鉱車に積み入れるための設備。シュート。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐けんぱき【鉱石検波器】クワウ‥
鉱物と金属針との接触面の整流作用を利用した検波器。初期のラジオ受信に用いた。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐こう【黄石公】クワウ‥
秦末の隠士。漢の張良に兵書を授けたという老人。圯上老人いじょうろうじん。
こうせき‐こうぶつ【鉱石鉱物】クワウ‥クワウ‥
鉱石を構成する鉱物。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせきしき‐じゅしんき【鉱石式受信機】クワウ‥
鉱石検波器を用いた簡単なラジオ受信機。鉱石ラジオ。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐せい【洪積世】
(→)更新世に同じ。氷期に広域をおおった氷床の堆積物を大洪水の堆積物と誤認したところからの名。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐そう【洪積層】
①洪積世に形成された地層。
②中部ヨーロッパにおいて、台地を作って広く分布する砂礫層。かつて大洪水の堆積物と考えられた。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐だいち【洪積台地】
洪積層の構成する台地。洪積世(更新世)に形成された扇状地・三角洲などが隆起してやや浸食されたもの。武蔵野台地・下総台地など。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐とう【洪積統】
(→)洪積層1に同じ。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐どじょう【洪積土壌】‥ジヤウ
洪積層の上に発達した土壌。高師ヶ原や三方ヶ原など洪積段丘上の土壌で、東海地方から西南日本では黄褐色・赤褐色を呈するものが多い。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐ほう【鉱石法】クワウ‥ハフ
平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄より銑鉄の割合を多くし(60〜70パーセント)、酸化剤として多量の鉄鉱石を用いて操業する方法。鉱石中の酸化鉄が炭素・酸化炭素によって還元され鉄となり、炭素を吸収する。↔屑鉄法
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐りだつ【皇籍離脱】クワウ‥
皇族がその身分を離れて一般の国民となること。皇太子・皇太孫を除く皇族は皇室会議の議を経ればそれができる。旧制の臣籍降下に当たる。
⇒こう‐せき【皇籍】
こう‐ぜち【講説】カウ‥
(ゼチは呉音)講師こうじの説法。源氏物語鈴虫「―の折は、大方の鳴りをしづめて」
こう‐せつ【公設】
国家または公共団体が設立すること。↔私設。
⇒こうせつ‐いちば【公設市場】
⇒こうせつ‐しちや【公設質屋】
こう‐せつ【巧拙】カウ‥
巧みなこととまずいこと。上手と下手へた。「―を論じる」
こう‐せつ【交接】カウ‥
①まじわり近づくこと。交際。
②性交。交尾。
こう‐せつ【狎褻】カフ‥
なれてみだらになること。
こう‐せつ【巷説】カウ‥
ちまたのうわさ。世間のとりざた。風説。「―にまどわされる」
こう‐せつ【紅雪】
(→)赤雪せきせつに同じ。
こう‐せつ【荒説】クワウ‥
でたらめな説。取りとめのない風説。
こう‐せつ【降雪】カウ‥
雪のふること。また、ふった雪。
⇒こうせつ‐りょう【降雪量】
こう‐せつ【高節】カウ‥
けだかい節操。すぐれたみさお。
こう‐せつ【高説】カウ‥
①すぐれた説。
②他人の説の尊敬語。「御―を拝聴する」
こう‐せつ【膠接】カウ‥
ねばりつくこと。
こう‐せつ【講説】カウ‥
(コウゼツとも)講義して説明すること。また、その講義。日葡辞書「キャウヲカウゼッスル」
こう‐ぜつ【口舌】
①くちとした。
②ものいい。くちさき。弁舌。
⇒こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】
⇒こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
⇒こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
こう‐ぜつ【黄舌】クワウ‥
音声のまだ若くてととのわないこと。黄口こうこうの舌。謡曲、歌占「―の囀り」
こう‐ぜつ【喉舌】
のどとした。すなわち、ことばを発する大切なところ。
⇒こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】
ごう‐せつ【豪雪】ガウ‥
大量の降雪。大雪おおゆき。「―地帯」
こうせつ‐いちば【公設市場】
生活必需品を公正な価格で需要者に供給するため公設された市場。
⇒こう‐せつ【公設】
こうせつ‐おんしょう【高設温床】カウ‥ヲンシヤウ
発熱部が地上にある温床。排水不良の土地などで用いる。
こう‐せっけん【硬石鹸】カウセキ‥
(→)ソーダ石鹸に同じ。
こう‐せっこう【硬石膏】カウセキカウ
硫酸カルシウムの鉱物。斜方晶系で、白色または淡青色。
こうせつ‐しちや【公設質屋】
(→)公益質屋に同じ。
⇒こう‐せつ【公設】
ごう‐せっ‐とう【強窃盗】ガウ‥タウ
強盗と窃盗。
こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】‥アラソヒ
言いあらそい。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】‥クワン
[詩経大雅、烝民](君主の言葉を下へ伝える者の意)宰相。日本で、大納言の異称。
⇒こう‐ぜつ【喉舌】
こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
弁舌だけにすぐれて、実行力のない者。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
弁舌の巧みな人。口達者くちだっしゃ。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうせつ‐りょう【降雪量】カウ‥リヤウ
地上に降った雪の量。融かして液体の水にしたときの深さをミリメートルの単位で測ることが多い。その値を10倍すると積雪深に近くなる。→降水量
⇒こう‐せつ【降雪】
こう‐せん【口占】
①くちずさむこと。
②口づてに人に伝えること。
こう‐せん【口宣】
口で述べること。
こう‐せん【口銭・貢銭】
売買の仲介をした手数料。問屋口銭。コミッション。「五分の―を取る」→くちせん
こう‐せん【工専】
旧制の工業専門学校の略称。
こう‐せん【工船】
加工設備を船内に有し、漁獲物をただちに擂すり身・冷凍魚・魚粉などに加工する船。擂り身工船・冷凍工船の類。
こう‐せん【工銭】
工事の手間賃。工賃。
こう‐せん【公船】
①私法上、公用に供する船舶。多くは官公署の所有に属する。軍艦・測量船・練習船の類。
②国際法上、国家の公権を行使する船舶。軍艦、警察用・税関用の船舶の類。
こう‐せん【公賤】
(→)官賤に同じ。
こう‐せん【公選】
①公正な手段で選ぶこと。
②公共の職務に就く者を広く一般国民の投票によって選挙すること。「知事―」↔官選
こうせん【勾践・句践】
春秋時代の越の王。父王の頃から呉と争い、父の没後、呉王闔閭こうりょを敗死させたが、前494年闔閭の子夫差に囚われ、ようやく赦されて帰り、のち范蠡はんれいと謀って前477年遂に呉を討滅。( 〜前465)→臥薪嘗胆がしんしょうたん→会稽かいけいの恥
こう‐せん【功銭】
①奈良・平安時代、雇われた者に対する工賃で、銭貨で支払われるもの。布帛ふはくで支払われるものを功布、稲穀で支払われるものを功稲こうとうという。
②鎌倉時代、幕府の家人けにんなどが官に就く時の官への献金。
こう‐せん【広宣】クワウ‥
〔仏〕広く仏法を宣布すること。「―流布るふ」
こう‐せん【交戦】カウ‥
戦いを交えること。相戦うこと。互いに兵力を以て戦闘行為をなすこと。
⇒こうせん‐くいき【交戦区域】
⇒こうせん‐けん【交戦権】
⇒こうせん‐こく【交戦国】
⇒こうせん‐だんたい【交戦団体】
⇒こうせん‐ほうき【交戦法規】
こう‐せん【交線】カウ‥
平面と平面とが交わってできる線。特に、2平面の交わりをいう。
こう‐せん【光線】クワウ‥
①ひかり。光のさすすじ。
②光が空間を伝播する様子を光のエネルギーの流れる経路で表す線。
⇒こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】
こう‐せん【好戦】カウ‥
戦いを好むこと。すぐ武力に訴えようとすること。
⇒こうせん‐てき【好戦的】
こう‐せん【抗戦】カウ‥
抵抗してたたかうこと。「徹底―」
こう‐せん【攻戦】
攻め戦うこと。
こう‐せん【後先】
あとさき。先後。前後。
こう‐せん【香煎】カウ‥
①麦・米などを炒いって挽いた粉。砂糖を混ぜてそのまま、あるいは水や湯で練って食べる。また、菓子の材料に用いる。はったい。いりむぎ。麦こがし。
②山椒や薬草の粉などを調合したもの。湯をそそいで飲む。香煎湯。
こう‐せん【香饌】カウ‥
(→)施物せもつに同じ。
こう‐せん【高専】カウ‥
①高等専門学校の略称。
②旧制の高等学校・専門学校を総称する略称。
こう‐せん【黄泉】クワウ‥
(中国で、地の色を黄に配するからいう)
①地下の泉。
②死者の行く所。よみ。よみじ。冥土。九泉きゅうせん。平家物語6「―中有ちゅううの旅の空に」
こう‐せん【黄筌】クワウ‥
五代(蜀)の画家。字は要叔。四川成都の人。花鳥画にすぐれ、明確な輪郭線と濃厚な着色とによる精密な画風は黄氏体と呼ばれて、徐 じょきの徐氏体と対比され、院体花鳥画の基礎をなした。( 〜965)
こう‐せん【腔線】カウ‥
銃砲身の内面に螺旋らせん状に彫った溝。発射弾に回転運動を与え弾道を安定させる。腔綫。ライフル。
こう‐せん【鉱泉】クワウ‥
鉱物質またはガスを多量に含む泉水。広義には温泉と冷泉との総称で、狭義には冷泉だけをいう。→温泉。
⇒こうせん‐えん【鉱泉塩】
こう‐せん【鋼船】カウ‥
鋼鉄で造った船。
こう‐せん【講銭】カウ‥
講中の掛け金。
こう‐ぜん【公然】
①おおっぴらなさま。一般に知れわたったさま。おもてむき。「白昼―と押し入る」「―たる事実」
②〔法〕ある事柄を不特定多数の人または利害関係ある人に秘密にせず、明白な形式でするさま。
⇒こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
⇒こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
こう‐ぜん【呷然】カフ‥
大声をあげるさま。内田魯庵、くれの廿八日「独り黒斜子の五紋は―として笑出した」
こう‐ぜん【哄然】
どっと笑うさま。
こう‐ぜん【昂然】カウ‥
自負があって意気のあがるさま。「―たる態度」「―として言い放つ」
こう‐ぜん【紅髯】
①あかいひげ。
②西洋人のひげ。また、西洋人。
③エビの異称。
こう‐ぜん【浩然】カウ‥
①水が盛んに流れるさま。
②心などが広くゆったりしているさま。「―たる態度」
⇒こうぜん‐の‐き【浩然の気】
こう‐ぜん【耿然】カウ‥
明るいさま。心のはればれとしたさま。
こう‐ぜん【皓然】カウ‥
白いさま。明らかなさま。「―たる月光」
こう‐ぜん【煌然】クワウ‥
かがやくさま。
こう‐ぜん【曠然】クワウ‥
広々としたさま。「―たる原野」
こう‐ぜん【鏗然】カウ‥
金属・石など堅いものが当たってかん高い音の出るさま。
ごう‐せん【合繊】ガフ‥
合成繊維の略。
ごう‐ぜん【傲然】ガウ‥
おごりたかぶるさま。「―と肩をそびやかす」「―たる態度」
ごう‐ぜん【豪然】ガウ‥
力強く、すぐれているさま。また、尊大で、おごっているさま。
ごう‐ぜん【囂然】ガウ‥
かまびすしいさま。「場内―」
ごう‐ぜん【轟然】ガウ‥
とどろき響くさま。「―たる発射音」
こうせん‐えん【鉱泉塩】クワウ‥
鉱泉を蒸発させて得た塩類。また、人工的にこれを模造した塩類。
⇒こう‐せん【鉱泉】
こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】クワウ‥クワ‥シヤウ
通常は異常を起こさない量や波長の光線で発赤・皮疹などの皮膚症状を起こす病態。多形日光疹・日光蕁じん麻疹・色素性乾皮症・ポルフィリン症などがある。
⇒こう‐せん【光線】
こう‐せんきょ【閘船渠】カフ‥
ドックの一種。潮汐の大きな港で、満潮を利用して船舶の出入・碇繋ていけいをさせるため、入口に閘門を備え、干潮でも水深を一定に保たせる。繋船ドック。
こうせん‐くいき【交戦区域】カウ‥ヰキ
交戦国兵力が互いに敵対行為を行い得べき地域。交戦国の領土・領海・領空ならびに公海などで、中立領域を含まない。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐くうご【曠前空後】クワウ‥
後にも先にもないこと。きわめて珍しいこと。空前絶後。
こうせん‐けん【交戦権】カウ‥
国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に行使し得る権利。自衛のための交戦権の有無が日本国憲法第9条の解釈上の一争点となっている。
→参照条文:日本国憲法第9条
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐こく【交戦国】カウ‥
戦争の当事者たる国家。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜんごこくろん【興禅護国論】
栄西の著。3巻。1198年(建久9)成る。栄西が宋から帰朝して禅宗を伝えた時にまき起こった仏教界からの非難に対して、禅による国家の繁栄を主張したもの。
こう‐せんし【高仙芝】カウ‥
高句麗出身の唐の武将。西域経営に功績をたて安西都護となる。751年、タラス河畔の戦でアッバース軍に大敗。( 〜755)
こうせん‐だんたい【交戦団体】カウ‥
国際法上の交戦者としての資格を認められた反乱団体。「―の承認」
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐てき【好戦的】カウ‥
戦いを好む傾向のあるさま。「―な部族」
⇒こう‐せん【好戦】
こうせん‐とう【交閃灯】カウ‥
回転して異なった色の光を交互に放つ灯火。
こうぜん‐の‐き【浩然の気】カウ‥
[孟子公孫丑上「我善く吾が浩然の気を養う」]
①天地の間に満ち満ちている非常に盛んな精気。
②俗事から解放された屈託のない心境。「―を養う」
⇒こう‐ぜん【浩然】
こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
表向き秘密であることにはなっているが、実際には世間に知れ渡ってしまっていること。
⇒こう‐ぜん【公然】
こうせん‐ほうき【交戦法規】カウ‥ハフ‥
戦争の当事者がどのような戦闘手段を用いることを許されるかなど、交戦国の行動を律する国際法規。近年は、戦争犠牲者の保護を目的とする国際人道法の一部分として扱われることもある。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
不特定・多数の人が認識できる状態で猥褻の行為をする罪。→猥褻罪
⇒こう‐ぜん【公然】
こう‐そ【公租】
おおやけの目的のために課せられる金銭負担の一つ。国税・地方税の総称。「―公課」
こう‐そ【公訴】
〔法〕
①刑事に関する訴訟。
②刑事に関して検察官が起訴状を提出して裁判所の審判を求めること。「―権」「―の提起」
⇒こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
⇒こうそ‐じこう【公訴時効】
⇒こうそ‐じじつ【公訴事実】
こうそ【江蘇】カウ‥
(Jiangsu)中国東部、長江下流の沿海の省。面積約10万平方キロメートル。省南部の長江デルタ地帯には上海と南京を結ぶ交通線上に新興工業都市が林立。稲作灌漑のため全省に運河・クリークが発達し、全国有数の穀倉地帯。省都は南京。略称、蘇。→中華人民共和国(図)
こう‐そ【後素】
[論語八佾「絵事後素」]絵画。絵。→絵事かいじは素を後にす(「絵事」成句)
こう‐そ【皇祖】クワウ‥
天皇の先祖。天照大神あまてらすおおみかみまたは神武天皇の称。また、天照大神から神武天皇まで代々の総称。→皇宗。
⇒こうそ‐こうそう【皇祖皇宗】
こう‐そ【皇祚】クワウ‥
天皇の位。帝位。
こう‐そ【貢租】
田地に課せられる租税。ねんぐ。
こう‐そ【高祖】カウ‥
①祖父母の祖父母。
②遠い祖先。
③一宗一派を開いた僧を敬っていう語。「―日蓮」
④中国王朝で最初の天子。特に、漢の劉邦および唐の李淵。
こう‐そ【控訴】
〔法〕第一審の判決を不服とする場合に、その取消し・変更を直接上級裁判所に求める訴訟手続。
⇒こうそ‐いん【控訴院】
⇒こうそ‐きかん【控訴期間】
⇒こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
⇒こうそ‐さいばんしょ【控訴裁判所】
⇒こうそ‐しゅいしょ【控訴趣意書】
⇒こうそ‐しん【控訴審】
⇒こうそ‐にん【控訴人】
こう‐そ【酵素】カウ‥
(enzyme)生体内で営まれる化学反応に触媒として作用する高分子物質。生体内で物質代謝に関与する。蛋白質またはこれと補酵素と呼ばれる低分子物質との複合体。触媒する反応の型によってオキシダーゼ・レダクターゼ・ヒドロラーゼ・デヒドロゲナーゼ・イソメラーゼなどに分類され、それぞれ特定の化合物に対して特異的に作用する。熱・金属イオンなどによって活性を失う。エンザイム。
酵素の分類(表)
じょきの徐氏体と対比され、院体花鳥画の基礎をなした。( 〜965)
こう‐せん【腔線】カウ‥
銃砲身の内面に螺旋らせん状に彫った溝。発射弾に回転運動を与え弾道を安定させる。腔綫。ライフル。
こう‐せん【鉱泉】クワウ‥
鉱物質またはガスを多量に含む泉水。広義には温泉と冷泉との総称で、狭義には冷泉だけをいう。→温泉。
⇒こうせん‐えん【鉱泉塩】
こう‐せん【鋼船】カウ‥
鋼鉄で造った船。
こう‐せん【講銭】カウ‥
講中の掛け金。
こう‐ぜん【公然】
①おおっぴらなさま。一般に知れわたったさま。おもてむき。「白昼―と押し入る」「―たる事実」
②〔法〕ある事柄を不特定多数の人または利害関係ある人に秘密にせず、明白な形式でするさま。
⇒こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
⇒こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
こう‐ぜん【呷然】カフ‥
大声をあげるさま。内田魯庵、くれの廿八日「独り黒斜子の五紋は―として笑出した」
こう‐ぜん【哄然】
どっと笑うさま。
こう‐ぜん【昂然】カウ‥
自負があって意気のあがるさま。「―たる態度」「―として言い放つ」
こう‐ぜん【紅髯】
①あかいひげ。
②西洋人のひげ。また、西洋人。
③エビの異称。
こう‐ぜん【浩然】カウ‥
①水が盛んに流れるさま。
②心などが広くゆったりしているさま。「―たる態度」
⇒こうぜん‐の‐き【浩然の気】
こう‐ぜん【耿然】カウ‥
明るいさま。心のはればれとしたさま。
こう‐ぜん【皓然】カウ‥
白いさま。明らかなさま。「―たる月光」
こう‐ぜん【煌然】クワウ‥
かがやくさま。
こう‐ぜん【曠然】クワウ‥
広々としたさま。「―たる原野」
こう‐ぜん【鏗然】カウ‥
金属・石など堅いものが当たってかん高い音の出るさま。
ごう‐せん【合繊】ガフ‥
合成繊維の略。
ごう‐ぜん【傲然】ガウ‥
おごりたかぶるさま。「―と肩をそびやかす」「―たる態度」
ごう‐ぜん【豪然】ガウ‥
力強く、すぐれているさま。また、尊大で、おごっているさま。
ごう‐ぜん【囂然】ガウ‥
かまびすしいさま。「場内―」
ごう‐ぜん【轟然】ガウ‥
とどろき響くさま。「―たる発射音」
こうせん‐えん【鉱泉塩】クワウ‥
鉱泉を蒸発させて得た塩類。また、人工的にこれを模造した塩類。
⇒こう‐せん【鉱泉】
こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】クワウ‥クワ‥シヤウ
通常は異常を起こさない量や波長の光線で発赤・皮疹などの皮膚症状を起こす病態。多形日光疹・日光蕁じん麻疹・色素性乾皮症・ポルフィリン症などがある。
⇒こう‐せん【光線】
こう‐せんきょ【閘船渠】カフ‥
ドックの一種。潮汐の大きな港で、満潮を利用して船舶の出入・碇繋ていけいをさせるため、入口に閘門を備え、干潮でも水深を一定に保たせる。繋船ドック。
こうせん‐くいき【交戦区域】カウ‥ヰキ
交戦国兵力が互いに敵対行為を行い得べき地域。交戦国の領土・領海・領空ならびに公海などで、中立領域を含まない。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐くうご【曠前空後】クワウ‥
後にも先にもないこと。きわめて珍しいこと。空前絶後。
こうせん‐けん【交戦権】カウ‥
国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に行使し得る権利。自衛のための交戦権の有無が日本国憲法第9条の解釈上の一争点となっている。
→参照条文:日本国憲法第9条
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐こく【交戦国】カウ‥
戦争の当事者たる国家。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜんごこくろん【興禅護国論】
栄西の著。3巻。1198年(建久9)成る。栄西が宋から帰朝して禅宗を伝えた時にまき起こった仏教界からの非難に対して、禅による国家の繁栄を主張したもの。
こう‐せんし【高仙芝】カウ‥
高句麗出身の唐の武将。西域経営に功績をたて安西都護となる。751年、タラス河畔の戦でアッバース軍に大敗。( 〜755)
こうせん‐だんたい【交戦団体】カウ‥
国際法上の交戦者としての資格を認められた反乱団体。「―の承認」
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐てき【好戦的】カウ‥
戦いを好む傾向のあるさま。「―な部族」
⇒こう‐せん【好戦】
こうせん‐とう【交閃灯】カウ‥
回転して異なった色の光を交互に放つ灯火。
こうぜん‐の‐き【浩然の気】カウ‥
[孟子公孫丑上「我善く吾が浩然の気を養う」]
①天地の間に満ち満ちている非常に盛んな精気。
②俗事から解放された屈託のない心境。「―を養う」
⇒こう‐ぜん【浩然】
こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
表向き秘密であることにはなっているが、実際には世間に知れ渡ってしまっていること。
⇒こう‐ぜん【公然】
こうせん‐ほうき【交戦法規】カウ‥ハフ‥
戦争の当事者がどのような戦闘手段を用いることを許されるかなど、交戦国の行動を律する国際法規。近年は、戦争犠牲者の保護を目的とする国際人道法の一部分として扱われることもある。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
不特定・多数の人が認識できる状態で猥褻の行為をする罪。→猥褻罪
⇒こう‐ぜん【公然】
こう‐そ【公租】
おおやけの目的のために課せられる金銭負担の一つ。国税・地方税の総称。「―公課」
こう‐そ【公訴】
〔法〕
①刑事に関する訴訟。
②刑事に関して検察官が起訴状を提出して裁判所の審判を求めること。「―権」「―の提起」
⇒こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
⇒こうそ‐じこう【公訴時効】
⇒こうそ‐じじつ【公訴事実】
こうそ【江蘇】カウ‥
(Jiangsu)中国東部、長江下流の沿海の省。面積約10万平方キロメートル。省南部の長江デルタ地帯には上海と南京を結ぶ交通線上に新興工業都市が林立。稲作灌漑のため全省に運河・クリークが発達し、全国有数の穀倉地帯。省都は南京。略称、蘇。→中華人民共和国(図)
こう‐そ【後素】
[論語八佾「絵事後素」]絵画。絵。→絵事かいじは素を後にす(「絵事」成句)
こう‐そ【皇祖】クワウ‥
天皇の先祖。天照大神あまてらすおおみかみまたは神武天皇の称。また、天照大神から神武天皇まで代々の総称。→皇宗。
⇒こうそ‐こうそう【皇祖皇宗】
こう‐そ【皇祚】クワウ‥
天皇の位。帝位。
こう‐そ【貢租】
田地に課せられる租税。ねんぐ。
こう‐そ【高祖】カウ‥
①祖父母の祖父母。
②遠い祖先。
③一宗一派を開いた僧を敬っていう語。「―日蓮」
④中国王朝で最初の天子。特に、漢の劉邦および唐の李淵。
こう‐そ【控訴】
〔法〕第一審の判決を不服とする場合に、その取消し・変更を直接上級裁判所に求める訴訟手続。
⇒こうそ‐いん【控訴院】
⇒こうそ‐きかん【控訴期間】
⇒こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
⇒こうそ‐さいばんしょ【控訴裁判所】
⇒こうそ‐しゅいしょ【控訴趣意書】
⇒こうそ‐しん【控訴審】
⇒こうそ‐にん【控訴人】
こう‐そ【酵素】カウ‥
(enzyme)生体内で営まれる化学反応に触媒として作用する高分子物質。生体内で物質代謝に関与する。蛋白質またはこれと補酵素と呼ばれる低分子物質との複合体。触媒する反応の型によってオキシダーゼ・レダクターゼ・ヒドロラーゼ・デヒドロゲナーゼ・イソメラーゼなどに分類され、それぞれ特定の化合物に対して特異的に作用する。熱・金属イオンなどによって活性を失う。エンザイム。
酵素の分類(表)
 こう‐そ【縞素】カウ‥
白色の喪服。
こうぞ【楮】カウゾ
(カミソ(紙麻)の音便)クワ科の落葉低木。西日本の山地に自生し、繊維作物として各地で栽培。高さ約3メートルに達する。葉は桑に似て質はやや薄く粗い。雌雄同株。6月頃、淡黄緑色の花を開く。果実は赤熟、桑の実に似る。樹皮は和紙の原料。かぞ。かんず。伊呂波字類抄「楮、カウソ」
こうぞ
こう‐そ【縞素】カウ‥
白色の喪服。
こうぞ【楮】カウゾ
(カミソ(紙麻)の音便)クワ科の落葉低木。西日本の山地に自生し、繊維作物として各地で栽培。高さ約3メートルに達する。葉は桑に似て質はやや薄く粗い。雌雄同株。6月頃、淡黄緑色の花を開く。果実は赤熟、桑の実に似る。樹皮は和紙の原料。かぞ。かんず。伊呂波字類抄「楮、カウソ」
こうぞ
 コウゾ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
コウゾ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 コウゾ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
コウゾ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒こうぞ‐がみ【楮紙】
ごう‐そ【拷訴】ガウ‥
罪人をあらあらしく責めつけること。
ごう‐そ【強訴・嗷訴】ガウ‥
為政者に対し、徒党を組んで強硬に訴えること。院政期前後の、南都北嶺の僧兵らの動座入洛は有名。太平記21「山門の―今に有りなん」
こうそ‐いん【控訴院】‥ヰン
旧制で、地方裁判所の直接上級裁判所。現在の高等裁判所に相当する。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そう【口奏】
口頭で奏上すること。
こう‐そう【公葬】‥サウ
功労のあった人などのために、公費で営む葬儀。
こう‐そう【広壮・宏壮】クワウサウ
広く大きくりっぱなこと。「―な邸宅」
こう‐そう【好走】カウ‥
野球・マラソンなどのスポーツで、よい走りをすること。
こう‐そう【行装】カウサウ
旅行の支度。たびじたく。旅装。
こう‐そう【抗争】カウサウ
さからいあらそうこと。はりあいあらそうこと。「大国間の―」
こう‐そう【厚葬】‥サウ
手厚く埋葬すること。↔薄葬
こう‐そう【咬創】カウサウ
かまれたきず。かみきず。
こう‐そう【後奏】
独奏・独唱などが終わった後に奏する伴奏部分。↔前奏。
⇒こうそう‐きょく【後奏曲】
こう‐そう【後送】
①後方へ送ること。特に戦場などで、前線から後方へ送ること。
②あとから送ること。
こう‐そう【後装】‥サウ
銃の遊底または砲の閉鎖機を開閉して弾薬を装填そうてんすること。もとごめ。↔前装
こう‐そう【皇宗】クワウ‥
天皇の代々の祖先。第2代以後の歴代を指す。→皇祖
こう‐そう【紅藻】‥サウ
紅藻綱の総称。細胞にクロロフィルaとフィコエリトリンを含む葉緑体を持ち、体色は紅色または紫色を呈す。紅藻澱粉を生成。多くは多細胞で、糸状・葉状・羽状・殻状。世界に約5500種。主に海藻で、淡水産は約150種。食用や寒天原藻になるものを含む。海産種は、アサクサノリ・オゴノリ・マクサ・フクロフノリ・トサカノリなど。淡水産種には、カワモズク・チスジノリなど。紅色植物。
こう‐そう【香草】カウサウ
においのよい草。香気のある草。
こう‐そう【倥偬】
いそがしいこと。「兵馬―の間かん」
こう‐そう【校葬】カウサウ
学校が主催して営む葬儀。
こう‐そう【航走】カウ‥
船が水上を進むこと。航行。
こう‐そう【航送】カウ‥
船舶または航空機によって物を輸送すること。
こう‐そう【訌争】‥サウ
うちわもめのあらそい。内訌。内紛。
こう‐そう【降霜】カウサウ
霜のふること。また、ふった霜。
こう‐そう【高宗】カウ‥
唐の第3代、南宋の初代、清の第6代(乾隆帝)、朝鮮李朝の26代(李太王)などの皇帝の廟号。
こう‐そう【高相】カウサウ
高貴な人相。また、そのような人。宇治拾遺物語1「やんごとなき―の夢見てけり」
こう‐そう【高僧】カウ‥
①知徳のすぐれた僧。
②官位の高い僧。
⇒こうそう‐でん【高僧伝】
こう‐そう【高層】カウ‥
①層が幾重にも高く重なっていること。建物の階数が多いこと。「―建築」
②大気圏の上方の層。「―気象台」
⇒こうそう‐うん【高層雲】
⇒こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】
⇒こうそう‐きしょうだい【高層気象台】
⇒こうそう‐てんきず【高層天気図】
こう‐そう【高燥】カウサウ
土地が高くて湿気の少ないこと。「―の地」↔低湿
こう‐そう【黄巣】クワウサウ
唐末農民反乱の指導者。山東曹州の人。科挙に落第して、塩の闇商人となる。( 〜884)
⇒こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】
こう‐そう【鉱層】クワウ‥
海水や湖水などに溶けていた化学成分が沈殿・堆積して層状になった鉱床。世界の主要な鉄鉱床は、この型に属する。成層鉱床。
こう‐そう【構想】‥サウ
①考えを組み立てること。また、その考え。「組閣の―を練る」
②芸術作品を制作する場合、主題・仕組・思想内容・表現形式などあらゆる要素の構成を思考すること。
⇒こうそう‐りょく【構想力】
こう‐そう【鴻爪】‥サウ
[蘇軾、子由澠池旧を懐おもうに和する詩](鴻が南に来る時には、後の心覚えに雪に爪痕をつけるが、北に帰る時には、雪とともにその痕が消えていることからいう)往時の痕跡。また、跡形が残らないこと。行方ゆくえのはっきりしないこと。雪泥の鴻爪。
こう‐そう【鏗鏘】カウサウ
金石・琴などの鳴る音。
こう‐ぞう【行障】カウザウ
⇒こうしょう
こう‐ぞう【行蔵】カウザウ
世に出て道を行うことと隠遁して世に出ないこと。出処進退。
こう‐ぞう【香象】カウザウ
青色で香気を帯び、河海を歩いてわたるという想像上の大きな象。太平記14「―の浪を踏んで大海を渡らん勢ひの如く」
こう‐ぞう【構造】‥ザウ
①いくつかの材料を組み合わせてこしらえられたもの。また、そのしくみ。くみたて。「柔―のビル」
②全体を構成する諸要素の、互いの対立や矛盾、また依存の関係などの総称。「汚職の―」
⇒こうぞう‐いせい【構造異性】
⇒こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】
⇒こうぞう‐うんどう【構造運動】
⇒こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】
⇒こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】
⇒こうぞう‐けいさん【構造計算】
⇒こうぞう‐げんごがく【構造言語学】
⇒こうぞう‐しき【構造式】
⇒こうぞう‐じしん【構造地震】
⇒こうぞう‐しゅぎ【構造主義】
⇒こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】
⇒こうぞう‐せん【構造線】
⇒こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】
⇒こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】
⇒こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】
⇒こうぞう‐ど【構造土】
⇒こうぞう‐ようざい【構造用材】
ごう‐そう【合装】ガフサウ
①一つに合わせて荷づくりすること。
②一つに合わせて綴じること。
ごう‐そう【豪壮】ガウサウ
はでやかで勢いの盛んなこと。豪勢で立派なこと。「―な邸宅」
ごう‐そう【豪爽】ガウサウ
気性が、すぐれてさわやかなこと。豪快で、ことばや動作が人に快く感じられること。
こうぞう‐いせい【構造異性】‥ザウ‥
分子式は同じであるが構造式が異なることによる異性。ブタン(CH3CH2CH2CH3)とイソブタン((CH3)3CH)の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】‥ザウヰ‥
酵素や筋肉などの蛋白質のアミノ酸配列やRNAの塩基配列を決めている遺伝子。調節遺伝子と対比される。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐うん【高層雲】カウ‥
十種雲級の一つ。中層雲に属し、中緯度帯では2〜7キロメートルの高さに現れる。上空に広がってほとんど満天を覆う、やや濃い灰色を呈する幕のような雲。おぼろぐも。記号As →雲級(表)。
高層雲
撮影:高橋健司
⇒こうぞ‐がみ【楮紙】
ごう‐そ【拷訴】ガウ‥
罪人をあらあらしく責めつけること。
ごう‐そ【強訴・嗷訴】ガウ‥
為政者に対し、徒党を組んで強硬に訴えること。院政期前後の、南都北嶺の僧兵らの動座入洛は有名。太平記21「山門の―今に有りなん」
こうそ‐いん【控訴院】‥ヰン
旧制で、地方裁判所の直接上級裁判所。現在の高等裁判所に相当する。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そう【口奏】
口頭で奏上すること。
こう‐そう【公葬】‥サウ
功労のあった人などのために、公費で営む葬儀。
こう‐そう【広壮・宏壮】クワウサウ
広く大きくりっぱなこと。「―な邸宅」
こう‐そう【好走】カウ‥
野球・マラソンなどのスポーツで、よい走りをすること。
こう‐そう【行装】カウサウ
旅行の支度。たびじたく。旅装。
こう‐そう【抗争】カウサウ
さからいあらそうこと。はりあいあらそうこと。「大国間の―」
こう‐そう【厚葬】‥サウ
手厚く埋葬すること。↔薄葬
こう‐そう【咬創】カウサウ
かまれたきず。かみきず。
こう‐そう【後奏】
独奏・独唱などが終わった後に奏する伴奏部分。↔前奏。
⇒こうそう‐きょく【後奏曲】
こう‐そう【後送】
①後方へ送ること。特に戦場などで、前線から後方へ送ること。
②あとから送ること。
こう‐そう【後装】‥サウ
銃の遊底または砲の閉鎖機を開閉して弾薬を装填そうてんすること。もとごめ。↔前装
こう‐そう【皇宗】クワウ‥
天皇の代々の祖先。第2代以後の歴代を指す。→皇祖
こう‐そう【紅藻】‥サウ
紅藻綱の総称。細胞にクロロフィルaとフィコエリトリンを含む葉緑体を持ち、体色は紅色または紫色を呈す。紅藻澱粉を生成。多くは多細胞で、糸状・葉状・羽状・殻状。世界に約5500種。主に海藻で、淡水産は約150種。食用や寒天原藻になるものを含む。海産種は、アサクサノリ・オゴノリ・マクサ・フクロフノリ・トサカノリなど。淡水産種には、カワモズク・チスジノリなど。紅色植物。
こう‐そう【香草】カウサウ
においのよい草。香気のある草。
こう‐そう【倥偬】
いそがしいこと。「兵馬―の間かん」
こう‐そう【校葬】カウサウ
学校が主催して営む葬儀。
こう‐そう【航走】カウ‥
船が水上を進むこと。航行。
こう‐そう【航送】カウ‥
船舶または航空機によって物を輸送すること。
こう‐そう【訌争】‥サウ
うちわもめのあらそい。内訌。内紛。
こう‐そう【降霜】カウサウ
霜のふること。また、ふった霜。
こう‐そう【高宗】カウ‥
唐の第3代、南宋の初代、清の第6代(乾隆帝)、朝鮮李朝の26代(李太王)などの皇帝の廟号。
こう‐そう【高相】カウサウ
高貴な人相。また、そのような人。宇治拾遺物語1「やんごとなき―の夢見てけり」
こう‐そう【高僧】カウ‥
①知徳のすぐれた僧。
②官位の高い僧。
⇒こうそう‐でん【高僧伝】
こう‐そう【高層】カウ‥
①層が幾重にも高く重なっていること。建物の階数が多いこと。「―建築」
②大気圏の上方の層。「―気象台」
⇒こうそう‐うん【高層雲】
⇒こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】
⇒こうそう‐きしょうだい【高層気象台】
⇒こうそう‐てんきず【高層天気図】
こう‐そう【高燥】カウサウ
土地が高くて湿気の少ないこと。「―の地」↔低湿
こう‐そう【黄巣】クワウサウ
唐末農民反乱の指導者。山東曹州の人。科挙に落第して、塩の闇商人となる。( 〜884)
⇒こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】
こう‐そう【鉱層】クワウ‥
海水や湖水などに溶けていた化学成分が沈殿・堆積して層状になった鉱床。世界の主要な鉄鉱床は、この型に属する。成層鉱床。
こう‐そう【構想】‥サウ
①考えを組み立てること。また、その考え。「組閣の―を練る」
②芸術作品を制作する場合、主題・仕組・思想内容・表現形式などあらゆる要素の構成を思考すること。
⇒こうそう‐りょく【構想力】
こう‐そう【鴻爪】‥サウ
[蘇軾、子由澠池旧を懐おもうに和する詩](鴻が南に来る時には、後の心覚えに雪に爪痕をつけるが、北に帰る時には、雪とともにその痕が消えていることからいう)往時の痕跡。また、跡形が残らないこと。行方ゆくえのはっきりしないこと。雪泥の鴻爪。
こう‐そう【鏗鏘】カウサウ
金石・琴などの鳴る音。
こう‐ぞう【行障】カウザウ
⇒こうしょう
こう‐ぞう【行蔵】カウザウ
世に出て道を行うことと隠遁して世に出ないこと。出処進退。
こう‐ぞう【香象】カウザウ
青色で香気を帯び、河海を歩いてわたるという想像上の大きな象。太平記14「―の浪を踏んで大海を渡らん勢ひの如く」
こう‐ぞう【構造】‥ザウ
①いくつかの材料を組み合わせてこしらえられたもの。また、そのしくみ。くみたて。「柔―のビル」
②全体を構成する諸要素の、互いの対立や矛盾、また依存の関係などの総称。「汚職の―」
⇒こうぞう‐いせい【構造異性】
⇒こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】
⇒こうぞう‐うんどう【構造運動】
⇒こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】
⇒こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】
⇒こうぞう‐けいさん【構造計算】
⇒こうぞう‐げんごがく【構造言語学】
⇒こうぞう‐しき【構造式】
⇒こうぞう‐じしん【構造地震】
⇒こうぞう‐しゅぎ【構造主義】
⇒こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】
⇒こうぞう‐せん【構造線】
⇒こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】
⇒こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】
⇒こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】
⇒こうぞう‐ど【構造土】
⇒こうぞう‐ようざい【構造用材】
ごう‐そう【合装】ガフサウ
①一つに合わせて荷づくりすること。
②一つに合わせて綴じること。
ごう‐そう【豪壮】ガウサウ
はでやかで勢いの盛んなこと。豪勢で立派なこと。「―な邸宅」
ごう‐そう【豪爽】ガウサウ
気性が、すぐれてさわやかなこと。豪快で、ことばや動作が人に快く感じられること。
こうぞう‐いせい【構造異性】‥ザウ‥
分子式は同じであるが構造式が異なることによる異性。ブタン(CH3CH2CH2CH3)とイソブタン((CH3)3CH)の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】‥ザウヰ‥
酵素や筋肉などの蛋白質のアミノ酸配列やRNAの塩基配列を決めている遺伝子。調節遺伝子と対比される。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐うん【高層雲】カウ‥
十種雲級の一つ。中層雲に属し、中緯度帯では2〜7キロメートルの高さに現れる。上空に広がってほとんど満天を覆う、やや濃い灰色を呈する幕のような雲。おぼろぐも。記号As →雲級(表)。
高層雲
撮影:高橋健司
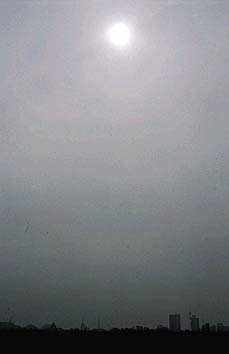 ⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐うんどう【構造運動】‥ザウ‥
地層や岩石に褶曲しゅうきょく・断層など変形・破壊をひきおこす地殻の運動の総称。主要なものは造山運動に伴って起きる。造構造運動。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐かい【紅槍会】‥サウクワイ
(紅い房のついた槍を用いたからいう)清末以降、軍閥・匪賊の圧迫・搾取に対抗した中国華北農民の武装自衛の秘密結社。
こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】‥ザウ‥
社会主義に移行するための政治理論の一つ。労働者階級が国家権力を掌握する以前の段階でも独占資本の構造を部分的に改革することを通じて段階的に社会主義を実現できるとした。トリアッティらが提唱。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】‥ザウクワ‥
(structured programming)コンピューターのプログラム作成の方法論の一つ。プログラムの構造を階層化・抽象化し、段階的に詳細化することで、大規模で複雑なプログラムを正確に作成する。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうぎ【黄宗羲】クワウ‥
明末・清初の学者・思想家。字は太沖。号は梨洲・南雷。諡は文孝。浙江余姚の人。陽明学の流れを汲み、実用政治学のほか、歴史・天文・数学にも精通。著「宋元学案」「明儒学案」「易学象数論」「明夷待訪録」など。(1610〜1695)
こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】カウ‥シヤウクワン‥
高層大気中の気象の観測。凧たこ・気球・ラジオゾンデ・飛行機・気象ロケットなどでの観測のほか、レーダー・人工衛星を利用した観測も行われている。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きしょうだい【高層気象台】カウ‥シヤウ‥
気象庁の機関の一つ。茨城県つくば市にあり、高層気象の精密な観測・調査、測器の試験・改良などを行う。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きょく【後奏曲】
礼拝後などに奏するオルガンなどの楽曲。
⇒こう‐そう【後奏】
こうぞう‐けいさん【構造計算】‥ザウ‥
構造物に加わる自重、積載荷重、積雪・風圧・地震などの外力に対する安全性を数値計算すること。「―書」
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐げんごがく【構造言語学】‥ザウ‥
(structural linguistics)言語を作る要素の関係性に注目して、言語の体系や構造を解明することを目的とする言語理論。ソシュールを先駆者とし、その流れをひくフランス‐スイス学派・プラーグ学派・コペンハーゲン学派などがある。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しき【構造式】‥ザウ‥
元素記号を短い線(価標)で結びつけて、分子内の各原子の結合のしかたを表す化学式。水をH‐O‐Hとする類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じしん【構造地震】‥ザウヂ‥
地質学上の断層と密接な関係のある地震。多くの地震はこれに属すると考えられる。断層地震。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しゅぎ【構造主義】‥ザウ‥
(structuralism)一般に、研究対象の構造の研究を主とする研究方法。また、その立場。
①言語(ラング)に内在する構造(structure)をつかみ出し、各要素の機能的連関を明らかにする言語学の立場。ソシュールに始まる。
②社会・文化現象の意味秩序も言語構造と類比的なものと見て、これを分析方法に導入する学問的立場の総称。ヤコブソンやムカジョフスキー(J. Mukařovský1891〜1975)の構造主義的美学・詩学があるが、特にレヴィ=ストロースが人類学にこの方法を導入、未開社会の複雑多様な親族組織の分析に成功して以来、フランスを中心にラカン・アルチュセール・M.フーコーらによって、反人間中心主義的な人文科学の方法として活用された。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】‥ザウ‥
(anthropologie structurale フランス)構造主義的な立場をとる人類学。レヴィ=ストロースが創始。ある親族・婚姻体系や神話などを、他の体系や神話を論理的に変換したものととらえ、その変換の関係を明らかにしようとする。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐せん【構造線】‥ザウ‥
〔地〕規模の大きな断層または断層群。中央構造線の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうそん【皇曾孫】クワウ‥
天皇のひまご。
こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】‥ザウ‥
地層や岩体の構造とその発達史を調べ、どのような運動や作用で生じたかを明らかにする地質学の一分野。褶曲しゅうきょくや断層で代表される変形や破壊現象に加えて、岩石や鉱物の物性論も扱う。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】‥ザウ‥ゲフ
経済構造の変化に伴って衰退する産業や地域で発生する慢性的失業。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】‥ザウ‥キヤウ
景気循環に伴う全般的不況ではなく、特定の産業が、産業構造・需要構造など経済の変化への対応が遅れたために陥る不況。構造不況。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐でん【高僧伝】カウ‥
①高僧の伝記を集成したもの。中国には、梁高僧伝(14巻、慧皎えこう撰、519年成る)のほか、続高僧伝(唐高僧伝、30巻、道宣撰)・宋高僧伝(30巻、賛寧撰)・大明高僧伝(8巻、如惺にょせい撰)などがあり、日本には本朝高僧伝などがある。
②特に、仏教伝来より当代に至る高僧の伝記を集成した梁高僧伝を指す。
⇒こう‐そう【高僧】
こうそう‐てんきず【高層天気図】カウ‥ヅ
上空の気象状況を示す天気図。ふつう一定気圧面の高度分布と共に気温・風向・風速などを記入・解析してある。等圧面天気図。
⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐ど【構造土】‥ザウ‥
岩屑や草叢くさむらが円形・多角形・縞状・階段状などの幾何学模様を呈する地表面。周氷河地形の一種。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】クワウサウ‥
唐末に起こった農民反乱。875年、王仙芝の河北での挙兵に黄巣が山東で呼応、四川を除きほとんど全中国に転戦し、880年洛陽・長安を占領して帝位につき、国号を大斉と号したが、唐朝の反撃で884年に鎮圧された。唐朝滅亡の近因となる。
⇒こう‐そう【黄巣】
こうぞう‐ようざい【構造用材】‥ザウ‥
木造建築の土台・柱・梁などに使用する木材。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐りょく【構想力】‥サウ‥
①これから実現しようとする物事を考えの中で組み立てる能力。
②哲学で、(→)想像力に同じ。特にカント哲学では、対象が現前しないのに、対象を直観において表象する能力とされる。
⇒こう‐そう【構想】
こうぞ‐がみ【楮紙】カウゾ‥
和紙の一種。コウゾの樹皮の繊維を原料として漉すいた紙。杉原紙・美濃紙・西の内紙・清張紙・吉野紙・奉書など、品種が多い。古くから写経用紙・書類用紙・障子紙・傘紙・紙子紙などに広く用いられた。穀紙こくし。構紙かじがみ。ちょし。
⇒こうぞ【楮】
こうそ‐きかん【控訴期間】
控訴することのできる期間。民事訴訟では判決の送達日から、刑事訴訟では判決の告知日からそれぞれ2週間(14日間)。
⇒こう‐そ【控訴】
こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
刑事訴訟上、公訴提起が有効であるための条件(訴訟条件)を欠くため、公訴を無効として手続を打ち切る裁判。
⇒こう‐そ【公訴】
こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
控訴による不服申立ての理由がないとする裁判。原判決が維持される。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そく【光束】クワウ‥
①幾何光学で光線の束のこと。
②ある面をある時間に通過する光の量。国際単位系での単位はルーメン(lm)。
こう‐そく【光速】クワウ‥
(→)光速度に同じ。
こう‐そく【拘束】
①行動の自由を制限し、または停止すること。
②拘引して束縛すること。「身柄を―する」
⇒こうそく‐じかん【拘束時間】
⇒こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
⇒こうそく‐りょく【拘束力】
こう‐そく【後足】
後部の足。あとあし。
こう‐そく【校則】カウ‥
児童・生徒を対象に、学校が制定した規則。生活指導文書的性格のものから、拘束性の強いものまで多岐にわたる。生徒心得。
こう‐そく【高足】カウ‥
①(もと、すぐれた馬の意)(→)高弟に同じ。
②田楽や田植の神事などに用いる、柱の長さ7尺、横木1尺ほどの1本のたけうま。また、この横木に両足をのせて跳ぶ芸。唐の散楽の一種目。一足いっそく。たかあし。
こう‐そく【高速】カウ‥
速度がはやいこと。高速度。「―で飛ばす」「―艇」
⇒こうそく‐きかん【高速機関】
⇒こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】
⇒こうそく‐どうろ【高速道路】
こう‐そく【梗塞】カウ‥
①ふさがって通じないこと。
②動脈が血栓などのためにふさがり、血液が流れなくなって、その動脈の支配する細胞・組織が壊死えしに陥る病変。心筋梗塞・脳梗塞など。
こう‐そく【港則】カウ‥
港湾を取り締まるための規則。
こう‐ぞく【公族】
1910年、韓国併合の後、前韓国王族李堈りこう・李熹りき・李埈およびその子孫で公として皇族の礼遇をうけた一族の称号。第二次大戦後、廃止。
こう‐ぞく【甲族】カフ‥
貴い家柄。貴族。門閥。
こう‐ぞく【後続】
あとから続くこと。「―部隊」
こう‐ぞく【皇族】クワウ‥
天皇の一族。天皇を除き皇胤こういんの男子およびその配偶者ならびに皇胤の女子をいう。皇后・太皇太后・皇太后・親王(皇太子・皇太孫を含む)・親王妃・内親王・王・王妃・女王の総称。現憲法はこれを国民として取り扱い、政治上の特権を認めない。→宮家。
⇒こうぞく‐かいぎ【皇族会議】
⇒こうぞく‐ひ【皇族費】
⇒こうぞく‐ふ【皇族譜】
ごう‐ぞく【強賊】ガウ‥
⇒きょうぞく
ごう‐ぞく【豪族】ガウ‥
地方に土着し、勢力をもつ一族。今昔物語集1「当国・隣国の―の人来りて乞ふ」
こうぞく‐かいぎ【皇族会議】クワウ‥クワイ‥
旧皇室典範上の機関で、皇族の大事を議した親族会議。成年の皇族男子で構成され、内大臣らも参列。→皇室会議。
⇒こう‐ぞく【皇族】
こうそく‐きかん【高速機関】カウ‥クワン
自動車や航空機などに用いる回転速度の大きい機関。
⇒こう‐そく【高速】
こうぞく‐きょり【航続距離】カウ‥
船舶または航空機が、途中で給油することなく航海または航空を続行できる距離。
こうそく‐じ【光触寺】クワウ‥
鎌倉市十二所じゅにそにある時宗の寺。一遍の創建と伝え、本尊の伝運慶作頬焼ほおやき阿弥陀如来のほか、頬焼阿弥陀縁起絵巻などがある。
光触寺
撮影:関戸 勇
⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐うんどう【構造運動】‥ザウ‥
地層や岩石に褶曲しゅうきょく・断層など変形・破壊をひきおこす地殻の運動の総称。主要なものは造山運動に伴って起きる。造構造運動。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐かい【紅槍会】‥サウクワイ
(紅い房のついた槍を用いたからいう)清末以降、軍閥・匪賊の圧迫・搾取に対抗した中国華北農民の武装自衛の秘密結社。
こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】‥ザウ‥
社会主義に移行するための政治理論の一つ。労働者階級が国家権力を掌握する以前の段階でも独占資本の構造を部分的に改革することを通じて段階的に社会主義を実現できるとした。トリアッティらが提唱。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】‥ザウクワ‥
(structured programming)コンピューターのプログラム作成の方法論の一つ。プログラムの構造を階層化・抽象化し、段階的に詳細化することで、大規模で複雑なプログラムを正確に作成する。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうぎ【黄宗羲】クワウ‥
明末・清初の学者・思想家。字は太沖。号は梨洲・南雷。諡は文孝。浙江余姚の人。陽明学の流れを汲み、実用政治学のほか、歴史・天文・数学にも精通。著「宋元学案」「明儒学案」「易学象数論」「明夷待訪録」など。(1610〜1695)
こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】カウ‥シヤウクワン‥
高層大気中の気象の観測。凧たこ・気球・ラジオゾンデ・飛行機・気象ロケットなどでの観測のほか、レーダー・人工衛星を利用した観測も行われている。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きしょうだい【高層気象台】カウ‥シヤウ‥
気象庁の機関の一つ。茨城県つくば市にあり、高層気象の精密な観測・調査、測器の試験・改良などを行う。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きょく【後奏曲】
礼拝後などに奏するオルガンなどの楽曲。
⇒こう‐そう【後奏】
こうぞう‐けいさん【構造計算】‥ザウ‥
構造物に加わる自重、積載荷重、積雪・風圧・地震などの外力に対する安全性を数値計算すること。「―書」
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐げんごがく【構造言語学】‥ザウ‥
(structural linguistics)言語を作る要素の関係性に注目して、言語の体系や構造を解明することを目的とする言語理論。ソシュールを先駆者とし、その流れをひくフランス‐スイス学派・プラーグ学派・コペンハーゲン学派などがある。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しき【構造式】‥ザウ‥
元素記号を短い線(価標)で結びつけて、分子内の各原子の結合のしかたを表す化学式。水をH‐O‐Hとする類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じしん【構造地震】‥ザウヂ‥
地質学上の断層と密接な関係のある地震。多くの地震はこれに属すると考えられる。断層地震。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しゅぎ【構造主義】‥ザウ‥
(structuralism)一般に、研究対象の構造の研究を主とする研究方法。また、その立場。
①言語(ラング)に内在する構造(structure)をつかみ出し、各要素の機能的連関を明らかにする言語学の立場。ソシュールに始まる。
②社会・文化現象の意味秩序も言語構造と類比的なものと見て、これを分析方法に導入する学問的立場の総称。ヤコブソンやムカジョフスキー(J. Mukařovský1891〜1975)の構造主義的美学・詩学があるが、特にレヴィ=ストロースが人類学にこの方法を導入、未開社会の複雑多様な親族組織の分析に成功して以来、フランスを中心にラカン・アルチュセール・M.フーコーらによって、反人間中心主義的な人文科学の方法として活用された。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】‥ザウ‥
(anthropologie structurale フランス)構造主義的な立場をとる人類学。レヴィ=ストロースが創始。ある親族・婚姻体系や神話などを、他の体系や神話を論理的に変換したものととらえ、その変換の関係を明らかにしようとする。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐せん【構造線】‥ザウ‥
〔地〕規模の大きな断層または断層群。中央構造線の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうそん【皇曾孫】クワウ‥
天皇のひまご。
こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】‥ザウ‥
地層や岩体の構造とその発達史を調べ、どのような運動や作用で生じたかを明らかにする地質学の一分野。褶曲しゅうきょくや断層で代表される変形や破壊現象に加えて、岩石や鉱物の物性論も扱う。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】‥ザウ‥ゲフ
経済構造の変化に伴って衰退する産業や地域で発生する慢性的失業。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】‥ザウ‥キヤウ
景気循環に伴う全般的不況ではなく、特定の産業が、産業構造・需要構造など経済の変化への対応が遅れたために陥る不況。構造不況。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐でん【高僧伝】カウ‥
①高僧の伝記を集成したもの。中国には、梁高僧伝(14巻、慧皎えこう撰、519年成る)のほか、続高僧伝(唐高僧伝、30巻、道宣撰)・宋高僧伝(30巻、賛寧撰)・大明高僧伝(8巻、如惺にょせい撰)などがあり、日本には本朝高僧伝などがある。
②特に、仏教伝来より当代に至る高僧の伝記を集成した梁高僧伝を指す。
⇒こう‐そう【高僧】
こうそう‐てんきず【高層天気図】カウ‥ヅ
上空の気象状況を示す天気図。ふつう一定気圧面の高度分布と共に気温・風向・風速などを記入・解析してある。等圧面天気図。
⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐ど【構造土】‥ザウ‥
岩屑や草叢くさむらが円形・多角形・縞状・階段状などの幾何学模様を呈する地表面。周氷河地形の一種。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】クワウサウ‥
唐末に起こった農民反乱。875年、王仙芝の河北での挙兵に黄巣が山東で呼応、四川を除きほとんど全中国に転戦し、880年洛陽・長安を占領して帝位につき、国号を大斉と号したが、唐朝の反撃で884年に鎮圧された。唐朝滅亡の近因となる。
⇒こう‐そう【黄巣】
こうぞう‐ようざい【構造用材】‥ザウ‥
木造建築の土台・柱・梁などに使用する木材。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐りょく【構想力】‥サウ‥
①これから実現しようとする物事を考えの中で組み立てる能力。
②哲学で、(→)想像力に同じ。特にカント哲学では、対象が現前しないのに、対象を直観において表象する能力とされる。
⇒こう‐そう【構想】
こうぞ‐がみ【楮紙】カウゾ‥
和紙の一種。コウゾの樹皮の繊維を原料として漉すいた紙。杉原紙・美濃紙・西の内紙・清張紙・吉野紙・奉書など、品種が多い。古くから写経用紙・書類用紙・障子紙・傘紙・紙子紙などに広く用いられた。穀紙こくし。構紙かじがみ。ちょし。
⇒こうぞ【楮】
こうそ‐きかん【控訴期間】
控訴することのできる期間。民事訴訟では判決の送達日から、刑事訴訟では判決の告知日からそれぞれ2週間(14日間)。
⇒こう‐そ【控訴】
こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
刑事訴訟上、公訴提起が有効であるための条件(訴訟条件)を欠くため、公訴を無効として手続を打ち切る裁判。
⇒こう‐そ【公訴】
こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
控訴による不服申立ての理由がないとする裁判。原判決が維持される。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そく【光束】クワウ‥
①幾何光学で光線の束のこと。
②ある面をある時間に通過する光の量。国際単位系での単位はルーメン(lm)。
こう‐そく【光速】クワウ‥
(→)光速度に同じ。
こう‐そく【拘束】
①行動の自由を制限し、または停止すること。
②拘引して束縛すること。「身柄を―する」
⇒こうそく‐じかん【拘束時間】
⇒こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
⇒こうそく‐りょく【拘束力】
こう‐そく【後足】
後部の足。あとあし。
こう‐そく【校則】カウ‥
児童・生徒を対象に、学校が制定した規則。生活指導文書的性格のものから、拘束性の強いものまで多岐にわたる。生徒心得。
こう‐そく【高足】カウ‥
①(もと、すぐれた馬の意)(→)高弟に同じ。
②田楽や田植の神事などに用いる、柱の長さ7尺、横木1尺ほどの1本のたけうま。また、この横木に両足をのせて跳ぶ芸。唐の散楽の一種目。一足いっそく。たかあし。
こう‐そく【高速】カウ‥
速度がはやいこと。高速度。「―で飛ばす」「―艇」
⇒こうそく‐きかん【高速機関】
⇒こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】
⇒こうそく‐どうろ【高速道路】
こう‐そく【梗塞】カウ‥
①ふさがって通じないこと。
②動脈が血栓などのためにふさがり、血液が流れなくなって、その動脈の支配する細胞・組織が壊死えしに陥る病変。心筋梗塞・脳梗塞など。
こう‐そく【港則】カウ‥
港湾を取り締まるための規則。
こう‐ぞく【公族】
1910年、韓国併合の後、前韓国王族李堈りこう・李熹りき・李埈およびその子孫で公として皇族の礼遇をうけた一族の称号。第二次大戦後、廃止。
こう‐ぞく【甲族】カフ‥
貴い家柄。貴族。門閥。
こう‐ぞく【後続】
あとから続くこと。「―部隊」
こう‐ぞく【皇族】クワウ‥
天皇の一族。天皇を除き皇胤こういんの男子およびその配偶者ならびに皇胤の女子をいう。皇后・太皇太后・皇太后・親王(皇太子・皇太孫を含む)・親王妃・内親王・王・王妃・女王の総称。現憲法はこれを国民として取り扱い、政治上の特権を認めない。→宮家。
⇒こうぞく‐かいぎ【皇族会議】
⇒こうぞく‐ひ【皇族費】
⇒こうぞく‐ふ【皇族譜】
ごう‐ぞく【強賊】ガウ‥
⇒きょうぞく
ごう‐ぞく【豪族】ガウ‥
地方に土着し、勢力をもつ一族。今昔物語集1「当国・隣国の―の人来りて乞ふ」
こうぞく‐かいぎ【皇族会議】クワウ‥クワイ‥
旧皇室典範上の機関で、皇族の大事を議した親族会議。成年の皇族男子で構成され、内大臣らも参列。→皇室会議。
⇒こう‐ぞく【皇族】
こうそく‐きかん【高速機関】カウ‥クワン
自動車や航空機などに用いる回転速度の大きい機関。
⇒こう‐そく【高速】
こうぞく‐きょり【航続距離】カウ‥
船舶または航空機が、途中で給油することなく航海または航空を続行できる距離。
こうそく‐じ【光触寺】クワウ‥
鎌倉市十二所じゅにそにある時宗の寺。一遍の創建と伝え、本尊の伝運慶作頬焼ほおやき阿弥陀如来のほか、頬焼阿弥陀縁起絵巻などがある。
光触寺
撮影:関戸 勇
 こうそく‐じかん【拘束時間】
休憩時間を含む労働時間。↔実働時間。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
銀行が貸出しの際に、預貸率の改善、貸出しの担保の保全を目的として積ませる預金。→歩積ぶづみ預金→両建預金。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】カウ‥
(fast breeder reactor)高速の中性子を用いて、ウラン238からプルトニウム239への転換率を1より大、すなわち増殖するように設計された原子炉。高速炉。FBR→増殖炉。
⇒こう‐そく【高速】
こう‐そくど【光速度】クワウ‥
光の伝播する速さ。真空中の光速度(毎秒29.9792458万キロメートル)は基礎定数の一つで、この数値をもとに1メートルの長さが定義されている。光速。記号c
こう‐そくど【高速度】カウ‥
速度がはやいこと。高速。
⇒こうそくど‐えいが【高速度映画】
⇒こうそくど‐こう【高速度鋼】
⇒こうそくど‐しゃしん【高速度写真】
こうそく‐どうろ【高速道路】カウ‥ダウ‥
高速で走る自動車のための専用道路。ハイウェー。フリーウェー。
⇒こう‐そく【高速】
こうそくど‐えいが【高速度映画】カウ‥グワ
1秒間あたりおよそ50こま以上の撮影速度で撮った映画。標準速度で映写すれば、被写体の動きがゆっくりとなり、それを詳しく観察することができる。
⇒こう‐そくど【高速度】
こうそくど‐こう【高速度鋼】カウ‥カウ
高速度で金属材料を切削する工具の製作に用いる特殊鋼。セ氏600度くらいの高温まで硬さと耐
こうそく‐じかん【拘束時間】
休憩時間を含む労働時間。↔実働時間。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
銀行が貸出しの際に、預貸率の改善、貸出しの担保の保全を目的として積ませる預金。→歩積ぶづみ預金→両建預金。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】カウ‥
(fast breeder reactor)高速の中性子を用いて、ウラン238からプルトニウム239への転換率を1より大、すなわち増殖するように設計された原子炉。高速炉。FBR→増殖炉。
⇒こう‐そく【高速】
こう‐そくど【光速度】クワウ‥
光の伝播する速さ。真空中の光速度(毎秒29.9792458万キロメートル)は基礎定数の一つで、この数値をもとに1メートルの長さが定義されている。光速。記号c
こう‐そくど【高速度】カウ‥
速度がはやいこと。高速。
⇒こうそくど‐えいが【高速度映画】
⇒こうそくど‐こう【高速度鋼】
⇒こうそくど‐しゃしん【高速度写真】
こうそく‐どうろ【高速道路】カウ‥ダウ‥
高速で走る自動車のための専用道路。ハイウェー。フリーウェー。
⇒こう‐そく【高速】
こうそくど‐えいが【高速度映画】カウ‥グワ
1秒間あたりおよそ50こま以上の撮影速度で撮った映画。標準速度で映写すれば、被写体の動きがゆっくりとなり、それを詳しく観察することができる。
⇒こう‐そくど【高速度】
こうそくど‐こう【高速度鋼】カウ‥カウ
高速度で金属材料を切削する工具の製作に用いる特殊鋼。セ氏600度くらいの高温まで硬さと耐
 こうせき‐おとし【鉱石落し】クワウ‥
採鉱場から下位の坑道に鉱石を落とし、鉱車に積み入れるための設備。シュート。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐けんぱき【鉱石検波器】クワウ‥
鉱物と金属針との接触面の整流作用を利用した検波器。初期のラジオ受信に用いた。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐こう【黄石公】クワウ‥
秦末の隠士。漢の張良に兵書を授けたという老人。圯上老人いじょうろうじん。
こうせき‐こうぶつ【鉱石鉱物】クワウ‥クワウ‥
鉱石を構成する鉱物。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせきしき‐じゅしんき【鉱石式受信機】クワウ‥
鉱石検波器を用いた簡単なラジオ受信機。鉱石ラジオ。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐せい【洪積世】
(→)更新世に同じ。氷期に広域をおおった氷床の堆積物を大洪水の堆積物と誤認したところからの名。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐そう【洪積層】
①洪積世に形成された地層。
②中部ヨーロッパにおいて、台地を作って広く分布する砂礫層。かつて大洪水の堆積物と考えられた。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐だいち【洪積台地】
洪積層の構成する台地。洪積世(更新世)に形成された扇状地・三角洲などが隆起してやや浸食されたもの。武蔵野台地・下総台地など。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐とう【洪積統】
(→)洪積層1に同じ。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐どじょう【洪積土壌】‥ジヤウ
洪積層の上に発達した土壌。高師ヶ原や三方ヶ原など洪積段丘上の土壌で、東海地方から西南日本では黄褐色・赤褐色を呈するものが多い。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐ほう【鉱石法】クワウ‥ハフ
平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄より銑鉄の割合を多くし(60〜70パーセント)、酸化剤として多量の鉄鉱石を用いて操業する方法。鉱石中の酸化鉄が炭素・酸化炭素によって還元され鉄となり、炭素を吸収する。↔屑鉄法
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐りだつ【皇籍離脱】クワウ‥
皇族がその身分を離れて一般の国民となること。皇太子・皇太孫を除く皇族は皇室会議の議を経ればそれができる。旧制の臣籍降下に当たる。
⇒こう‐せき【皇籍】
こう‐ぜち【講説】カウ‥
(ゼチは呉音)講師こうじの説法。源氏物語鈴虫「―の折は、大方の鳴りをしづめて」
こう‐せつ【公設】
国家または公共団体が設立すること。↔私設。
⇒こうせつ‐いちば【公設市場】
⇒こうせつ‐しちや【公設質屋】
こう‐せつ【巧拙】カウ‥
巧みなこととまずいこと。上手と下手へた。「―を論じる」
こう‐せつ【交接】カウ‥
①まじわり近づくこと。交際。
②性交。交尾。
こう‐せつ【狎褻】カフ‥
なれてみだらになること。
こう‐せつ【巷説】カウ‥
ちまたのうわさ。世間のとりざた。風説。「―にまどわされる」
こう‐せつ【紅雪】
(→)赤雪せきせつに同じ。
こう‐せつ【荒説】クワウ‥
でたらめな説。取りとめのない風説。
こう‐せつ【降雪】カウ‥
雪のふること。また、ふった雪。
⇒こうせつ‐りょう【降雪量】
こう‐せつ【高節】カウ‥
けだかい節操。すぐれたみさお。
こう‐せつ【高説】カウ‥
①すぐれた説。
②他人の説の尊敬語。「御―を拝聴する」
こう‐せつ【膠接】カウ‥
ねばりつくこと。
こう‐せつ【講説】カウ‥
(コウゼツとも)講義して説明すること。また、その講義。日葡辞書「キャウヲカウゼッスル」
こう‐ぜつ【口舌】
①くちとした。
②ものいい。くちさき。弁舌。
⇒こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】
⇒こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
⇒こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
こう‐ぜつ【黄舌】クワウ‥
音声のまだ若くてととのわないこと。黄口こうこうの舌。謡曲、歌占「―の囀り」
こう‐ぜつ【喉舌】
のどとした。すなわち、ことばを発する大切なところ。
⇒こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】
ごう‐せつ【豪雪】ガウ‥
大量の降雪。大雪おおゆき。「―地帯」
こうせつ‐いちば【公設市場】
生活必需品を公正な価格で需要者に供給するため公設された市場。
⇒こう‐せつ【公設】
こうせつ‐おんしょう【高設温床】カウ‥ヲンシヤウ
発熱部が地上にある温床。排水不良の土地などで用いる。
こう‐せっけん【硬石鹸】カウセキ‥
(→)ソーダ石鹸に同じ。
こう‐せっこう【硬石膏】カウセキカウ
硫酸カルシウムの鉱物。斜方晶系で、白色または淡青色。
こうせつ‐しちや【公設質屋】
(→)公益質屋に同じ。
⇒こう‐せつ【公設】
ごう‐せっ‐とう【強窃盗】ガウ‥タウ
強盗と窃盗。
こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】‥アラソヒ
言いあらそい。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】‥クワン
[詩経大雅、烝民](君主の言葉を下へ伝える者の意)宰相。日本で、大納言の異称。
⇒こう‐ぜつ【喉舌】
こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
弁舌だけにすぐれて、実行力のない者。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
弁舌の巧みな人。口達者くちだっしゃ。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうせつ‐りょう【降雪量】カウ‥リヤウ
地上に降った雪の量。融かして液体の水にしたときの深さをミリメートルの単位で測ることが多い。その値を10倍すると積雪深に近くなる。→降水量
⇒こう‐せつ【降雪】
こう‐せん【口占】
①くちずさむこと。
②口づてに人に伝えること。
こう‐せん【口宣】
口で述べること。
こう‐せん【口銭・貢銭】
売買の仲介をした手数料。問屋口銭。コミッション。「五分の―を取る」→くちせん
こう‐せん【工専】
旧制の工業専門学校の略称。
こう‐せん【工船】
加工設備を船内に有し、漁獲物をただちに擂すり身・冷凍魚・魚粉などに加工する船。擂り身工船・冷凍工船の類。
こう‐せん【工銭】
工事の手間賃。工賃。
こう‐せん【公船】
①私法上、公用に供する船舶。多くは官公署の所有に属する。軍艦・測量船・練習船の類。
②国際法上、国家の公権を行使する船舶。軍艦、警察用・税関用の船舶の類。
こう‐せん【公賤】
(→)官賤に同じ。
こう‐せん【公選】
①公正な手段で選ぶこと。
②公共の職務に就く者を広く一般国民の投票によって選挙すること。「知事―」↔官選
こうせん【勾践・句践】
春秋時代の越の王。父王の頃から呉と争い、父の没後、呉王闔閭こうりょを敗死させたが、前494年闔閭の子夫差に囚われ、ようやく赦されて帰り、のち范蠡はんれいと謀って前477年遂に呉を討滅。( 〜前465)→臥薪嘗胆がしんしょうたん→会稽かいけいの恥
こう‐せん【功銭】
①奈良・平安時代、雇われた者に対する工賃で、銭貨で支払われるもの。布帛ふはくで支払われるものを功布、稲穀で支払われるものを功稲こうとうという。
②鎌倉時代、幕府の家人けにんなどが官に就く時の官への献金。
こう‐せん【広宣】クワウ‥
〔仏〕広く仏法を宣布すること。「―流布るふ」
こう‐せん【交戦】カウ‥
戦いを交えること。相戦うこと。互いに兵力を以て戦闘行為をなすこと。
⇒こうせん‐くいき【交戦区域】
⇒こうせん‐けん【交戦権】
⇒こうせん‐こく【交戦国】
⇒こうせん‐だんたい【交戦団体】
⇒こうせん‐ほうき【交戦法規】
こう‐せん【交線】カウ‥
平面と平面とが交わってできる線。特に、2平面の交わりをいう。
こう‐せん【光線】クワウ‥
①ひかり。光のさすすじ。
②光が空間を伝播する様子を光のエネルギーの流れる経路で表す線。
⇒こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】
こう‐せん【好戦】カウ‥
戦いを好むこと。すぐ武力に訴えようとすること。
⇒こうせん‐てき【好戦的】
こう‐せん【抗戦】カウ‥
抵抗してたたかうこと。「徹底―」
こう‐せん【攻戦】
攻め戦うこと。
こう‐せん【後先】
あとさき。先後。前後。
こう‐せん【香煎】カウ‥
①麦・米などを炒いって挽いた粉。砂糖を混ぜてそのまま、あるいは水や湯で練って食べる。また、菓子の材料に用いる。はったい。いりむぎ。麦こがし。
②山椒や薬草の粉などを調合したもの。湯をそそいで飲む。香煎湯。
こう‐せん【香饌】カウ‥
(→)施物せもつに同じ。
こう‐せん【高専】カウ‥
①高等専門学校の略称。
②旧制の高等学校・専門学校を総称する略称。
こう‐せん【黄泉】クワウ‥
(中国で、地の色を黄に配するからいう)
①地下の泉。
②死者の行く所。よみ。よみじ。冥土。九泉きゅうせん。平家物語6「―中有ちゅううの旅の空に」
こう‐せん【黄筌】クワウ‥
五代(蜀)の画家。字は要叔。四川成都の人。花鳥画にすぐれ、明確な輪郭線と濃厚な着色とによる精密な画風は黄氏体と呼ばれて、徐
こうせき‐おとし【鉱石落し】クワウ‥
採鉱場から下位の坑道に鉱石を落とし、鉱車に積み入れるための設備。シュート。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐けんぱき【鉱石検波器】クワウ‥
鉱物と金属針との接触面の整流作用を利用した検波器。初期のラジオ受信に用いた。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐こう【黄石公】クワウ‥
秦末の隠士。漢の張良に兵書を授けたという老人。圯上老人いじょうろうじん。
こうせき‐こうぶつ【鉱石鉱物】クワウ‥クワウ‥
鉱石を構成する鉱物。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせきしき‐じゅしんき【鉱石式受信機】クワウ‥
鉱石検波器を用いた簡単なラジオ受信機。鉱石ラジオ。
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐せい【洪積世】
(→)更新世に同じ。氷期に広域をおおった氷床の堆積物を大洪水の堆積物と誤認したところからの名。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐そう【洪積層】
①洪積世に形成された地層。
②中部ヨーロッパにおいて、台地を作って広く分布する砂礫層。かつて大洪水の堆積物と考えられた。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐だいち【洪積台地】
洪積層の構成する台地。洪積世(更新世)に形成された扇状地・三角洲などが隆起してやや浸食されたもの。武蔵野台地・下総台地など。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐とう【洪積統】
(→)洪積層1に同じ。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐どじょう【洪積土壌】‥ジヤウ
洪積層の上に発達した土壌。高師ヶ原や三方ヶ原など洪積段丘上の土壌で、東海地方から西南日本では黄褐色・赤褐色を呈するものが多い。
⇒こう‐せき【洪積】
こうせき‐ほう【鉱石法】クワウ‥ハフ
平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄より銑鉄の割合を多くし(60〜70パーセント)、酸化剤として多量の鉄鉱石を用いて操業する方法。鉱石中の酸化鉄が炭素・酸化炭素によって還元され鉄となり、炭素を吸収する。↔屑鉄法
⇒こう‐せき【鉱石】
こうせき‐りだつ【皇籍離脱】クワウ‥
皇族がその身分を離れて一般の国民となること。皇太子・皇太孫を除く皇族は皇室会議の議を経ればそれができる。旧制の臣籍降下に当たる。
⇒こう‐せき【皇籍】
こう‐ぜち【講説】カウ‥
(ゼチは呉音)講師こうじの説法。源氏物語鈴虫「―の折は、大方の鳴りをしづめて」
こう‐せつ【公設】
国家または公共団体が設立すること。↔私設。
⇒こうせつ‐いちば【公設市場】
⇒こうせつ‐しちや【公設質屋】
こう‐せつ【巧拙】カウ‥
巧みなこととまずいこと。上手と下手へた。「―を論じる」
こう‐せつ【交接】カウ‥
①まじわり近づくこと。交際。
②性交。交尾。
こう‐せつ【狎褻】カフ‥
なれてみだらになること。
こう‐せつ【巷説】カウ‥
ちまたのうわさ。世間のとりざた。風説。「―にまどわされる」
こう‐せつ【紅雪】
(→)赤雪せきせつに同じ。
こう‐せつ【荒説】クワウ‥
でたらめな説。取りとめのない風説。
こう‐せつ【降雪】カウ‥
雪のふること。また、ふった雪。
⇒こうせつ‐りょう【降雪量】
こう‐せつ【高節】カウ‥
けだかい節操。すぐれたみさお。
こう‐せつ【高説】カウ‥
①すぐれた説。
②他人の説の尊敬語。「御―を拝聴する」
こう‐せつ【膠接】カウ‥
ねばりつくこと。
こう‐せつ【講説】カウ‥
(コウゼツとも)講義して説明すること。また、その講義。日葡辞書「キャウヲカウゼッスル」
こう‐ぜつ【口舌】
①くちとした。
②ものいい。くちさき。弁舌。
⇒こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】
⇒こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
⇒こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
こう‐ぜつ【黄舌】クワウ‥
音声のまだ若くてととのわないこと。黄口こうこうの舌。謡曲、歌占「―の囀り」
こう‐ぜつ【喉舌】
のどとした。すなわち、ことばを発する大切なところ。
⇒こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】
ごう‐せつ【豪雪】ガウ‥
大量の降雪。大雪おおゆき。「―地帯」
こうせつ‐いちば【公設市場】
生活必需品を公正な価格で需要者に供給するため公設された市場。
⇒こう‐せつ【公設】
こうせつ‐おんしょう【高設温床】カウ‥ヲンシヤウ
発熱部が地上にある温床。排水不良の土地などで用いる。
こう‐せっけん【硬石鹸】カウセキ‥
(→)ソーダ石鹸に同じ。
こう‐せっこう【硬石膏】カウセキカウ
硫酸カルシウムの鉱物。斜方晶系で、白色または淡青色。
こうせつ‐しちや【公設質屋】
(→)公益質屋に同じ。
⇒こう‐せつ【公設】
ごう‐せっ‐とう【強窃盗】ガウ‥タウ
強盗と窃盗。
こうぜつ‐の‐あらそい【口舌の争い】‥アラソヒ
言いあらそい。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐かん【喉舌の官】‥クワン
[詩経大雅、烝民](君主の言葉を下へ伝える者の意)宰相。日本で、大納言の異称。
⇒こう‐ぜつ【喉舌】
こうぜつ‐の‐と【口舌の徒】
弁舌だけにすぐれて、実行力のない者。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうぜつ‐の‐ゆう【口舌の雄】
弁舌の巧みな人。口達者くちだっしゃ。
⇒こう‐ぜつ【口舌】
こうせつ‐りょう【降雪量】カウ‥リヤウ
地上に降った雪の量。融かして液体の水にしたときの深さをミリメートルの単位で測ることが多い。その値を10倍すると積雪深に近くなる。→降水量
⇒こう‐せつ【降雪】
こう‐せん【口占】
①くちずさむこと。
②口づてに人に伝えること。
こう‐せん【口宣】
口で述べること。
こう‐せん【口銭・貢銭】
売買の仲介をした手数料。問屋口銭。コミッション。「五分の―を取る」→くちせん
こう‐せん【工専】
旧制の工業専門学校の略称。
こう‐せん【工船】
加工設備を船内に有し、漁獲物をただちに擂すり身・冷凍魚・魚粉などに加工する船。擂り身工船・冷凍工船の類。
こう‐せん【工銭】
工事の手間賃。工賃。
こう‐せん【公船】
①私法上、公用に供する船舶。多くは官公署の所有に属する。軍艦・測量船・練習船の類。
②国際法上、国家の公権を行使する船舶。軍艦、警察用・税関用の船舶の類。
こう‐せん【公賤】
(→)官賤に同じ。
こう‐せん【公選】
①公正な手段で選ぶこと。
②公共の職務に就く者を広く一般国民の投票によって選挙すること。「知事―」↔官選
こうせん【勾践・句践】
春秋時代の越の王。父王の頃から呉と争い、父の没後、呉王闔閭こうりょを敗死させたが、前494年闔閭の子夫差に囚われ、ようやく赦されて帰り、のち范蠡はんれいと謀って前477年遂に呉を討滅。( 〜前465)→臥薪嘗胆がしんしょうたん→会稽かいけいの恥
こう‐せん【功銭】
①奈良・平安時代、雇われた者に対する工賃で、銭貨で支払われるもの。布帛ふはくで支払われるものを功布、稲穀で支払われるものを功稲こうとうという。
②鎌倉時代、幕府の家人けにんなどが官に就く時の官への献金。
こう‐せん【広宣】クワウ‥
〔仏〕広く仏法を宣布すること。「―流布るふ」
こう‐せん【交戦】カウ‥
戦いを交えること。相戦うこと。互いに兵力を以て戦闘行為をなすこと。
⇒こうせん‐くいき【交戦区域】
⇒こうせん‐けん【交戦権】
⇒こうせん‐こく【交戦国】
⇒こうせん‐だんたい【交戦団体】
⇒こうせん‐ほうき【交戦法規】
こう‐せん【交線】カウ‥
平面と平面とが交わってできる線。特に、2平面の交わりをいう。
こう‐せん【光線】クワウ‥
①ひかり。光のさすすじ。
②光が空間を伝播する様子を光のエネルギーの流れる経路で表す線。
⇒こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】
こう‐せん【好戦】カウ‥
戦いを好むこと。すぐ武力に訴えようとすること。
⇒こうせん‐てき【好戦的】
こう‐せん【抗戦】カウ‥
抵抗してたたかうこと。「徹底―」
こう‐せん【攻戦】
攻め戦うこと。
こう‐せん【後先】
あとさき。先後。前後。
こう‐せん【香煎】カウ‥
①麦・米などを炒いって挽いた粉。砂糖を混ぜてそのまま、あるいは水や湯で練って食べる。また、菓子の材料に用いる。はったい。いりむぎ。麦こがし。
②山椒や薬草の粉などを調合したもの。湯をそそいで飲む。香煎湯。
こう‐せん【香饌】カウ‥
(→)施物せもつに同じ。
こう‐せん【高専】カウ‥
①高等専門学校の略称。
②旧制の高等学校・専門学校を総称する略称。
こう‐せん【黄泉】クワウ‥
(中国で、地の色を黄に配するからいう)
①地下の泉。
②死者の行く所。よみ。よみじ。冥土。九泉きゅうせん。平家物語6「―中有ちゅううの旅の空に」
こう‐せん【黄筌】クワウ‥
五代(蜀)の画家。字は要叔。四川成都の人。花鳥画にすぐれ、明確な輪郭線と濃厚な着色とによる精密な画風は黄氏体と呼ばれて、徐 じょきの徐氏体と対比され、院体花鳥画の基礎をなした。( 〜965)
こう‐せん【腔線】カウ‥
銃砲身の内面に螺旋らせん状に彫った溝。発射弾に回転運動を与え弾道を安定させる。腔綫。ライフル。
こう‐せん【鉱泉】クワウ‥
鉱物質またはガスを多量に含む泉水。広義には温泉と冷泉との総称で、狭義には冷泉だけをいう。→温泉。
⇒こうせん‐えん【鉱泉塩】
こう‐せん【鋼船】カウ‥
鋼鉄で造った船。
こう‐せん【講銭】カウ‥
講中の掛け金。
こう‐ぜん【公然】
①おおっぴらなさま。一般に知れわたったさま。おもてむき。「白昼―と押し入る」「―たる事実」
②〔法〕ある事柄を不特定多数の人または利害関係ある人に秘密にせず、明白な形式でするさま。
⇒こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
⇒こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
こう‐ぜん【呷然】カフ‥
大声をあげるさま。内田魯庵、くれの廿八日「独り黒斜子の五紋は―として笑出した」
こう‐ぜん【哄然】
どっと笑うさま。
こう‐ぜん【昂然】カウ‥
自負があって意気のあがるさま。「―たる態度」「―として言い放つ」
こう‐ぜん【紅髯】
①あかいひげ。
②西洋人のひげ。また、西洋人。
③エビの異称。
こう‐ぜん【浩然】カウ‥
①水が盛んに流れるさま。
②心などが広くゆったりしているさま。「―たる態度」
⇒こうぜん‐の‐き【浩然の気】
こう‐ぜん【耿然】カウ‥
明るいさま。心のはればれとしたさま。
こう‐ぜん【皓然】カウ‥
白いさま。明らかなさま。「―たる月光」
こう‐ぜん【煌然】クワウ‥
かがやくさま。
こう‐ぜん【曠然】クワウ‥
広々としたさま。「―たる原野」
こう‐ぜん【鏗然】カウ‥
金属・石など堅いものが当たってかん高い音の出るさま。
ごう‐せん【合繊】ガフ‥
合成繊維の略。
ごう‐ぜん【傲然】ガウ‥
おごりたかぶるさま。「―と肩をそびやかす」「―たる態度」
ごう‐ぜん【豪然】ガウ‥
力強く、すぐれているさま。また、尊大で、おごっているさま。
ごう‐ぜん【囂然】ガウ‥
かまびすしいさま。「場内―」
ごう‐ぜん【轟然】ガウ‥
とどろき響くさま。「―たる発射音」
こうせん‐えん【鉱泉塩】クワウ‥
鉱泉を蒸発させて得た塩類。また、人工的にこれを模造した塩類。
⇒こう‐せん【鉱泉】
こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】クワウ‥クワ‥シヤウ
通常は異常を起こさない量や波長の光線で発赤・皮疹などの皮膚症状を起こす病態。多形日光疹・日光蕁じん麻疹・色素性乾皮症・ポルフィリン症などがある。
⇒こう‐せん【光線】
こう‐せんきょ【閘船渠】カフ‥
ドックの一種。潮汐の大きな港で、満潮を利用して船舶の出入・碇繋ていけいをさせるため、入口に閘門を備え、干潮でも水深を一定に保たせる。繋船ドック。
こうせん‐くいき【交戦区域】カウ‥ヰキ
交戦国兵力が互いに敵対行為を行い得べき地域。交戦国の領土・領海・領空ならびに公海などで、中立領域を含まない。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐くうご【曠前空後】クワウ‥
後にも先にもないこと。きわめて珍しいこと。空前絶後。
こうせん‐けん【交戦権】カウ‥
国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に行使し得る権利。自衛のための交戦権の有無が日本国憲法第9条の解釈上の一争点となっている。
→参照条文:日本国憲法第9条
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐こく【交戦国】カウ‥
戦争の当事者たる国家。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜんごこくろん【興禅護国論】
栄西の著。3巻。1198年(建久9)成る。栄西が宋から帰朝して禅宗を伝えた時にまき起こった仏教界からの非難に対して、禅による国家の繁栄を主張したもの。
こう‐せんし【高仙芝】カウ‥
高句麗出身の唐の武将。西域経営に功績をたて安西都護となる。751年、タラス河畔の戦でアッバース軍に大敗。( 〜755)
こうせん‐だんたい【交戦団体】カウ‥
国際法上の交戦者としての資格を認められた反乱団体。「―の承認」
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐てき【好戦的】カウ‥
戦いを好む傾向のあるさま。「―な部族」
⇒こう‐せん【好戦】
こうせん‐とう【交閃灯】カウ‥
回転して異なった色の光を交互に放つ灯火。
こうぜん‐の‐き【浩然の気】カウ‥
[孟子公孫丑上「我善く吾が浩然の気を養う」]
①天地の間に満ち満ちている非常に盛んな精気。
②俗事から解放された屈託のない心境。「―を養う」
⇒こう‐ぜん【浩然】
こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
表向き秘密であることにはなっているが、実際には世間に知れ渡ってしまっていること。
⇒こう‐ぜん【公然】
こうせん‐ほうき【交戦法規】カウ‥ハフ‥
戦争の当事者がどのような戦闘手段を用いることを許されるかなど、交戦国の行動を律する国際法規。近年は、戦争犠牲者の保護を目的とする国際人道法の一部分として扱われることもある。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
不特定・多数の人が認識できる状態で猥褻の行為をする罪。→猥褻罪
⇒こう‐ぜん【公然】
こう‐そ【公租】
おおやけの目的のために課せられる金銭負担の一つ。国税・地方税の総称。「―公課」
こう‐そ【公訴】
〔法〕
①刑事に関する訴訟。
②刑事に関して検察官が起訴状を提出して裁判所の審判を求めること。「―権」「―の提起」
⇒こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
⇒こうそ‐じこう【公訴時効】
⇒こうそ‐じじつ【公訴事実】
こうそ【江蘇】カウ‥
(Jiangsu)中国東部、長江下流の沿海の省。面積約10万平方キロメートル。省南部の長江デルタ地帯には上海と南京を結ぶ交通線上に新興工業都市が林立。稲作灌漑のため全省に運河・クリークが発達し、全国有数の穀倉地帯。省都は南京。略称、蘇。→中華人民共和国(図)
こう‐そ【後素】
[論語八佾「絵事後素」]絵画。絵。→絵事かいじは素を後にす(「絵事」成句)
こう‐そ【皇祖】クワウ‥
天皇の先祖。天照大神あまてらすおおみかみまたは神武天皇の称。また、天照大神から神武天皇まで代々の総称。→皇宗。
⇒こうそ‐こうそう【皇祖皇宗】
こう‐そ【皇祚】クワウ‥
天皇の位。帝位。
こう‐そ【貢租】
田地に課せられる租税。ねんぐ。
こう‐そ【高祖】カウ‥
①祖父母の祖父母。
②遠い祖先。
③一宗一派を開いた僧を敬っていう語。「―日蓮」
④中国王朝で最初の天子。特に、漢の劉邦および唐の李淵。
こう‐そ【控訴】
〔法〕第一審の判決を不服とする場合に、その取消し・変更を直接上級裁判所に求める訴訟手続。
⇒こうそ‐いん【控訴院】
⇒こうそ‐きかん【控訴期間】
⇒こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
⇒こうそ‐さいばんしょ【控訴裁判所】
⇒こうそ‐しゅいしょ【控訴趣意書】
⇒こうそ‐しん【控訴審】
⇒こうそ‐にん【控訴人】
こう‐そ【酵素】カウ‥
(enzyme)生体内で営まれる化学反応に触媒として作用する高分子物質。生体内で物質代謝に関与する。蛋白質またはこれと補酵素と呼ばれる低分子物質との複合体。触媒する反応の型によってオキシダーゼ・レダクターゼ・ヒドロラーゼ・デヒドロゲナーゼ・イソメラーゼなどに分類され、それぞれ特定の化合物に対して特異的に作用する。熱・金属イオンなどによって活性を失う。エンザイム。
酵素の分類(表)
じょきの徐氏体と対比され、院体花鳥画の基礎をなした。( 〜965)
こう‐せん【腔線】カウ‥
銃砲身の内面に螺旋らせん状に彫った溝。発射弾に回転運動を与え弾道を安定させる。腔綫。ライフル。
こう‐せん【鉱泉】クワウ‥
鉱物質またはガスを多量に含む泉水。広義には温泉と冷泉との総称で、狭義には冷泉だけをいう。→温泉。
⇒こうせん‐えん【鉱泉塩】
こう‐せん【鋼船】カウ‥
鋼鉄で造った船。
こう‐せん【講銭】カウ‥
講中の掛け金。
こう‐ぜん【公然】
①おおっぴらなさま。一般に知れわたったさま。おもてむき。「白昼―と押し入る」「―たる事実」
②〔法〕ある事柄を不特定多数の人または利害関係ある人に秘密にせず、明白な形式でするさま。
⇒こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
⇒こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
こう‐ぜん【呷然】カフ‥
大声をあげるさま。内田魯庵、くれの廿八日「独り黒斜子の五紋は―として笑出した」
こう‐ぜん【哄然】
どっと笑うさま。
こう‐ぜん【昂然】カウ‥
自負があって意気のあがるさま。「―たる態度」「―として言い放つ」
こう‐ぜん【紅髯】
①あかいひげ。
②西洋人のひげ。また、西洋人。
③エビの異称。
こう‐ぜん【浩然】カウ‥
①水が盛んに流れるさま。
②心などが広くゆったりしているさま。「―たる態度」
⇒こうぜん‐の‐き【浩然の気】
こう‐ぜん【耿然】カウ‥
明るいさま。心のはればれとしたさま。
こう‐ぜん【皓然】カウ‥
白いさま。明らかなさま。「―たる月光」
こう‐ぜん【煌然】クワウ‥
かがやくさま。
こう‐ぜん【曠然】クワウ‥
広々としたさま。「―たる原野」
こう‐ぜん【鏗然】カウ‥
金属・石など堅いものが当たってかん高い音の出るさま。
ごう‐せん【合繊】ガフ‥
合成繊維の略。
ごう‐ぜん【傲然】ガウ‥
おごりたかぶるさま。「―と肩をそびやかす」「―たる態度」
ごう‐ぜん【豪然】ガウ‥
力強く、すぐれているさま。また、尊大で、おごっているさま。
ごう‐ぜん【囂然】ガウ‥
かまびすしいさま。「場内―」
ごう‐ぜん【轟然】ガウ‥
とどろき響くさま。「―たる発射音」
こうせん‐えん【鉱泉塩】クワウ‥
鉱泉を蒸発させて得た塩類。また、人工的にこれを模造した塩類。
⇒こう‐せん【鉱泉】
こうせん‐かびんしょう【光線過敏症】クワウ‥クワ‥シヤウ
通常は異常を起こさない量や波長の光線で発赤・皮疹などの皮膚症状を起こす病態。多形日光疹・日光蕁じん麻疹・色素性乾皮症・ポルフィリン症などがある。
⇒こう‐せん【光線】
こう‐せんきょ【閘船渠】カフ‥
ドックの一種。潮汐の大きな港で、満潮を利用して船舶の出入・碇繋ていけいをさせるため、入口に閘門を備え、干潮でも水深を一定に保たせる。繋船ドック。
こうせん‐くいき【交戦区域】カウ‥ヰキ
交戦国兵力が互いに敵対行為を行い得べき地域。交戦国の領土・領海・領空ならびに公海などで、中立領域を含まない。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐くうご【曠前空後】クワウ‥
後にも先にもないこと。きわめて珍しいこと。空前絶後。
こうせん‐けん【交戦権】カウ‥
国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に行使し得る権利。自衛のための交戦権の有無が日本国憲法第9条の解釈上の一争点となっている。
→参照条文:日本国憲法第9条
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐こく【交戦国】カウ‥
戦争の当事者たる国家。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜんごこくろん【興禅護国論】
栄西の著。3巻。1198年(建久9)成る。栄西が宋から帰朝して禅宗を伝えた時にまき起こった仏教界からの非難に対して、禅による国家の繁栄を主張したもの。
こう‐せんし【高仙芝】カウ‥
高句麗出身の唐の武将。西域経営に功績をたて安西都護となる。751年、タラス河畔の戦でアッバース軍に大敗。( 〜755)
こうせん‐だんたい【交戦団体】カウ‥
国際法上の交戦者としての資格を認められた反乱団体。「―の承認」
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐てき【好戦的】カウ‥
戦いを好む傾向のあるさま。「―な部族」
⇒こう‐せん【好戦】
こうせん‐とう【交閃灯】カウ‥
回転して異なった色の光を交互に放つ灯火。
こうぜん‐の‐き【浩然の気】カウ‥
[孟子公孫丑上「我善く吾が浩然の気を養う」]
①天地の間に満ち満ちている非常に盛んな精気。
②俗事から解放された屈託のない心境。「―を養う」
⇒こう‐ぜん【浩然】
こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
表向き秘密であることにはなっているが、実際には世間に知れ渡ってしまっていること。
⇒こう‐ぜん【公然】
こうせん‐ほうき【交戦法規】カウ‥ハフ‥
戦争の当事者がどのような戦闘手段を用いることを許されるかなど、交戦国の行動を律する国際法規。近年は、戦争犠牲者の保護を目的とする国際人道法の一部分として扱われることもある。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
不特定・多数の人が認識できる状態で猥褻の行為をする罪。→猥褻罪
⇒こう‐ぜん【公然】
こう‐そ【公租】
おおやけの目的のために課せられる金銭負担の一つ。国税・地方税の総称。「―公課」
こう‐そ【公訴】
〔法〕
①刑事に関する訴訟。
②刑事に関して検察官が起訴状を提出して裁判所の審判を求めること。「―権」「―の提起」
⇒こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
⇒こうそ‐じこう【公訴時効】
⇒こうそ‐じじつ【公訴事実】
こうそ【江蘇】カウ‥
(Jiangsu)中国東部、長江下流の沿海の省。面積約10万平方キロメートル。省南部の長江デルタ地帯には上海と南京を結ぶ交通線上に新興工業都市が林立。稲作灌漑のため全省に運河・クリークが発達し、全国有数の穀倉地帯。省都は南京。略称、蘇。→中華人民共和国(図)
こう‐そ【後素】
[論語八佾「絵事後素」]絵画。絵。→絵事かいじは素を後にす(「絵事」成句)
こう‐そ【皇祖】クワウ‥
天皇の先祖。天照大神あまてらすおおみかみまたは神武天皇の称。また、天照大神から神武天皇まで代々の総称。→皇宗。
⇒こうそ‐こうそう【皇祖皇宗】
こう‐そ【皇祚】クワウ‥
天皇の位。帝位。
こう‐そ【貢租】
田地に課せられる租税。ねんぐ。
こう‐そ【高祖】カウ‥
①祖父母の祖父母。
②遠い祖先。
③一宗一派を開いた僧を敬っていう語。「―日蓮」
④中国王朝で最初の天子。特に、漢の劉邦および唐の李淵。
こう‐そ【控訴】
〔法〕第一審の判決を不服とする場合に、その取消し・変更を直接上級裁判所に求める訴訟手続。
⇒こうそ‐いん【控訴院】
⇒こうそ‐きかん【控訴期間】
⇒こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
⇒こうそ‐さいばんしょ【控訴裁判所】
⇒こうそ‐しゅいしょ【控訴趣意書】
⇒こうそ‐しん【控訴審】
⇒こうそ‐にん【控訴人】
こう‐そ【酵素】カウ‥
(enzyme)生体内で営まれる化学反応に触媒として作用する高分子物質。生体内で物質代謝に関与する。蛋白質またはこれと補酵素と呼ばれる低分子物質との複合体。触媒する反応の型によってオキシダーゼ・レダクターゼ・ヒドロラーゼ・デヒドロゲナーゼ・イソメラーゼなどに分類され、それぞれ特定の化合物に対して特異的に作用する。熱・金属イオンなどによって活性を失う。エンザイム。
酵素の分類(表)
 こう‐そ【縞素】カウ‥
白色の喪服。
こうぞ【楮】カウゾ
(カミソ(紙麻)の音便)クワ科の落葉低木。西日本の山地に自生し、繊維作物として各地で栽培。高さ約3メートルに達する。葉は桑に似て質はやや薄く粗い。雌雄同株。6月頃、淡黄緑色の花を開く。果実は赤熟、桑の実に似る。樹皮は和紙の原料。かぞ。かんず。伊呂波字類抄「楮、カウソ」
こうぞ
こう‐そ【縞素】カウ‥
白色の喪服。
こうぞ【楮】カウゾ
(カミソ(紙麻)の音便)クワ科の落葉低木。西日本の山地に自生し、繊維作物として各地で栽培。高さ約3メートルに達する。葉は桑に似て質はやや薄く粗い。雌雄同株。6月頃、淡黄緑色の花を開く。果実は赤熟、桑の実に似る。樹皮は和紙の原料。かぞ。かんず。伊呂波字類抄「楮、カウソ」
こうぞ
 コウゾ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
コウゾ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 コウゾ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
コウゾ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒こうぞ‐がみ【楮紙】
ごう‐そ【拷訴】ガウ‥
罪人をあらあらしく責めつけること。
ごう‐そ【強訴・嗷訴】ガウ‥
為政者に対し、徒党を組んで強硬に訴えること。院政期前後の、南都北嶺の僧兵らの動座入洛は有名。太平記21「山門の―今に有りなん」
こうそ‐いん【控訴院】‥ヰン
旧制で、地方裁判所の直接上級裁判所。現在の高等裁判所に相当する。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そう【口奏】
口頭で奏上すること。
こう‐そう【公葬】‥サウ
功労のあった人などのために、公費で営む葬儀。
こう‐そう【広壮・宏壮】クワウサウ
広く大きくりっぱなこと。「―な邸宅」
こう‐そう【好走】カウ‥
野球・マラソンなどのスポーツで、よい走りをすること。
こう‐そう【行装】カウサウ
旅行の支度。たびじたく。旅装。
こう‐そう【抗争】カウサウ
さからいあらそうこと。はりあいあらそうこと。「大国間の―」
こう‐そう【厚葬】‥サウ
手厚く埋葬すること。↔薄葬
こう‐そう【咬創】カウサウ
かまれたきず。かみきず。
こう‐そう【後奏】
独奏・独唱などが終わった後に奏する伴奏部分。↔前奏。
⇒こうそう‐きょく【後奏曲】
こう‐そう【後送】
①後方へ送ること。特に戦場などで、前線から後方へ送ること。
②あとから送ること。
こう‐そう【後装】‥サウ
銃の遊底または砲の閉鎖機を開閉して弾薬を装填そうてんすること。もとごめ。↔前装
こう‐そう【皇宗】クワウ‥
天皇の代々の祖先。第2代以後の歴代を指す。→皇祖
こう‐そう【紅藻】‥サウ
紅藻綱の総称。細胞にクロロフィルaとフィコエリトリンを含む葉緑体を持ち、体色は紅色または紫色を呈す。紅藻澱粉を生成。多くは多細胞で、糸状・葉状・羽状・殻状。世界に約5500種。主に海藻で、淡水産は約150種。食用や寒天原藻になるものを含む。海産種は、アサクサノリ・オゴノリ・マクサ・フクロフノリ・トサカノリなど。淡水産種には、カワモズク・チスジノリなど。紅色植物。
こう‐そう【香草】カウサウ
においのよい草。香気のある草。
こう‐そう【倥偬】
いそがしいこと。「兵馬―の間かん」
こう‐そう【校葬】カウサウ
学校が主催して営む葬儀。
こう‐そう【航走】カウ‥
船が水上を進むこと。航行。
こう‐そう【航送】カウ‥
船舶または航空機によって物を輸送すること。
こう‐そう【訌争】‥サウ
うちわもめのあらそい。内訌。内紛。
こう‐そう【降霜】カウサウ
霜のふること。また、ふった霜。
こう‐そう【高宗】カウ‥
唐の第3代、南宋の初代、清の第6代(乾隆帝)、朝鮮李朝の26代(李太王)などの皇帝の廟号。
こう‐そう【高相】カウサウ
高貴な人相。また、そのような人。宇治拾遺物語1「やんごとなき―の夢見てけり」
こう‐そう【高僧】カウ‥
①知徳のすぐれた僧。
②官位の高い僧。
⇒こうそう‐でん【高僧伝】
こう‐そう【高層】カウ‥
①層が幾重にも高く重なっていること。建物の階数が多いこと。「―建築」
②大気圏の上方の層。「―気象台」
⇒こうそう‐うん【高層雲】
⇒こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】
⇒こうそう‐きしょうだい【高層気象台】
⇒こうそう‐てんきず【高層天気図】
こう‐そう【高燥】カウサウ
土地が高くて湿気の少ないこと。「―の地」↔低湿
こう‐そう【黄巣】クワウサウ
唐末農民反乱の指導者。山東曹州の人。科挙に落第して、塩の闇商人となる。( 〜884)
⇒こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】
こう‐そう【鉱層】クワウ‥
海水や湖水などに溶けていた化学成分が沈殿・堆積して層状になった鉱床。世界の主要な鉄鉱床は、この型に属する。成層鉱床。
こう‐そう【構想】‥サウ
①考えを組み立てること。また、その考え。「組閣の―を練る」
②芸術作品を制作する場合、主題・仕組・思想内容・表現形式などあらゆる要素の構成を思考すること。
⇒こうそう‐りょく【構想力】
こう‐そう【鴻爪】‥サウ
[蘇軾、子由澠池旧を懐おもうに和する詩](鴻が南に来る時には、後の心覚えに雪に爪痕をつけるが、北に帰る時には、雪とともにその痕が消えていることからいう)往時の痕跡。また、跡形が残らないこと。行方ゆくえのはっきりしないこと。雪泥の鴻爪。
こう‐そう【鏗鏘】カウサウ
金石・琴などの鳴る音。
こう‐ぞう【行障】カウザウ
⇒こうしょう
こう‐ぞう【行蔵】カウザウ
世に出て道を行うことと隠遁して世に出ないこと。出処進退。
こう‐ぞう【香象】カウザウ
青色で香気を帯び、河海を歩いてわたるという想像上の大きな象。太平記14「―の浪を踏んで大海を渡らん勢ひの如く」
こう‐ぞう【構造】‥ザウ
①いくつかの材料を組み合わせてこしらえられたもの。また、そのしくみ。くみたて。「柔―のビル」
②全体を構成する諸要素の、互いの対立や矛盾、また依存の関係などの総称。「汚職の―」
⇒こうぞう‐いせい【構造異性】
⇒こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】
⇒こうぞう‐うんどう【構造運動】
⇒こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】
⇒こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】
⇒こうぞう‐けいさん【構造計算】
⇒こうぞう‐げんごがく【構造言語学】
⇒こうぞう‐しき【構造式】
⇒こうぞう‐じしん【構造地震】
⇒こうぞう‐しゅぎ【構造主義】
⇒こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】
⇒こうぞう‐せん【構造線】
⇒こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】
⇒こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】
⇒こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】
⇒こうぞう‐ど【構造土】
⇒こうぞう‐ようざい【構造用材】
ごう‐そう【合装】ガフサウ
①一つに合わせて荷づくりすること。
②一つに合わせて綴じること。
ごう‐そう【豪壮】ガウサウ
はでやかで勢いの盛んなこと。豪勢で立派なこと。「―な邸宅」
ごう‐そう【豪爽】ガウサウ
気性が、すぐれてさわやかなこと。豪快で、ことばや動作が人に快く感じられること。
こうぞう‐いせい【構造異性】‥ザウ‥
分子式は同じであるが構造式が異なることによる異性。ブタン(CH3CH2CH2CH3)とイソブタン((CH3)3CH)の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】‥ザウヰ‥
酵素や筋肉などの蛋白質のアミノ酸配列やRNAの塩基配列を決めている遺伝子。調節遺伝子と対比される。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐うん【高層雲】カウ‥
十種雲級の一つ。中層雲に属し、中緯度帯では2〜7キロメートルの高さに現れる。上空に広がってほとんど満天を覆う、やや濃い灰色を呈する幕のような雲。おぼろぐも。記号As →雲級(表)。
高層雲
撮影:高橋健司
⇒こうぞ‐がみ【楮紙】
ごう‐そ【拷訴】ガウ‥
罪人をあらあらしく責めつけること。
ごう‐そ【強訴・嗷訴】ガウ‥
為政者に対し、徒党を組んで強硬に訴えること。院政期前後の、南都北嶺の僧兵らの動座入洛は有名。太平記21「山門の―今に有りなん」
こうそ‐いん【控訴院】‥ヰン
旧制で、地方裁判所の直接上級裁判所。現在の高等裁判所に相当する。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そう【口奏】
口頭で奏上すること。
こう‐そう【公葬】‥サウ
功労のあった人などのために、公費で営む葬儀。
こう‐そう【広壮・宏壮】クワウサウ
広く大きくりっぱなこと。「―な邸宅」
こう‐そう【好走】カウ‥
野球・マラソンなどのスポーツで、よい走りをすること。
こう‐そう【行装】カウサウ
旅行の支度。たびじたく。旅装。
こう‐そう【抗争】カウサウ
さからいあらそうこと。はりあいあらそうこと。「大国間の―」
こう‐そう【厚葬】‥サウ
手厚く埋葬すること。↔薄葬
こう‐そう【咬創】カウサウ
かまれたきず。かみきず。
こう‐そう【後奏】
独奏・独唱などが終わった後に奏する伴奏部分。↔前奏。
⇒こうそう‐きょく【後奏曲】
こう‐そう【後送】
①後方へ送ること。特に戦場などで、前線から後方へ送ること。
②あとから送ること。
こう‐そう【後装】‥サウ
銃の遊底または砲の閉鎖機を開閉して弾薬を装填そうてんすること。もとごめ。↔前装
こう‐そう【皇宗】クワウ‥
天皇の代々の祖先。第2代以後の歴代を指す。→皇祖
こう‐そう【紅藻】‥サウ
紅藻綱の総称。細胞にクロロフィルaとフィコエリトリンを含む葉緑体を持ち、体色は紅色または紫色を呈す。紅藻澱粉を生成。多くは多細胞で、糸状・葉状・羽状・殻状。世界に約5500種。主に海藻で、淡水産は約150種。食用や寒天原藻になるものを含む。海産種は、アサクサノリ・オゴノリ・マクサ・フクロフノリ・トサカノリなど。淡水産種には、カワモズク・チスジノリなど。紅色植物。
こう‐そう【香草】カウサウ
においのよい草。香気のある草。
こう‐そう【倥偬】
いそがしいこと。「兵馬―の間かん」
こう‐そう【校葬】カウサウ
学校が主催して営む葬儀。
こう‐そう【航走】カウ‥
船が水上を進むこと。航行。
こう‐そう【航送】カウ‥
船舶または航空機によって物を輸送すること。
こう‐そう【訌争】‥サウ
うちわもめのあらそい。内訌。内紛。
こう‐そう【降霜】カウサウ
霜のふること。また、ふった霜。
こう‐そう【高宗】カウ‥
唐の第3代、南宋の初代、清の第6代(乾隆帝)、朝鮮李朝の26代(李太王)などの皇帝の廟号。
こう‐そう【高相】カウサウ
高貴な人相。また、そのような人。宇治拾遺物語1「やんごとなき―の夢見てけり」
こう‐そう【高僧】カウ‥
①知徳のすぐれた僧。
②官位の高い僧。
⇒こうそう‐でん【高僧伝】
こう‐そう【高層】カウ‥
①層が幾重にも高く重なっていること。建物の階数が多いこと。「―建築」
②大気圏の上方の層。「―気象台」
⇒こうそう‐うん【高層雲】
⇒こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】
⇒こうそう‐きしょうだい【高層気象台】
⇒こうそう‐てんきず【高層天気図】
こう‐そう【高燥】カウサウ
土地が高くて湿気の少ないこと。「―の地」↔低湿
こう‐そう【黄巣】クワウサウ
唐末農民反乱の指導者。山東曹州の人。科挙に落第して、塩の闇商人となる。( 〜884)
⇒こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】
こう‐そう【鉱層】クワウ‥
海水や湖水などに溶けていた化学成分が沈殿・堆積して層状になった鉱床。世界の主要な鉄鉱床は、この型に属する。成層鉱床。
こう‐そう【構想】‥サウ
①考えを組み立てること。また、その考え。「組閣の―を練る」
②芸術作品を制作する場合、主題・仕組・思想内容・表現形式などあらゆる要素の構成を思考すること。
⇒こうそう‐りょく【構想力】
こう‐そう【鴻爪】‥サウ
[蘇軾、子由澠池旧を懐おもうに和する詩](鴻が南に来る時には、後の心覚えに雪に爪痕をつけるが、北に帰る時には、雪とともにその痕が消えていることからいう)往時の痕跡。また、跡形が残らないこと。行方ゆくえのはっきりしないこと。雪泥の鴻爪。
こう‐そう【鏗鏘】カウサウ
金石・琴などの鳴る音。
こう‐ぞう【行障】カウザウ
⇒こうしょう
こう‐ぞう【行蔵】カウザウ
世に出て道を行うことと隠遁して世に出ないこと。出処進退。
こう‐ぞう【香象】カウザウ
青色で香気を帯び、河海を歩いてわたるという想像上の大きな象。太平記14「―の浪を踏んで大海を渡らん勢ひの如く」
こう‐ぞう【構造】‥ザウ
①いくつかの材料を組み合わせてこしらえられたもの。また、そのしくみ。くみたて。「柔―のビル」
②全体を構成する諸要素の、互いの対立や矛盾、また依存の関係などの総称。「汚職の―」
⇒こうぞう‐いせい【構造異性】
⇒こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】
⇒こうぞう‐うんどう【構造運動】
⇒こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】
⇒こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】
⇒こうぞう‐けいさん【構造計算】
⇒こうぞう‐げんごがく【構造言語学】
⇒こうぞう‐しき【構造式】
⇒こうぞう‐じしん【構造地震】
⇒こうぞう‐しゅぎ【構造主義】
⇒こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】
⇒こうぞう‐せん【構造線】
⇒こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】
⇒こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】
⇒こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】
⇒こうぞう‐ど【構造土】
⇒こうぞう‐ようざい【構造用材】
ごう‐そう【合装】ガフサウ
①一つに合わせて荷づくりすること。
②一つに合わせて綴じること。
ごう‐そう【豪壮】ガウサウ
はでやかで勢いの盛んなこと。豪勢で立派なこと。「―な邸宅」
ごう‐そう【豪爽】ガウサウ
気性が、すぐれてさわやかなこと。豪快で、ことばや動作が人に快く感じられること。
こうぞう‐いせい【構造異性】‥ザウ‥
分子式は同じであるが構造式が異なることによる異性。ブタン(CH3CH2CH2CH3)とイソブタン((CH3)3CH)の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐いでんし【構造遺伝子】‥ザウヰ‥
酵素や筋肉などの蛋白質のアミノ酸配列やRNAの塩基配列を決めている遺伝子。調節遺伝子と対比される。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐うん【高層雲】カウ‥
十種雲級の一つ。中層雲に属し、中緯度帯では2〜7キロメートルの高さに現れる。上空に広がってほとんど満天を覆う、やや濃い灰色を呈する幕のような雲。おぼろぐも。記号As →雲級(表)。
高層雲
撮影:高橋健司
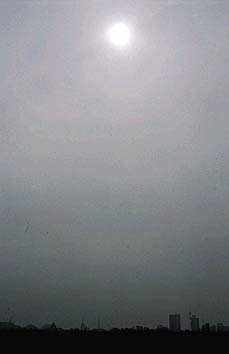 ⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐うんどう【構造運動】‥ザウ‥
地層や岩石に褶曲しゅうきょく・断層など変形・破壊をひきおこす地殻の運動の総称。主要なものは造山運動に伴って起きる。造構造運動。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐かい【紅槍会】‥サウクワイ
(紅い房のついた槍を用いたからいう)清末以降、軍閥・匪賊の圧迫・搾取に対抗した中国華北農民の武装自衛の秘密結社。
こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】‥ザウ‥
社会主義に移行するための政治理論の一つ。労働者階級が国家権力を掌握する以前の段階でも独占資本の構造を部分的に改革することを通じて段階的に社会主義を実現できるとした。トリアッティらが提唱。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】‥ザウクワ‥
(structured programming)コンピューターのプログラム作成の方法論の一つ。プログラムの構造を階層化・抽象化し、段階的に詳細化することで、大規模で複雑なプログラムを正確に作成する。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうぎ【黄宗羲】クワウ‥
明末・清初の学者・思想家。字は太沖。号は梨洲・南雷。諡は文孝。浙江余姚の人。陽明学の流れを汲み、実用政治学のほか、歴史・天文・数学にも精通。著「宋元学案」「明儒学案」「易学象数論」「明夷待訪録」など。(1610〜1695)
こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】カウ‥シヤウクワン‥
高層大気中の気象の観測。凧たこ・気球・ラジオゾンデ・飛行機・気象ロケットなどでの観測のほか、レーダー・人工衛星を利用した観測も行われている。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きしょうだい【高層気象台】カウ‥シヤウ‥
気象庁の機関の一つ。茨城県つくば市にあり、高層気象の精密な観測・調査、測器の試験・改良などを行う。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きょく【後奏曲】
礼拝後などに奏するオルガンなどの楽曲。
⇒こう‐そう【後奏】
こうぞう‐けいさん【構造計算】‥ザウ‥
構造物に加わる自重、積載荷重、積雪・風圧・地震などの外力に対する安全性を数値計算すること。「―書」
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐げんごがく【構造言語学】‥ザウ‥
(structural linguistics)言語を作る要素の関係性に注目して、言語の体系や構造を解明することを目的とする言語理論。ソシュールを先駆者とし、その流れをひくフランス‐スイス学派・プラーグ学派・コペンハーゲン学派などがある。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しき【構造式】‥ザウ‥
元素記号を短い線(価標)で結びつけて、分子内の各原子の結合のしかたを表す化学式。水をH‐O‐Hとする類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じしん【構造地震】‥ザウヂ‥
地質学上の断層と密接な関係のある地震。多くの地震はこれに属すると考えられる。断層地震。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しゅぎ【構造主義】‥ザウ‥
(structuralism)一般に、研究対象の構造の研究を主とする研究方法。また、その立場。
①言語(ラング)に内在する構造(structure)をつかみ出し、各要素の機能的連関を明らかにする言語学の立場。ソシュールに始まる。
②社会・文化現象の意味秩序も言語構造と類比的なものと見て、これを分析方法に導入する学問的立場の総称。ヤコブソンやムカジョフスキー(J. Mukařovský1891〜1975)の構造主義的美学・詩学があるが、特にレヴィ=ストロースが人類学にこの方法を導入、未開社会の複雑多様な親族組織の分析に成功して以来、フランスを中心にラカン・アルチュセール・M.フーコーらによって、反人間中心主義的な人文科学の方法として活用された。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】‥ザウ‥
(anthropologie structurale フランス)構造主義的な立場をとる人類学。レヴィ=ストロースが創始。ある親族・婚姻体系や神話などを、他の体系や神話を論理的に変換したものととらえ、その変換の関係を明らかにしようとする。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐せん【構造線】‥ザウ‥
〔地〕規模の大きな断層または断層群。中央構造線の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうそん【皇曾孫】クワウ‥
天皇のひまご。
こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】‥ザウ‥
地層や岩体の構造とその発達史を調べ、どのような運動や作用で生じたかを明らかにする地質学の一分野。褶曲しゅうきょくや断層で代表される変形や破壊現象に加えて、岩石や鉱物の物性論も扱う。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】‥ザウ‥ゲフ
経済構造の変化に伴って衰退する産業や地域で発生する慢性的失業。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】‥ザウ‥キヤウ
景気循環に伴う全般的不況ではなく、特定の産業が、産業構造・需要構造など経済の変化への対応が遅れたために陥る不況。構造不況。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐でん【高僧伝】カウ‥
①高僧の伝記を集成したもの。中国には、梁高僧伝(14巻、慧皎えこう撰、519年成る)のほか、続高僧伝(唐高僧伝、30巻、道宣撰)・宋高僧伝(30巻、賛寧撰)・大明高僧伝(8巻、如惺にょせい撰)などがあり、日本には本朝高僧伝などがある。
②特に、仏教伝来より当代に至る高僧の伝記を集成した梁高僧伝を指す。
⇒こう‐そう【高僧】
こうそう‐てんきず【高層天気図】カウ‥ヅ
上空の気象状況を示す天気図。ふつう一定気圧面の高度分布と共に気温・風向・風速などを記入・解析してある。等圧面天気図。
⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐ど【構造土】‥ザウ‥
岩屑や草叢くさむらが円形・多角形・縞状・階段状などの幾何学模様を呈する地表面。周氷河地形の一種。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】クワウサウ‥
唐末に起こった農民反乱。875年、王仙芝の河北での挙兵に黄巣が山東で呼応、四川を除きほとんど全中国に転戦し、880年洛陽・長安を占領して帝位につき、国号を大斉と号したが、唐朝の反撃で884年に鎮圧された。唐朝滅亡の近因となる。
⇒こう‐そう【黄巣】
こうぞう‐ようざい【構造用材】‥ザウ‥
木造建築の土台・柱・梁などに使用する木材。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐りょく【構想力】‥サウ‥
①これから実現しようとする物事を考えの中で組み立てる能力。
②哲学で、(→)想像力に同じ。特にカント哲学では、対象が現前しないのに、対象を直観において表象する能力とされる。
⇒こう‐そう【構想】
こうぞ‐がみ【楮紙】カウゾ‥
和紙の一種。コウゾの樹皮の繊維を原料として漉すいた紙。杉原紙・美濃紙・西の内紙・清張紙・吉野紙・奉書など、品種が多い。古くから写経用紙・書類用紙・障子紙・傘紙・紙子紙などに広く用いられた。穀紙こくし。構紙かじがみ。ちょし。
⇒こうぞ【楮】
こうそ‐きかん【控訴期間】
控訴することのできる期間。民事訴訟では判決の送達日から、刑事訴訟では判決の告知日からそれぞれ2週間(14日間)。
⇒こう‐そ【控訴】
こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
刑事訴訟上、公訴提起が有効であるための条件(訴訟条件)を欠くため、公訴を無効として手続を打ち切る裁判。
⇒こう‐そ【公訴】
こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
控訴による不服申立ての理由がないとする裁判。原判決が維持される。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そく【光束】クワウ‥
①幾何光学で光線の束のこと。
②ある面をある時間に通過する光の量。国際単位系での単位はルーメン(lm)。
こう‐そく【光速】クワウ‥
(→)光速度に同じ。
こう‐そく【拘束】
①行動の自由を制限し、または停止すること。
②拘引して束縛すること。「身柄を―する」
⇒こうそく‐じかん【拘束時間】
⇒こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
⇒こうそく‐りょく【拘束力】
こう‐そく【後足】
後部の足。あとあし。
こう‐そく【校則】カウ‥
児童・生徒を対象に、学校が制定した規則。生活指導文書的性格のものから、拘束性の強いものまで多岐にわたる。生徒心得。
こう‐そく【高足】カウ‥
①(もと、すぐれた馬の意)(→)高弟に同じ。
②田楽や田植の神事などに用いる、柱の長さ7尺、横木1尺ほどの1本のたけうま。また、この横木に両足をのせて跳ぶ芸。唐の散楽の一種目。一足いっそく。たかあし。
こう‐そく【高速】カウ‥
速度がはやいこと。高速度。「―で飛ばす」「―艇」
⇒こうそく‐きかん【高速機関】
⇒こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】
⇒こうそく‐どうろ【高速道路】
こう‐そく【梗塞】カウ‥
①ふさがって通じないこと。
②動脈が血栓などのためにふさがり、血液が流れなくなって、その動脈の支配する細胞・組織が壊死えしに陥る病変。心筋梗塞・脳梗塞など。
こう‐そく【港則】カウ‥
港湾を取り締まるための規則。
こう‐ぞく【公族】
1910年、韓国併合の後、前韓国王族李堈りこう・李熹りき・李埈およびその子孫で公として皇族の礼遇をうけた一族の称号。第二次大戦後、廃止。
こう‐ぞく【甲族】カフ‥
貴い家柄。貴族。門閥。
こう‐ぞく【後続】
あとから続くこと。「―部隊」
こう‐ぞく【皇族】クワウ‥
天皇の一族。天皇を除き皇胤こういんの男子およびその配偶者ならびに皇胤の女子をいう。皇后・太皇太后・皇太后・親王(皇太子・皇太孫を含む)・親王妃・内親王・王・王妃・女王の総称。現憲法はこれを国民として取り扱い、政治上の特権を認めない。→宮家。
⇒こうぞく‐かいぎ【皇族会議】
⇒こうぞく‐ひ【皇族費】
⇒こうぞく‐ふ【皇族譜】
ごう‐ぞく【強賊】ガウ‥
⇒きょうぞく
ごう‐ぞく【豪族】ガウ‥
地方に土着し、勢力をもつ一族。今昔物語集1「当国・隣国の―の人来りて乞ふ」
こうぞく‐かいぎ【皇族会議】クワウ‥クワイ‥
旧皇室典範上の機関で、皇族の大事を議した親族会議。成年の皇族男子で構成され、内大臣らも参列。→皇室会議。
⇒こう‐ぞく【皇族】
こうそく‐きかん【高速機関】カウ‥クワン
自動車や航空機などに用いる回転速度の大きい機関。
⇒こう‐そく【高速】
こうぞく‐きょり【航続距離】カウ‥
船舶または航空機が、途中で給油することなく航海または航空を続行できる距離。
こうそく‐じ【光触寺】クワウ‥
鎌倉市十二所じゅにそにある時宗の寺。一遍の創建と伝え、本尊の伝運慶作頬焼ほおやき阿弥陀如来のほか、頬焼阿弥陀縁起絵巻などがある。
光触寺
撮影:関戸 勇
⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐うんどう【構造運動】‥ザウ‥
地層や岩石に褶曲しゅうきょく・断層など変形・破壊をひきおこす地殻の運動の総称。主要なものは造山運動に伴って起きる。造構造運動。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐かい【紅槍会】‥サウクワイ
(紅い房のついた槍を用いたからいう)清末以降、軍閥・匪賊の圧迫・搾取に対抗した中国華北農民の武装自衛の秘密結社。
こうぞう‐かいかく‐ろん【構造改革論】‥ザウ‥
社会主義に移行するための政治理論の一つ。労働者階級が国家権力を掌握する以前の段階でも独占資本の構造を部分的に改革することを通じて段階的に社会主義を実現できるとした。トリアッティらが提唱。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうか‐プログラミング【構造化プログラミング】‥ザウクワ‥
(structured programming)コンピューターのプログラム作成の方法論の一つ。プログラムの構造を階層化・抽象化し、段階的に詳細化することで、大規模で複雑なプログラムを正確に作成する。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうぎ【黄宗羲】クワウ‥
明末・清初の学者・思想家。字は太沖。号は梨洲・南雷。諡は文孝。浙江余姚の人。陽明学の流れを汲み、実用政治学のほか、歴史・天文・数学にも精通。著「宋元学案」「明儒学案」「易学象数論」「明夷待訪録」など。(1610〜1695)
こうそう‐きしょう‐かんそく【高層気象観測】カウ‥シヤウクワン‥
高層大気中の気象の観測。凧たこ・気球・ラジオゾンデ・飛行機・気象ロケットなどでの観測のほか、レーダー・人工衛星を利用した観測も行われている。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きしょうだい【高層気象台】カウ‥シヤウ‥
気象庁の機関の一つ。茨城県つくば市にあり、高層気象の精密な観測・調査、測器の試験・改良などを行う。
⇒こう‐そう【高層】
こうそう‐きょく【後奏曲】
礼拝後などに奏するオルガンなどの楽曲。
⇒こう‐そう【後奏】
こうぞう‐けいさん【構造計算】‥ザウ‥
構造物に加わる自重、積載荷重、積雪・風圧・地震などの外力に対する安全性を数値計算すること。「―書」
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐げんごがく【構造言語学】‥ザウ‥
(structural linguistics)言語を作る要素の関係性に注目して、言語の体系や構造を解明することを目的とする言語理論。ソシュールを先駆者とし、その流れをひくフランス‐スイス学派・プラーグ学派・コペンハーゲン学派などがある。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しき【構造式】‥ザウ‥
元素記号を短い線(価標)で結びつけて、分子内の各原子の結合のしかたを表す化学式。水をH‐O‐Hとする類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じしん【構造地震】‥ザウヂ‥
地質学上の断層と密接な関係のある地震。多くの地震はこれに属すると考えられる。断層地震。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐しゅぎ【構造主義】‥ザウ‥
(structuralism)一般に、研究対象の構造の研究を主とする研究方法。また、その立場。
①言語(ラング)に内在する構造(structure)をつかみ出し、各要素の機能的連関を明らかにする言語学の立場。ソシュールに始まる。
②社会・文化現象の意味秩序も言語構造と類比的なものと見て、これを分析方法に導入する学問的立場の総称。ヤコブソンやムカジョフスキー(J. Mukařovský1891〜1975)の構造主義的美学・詩学があるが、特にレヴィ=ストロースが人類学にこの方法を導入、未開社会の複雑多様な親族組織の分析に成功して以来、フランスを中心にラカン・アルチュセール・M.フーコーらによって、反人間中心主義的な人文科学の方法として活用された。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐じんるいがく【構造人類学】‥ザウ‥
(anthropologie structurale フランス)構造主義的な立場をとる人類学。レヴィ=ストロースが創始。ある親族・婚姻体系や神話などを、他の体系や神話を論理的に変換したものととらえ、その変換の関係を明らかにしようとする。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞう‐せん【構造線】‥ザウ‥
〔地〕規模の大きな断層または断層群。中央構造線の類。
⇒こう‐ぞう【構造】
こう‐そうそん【皇曾孫】クワウ‥
天皇のひまご。
こうぞう‐ちしつがく【構造地質学】‥ザウ‥
地層や岩体の構造とその発達史を調べ、どのような運動や作用で生じたかを明らかにする地質学の一分野。褶曲しゅうきょくや断層で代表される変形や破壊現象に加えて、岩石や鉱物の物性論も扱う。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐しつぎょう【構造的失業】‥ザウ‥ゲフ
経済構造の変化に伴って衰退する産業や地域で発生する慢性的失業。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうぞうてき‐ふきょう【構造的不況】‥ザウ‥キヤウ
景気循環に伴う全般的不況ではなく、特定の産業が、産業構造・需要構造など経済の変化への対応が遅れたために陥る不況。構造不況。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐でん【高僧伝】カウ‥
①高僧の伝記を集成したもの。中国には、梁高僧伝(14巻、慧皎えこう撰、519年成る)のほか、続高僧伝(唐高僧伝、30巻、道宣撰)・宋高僧伝(30巻、賛寧撰)・大明高僧伝(8巻、如惺にょせい撰)などがあり、日本には本朝高僧伝などがある。
②特に、仏教伝来より当代に至る高僧の伝記を集成した梁高僧伝を指す。
⇒こう‐そう【高僧】
こうそう‐てんきず【高層天気図】カウ‥ヅ
上空の気象状況を示す天気図。ふつう一定気圧面の高度分布と共に気温・風向・風速などを記入・解析してある。等圧面天気図。
⇒こう‐そう【高層】
こうぞう‐ど【構造土】‥ザウ‥
岩屑や草叢くさむらが円形・多角形・縞状・階段状などの幾何学模様を呈する地表面。周氷河地形の一種。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐の‐らん【黄巣の乱】クワウサウ‥
唐末に起こった農民反乱。875年、王仙芝の河北での挙兵に黄巣が山東で呼応、四川を除きほとんど全中国に転戦し、880年洛陽・長安を占領して帝位につき、国号を大斉と号したが、唐朝の反撃で884年に鎮圧された。唐朝滅亡の近因となる。
⇒こう‐そう【黄巣】
こうぞう‐ようざい【構造用材】‥ザウ‥
木造建築の土台・柱・梁などに使用する木材。
⇒こう‐ぞう【構造】
こうそう‐りょく【構想力】‥サウ‥
①これから実現しようとする物事を考えの中で組み立てる能力。
②哲学で、(→)想像力に同じ。特にカント哲学では、対象が現前しないのに、対象を直観において表象する能力とされる。
⇒こう‐そう【構想】
こうぞ‐がみ【楮紙】カウゾ‥
和紙の一種。コウゾの樹皮の繊維を原料として漉すいた紙。杉原紙・美濃紙・西の内紙・清張紙・吉野紙・奉書など、品種が多い。古くから写経用紙・書類用紙・障子紙・傘紙・紙子紙などに広く用いられた。穀紙こくし。構紙かじがみ。ちょし。
⇒こうぞ【楮】
こうそ‐きかん【控訴期間】
控訴することのできる期間。民事訴訟では判決の送達日から、刑事訴訟では判決の告知日からそれぞれ2週間(14日間)。
⇒こう‐そ【控訴】
こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
刑事訴訟上、公訴提起が有効であるための条件(訴訟条件)を欠くため、公訴を無効として手続を打ち切る裁判。
⇒こう‐そ【公訴】
こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
控訴による不服申立ての理由がないとする裁判。原判決が維持される。
⇒こう‐そ【控訴】
こう‐そく【光束】クワウ‥
①幾何光学で光線の束のこと。
②ある面をある時間に通過する光の量。国際単位系での単位はルーメン(lm)。
こう‐そく【光速】クワウ‥
(→)光速度に同じ。
こう‐そく【拘束】
①行動の自由を制限し、または停止すること。
②拘引して束縛すること。「身柄を―する」
⇒こうそく‐じかん【拘束時間】
⇒こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
⇒こうそく‐りょく【拘束力】
こう‐そく【後足】
後部の足。あとあし。
こう‐そく【校則】カウ‥
児童・生徒を対象に、学校が制定した規則。生活指導文書的性格のものから、拘束性の強いものまで多岐にわたる。生徒心得。
こう‐そく【高足】カウ‥
①(もと、すぐれた馬の意)(→)高弟に同じ。
②田楽や田植の神事などに用いる、柱の長さ7尺、横木1尺ほどの1本のたけうま。また、この横木に両足をのせて跳ぶ芸。唐の散楽の一種目。一足いっそく。たかあし。
こう‐そく【高速】カウ‥
速度がはやいこと。高速度。「―で飛ばす」「―艇」
⇒こうそく‐きかん【高速機関】
⇒こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】
⇒こうそく‐どうろ【高速道路】
こう‐そく【梗塞】カウ‥
①ふさがって通じないこと。
②動脈が血栓などのためにふさがり、血液が流れなくなって、その動脈の支配する細胞・組織が壊死えしに陥る病変。心筋梗塞・脳梗塞など。
こう‐そく【港則】カウ‥
港湾を取り締まるための規則。
こう‐ぞく【公族】
1910年、韓国併合の後、前韓国王族李堈りこう・李熹りき・李埈およびその子孫で公として皇族の礼遇をうけた一族の称号。第二次大戦後、廃止。
こう‐ぞく【甲族】カフ‥
貴い家柄。貴族。門閥。
こう‐ぞく【後続】
あとから続くこと。「―部隊」
こう‐ぞく【皇族】クワウ‥
天皇の一族。天皇を除き皇胤こういんの男子およびその配偶者ならびに皇胤の女子をいう。皇后・太皇太后・皇太后・親王(皇太子・皇太孫を含む)・親王妃・内親王・王・王妃・女王の総称。現憲法はこれを国民として取り扱い、政治上の特権を認めない。→宮家。
⇒こうぞく‐かいぎ【皇族会議】
⇒こうぞく‐ひ【皇族費】
⇒こうぞく‐ふ【皇族譜】
ごう‐ぞく【強賊】ガウ‥
⇒きょうぞく
ごう‐ぞく【豪族】ガウ‥
地方に土着し、勢力をもつ一族。今昔物語集1「当国・隣国の―の人来りて乞ふ」
こうぞく‐かいぎ【皇族会議】クワウ‥クワイ‥
旧皇室典範上の機関で、皇族の大事を議した親族会議。成年の皇族男子で構成され、内大臣らも参列。→皇室会議。
⇒こう‐ぞく【皇族】
こうそく‐きかん【高速機関】カウ‥クワン
自動車や航空機などに用いる回転速度の大きい機関。
⇒こう‐そく【高速】
こうぞく‐きょり【航続距離】カウ‥
船舶または航空機が、途中で給油することなく航海または航空を続行できる距離。
こうそく‐じ【光触寺】クワウ‥
鎌倉市十二所じゅにそにある時宗の寺。一遍の創建と伝え、本尊の伝運慶作頬焼ほおやき阿弥陀如来のほか、頬焼阿弥陀縁起絵巻などがある。
光触寺
撮影:関戸 勇
 こうそく‐じかん【拘束時間】
休憩時間を含む労働時間。↔実働時間。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
銀行が貸出しの際に、預貸率の改善、貸出しの担保の保全を目的として積ませる預金。→歩積ぶづみ預金→両建預金。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】カウ‥
(fast breeder reactor)高速の中性子を用いて、ウラン238からプルトニウム239への転換率を1より大、すなわち増殖するように設計された原子炉。高速炉。FBR→増殖炉。
⇒こう‐そく【高速】
こう‐そくど【光速度】クワウ‥
光の伝播する速さ。真空中の光速度(毎秒29.9792458万キロメートル)は基礎定数の一つで、この数値をもとに1メートルの長さが定義されている。光速。記号c
こう‐そくど【高速度】カウ‥
速度がはやいこと。高速。
⇒こうそくど‐えいが【高速度映画】
⇒こうそくど‐こう【高速度鋼】
⇒こうそくど‐しゃしん【高速度写真】
こうそく‐どうろ【高速道路】カウ‥ダウ‥
高速で走る自動車のための専用道路。ハイウェー。フリーウェー。
⇒こう‐そく【高速】
こうそくど‐えいが【高速度映画】カウ‥グワ
1秒間あたりおよそ50こま以上の撮影速度で撮った映画。標準速度で映写すれば、被写体の動きがゆっくりとなり、それを詳しく観察することができる。
⇒こう‐そくど【高速度】
こうそくど‐こう【高速度鋼】カウ‥カウ
高速度で金属材料を切削する工具の製作に用いる特殊鋼。セ氏600度くらいの高温まで硬さと耐
こうそく‐じかん【拘束時間】
休憩時間を含む労働時間。↔実働時間。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそくせい‐よきん【拘束性預金】
銀行が貸出しの際に、預貸率の改善、貸出しの担保の保全を目的として積ませる預金。→歩積ぶづみ預金→両建預金。
⇒こう‐そく【拘束】
こうそく‐ぞうしょくろ【高速増殖炉】カウ‥
(fast breeder reactor)高速の中性子を用いて、ウラン238からプルトニウム239への転換率を1より大、すなわち増殖するように設計された原子炉。高速炉。FBR→増殖炉。
⇒こう‐そく【高速】
こう‐そくど【光速度】クワウ‥
光の伝播する速さ。真空中の光速度(毎秒29.9792458万キロメートル)は基礎定数の一つで、この数値をもとに1メートルの長さが定義されている。光速。記号c
こう‐そくど【高速度】カウ‥
速度がはやいこと。高速。
⇒こうそくど‐えいが【高速度映画】
⇒こうそくど‐こう【高速度鋼】
⇒こうそくど‐しゃしん【高速度写真】
こうそく‐どうろ【高速道路】カウ‥ダウ‥
高速で走る自動車のための専用道路。ハイウェー。フリーウェー。
⇒こう‐そく【高速】
こうそくど‐えいが【高速度映画】カウ‥グワ
1秒間あたりおよそ50こま以上の撮影速度で撮った映画。標準速度で映写すれば、被写体の動きがゆっくりとなり、それを詳しく観察することができる。
⇒こう‐そくど【高速度】
こうそくど‐こう【高速度鋼】カウ‥カウ
高速度で金属材料を切削する工具の製作に用いる特殊鋼。セ氏600度くらいの高温まで硬さと耐広辞苑 ページ 6685 での【○孔席暖まらず、墨突黔まず】単語。