複数辞典一括検索+![]()
![]()
○四の五の言うしのごのいう🔗⭐🔉
○四の五の言うしのごのいう
なんのかのと文句を言う。とやかく言う。好色一代女2「それを四の五の言へば」
⇒し【四】
しのざき【篠崎】
姓氏の一つ。
⇒しのざき‐しょうちく【篠崎小竹】
しのざき‐しょうちく【篠崎小竹】‥セウ‥
江戸後期の儒学者・漢詩人。大坂の人。古賀精里に朱子学を学び、詩文・書をよくした。著「小竹斎詩鈔」など。(1781〜1851)
⇒しのざき【篠崎】
しの‐ざさ【篠笹】
(→)「しのだけ」に同じ。
し‐の‐じ【しの字】
女の髪の結い方。幕府・大名家の下級女中などの髪型。しの字上げ。しの字髷。
しの字
 じ‐のし【地伸し】ヂ‥
(→)「地直し」に同じ。
し‐の‐しょうにん【死の商人】‥シヤウ‥
軍需品を製造・販売して巨利を得る大資本を指していう語。
しのしょうり【死の勝利】
(Il trionfo della morte イタリア)ダンヌンツィオの小説。1894年刊。恋人イッポーリタを抱いて断崖に身を投ずる主人公ジョルジョの性愛心理を語る。
しの‐すがき【篠簀掻】
篠竹をつづり合わせてつくった簀子すのこ。
しの‐すすき【篠薄】
①細竹の群がり生えるもの。篠の小薄おすすき。万葉集7「妹等がりわが行く道の―」
②まだ穂の出ない薄すすき。源氏物語宿木「ほに出でぬ物思ふらし―」
しの‐すだれ【篠簾】
篠竹を編んでつくった簾。新撰六帖2「隔つれどまばらに編める―」
しの‐すねあて【篠臑当】
家地いえじの布帛に篠金物をとりつけた臑当。しのたてすねあて。
し‐の‐せん【使の宣】
「しのせんじ」の略。源平盛衰記41「―を蒙つて」
し‐の‐ぜん【四の膳】
⇒よのぜん
し‐の‐せんじ【使の宣旨】
奉幣使・検非違使けびいしなどを任命する時に発行された宣旨。しのせん。
しの‐そうしん【志野宗信】
志野流香道の祖。通称、三郎右衛門。磐城の人。三条西実隆に従って香道の奥義を究める。足利義政に仕え、聞香ぶんこう作法を確立。(1445?〜1523)
⇒しの【志野】
しのだ【信太・信田】
大阪府泉北郡の旧村名。今は和泉市に属する。信太の森がある。
⇒しのだ‐ずし【信太鮨】
⇒しのだ‐づま【信太妻】
⇒しのだ‐の‐もり【信太の森】
⇒しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
し‐の‐たいふ【史大夫】
大史だいしの従五位下に叙せられた者。
しの‐だけ【篠竹】
全体に細く、葉も細かな竹・笹の類の俗称。スズタケ・アズマネザサなど。しのざさ。
しのだ‐ずし【信太鮨】
(狐は油揚を好むということから、信太の森の狐の伝説によって命名されたという)稲荷鮨いなりずしの別名。
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐づま【信太妻】
信太の森の葛の葉狐くずのはぎつねが安倍保名あべのやすなと結婚し、1子をもうけたという伝説。説経・浄瑠璃・歌舞伎などの題材となった。→葛の葉。
⇒しのだ【信太・信田】
しのたて‐すねあて【篠立臑当】
(→)「しのすねあて」に同じ。
しの‐だな【志野棚】
志野宗信と嗣子の宗温が創製した袋棚。上段に香道具を納める乱れ箱、中段右に予備の添香炉、左に阿古陀香炉、下段に重ね硯を飾る。桑や桐で製する。
しのだ‐の‐もり【信太の森】
大阪府和泉市信太山にある森。樟の大樹の下に、白狐のすんだという洞窟がある。葛の葉の伝説で有名。時雨・紅葉の名所。「篠田の森」とも書く。(歌枕) 源氏物語若菜上「この―を道のしるべにてまうで給ふ」
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
(油揚を用いるので、信太狐の伝説によって命名されたという)魚介・野菜・乾物などを刻み合わせて、油揚を袋状にした中に詰めたり、巻いたりしたものを甘く煮た料理。
⇒しのだ【信太・信田】
しの‐だれ【篠垂・鎬垂】
兜かぶとの鉢の正面または前後・左右に伏せた細長い筋金。1条・2条ないし5条のものがある。正面の篠垂は多く金銅で剣形とするが、後世は銀杏形・蜥蜴頭とかげがしらで、銀または白鑞しろめで飾った。撓垂しなだれ。→兜(図)
し‐の‐ちょう【使の庁】‥チヤウ
検非違使庁けびいしちょうのこと。
しのづか‐りゅう【篠塚流】‥リウ
京舞の一流派。文政(1818〜1830)の頃、京都の歌舞伎舞踊の振付師篠塚文三郎( 〜1845)が創始。
じ‐の‐つき【瓷】
(→)「じのうつわもの」に同じ。字鏡集「瓷、シノツキ・ジノウツハモノ」
しの‐つく‐あめ【篠突く雨】
篠をたばねて突きおろすようにはげしく降る雨。
しの‐づけ【罧】
(→)柴漬ふしづけ2に同じ。
し‐の‐つづみ【四の鼓】
古代の雅楽の打楽器。細腰鼓さいようこの一種。四鼓。→細腰鼓
し‐の‐て【真の手】
(シンノテのンの無表記)真書。楷書。宇津保物語国譲上「山吹につけたるは―春の字」
じ‐の‐なぞ【字の謎】
⇒じなぞ(字謎)
し‐の‐に【四の二】
①賽さいの目の四と二。狂言、双六「我はそこにて―けり(「死にけり」にかける)」
②六をしゃれていう語。
しの‐に
〔副〕
①(露などで)しっとりと濡れて。また、(悲しみなどで)しっとり、しみじみした気分になって。万葉集10「秋の穂を―押しなべ置く露の」。万葉集3「淡海の海夕浪千鳥なが鳴けば心も―古へおもほゆ」
②しげく。しきりに。新古今和歌集恋「逢ふ事はかたのの里の笹の庵―露散る夜はの床かな」
シノニム【synonym】
同義語。↔アントニム
しのね【羊蹄】
〔植〕ギシギシの古称。特に、その根。
しののい【篠ノ井】‥ヰ
長野市南部の地名。交通の要衝。
⇒しののい‐せん【篠ノ井線】
しののい‐せん【篠ノ井線】‥ヰ‥
中央本線の塩尻から松本を経て信越本線の篠ノ井に至るJR線。全長66.7キロメートル。
⇒しののい【篠ノ井】
しの‐の‐おざさ【篠の小笹】‥ヲ‥
(→)篠1に同じ。新古今和歌集旅「ふしわびぬ―のかり枕」
しの‐の‐おすすき【篠の小薄】‥ヲ‥
(→)「しのすすき」1に同じ。古今和歌集六帖6「相坂の―老いはてぬとも」
しの‐の‐おふぶき【篠の小吹雪】‥ヲ‥
篠を吹くはげしい風に雪が散ること。一説に、篠を吹きなびかす風。催馬楽、逢路「あふみぢの―、はや曳かず」
しのの‐に
〔副〕
ぐっしょりぬれるさまをいう。しとどに。しっぽりと。万葉集10「朝霧に―ぬれて」
しののは‐ぐさ【篠の葉草】
(→)篠1に同じ。新古今和歌集恋「散らすなよ―のかりにても」
しの‐の‐め【東雲】
(一説に、「め」は原始的住居の明り取りの役目を果たしていた網代様あじろようの粗い編み目のことで、篠竹を材料として作られた「め」が「篠の目」と呼ばれた。これが、明り取りそのものの意になり、転じて夜明けの薄明り、さらに夜明けそのものの意になったとする)
①東の空がわずかに明るくなる頃。あけがた。あかつき。あけぼの。古今和歌集恋「―のほがらほがらと明けゆけば」
②明け方に、東の空にたなびく雲。
⇒しののめ‐ぐさ【東雲草】
しののめ‐ぐさ【東雲草】
アサガオの異称。
⇒しの‐の‐め【東雲】
しののめ‐しんぶん【東雲新聞】
1888年(明治21)中江兆民を主筆に大阪で創刊された自由民権派系の新聞。革新的論調で声価を高めた。91年頃休刊。
しののめ‐ぶし【東雲節】
明治後期の流行歌。1899年(明治32)名古屋旭新地の東雲楼の娼妓がストライキを起して廃業した後に起こったという。ストライキ節。斎藤緑雨、半文銭「サイショネの磯節や、ナントショの―や、天下の乞丐こじきもよく之を諳誦す」
しの‐ば【収納場】
(→)「しのぐら(収納倉)」に同じ。
し‐の‐はい【死の灰】‥ハヒ
(1954年第五福竜丸事件の際、日本の新聞が造った語)核兵器の爆発、また原子炉内の核反応によって大量に生ずる放射性生成物の通称。ストロンチウム90、セシウム137などが、直接あるいは間接に人体に害を及ぼす。
しのはく【偲はく】
(シノフのク語法)はるかに思い慕うこと。恋しく思うこと。万葉集19「ほととぎす聞けば―あはぬ日を多み」
し‐の‐はこ【尿の箱・清箱】
便器。おまる。〈倭名類聚鈔14〉→おおつぼ
しのば・し【偲ばし】
〔形シク〕
慕わしい。忘れにくい。撰集抄「今更むかしも恋しく、そのあとも―・しく」
しのは・す【偲はす】
〔自四〕
(平安時代以後はシノバス。スは尊敬の意)お思い出しになる。万葉集4「わがかたみ見つつ―・せ」
しのばず‐の‐いけ【不忍池】
東京、上野公園の南西にある池。1625年(寛永2)寛永寺建立の際、池に弁財天を祀ってから有名になる。蓮の名所。
不忍池
提供:東京都
じ‐のし【地伸し】ヂ‥
(→)「地直し」に同じ。
し‐の‐しょうにん【死の商人】‥シヤウ‥
軍需品を製造・販売して巨利を得る大資本を指していう語。
しのしょうり【死の勝利】
(Il trionfo della morte イタリア)ダンヌンツィオの小説。1894年刊。恋人イッポーリタを抱いて断崖に身を投ずる主人公ジョルジョの性愛心理を語る。
しの‐すがき【篠簀掻】
篠竹をつづり合わせてつくった簀子すのこ。
しの‐すすき【篠薄】
①細竹の群がり生えるもの。篠の小薄おすすき。万葉集7「妹等がりわが行く道の―」
②まだ穂の出ない薄すすき。源氏物語宿木「ほに出でぬ物思ふらし―」
しの‐すだれ【篠簾】
篠竹を編んでつくった簾。新撰六帖2「隔つれどまばらに編める―」
しの‐すねあて【篠臑当】
家地いえじの布帛に篠金物をとりつけた臑当。しのたてすねあて。
し‐の‐せん【使の宣】
「しのせんじ」の略。源平盛衰記41「―を蒙つて」
し‐の‐ぜん【四の膳】
⇒よのぜん
し‐の‐せんじ【使の宣旨】
奉幣使・検非違使けびいしなどを任命する時に発行された宣旨。しのせん。
しの‐そうしん【志野宗信】
志野流香道の祖。通称、三郎右衛門。磐城の人。三条西実隆に従って香道の奥義を究める。足利義政に仕え、聞香ぶんこう作法を確立。(1445?〜1523)
⇒しの【志野】
しのだ【信太・信田】
大阪府泉北郡の旧村名。今は和泉市に属する。信太の森がある。
⇒しのだ‐ずし【信太鮨】
⇒しのだ‐づま【信太妻】
⇒しのだ‐の‐もり【信太の森】
⇒しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
し‐の‐たいふ【史大夫】
大史だいしの従五位下に叙せられた者。
しの‐だけ【篠竹】
全体に細く、葉も細かな竹・笹の類の俗称。スズタケ・アズマネザサなど。しのざさ。
しのだ‐ずし【信太鮨】
(狐は油揚を好むということから、信太の森の狐の伝説によって命名されたという)稲荷鮨いなりずしの別名。
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐づま【信太妻】
信太の森の葛の葉狐くずのはぎつねが安倍保名あべのやすなと結婚し、1子をもうけたという伝説。説経・浄瑠璃・歌舞伎などの題材となった。→葛の葉。
⇒しのだ【信太・信田】
しのたて‐すねあて【篠立臑当】
(→)「しのすねあて」に同じ。
しの‐だな【志野棚】
志野宗信と嗣子の宗温が創製した袋棚。上段に香道具を納める乱れ箱、中段右に予備の添香炉、左に阿古陀香炉、下段に重ね硯を飾る。桑や桐で製する。
しのだ‐の‐もり【信太の森】
大阪府和泉市信太山にある森。樟の大樹の下に、白狐のすんだという洞窟がある。葛の葉の伝説で有名。時雨・紅葉の名所。「篠田の森」とも書く。(歌枕) 源氏物語若菜上「この―を道のしるべにてまうで給ふ」
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
(油揚を用いるので、信太狐の伝説によって命名されたという)魚介・野菜・乾物などを刻み合わせて、油揚を袋状にした中に詰めたり、巻いたりしたものを甘く煮た料理。
⇒しのだ【信太・信田】
しの‐だれ【篠垂・鎬垂】
兜かぶとの鉢の正面または前後・左右に伏せた細長い筋金。1条・2条ないし5条のものがある。正面の篠垂は多く金銅で剣形とするが、後世は銀杏形・蜥蜴頭とかげがしらで、銀または白鑞しろめで飾った。撓垂しなだれ。→兜(図)
し‐の‐ちょう【使の庁】‥チヤウ
検非違使庁けびいしちょうのこと。
しのづか‐りゅう【篠塚流】‥リウ
京舞の一流派。文政(1818〜1830)の頃、京都の歌舞伎舞踊の振付師篠塚文三郎( 〜1845)が創始。
じ‐の‐つき【瓷】
(→)「じのうつわもの」に同じ。字鏡集「瓷、シノツキ・ジノウツハモノ」
しの‐つく‐あめ【篠突く雨】
篠をたばねて突きおろすようにはげしく降る雨。
しの‐づけ【罧】
(→)柴漬ふしづけ2に同じ。
し‐の‐つづみ【四の鼓】
古代の雅楽の打楽器。細腰鼓さいようこの一種。四鼓。→細腰鼓
し‐の‐て【真の手】
(シンノテのンの無表記)真書。楷書。宇津保物語国譲上「山吹につけたるは―春の字」
じ‐の‐なぞ【字の謎】
⇒じなぞ(字謎)
し‐の‐に【四の二】
①賽さいの目の四と二。狂言、双六「我はそこにて―けり(「死にけり」にかける)」
②六をしゃれていう語。
しの‐に
〔副〕
①(露などで)しっとりと濡れて。また、(悲しみなどで)しっとり、しみじみした気分になって。万葉集10「秋の穂を―押しなべ置く露の」。万葉集3「淡海の海夕浪千鳥なが鳴けば心も―古へおもほゆ」
②しげく。しきりに。新古今和歌集恋「逢ふ事はかたのの里の笹の庵―露散る夜はの床かな」
シノニム【synonym】
同義語。↔アントニム
しのね【羊蹄】
〔植〕ギシギシの古称。特に、その根。
しののい【篠ノ井】‥ヰ
長野市南部の地名。交通の要衝。
⇒しののい‐せん【篠ノ井線】
しののい‐せん【篠ノ井線】‥ヰ‥
中央本線の塩尻から松本を経て信越本線の篠ノ井に至るJR線。全長66.7キロメートル。
⇒しののい【篠ノ井】
しの‐の‐おざさ【篠の小笹】‥ヲ‥
(→)篠1に同じ。新古今和歌集旅「ふしわびぬ―のかり枕」
しの‐の‐おすすき【篠の小薄】‥ヲ‥
(→)「しのすすき」1に同じ。古今和歌集六帖6「相坂の―老いはてぬとも」
しの‐の‐おふぶき【篠の小吹雪】‥ヲ‥
篠を吹くはげしい風に雪が散ること。一説に、篠を吹きなびかす風。催馬楽、逢路「あふみぢの―、はや曳かず」
しのの‐に
〔副〕
ぐっしょりぬれるさまをいう。しとどに。しっぽりと。万葉集10「朝霧に―ぬれて」
しののは‐ぐさ【篠の葉草】
(→)篠1に同じ。新古今和歌集恋「散らすなよ―のかりにても」
しの‐の‐め【東雲】
(一説に、「め」は原始的住居の明り取りの役目を果たしていた網代様あじろようの粗い編み目のことで、篠竹を材料として作られた「め」が「篠の目」と呼ばれた。これが、明り取りそのものの意になり、転じて夜明けの薄明り、さらに夜明けそのものの意になったとする)
①東の空がわずかに明るくなる頃。あけがた。あかつき。あけぼの。古今和歌集恋「―のほがらほがらと明けゆけば」
②明け方に、東の空にたなびく雲。
⇒しののめ‐ぐさ【東雲草】
しののめ‐ぐさ【東雲草】
アサガオの異称。
⇒しの‐の‐め【東雲】
しののめ‐しんぶん【東雲新聞】
1888年(明治21)中江兆民を主筆に大阪で創刊された自由民権派系の新聞。革新的論調で声価を高めた。91年頃休刊。
しののめ‐ぶし【東雲節】
明治後期の流行歌。1899年(明治32)名古屋旭新地の東雲楼の娼妓がストライキを起して廃業した後に起こったという。ストライキ節。斎藤緑雨、半文銭「サイショネの磯節や、ナントショの―や、天下の乞丐こじきもよく之を諳誦す」
しの‐ば【収納場】
(→)「しのぐら(収納倉)」に同じ。
し‐の‐はい【死の灰】‥ハヒ
(1954年第五福竜丸事件の際、日本の新聞が造った語)核兵器の爆発、また原子炉内の核反応によって大量に生ずる放射性生成物の通称。ストロンチウム90、セシウム137などが、直接あるいは間接に人体に害を及ぼす。
しのはく【偲はく】
(シノフのク語法)はるかに思い慕うこと。恋しく思うこと。万葉集19「ほととぎす聞けば―あはぬ日を多み」
し‐の‐はこ【尿の箱・清箱】
便器。おまる。〈倭名類聚鈔14〉→おおつぼ
しのば・し【偲ばし】
〔形シク〕
慕わしい。忘れにくい。撰集抄「今更むかしも恋しく、そのあとも―・しく」
しのは・す【偲はす】
〔自四〕
(平安時代以後はシノバス。スは尊敬の意)お思い出しになる。万葉集4「わがかたみ見つつ―・せ」
しのばず‐の‐いけ【不忍池】
東京、上野公園の南西にある池。1625年(寛永2)寛永寺建立の際、池に弁財天を祀ってから有名になる。蓮の名所。
不忍池
提供:東京都
 しのばず‐ぶんこ【不忍文庫】
江戸後期、屋代弘賢やしろひろかたが不忍池畔の邸宅に設けた文庫。蔵書はのちに阿波国文庫あわのくにぶんこに献納。
しのば・せる【忍ばせる】
〔他下一〕
人に知られないようにする。こっそりと隠しておく。「足音を―・せる」「ポケットにピストルを―・せる」「敵中にスパイを―・せる」
しのは‐ゆ【偲はゆ】
(平安時代以後はシノバユ。ユは自発の助動詞)しのばれる。万葉集6「日け長くあれば家し―」
しの‐はら【篠原】
篠竹の生えた原。ささはら。万葉集7「われし通はばなびけ―」
しのひ【偲ひ・慕ひ】
(シノフの連用形から。平安時代以後はシノビ)深く思うこと。慕うこと。賞美すること。万葉集9「後人のちひとの―にせむと」
しのび【忍び】
①こらえること。我慢すること。
②ひそかにすること。
㋐身を隠して敵陣または城・人家などに入りこむ術。忍びの術。忍術。
㋑「忍びの者」の略。太平記20「或夜の雨風の紛れに、逸物の―を八幡山へ入れて」
㋒「忍び歩あるき」の略。おしのび。
㋓窃盗せっとうの異名。
㋔表に小さく裏に大きな針目で縫いつけること。
⇒しのび‐あい【忍び逢い】
⇒しのび‐あし【忍び足】
⇒しのび‐あみがさ【忍び編笠】
⇒しのび‐あるき【忍び歩き】
⇒しのび‐おとこ【忍び男】
⇒しのび‐おんな【忍び女】
⇒しのび‐がえし【忍び返し】
⇒しのび‐がき【忍び垣】
⇒しのび‐かご【忍び駕籠】
⇒しのび‐くぎ【忍び釘】
⇒しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
⇒しのび‐ぐみ【忍び組】
⇒しのび‐ぐるま【忍び車】
⇒しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
⇒しのび‐ごえ【忍び声】
⇒しのび‐ごと【忍び言】
⇒しのび‐ごと【忍び事】
⇒しのび‐ごま【忍駒】
⇒しのび‐さんじゅう【忍三重】
⇒しのび‐じ【忍び路】
⇒しのび‐しのび【忍び忍び】
⇒しのび‐ずきん【忍び頭巾】
⇒しのび‐すげ【忍び菅】
⇒しのび‐だ【忍び田】
⇒しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】
⇒しのび‐づま【忍び夫】
⇒しのび‐づま【忍び妻】
⇒しのび‐で【忍び手・短手】
⇒しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
⇒しのび‐とり【忍び取り】
⇒しのび‐ながし【忍び流し】
⇒しのび‐なき【忍び泣き】
⇒しのび‐なみだ【忍び涙】
⇒しのび‐に【忍びに】
⇒しのび‐ね【忍び音】
⇒しのび‐ねお【忍根緒】
⇒しのび‐の‐お【忍の緒】
⇒しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
⇒しのび‐の‐もの【忍びの者】
⇒しのび‐び【忍び火】
⇒しのび‐びと【忍び人】
⇒しのび‐ぶね【忍び船】
⇒しのび‐まわり【忍び回り】
⇒しのび‐めつけ【忍目付】
⇒しのび‐もとゆい【忍元結】
⇒しのび‐ものみ【忍び物見】
⇒しのび‐わらい【忍び笑い】
しのび‐あい【忍び逢い】‥アヒ
男女が人目をさけて逢うこと。密会。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あ・う【忍び逢う】‥アフ
〔自五〕
思いあう男女が人目を避けてあう。密会する。
しのび‐あし【忍び足】
他人に気づかれないようにこっそりと歩く足どり。ぬきあし。「―で近づく」
⇒しのび【忍び】
しのび‐あみがさ【忍び編笠】
遊里に遊ぶ者が顔をかくすためにかぶった編笠。忍び笠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あるき【忍び歩き】
①(身分の高い者などが)他人に知られないように身をやつして外出すること。微行。おしのび。しのびありき。
②(→)「しのびあし」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐い・る【忍び入る】
〔自五〕
人に知れないように入り込む。
しのび‐おとこ【忍び男】‥ヲトコ
かくし男。まおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐おんな【忍び女】‥ヲンナ
①かくし女。情婦。
②私娼。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がえし【忍び返し】‥ガヘシ
塀などの上にとがった竹・木・鉄などをつらね立てた設備。盗賊などの忍び入るのを防ぐためのもの。矢切やぎり。日葡辞書「シノビガエシ、また、シノビガエリ」
忍び返し
しのばず‐ぶんこ【不忍文庫】
江戸後期、屋代弘賢やしろひろかたが不忍池畔の邸宅に設けた文庫。蔵書はのちに阿波国文庫あわのくにぶんこに献納。
しのば・せる【忍ばせる】
〔他下一〕
人に知られないようにする。こっそりと隠しておく。「足音を―・せる」「ポケットにピストルを―・せる」「敵中にスパイを―・せる」
しのは‐ゆ【偲はゆ】
(平安時代以後はシノバユ。ユは自発の助動詞)しのばれる。万葉集6「日け長くあれば家し―」
しの‐はら【篠原】
篠竹の生えた原。ささはら。万葉集7「われし通はばなびけ―」
しのひ【偲ひ・慕ひ】
(シノフの連用形から。平安時代以後はシノビ)深く思うこと。慕うこと。賞美すること。万葉集9「後人のちひとの―にせむと」
しのび【忍び】
①こらえること。我慢すること。
②ひそかにすること。
㋐身を隠して敵陣または城・人家などに入りこむ術。忍びの術。忍術。
㋑「忍びの者」の略。太平記20「或夜の雨風の紛れに、逸物の―を八幡山へ入れて」
㋒「忍び歩あるき」の略。おしのび。
㋓窃盗せっとうの異名。
㋔表に小さく裏に大きな針目で縫いつけること。
⇒しのび‐あい【忍び逢い】
⇒しのび‐あし【忍び足】
⇒しのび‐あみがさ【忍び編笠】
⇒しのび‐あるき【忍び歩き】
⇒しのび‐おとこ【忍び男】
⇒しのび‐おんな【忍び女】
⇒しのび‐がえし【忍び返し】
⇒しのび‐がき【忍び垣】
⇒しのび‐かご【忍び駕籠】
⇒しのび‐くぎ【忍び釘】
⇒しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
⇒しのび‐ぐみ【忍び組】
⇒しのび‐ぐるま【忍び車】
⇒しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
⇒しのび‐ごえ【忍び声】
⇒しのび‐ごと【忍び言】
⇒しのび‐ごと【忍び事】
⇒しのび‐ごま【忍駒】
⇒しのび‐さんじゅう【忍三重】
⇒しのび‐じ【忍び路】
⇒しのび‐しのび【忍び忍び】
⇒しのび‐ずきん【忍び頭巾】
⇒しのび‐すげ【忍び菅】
⇒しのび‐だ【忍び田】
⇒しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】
⇒しのび‐づま【忍び夫】
⇒しのび‐づま【忍び妻】
⇒しのび‐で【忍び手・短手】
⇒しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
⇒しのび‐とり【忍び取り】
⇒しのび‐ながし【忍び流し】
⇒しのび‐なき【忍び泣き】
⇒しのび‐なみだ【忍び涙】
⇒しのび‐に【忍びに】
⇒しのび‐ね【忍び音】
⇒しのび‐ねお【忍根緒】
⇒しのび‐の‐お【忍の緒】
⇒しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
⇒しのび‐の‐もの【忍びの者】
⇒しのび‐び【忍び火】
⇒しのび‐びと【忍び人】
⇒しのび‐ぶね【忍び船】
⇒しのび‐まわり【忍び回り】
⇒しのび‐めつけ【忍目付】
⇒しのび‐もとゆい【忍元結】
⇒しのび‐ものみ【忍び物見】
⇒しのび‐わらい【忍び笑い】
しのび‐あい【忍び逢い】‥アヒ
男女が人目をさけて逢うこと。密会。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あ・う【忍び逢う】‥アフ
〔自五〕
思いあう男女が人目を避けてあう。密会する。
しのび‐あし【忍び足】
他人に気づかれないようにこっそりと歩く足どり。ぬきあし。「―で近づく」
⇒しのび【忍び】
しのび‐あみがさ【忍び編笠】
遊里に遊ぶ者が顔をかくすためにかぶった編笠。忍び笠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あるき【忍び歩き】
①(身分の高い者などが)他人に知られないように身をやつして外出すること。微行。おしのび。しのびありき。
②(→)「しのびあし」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐い・る【忍び入る】
〔自五〕
人に知れないように入り込む。
しのび‐おとこ【忍び男】‥ヲトコ
かくし男。まおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐おんな【忍び女】‥ヲンナ
①かくし女。情婦。
②私娼。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がえし【忍び返し】‥ガヘシ
塀などの上にとがった竹・木・鉄などをつらね立てた設備。盗賊などの忍び入るのを防ぐためのもの。矢切やぎり。日葡辞書「シノビガエシ、また、シノビガエリ」
忍び返し
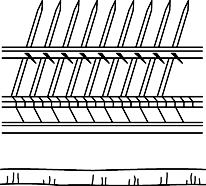 ⇒しのび【忍び】
しのび‐かえ・す【忍び返す】‥カヘス
〔自四〕
苦しい気持などをおさえる。源氏物語宿木「―・しつつ聞きも入れぬさまにて過し給ふ」
しのび‐がき【忍び垣】
高さ約2メートル、上・中・下3段に分かれ、上段は建仁寺垣のようにし、中段は葭よしを用い櫛形のすかしなどを設け、下段は大竹の二つ割にしたのを斜めに組み合わせた垣。
⇒しのび【忍び】
しのび‐かご【忍び駕籠】
人目をしのんで駕籠に乗ること。また、その駕籠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がた・い【忍び難い】
〔形〕[文]しのびがた・し(ク)
我慢することができない。耐えがたい。森鴎外、渋江抽斎「五百いおは情として―・くはあつたが」
しのび‐くぎ【忍び釘】
かくしくぎ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
慕い思う原因となるもの。しのぶぐさ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐみ【忍び組】
忍びの者の仲間。伊賀組・甲賀組の類。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐるま【忍び車】
人目に立たないように隠れて車に乗って行くこと。また、その車。
⇒しのび【忍び】
しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
近世、江戸で倹飩そばを運ぶのに用いた長方形の箱。中にしきりがあって狭い方に汁つぎ・辛みなどを入れた。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごえ【忍び声】‥ゴヱ
他に聞こえないように発する低い声。ひそひそ声。しのびね。
⇒しのび【忍び】
しのひ‐ごと【誄】
(平安時代以後はシノビゴト)貴人の死を悼み生前の徳などを追憶して述べる詞。誄辞るいじ。敏達紀「馬子宿祢大臣刀を佩はきて―たてまつる」
しのび‐ごと【忍び言】
ひそひそばなし。内証話。私語。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごと【忍び事】
かくしごと。内証ごと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごま【忍駒】
①三味線の音を小さくするために用いる駒。
②地歌の曲名。峰崎勾当作曲。
⇒しのび【忍び】
しのび‐こ・む【忍び込む】
〔自五〕
忍んではいりこむ。しのびいる。「留守宅に―・む」
しのび‐こ・む【忍び籠む】
〔他下二〕
心に深く包み隠す。源氏物語椎本「ひとことうち出で聞ゆるついでなく―・めたりければ」
しのび‐さんじゅう【忍三重】‥ヂユウ
下座げざ音楽。暗中の手探りの動きなどに用いる三味線の旋律。→三重2㋔。
⇒しのび【忍び】
しのび‐じ【忍び路】‥ヂ
隠れしのんで行くみち。特に男女がひそかに互いのもとに通うこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐しのび【忍び忍び】
特に人目を避けること。源氏物語帚木「―の御方違所おんかたたがえどころ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ずきん【忍び頭巾】‥ヅ‥
遊里通いなど、忍び歩きに用いた頭巾。
⇒しのび【忍び】
しのび‐すげ【忍び菅】
地中に根の生え広がった菅。
⇒しのび【忍び】
しのび‐だ【忍び田】
隠して年貢を納めない田地。隠し田。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】‥ヂヤウ‥
①貴人が人目をしのんで夜出かける時に用いた、替え紋の提灯。
②「がんどうぢょうちん」の別称。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び夫】
かくしおとこ。みそかお。しのびおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び妻】
かくしおんな。かくしめ。かこいもの。しのびおんな。
⇒しのび【忍び】
しのび‐で【忍び手・短手】
(シノビテとも)音の立たないように打ち合わす拍手かしわで。神道の葬儀で行う。
⇒しのび【忍び】
しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
①かくれひそむ所。忍んで通う所。源氏物語紅梅「通ひ給ふ―多く」
②なつかしく思うこと。また、その所。源氏物語真木柱「ここら年経給へる御すみかの、いかでか―なくはあらむ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐とり【忍び取り】
ひそかに侵入して敵城を乗っ取ること。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ない【忍びない】
がまんできない。耐えられない。「聞くに―」
しのび‐ながし【忍び流し】
表面的には栄転であるが、実は退けて遠方の官にうつすこと。左遷。孝徳紀「是れ隠流しのびながしか」
⇒しのび【忍び】
しのび‐なき【忍び泣き】
声を立てずに泣くこと。人知れず泣くこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐な・く【忍び泣く】
〔自五〕
人に気づかれないように泣く。声を立てずに泣く。
しのび‐なみだ【忍び涙】
人知れず流す涙。忍び泣きの涙。
⇒しのび【忍び】
しのび‐に【忍びに】
〔副〕
人知れず。ひそかに。源氏物語帚木「―御文通はしなどして」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ね【忍び音】
①ひそひそ声。しのびごえ。源平盛衰記31「夜ふくるまでは―に念仏申し」
②陰暦4月頃、ホトトギスがまだ声をひそめて鳴くこと。また、その声。落窪物語3「ほととぎす待ちつる宵の―はまどろまねども驚かれけり」
③忍び泣くこと。また、そのかすかな声。更級日記「―をのみ泣きて」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ねお【忍根緒】‥ヲ
(→)「しのびのお」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐お【忍の緒】‥ヲ
兜かぶとの鉢につけてあごのところで結ぶ紐ひも。しのびねお。兜の緒。
⇒しのび【忍び】
しのび‐のこ・す【忍び残す】
〔他四〕
隠して出さずに置く。源氏物語薄雲「そこにはかく―・されたる事ありけるを」
しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
敵情偵察・暗殺などの目的で、ひそかに敵陣や人家に入り込む術。にんじゅつ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐もの【忍びの者】
忍びの術を使う者。間者。しのび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐び【忍び火】
音を立てずに打つ切火きりび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐びと【忍び人】
①人目を忍んで通う人。
②世を隠れ忍ぶ人。隠者。
③(→)「忍びの者」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぶね【忍び船】
人目を忍んで漕ぐ船。
⇒しのび【忍び】
しのび‐まわり【忍び回り】‥マハリ
①ひそかに巡回して見回ること。また、その人。
②(→)忍目付しのびめつけに同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐めつけ【忍目付】
内密に調査を必要とする地方を視察し、主人に報告する武家の役。しのびまわり。→お庭番。
⇒しのび【忍び】
しのび‐もとゆい【忍元結】‥ユヒ
元結の掛け方の一つ。外部から見えないように結ぶもの。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ものみ【忍び物見】
戦場で、山野に隠れて敵情をさぐる者。足軽などがこれに当たった。かすりものみ。しばみ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐やか【忍びやか】
しのんでするさま。ひそかにするさま。源氏物語夕霧「―なる声づかひなどを、よろしう聞きなし給へり」。「―な足音」「―に近づく」
しのび‐よ・る【忍び寄る】
〔自五〕
相手が気づかないうちにそっと近づく。太平記14「敵の陣近く―・り」。「―・る秋」「インフレが―・る」
しのび‐わた・る【忍び渡る】
〔自四〕
①(「偲び渡る」とも混同して)恋い慕う気持を我慢しながら、長い年月を過ごす。源氏物語夕霧「年ごろ―・り給ひける心のうちを」
②ひそかに行く。人目を避けて来る。夜の寝覚3「夜さりしのびてわたらせ給ひて」
しのび‐わた・る【偲び渡る】
〔他四〕
(奈良時代にはシノヒワタル)長い間慕いつづける。万葉集13「千世にも―・れと」
しのび‐わらい【忍び笑い】‥ワラヒ
人に気づかれないように声を殺して笑うこと。また、その笑い。
⇒しのび【忍び】
しの・ふ【偲ふ】
〔他四〕
⇒しのぶ(偲ぶ)
しのぶ【忍】
①シノブ科のシダ。茎は淡褐色の鱗毛を密生。葉柄は淡褐色で、長さ約5〜10センチメートル。葉は数回羽状に分裂。根茎をからみ合わせてしのぶ玉・釣忍つりしのぶとして観賞用に軒下などに吊す。シノブグサ。
②忍摺しのぶずりの略。
③襲かさねの色目。表は薄い萌葱もえぎ、裏は青。
④忍髷しのぶわげの略。
⇒しのぶ‐いし【忍石】
⇒しのぶ‐ぐさ【忍草】
⇒しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
⇒しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
⇒しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
⇒しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】
⇒しのぶ‐もじずり【忍捩摺】
⇒しのぶ‐わげ【忍髷】
しのぶ【信夫】
福島県の旧郡名。はじめ石背いわせ国、のち陸奥国の一部。今の福島市南部に当たる。
しの・ぶ【忍ぶ】
[一]〔他上二〕
(現代語では五段活用で用いるが、打消に続く時は「しのび」の形も用いる)
①こらえる。我慢する。耐える。万葉集17「わが背子が抓つみし手見つつ―・びかねつも」。源氏物語賢木「―・ぶれど涙ほろほろとこぼれ給ひぬ」。「捨てるに―・びない」
②秘密にする。かくす。源氏物語夕顔「―・ぶるやうこそはと、あながちにも問ひいで給はず」
③(自動詞的に)人目を避ける。かくれる。源氏物語松風「惟光の朝臣例の―・ぶる道はいつとなくいろひ仕うまつる人なれば」
[二]〔他五〕
(意味上の類似から平安時代以後、四段活用の偲ブと混同して生じた活用形)
①こらえる。我慢する。平中物語「こと局に人あまた見ゆるを、え―・ばで言ひやる」。「不便を―・ぶ」「恥を―・ぶ」
②表立たないようにする。人目を避ける。(自動詞的にも使う)拾遺和歌集恋「―・ばむに―・ばれぬべき恋ならばつらきにつけてやみもしなまし」。平家物語灌頂「何者のとひ来るやらむ。あれ見よや。―・ぶべきものならば急ぎ―・ばむ」。「世を―・ぶ姿」「人目を―・んで泣く」
しの・ぶ【偲ぶ】
[一]〔他五〕
(奈良時代にはシノフと清音)
①過ぎ去ったこと、離れている人のことなどをひそかに思い慕う。恋いしたう。万葉集20「わが妻も絵にかきとらむ暇いづまもが旅ゆく我は見つつ―・はむ」。源氏物語明石「なほざりに頼めおくなる一ことをつきせぬねにやかけて―・ばむ」。「昔を―・ぶ」「故人を―・ぶ」
②心ひかれて(見えないところなどに)思いをはせる。「人柄が―・ばれる」
③賞美する。万葉集19「あしひきの山下ひかげ鬘かずらける上にやさらに梅を―・はむ」
[二]〔他上二〕
(意味上の類似から平安時代以後、上二段活用の忍ブと混同して生じた活用形)ひそかに思い慕う。心中で恋い慕う。源氏物語幻「なき人を―・ぶる宵の村雨に」。源氏物語賢木「あひ見ずて―・ぶる頃の涙をも」
しのぶ‐いし【忍石】
シノブの葉に似た模様のある岩石。岩石の割れ目に二酸化マンガンが沈殿してできる、偽化石の一種。模樹石。
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶえ【篠笛】
細い篠竹で作った横笛。指孔は7孔が標準だが、6孔・5孔以下もある。基音の高低により長短12本の種類があり、一本調子は最も低く、順次十二律に対応する。獅子舞・里神楽などの民俗芸能や歌舞伎囃子に用いる。竹笛。しの。
しのぶがおか【忍ヶ岡】‥ヲカ
東京、上野公園一帯の古名。しのぶのおか。
しのぶ‐ぐさ【忍草】
①シノブ・ノキシノブなどのシダ植物。源氏物語夕顔「荒れたる門かどの―茂りて」
②(シノフ(偲ふ)にかけて)慕い思う原因となるもの。心配のたね。しのびぐさ。万葉集6「石いわに生ふる菅の根取りて―はらへてましを」
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶくろ【志野袋】
志野流香道の簡略化した手前で、香包と銀葉包を収める袋。口を閉める紐は12カ月の花結びを用いる。
しのぶ‐こいじ【忍ぶ恋路】‥コヒヂ
しのびあう恋の苦しさを表す語。端唄はうた・うた沢に同名の曲がある。
シノプシス【synopsis】
梗概。シナリオなどのあらすじ。
しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
摺込染すりこみぞめの一種。昔、陸奥国信夫しのぶ郡から産出した忍草の茎・葉などの色素で捩もじれたように文様を布帛ふはくに摺りつけたもの。捩摺もじずりともいい、その文様が捩れからまっているからとも、捩れ乱れた文様のある石(もじずりいし)に布をあてて摺ったからともいう。しのぶもじずり。草の捩摺。しのぶ。伊勢物語「この男―の狩衣をなむ着たりける」
⇒しのぶ【忍】
し‐の‐ぶとう【死の舞踏】‥タフ
〔美〕(Totentanz ドイツ・danse macabre フランス)死を象徴する骸骨が、人々を巻き込んで踊る図像。中世末から近世初期にかけてヨーロッパ各地に広まった。ホルバインの木版画集が著名。
しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
しのぶずりの衣。通例、人目を忍んで涙にぬれること、または、堪え難くて涙にぬれることにたとえて用いる。新勅撰和歌集恋「逢ふことは―あはれなどまれなる色に乱れそめけん」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのそうた【忍ぶの惣太】
歌舞伎脚本「都鳥廓白浪みやこどりながれのしらなみ」の通称。河竹黙阿弥作の世話物。1854年(嘉永7)江戸河原崎座初演。隅田川物で、鳥目の侠客(4世市川小団次)が梅若を殺すくだりが評判となる。
しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
忍の衣の袖。また、忍の衣。源平盛衰記32「―をぞしぼられける」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのやかしゅう【志濃夫廼舎歌集】‥シフ
歌集。5巻。橘曙覧たちばなあけみの草稿をその子井手今滋が編。1878年(明治11)刊。万葉・古今風を融合し、日常的な素材・用語をも嫌わぬ独特の歌風をもつ。
しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】‥ヂユウ
春日かすが饅頭の別称。
⇒しのぶ【忍】
しのぶ‐もじずり【忍捩摺】‥モヂ‥
(→)「しのぶずり」に同じ。伊勢物語「みちのくの―誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに」
⇒しのぶ【忍】
しのふら・う【忍ふらふ】シノフラフ
〔他四〕
(上二段活用のシノフに動作の反復・継続を表す接尾語フの付いた語)ずっとがまんする。堪えつづける。万葉集16「とねりをとこも―・ひかへらひ見つつ」
しのぶ‐わげ【忍髷】
女の髪の結い方。髷をつくり、その余りを二分して根の左右に小さい輪を作り、髷の根元に笄こうがいを横にさす。元文(1736〜1741)初年上方に始まり、のち江戸吉原の遊女の間にも流行。また、これにかたどった歌舞伎女形用のかつら。信夫しのぶ返し。しのぶ。通言総籬つうげんそうまがき「髪は―」
⇒しのぶ【忍】
じ‐の‐ぶん【地の文】ヂ‥
小説や戯曲などで、会話文以外の説明や描写の文。
しのべ‐だけ【忍竹】
①メダケの別称。
②(→)ヤダケ2に同じ。〈日葡辞書〉
じ‐のみ【地蚤】ヂ‥
キボシマルトビムシの別称。
しの‐め【篠芽】
①おそく生えて色が青く、味のにがいたけのこ。長間笋。〈倭名類聚鈔20〉
②篠芽竹。
⇒しのめ‐だけ【篠芽竹】
しのめ‐だけ【篠芽竹】
(→)ヤダケ2に同じ。
⇒しの‐め【篠芽】
しの‐や【篠屋】
篠で葺ふいた小屋。永久百首「旅人のかりの―に年くれて」
しの‐やき【志野焼】
桃山時代、美濃(岐阜県土岐市・可児かに市)で焼かれた陶器。白釉(長石釉)を厚く施し、下に鉄で簡素な文様を描いた絵志野や、鼠色をし象眼風の文様のある鼠志野などがある。茶碗や水指に秀作が多い。
じ‐のり【地乗り】ヂ‥
①駻馬かんばを乗りこなすこと。
②馬の足並みをそろえて進ませること。地足。
しの‐りゅう【志野流】‥リウ
香道の流派。志野宗信そうしんを祖とし、4代以降は蜂谷家が伝承、享保の頃家元制度を整える。志野流茶道の家元でもある。
シノロジー【Sinology】
中国学。
し‐の‐わかれ【死の別れ】
一方が死んで別れとなること。しにわかれ。宇治拾遺物語9「―にぞわかれにける」
シノワズリー【chinoiserie フランス】
中国趣味。17〜18世紀の頃、ヨーロッパで流行。東洋の題材をとりあげ、あるいは中国風を取り入れた芸術。
しの‐わた【篠綿】
綿糸紡績工程で、梳綿そめんによって作られた、撚よりのかからない太い綱状の繊維束。スライバー。
⇒しのび【忍び】
しのび‐かえ・す【忍び返す】‥カヘス
〔自四〕
苦しい気持などをおさえる。源氏物語宿木「―・しつつ聞きも入れぬさまにて過し給ふ」
しのび‐がき【忍び垣】
高さ約2メートル、上・中・下3段に分かれ、上段は建仁寺垣のようにし、中段は葭よしを用い櫛形のすかしなどを設け、下段は大竹の二つ割にしたのを斜めに組み合わせた垣。
⇒しのび【忍び】
しのび‐かご【忍び駕籠】
人目をしのんで駕籠に乗ること。また、その駕籠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がた・い【忍び難い】
〔形〕[文]しのびがた・し(ク)
我慢することができない。耐えがたい。森鴎外、渋江抽斎「五百いおは情として―・くはあつたが」
しのび‐くぎ【忍び釘】
かくしくぎ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
慕い思う原因となるもの。しのぶぐさ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐみ【忍び組】
忍びの者の仲間。伊賀組・甲賀組の類。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐるま【忍び車】
人目に立たないように隠れて車に乗って行くこと。また、その車。
⇒しのび【忍び】
しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
近世、江戸で倹飩そばを運ぶのに用いた長方形の箱。中にしきりがあって狭い方に汁つぎ・辛みなどを入れた。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごえ【忍び声】‥ゴヱ
他に聞こえないように発する低い声。ひそひそ声。しのびね。
⇒しのび【忍び】
しのひ‐ごと【誄】
(平安時代以後はシノビゴト)貴人の死を悼み生前の徳などを追憶して述べる詞。誄辞るいじ。敏達紀「馬子宿祢大臣刀を佩はきて―たてまつる」
しのび‐ごと【忍び言】
ひそひそばなし。内証話。私語。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごと【忍び事】
かくしごと。内証ごと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごま【忍駒】
①三味線の音を小さくするために用いる駒。
②地歌の曲名。峰崎勾当作曲。
⇒しのび【忍び】
しのび‐こ・む【忍び込む】
〔自五〕
忍んではいりこむ。しのびいる。「留守宅に―・む」
しのび‐こ・む【忍び籠む】
〔他下二〕
心に深く包み隠す。源氏物語椎本「ひとことうち出で聞ゆるついでなく―・めたりければ」
しのび‐さんじゅう【忍三重】‥ヂユウ
下座げざ音楽。暗中の手探りの動きなどに用いる三味線の旋律。→三重2㋔。
⇒しのび【忍び】
しのび‐じ【忍び路】‥ヂ
隠れしのんで行くみち。特に男女がひそかに互いのもとに通うこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐しのび【忍び忍び】
特に人目を避けること。源氏物語帚木「―の御方違所おんかたたがえどころ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ずきん【忍び頭巾】‥ヅ‥
遊里通いなど、忍び歩きに用いた頭巾。
⇒しのび【忍び】
しのび‐すげ【忍び菅】
地中に根の生え広がった菅。
⇒しのび【忍び】
しのび‐だ【忍び田】
隠して年貢を納めない田地。隠し田。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】‥ヂヤウ‥
①貴人が人目をしのんで夜出かける時に用いた、替え紋の提灯。
②「がんどうぢょうちん」の別称。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び夫】
かくしおとこ。みそかお。しのびおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び妻】
かくしおんな。かくしめ。かこいもの。しのびおんな。
⇒しのび【忍び】
しのび‐で【忍び手・短手】
(シノビテとも)音の立たないように打ち合わす拍手かしわで。神道の葬儀で行う。
⇒しのび【忍び】
しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
①かくれひそむ所。忍んで通う所。源氏物語紅梅「通ひ給ふ―多く」
②なつかしく思うこと。また、その所。源氏物語真木柱「ここら年経給へる御すみかの、いかでか―なくはあらむ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐とり【忍び取り】
ひそかに侵入して敵城を乗っ取ること。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ない【忍びない】
がまんできない。耐えられない。「聞くに―」
しのび‐ながし【忍び流し】
表面的には栄転であるが、実は退けて遠方の官にうつすこと。左遷。孝徳紀「是れ隠流しのびながしか」
⇒しのび【忍び】
しのび‐なき【忍び泣き】
声を立てずに泣くこと。人知れず泣くこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐な・く【忍び泣く】
〔自五〕
人に気づかれないように泣く。声を立てずに泣く。
しのび‐なみだ【忍び涙】
人知れず流す涙。忍び泣きの涙。
⇒しのび【忍び】
しのび‐に【忍びに】
〔副〕
人知れず。ひそかに。源氏物語帚木「―御文通はしなどして」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ね【忍び音】
①ひそひそ声。しのびごえ。源平盛衰記31「夜ふくるまでは―に念仏申し」
②陰暦4月頃、ホトトギスがまだ声をひそめて鳴くこと。また、その声。落窪物語3「ほととぎす待ちつる宵の―はまどろまねども驚かれけり」
③忍び泣くこと。また、そのかすかな声。更級日記「―をのみ泣きて」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ねお【忍根緒】‥ヲ
(→)「しのびのお」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐お【忍の緒】‥ヲ
兜かぶとの鉢につけてあごのところで結ぶ紐ひも。しのびねお。兜の緒。
⇒しのび【忍び】
しのび‐のこ・す【忍び残す】
〔他四〕
隠して出さずに置く。源氏物語薄雲「そこにはかく―・されたる事ありけるを」
しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
敵情偵察・暗殺などの目的で、ひそかに敵陣や人家に入り込む術。にんじゅつ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐もの【忍びの者】
忍びの術を使う者。間者。しのび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐び【忍び火】
音を立てずに打つ切火きりび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐びと【忍び人】
①人目を忍んで通う人。
②世を隠れ忍ぶ人。隠者。
③(→)「忍びの者」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぶね【忍び船】
人目を忍んで漕ぐ船。
⇒しのび【忍び】
しのび‐まわり【忍び回り】‥マハリ
①ひそかに巡回して見回ること。また、その人。
②(→)忍目付しのびめつけに同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐めつけ【忍目付】
内密に調査を必要とする地方を視察し、主人に報告する武家の役。しのびまわり。→お庭番。
⇒しのび【忍び】
しのび‐もとゆい【忍元結】‥ユヒ
元結の掛け方の一つ。外部から見えないように結ぶもの。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ものみ【忍び物見】
戦場で、山野に隠れて敵情をさぐる者。足軽などがこれに当たった。かすりものみ。しばみ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐やか【忍びやか】
しのんでするさま。ひそかにするさま。源氏物語夕霧「―なる声づかひなどを、よろしう聞きなし給へり」。「―な足音」「―に近づく」
しのび‐よ・る【忍び寄る】
〔自五〕
相手が気づかないうちにそっと近づく。太平記14「敵の陣近く―・り」。「―・る秋」「インフレが―・る」
しのび‐わた・る【忍び渡る】
〔自四〕
①(「偲び渡る」とも混同して)恋い慕う気持を我慢しながら、長い年月を過ごす。源氏物語夕霧「年ごろ―・り給ひける心のうちを」
②ひそかに行く。人目を避けて来る。夜の寝覚3「夜さりしのびてわたらせ給ひて」
しのび‐わた・る【偲び渡る】
〔他四〕
(奈良時代にはシノヒワタル)長い間慕いつづける。万葉集13「千世にも―・れと」
しのび‐わらい【忍び笑い】‥ワラヒ
人に気づかれないように声を殺して笑うこと。また、その笑い。
⇒しのび【忍び】
しの・ふ【偲ふ】
〔他四〕
⇒しのぶ(偲ぶ)
しのぶ【忍】
①シノブ科のシダ。茎は淡褐色の鱗毛を密生。葉柄は淡褐色で、長さ約5〜10センチメートル。葉は数回羽状に分裂。根茎をからみ合わせてしのぶ玉・釣忍つりしのぶとして観賞用に軒下などに吊す。シノブグサ。
②忍摺しのぶずりの略。
③襲かさねの色目。表は薄い萌葱もえぎ、裏は青。
④忍髷しのぶわげの略。
⇒しのぶ‐いし【忍石】
⇒しのぶ‐ぐさ【忍草】
⇒しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
⇒しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
⇒しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
⇒しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】
⇒しのぶ‐もじずり【忍捩摺】
⇒しのぶ‐わげ【忍髷】
しのぶ【信夫】
福島県の旧郡名。はじめ石背いわせ国、のち陸奥国の一部。今の福島市南部に当たる。
しの・ぶ【忍ぶ】
[一]〔他上二〕
(現代語では五段活用で用いるが、打消に続く時は「しのび」の形も用いる)
①こらえる。我慢する。耐える。万葉集17「わが背子が抓つみし手見つつ―・びかねつも」。源氏物語賢木「―・ぶれど涙ほろほろとこぼれ給ひぬ」。「捨てるに―・びない」
②秘密にする。かくす。源氏物語夕顔「―・ぶるやうこそはと、あながちにも問ひいで給はず」
③(自動詞的に)人目を避ける。かくれる。源氏物語松風「惟光の朝臣例の―・ぶる道はいつとなくいろひ仕うまつる人なれば」
[二]〔他五〕
(意味上の類似から平安時代以後、四段活用の偲ブと混同して生じた活用形)
①こらえる。我慢する。平中物語「こと局に人あまた見ゆるを、え―・ばで言ひやる」。「不便を―・ぶ」「恥を―・ぶ」
②表立たないようにする。人目を避ける。(自動詞的にも使う)拾遺和歌集恋「―・ばむに―・ばれぬべき恋ならばつらきにつけてやみもしなまし」。平家物語灌頂「何者のとひ来るやらむ。あれ見よや。―・ぶべきものならば急ぎ―・ばむ」。「世を―・ぶ姿」「人目を―・んで泣く」
しの・ぶ【偲ぶ】
[一]〔他五〕
(奈良時代にはシノフと清音)
①過ぎ去ったこと、離れている人のことなどをひそかに思い慕う。恋いしたう。万葉集20「わが妻も絵にかきとらむ暇いづまもが旅ゆく我は見つつ―・はむ」。源氏物語明石「なほざりに頼めおくなる一ことをつきせぬねにやかけて―・ばむ」。「昔を―・ぶ」「故人を―・ぶ」
②心ひかれて(見えないところなどに)思いをはせる。「人柄が―・ばれる」
③賞美する。万葉集19「あしひきの山下ひかげ鬘かずらける上にやさらに梅を―・はむ」
[二]〔他上二〕
(意味上の類似から平安時代以後、上二段活用の忍ブと混同して生じた活用形)ひそかに思い慕う。心中で恋い慕う。源氏物語幻「なき人を―・ぶる宵の村雨に」。源氏物語賢木「あひ見ずて―・ぶる頃の涙をも」
しのぶ‐いし【忍石】
シノブの葉に似た模様のある岩石。岩石の割れ目に二酸化マンガンが沈殿してできる、偽化石の一種。模樹石。
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶえ【篠笛】
細い篠竹で作った横笛。指孔は7孔が標準だが、6孔・5孔以下もある。基音の高低により長短12本の種類があり、一本調子は最も低く、順次十二律に対応する。獅子舞・里神楽などの民俗芸能や歌舞伎囃子に用いる。竹笛。しの。
しのぶがおか【忍ヶ岡】‥ヲカ
東京、上野公園一帯の古名。しのぶのおか。
しのぶ‐ぐさ【忍草】
①シノブ・ノキシノブなどのシダ植物。源氏物語夕顔「荒れたる門かどの―茂りて」
②(シノフ(偲ふ)にかけて)慕い思う原因となるもの。心配のたね。しのびぐさ。万葉集6「石いわに生ふる菅の根取りて―はらへてましを」
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶくろ【志野袋】
志野流香道の簡略化した手前で、香包と銀葉包を収める袋。口を閉める紐は12カ月の花結びを用いる。
しのぶ‐こいじ【忍ぶ恋路】‥コヒヂ
しのびあう恋の苦しさを表す語。端唄はうた・うた沢に同名の曲がある。
シノプシス【synopsis】
梗概。シナリオなどのあらすじ。
しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
摺込染すりこみぞめの一種。昔、陸奥国信夫しのぶ郡から産出した忍草の茎・葉などの色素で捩もじれたように文様を布帛ふはくに摺りつけたもの。捩摺もじずりともいい、その文様が捩れからまっているからとも、捩れ乱れた文様のある石(もじずりいし)に布をあてて摺ったからともいう。しのぶもじずり。草の捩摺。しのぶ。伊勢物語「この男―の狩衣をなむ着たりける」
⇒しのぶ【忍】
し‐の‐ぶとう【死の舞踏】‥タフ
〔美〕(Totentanz ドイツ・danse macabre フランス)死を象徴する骸骨が、人々を巻き込んで踊る図像。中世末から近世初期にかけてヨーロッパ各地に広まった。ホルバインの木版画集が著名。
しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
しのぶずりの衣。通例、人目を忍んで涙にぬれること、または、堪え難くて涙にぬれることにたとえて用いる。新勅撰和歌集恋「逢ふことは―あはれなどまれなる色に乱れそめけん」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのそうた【忍ぶの惣太】
歌舞伎脚本「都鳥廓白浪みやこどりながれのしらなみ」の通称。河竹黙阿弥作の世話物。1854年(嘉永7)江戸河原崎座初演。隅田川物で、鳥目の侠客(4世市川小団次)が梅若を殺すくだりが評判となる。
しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
忍の衣の袖。また、忍の衣。源平盛衰記32「―をぞしぼられける」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのやかしゅう【志濃夫廼舎歌集】‥シフ
歌集。5巻。橘曙覧たちばなあけみの草稿をその子井手今滋が編。1878年(明治11)刊。万葉・古今風を融合し、日常的な素材・用語をも嫌わぬ独特の歌風をもつ。
しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】‥ヂユウ
春日かすが饅頭の別称。
⇒しのぶ【忍】
しのぶ‐もじずり【忍捩摺】‥モヂ‥
(→)「しのぶずり」に同じ。伊勢物語「みちのくの―誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに」
⇒しのぶ【忍】
しのふら・う【忍ふらふ】シノフラフ
〔他四〕
(上二段活用のシノフに動作の反復・継続を表す接尾語フの付いた語)ずっとがまんする。堪えつづける。万葉集16「とねりをとこも―・ひかへらひ見つつ」
しのぶ‐わげ【忍髷】
女の髪の結い方。髷をつくり、その余りを二分して根の左右に小さい輪を作り、髷の根元に笄こうがいを横にさす。元文(1736〜1741)初年上方に始まり、のち江戸吉原の遊女の間にも流行。また、これにかたどった歌舞伎女形用のかつら。信夫しのぶ返し。しのぶ。通言総籬つうげんそうまがき「髪は―」
⇒しのぶ【忍】
じ‐の‐ぶん【地の文】ヂ‥
小説や戯曲などで、会話文以外の説明や描写の文。
しのべ‐だけ【忍竹】
①メダケの別称。
②(→)ヤダケ2に同じ。〈日葡辞書〉
じ‐のみ【地蚤】ヂ‥
キボシマルトビムシの別称。
しの‐め【篠芽】
①おそく生えて色が青く、味のにがいたけのこ。長間笋。〈倭名類聚鈔20〉
②篠芽竹。
⇒しのめ‐だけ【篠芽竹】
しのめ‐だけ【篠芽竹】
(→)ヤダケ2に同じ。
⇒しの‐め【篠芽】
しの‐や【篠屋】
篠で葺ふいた小屋。永久百首「旅人のかりの―に年くれて」
しの‐やき【志野焼】
桃山時代、美濃(岐阜県土岐市・可児かに市)で焼かれた陶器。白釉(長石釉)を厚く施し、下に鉄で簡素な文様を描いた絵志野や、鼠色をし象眼風の文様のある鼠志野などがある。茶碗や水指に秀作が多い。
じ‐のり【地乗り】ヂ‥
①駻馬かんばを乗りこなすこと。
②馬の足並みをそろえて進ませること。地足。
しの‐りゅう【志野流】‥リウ
香道の流派。志野宗信そうしんを祖とし、4代以降は蜂谷家が伝承、享保の頃家元制度を整える。志野流茶道の家元でもある。
シノロジー【Sinology】
中国学。
し‐の‐わかれ【死の別れ】
一方が死んで別れとなること。しにわかれ。宇治拾遺物語9「―にぞわかれにける」
シノワズリー【chinoiserie フランス】
中国趣味。17〜18世紀の頃、ヨーロッパで流行。東洋の題材をとりあげ、あるいは中国風を取り入れた芸術。
しの‐わた【篠綿】
綿糸紡績工程で、梳綿そめんによって作られた、撚よりのかからない太い綱状の繊維束。スライバー。
 じ‐のし【地伸し】ヂ‥
(→)「地直し」に同じ。
し‐の‐しょうにん【死の商人】‥シヤウ‥
軍需品を製造・販売して巨利を得る大資本を指していう語。
しのしょうり【死の勝利】
(Il trionfo della morte イタリア)ダンヌンツィオの小説。1894年刊。恋人イッポーリタを抱いて断崖に身を投ずる主人公ジョルジョの性愛心理を語る。
しの‐すがき【篠簀掻】
篠竹をつづり合わせてつくった簀子すのこ。
しの‐すすき【篠薄】
①細竹の群がり生えるもの。篠の小薄おすすき。万葉集7「妹等がりわが行く道の―」
②まだ穂の出ない薄すすき。源氏物語宿木「ほに出でぬ物思ふらし―」
しの‐すだれ【篠簾】
篠竹を編んでつくった簾。新撰六帖2「隔つれどまばらに編める―」
しの‐すねあて【篠臑当】
家地いえじの布帛に篠金物をとりつけた臑当。しのたてすねあて。
し‐の‐せん【使の宣】
「しのせんじ」の略。源平盛衰記41「―を蒙つて」
し‐の‐ぜん【四の膳】
⇒よのぜん
し‐の‐せんじ【使の宣旨】
奉幣使・検非違使けびいしなどを任命する時に発行された宣旨。しのせん。
しの‐そうしん【志野宗信】
志野流香道の祖。通称、三郎右衛門。磐城の人。三条西実隆に従って香道の奥義を究める。足利義政に仕え、聞香ぶんこう作法を確立。(1445?〜1523)
⇒しの【志野】
しのだ【信太・信田】
大阪府泉北郡の旧村名。今は和泉市に属する。信太の森がある。
⇒しのだ‐ずし【信太鮨】
⇒しのだ‐づま【信太妻】
⇒しのだ‐の‐もり【信太の森】
⇒しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
し‐の‐たいふ【史大夫】
大史だいしの従五位下に叙せられた者。
しの‐だけ【篠竹】
全体に細く、葉も細かな竹・笹の類の俗称。スズタケ・アズマネザサなど。しのざさ。
しのだ‐ずし【信太鮨】
(狐は油揚を好むということから、信太の森の狐の伝説によって命名されたという)稲荷鮨いなりずしの別名。
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐づま【信太妻】
信太の森の葛の葉狐くずのはぎつねが安倍保名あべのやすなと結婚し、1子をもうけたという伝説。説経・浄瑠璃・歌舞伎などの題材となった。→葛の葉。
⇒しのだ【信太・信田】
しのたて‐すねあて【篠立臑当】
(→)「しのすねあて」に同じ。
しの‐だな【志野棚】
志野宗信と嗣子の宗温が創製した袋棚。上段に香道具を納める乱れ箱、中段右に予備の添香炉、左に阿古陀香炉、下段に重ね硯を飾る。桑や桐で製する。
しのだ‐の‐もり【信太の森】
大阪府和泉市信太山にある森。樟の大樹の下に、白狐のすんだという洞窟がある。葛の葉の伝説で有名。時雨・紅葉の名所。「篠田の森」とも書く。(歌枕) 源氏物語若菜上「この―を道のしるべにてまうで給ふ」
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
(油揚を用いるので、信太狐の伝説によって命名されたという)魚介・野菜・乾物などを刻み合わせて、油揚を袋状にした中に詰めたり、巻いたりしたものを甘く煮た料理。
⇒しのだ【信太・信田】
しの‐だれ【篠垂・鎬垂】
兜かぶとの鉢の正面または前後・左右に伏せた細長い筋金。1条・2条ないし5条のものがある。正面の篠垂は多く金銅で剣形とするが、後世は銀杏形・蜥蜴頭とかげがしらで、銀または白鑞しろめで飾った。撓垂しなだれ。→兜(図)
し‐の‐ちょう【使の庁】‥チヤウ
検非違使庁けびいしちょうのこと。
しのづか‐りゅう【篠塚流】‥リウ
京舞の一流派。文政(1818〜1830)の頃、京都の歌舞伎舞踊の振付師篠塚文三郎( 〜1845)が創始。
じ‐の‐つき【瓷】
(→)「じのうつわもの」に同じ。字鏡集「瓷、シノツキ・ジノウツハモノ」
しの‐つく‐あめ【篠突く雨】
篠をたばねて突きおろすようにはげしく降る雨。
しの‐づけ【罧】
(→)柴漬ふしづけ2に同じ。
し‐の‐つづみ【四の鼓】
古代の雅楽の打楽器。細腰鼓さいようこの一種。四鼓。→細腰鼓
し‐の‐て【真の手】
(シンノテのンの無表記)真書。楷書。宇津保物語国譲上「山吹につけたるは―春の字」
じ‐の‐なぞ【字の謎】
⇒じなぞ(字謎)
し‐の‐に【四の二】
①賽さいの目の四と二。狂言、双六「我はそこにて―けり(「死にけり」にかける)」
②六をしゃれていう語。
しの‐に
〔副〕
①(露などで)しっとりと濡れて。また、(悲しみなどで)しっとり、しみじみした気分になって。万葉集10「秋の穂を―押しなべ置く露の」。万葉集3「淡海の海夕浪千鳥なが鳴けば心も―古へおもほゆ」
②しげく。しきりに。新古今和歌集恋「逢ふ事はかたのの里の笹の庵―露散る夜はの床かな」
シノニム【synonym】
同義語。↔アントニム
しのね【羊蹄】
〔植〕ギシギシの古称。特に、その根。
しののい【篠ノ井】‥ヰ
長野市南部の地名。交通の要衝。
⇒しののい‐せん【篠ノ井線】
しののい‐せん【篠ノ井線】‥ヰ‥
中央本線の塩尻から松本を経て信越本線の篠ノ井に至るJR線。全長66.7キロメートル。
⇒しののい【篠ノ井】
しの‐の‐おざさ【篠の小笹】‥ヲ‥
(→)篠1に同じ。新古今和歌集旅「ふしわびぬ―のかり枕」
しの‐の‐おすすき【篠の小薄】‥ヲ‥
(→)「しのすすき」1に同じ。古今和歌集六帖6「相坂の―老いはてぬとも」
しの‐の‐おふぶき【篠の小吹雪】‥ヲ‥
篠を吹くはげしい風に雪が散ること。一説に、篠を吹きなびかす風。催馬楽、逢路「あふみぢの―、はや曳かず」
しのの‐に
〔副〕
ぐっしょりぬれるさまをいう。しとどに。しっぽりと。万葉集10「朝霧に―ぬれて」
しののは‐ぐさ【篠の葉草】
(→)篠1に同じ。新古今和歌集恋「散らすなよ―のかりにても」
しの‐の‐め【東雲】
(一説に、「め」は原始的住居の明り取りの役目を果たしていた網代様あじろようの粗い編み目のことで、篠竹を材料として作られた「め」が「篠の目」と呼ばれた。これが、明り取りそのものの意になり、転じて夜明けの薄明り、さらに夜明けそのものの意になったとする)
①東の空がわずかに明るくなる頃。あけがた。あかつき。あけぼの。古今和歌集恋「―のほがらほがらと明けゆけば」
②明け方に、東の空にたなびく雲。
⇒しののめ‐ぐさ【東雲草】
しののめ‐ぐさ【東雲草】
アサガオの異称。
⇒しの‐の‐め【東雲】
しののめ‐しんぶん【東雲新聞】
1888年(明治21)中江兆民を主筆に大阪で創刊された自由民権派系の新聞。革新的論調で声価を高めた。91年頃休刊。
しののめ‐ぶし【東雲節】
明治後期の流行歌。1899年(明治32)名古屋旭新地の東雲楼の娼妓がストライキを起して廃業した後に起こったという。ストライキ節。斎藤緑雨、半文銭「サイショネの磯節や、ナントショの―や、天下の乞丐こじきもよく之を諳誦す」
しの‐ば【収納場】
(→)「しのぐら(収納倉)」に同じ。
し‐の‐はい【死の灰】‥ハヒ
(1954年第五福竜丸事件の際、日本の新聞が造った語)核兵器の爆発、また原子炉内の核反応によって大量に生ずる放射性生成物の通称。ストロンチウム90、セシウム137などが、直接あるいは間接に人体に害を及ぼす。
しのはく【偲はく】
(シノフのク語法)はるかに思い慕うこと。恋しく思うこと。万葉集19「ほととぎす聞けば―あはぬ日を多み」
し‐の‐はこ【尿の箱・清箱】
便器。おまる。〈倭名類聚鈔14〉→おおつぼ
しのば・し【偲ばし】
〔形シク〕
慕わしい。忘れにくい。撰集抄「今更むかしも恋しく、そのあとも―・しく」
しのは・す【偲はす】
〔自四〕
(平安時代以後はシノバス。スは尊敬の意)お思い出しになる。万葉集4「わがかたみ見つつ―・せ」
しのばず‐の‐いけ【不忍池】
東京、上野公園の南西にある池。1625年(寛永2)寛永寺建立の際、池に弁財天を祀ってから有名になる。蓮の名所。
不忍池
提供:東京都
じ‐のし【地伸し】ヂ‥
(→)「地直し」に同じ。
し‐の‐しょうにん【死の商人】‥シヤウ‥
軍需品を製造・販売して巨利を得る大資本を指していう語。
しのしょうり【死の勝利】
(Il trionfo della morte イタリア)ダンヌンツィオの小説。1894年刊。恋人イッポーリタを抱いて断崖に身を投ずる主人公ジョルジョの性愛心理を語る。
しの‐すがき【篠簀掻】
篠竹をつづり合わせてつくった簀子すのこ。
しの‐すすき【篠薄】
①細竹の群がり生えるもの。篠の小薄おすすき。万葉集7「妹等がりわが行く道の―」
②まだ穂の出ない薄すすき。源氏物語宿木「ほに出でぬ物思ふらし―」
しの‐すだれ【篠簾】
篠竹を編んでつくった簾。新撰六帖2「隔つれどまばらに編める―」
しの‐すねあて【篠臑当】
家地いえじの布帛に篠金物をとりつけた臑当。しのたてすねあて。
し‐の‐せん【使の宣】
「しのせんじ」の略。源平盛衰記41「―を蒙つて」
し‐の‐ぜん【四の膳】
⇒よのぜん
し‐の‐せんじ【使の宣旨】
奉幣使・検非違使けびいしなどを任命する時に発行された宣旨。しのせん。
しの‐そうしん【志野宗信】
志野流香道の祖。通称、三郎右衛門。磐城の人。三条西実隆に従って香道の奥義を究める。足利義政に仕え、聞香ぶんこう作法を確立。(1445?〜1523)
⇒しの【志野】
しのだ【信太・信田】
大阪府泉北郡の旧村名。今は和泉市に属する。信太の森がある。
⇒しのだ‐ずし【信太鮨】
⇒しのだ‐づま【信太妻】
⇒しのだ‐の‐もり【信太の森】
⇒しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
し‐の‐たいふ【史大夫】
大史だいしの従五位下に叙せられた者。
しの‐だけ【篠竹】
全体に細く、葉も細かな竹・笹の類の俗称。スズタケ・アズマネザサなど。しのざさ。
しのだ‐ずし【信太鮨】
(狐は油揚を好むということから、信太の森の狐の伝説によって命名されたという)稲荷鮨いなりずしの別名。
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐づま【信太妻】
信太の森の葛の葉狐くずのはぎつねが安倍保名あべのやすなと結婚し、1子をもうけたという伝説。説経・浄瑠璃・歌舞伎などの題材となった。→葛の葉。
⇒しのだ【信太・信田】
しのたて‐すねあて【篠立臑当】
(→)「しのすねあて」に同じ。
しの‐だな【志野棚】
志野宗信と嗣子の宗温が創製した袋棚。上段に香道具を納める乱れ箱、中段右に予備の添香炉、左に阿古陀香炉、下段に重ね硯を飾る。桑や桐で製する。
しのだ‐の‐もり【信太の森】
大阪府和泉市信太山にある森。樟の大樹の下に、白狐のすんだという洞窟がある。葛の葉の伝説で有名。時雨・紅葉の名所。「篠田の森」とも書く。(歌枕) 源氏物語若菜上「この―を道のしるべにてまうで給ふ」
⇒しのだ【信太・信田】
しのだ‐まき【信太巻・信田巻】
(油揚を用いるので、信太狐の伝説によって命名されたという)魚介・野菜・乾物などを刻み合わせて、油揚を袋状にした中に詰めたり、巻いたりしたものを甘く煮た料理。
⇒しのだ【信太・信田】
しの‐だれ【篠垂・鎬垂】
兜かぶとの鉢の正面または前後・左右に伏せた細長い筋金。1条・2条ないし5条のものがある。正面の篠垂は多く金銅で剣形とするが、後世は銀杏形・蜥蜴頭とかげがしらで、銀または白鑞しろめで飾った。撓垂しなだれ。→兜(図)
し‐の‐ちょう【使の庁】‥チヤウ
検非違使庁けびいしちょうのこと。
しのづか‐りゅう【篠塚流】‥リウ
京舞の一流派。文政(1818〜1830)の頃、京都の歌舞伎舞踊の振付師篠塚文三郎( 〜1845)が創始。
じ‐の‐つき【瓷】
(→)「じのうつわもの」に同じ。字鏡集「瓷、シノツキ・ジノウツハモノ」
しの‐つく‐あめ【篠突く雨】
篠をたばねて突きおろすようにはげしく降る雨。
しの‐づけ【罧】
(→)柴漬ふしづけ2に同じ。
し‐の‐つづみ【四の鼓】
古代の雅楽の打楽器。細腰鼓さいようこの一種。四鼓。→細腰鼓
し‐の‐て【真の手】
(シンノテのンの無表記)真書。楷書。宇津保物語国譲上「山吹につけたるは―春の字」
じ‐の‐なぞ【字の謎】
⇒じなぞ(字謎)
し‐の‐に【四の二】
①賽さいの目の四と二。狂言、双六「我はそこにて―けり(「死にけり」にかける)」
②六をしゃれていう語。
しの‐に
〔副〕
①(露などで)しっとりと濡れて。また、(悲しみなどで)しっとり、しみじみした気分になって。万葉集10「秋の穂を―押しなべ置く露の」。万葉集3「淡海の海夕浪千鳥なが鳴けば心も―古へおもほゆ」
②しげく。しきりに。新古今和歌集恋「逢ふ事はかたのの里の笹の庵―露散る夜はの床かな」
シノニム【synonym】
同義語。↔アントニム
しのね【羊蹄】
〔植〕ギシギシの古称。特に、その根。
しののい【篠ノ井】‥ヰ
長野市南部の地名。交通の要衝。
⇒しののい‐せん【篠ノ井線】
しののい‐せん【篠ノ井線】‥ヰ‥
中央本線の塩尻から松本を経て信越本線の篠ノ井に至るJR線。全長66.7キロメートル。
⇒しののい【篠ノ井】
しの‐の‐おざさ【篠の小笹】‥ヲ‥
(→)篠1に同じ。新古今和歌集旅「ふしわびぬ―のかり枕」
しの‐の‐おすすき【篠の小薄】‥ヲ‥
(→)「しのすすき」1に同じ。古今和歌集六帖6「相坂の―老いはてぬとも」
しの‐の‐おふぶき【篠の小吹雪】‥ヲ‥
篠を吹くはげしい風に雪が散ること。一説に、篠を吹きなびかす風。催馬楽、逢路「あふみぢの―、はや曳かず」
しのの‐に
〔副〕
ぐっしょりぬれるさまをいう。しとどに。しっぽりと。万葉集10「朝霧に―ぬれて」
しののは‐ぐさ【篠の葉草】
(→)篠1に同じ。新古今和歌集恋「散らすなよ―のかりにても」
しの‐の‐め【東雲】
(一説に、「め」は原始的住居の明り取りの役目を果たしていた網代様あじろようの粗い編み目のことで、篠竹を材料として作られた「め」が「篠の目」と呼ばれた。これが、明り取りそのものの意になり、転じて夜明けの薄明り、さらに夜明けそのものの意になったとする)
①東の空がわずかに明るくなる頃。あけがた。あかつき。あけぼの。古今和歌集恋「―のほがらほがらと明けゆけば」
②明け方に、東の空にたなびく雲。
⇒しののめ‐ぐさ【東雲草】
しののめ‐ぐさ【東雲草】
アサガオの異称。
⇒しの‐の‐め【東雲】
しののめ‐しんぶん【東雲新聞】
1888年(明治21)中江兆民を主筆に大阪で創刊された自由民権派系の新聞。革新的論調で声価を高めた。91年頃休刊。
しののめ‐ぶし【東雲節】
明治後期の流行歌。1899年(明治32)名古屋旭新地の東雲楼の娼妓がストライキを起して廃業した後に起こったという。ストライキ節。斎藤緑雨、半文銭「サイショネの磯節や、ナントショの―や、天下の乞丐こじきもよく之を諳誦す」
しの‐ば【収納場】
(→)「しのぐら(収納倉)」に同じ。
し‐の‐はい【死の灰】‥ハヒ
(1954年第五福竜丸事件の際、日本の新聞が造った語)核兵器の爆発、また原子炉内の核反応によって大量に生ずる放射性生成物の通称。ストロンチウム90、セシウム137などが、直接あるいは間接に人体に害を及ぼす。
しのはく【偲はく】
(シノフのク語法)はるかに思い慕うこと。恋しく思うこと。万葉集19「ほととぎす聞けば―あはぬ日を多み」
し‐の‐はこ【尿の箱・清箱】
便器。おまる。〈倭名類聚鈔14〉→おおつぼ
しのば・し【偲ばし】
〔形シク〕
慕わしい。忘れにくい。撰集抄「今更むかしも恋しく、そのあとも―・しく」
しのは・す【偲はす】
〔自四〕
(平安時代以後はシノバス。スは尊敬の意)お思い出しになる。万葉集4「わがかたみ見つつ―・せ」
しのばず‐の‐いけ【不忍池】
東京、上野公園の南西にある池。1625年(寛永2)寛永寺建立の際、池に弁財天を祀ってから有名になる。蓮の名所。
不忍池
提供:東京都
 しのばず‐ぶんこ【不忍文庫】
江戸後期、屋代弘賢やしろひろかたが不忍池畔の邸宅に設けた文庫。蔵書はのちに阿波国文庫あわのくにぶんこに献納。
しのば・せる【忍ばせる】
〔他下一〕
人に知られないようにする。こっそりと隠しておく。「足音を―・せる」「ポケットにピストルを―・せる」「敵中にスパイを―・せる」
しのは‐ゆ【偲はゆ】
(平安時代以後はシノバユ。ユは自発の助動詞)しのばれる。万葉集6「日け長くあれば家し―」
しの‐はら【篠原】
篠竹の生えた原。ささはら。万葉集7「われし通はばなびけ―」
しのひ【偲ひ・慕ひ】
(シノフの連用形から。平安時代以後はシノビ)深く思うこと。慕うこと。賞美すること。万葉集9「後人のちひとの―にせむと」
しのび【忍び】
①こらえること。我慢すること。
②ひそかにすること。
㋐身を隠して敵陣または城・人家などに入りこむ術。忍びの術。忍術。
㋑「忍びの者」の略。太平記20「或夜の雨風の紛れに、逸物の―を八幡山へ入れて」
㋒「忍び歩あるき」の略。おしのび。
㋓窃盗せっとうの異名。
㋔表に小さく裏に大きな針目で縫いつけること。
⇒しのび‐あい【忍び逢い】
⇒しのび‐あし【忍び足】
⇒しのび‐あみがさ【忍び編笠】
⇒しのび‐あるき【忍び歩き】
⇒しのび‐おとこ【忍び男】
⇒しのび‐おんな【忍び女】
⇒しのび‐がえし【忍び返し】
⇒しのび‐がき【忍び垣】
⇒しのび‐かご【忍び駕籠】
⇒しのび‐くぎ【忍び釘】
⇒しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
⇒しのび‐ぐみ【忍び組】
⇒しのび‐ぐるま【忍び車】
⇒しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
⇒しのび‐ごえ【忍び声】
⇒しのび‐ごと【忍び言】
⇒しのび‐ごと【忍び事】
⇒しのび‐ごま【忍駒】
⇒しのび‐さんじゅう【忍三重】
⇒しのび‐じ【忍び路】
⇒しのび‐しのび【忍び忍び】
⇒しのび‐ずきん【忍び頭巾】
⇒しのび‐すげ【忍び菅】
⇒しのび‐だ【忍び田】
⇒しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】
⇒しのび‐づま【忍び夫】
⇒しのび‐づま【忍び妻】
⇒しのび‐で【忍び手・短手】
⇒しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
⇒しのび‐とり【忍び取り】
⇒しのび‐ながし【忍び流し】
⇒しのび‐なき【忍び泣き】
⇒しのび‐なみだ【忍び涙】
⇒しのび‐に【忍びに】
⇒しのび‐ね【忍び音】
⇒しのび‐ねお【忍根緒】
⇒しのび‐の‐お【忍の緒】
⇒しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
⇒しのび‐の‐もの【忍びの者】
⇒しのび‐び【忍び火】
⇒しのび‐びと【忍び人】
⇒しのび‐ぶね【忍び船】
⇒しのび‐まわり【忍び回り】
⇒しのび‐めつけ【忍目付】
⇒しのび‐もとゆい【忍元結】
⇒しのび‐ものみ【忍び物見】
⇒しのび‐わらい【忍び笑い】
しのび‐あい【忍び逢い】‥アヒ
男女が人目をさけて逢うこと。密会。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あ・う【忍び逢う】‥アフ
〔自五〕
思いあう男女が人目を避けてあう。密会する。
しのび‐あし【忍び足】
他人に気づかれないようにこっそりと歩く足どり。ぬきあし。「―で近づく」
⇒しのび【忍び】
しのび‐あみがさ【忍び編笠】
遊里に遊ぶ者が顔をかくすためにかぶった編笠。忍び笠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あるき【忍び歩き】
①(身分の高い者などが)他人に知られないように身をやつして外出すること。微行。おしのび。しのびありき。
②(→)「しのびあし」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐い・る【忍び入る】
〔自五〕
人に知れないように入り込む。
しのび‐おとこ【忍び男】‥ヲトコ
かくし男。まおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐おんな【忍び女】‥ヲンナ
①かくし女。情婦。
②私娼。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がえし【忍び返し】‥ガヘシ
塀などの上にとがった竹・木・鉄などをつらね立てた設備。盗賊などの忍び入るのを防ぐためのもの。矢切やぎり。日葡辞書「シノビガエシ、また、シノビガエリ」
忍び返し
しのばず‐ぶんこ【不忍文庫】
江戸後期、屋代弘賢やしろひろかたが不忍池畔の邸宅に設けた文庫。蔵書はのちに阿波国文庫あわのくにぶんこに献納。
しのば・せる【忍ばせる】
〔他下一〕
人に知られないようにする。こっそりと隠しておく。「足音を―・せる」「ポケットにピストルを―・せる」「敵中にスパイを―・せる」
しのは‐ゆ【偲はゆ】
(平安時代以後はシノバユ。ユは自発の助動詞)しのばれる。万葉集6「日け長くあれば家し―」
しの‐はら【篠原】
篠竹の生えた原。ささはら。万葉集7「われし通はばなびけ―」
しのひ【偲ひ・慕ひ】
(シノフの連用形から。平安時代以後はシノビ)深く思うこと。慕うこと。賞美すること。万葉集9「後人のちひとの―にせむと」
しのび【忍び】
①こらえること。我慢すること。
②ひそかにすること。
㋐身を隠して敵陣または城・人家などに入りこむ術。忍びの術。忍術。
㋑「忍びの者」の略。太平記20「或夜の雨風の紛れに、逸物の―を八幡山へ入れて」
㋒「忍び歩あるき」の略。おしのび。
㋓窃盗せっとうの異名。
㋔表に小さく裏に大きな針目で縫いつけること。
⇒しのび‐あい【忍び逢い】
⇒しのび‐あし【忍び足】
⇒しのび‐あみがさ【忍び編笠】
⇒しのび‐あるき【忍び歩き】
⇒しのび‐おとこ【忍び男】
⇒しのび‐おんな【忍び女】
⇒しのび‐がえし【忍び返し】
⇒しのび‐がき【忍び垣】
⇒しのび‐かご【忍び駕籠】
⇒しのび‐くぎ【忍び釘】
⇒しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
⇒しのび‐ぐみ【忍び組】
⇒しのび‐ぐるま【忍び車】
⇒しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
⇒しのび‐ごえ【忍び声】
⇒しのび‐ごと【忍び言】
⇒しのび‐ごと【忍び事】
⇒しのび‐ごま【忍駒】
⇒しのび‐さんじゅう【忍三重】
⇒しのび‐じ【忍び路】
⇒しのび‐しのび【忍び忍び】
⇒しのび‐ずきん【忍び頭巾】
⇒しのび‐すげ【忍び菅】
⇒しのび‐だ【忍び田】
⇒しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】
⇒しのび‐づま【忍び夫】
⇒しのび‐づま【忍び妻】
⇒しのび‐で【忍び手・短手】
⇒しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
⇒しのび‐とり【忍び取り】
⇒しのび‐ながし【忍び流し】
⇒しのび‐なき【忍び泣き】
⇒しのび‐なみだ【忍び涙】
⇒しのび‐に【忍びに】
⇒しのび‐ね【忍び音】
⇒しのび‐ねお【忍根緒】
⇒しのび‐の‐お【忍の緒】
⇒しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
⇒しのび‐の‐もの【忍びの者】
⇒しのび‐び【忍び火】
⇒しのび‐びと【忍び人】
⇒しのび‐ぶね【忍び船】
⇒しのび‐まわり【忍び回り】
⇒しのび‐めつけ【忍目付】
⇒しのび‐もとゆい【忍元結】
⇒しのび‐ものみ【忍び物見】
⇒しのび‐わらい【忍び笑い】
しのび‐あい【忍び逢い】‥アヒ
男女が人目をさけて逢うこと。密会。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あ・う【忍び逢う】‥アフ
〔自五〕
思いあう男女が人目を避けてあう。密会する。
しのび‐あし【忍び足】
他人に気づかれないようにこっそりと歩く足どり。ぬきあし。「―で近づく」
⇒しのび【忍び】
しのび‐あみがさ【忍び編笠】
遊里に遊ぶ者が顔をかくすためにかぶった編笠。忍び笠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐あるき【忍び歩き】
①(身分の高い者などが)他人に知られないように身をやつして外出すること。微行。おしのび。しのびありき。
②(→)「しのびあし」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐い・る【忍び入る】
〔自五〕
人に知れないように入り込む。
しのび‐おとこ【忍び男】‥ヲトコ
かくし男。まおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐おんな【忍び女】‥ヲンナ
①かくし女。情婦。
②私娼。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がえし【忍び返し】‥ガヘシ
塀などの上にとがった竹・木・鉄などをつらね立てた設備。盗賊などの忍び入るのを防ぐためのもの。矢切やぎり。日葡辞書「シノビガエシ、また、シノビガエリ」
忍び返し
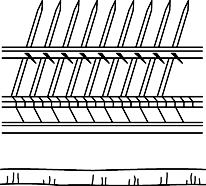 ⇒しのび【忍び】
しのび‐かえ・す【忍び返す】‥カヘス
〔自四〕
苦しい気持などをおさえる。源氏物語宿木「―・しつつ聞きも入れぬさまにて過し給ふ」
しのび‐がき【忍び垣】
高さ約2メートル、上・中・下3段に分かれ、上段は建仁寺垣のようにし、中段は葭よしを用い櫛形のすかしなどを設け、下段は大竹の二つ割にしたのを斜めに組み合わせた垣。
⇒しのび【忍び】
しのび‐かご【忍び駕籠】
人目をしのんで駕籠に乗ること。また、その駕籠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がた・い【忍び難い】
〔形〕[文]しのびがた・し(ク)
我慢することができない。耐えがたい。森鴎外、渋江抽斎「五百いおは情として―・くはあつたが」
しのび‐くぎ【忍び釘】
かくしくぎ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
慕い思う原因となるもの。しのぶぐさ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐみ【忍び組】
忍びの者の仲間。伊賀組・甲賀組の類。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐるま【忍び車】
人目に立たないように隠れて車に乗って行くこと。また、その車。
⇒しのび【忍び】
しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
近世、江戸で倹飩そばを運ぶのに用いた長方形の箱。中にしきりがあって狭い方に汁つぎ・辛みなどを入れた。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごえ【忍び声】‥ゴヱ
他に聞こえないように発する低い声。ひそひそ声。しのびね。
⇒しのび【忍び】
しのひ‐ごと【誄】
(平安時代以後はシノビゴト)貴人の死を悼み生前の徳などを追憶して述べる詞。誄辞るいじ。敏達紀「馬子宿祢大臣刀を佩はきて―たてまつる」
しのび‐ごと【忍び言】
ひそひそばなし。内証話。私語。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごと【忍び事】
かくしごと。内証ごと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごま【忍駒】
①三味線の音を小さくするために用いる駒。
②地歌の曲名。峰崎勾当作曲。
⇒しのび【忍び】
しのび‐こ・む【忍び込む】
〔自五〕
忍んではいりこむ。しのびいる。「留守宅に―・む」
しのび‐こ・む【忍び籠む】
〔他下二〕
心に深く包み隠す。源氏物語椎本「ひとことうち出で聞ゆるついでなく―・めたりければ」
しのび‐さんじゅう【忍三重】‥ヂユウ
下座げざ音楽。暗中の手探りの動きなどに用いる三味線の旋律。→三重2㋔。
⇒しのび【忍び】
しのび‐じ【忍び路】‥ヂ
隠れしのんで行くみち。特に男女がひそかに互いのもとに通うこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐しのび【忍び忍び】
特に人目を避けること。源氏物語帚木「―の御方違所おんかたたがえどころ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ずきん【忍び頭巾】‥ヅ‥
遊里通いなど、忍び歩きに用いた頭巾。
⇒しのび【忍び】
しのび‐すげ【忍び菅】
地中に根の生え広がった菅。
⇒しのび【忍び】
しのび‐だ【忍び田】
隠して年貢を納めない田地。隠し田。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】‥ヂヤウ‥
①貴人が人目をしのんで夜出かける時に用いた、替え紋の提灯。
②「がんどうぢょうちん」の別称。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び夫】
かくしおとこ。みそかお。しのびおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び妻】
かくしおんな。かくしめ。かこいもの。しのびおんな。
⇒しのび【忍び】
しのび‐で【忍び手・短手】
(シノビテとも)音の立たないように打ち合わす拍手かしわで。神道の葬儀で行う。
⇒しのび【忍び】
しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
①かくれひそむ所。忍んで通う所。源氏物語紅梅「通ひ給ふ―多く」
②なつかしく思うこと。また、その所。源氏物語真木柱「ここら年経給へる御すみかの、いかでか―なくはあらむ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐とり【忍び取り】
ひそかに侵入して敵城を乗っ取ること。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ない【忍びない】
がまんできない。耐えられない。「聞くに―」
しのび‐ながし【忍び流し】
表面的には栄転であるが、実は退けて遠方の官にうつすこと。左遷。孝徳紀「是れ隠流しのびながしか」
⇒しのび【忍び】
しのび‐なき【忍び泣き】
声を立てずに泣くこと。人知れず泣くこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐な・く【忍び泣く】
〔自五〕
人に気づかれないように泣く。声を立てずに泣く。
しのび‐なみだ【忍び涙】
人知れず流す涙。忍び泣きの涙。
⇒しのび【忍び】
しのび‐に【忍びに】
〔副〕
人知れず。ひそかに。源氏物語帚木「―御文通はしなどして」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ね【忍び音】
①ひそひそ声。しのびごえ。源平盛衰記31「夜ふくるまでは―に念仏申し」
②陰暦4月頃、ホトトギスがまだ声をひそめて鳴くこと。また、その声。落窪物語3「ほととぎす待ちつる宵の―はまどろまねども驚かれけり」
③忍び泣くこと。また、そのかすかな声。更級日記「―をのみ泣きて」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ねお【忍根緒】‥ヲ
(→)「しのびのお」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐お【忍の緒】‥ヲ
兜かぶとの鉢につけてあごのところで結ぶ紐ひも。しのびねお。兜の緒。
⇒しのび【忍び】
しのび‐のこ・す【忍び残す】
〔他四〕
隠して出さずに置く。源氏物語薄雲「そこにはかく―・されたる事ありけるを」
しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
敵情偵察・暗殺などの目的で、ひそかに敵陣や人家に入り込む術。にんじゅつ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐もの【忍びの者】
忍びの術を使う者。間者。しのび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐び【忍び火】
音を立てずに打つ切火きりび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐びと【忍び人】
①人目を忍んで通う人。
②世を隠れ忍ぶ人。隠者。
③(→)「忍びの者」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぶね【忍び船】
人目を忍んで漕ぐ船。
⇒しのび【忍び】
しのび‐まわり【忍び回り】‥マハリ
①ひそかに巡回して見回ること。また、その人。
②(→)忍目付しのびめつけに同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐めつけ【忍目付】
内密に調査を必要とする地方を視察し、主人に報告する武家の役。しのびまわり。→お庭番。
⇒しのび【忍び】
しのび‐もとゆい【忍元結】‥ユヒ
元結の掛け方の一つ。外部から見えないように結ぶもの。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ものみ【忍び物見】
戦場で、山野に隠れて敵情をさぐる者。足軽などがこれに当たった。かすりものみ。しばみ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐やか【忍びやか】
しのんでするさま。ひそかにするさま。源氏物語夕霧「―なる声づかひなどを、よろしう聞きなし給へり」。「―な足音」「―に近づく」
しのび‐よ・る【忍び寄る】
〔自五〕
相手が気づかないうちにそっと近づく。太平記14「敵の陣近く―・り」。「―・る秋」「インフレが―・る」
しのび‐わた・る【忍び渡る】
〔自四〕
①(「偲び渡る」とも混同して)恋い慕う気持を我慢しながら、長い年月を過ごす。源氏物語夕霧「年ごろ―・り給ひける心のうちを」
②ひそかに行く。人目を避けて来る。夜の寝覚3「夜さりしのびてわたらせ給ひて」
しのび‐わた・る【偲び渡る】
〔他四〕
(奈良時代にはシノヒワタル)長い間慕いつづける。万葉集13「千世にも―・れと」
しのび‐わらい【忍び笑い】‥ワラヒ
人に気づかれないように声を殺して笑うこと。また、その笑い。
⇒しのび【忍び】
しの・ふ【偲ふ】
〔他四〕
⇒しのぶ(偲ぶ)
しのぶ【忍】
①シノブ科のシダ。茎は淡褐色の鱗毛を密生。葉柄は淡褐色で、長さ約5〜10センチメートル。葉は数回羽状に分裂。根茎をからみ合わせてしのぶ玉・釣忍つりしのぶとして観賞用に軒下などに吊す。シノブグサ。
②忍摺しのぶずりの略。
③襲かさねの色目。表は薄い萌葱もえぎ、裏は青。
④忍髷しのぶわげの略。
⇒しのぶ‐いし【忍石】
⇒しのぶ‐ぐさ【忍草】
⇒しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
⇒しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
⇒しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
⇒しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】
⇒しのぶ‐もじずり【忍捩摺】
⇒しのぶ‐わげ【忍髷】
しのぶ【信夫】
福島県の旧郡名。はじめ石背いわせ国、のち陸奥国の一部。今の福島市南部に当たる。
しの・ぶ【忍ぶ】
[一]〔他上二〕
(現代語では五段活用で用いるが、打消に続く時は「しのび」の形も用いる)
①こらえる。我慢する。耐える。万葉集17「わが背子が抓つみし手見つつ―・びかねつも」。源氏物語賢木「―・ぶれど涙ほろほろとこぼれ給ひぬ」。「捨てるに―・びない」
②秘密にする。かくす。源氏物語夕顔「―・ぶるやうこそはと、あながちにも問ひいで給はず」
③(自動詞的に)人目を避ける。かくれる。源氏物語松風「惟光の朝臣例の―・ぶる道はいつとなくいろひ仕うまつる人なれば」
[二]〔他五〕
(意味上の類似から平安時代以後、四段活用の偲ブと混同して生じた活用形)
①こらえる。我慢する。平中物語「こと局に人あまた見ゆるを、え―・ばで言ひやる」。「不便を―・ぶ」「恥を―・ぶ」
②表立たないようにする。人目を避ける。(自動詞的にも使う)拾遺和歌集恋「―・ばむに―・ばれぬべき恋ならばつらきにつけてやみもしなまし」。平家物語灌頂「何者のとひ来るやらむ。あれ見よや。―・ぶべきものならば急ぎ―・ばむ」。「世を―・ぶ姿」「人目を―・んで泣く」
しの・ぶ【偲ぶ】
[一]〔他五〕
(奈良時代にはシノフと清音)
①過ぎ去ったこと、離れている人のことなどをひそかに思い慕う。恋いしたう。万葉集20「わが妻も絵にかきとらむ暇いづまもが旅ゆく我は見つつ―・はむ」。源氏物語明石「なほざりに頼めおくなる一ことをつきせぬねにやかけて―・ばむ」。「昔を―・ぶ」「故人を―・ぶ」
②心ひかれて(見えないところなどに)思いをはせる。「人柄が―・ばれる」
③賞美する。万葉集19「あしひきの山下ひかげ鬘かずらける上にやさらに梅を―・はむ」
[二]〔他上二〕
(意味上の類似から平安時代以後、上二段活用の忍ブと混同して生じた活用形)ひそかに思い慕う。心中で恋い慕う。源氏物語幻「なき人を―・ぶる宵の村雨に」。源氏物語賢木「あひ見ずて―・ぶる頃の涙をも」
しのぶ‐いし【忍石】
シノブの葉に似た模様のある岩石。岩石の割れ目に二酸化マンガンが沈殿してできる、偽化石の一種。模樹石。
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶえ【篠笛】
細い篠竹で作った横笛。指孔は7孔が標準だが、6孔・5孔以下もある。基音の高低により長短12本の種類があり、一本調子は最も低く、順次十二律に対応する。獅子舞・里神楽などの民俗芸能や歌舞伎囃子に用いる。竹笛。しの。
しのぶがおか【忍ヶ岡】‥ヲカ
東京、上野公園一帯の古名。しのぶのおか。
しのぶ‐ぐさ【忍草】
①シノブ・ノキシノブなどのシダ植物。源氏物語夕顔「荒れたる門かどの―茂りて」
②(シノフ(偲ふ)にかけて)慕い思う原因となるもの。心配のたね。しのびぐさ。万葉集6「石いわに生ふる菅の根取りて―はらへてましを」
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶくろ【志野袋】
志野流香道の簡略化した手前で、香包と銀葉包を収める袋。口を閉める紐は12カ月の花結びを用いる。
しのぶ‐こいじ【忍ぶ恋路】‥コヒヂ
しのびあう恋の苦しさを表す語。端唄はうた・うた沢に同名の曲がある。
シノプシス【synopsis】
梗概。シナリオなどのあらすじ。
しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
摺込染すりこみぞめの一種。昔、陸奥国信夫しのぶ郡から産出した忍草の茎・葉などの色素で捩もじれたように文様を布帛ふはくに摺りつけたもの。捩摺もじずりともいい、その文様が捩れからまっているからとも、捩れ乱れた文様のある石(もじずりいし)に布をあてて摺ったからともいう。しのぶもじずり。草の捩摺。しのぶ。伊勢物語「この男―の狩衣をなむ着たりける」
⇒しのぶ【忍】
し‐の‐ぶとう【死の舞踏】‥タフ
〔美〕(Totentanz ドイツ・danse macabre フランス)死を象徴する骸骨が、人々を巻き込んで踊る図像。中世末から近世初期にかけてヨーロッパ各地に広まった。ホルバインの木版画集が著名。
しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
しのぶずりの衣。通例、人目を忍んで涙にぬれること、または、堪え難くて涙にぬれることにたとえて用いる。新勅撰和歌集恋「逢ふことは―あはれなどまれなる色に乱れそめけん」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのそうた【忍ぶの惣太】
歌舞伎脚本「都鳥廓白浪みやこどりながれのしらなみ」の通称。河竹黙阿弥作の世話物。1854年(嘉永7)江戸河原崎座初演。隅田川物で、鳥目の侠客(4世市川小団次)が梅若を殺すくだりが評判となる。
しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
忍の衣の袖。また、忍の衣。源平盛衰記32「―をぞしぼられける」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのやかしゅう【志濃夫廼舎歌集】‥シフ
歌集。5巻。橘曙覧たちばなあけみの草稿をその子井手今滋が編。1878年(明治11)刊。万葉・古今風を融合し、日常的な素材・用語をも嫌わぬ独特の歌風をもつ。
しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】‥ヂユウ
春日かすが饅頭の別称。
⇒しのぶ【忍】
しのぶ‐もじずり【忍捩摺】‥モヂ‥
(→)「しのぶずり」に同じ。伊勢物語「みちのくの―誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに」
⇒しのぶ【忍】
しのふら・う【忍ふらふ】シノフラフ
〔他四〕
(上二段活用のシノフに動作の反復・継続を表す接尾語フの付いた語)ずっとがまんする。堪えつづける。万葉集16「とねりをとこも―・ひかへらひ見つつ」
しのぶ‐わげ【忍髷】
女の髪の結い方。髷をつくり、その余りを二分して根の左右に小さい輪を作り、髷の根元に笄こうがいを横にさす。元文(1736〜1741)初年上方に始まり、のち江戸吉原の遊女の間にも流行。また、これにかたどった歌舞伎女形用のかつら。信夫しのぶ返し。しのぶ。通言総籬つうげんそうまがき「髪は―」
⇒しのぶ【忍】
じ‐の‐ぶん【地の文】ヂ‥
小説や戯曲などで、会話文以外の説明や描写の文。
しのべ‐だけ【忍竹】
①メダケの別称。
②(→)ヤダケ2に同じ。〈日葡辞書〉
じ‐のみ【地蚤】ヂ‥
キボシマルトビムシの別称。
しの‐め【篠芽】
①おそく生えて色が青く、味のにがいたけのこ。長間笋。〈倭名類聚鈔20〉
②篠芽竹。
⇒しのめ‐だけ【篠芽竹】
しのめ‐だけ【篠芽竹】
(→)ヤダケ2に同じ。
⇒しの‐め【篠芽】
しの‐や【篠屋】
篠で葺ふいた小屋。永久百首「旅人のかりの―に年くれて」
しの‐やき【志野焼】
桃山時代、美濃(岐阜県土岐市・可児かに市)で焼かれた陶器。白釉(長石釉)を厚く施し、下に鉄で簡素な文様を描いた絵志野や、鼠色をし象眼風の文様のある鼠志野などがある。茶碗や水指に秀作が多い。
じ‐のり【地乗り】ヂ‥
①駻馬かんばを乗りこなすこと。
②馬の足並みをそろえて進ませること。地足。
しの‐りゅう【志野流】‥リウ
香道の流派。志野宗信そうしんを祖とし、4代以降は蜂谷家が伝承、享保の頃家元制度を整える。志野流茶道の家元でもある。
シノロジー【Sinology】
中国学。
し‐の‐わかれ【死の別れ】
一方が死んで別れとなること。しにわかれ。宇治拾遺物語9「―にぞわかれにける」
シノワズリー【chinoiserie フランス】
中国趣味。17〜18世紀の頃、ヨーロッパで流行。東洋の題材をとりあげ、あるいは中国風を取り入れた芸術。
しの‐わた【篠綿】
綿糸紡績工程で、梳綿そめんによって作られた、撚よりのかからない太い綱状の繊維束。スライバー。
⇒しのび【忍び】
しのび‐かえ・す【忍び返す】‥カヘス
〔自四〕
苦しい気持などをおさえる。源氏物語宿木「―・しつつ聞きも入れぬさまにて過し給ふ」
しのび‐がき【忍び垣】
高さ約2メートル、上・中・下3段に分かれ、上段は建仁寺垣のようにし、中段は葭よしを用い櫛形のすかしなどを設け、下段は大竹の二つ割にしたのを斜めに組み合わせた垣。
⇒しのび【忍び】
しのび‐かご【忍び駕籠】
人目をしのんで駕籠に乗ること。また、その駕籠。
⇒しのび【忍び】
しのび‐がた・い【忍び難い】
〔形〕[文]しのびがた・し(ク)
我慢することができない。耐えがたい。森鴎外、渋江抽斎「五百いおは情として―・くはあつたが」
しのび‐くぎ【忍び釘】
かくしくぎ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】
慕い思う原因となるもの。しのぶぐさ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐみ【忍び組】
忍びの者の仲間。伊賀組・甲賀組の類。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぐるま【忍び車】
人目に立たないように隠れて車に乗って行くこと。また、その車。
⇒しのび【忍び】
しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】
近世、江戸で倹飩そばを運ぶのに用いた長方形の箱。中にしきりがあって狭い方に汁つぎ・辛みなどを入れた。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごえ【忍び声】‥ゴヱ
他に聞こえないように発する低い声。ひそひそ声。しのびね。
⇒しのび【忍び】
しのひ‐ごと【誄】
(平安時代以後はシノビゴト)貴人の死を悼み生前の徳などを追憶して述べる詞。誄辞るいじ。敏達紀「馬子宿祢大臣刀を佩はきて―たてまつる」
しのび‐ごと【忍び言】
ひそひそばなし。内証話。私語。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごと【忍び事】
かくしごと。内証ごと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ごま【忍駒】
①三味線の音を小さくするために用いる駒。
②地歌の曲名。峰崎勾当作曲。
⇒しのび【忍び】
しのび‐こ・む【忍び込む】
〔自五〕
忍んではいりこむ。しのびいる。「留守宅に―・む」
しのび‐こ・む【忍び籠む】
〔他下二〕
心に深く包み隠す。源氏物語椎本「ひとことうち出で聞ゆるついでなく―・めたりければ」
しのび‐さんじゅう【忍三重】‥ヂユウ
下座げざ音楽。暗中の手探りの動きなどに用いる三味線の旋律。→三重2㋔。
⇒しのび【忍び】
しのび‐じ【忍び路】‥ヂ
隠れしのんで行くみち。特に男女がひそかに互いのもとに通うこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐しのび【忍び忍び】
特に人目を避けること。源氏物語帚木「―の御方違所おんかたたがえどころ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ずきん【忍び頭巾】‥ヅ‥
遊里通いなど、忍び歩きに用いた頭巾。
⇒しのび【忍び】
しのび‐すげ【忍び菅】
地中に根の生え広がった菅。
⇒しのび【忍び】
しのび‐だ【忍び田】
隠して年貢を納めない田地。隠し田。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】‥ヂヤウ‥
①貴人が人目をしのんで夜出かける時に用いた、替え紋の提灯。
②「がんどうぢょうちん」の別称。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び夫】
かくしおとこ。みそかお。しのびおとこ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐づま【忍び妻】
かくしおんな。かくしめ。かこいもの。しのびおんな。
⇒しのび【忍び】
しのび‐で【忍び手・短手】
(シノビテとも)音の立たないように打ち合わす拍手かしわで。神道の葬儀で行う。
⇒しのび【忍び】
しのび‐どころ【忍び所・偲び所】
①かくれひそむ所。忍んで通う所。源氏物語紅梅「通ひ給ふ―多く」
②なつかしく思うこと。また、その所。源氏物語真木柱「ここら年経給へる御すみかの、いかでか―なくはあらむ」
⇒しのび【忍び】
しのび‐とり【忍び取り】
ひそかに侵入して敵城を乗っ取ること。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ない【忍びない】
がまんできない。耐えられない。「聞くに―」
しのび‐ながし【忍び流し】
表面的には栄転であるが、実は退けて遠方の官にうつすこと。左遷。孝徳紀「是れ隠流しのびながしか」
⇒しのび【忍び】
しのび‐なき【忍び泣き】
声を立てずに泣くこと。人知れず泣くこと。
⇒しのび【忍び】
しのび‐な・く【忍び泣く】
〔自五〕
人に気づかれないように泣く。声を立てずに泣く。
しのび‐なみだ【忍び涙】
人知れず流す涙。忍び泣きの涙。
⇒しのび【忍び】
しのび‐に【忍びに】
〔副〕
人知れず。ひそかに。源氏物語帚木「―御文通はしなどして」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ね【忍び音】
①ひそひそ声。しのびごえ。源平盛衰記31「夜ふくるまでは―に念仏申し」
②陰暦4月頃、ホトトギスがまだ声をひそめて鳴くこと。また、その声。落窪物語3「ほととぎす待ちつる宵の―はまどろまねども驚かれけり」
③忍び泣くこと。また、そのかすかな声。更級日記「―をのみ泣きて」
⇒しのび【忍び】
しのび‐ねお【忍根緒】‥ヲ
(→)「しのびのお」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐お【忍の緒】‥ヲ
兜かぶとの鉢につけてあごのところで結ぶ紐ひも。しのびねお。兜の緒。
⇒しのび【忍び】
しのび‐のこ・す【忍び残す】
〔他四〕
隠して出さずに置く。源氏物語薄雲「そこにはかく―・されたる事ありけるを」
しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】
敵情偵察・暗殺などの目的で、ひそかに敵陣や人家に入り込む術。にんじゅつ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐の‐もの【忍びの者】
忍びの術を使う者。間者。しのび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐び【忍び火】
音を立てずに打つ切火きりび。
⇒しのび【忍び】
しのび‐びと【忍び人】
①人目を忍んで通う人。
②世を隠れ忍ぶ人。隠者。
③(→)「忍びの者」に同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ぶね【忍び船】
人目を忍んで漕ぐ船。
⇒しのび【忍び】
しのび‐まわり【忍び回り】‥マハリ
①ひそかに巡回して見回ること。また、その人。
②(→)忍目付しのびめつけに同じ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐めつけ【忍目付】
内密に調査を必要とする地方を視察し、主人に報告する武家の役。しのびまわり。→お庭番。
⇒しのび【忍び】
しのび‐もとゆい【忍元結】‥ユヒ
元結の掛け方の一つ。外部から見えないように結ぶもの。
⇒しのび【忍び】
しのび‐ものみ【忍び物見】
戦場で、山野に隠れて敵情をさぐる者。足軽などがこれに当たった。かすりものみ。しばみ。
⇒しのび【忍び】
しのび‐やか【忍びやか】
しのんでするさま。ひそかにするさま。源氏物語夕霧「―なる声づかひなどを、よろしう聞きなし給へり」。「―な足音」「―に近づく」
しのび‐よ・る【忍び寄る】
〔自五〕
相手が気づかないうちにそっと近づく。太平記14「敵の陣近く―・り」。「―・る秋」「インフレが―・る」
しのび‐わた・る【忍び渡る】
〔自四〕
①(「偲び渡る」とも混同して)恋い慕う気持を我慢しながら、長い年月を過ごす。源氏物語夕霧「年ごろ―・り給ひける心のうちを」
②ひそかに行く。人目を避けて来る。夜の寝覚3「夜さりしのびてわたらせ給ひて」
しのび‐わた・る【偲び渡る】
〔他四〕
(奈良時代にはシノヒワタル)長い間慕いつづける。万葉集13「千世にも―・れと」
しのび‐わらい【忍び笑い】‥ワラヒ
人に気づかれないように声を殺して笑うこと。また、その笑い。
⇒しのび【忍び】
しの・ふ【偲ふ】
〔他四〕
⇒しのぶ(偲ぶ)
しのぶ【忍】
①シノブ科のシダ。茎は淡褐色の鱗毛を密生。葉柄は淡褐色で、長さ約5〜10センチメートル。葉は数回羽状に分裂。根茎をからみ合わせてしのぶ玉・釣忍つりしのぶとして観賞用に軒下などに吊す。シノブグサ。
②忍摺しのぶずりの略。
③襲かさねの色目。表は薄い萌葱もえぎ、裏は青。
④忍髷しのぶわげの略。
⇒しのぶ‐いし【忍石】
⇒しのぶ‐ぐさ【忍草】
⇒しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
⇒しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
⇒しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
⇒しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】
⇒しのぶ‐もじずり【忍捩摺】
⇒しのぶ‐わげ【忍髷】
しのぶ【信夫】
福島県の旧郡名。はじめ石背いわせ国、のち陸奥国の一部。今の福島市南部に当たる。
しの・ぶ【忍ぶ】
[一]〔他上二〕
(現代語では五段活用で用いるが、打消に続く時は「しのび」の形も用いる)
①こらえる。我慢する。耐える。万葉集17「わが背子が抓つみし手見つつ―・びかねつも」。源氏物語賢木「―・ぶれど涙ほろほろとこぼれ給ひぬ」。「捨てるに―・びない」
②秘密にする。かくす。源氏物語夕顔「―・ぶるやうこそはと、あながちにも問ひいで給はず」
③(自動詞的に)人目を避ける。かくれる。源氏物語松風「惟光の朝臣例の―・ぶる道はいつとなくいろひ仕うまつる人なれば」
[二]〔他五〕
(意味上の類似から平安時代以後、四段活用の偲ブと混同して生じた活用形)
①こらえる。我慢する。平中物語「こと局に人あまた見ゆるを、え―・ばで言ひやる」。「不便を―・ぶ」「恥を―・ぶ」
②表立たないようにする。人目を避ける。(自動詞的にも使う)拾遺和歌集恋「―・ばむに―・ばれぬべき恋ならばつらきにつけてやみもしなまし」。平家物語灌頂「何者のとひ来るやらむ。あれ見よや。―・ぶべきものならば急ぎ―・ばむ」。「世を―・ぶ姿」「人目を―・んで泣く」
しの・ぶ【偲ぶ】
[一]〔他五〕
(奈良時代にはシノフと清音)
①過ぎ去ったこと、離れている人のことなどをひそかに思い慕う。恋いしたう。万葉集20「わが妻も絵にかきとらむ暇いづまもが旅ゆく我は見つつ―・はむ」。源氏物語明石「なほざりに頼めおくなる一ことをつきせぬねにやかけて―・ばむ」。「昔を―・ぶ」「故人を―・ぶ」
②心ひかれて(見えないところなどに)思いをはせる。「人柄が―・ばれる」
③賞美する。万葉集19「あしひきの山下ひかげ鬘かずらける上にやさらに梅を―・はむ」
[二]〔他上二〕
(意味上の類似から平安時代以後、上二段活用の忍ブと混同して生じた活用形)ひそかに思い慕う。心中で恋い慕う。源氏物語幻「なき人を―・ぶる宵の村雨に」。源氏物語賢木「あひ見ずて―・ぶる頃の涙をも」
しのぶ‐いし【忍石】
シノブの葉に似た模様のある岩石。岩石の割れ目に二酸化マンガンが沈殿してできる、偽化石の一種。模樹石。
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶえ【篠笛】
細い篠竹で作った横笛。指孔は7孔が標準だが、6孔・5孔以下もある。基音の高低により長短12本の種類があり、一本調子は最も低く、順次十二律に対応する。獅子舞・里神楽などの民俗芸能や歌舞伎囃子に用いる。竹笛。しの。
しのぶがおか【忍ヶ岡】‥ヲカ
東京、上野公園一帯の古名。しのぶのおか。
しのぶ‐ぐさ【忍草】
①シノブ・ノキシノブなどのシダ植物。源氏物語夕顔「荒れたる門かどの―茂りて」
②(シノフ(偲ふ)にかけて)慕い思う原因となるもの。心配のたね。しのびぐさ。万葉集6「石いわに生ふる菅の根取りて―はらへてましを」
⇒しのぶ【忍】
しの‐ぶくろ【志野袋】
志野流香道の簡略化した手前で、香包と銀葉包を収める袋。口を閉める紐は12カ月の花結びを用いる。
しのぶ‐こいじ【忍ぶ恋路】‥コヒヂ
しのびあう恋の苦しさを表す語。端唄はうた・うた沢に同名の曲がある。
シノプシス【synopsis】
梗概。シナリオなどのあらすじ。
しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】
摺込染すりこみぞめの一種。昔、陸奥国信夫しのぶ郡から産出した忍草の茎・葉などの色素で捩もじれたように文様を布帛ふはくに摺りつけたもの。捩摺もじずりともいい、その文様が捩れからまっているからとも、捩れ乱れた文様のある石(もじずりいし)に布をあてて摺ったからともいう。しのぶもじずり。草の捩摺。しのぶ。伊勢物語「この男―の狩衣をなむ着たりける」
⇒しのぶ【忍】
し‐の‐ぶとう【死の舞踏】‥タフ
〔美〕(Totentanz ドイツ・danse macabre フランス)死を象徴する骸骨が、人々を巻き込んで踊る図像。中世末から近世初期にかけてヨーロッパ各地に広まった。ホルバインの木版画集が著名。
しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】
しのぶずりの衣。通例、人目を忍んで涙にぬれること、または、堪え難くて涙にぬれることにたとえて用いる。新勅撰和歌集恋「逢ふことは―あはれなどまれなる色に乱れそめけん」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのそうた【忍ぶの惣太】
歌舞伎脚本「都鳥廓白浪みやこどりながれのしらなみ」の通称。河竹黙阿弥作の世話物。1854年(嘉永7)江戸河原崎座初演。隅田川物で、鳥目の侠客(4世市川小団次)が梅若を殺すくだりが評判となる。
しのぶ‐の‐そで【忍の袖】
忍の衣の袖。また、忍の衣。源平盛衰記32「―をぞしぼられける」
⇒しのぶ【忍】
しのぶのやかしゅう【志濃夫廼舎歌集】‥シフ
歌集。5巻。橘曙覧たちばなあけみの草稿をその子井手今滋が編。1878年(明治11)刊。万葉・古今風を融合し、日常的な素材・用語をも嫌わぬ独特の歌風をもつ。
しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】‥ヂユウ
春日かすが饅頭の別称。
⇒しのぶ【忍】
しのぶ‐もじずり【忍捩摺】‥モヂ‥
(→)「しのぶずり」に同じ。伊勢物語「みちのくの―誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに」
⇒しのぶ【忍】
しのふら・う【忍ふらふ】シノフラフ
〔他四〕
(上二段活用のシノフに動作の反復・継続を表す接尾語フの付いた語)ずっとがまんする。堪えつづける。万葉集16「とねりをとこも―・ひかへらひ見つつ」
しのぶ‐わげ【忍髷】
女の髪の結い方。髷をつくり、その余りを二分して根の左右に小さい輪を作り、髷の根元に笄こうがいを横にさす。元文(1736〜1741)初年上方に始まり、のち江戸吉原の遊女の間にも流行。また、これにかたどった歌舞伎女形用のかつら。信夫しのぶ返し。しのぶ。通言総籬つうげんそうまがき「髪は―」
⇒しのぶ【忍】
じ‐の‐ぶん【地の文】ヂ‥
小説や戯曲などで、会話文以外の説明や描写の文。
しのべ‐だけ【忍竹】
①メダケの別称。
②(→)ヤダケ2に同じ。〈日葡辞書〉
じ‐のみ【地蚤】ヂ‥
キボシマルトビムシの別称。
しの‐め【篠芽】
①おそく生えて色が青く、味のにがいたけのこ。長間笋。〈倭名類聚鈔20〉
②篠芽竹。
⇒しのめ‐だけ【篠芽竹】
しのめ‐だけ【篠芽竹】
(→)ヤダケ2に同じ。
⇒しの‐め【篠芽】
しの‐や【篠屋】
篠で葺ふいた小屋。永久百首「旅人のかりの―に年くれて」
しの‐やき【志野焼】
桃山時代、美濃(岐阜県土岐市・可児かに市)で焼かれた陶器。白釉(長石釉)を厚く施し、下に鉄で簡素な文様を描いた絵志野や、鼠色をし象眼風の文様のある鼠志野などがある。茶碗や水指に秀作が多い。
じ‐のり【地乗り】ヂ‥
①駻馬かんばを乗りこなすこと。
②馬の足並みをそろえて進ませること。地足。
しの‐りゅう【志野流】‥リウ
香道の流派。志野宗信そうしんを祖とし、4代以降は蜂谷家が伝承、享保の頃家元制度を整える。志野流茶道の家元でもある。
シノロジー【Sinology】
中国学。
し‐の‐わかれ【死の別れ】
一方が死んで別れとなること。しにわかれ。宇治拾遺物語9「―にぞわかれにける」
シノワズリー【chinoiserie フランス】
中国趣味。17〜18世紀の頃、ヨーロッパで流行。東洋の題材をとりあげ、あるいは中国風を取り入れた芸術。
しの‐わた【篠綿】
綿糸紡績工程で、梳綿そめんによって作られた、撚よりのかからない太い綱状の繊維束。スライバー。
広辞苑 ページ 8920 での【○四の五の言う】単語。