複数辞典一括検索+![]()
![]()
ら(音節)🔗⭐🔉
ら
①舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ra〕
②平仮名「ら」は「良」の草体。片仮名「ラ」は「良」の最初の2画。
ら【拉】🔗⭐🔉
ら【拉】
拉丁ラテンの略。「―葡日対訳辞典」
ら【羅】🔗⭐🔉
ら【羅】
①薄く織った絹の布。うすぎぬ。うすもの。うすはた。源氏物語賢木「玉の軸―の表紙…も世になきさまに整へさせ給へり」
②㋐羅甸ラテンの略。
㋑羅馬ローマの略。
㋒羅馬尼亜ルーマニアの略。
㋓梵語の音訳字。「曼荼羅まんだら」
ラ【la イタリア】🔗⭐🔉
ラ【la イタリア】
〔音〕
①七音音階の第6階名。
②イ(A)音のイタリア音名。
ら(助動詞)🔗⭐🔉
ら
〔助動〕
完了・存続の助動詞「り」の未然形。万葉集15「西の御厩みまやの外とに立て―まし」
ら(助詞)🔗⭐🔉
ら
〔助詞〕
口調を整え、また親愛の意を表すために添える語。狂言、比丘貞「聞き馴れた声で表に物申すと有る。案内とはたそ―」
ら【等】🔗⭐🔉
ら【等】
〔接尾〕
①体言の下に付いて複数を表す。万葉集5「腐くたし棄つらむ絹綿―はも」。万葉集6「あま少女―が乗れる舟見ゆ」。「子供―」
②人を表す名詞や代名詞に付いて、親愛・謙譲・蔑視の気持を表す。ろ。允恭紀「我が愛めづる子―」。万葉集3「憶良―は今は罷らむ」
③おおよその状態を指し示す。万葉集16「弥彦いやひこ神のふもとに今日―もか」
④形容詞の語幹に付いて状態を表す名詞を作る。万葉集3「あなみにく賢さかし―をすと酒飲まぬ人をよく見ば」。「清―」
⑤方向・場所を示す。万葉集3「磯の上に根延ふ室むろの木見し人をいづ―と問はば語り告げむか」。古今和歌集秋「里は荒れて人はふりにし宿なれや庭も籬も秋の野―なる」。「ここ―で休もう」
ラーガ【rāga ヒンディー】🔗⭐🔉
ラーガ【rāga ヒンディー】
インド音楽における旋法。南インドでは72種、北インドでは10種を基本とするが、派生したものも多い。それぞれは、音階の構成音、固有の上行や下行の動き方、装飾のつけ方、気分などによって規定される。
ラーゲリ【lager' ロシア】🔗⭐🔉
ラーゲリ【lager' ロシア】
戦争捕虜・政治犯などの強制収容所。1920年代末からソ連で人民抑圧の機構となった。ラーゲル。
ラーゲルクヴィスト【Pär Fabian Lagerkvist】🔗⭐🔉
ラーゲルクヴィスト【Pär Fabian Lagerkvist】
スウェーデンの作家・詩人。表現派文学の提唱者で、人間性に潜む悪や蛮性、信仰と懐疑などをテーマとした。小説「こびと」「バラバ」「巫女」、詩集「黄昏の国」など。ノーベル賞。(1891〜1974)
ラーゲルレーヴ【Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf】🔗⭐🔉
ラーゲルレーヴ【Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf】
スウェーデンの女性作家。同国ネオロマン主義文学の代表格で、愛や善意、英雄的行為や神を賛美する幻想的小説のほか、児童文学でも名声を博した。「イェスタ=バーリング物語」「地主の家の物語」「エルサレム」、児童文学「ニルスの不思議な旅」など。ノーベル賞。(1858〜1940)
ラーケン【laken オランダ】🔗⭐🔉
ラーケン【laken オランダ】
近世、舶来のラシャの称。ランケン。
ラージ‐ヒル【large hill】🔗⭐🔉
ラージ‐ヒル【large hill】
スキーのジャンプ競技の一つ。また、それに用いるジャンプ台。旧称、90メートル級。→ノーマル‐ヒル
ラージプート【Rājpūt ヒンディー】🔗⭐🔉
ラージプート【Rājpūt ヒンディー】
インドのラージャスターン州を中心に歴史上大きな役割を果たしたカースト集団。クシャトリヤの後裔と自称。8〜13世紀、北インドに諸王朝を分立。イスラム勢力侵入によりその支配下に入ったが19世紀に藩王国を形成。
ラージャ【rāja 梵】🔗⭐🔉
ラージャ【rāja 梵】
(王の意)インドや東南アジアにおける王の称号。王の中にはマハーラージャ(大王)と称した者も多い。
ラージャグリハ【Rājagṛha 梵】🔗⭐🔉
ラージャグリハ【Rājagṛha 梵】
王舎城おうしゃじょうの梵語名。
ラージャスターン【Rajasthan】🔗⭐🔉
ラージャスターン【Rajasthan】
インド北西部の州。西はパキスタンに接する。農業が主要産業だが、工業も発展。鉱山資源も豊富。州都ジャイプールは観光都市としても有名。
ラージン【Stepan Timofeevich Razin】🔗⭐🔉
ラージン【Stepan Timofeevich Razin】
ロシアのドン‐カザーク反乱の指導者。1667年ヴォルガ沿岸地方で反乱を起こしたが、シンビルスクでツァーリ軍に敗れ、モスクワで処刑。ステンカ=ラージン。(1630頃〜1671)
ラード【lard】🔗⭐🔉
ラード【lard】
豚の脂肪から精製した半固体の料理用の油。豚脂。
ラードナー【Ring Lardner】🔗⭐🔉
ラードナー【Ring Lardner】
アメリカの作家・ジャーナリスト。庶民の生活を題材に苦いユーモアと諷刺の連作短編を多数執筆。小説「おれは駆け出し投手」など。(1885〜1933)
ラートブルッフ【Gustav Radbruch】🔗⭐🔉
ラートブルッフ【Gustav Radbruch】
ドイツの法律学者。新カント哲学を基礎として価値相対主義の法哲学を展開。また、相当因果関係論の研究により刑法理論の確立に貢献。著「法哲学」「法学入門」など。(1878〜1949)
ラードロフ【Vasilii Vasil'evich Radlov】🔗⭐🔉
ラードロフ【Vasilii Vasil'evich Radlov】
ロシアの東洋学者。中央アジア・トルコ系諸民族の言語・文学の研究にすぐれた業績を残す。主著「トルコ方言辞典稿」「北方トルコ諸部族民族文学資料」。(1837〜1918)
ラーナー【Karl Rahner】🔗⭐🔉
ラーナー【Karl Rahner】
ドイツのカトリック神学者。第二ヴァチカン公会議の神学顧問。「匿名のキリスト者」論で、キリスト教会に属さない人々もキリストによる救いに参与することを説く。(1904〜1984)
ラーベ【Wilhelm Raabe】🔗⭐🔉
ラーベ【Wilhelm Raabe】
ドイツの作家。写実主義の小説「雀横丁年代記」など。(1831〜1910)
ラーマーヤナ【Rāmāyaṇa 梵】🔗⭐🔉
ラーマーヤナ【Rāmāyaṇa 梵】
古代インドの大叙事詩。マハーバーラタと並び称される。ヴァールミーキ作と伝える。コーサラ国の王子ラーマが羅刹らせつ王ラーヴァナに掠奪された妃シーターを奪回するという筋。全7編。現存のものは2世紀末頃の成立。
ラーマ‐ごせい【ラーマ五世】🔗⭐🔉
ラーマ‐ごせい【ラーマ五世】
(Rama)タイ国王チュラロンコンのこと。
ラーマン【S. M. Rahmān】🔗⭐🔉
ラーマン【S. M. Rahmān】
⇒ラフマーン
ラーメン【拉麺】🔗⭐🔉
ラーメン【拉麺】
(中国語から)中国風に仕立てた汁そば。小麦粉に鶏卵・塩・梘水かんすい・水を入れてよく練り、そばのようにしたものを茹ゆで、スープに入れたもの。支那そば。中華そば。
ラーメン【Rahmen ドイツ】🔗⭐🔉
ラーメン【Rahmen ドイツ】
〔建〕材と材とを結合して組み立てる構造物すなわち骨組の一形式。節点がすべて剛節すなわち変形しにくい結合から成る。現代の建築物、特に鉄筋コンクリートの骨組はほとんどこの種の構造。剛節架構。↔トラス。
⇒ラーメン‐きょう【ラーメン橋】
ラーメン‐きょう【ラーメン橋】‥ケウ🔗⭐🔉
ラーメン‐きょう【ラーメン橋】‥ケウ
主桁しゅげたがラーメン構造の橋。
ラーメン橋
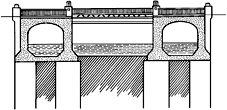 ⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】
⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】
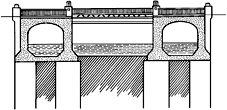 ⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】
⇒ラーメン【Rahmen ドイツ】
ラーユ【辣油】🔗⭐🔉
ラーユ【辣油】
(中国語)植物油に唐辛子の辛味をうつした調味料。中国料理の調味に用いる。
ラーロウ【臘肉】🔗⭐🔉
ラーロウ【臘肉】
(中国語)豚肉の塩漬を干したり燻製くんせいにしたりしたもの。
ラーワルピンディー【Rawalpindi】🔗⭐🔉
ラーワルピンディー【Rawalpindi】
パキスタン北部の都市。1959〜66年暫定首都。近郊のタキシラーはガンダーラ文化の遺跡。人口141万(1998)。→イスラマバード
らい【来】🔗⭐🔉
らい【来】
①これから来る時。次にくること。つぎの。「―学年」
②このかた。そののち。「昨年―」
らい【来】(姓氏)🔗⭐🔉
らい【雷】🔗⭐🔉
らい【雷】
かみなり。いかずち。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライガヲチカカル」
らい【頼】(姓氏)🔗⭐🔉
らい【籟】🔗⭐🔉
らい【籟】
三つの穴のある笛。また、笛の音。
ら‐い【羅衣】🔗⭐🔉
ら‐い【羅衣】
うすものの着物。和漢朗詠集「ただ―の御香に染めたるのみあり」
ライ【lie】🔗⭐🔉
ライ【lie】
ゴルフで、ボールがグリーン以外で静止したとき、その場所や状態。
ライ【rye】🔗⭐🔉
ライ【rye】
ライ麦のこと。
🄰RAI🔗⭐🔉
RAI(ライ)
[Radiotelevisione Italiana イタリア]イタリア放送協会.
広辞苑に「ラ」で始まるの検索結果 1-46。もっと読み込む