複数辞典一括検索+![]()
![]()
くるる【枢】🔗⭐🔉
くるる【枢】
①扉の端の上下につけた突起(とまら)をかまちの穴(とぼそ)にさし込んで開閉させるための装置。くる。くろろ。拾玉集4「納殿の―の妻戸おし開けて」
②戸の桟。さる。
③回転装置の心棒。枢軸。
⇒くるる‐ぎ【枢木】
⇒くるる‐ど【枢戸】
すう‐き【枢機】🔗⭐🔉
すう‐き【枢機】
(「枢」は戸のくるる、「機」は弩いしゆみの引金)
①[易経繋辞上]物事の極めて重要なところ。かなめ。肝要。枢要。
②重要な政務。「国政の―」
⇒すうき‐きょう【枢機卿】
すうき‐きょう【枢機卿】‥キヤウ🔗⭐🔉
すうき‐きょう【枢機卿】‥キヤウ
(cardinalis ラテン)ローマ教皇の最高顧問。枢機卿会を構成し、教皇選挙権を持ち、教会行政の要職などに任ずる。司教中から選出。すうきけい。カーディナル。
⇒すう‐き【枢機】
すう‐じく【枢軸】‥ヂク🔗⭐🔉
すう‐じく【枢軸】‥ヂク
(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)
①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。
②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。
⇒すうじく‐こく【枢軸国】
すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥🔗⭐🔉
すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥
日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2
⇒すう‐じく【枢軸】
すう‐しょう【枢相】‥シヤウ🔗⭐🔉
すう‐しょう【枢相】‥シヤウ
枢密院議長の略称。
すう‐ふ【枢府】🔗⭐🔉
すう‐ふ【枢府】
枢密院の異称。
すう‐みつ【枢密】🔗⭐🔉
すう‐みつ【枢密】
枢要の機密。政治の機密。
⇒すうみつ‐いん【枢密院】
⇒すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】
すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン🔗⭐🔉
すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン
君主の最高諮問機関。
①唐では宦官が機密をつかさどった官庁。五代・宋・元は文官を用い、軍政をつかさどった。行政の中書省と相対し、軍事権を統轄。明代に廃止。
②明治憲法下で、重要な国務および皇室の大事に関し、天皇の諮詢しじゅんに応えることを任務とした合議機関。議長・副議長・顧問官で組織し、国務大臣および成年以上の親王も列し得た。1888年(明治21)設置。1947年廃止。枢府。中江兆民、警世放言「―は伊藤侯総理大臣たりし時の遺物なり」
⇒すう‐みつ【枢密】
すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン🔗⭐🔉
すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン
枢密院2を構成した顧問官。
⇒すう‐みつ【枢密】
すう‐む【枢務】🔗⭐🔉
すう‐む【枢務】
枢要な政務。機密の事務。
すう‐よう【枢要】‥エウ🔗⭐🔉
すう‐よう【枢要】‥エウ
かんじんなところ。かなめ。「―な地位」
⇒すうよう‐とく【枢要徳】
すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥🔗⭐🔉
すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥
〔哲〕(cardinal virtues)もろもろの徳を集大成する最も根本的な徳。アリストテレス以来、賢慮・勇気・節制・正義の四徳が枢要徳として重視され、キリスト教、特にカトリシズムでは、信仰・愛・希望の神学的徳(対神徳)が枢要徳を完成するとしている。元徳。主徳。
⇒すう‐よう【枢要】
と‐ぼそ【枢・扃】🔗⭐🔉
と‐ぼそ【枢・扃】
(「戸臍とほぞ」の意)
①開き戸のかまちに設けた、枢とまらを受ける穴。俗に、「とまら」とも。〈倭名類聚鈔10〉
②転じて、扉または戸の称。平家物語灌頂「甍いらかやぶれては霧不断の香をたき、―おちては月常住の灯をかかぐ」
と‐まら【枢】🔗⭐🔉
と‐まら【枢】
(ト(戸)マラ(陰茎)の意)開き戸の回転軸として、扃とぼそに差し入れる突起部。〈倭名類聚鈔10〉
[漢]枢🔗⭐🔉
枢 字形
 筆順
筆順
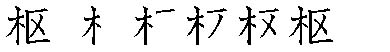 〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕
[樞] 字形
〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕
[樞] 字形
 〔木部11画/15画/6068・5C64〕
〔音〕スウ(慣) シュ(漢)
〔訓〕とぼそ・くるる
[意味]
①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」
②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」
[解字]
形声。「木」+音符「
〔木部11画/15画/6068・5C64〕
〔音〕スウ(慣) シュ(漢)
〔訓〕とぼそ・くるる
[意味]
①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」
②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」
[解字]
形声。「木」+音符「 」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。
」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。
 筆順
筆順
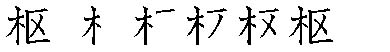 〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕
[樞] 字形
〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕
[樞] 字形
 〔木部11画/15画/6068・5C64〕
〔音〕スウ(慣) シュ(漢)
〔訓〕とぼそ・くるる
[意味]
①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」
②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」
[解字]
形声。「木」+音符「
〔木部11画/15画/6068・5C64〕
〔音〕スウ(慣) シュ(漢)
〔訓〕とぼそ・くるる
[意味]
①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」
②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」
[解字]
形声。「木」+音符「 」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。
」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。
広辞苑に「枢」で始まるの検索結果 1-20。