複数辞典一括検索+![]()
![]()
き【柵・城】🔗⭐🔉
き【柵・城】
敵を防ぐための構築物。垣や堀など。城塞。垂仁紀「稲を積みて―を作る」。播磨風土記「―を掘りし処は」
き‐か・う【柵養ふ】‥カフ🔗⭐🔉
き‐か・う【柵養ふ】‥カフ
〔他四〕
未詳。囲いの中に飼うの意か。また、その意の名詞か。また、柵の役人の指揮に従う意、陸奥の国にあった地名とも。斉明紀「―・ふの蝦夷九人」
き‐の‐へ【柵戸】🔗⭐🔉
き‐の‐へ【柵戸】
古代、蝦夷えぞに備えるための城柵に付属させた民戸。屯田兵の一種。きへ。さくこ。
くべ【垣・柵】🔗⭐🔉
くべ【垣・柵】
(奈良時代にはクヘ)かき。さく。万葉集14「―越しに麦食はむ小馬の」
さく【柵】🔗⭐🔉
さく【柵】
①角材または丸太をまばらに立てて貫ぬきを通し、土地の境界・区画などに設けるかこい。
柵
撮影:関戸 勇
 ②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。
③しがらみ。
②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。
③しがらみ。
 ②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。
③しがらみ。
②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。
③しがらみ。
さく‐いたべい【柵板塀】🔗⭐🔉
さく‐いたべい【柵板塀】
柵の裏に板を張った塀。
柵板塀


さくじょう‐そしき【柵状組織】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
さくじょう‐そしき【柵状組織】‥ジヤウ‥
海綿状組織とともに葉肉を構成する重要な組織。柱状の細胞が密接してほとんど間隙をつくらずに並ぶ。葉の上面の表皮下にあり、葉緑体を含み、光合成を行う。
さく‐の‐き【柵の木】🔗⭐🔉
さく‐の‐き【柵の木】
(→)「さく(柵)」に同じ。
さく‐もん【柵門】🔗⭐🔉
さく‐もん【柵門】
城柵の入口の門。
さく‐やらい【柵矢来】🔗⭐🔉
さく‐やらい【柵矢来】
木の柵で作った矢来。
さく‐るい【柵塁】🔗⭐🔉
さく‐るい【柵塁】
木柵を立てて構えたとりで。
しがらみ【柵】🔗⭐🔉
しがらみ【柵】
①水流を塞せきとめるために杭くいを打ちならべて、これに竹や木を渡したもの。万葉集2「あすか川―渡しせかませば」
柵
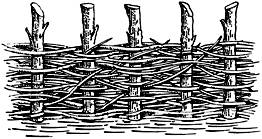 ②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」
②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」
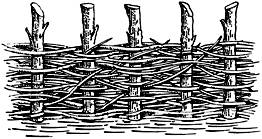 ②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」
②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」
しがら・む【柵む】🔗⭐🔉
しがら・む【柵む】
〔他四〕
①からみつける。古今和歌集秋「秋萩を―・みふせて鳴く鹿の」
②しがらみを設けて水流を塞せきとめる。狭衣物語2「涙川流るる跡はそれながら―・みとむる面影ぞなき」
[漢]柵🔗⭐🔉
柵 字形
 〔木部5画/9画/2684・3A74〕
〔音〕サク(漢)
〔訓〕しがらみ
[意味]
①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」
②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。
▷[
〔木部5画/9画/2684・3A74〕
〔音〕サク(漢)
〔訓〕しがらみ
[意味]
①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」
②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。
▷[ ]は異体字。
]は異体字。
 〔木部5画/9画/2684・3A74〕
〔音〕サク(漢)
〔訓〕しがらみ
[意味]
①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」
②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。
▷[
〔木部5画/9画/2684・3A74〕
〔音〕サク(漢)
〔訓〕しがらみ
[意味]
①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」
②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。
▷[ ]は異体字。
]は異体字。
広辞苑に「柵」で始まるの検索結果 1-14。