複数辞典一括検索+![]()
![]()
うみ‐まつ【海松】🔗⭐🔉
うみ‐まつ【海松】
①海辺の松。
②ウミカラマツの別称。
③ミルの異称。土佐日記「海人あまならば―をだに引かましものを」
○海も見えぬに船用意うみもみえぬにふなようい
事を早まってすることのたとえ。浄瑠璃、日本振袖始「なんぞ今から―」
⇒うみ【海】
みる【海松・水松】🔗⭐🔉
みる【海松・水松】
海産の緑藻。アオサ藻綱ミル目の一種。浅海の岩石に着生する。全体に濃緑色(梅松色)を呈し、直径3ミリメートルくらいの円柱形肉質の幹が多数に二股ふたまた分岐する。高さ約20センチメートル。ミル属には、他にナガミル・クロミル・タマミルなどがある。食用。みるめ。みるな。みるぶさ。またみる。〈[季]春〉。万葉集6「沖辺には深―採り」→みるいろ(海松色)
みる
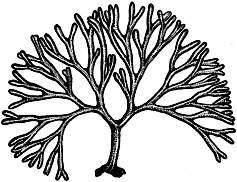
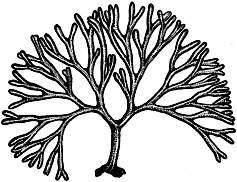
みる‐いろ【海松色・水松色】🔗⭐🔉
みる‐いろ【海松色・水松色】
①黒みを帯びた萌葱もえぎ色。とくさいろ。
Munsell color system: 9Y4/3
②襲かさねの色目。山科流では表は萌葱、裏は青。または、表は黒萌葱、裏は白。
みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ🔗⭐🔉
みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ
(→)ミルクイガイの別称。
○見る影も無いみるかげもない
以前の面影がすっかり変わって、見るに堪えないさまである。みすぼらしい。
⇒みる【見る・視る・観る】
みる‐くい【海松食・水松食】‥クヒ🔗⭐🔉
みる‐くい【海松食・水松食】‥クヒ
(→)ミルクイガイのこと。浄瑠璃、国性爺合戦「人の―わすれ貝」
⇒みるくい‐がい【海松食貝】
みるくい‐がい【海松食貝】‥クヒガヒ🔗⭐🔉
みるくい‐がい【海松食貝】‥クヒガヒ
バカガイ科の二枚貝。殻はやや長方形で、殻長約10センチメートル。黒褐色の殻皮をかぶり、それが長い水管をも覆う。水管の先にミルが着生し、それを食うように見えるので名づけられたという。日本各地の内湾浅海に広く産し、主に水管部を食用。特に鮨種すしだねとして好まれる。みる貝。ミルクイ。
⇒みる‐くい【海松食・水松食】
みる‐ちゃ【海松茶】🔗⭐🔉
みる‐ちゃ【海松茶】
海松みる色を帯びた茶色。日本永代蔵2「ひとつは―染にせし事」
みる‐ぶさ【海松房・水松房】🔗⭐🔉
みる‐ぶさ【海松房・水松房】
枝が房になって生えた海松みる。髪そぎ・鬢びんそぎの儀に用いられた。〈[季]春〉
○見る間にみるまに
見ている少しの間にも。またたく間に。「川の水位が―上昇した」
⇒みる【見る・視る・観る】
みる‐め【海松布・水松布】🔗⭐🔉
みる‐め【海松布・水松布】
(「め」は海藻の意)(→)海松みるに同じ。歌では多く「見る目」にかけて用いる。〈[季]春〉。古今和歌集恋「はやきせに―おひせば」
○見る目嗅ぐ鼻みるめかぐはな
①閻魔えんまの庁にあるという、男女の人頭を幢はたほこの上にのせたもの。よく亡者の善悪を判別するという。
②世間のうるさい耳目をいう。
⇒みる‐め【見る目】
広辞苑に「海松」で始まるの検索結果 1-9。