複数辞典一括検索+![]()
![]()
せ【瀬・湍】🔗⭐🔉
せ【瀬・湍】
①川などの浅くて徒歩で渡れるところ。あさせ。万葉集6「神名火かむなびの淵は浅あせにて―にかなるらむ」
②水流の急なところ。はやせ。〈倭名類聚鈔1〉。「―を乗り切る」
③(渡るための狭い所の意から)
㋐事に出あう時。折。場合。後撰和歌集恋「涙川嬉しき―にも流れあふやと」。「浮かぶ―がない」「又の逢う―」
㋑その場所。立場。新古今和歌集夏「聞かずともここを―にせむ時鳥」。「立つ―がない」
㋒点。ふし。源氏物語柏木「憂きにもうれしき―はまじり侍りけり」
せ‐おと【瀬音】🔗⭐🔉
せ‐おと【瀬音】
川が浅瀬を流れる水音。せせらぎ。
せ‐がえ【瀬替】‥ガヘ🔗⭐🔉
せ‐がえ【瀬替】‥ガヘ
河川の人工的な流路変更のこと。戦国時代末期から江戸時代にかけて行われた治水の一工法。江戸初期、伊奈備前守が行なった利根川・荒川の瀬替がその代表例。つけかえ。
せ‐がしら【瀬頭】🔗⭐🔉
せ‐がしら【瀬頭】
瀬のはじまる所。ゆるやかな流れから波がたちはじめて瀬になりかかる所。太平記19「川の―に打ちのぞみ」↔瀬尻
せがわ【瀬川】‥ガハ🔗⭐🔉
せがわ‐きくのじょう【瀬川菊之丞】‥ガハ‥🔗⭐🔉
せがわ‐きくのじょう【瀬川菊之丞】‥ガハ‥
歌舞伎俳優。屋号、浜村屋。各代俳名は路考。
①(初代)大坂で初演。江戸で所作事に成功し盛名を謳われた。(1693〜1749)
②(2代)初代の養子。王子路考と呼ばれ美貌。(1741〜1773)
③(5代)3代の孫。通称、多門路考。当り役は「五大力」の小万。(1802〜1832)
④(6代)1932年に前進座に参加、翌年襲名。立役から女形、老け役まで広く活躍。(1907〜1976)
⇒せがわ【瀬川】
せがわ‐じょこう【瀬川如皐】‥ガハ‥カウ🔗⭐🔉
せがわ‐じょこう【瀬川如皐】‥ガハ‥カウ
歌舞伎脚本作者。
①(初世)大坂の人。3代瀬川菊之丞の兄。江戸へ下り作者に転じた。(1739〜1794)
②(3世)俗称、吉兵衛。糶せり呉服商であったが、5世鶴屋南北の門に入り、1850年(嘉永3)襲名。代表作「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」など。(1806〜1881)
→文献資料[与話情浮名横櫛(源氏店の場)]
⇒せがわ【瀬川】
せがわ‐ぼうし【瀬川帽子】‥ガハ‥🔗⭐🔉
せがわ‐ぼうし【瀬川帽子】‥ガハ‥
女性の帽子の一つ。享保(1716〜1736)の頃、大坂の初代瀬川菊之丞が屋敷女中の扮装に用い始めてから流行したという。
⇒せがわ【瀬川】
せ‐ぎり【瀬切り】🔗⭐🔉
せ‐ぎり【瀬切り】
水が瀬をおしきって流れ行くこと。また、その所。早瀬。古今和歌集六帖1「立田川、滝の―に祓へつつ」
せ‐ぎ・る【瀬切る】🔗⭐🔉
せ‐ぎ・る【瀬切る】
〔他四〕
水の流れをさえぎりとめる。また、一般に、さえぎる。椿説弓張月後編「路を―・りて」
○瀬越しをかけるせごしをかける🔗⭐🔉
○瀬越しをかけるせごしをかける
困難な目にあわせる。責める。
⇒せ‐ごし【瀬越し】
せ‐ご・す【瀬越す】
〔他四〕
責める。いじめる。浄瑠璃、新版歌祭文「何もかも吐き出しをろと―・す後ろに」
せこ‐だいこ【勢子太鼓】
勢子が鳥獣を駆りたてるために打ち鳴らす太鼓。
せこ‐なわ【勢子縄】‥ナハ
勢子が鳥獣を駆りたてるとき用いる縄。夫木和歌抄36「―に引きこめらるる鹿ばかり」
せ‐ご・す【瀬越す】🔗⭐🔉
せ‐ご・す【瀬越す】
〔他四〕
責める。いじめる。浄瑠璃、新版歌祭文「何もかも吐き出しをろと―・す後ろに」
せ‐ごり【瀬垢離】🔗⭐🔉
せ‐ごり【瀬垢離】
川瀬でする垢離。治承二年二十二番歌合「岩田川―に身をばすすげども」
せしめ‐うるし【瀬〆漆】🔗⭐🔉
せしめ‐うるし【瀬〆漆】
伐採し水に浸しておいた漆の枝から掻き取った漆液。水分が少なくねばりが強い。石漆。
せ‐じり【瀬尻】🔗⭐🔉
せ‐じり【瀬尻】
瀬のすえ。瀬が終わって、淵や淀に移ろうとする所。↔瀬頭せがしら
せ‐ぜ【瀬瀬】🔗⭐🔉
せ‐ぜ【瀬瀬】
①かずかずの瀬。多くの瀬。万葉集13「あすか川―の玉藻のうちなびき」
②折々おりおり。源氏物語早蕨「身を投げむ涙の川に沈みても恋しき―に忘れしもせじ」
ぜぜ‐まん【瀬瀬幔】🔗⭐🔉
ぜぜ‐まん【瀬瀬幔】
台所などで用いる粗末な幔幕。
せた【瀬田】🔗⭐🔉
せた【瀬田】
(古くは「勢田」「勢多」とも書く)滋賀県大津市の地名。瀬田川の左岸にあり、同市石山と対する。東海道・中山道から京都に至る要地で、古来しばしば戦場となった。元官幣大社建部神社がある。「瀬田の夕照」は近江八景の一つ。→瀬田の橋
せ‐だえ【瀬絶え】🔗⭐🔉
せ‐だえ【瀬絶え】
瀬を流れる水が絶えること。千載和歌集恋「すみなれし佐野の中川―して」
せた‐おり【瀬田折】‥ヲリ🔗⭐🔉
せた‐おり【瀬田折】‥ヲリ
着物の左右の褄つまを取って、前で帯に挟むこと。あずまからげ。せたからげ。
せた‐からげ【瀬田紮げ】🔗⭐🔉
せた‐からげ【瀬田紮げ】
(→)瀬田折せたおりに同じ。
せた‐がわ【瀬田川】‥ガハ🔗⭐🔉
せた‐がわ【瀬田川】‥ガハ
滋賀県大津市瀬田で琵琶湖から流れ出る川。下流は宇治川、さらに淀川となる。
瀬田川
撮影:的場 啓


せた‐しじみ【瀬田蜆】🔗⭐🔉
せた‐しじみ【瀬田蜆】
シジミ科の二枚貝。琵琶湖・瀬田川など琵琶湖水系の特産種。→しじみ
せた‐の‐からはし【瀬田の唐橋】🔗⭐🔉
せた‐の‐からはし【瀬田の唐橋】
(その様式が唐風だからいう)(→)「瀬田の橋」の別称。
せた‐の‐ながはし【瀬田の長橋】🔗⭐🔉
せた‐の‐ながはし【瀬田の長橋】
(→)「瀬田の橋」の別称。新古今和歌集雑「幾世へぬらむ―」
せた‐の‐はし【瀬田の橋】🔗⭐🔉
せた‐の‐はし【瀬田の橋】
滋賀県瀬田川に架かる橋。大津市瀬田橋本町から、同市鳥居川町に通ずる。関東から京都への入口に当たり、古来、京都を守る要衝。宇治・山崎の橋と共に有名。瀬田の唐橋。瀬田の長橋。
瀬田唐橋
撮影:山梨勝弘


せ‐つき【瀬付き】🔗⭐🔉
せ‐つき【瀬付き】
回遊魚が島嶼や暗礁など餌が多い所に留まること。また、川魚では魚が産卵場に集まること。せづき。
せ‐づり【瀬釣り】🔗⭐🔉
せ‐づり【瀬釣り】
川の瀬で、アユ・ウグイ・ヤマメなどを釣ること。
せ‐と【瀬戸】🔗⭐🔉
せ‐と【瀬戸】
(「狭せ門と」の意)
①幅の狭い海峡。潮汐の干満によって激しい潮流を生ずる。万葉集12「室の浦の―の崎なる鳴島なきしまの」
②(→)「せとぎわ」2の略。「生死の―に立つ」
せと【瀬戸】(地名)🔗⭐🔉
せと【瀬戸】
①愛知県北西部の市。付近の丘陵に陶土を産し、燃料の黒松が多いので、陶祖加藤景正以来瀬戸焼の名を全国に馳せた。日本最大の陶磁器工業地として陶都の称がある。人口13万2千。
②「せともの」「せとやき」の略。
せと‐うち【瀬戸内】🔗⭐🔉
せと‐うち【瀬戸内】
①瀬戸内海およびその沿岸地方。海上交通が古くから発達し、沿岸に港町が栄えた。
②岡山県南東部の市。瀬戸内海に面し、島嶼が点在する。農業・漁業が産業の中心。人口3万9千。
せと‐おおはし【瀬戸大橋】‥オホ‥🔗⭐🔉
せと‐おおはし【瀬戸大橋】‥オホ‥
本州四国連絡橋の一つ。岡山県倉敷市児島から塩飽しわく諸島の櫃石ひついし島・与島などを経て香川県坂出市まで9.4キロメートルの海峡部を結ぶ橋。下津井瀬戸大橋、南・北備讃瀬戸大橋など道路・鉄道併用の6橋から構成。1988年完成。
瀬戸大橋(倉敷)
撮影:山梨勝弘
 瀬戸大橋(坂出)
撮影:山梨勝弘
瀬戸大橋(坂出)
撮影:山梨勝弘
 ⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】
⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】
 瀬戸大橋(坂出)
撮影:山梨勝弘
瀬戸大橋(坂出)
撮影:山梨勝弘
 ⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】
⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】
せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥🔗⭐🔉
せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥
瀬戸内海を横断し、岡山・香川両県を結ぶJR本四備讃線の通称。茶屋町・宇多津間、全長31.0キロメートル。
⇒せと‐おおはし【瀬戸大橋】
せと‐からつ【瀬戸唐津】🔗⭐🔉
せと‐からつ【瀬戸唐津】
白色の長石釉のかかった唐津焼の一種。白釉が瀬戸焼の陶器に似ることからの称という。せとがらつ。
せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ🔗⭐🔉
せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ
①瀬戸と海とのさかい。
②安危・成敗・生死のわかれる、さしせまった場合。運命のわかれめ。浄瑠璃、大塔宮曦鎧「この―に思案どころか」。「命の―」
せと‐ぐち【瀬戸口】🔗⭐🔉
せと‐ぐち【瀬戸口】
瀬戸の入口。山家集「―にたけるうしほの大淀み」
せと‐ぐろ【瀬戸黒】🔗⭐🔉
せと‐ぐろ【瀬戸黒】
桃山時代に美濃窯で作られた漆黒の茶碗。瀬戸黒茶碗。天正てんしょう黒。
せと‐ないかい【瀬戸内海】🔗⭐🔉
せと‐ないかい【瀬戸内海】
本州と四国・九州とに囲まれた内海。沖積世初期に中央構造線の北縁に沿う陥没帯が海となったもの。友ヶ島水道(紀淡海峡)・鳴門海峡・豊予海峡・関門海峡によってわずかに外洋に通じ、大小約3000の島々が散在し、天然の美観に恵まれ、国立公園に指定されている。沿岸には良港が多く、古くから海上交通が盛ん。
瀬戸内海夕景
撮影:山梨勝弘
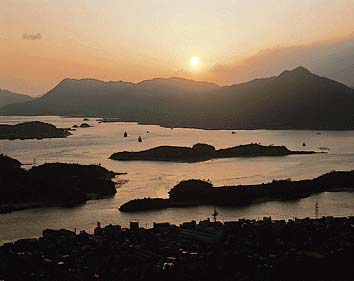 ⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】
⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】
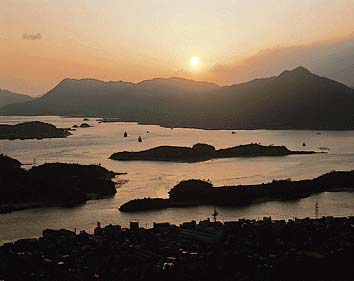 ⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】
⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】
せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン🔗⭐🔉
せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン
中国地方と四国の瀬戸内海沿岸および和歌山県の紀淡海峡に臨む地区などを包含する国立公園。リアス海岸と多島海に特色。
⇒せと‐ないかい【瀬戸内海】
せと‐ひき【瀬戸引】🔗⭐🔉
せと‐ひき【瀬戸引】
鉄製の鍋などの内部に琺瑯ほうろうを引くこと。また、そのもの。琺瑯引。
せと‐もの【瀬戸物】🔗⭐🔉
せと‐もの【瀬戸物】
①(→)瀬戸焼に同じ。
②陶磁器の総称。「―の茶碗」
せと‐やき【瀬戸焼】🔗⭐🔉
せと‐やき【瀬戸焼】
愛知県瀬戸市およびその付近から産出する陶磁器の総称。平安中期頃から灰釉かいゆう陶器を焼成したが、鎌倉時代に加藤景正(初代藤四郎)が宋に渡って陶法を伝来し、瀬戸焼を開いたと伝える。この時代には灰釉はいぐすりのほか飴色の釉うわぐすりを、室町時代には天目釉てんもくゆうを多く用いた。江戸時代中頃に衰退したのち、文化(1804〜1818)年間、加藤民吉が肥前に赴き磁器の製法を将来。以後、陶器に代わって磁器が瀬戸焼の主流を占め、再び活気を呈した。なお、近世には美濃南東部で焼かれたものを含めて瀬戸焼と呼んだ。せともの。せと。
せ‐どり【瀬取】🔗⭐🔉
せ‐どり【瀬取】
親船の積荷を小船に移し取ること。
せ‐ぶし【瀬伏し】🔗⭐🔉
せ‐ぶし【瀬伏し】
川の瀬にひそむこと。永久百首「―の鮎あゆのゆく方やなき」
せ‐ぶみ【瀬踏み】🔗⭐🔉
せ‐ぶみ【瀬踏み】
①瀬の深さを、足を踏み入れて測ること。源平盛衰記35「物の具ぬぎて―して、川の案内を試みるべし」
②転じて、前もってためしてみること。浮世草子、鬼一法眼虎の巻「こよひ五条へ―につかはし」。「―をしてから実行する」
せ‐ぼし【瀬乾し】🔗⭐🔉
せ‐ぼし【瀬乾し】
川の流れを堰き止めて、下流の水を涸らし、魚をとる漁法。堰せき乾し。
せ‐ほろぼし【瀬滅ぼし】🔗⭐🔉
せ‐ほろぼし【瀬滅ぼし】
川に仕掛けた簗やなが、魚をさんざんとったあと朽ちて崩れること。転じて、罪ほろぼし。浄瑠璃、釈迦如来誕生会「命の瀬踏み―、思ひ知れや」
せ‐まくら【瀬枕】🔗⭐🔉
せ‐まくら【瀬枕】
①(その形状から)川の早瀬の波が物にあたって高くなったところ。万代和歌集雑「寒き夜に―見えて澄める月影」
②(西鶴の作品で)船中で寝る意。好色一代男3「舟子の―、忍女ある所ぞかし」
せ‐まつり【瀬祭】🔗⭐🔉
せ‐まつり【瀬祭】
漁師の行う海神祭。祭の作法と祭日とは地方により異なる。竜宮祭。潮祭。浦祭。
せみ‐の‐おがわ【瀬見の小川】‥ヲガハ🔗⭐🔉
せみ‐の‐おがわ【瀬見の小川】‥ヲガハ
京都市左京区下鴨の東部を流れる細流。賀茂御祖みおや神社糺森ただすのもりの南方で賀茂川に入る。瀬見は川の瀬の見える浅川の意。今、「蝉の小川」とする。石川の瀬見の小川。
瀬見の小川
撮影:的場 啓


せ‐むし【瀬虫】🔗⭐🔉
せ‐むし【瀬虫】
「いさごむし」の別称。
せやま‐りゅう【瀬山流】‥リウ🔗⭐🔉
せやま‐りゅう【瀬山流】‥リウ
日本舞踊の一流派。安永・天明頃に上方で活躍した瀬山七左衛門を祖とする。
[漢]瀬🔗⭐🔉
瀬 字形
 筆順
筆順
 〔水(氵・氺)部16画/19画/常用/3205・4025〕
[
〔水(氵・氺)部16画/19画/常用/3205・4025〕
[ ] 字形
] 字形
 〔水(氵・氺)部16画/19画〕
〔音〕ライ(呉)(漢)
〔訓〕せ
[意味]
川や潮の流れが急な所。せ。
[解字]
形声。「水」+音符「
〔水(氵・氺)部16画/19画〕
〔音〕ライ(呉)(漢)
〔訓〕せ
[意味]
川や潮の流れが急な所。せ。
[解字]
形声。「水」+音符「 」。
」。
 筆順
筆順
 〔水(氵・氺)部16画/19画/常用/3205・4025〕
[
〔水(氵・氺)部16画/19画/常用/3205・4025〕
[ ] 字形
] 字形
 〔水(氵・氺)部16画/19画〕
〔音〕ライ(呉)(漢)
〔訓〕せ
[意味]
川や潮の流れが急な所。せ。
[解字]
形声。「水」+音符「
〔水(氵・氺)部16画/19画〕
〔音〕ライ(呉)(漢)
〔訓〕せ
[意味]
川や潮の流れが急な所。せ。
[解字]
形声。「水」+音符「 」。
」。
広辞苑に「瀬」で始まるの検索結果 1-57。