複数辞典一括検索+![]()
![]()
くるし・い【苦しい】🔗⭐🔉
くるし・い【苦しい】
〔形〕[文]くる・し(シク)
身心に苦痛を感じるさま、または、そのような感じを起こさせる事物の状態を表す。
①身体が痛んでつらい。天智紀「み吉野の吉野の鮎鮎こそは島傍しまへも良えきえ―・しゑ水葱なぎの下もと芹の下もと吾は―・しゑ」。竹取物語「翁心地悪しく―・しき時も、この子を見れば―・しき事も止みぬ」。「胸が―・い」
②心がもだえて安らかでない。せつない。悩ましい。万葉集12「早来ませ君待たば―・しも」。拾遺和歌集雑恋「わがせこを恋ふるも―・し」。「―・い恋」
③心配である。心づかいがされる。源氏物語紅葉賀「なにくれと宣ふも似げなく人や見つけむと―・しきを」
④(多く打消の語を伴って)差しつかえがある。はばかりがある。不都合だ。平家物語7「其人ならば―・しかるまじ。いれ申せ」。「―・しうない、近う近う」
⑤むずかしい。困難である。難儀である。落窪物語3「脚のけ起りて、装束することの―・しければなん」。「優勝は―・い」
⑥その場をやり過ごすのに苦労している。つらい。困窮している。苦境にある。源氏物語紅葉賀「いと見奉り分き難げなるを宮いと―・しと思せど」。「財政が―・い」「―・い言いわけ」
⑦動詞連用形の下に付いて、快くない、いとわしい、しにくい、などの意を表す。多く「ぐるしい」と濁音化する。源氏物語真木柱「あざやかなる御直衣などもえ取りあへたまはでいと見―・し」。「聞き―・い」
⇒苦しい時の神頼み
○苦しい時の神頼みくるしいときのかみだのみ
ふだん神を拝まない者が、災難にあったり困りぬいたりする時にだけ、神の助けをたよること。「叶わぬ時の神頼み」「困った時の神頼み」などとも。
⇒くるし・い【苦しい】
○苦しい時の神頼みくるしいときのかみだのみ🔗⭐🔉
○苦しい時の神頼みくるしいときのかみだのみ
ふだん神を拝まない者が、災難にあったり困りぬいたりする時にだけ、神の助けをたよること。「叶わぬ時の神頼み」「困った時の神頼み」などとも。
⇒くるし・い【苦しい】
くるしき‐うみ【苦しき海】
(→)苦海くかいに同じ。この世。現世。金葉和歌集雑「阿弥陀仏と唱ふる声を楫にてや―を漕ぎ離るらむ」
くるしび【苦しび】
苦しみ。宇津保物語吹上下「地獄の―をも救ひ申さむ」
くるし・ぶ【苦しぶ】
〔自四〕
(→)「くるしむ」(五段)に同じ。金光明最勝王経平安初期点「辞はばかり苦クルシブこと無かれ」
くるしま‐かいきょう【来島海峡】‥ケフ
愛媛県今治市の高縄半島と芸予諸島の大島との間にある水道。燧灘ひうちなだと安芸灘を結ぶ要路だが、潮流が急で、瀬戸内海有数の難所。
くるし‐まぎれ【苦し紛れ】
苦しさのあまりすること。「―の答弁」
くるしみ【苦しみ】
苦しむこと。なやみ。難儀。方丈記「心身の―を知れれば」。「―に耐える」「生きる―」
くるし・む【苦しむ】
[一]〔自五〕
①苦しいと思う。方丈記「―・む時は休めつ」。「腰の痛みに―・む」
②窮する。困る。「解釈に―・む」
③心力を労する。骨折る。「会社の再建に―・む」
[二]〔他下二〕
⇒くるしめる(下一)
くるし・める【苦しめる】
〔他下一〕[文]くるし・む(下二)
苦しませる。困らせる。いじめる。源氏物語少女「学問などに身を―・めん事は、いと遠くなん覚ゆべかめる」。「敵を―・める」
くるす【来栖】
姓氏の一つ。
⇒くるす‐さぶろう【来栖三郎】
クルス【cruz ポルトガル】
①(キリシタン用語)十字架。十字。こんてむつすむん地「―にかかり給ふ御姿を目前にすゑ奉れ」
②十字架にかたどった紋章。
くるす‐さぶろう【来栖三郎】‥ラウ
外交官。横浜市生れ。東京高商卒。日独伊三国同盟調印時の駐独大使。1941年特命全権大使として、日米交渉中の野村吉三郎大使を補佐するが、日米開戦により帰国。(1886〜1954)
⇒くるす【来栖】
くるすの【栗栖野】
①山城国宇治郡山科村(現、京都市山科区)の地名。
②京都市北区鷹峰の東、西賀茂の辺。みくるすの。(歌枕)
くるそん‐ぶつ【拘留孫仏】
〔仏〕過去七仏の第4の仏。賢劫げんごう一千仏の最首。
クルタ【kurta ヒンディー】
パンジャブ地方の民族衣装。膝丈までの長袖の上衣で、男女ともに着用。
グルタチオン【Glutathion ドイツ】
グルタミン酸・システイン・グリシンから成るトリペプチド。生体のポリペプチドのうち、初めて結晶化されたもの。動物体のあらゆる組織に含まれ、酸化されやすく、内呼吸に関係する。
グルタミン【glutamine】
グルタミン酸のアミド。針状結晶。遊離型または蛋白質の成分として広く動植物界に分布する。グルタミン酸とアンモニアから生合成され、窒素分の貯蔵、蛋白質代謝に重要。
⇒グルタミン‐さん【グルタミン酸】
グルタミン‐さん【グルタミン酸】
蛋白質を構成するアミノ酸の一つ。白色結晶。水に溶け、旨みがある。グルタミン酸のナトリウム塩は昆布の旨みを形成するもので、調味料としても製造される。
⇒グルタミン【glutamine】
クルツーア【Kultur ドイツ】
⇒カルチャー
グルック【Christoph Willibald Gluck】
ドイツ生れの作曲家。ボヘミアで育ち、ウィーン・パリで活躍。オペラを劇的表現を主眼とするものに改革した近世歌劇中興の祖。歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」「アウリスのイフィゲニア」「タウリスのイフィゲニア」など。(1714〜1787)
グルック
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 →歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」 精霊の踊り
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
クルックス‐かん【クルックス管】‥クワン
管内の気体の圧力が約10パスカル以下の真空放電管。イギリスの物理学者クルックス(W. Crookes1832〜1919)がはじめて用いた。
クルッツェン【Paul Crutzen】
オランダ生れの気象学者。マックス‐プランク化学研究所教授。成層圏のオゾンが窒素酸化物との反応で分解されることを解明し、オゾン層保護の重要性を指摘。また核戦争の大気への影響を予測して「核の冬」理論を発展させた。ノーベル賞。(1933〜)
くるっ‐と
〔副〕
①軽快に方向転換するさま。「―背を向ける」
②輪になったり丸くなったりするさま。「タオルを―巻きつける」
ぐるっ‐と
〔副〕
円や弧を描いて一回動くさま。「運動場を―ひとまわりする」「―見回す」
クルップ【Krupp ドイツ・格魯布】
〔医〕喉頭・気管のあたりに繊維素性の偽膜を生じる急性炎症。咽頭部の痛み、嗄声させい、窒息などを起こすが、その偽膜が容易にはがれる点がジフテリアと異なる。嗄声を表す古代英語が語源。クループ。コロップ。
クルップ【Krupp】
ドイツの製鋼業者の一族。1811年フリードリヒ=クルップ(Friedrich K.1787〜1826)が製鋼会社を創設。子孫が相継いで事業を拡張、兵器製造と製鋼によって巨大財閥をなした。第二次大戦後連合軍の管理下に置かれたが、西独再軍備で復活。
⇒クルップ‐ほう【クルップ砲】
⇒クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】
クルップ‐ほう【クルップ砲】‥ハウ
クルップ会社で製造した後装砲。砲身を鋳鉄で製造した最初のもの。
⇒クルップ【Krupp】
クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】‥ハフ
(Krupp-Renn method)製鋼法の一つ。回転炉で鉄鉱石や砂鉄などの粉鉱を還元したのち、磁力選鉱で粒鉄(ルッペ)を分離する方法。
⇒クルップ【Krupp】
グルッペ【Gruppe ドイツ】
⇒グループ。
⇒グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】
グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】‥ジフ‥
第二次大戦後の西ドイツの文学グループ。作家・編集者リヒター(Hans Werner Richter1908〜1993)が呼びかけ1947年に初会合。G.グラス・I.バッハマンらが参加。
⇒グルッペ【Gruppe ドイツ】
クルディスタン【Kurdistān】
トルコ東部からイラク北部、イラン北西部にまたがる山岳地帯。→クルド人
グルテン【gluten】
植物性の蛋白質の一つ。小麦など、植物の種子中にある。水溶液は灰褐色で粘性を示す。麩ふの原料に用いる。麩素。
グルデン【gulden オランダ】
オランダの貨幣単位。ギュルデン。ギルダー。旧称フロリン。1999年ユーロに移行。
くる‐とし【来る年】
新たに迎える年。明年。
クルド‐じん【クルド人】
(Kurds)クルディスタンに住むイラン系アジア人。第一次大戦後民族国家が成立せず、トルコ・イラク・イランなどに分属。独立運動が活発。その言語はインド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。大半はスンニー派イスラム教徒。
クルトン【croûton フランス】
采さいの目切りや様々な形に薄切りしたパンを、揚げたりバターで焼いたりしたもの。スープの浮き実、料理の付け合せに用いる。
ぐる‐に【ぐる煮】
采さいの目切りにした根菜・豆腐・こんにゃくなどを煮たもの。高知県の郷土料理。
グルニエ【grenier フランス】
(もと屋根裏の穀物倉の意)屋根裏部屋。
グルノーブル【Grenoble】
フランス南東部、アルプス山脈中の都市。豊富な水力を利用した発電やアルミ工業などが盛ん。アルプス観光の中心地。スタンダールの生地。人口15万4千(1999)。
くる‐ひ【来る日】
新しくやって来る日。明日。翌日。
くる‐びょう【痀瘻病・佝僂病】‥ビヤウ
ビタミンD不足による小児の骨の形成異常。ビタミンDは皮膚で前駆体から光線により生成されるため、日照の乏しい地方に発症しやすい。カルシウムの吸収が妨げられ、骨端軟骨の骨化が進まず、骨が軟らかく、脊柱・四肢などの発育不全、異常な湾曲を生じる。→骨軟化症
くる‐ぶし【踝】
足首の、脛すねとつながる部分にある内外両側の突起。内側の突起は脛骨けいこつの末端で内果と呼ばれ、外側の突起は腓骨ひこつの末端で外果と呼ばれる。くろぶし。つぶぶし。つぶなぎ。日葡辞書「クルブシ。または、アシノクルブシ」
くる‐べか・す【転べかす】
〔他四〕
(→)「くるめかす」に同じ。宇津保物語俊蔭「眼を車の輪の如く見―・して」
くる‐べき【反転】
糸を繰る道具。万葉集4「―に懸けて縁よせむと」
くる‐べ・く【転べく】
〔自四〕
くるくる回転する。くるめく。今昔物語集19「こまつぶりの如くくるくる―・きて」
くるま【車】
①軸に貫いて回転する仕組みの輪。車輪。
②車輪の回転によって動く仕掛けのものの総称。牛車・荷車・人力車など。現在では自動車を指すことが多い。万葉集16「後の世の鑑にせむと老人を送りし―持ち還り来し」。宇治拾遺物語2「―かけはづして搨しじをたてて」。幸田露伴、いさなとり「往き来の人肩を摩すり合ひ袂たもと触れ合ひ、人力車くるま飛び自転車走り」。「―を運転する」「―を拾う」
③輪状。わなり。
④紋所の名。車輪にかたどったもの。源氏車・風車・木下車・中川車など。
⇒くるま‐あらそい【車争い】
⇒くるま‐い【車井】
⇒くるま‐いす【車椅子】
⇒くるま‐いど【車井戸】
⇒くるま‐うし【車牛】
⇒くるま‐えび【車蝦】
⇒くるま‐がえし【車返し】
⇒くるま‐がえり【車返り・車翻り】
⇒くるま‐がかり【車懸り】
⇒くるま‐がき【車垣】
⇒くるま‐がさ【車笠】
⇒くるま‐かし【車貸し・車借】
⇒くるま‐がたな【車刀】
⇒くるま‐きしろい【車軋ろい】
⇒くるま‐ぎり【車切り】
⇒くるま‐げた【車桁】
⇒くるま‐ごし【車輿】
⇒くるま‐ごめ【車籠め】
⇒くるま‐ざ【車座】
⇒くるま‐ざき【車裂き】
⇒くるま‐じ【車路】
⇒くるま‐じかけ【車仕掛け】
⇒くるま‐しゃかい【車社会】
⇒くるま‐しゃっきん【車借金】
⇒くるま‐ぞい【車副】
⇒くるま‐ぞうし【車双紙】
⇒くるま‐そうぞく【車装束】
⇒くるま‐だい【車代】
⇒くるま‐だい【車鯛】
⇒くるま‐たけたば【車竹束】
⇒くるま‐だち【車裁ち】
⇒くるま‐だて【車楯】
⇒くるまたて‐ろん【車立て論】
⇒くるま‐ちん【車賃】
⇒くるま‐づか【車塚】
⇒くるま‐つくり【車作り】
⇒くるま‐つば【車鍔】
⇒くるま‐ど【車戸】
⇒くるま‐とう【車糖】
⇒くるま‐とだな【車戸棚】
⇒くるま‐どめ【車止め】
⇒くるま‐ながもち【車長持】
⇒くるま‐にんぎょう【車人形】
⇒くるま‐ばこ【車箱】
⇒くるまば‐そう【車葉草】
⇒くるま‐ばった【車蝗虫】
⇒くるま‐び【車火】
⇒くるま‐ひき【車引き・車曳き】
⇒くるま‐ひきあみ【車引網】
⇒くるま‐びし【車菱】
⇒くるま‐ぶ【車麩】
⇒くるま‐ぶね【車船】
⇒くるま‐へん【車偏】
⇒くるま‐まわし【車回し】
⇒くるま‐むし【車虫】
⇒くるまもち‐べ【車持部】
⇒くるま‐や【車屋】
⇒くるま‐やど【車宿】
⇒くるま‐やどり【車宿り】
⇒くるま‐ゆり【車百合】
⇒くるま‐よせ【車寄せ】
⇒車の両輪
⇒車は海へ船は山へ
⇒車は三寸の楔を以て千里を駆く
⇒車を懸く
⇒車を摧く
⇒車を捨てる
クルマ【Ahmadou Kourouma】
コート‐ディヴォアールの小説家。トーゴで働いた後、帰国。「独立の太陽」「金、凌辱、挑発」「アラーの神にもいわれなく」。(1927〜2003)
くるま‐あらそい【車争い】‥アラソヒ
物見の牛車ぎっしゃの立場たてばを牛飼童などが争うこと。くるまたてろん。源氏物語葵「祭の日…はかなかりし所の御―に」
⇒くるま【車】
くるま‐い【車井】‥ヰ
(→)車井戸に同じ。
⇒くるま【車】
くるま‐いす【車椅子】
歩行の不自由な人などが移動するための、車つきの椅子。
⇒くるま【車】
くるま‐いど【車井戸】‥ヰド
滑車の溝に綱をかけ、その両端に釣瓶つるべをつけて、綱をたぐって水を汲む装置の井戸。車井。
⇒くるま【車】
くるま‐うし【車牛】
牛車をひく牛。宇津保物語国譲下「黄あめなる御―懸けたり」
⇒くるま【車】
くるま‐えび【車蝦】
クルマエビ科のエビ。長さ20センチメートル前後。体は表面に毛がなく平滑で、淡褐色。各腹節に1本ずつ黒褐色の環があるので、体を曲げると車輪のように見える。尾は青色、黄色もまじり、多彩。本州中部以南の沿岸の浅海底にすむ。食用。人工養殖も行われる。斑節蝦。
くるまえび
→歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」 精霊の踊り
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
クルックス‐かん【クルックス管】‥クワン
管内の気体の圧力が約10パスカル以下の真空放電管。イギリスの物理学者クルックス(W. Crookes1832〜1919)がはじめて用いた。
クルッツェン【Paul Crutzen】
オランダ生れの気象学者。マックス‐プランク化学研究所教授。成層圏のオゾンが窒素酸化物との反応で分解されることを解明し、オゾン層保護の重要性を指摘。また核戦争の大気への影響を予測して「核の冬」理論を発展させた。ノーベル賞。(1933〜)
くるっ‐と
〔副〕
①軽快に方向転換するさま。「―背を向ける」
②輪になったり丸くなったりするさま。「タオルを―巻きつける」
ぐるっ‐と
〔副〕
円や弧を描いて一回動くさま。「運動場を―ひとまわりする」「―見回す」
クルップ【Krupp ドイツ・格魯布】
〔医〕喉頭・気管のあたりに繊維素性の偽膜を生じる急性炎症。咽頭部の痛み、嗄声させい、窒息などを起こすが、その偽膜が容易にはがれる点がジフテリアと異なる。嗄声を表す古代英語が語源。クループ。コロップ。
クルップ【Krupp】
ドイツの製鋼業者の一族。1811年フリードリヒ=クルップ(Friedrich K.1787〜1826)が製鋼会社を創設。子孫が相継いで事業を拡張、兵器製造と製鋼によって巨大財閥をなした。第二次大戦後連合軍の管理下に置かれたが、西独再軍備で復活。
⇒クルップ‐ほう【クルップ砲】
⇒クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】
クルップ‐ほう【クルップ砲】‥ハウ
クルップ会社で製造した後装砲。砲身を鋳鉄で製造した最初のもの。
⇒クルップ【Krupp】
クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】‥ハフ
(Krupp-Renn method)製鋼法の一つ。回転炉で鉄鉱石や砂鉄などの粉鉱を還元したのち、磁力選鉱で粒鉄(ルッペ)を分離する方法。
⇒クルップ【Krupp】
グルッペ【Gruppe ドイツ】
⇒グループ。
⇒グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】
グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】‥ジフ‥
第二次大戦後の西ドイツの文学グループ。作家・編集者リヒター(Hans Werner Richter1908〜1993)が呼びかけ1947年に初会合。G.グラス・I.バッハマンらが参加。
⇒グルッペ【Gruppe ドイツ】
クルディスタン【Kurdistān】
トルコ東部からイラク北部、イラン北西部にまたがる山岳地帯。→クルド人
グルテン【gluten】
植物性の蛋白質の一つ。小麦など、植物の種子中にある。水溶液は灰褐色で粘性を示す。麩ふの原料に用いる。麩素。
グルデン【gulden オランダ】
オランダの貨幣単位。ギュルデン。ギルダー。旧称フロリン。1999年ユーロに移行。
くる‐とし【来る年】
新たに迎える年。明年。
クルド‐じん【クルド人】
(Kurds)クルディスタンに住むイラン系アジア人。第一次大戦後民族国家が成立せず、トルコ・イラク・イランなどに分属。独立運動が活発。その言語はインド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。大半はスンニー派イスラム教徒。
クルトン【croûton フランス】
采さいの目切りや様々な形に薄切りしたパンを、揚げたりバターで焼いたりしたもの。スープの浮き実、料理の付け合せに用いる。
ぐる‐に【ぐる煮】
采さいの目切りにした根菜・豆腐・こんにゃくなどを煮たもの。高知県の郷土料理。
グルニエ【grenier フランス】
(もと屋根裏の穀物倉の意)屋根裏部屋。
グルノーブル【Grenoble】
フランス南東部、アルプス山脈中の都市。豊富な水力を利用した発電やアルミ工業などが盛ん。アルプス観光の中心地。スタンダールの生地。人口15万4千(1999)。
くる‐ひ【来る日】
新しくやって来る日。明日。翌日。
くる‐びょう【痀瘻病・佝僂病】‥ビヤウ
ビタミンD不足による小児の骨の形成異常。ビタミンDは皮膚で前駆体から光線により生成されるため、日照の乏しい地方に発症しやすい。カルシウムの吸収が妨げられ、骨端軟骨の骨化が進まず、骨が軟らかく、脊柱・四肢などの発育不全、異常な湾曲を生じる。→骨軟化症
くる‐ぶし【踝】
足首の、脛すねとつながる部分にある内外両側の突起。内側の突起は脛骨けいこつの末端で内果と呼ばれ、外側の突起は腓骨ひこつの末端で外果と呼ばれる。くろぶし。つぶぶし。つぶなぎ。日葡辞書「クルブシ。または、アシノクルブシ」
くる‐べか・す【転べかす】
〔他四〕
(→)「くるめかす」に同じ。宇津保物語俊蔭「眼を車の輪の如く見―・して」
くる‐べき【反転】
糸を繰る道具。万葉集4「―に懸けて縁よせむと」
くる‐べ・く【転べく】
〔自四〕
くるくる回転する。くるめく。今昔物語集19「こまつぶりの如くくるくる―・きて」
くるま【車】
①軸に貫いて回転する仕組みの輪。車輪。
②車輪の回転によって動く仕掛けのものの総称。牛車・荷車・人力車など。現在では自動車を指すことが多い。万葉集16「後の世の鑑にせむと老人を送りし―持ち還り来し」。宇治拾遺物語2「―かけはづして搨しじをたてて」。幸田露伴、いさなとり「往き来の人肩を摩すり合ひ袂たもと触れ合ひ、人力車くるま飛び自転車走り」。「―を運転する」「―を拾う」
③輪状。わなり。
④紋所の名。車輪にかたどったもの。源氏車・風車・木下車・中川車など。
⇒くるま‐あらそい【車争い】
⇒くるま‐い【車井】
⇒くるま‐いす【車椅子】
⇒くるま‐いど【車井戸】
⇒くるま‐うし【車牛】
⇒くるま‐えび【車蝦】
⇒くるま‐がえし【車返し】
⇒くるま‐がえり【車返り・車翻り】
⇒くるま‐がかり【車懸り】
⇒くるま‐がき【車垣】
⇒くるま‐がさ【車笠】
⇒くるま‐かし【車貸し・車借】
⇒くるま‐がたな【車刀】
⇒くるま‐きしろい【車軋ろい】
⇒くるま‐ぎり【車切り】
⇒くるま‐げた【車桁】
⇒くるま‐ごし【車輿】
⇒くるま‐ごめ【車籠め】
⇒くるま‐ざ【車座】
⇒くるま‐ざき【車裂き】
⇒くるま‐じ【車路】
⇒くるま‐じかけ【車仕掛け】
⇒くるま‐しゃかい【車社会】
⇒くるま‐しゃっきん【車借金】
⇒くるま‐ぞい【車副】
⇒くるま‐ぞうし【車双紙】
⇒くるま‐そうぞく【車装束】
⇒くるま‐だい【車代】
⇒くるま‐だい【車鯛】
⇒くるま‐たけたば【車竹束】
⇒くるま‐だち【車裁ち】
⇒くるま‐だて【車楯】
⇒くるまたて‐ろん【車立て論】
⇒くるま‐ちん【車賃】
⇒くるま‐づか【車塚】
⇒くるま‐つくり【車作り】
⇒くるま‐つば【車鍔】
⇒くるま‐ど【車戸】
⇒くるま‐とう【車糖】
⇒くるま‐とだな【車戸棚】
⇒くるま‐どめ【車止め】
⇒くるま‐ながもち【車長持】
⇒くるま‐にんぎょう【車人形】
⇒くるま‐ばこ【車箱】
⇒くるまば‐そう【車葉草】
⇒くるま‐ばった【車蝗虫】
⇒くるま‐び【車火】
⇒くるま‐ひき【車引き・車曳き】
⇒くるま‐ひきあみ【車引網】
⇒くるま‐びし【車菱】
⇒くるま‐ぶ【車麩】
⇒くるま‐ぶね【車船】
⇒くるま‐へん【車偏】
⇒くるま‐まわし【車回し】
⇒くるま‐むし【車虫】
⇒くるまもち‐べ【車持部】
⇒くるま‐や【車屋】
⇒くるま‐やど【車宿】
⇒くるま‐やどり【車宿り】
⇒くるま‐ゆり【車百合】
⇒くるま‐よせ【車寄せ】
⇒車の両輪
⇒車は海へ船は山へ
⇒車は三寸の楔を以て千里を駆く
⇒車を懸く
⇒車を摧く
⇒車を捨てる
クルマ【Ahmadou Kourouma】
コート‐ディヴォアールの小説家。トーゴで働いた後、帰国。「独立の太陽」「金、凌辱、挑発」「アラーの神にもいわれなく」。(1927〜2003)
くるま‐あらそい【車争い】‥アラソヒ
物見の牛車ぎっしゃの立場たてばを牛飼童などが争うこと。くるまたてろん。源氏物語葵「祭の日…はかなかりし所の御―に」
⇒くるま【車】
くるま‐い【車井】‥ヰ
(→)車井戸に同じ。
⇒くるま【車】
くるま‐いす【車椅子】
歩行の不自由な人などが移動するための、車つきの椅子。
⇒くるま【車】
くるま‐いど【車井戸】‥ヰド
滑車の溝に綱をかけ、その両端に釣瓶つるべをつけて、綱をたぐって水を汲む装置の井戸。車井。
⇒くるま【車】
くるま‐うし【車牛】
牛車をひく牛。宇津保物語国譲下「黄あめなる御―懸けたり」
⇒くるま【車】
くるま‐えび【車蝦】
クルマエビ科のエビ。長さ20センチメートル前後。体は表面に毛がなく平滑で、淡褐色。各腹節に1本ずつ黒褐色の環があるので、体を曲げると車輪のように見える。尾は青色、黄色もまじり、多彩。本州中部以南の沿岸の浅海底にすむ。食用。人工養殖も行われる。斑節蝦。
くるまえび
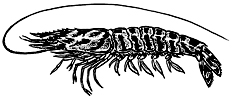 ⇒くるま【車】
くるま‐おおじ【車大路】‥オホヂ
①京都の三条粟田口から北へ向かい、黒谷へ至った道。
②京都の五条橋(今の松原橋)を渡って東山方面へ通ずる道。
くるま‐がえし【車返し】‥ガヘシ
①けわしい山路、聖域など、そこから先へは車が通れないために車を返す所。
②サクラの一品種。花は白く、大輪で5〜8弁。
⇒くるま【車】
くるま‐がえり【車返り・車翻り】‥ガヘリ
「もんどり」の一種。手をついて、続けざまに横に身を翻すこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がかり【車懸り】
①近世の越後流の陣法で、1番手・2番手・3番手と順次に分けておき、前が弱るに従って後が続き、循環して敵に攻めかかること。
②相撲や剣道で、勝ったものに新手が代わる代わるかかって行くこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がき【車垣】
茶席の庭などに設ける垣で、萩などを束ねて半円形の輪状にしたもの。
⇒くるま【車】
くるま‐がさ【車笠】
車輪状のかぶりがさ。
⇒くるま【車】
くるま‐かし【車貸し・車借】
①車で物を運んで賃銭を取ること。また、それを業とする人。今昔物語集29「その辺には―といふ者あまたあり」
②車を貸して賃銭をとること。また、その人。
⇒くるま【車】
くるま‐がたな【車刀】
護身のため、車中に備えておく刀。
⇒くるま【車】
くる‐まき【搯巻】
(→)「ろくろ」に同じ。太平記36「棟木をあげんとしけるに、―の縄に信濃皮むき千束入るべし」
くるま‐きしろい【車軋ろい】‥キシロヒ
車に乗る際に、その車や乗る人などの選択について争うこと。栄華物語初花「女房の―もありけれど」
⇒くるま【車】
くるま‐ぎり【車切り】
輪切り。太平記10「―・胴切・立破たてわりに仕つかまつり棄て度く」
⇒くるま【車】
ぐる‐まげ【ぐる髷】
(→)「ぐるぐるわげ」に同じ。
くるま‐げた【車桁】
井戸の滑車を釣っている桁。
⇒くるま【車】
くるま‐ごし【車輿】
牛車ぎっしゃから車輪を取り除いたような形の輿。院・親王・摂関の女むすめなどの乗用。
⇒くるま【車】
くるま‐ごめ【車籠め】
車に乗ったままであること。車ごと。蜻蛉日記下「―ひき入るるを見れば」
⇒くるま【車】
くるま‐ざ【車座】
大勢が輪になって座ること。
⇒くるま【車】
くるま‐ざき【車裂き】
戦国時代の刑。車2両に罪人の各片足を結びつけ、その肢体をひきさく。
⇒くるま【車】
くるま‐じ【車路】‥ヂ
車の行き通う路。車道。謡曲、百万「願ひも三つの―を都に帰る嬉しさよ」
⇒くるま【車】
くるま‐じかけ【車仕掛け】
器械の下に車をつけて移動しやすくしてあるもの。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃかい【車社会】‥クワイ
自動車によって生活がなりたつ社会。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃっきん【車借金】‥シヤク‥
江戸時代、数人連帯で借金し、毎月輪番で月賦でかえしたこと。
⇒くるま【車】
くるま‐ぜんしち【車善七】
江戸時代、江戸で、えた頭がしら弾左衛門の支配下にあって、代々、非人頭を勤めた者の称。
くるま‐ぞい【車副】‥ゾヒ
牛車ぎっしゃの左右について供をする者。源氏物語宿木「かの御前、随身、―、舎人などまで禄賜はす」
⇒くるま【車】
くるまぞう【車僧】
能。車に乗って行脚あんぎゃする僧が愛宕山の天狗太郎坊と禅問答の末、降伏ごうぶくする。
くるま‐ぞうし【車双紙】‥ザウ‥
手習草紙などの、包くるみ表紙にした本。
⇒くるま【車】
くるま‐そうぞく【車装束】‥サウ‥
車に装飾をすること。また、装飾をした車。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車代】
①車を買い、または車を借りた代金。
②車に乗った賃銭。車賃。また、その名目で支払う謝礼金。お車代。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車鯛】‥ダヒ
キントキダイ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。鯛型で、口と目は非常に大きい。体は淡赤色で、ひれの縁は黒い。幼魚では体側に明瞭な白色横帯がある。南日本産。食用。
⇒くるま【車】
くるま‐たけたば【車竹束】
竹束の下に車輪をとりつけ、回転・進退を自由にした防御用武具。→竹束。
⇒くるま【車】
くるま‐だち【車裁ち】
四つ身裁ちの一種で、身幅を広くとるための裁ち方。両身頃の用布全部を通して一定の幅を裁ち落とし、これを襟・掛襟とする。
⇒くるま【車】
くるま‐だて【車楯】
下部に車を装置して進退を自由にした楯。
⇒くるま【車】
くるまたて‐ろん【車立て論】
車あらそい。沙石集9「僧正の牛飼、御室の御車と―して」
⇒くるま【車】
くるま‐ちん【車賃】
自動車などに乗るための賃銭。また、荷車を雇って支払う賃銭。
⇒くるま【車】
くるま‐づか【車塚】
前方後円墳の俗称。
⇒くるま【車】
くるま‐つくり【車作り】
車を製作すること。また、その職人。
⇒くるま【車】
くるま‐つば【車鍔】
車輪の形に造った鍔。
⇒くるま【車】
くるま‐ど【車戸】
下に小さい車をつけ、開閉しやすくした戸。
⇒くるま【車】
くるま‐とう【車糖】‥タウ
上白・中白・三温さんおんなど、結晶の小さい精製糖の総称。
⇒くるま【車】
くるま‐とだな【車戸棚】
下に車輪をつけて動かしやすくした戸棚。
⇒くるま【車】
くるま‐どめ【車止め】
①車の通行を禁ずること。
②自動車などを動かないように止めておくこと。また、そのための器具。
③軌道の終端に、車両が線路外に逸走するのを防止するために設置する装置。
⇒くるま【車】
くるま‐ながもち【車長持】
大型の長持で、底に車をつけて移動しやすいようにしてあるもの。
車長持
⇒くるま【車】
くるま‐おおじ【車大路】‥オホヂ
①京都の三条粟田口から北へ向かい、黒谷へ至った道。
②京都の五条橋(今の松原橋)を渡って東山方面へ通ずる道。
くるま‐がえし【車返し】‥ガヘシ
①けわしい山路、聖域など、そこから先へは車が通れないために車を返す所。
②サクラの一品種。花は白く、大輪で5〜8弁。
⇒くるま【車】
くるま‐がえり【車返り・車翻り】‥ガヘリ
「もんどり」の一種。手をついて、続けざまに横に身を翻すこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がかり【車懸り】
①近世の越後流の陣法で、1番手・2番手・3番手と順次に分けておき、前が弱るに従って後が続き、循環して敵に攻めかかること。
②相撲や剣道で、勝ったものに新手が代わる代わるかかって行くこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がき【車垣】
茶席の庭などに設ける垣で、萩などを束ねて半円形の輪状にしたもの。
⇒くるま【車】
くるま‐がさ【車笠】
車輪状のかぶりがさ。
⇒くるま【車】
くるま‐かし【車貸し・車借】
①車で物を運んで賃銭を取ること。また、それを業とする人。今昔物語集29「その辺には―といふ者あまたあり」
②車を貸して賃銭をとること。また、その人。
⇒くるま【車】
くるま‐がたな【車刀】
護身のため、車中に備えておく刀。
⇒くるま【車】
くる‐まき【搯巻】
(→)「ろくろ」に同じ。太平記36「棟木をあげんとしけるに、―の縄に信濃皮むき千束入るべし」
くるま‐きしろい【車軋ろい】‥キシロヒ
車に乗る際に、その車や乗る人などの選択について争うこと。栄華物語初花「女房の―もありけれど」
⇒くるま【車】
くるま‐ぎり【車切り】
輪切り。太平記10「―・胴切・立破たてわりに仕つかまつり棄て度く」
⇒くるま【車】
ぐる‐まげ【ぐる髷】
(→)「ぐるぐるわげ」に同じ。
くるま‐げた【車桁】
井戸の滑車を釣っている桁。
⇒くるま【車】
くるま‐ごし【車輿】
牛車ぎっしゃから車輪を取り除いたような形の輿。院・親王・摂関の女むすめなどの乗用。
⇒くるま【車】
くるま‐ごめ【車籠め】
車に乗ったままであること。車ごと。蜻蛉日記下「―ひき入るるを見れば」
⇒くるま【車】
くるま‐ざ【車座】
大勢が輪になって座ること。
⇒くるま【車】
くるま‐ざき【車裂き】
戦国時代の刑。車2両に罪人の各片足を結びつけ、その肢体をひきさく。
⇒くるま【車】
くるま‐じ【車路】‥ヂ
車の行き通う路。車道。謡曲、百万「願ひも三つの―を都に帰る嬉しさよ」
⇒くるま【車】
くるま‐じかけ【車仕掛け】
器械の下に車をつけて移動しやすくしてあるもの。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃかい【車社会】‥クワイ
自動車によって生活がなりたつ社会。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃっきん【車借金】‥シヤク‥
江戸時代、数人連帯で借金し、毎月輪番で月賦でかえしたこと。
⇒くるま【車】
くるま‐ぜんしち【車善七】
江戸時代、江戸で、えた頭がしら弾左衛門の支配下にあって、代々、非人頭を勤めた者の称。
くるま‐ぞい【車副】‥ゾヒ
牛車ぎっしゃの左右について供をする者。源氏物語宿木「かの御前、随身、―、舎人などまで禄賜はす」
⇒くるま【車】
くるまぞう【車僧】
能。車に乗って行脚あんぎゃする僧が愛宕山の天狗太郎坊と禅問答の末、降伏ごうぶくする。
くるま‐ぞうし【車双紙】‥ザウ‥
手習草紙などの、包くるみ表紙にした本。
⇒くるま【車】
くるま‐そうぞく【車装束】‥サウ‥
車に装飾をすること。また、装飾をした車。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車代】
①車を買い、または車を借りた代金。
②車に乗った賃銭。車賃。また、その名目で支払う謝礼金。お車代。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車鯛】‥ダヒ
キントキダイ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。鯛型で、口と目は非常に大きい。体は淡赤色で、ひれの縁は黒い。幼魚では体側に明瞭な白色横帯がある。南日本産。食用。
⇒くるま【車】
くるま‐たけたば【車竹束】
竹束の下に車輪をとりつけ、回転・進退を自由にした防御用武具。→竹束。
⇒くるま【車】
くるま‐だち【車裁ち】
四つ身裁ちの一種で、身幅を広くとるための裁ち方。両身頃の用布全部を通して一定の幅を裁ち落とし、これを襟・掛襟とする。
⇒くるま【車】
くるま‐だて【車楯】
下部に車を装置して進退を自由にした楯。
⇒くるま【車】
くるまたて‐ろん【車立て論】
車あらそい。沙石集9「僧正の牛飼、御室の御車と―して」
⇒くるま【車】
くるま‐ちん【車賃】
自動車などに乗るための賃銭。また、荷車を雇って支払う賃銭。
⇒くるま【車】
くるま‐づか【車塚】
前方後円墳の俗称。
⇒くるま【車】
くるま‐つくり【車作り】
車を製作すること。また、その職人。
⇒くるま【車】
くるま‐つば【車鍔】
車輪の形に造った鍔。
⇒くるま【車】
くるま‐ど【車戸】
下に小さい車をつけ、開閉しやすくした戸。
⇒くるま【車】
くるま‐とう【車糖】‥タウ
上白・中白・三温さんおんなど、結晶の小さい精製糖の総称。
⇒くるま【車】
くるま‐とだな【車戸棚】
下に車輪をつけて動かしやすくした戸棚。
⇒くるま【車】
くるま‐どめ【車止め】
①車の通行を禁ずること。
②自動車などを動かないように止めておくこと。また、そのための器具。
③軌道の終端に、車両が線路外に逸走するのを防止するために設置する装置。
⇒くるま【車】
くるま‐ながもち【車長持】
大型の長持で、底に車をつけて移動しやすいようにしてあるもの。
車長持
 ⇒くるま【車】
くるま‐にんぎょう【車人形】‥ギヤウ
①操あやつり人形で、人形を轆轤ろくろ仕掛けで動かす装置。
②人形遣いの一様式。一人の遣手つかいてが自由自在に回転する小さな箱車に腰を掛け、遣手の足指と人形の足とを結びつけて遣う。出語でがたりは説経浄瑠璃を使用。天保(1830〜1844)末期、八王子在に発達し、現存。
車人形の轆轤車
提供:東京都
⇒くるま【車】
くるま‐にんぎょう【車人形】‥ギヤウ
①操あやつり人形で、人形を轆轤ろくろ仕掛けで動かす装置。
②人形遣いの一様式。一人の遣手つかいてが自由自在に回転する小さな箱車に腰を掛け、遣手の足指と人形の足とを結びつけて遣う。出語でがたりは説経浄瑠璃を使用。天保(1830〜1844)末期、八王子在に発達し、現存。
車人形の轆轤車
提供:東京都
 八王子車人形
提供:東京都
八王子車人形
提供:東京都
 ⇒くるま【車】
⇒くるま【車】
 →歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」 精霊の踊り
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
クルックス‐かん【クルックス管】‥クワン
管内の気体の圧力が約10パスカル以下の真空放電管。イギリスの物理学者クルックス(W. Crookes1832〜1919)がはじめて用いた。
クルッツェン【Paul Crutzen】
オランダ生れの気象学者。マックス‐プランク化学研究所教授。成層圏のオゾンが窒素酸化物との反応で分解されることを解明し、オゾン層保護の重要性を指摘。また核戦争の大気への影響を予測して「核の冬」理論を発展させた。ノーベル賞。(1933〜)
くるっ‐と
〔副〕
①軽快に方向転換するさま。「―背を向ける」
②輪になったり丸くなったりするさま。「タオルを―巻きつける」
ぐるっ‐と
〔副〕
円や弧を描いて一回動くさま。「運動場を―ひとまわりする」「―見回す」
クルップ【Krupp ドイツ・格魯布】
〔医〕喉頭・気管のあたりに繊維素性の偽膜を生じる急性炎症。咽頭部の痛み、嗄声させい、窒息などを起こすが、その偽膜が容易にはがれる点がジフテリアと異なる。嗄声を表す古代英語が語源。クループ。コロップ。
クルップ【Krupp】
ドイツの製鋼業者の一族。1811年フリードリヒ=クルップ(Friedrich K.1787〜1826)が製鋼会社を創設。子孫が相継いで事業を拡張、兵器製造と製鋼によって巨大財閥をなした。第二次大戦後連合軍の管理下に置かれたが、西独再軍備で復活。
⇒クルップ‐ほう【クルップ砲】
⇒クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】
クルップ‐ほう【クルップ砲】‥ハウ
クルップ会社で製造した後装砲。砲身を鋳鉄で製造した最初のもの。
⇒クルップ【Krupp】
クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】‥ハフ
(Krupp-Renn method)製鋼法の一つ。回転炉で鉄鉱石や砂鉄などの粉鉱を還元したのち、磁力選鉱で粒鉄(ルッペ)を分離する方法。
⇒クルップ【Krupp】
グルッペ【Gruppe ドイツ】
⇒グループ。
⇒グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】
グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】‥ジフ‥
第二次大戦後の西ドイツの文学グループ。作家・編集者リヒター(Hans Werner Richter1908〜1993)が呼びかけ1947年に初会合。G.グラス・I.バッハマンらが参加。
⇒グルッペ【Gruppe ドイツ】
クルディスタン【Kurdistān】
トルコ東部からイラク北部、イラン北西部にまたがる山岳地帯。→クルド人
グルテン【gluten】
植物性の蛋白質の一つ。小麦など、植物の種子中にある。水溶液は灰褐色で粘性を示す。麩ふの原料に用いる。麩素。
グルデン【gulden オランダ】
オランダの貨幣単位。ギュルデン。ギルダー。旧称フロリン。1999年ユーロに移行。
くる‐とし【来る年】
新たに迎える年。明年。
クルド‐じん【クルド人】
(Kurds)クルディスタンに住むイラン系アジア人。第一次大戦後民族国家が成立せず、トルコ・イラク・イランなどに分属。独立運動が活発。その言語はインド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。大半はスンニー派イスラム教徒。
クルトン【croûton フランス】
采さいの目切りや様々な形に薄切りしたパンを、揚げたりバターで焼いたりしたもの。スープの浮き実、料理の付け合せに用いる。
ぐる‐に【ぐる煮】
采さいの目切りにした根菜・豆腐・こんにゃくなどを煮たもの。高知県の郷土料理。
グルニエ【grenier フランス】
(もと屋根裏の穀物倉の意)屋根裏部屋。
グルノーブル【Grenoble】
フランス南東部、アルプス山脈中の都市。豊富な水力を利用した発電やアルミ工業などが盛ん。アルプス観光の中心地。スタンダールの生地。人口15万4千(1999)。
くる‐ひ【来る日】
新しくやって来る日。明日。翌日。
くる‐びょう【痀瘻病・佝僂病】‥ビヤウ
ビタミンD不足による小児の骨の形成異常。ビタミンDは皮膚で前駆体から光線により生成されるため、日照の乏しい地方に発症しやすい。カルシウムの吸収が妨げられ、骨端軟骨の骨化が進まず、骨が軟らかく、脊柱・四肢などの発育不全、異常な湾曲を生じる。→骨軟化症
くる‐ぶし【踝】
足首の、脛すねとつながる部分にある内外両側の突起。内側の突起は脛骨けいこつの末端で内果と呼ばれ、外側の突起は腓骨ひこつの末端で外果と呼ばれる。くろぶし。つぶぶし。つぶなぎ。日葡辞書「クルブシ。または、アシノクルブシ」
くる‐べか・す【転べかす】
〔他四〕
(→)「くるめかす」に同じ。宇津保物語俊蔭「眼を車の輪の如く見―・して」
くる‐べき【反転】
糸を繰る道具。万葉集4「―に懸けて縁よせむと」
くる‐べ・く【転べく】
〔自四〕
くるくる回転する。くるめく。今昔物語集19「こまつぶりの如くくるくる―・きて」
くるま【車】
①軸に貫いて回転する仕組みの輪。車輪。
②車輪の回転によって動く仕掛けのものの総称。牛車・荷車・人力車など。現在では自動車を指すことが多い。万葉集16「後の世の鑑にせむと老人を送りし―持ち還り来し」。宇治拾遺物語2「―かけはづして搨しじをたてて」。幸田露伴、いさなとり「往き来の人肩を摩すり合ひ袂たもと触れ合ひ、人力車くるま飛び自転車走り」。「―を運転する」「―を拾う」
③輪状。わなり。
④紋所の名。車輪にかたどったもの。源氏車・風車・木下車・中川車など。
⇒くるま‐あらそい【車争い】
⇒くるま‐い【車井】
⇒くるま‐いす【車椅子】
⇒くるま‐いど【車井戸】
⇒くるま‐うし【車牛】
⇒くるま‐えび【車蝦】
⇒くるま‐がえし【車返し】
⇒くるま‐がえり【車返り・車翻り】
⇒くるま‐がかり【車懸り】
⇒くるま‐がき【車垣】
⇒くるま‐がさ【車笠】
⇒くるま‐かし【車貸し・車借】
⇒くるま‐がたな【車刀】
⇒くるま‐きしろい【車軋ろい】
⇒くるま‐ぎり【車切り】
⇒くるま‐げた【車桁】
⇒くるま‐ごし【車輿】
⇒くるま‐ごめ【車籠め】
⇒くるま‐ざ【車座】
⇒くるま‐ざき【車裂き】
⇒くるま‐じ【車路】
⇒くるま‐じかけ【車仕掛け】
⇒くるま‐しゃかい【車社会】
⇒くるま‐しゃっきん【車借金】
⇒くるま‐ぞい【車副】
⇒くるま‐ぞうし【車双紙】
⇒くるま‐そうぞく【車装束】
⇒くるま‐だい【車代】
⇒くるま‐だい【車鯛】
⇒くるま‐たけたば【車竹束】
⇒くるま‐だち【車裁ち】
⇒くるま‐だて【車楯】
⇒くるまたて‐ろん【車立て論】
⇒くるま‐ちん【車賃】
⇒くるま‐づか【車塚】
⇒くるま‐つくり【車作り】
⇒くるま‐つば【車鍔】
⇒くるま‐ど【車戸】
⇒くるま‐とう【車糖】
⇒くるま‐とだな【車戸棚】
⇒くるま‐どめ【車止め】
⇒くるま‐ながもち【車長持】
⇒くるま‐にんぎょう【車人形】
⇒くるま‐ばこ【車箱】
⇒くるまば‐そう【車葉草】
⇒くるま‐ばった【車蝗虫】
⇒くるま‐び【車火】
⇒くるま‐ひき【車引き・車曳き】
⇒くるま‐ひきあみ【車引網】
⇒くるま‐びし【車菱】
⇒くるま‐ぶ【車麩】
⇒くるま‐ぶね【車船】
⇒くるま‐へん【車偏】
⇒くるま‐まわし【車回し】
⇒くるま‐むし【車虫】
⇒くるまもち‐べ【車持部】
⇒くるま‐や【車屋】
⇒くるま‐やど【車宿】
⇒くるま‐やどり【車宿り】
⇒くるま‐ゆり【車百合】
⇒くるま‐よせ【車寄せ】
⇒車の両輪
⇒車は海へ船は山へ
⇒車は三寸の楔を以て千里を駆く
⇒車を懸く
⇒車を摧く
⇒車を捨てる
クルマ【Ahmadou Kourouma】
コート‐ディヴォアールの小説家。トーゴで働いた後、帰国。「独立の太陽」「金、凌辱、挑発」「アラーの神にもいわれなく」。(1927〜2003)
くるま‐あらそい【車争い】‥アラソヒ
物見の牛車ぎっしゃの立場たてばを牛飼童などが争うこと。くるまたてろん。源氏物語葵「祭の日…はかなかりし所の御―に」
⇒くるま【車】
くるま‐い【車井】‥ヰ
(→)車井戸に同じ。
⇒くるま【車】
くるま‐いす【車椅子】
歩行の不自由な人などが移動するための、車つきの椅子。
⇒くるま【車】
くるま‐いど【車井戸】‥ヰド
滑車の溝に綱をかけ、その両端に釣瓶つるべをつけて、綱をたぐって水を汲む装置の井戸。車井。
⇒くるま【車】
くるま‐うし【車牛】
牛車をひく牛。宇津保物語国譲下「黄あめなる御―懸けたり」
⇒くるま【車】
くるま‐えび【車蝦】
クルマエビ科のエビ。長さ20センチメートル前後。体は表面に毛がなく平滑で、淡褐色。各腹節に1本ずつ黒褐色の環があるので、体を曲げると車輪のように見える。尾は青色、黄色もまじり、多彩。本州中部以南の沿岸の浅海底にすむ。食用。人工養殖も行われる。斑節蝦。
くるまえび
→歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」 精霊の踊り
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
クルックス‐かん【クルックス管】‥クワン
管内の気体の圧力が約10パスカル以下の真空放電管。イギリスの物理学者クルックス(W. Crookes1832〜1919)がはじめて用いた。
クルッツェン【Paul Crutzen】
オランダ生れの気象学者。マックス‐プランク化学研究所教授。成層圏のオゾンが窒素酸化物との反応で分解されることを解明し、オゾン層保護の重要性を指摘。また核戦争の大気への影響を予測して「核の冬」理論を発展させた。ノーベル賞。(1933〜)
くるっ‐と
〔副〕
①軽快に方向転換するさま。「―背を向ける」
②輪になったり丸くなったりするさま。「タオルを―巻きつける」
ぐるっ‐と
〔副〕
円や弧を描いて一回動くさま。「運動場を―ひとまわりする」「―見回す」
クルップ【Krupp ドイツ・格魯布】
〔医〕喉頭・気管のあたりに繊維素性の偽膜を生じる急性炎症。咽頭部の痛み、嗄声させい、窒息などを起こすが、その偽膜が容易にはがれる点がジフテリアと異なる。嗄声を表す古代英語が語源。クループ。コロップ。
クルップ【Krupp】
ドイツの製鋼業者の一族。1811年フリードリヒ=クルップ(Friedrich K.1787〜1826)が製鋼会社を創設。子孫が相継いで事業を拡張、兵器製造と製鋼によって巨大財閥をなした。第二次大戦後連合軍の管理下に置かれたが、西独再軍備で復活。
⇒クルップ‐ほう【クルップ砲】
⇒クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】
クルップ‐ほう【クルップ砲】‥ハウ
クルップ会社で製造した後装砲。砲身を鋳鉄で製造した最初のもの。
⇒クルップ【Krupp】
クルップ‐レン‐ほう【クルップレン法】‥ハフ
(Krupp-Renn method)製鋼法の一つ。回転炉で鉄鉱石や砂鉄などの粉鉱を還元したのち、磁力選鉱で粒鉄(ルッペ)を分離する方法。
⇒クルップ【Krupp】
グルッペ【Gruppe ドイツ】
⇒グループ。
⇒グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】
グルッペ‐よんじゅうなな【グルッペ47】‥ジフ‥
第二次大戦後の西ドイツの文学グループ。作家・編集者リヒター(Hans Werner Richter1908〜1993)が呼びかけ1947年に初会合。G.グラス・I.バッハマンらが参加。
⇒グルッペ【Gruppe ドイツ】
クルディスタン【Kurdistān】
トルコ東部からイラク北部、イラン北西部にまたがる山岳地帯。→クルド人
グルテン【gluten】
植物性の蛋白質の一つ。小麦など、植物の種子中にある。水溶液は灰褐色で粘性を示す。麩ふの原料に用いる。麩素。
グルデン【gulden オランダ】
オランダの貨幣単位。ギュルデン。ギルダー。旧称フロリン。1999年ユーロに移行。
くる‐とし【来る年】
新たに迎える年。明年。
クルド‐じん【クルド人】
(Kurds)クルディスタンに住むイラン系アジア人。第一次大戦後民族国家が成立せず、トルコ・イラク・イランなどに分属。独立運動が活発。その言語はインド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。大半はスンニー派イスラム教徒。
クルトン【croûton フランス】
采さいの目切りや様々な形に薄切りしたパンを、揚げたりバターで焼いたりしたもの。スープの浮き実、料理の付け合せに用いる。
ぐる‐に【ぐる煮】
采さいの目切りにした根菜・豆腐・こんにゃくなどを煮たもの。高知県の郷土料理。
グルニエ【grenier フランス】
(もと屋根裏の穀物倉の意)屋根裏部屋。
グルノーブル【Grenoble】
フランス南東部、アルプス山脈中の都市。豊富な水力を利用した発電やアルミ工業などが盛ん。アルプス観光の中心地。スタンダールの生地。人口15万4千(1999)。
くる‐ひ【来る日】
新しくやって来る日。明日。翌日。
くる‐びょう【痀瘻病・佝僂病】‥ビヤウ
ビタミンD不足による小児の骨の形成異常。ビタミンDは皮膚で前駆体から光線により生成されるため、日照の乏しい地方に発症しやすい。カルシウムの吸収が妨げられ、骨端軟骨の骨化が進まず、骨が軟らかく、脊柱・四肢などの発育不全、異常な湾曲を生じる。→骨軟化症
くる‐ぶし【踝】
足首の、脛すねとつながる部分にある内外両側の突起。内側の突起は脛骨けいこつの末端で内果と呼ばれ、外側の突起は腓骨ひこつの末端で外果と呼ばれる。くろぶし。つぶぶし。つぶなぎ。日葡辞書「クルブシ。または、アシノクルブシ」
くる‐べか・す【転べかす】
〔他四〕
(→)「くるめかす」に同じ。宇津保物語俊蔭「眼を車の輪の如く見―・して」
くる‐べき【反転】
糸を繰る道具。万葉集4「―に懸けて縁よせむと」
くる‐べ・く【転べく】
〔自四〕
くるくる回転する。くるめく。今昔物語集19「こまつぶりの如くくるくる―・きて」
くるま【車】
①軸に貫いて回転する仕組みの輪。車輪。
②車輪の回転によって動く仕掛けのものの総称。牛車・荷車・人力車など。現在では自動車を指すことが多い。万葉集16「後の世の鑑にせむと老人を送りし―持ち還り来し」。宇治拾遺物語2「―かけはづして搨しじをたてて」。幸田露伴、いさなとり「往き来の人肩を摩すり合ひ袂たもと触れ合ひ、人力車くるま飛び自転車走り」。「―を運転する」「―を拾う」
③輪状。わなり。
④紋所の名。車輪にかたどったもの。源氏車・風車・木下車・中川車など。
⇒くるま‐あらそい【車争い】
⇒くるま‐い【車井】
⇒くるま‐いす【車椅子】
⇒くるま‐いど【車井戸】
⇒くるま‐うし【車牛】
⇒くるま‐えび【車蝦】
⇒くるま‐がえし【車返し】
⇒くるま‐がえり【車返り・車翻り】
⇒くるま‐がかり【車懸り】
⇒くるま‐がき【車垣】
⇒くるま‐がさ【車笠】
⇒くるま‐かし【車貸し・車借】
⇒くるま‐がたな【車刀】
⇒くるま‐きしろい【車軋ろい】
⇒くるま‐ぎり【車切り】
⇒くるま‐げた【車桁】
⇒くるま‐ごし【車輿】
⇒くるま‐ごめ【車籠め】
⇒くるま‐ざ【車座】
⇒くるま‐ざき【車裂き】
⇒くるま‐じ【車路】
⇒くるま‐じかけ【車仕掛け】
⇒くるま‐しゃかい【車社会】
⇒くるま‐しゃっきん【車借金】
⇒くるま‐ぞい【車副】
⇒くるま‐ぞうし【車双紙】
⇒くるま‐そうぞく【車装束】
⇒くるま‐だい【車代】
⇒くるま‐だい【車鯛】
⇒くるま‐たけたば【車竹束】
⇒くるま‐だち【車裁ち】
⇒くるま‐だて【車楯】
⇒くるまたて‐ろん【車立て論】
⇒くるま‐ちん【車賃】
⇒くるま‐づか【車塚】
⇒くるま‐つくり【車作り】
⇒くるま‐つば【車鍔】
⇒くるま‐ど【車戸】
⇒くるま‐とう【車糖】
⇒くるま‐とだな【車戸棚】
⇒くるま‐どめ【車止め】
⇒くるま‐ながもち【車長持】
⇒くるま‐にんぎょう【車人形】
⇒くるま‐ばこ【車箱】
⇒くるまば‐そう【車葉草】
⇒くるま‐ばった【車蝗虫】
⇒くるま‐び【車火】
⇒くるま‐ひき【車引き・車曳き】
⇒くるま‐ひきあみ【車引網】
⇒くるま‐びし【車菱】
⇒くるま‐ぶ【車麩】
⇒くるま‐ぶね【車船】
⇒くるま‐へん【車偏】
⇒くるま‐まわし【車回し】
⇒くるま‐むし【車虫】
⇒くるまもち‐べ【車持部】
⇒くるま‐や【車屋】
⇒くるま‐やど【車宿】
⇒くるま‐やどり【車宿り】
⇒くるま‐ゆり【車百合】
⇒くるま‐よせ【車寄せ】
⇒車の両輪
⇒車は海へ船は山へ
⇒車は三寸の楔を以て千里を駆く
⇒車を懸く
⇒車を摧く
⇒車を捨てる
クルマ【Ahmadou Kourouma】
コート‐ディヴォアールの小説家。トーゴで働いた後、帰国。「独立の太陽」「金、凌辱、挑発」「アラーの神にもいわれなく」。(1927〜2003)
くるま‐あらそい【車争い】‥アラソヒ
物見の牛車ぎっしゃの立場たてばを牛飼童などが争うこと。くるまたてろん。源氏物語葵「祭の日…はかなかりし所の御―に」
⇒くるま【車】
くるま‐い【車井】‥ヰ
(→)車井戸に同じ。
⇒くるま【車】
くるま‐いす【車椅子】
歩行の不自由な人などが移動するための、車つきの椅子。
⇒くるま【車】
くるま‐いど【車井戸】‥ヰド
滑車の溝に綱をかけ、その両端に釣瓶つるべをつけて、綱をたぐって水を汲む装置の井戸。車井。
⇒くるま【車】
くるま‐うし【車牛】
牛車をひく牛。宇津保物語国譲下「黄あめなる御―懸けたり」
⇒くるま【車】
くるま‐えび【車蝦】
クルマエビ科のエビ。長さ20センチメートル前後。体は表面に毛がなく平滑で、淡褐色。各腹節に1本ずつ黒褐色の環があるので、体を曲げると車輪のように見える。尾は青色、黄色もまじり、多彩。本州中部以南の沿岸の浅海底にすむ。食用。人工養殖も行われる。斑節蝦。
くるまえび
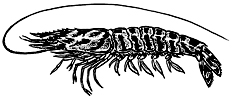 ⇒くるま【車】
くるま‐おおじ【車大路】‥オホヂ
①京都の三条粟田口から北へ向かい、黒谷へ至った道。
②京都の五条橋(今の松原橋)を渡って東山方面へ通ずる道。
くるま‐がえし【車返し】‥ガヘシ
①けわしい山路、聖域など、そこから先へは車が通れないために車を返す所。
②サクラの一品種。花は白く、大輪で5〜8弁。
⇒くるま【車】
くるま‐がえり【車返り・車翻り】‥ガヘリ
「もんどり」の一種。手をついて、続けざまに横に身を翻すこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がかり【車懸り】
①近世の越後流の陣法で、1番手・2番手・3番手と順次に分けておき、前が弱るに従って後が続き、循環して敵に攻めかかること。
②相撲や剣道で、勝ったものに新手が代わる代わるかかって行くこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がき【車垣】
茶席の庭などに設ける垣で、萩などを束ねて半円形の輪状にしたもの。
⇒くるま【車】
くるま‐がさ【車笠】
車輪状のかぶりがさ。
⇒くるま【車】
くるま‐かし【車貸し・車借】
①車で物を運んで賃銭を取ること。また、それを業とする人。今昔物語集29「その辺には―といふ者あまたあり」
②車を貸して賃銭をとること。また、その人。
⇒くるま【車】
くるま‐がたな【車刀】
護身のため、車中に備えておく刀。
⇒くるま【車】
くる‐まき【搯巻】
(→)「ろくろ」に同じ。太平記36「棟木をあげんとしけるに、―の縄に信濃皮むき千束入るべし」
くるま‐きしろい【車軋ろい】‥キシロヒ
車に乗る際に、その車や乗る人などの選択について争うこと。栄華物語初花「女房の―もありけれど」
⇒くるま【車】
くるま‐ぎり【車切り】
輪切り。太平記10「―・胴切・立破たてわりに仕つかまつり棄て度く」
⇒くるま【車】
ぐる‐まげ【ぐる髷】
(→)「ぐるぐるわげ」に同じ。
くるま‐げた【車桁】
井戸の滑車を釣っている桁。
⇒くるま【車】
くるま‐ごし【車輿】
牛車ぎっしゃから車輪を取り除いたような形の輿。院・親王・摂関の女むすめなどの乗用。
⇒くるま【車】
くるま‐ごめ【車籠め】
車に乗ったままであること。車ごと。蜻蛉日記下「―ひき入るるを見れば」
⇒くるま【車】
くるま‐ざ【車座】
大勢が輪になって座ること。
⇒くるま【車】
くるま‐ざき【車裂き】
戦国時代の刑。車2両に罪人の各片足を結びつけ、その肢体をひきさく。
⇒くるま【車】
くるま‐じ【車路】‥ヂ
車の行き通う路。車道。謡曲、百万「願ひも三つの―を都に帰る嬉しさよ」
⇒くるま【車】
くるま‐じかけ【車仕掛け】
器械の下に車をつけて移動しやすくしてあるもの。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃかい【車社会】‥クワイ
自動車によって生活がなりたつ社会。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃっきん【車借金】‥シヤク‥
江戸時代、数人連帯で借金し、毎月輪番で月賦でかえしたこと。
⇒くるま【車】
くるま‐ぜんしち【車善七】
江戸時代、江戸で、えた頭がしら弾左衛門の支配下にあって、代々、非人頭を勤めた者の称。
くるま‐ぞい【車副】‥ゾヒ
牛車ぎっしゃの左右について供をする者。源氏物語宿木「かの御前、随身、―、舎人などまで禄賜はす」
⇒くるま【車】
くるまぞう【車僧】
能。車に乗って行脚あんぎゃする僧が愛宕山の天狗太郎坊と禅問答の末、降伏ごうぶくする。
くるま‐ぞうし【車双紙】‥ザウ‥
手習草紙などの、包くるみ表紙にした本。
⇒くるま【車】
くるま‐そうぞく【車装束】‥サウ‥
車に装飾をすること。また、装飾をした車。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車代】
①車を買い、または車を借りた代金。
②車に乗った賃銭。車賃。また、その名目で支払う謝礼金。お車代。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車鯛】‥ダヒ
キントキダイ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。鯛型で、口と目は非常に大きい。体は淡赤色で、ひれの縁は黒い。幼魚では体側に明瞭な白色横帯がある。南日本産。食用。
⇒くるま【車】
くるま‐たけたば【車竹束】
竹束の下に車輪をとりつけ、回転・進退を自由にした防御用武具。→竹束。
⇒くるま【車】
くるま‐だち【車裁ち】
四つ身裁ちの一種で、身幅を広くとるための裁ち方。両身頃の用布全部を通して一定の幅を裁ち落とし、これを襟・掛襟とする。
⇒くるま【車】
くるま‐だて【車楯】
下部に車を装置して進退を自由にした楯。
⇒くるま【車】
くるまたて‐ろん【車立て論】
車あらそい。沙石集9「僧正の牛飼、御室の御車と―して」
⇒くるま【車】
くるま‐ちん【車賃】
自動車などに乗るための賃銭。また、荷車を雇って支払う賃銭。
⇒くるま【車】
くるま‐づか【車塚】
前方後円墳の俗称。
⇒くるま【車】
くるま‐つくり【車作り】
車を製作すること。また、その職人。
⇒くるま【車】
くるま‐つば【車鍔】
車輪の形に造った鍔。
⇒くるま【車】
くるま‐ど【車戸】
下に小さい車をつけ、開閉しやすくした戸。
⇒くるま【車】
くるま‐とう【車糖】‥タウ
上白・中白・三温さんおんなど、結晶の小さい精製糖の総称。
⇒くるま【車】
くるま‐とだな【車戸棚】
下に車輪をつけて動かしやすくした戸棚。
⇒くるま【車】
くるま‐どめ【車止め】
①車の通行を禁ずること。
②自動車などを動かないように止めておくこと。また、そのための器具。
③軌道の終端に、車両が線路外に逸走するのを防止するために設置する装置。
⇒くるま【車】
くるま‐ながもち【車長持】
大型の長持で、底に車をつけて移動しやすいようにしてあるもの。
車長持
⇒くるま【車】
くるま‐おおじ【車大路】‥オホヂ
①京都の三条粟田口から北へ向かい、黒谷へ至った道。
②京都の五条橋(今の松原橋)を渡って東山方面へ通ずる道。
くるま‐がえし【車返し】‥ガヘシ
①けわしい山路、聖域など、そこから先へは車が通れないために車を返す所。
②サクラの一品種。花は白く、大輪で5〜8弁。
⇒くるま【車】
くるま‐がえり【車返り・車翻り】‥ガヘリ
「もんどり」の一種。手をついて、続けざまに横に身を翻すこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がかり【車懸り】
①近世の越後流の陣法で、1番手・2番手・3番手と順次に分けておき、前が弱るに従って後が続き、循環して敵に攻めかかること。
②相撲や剣道で、勝ったものに新手が代わる代わるかかって行くこと。
⇒くるま【車】
くるま‐がき【車垣】
茶席の庭などに設ける垣で、萩などを束ねて半円形の輪状にしたもの。
⇒くるま【車】
くるま‐がさ【車笠】
車輪状のかぶりがさ。
⇒くるま【車】
くるま‐かし【車貸し・車借】
①車で物を運んで賃銭を取ること。また、それを業とする人。今昔物語集29「その辺には―といふ者あまたあり」
②車を貸して賃銭をとること。また、その人。
⇒くるま【車】
くるま‐がたな【車刀】
護身のため、車中に備えておく刀。
⇒くるま【車】
くる‐まき【搯巻】
(→)「ろくろ」に同じ。太平記36「棟木をあげんとしけるに、―の縄に信濃皮むき千束入るべし」
くるま‐きしろい【車軋ろい】‥キシロヒ
車に乗る際に、その車や乗る人などの選択について争うこと。栄華物語初花「女房の―もありけれど」
⇒くるま【車】
くるま‐ぎり【車切り】
輪切り。太平記10「―・胴切・立破たてわりに仕つかまつり棄て度く」
⇒くるま【車】
ぐる‐まげ【ぐる髷】
(→)「ぐるぐるわげ」に同じ。
くるま‐げた【車桁】
井戸の滑車を釣っている桁。
⇒くるま【車】
くるま‐ごし【車輿】
牛車ぎっしゃから車輪を取り除いたような形の輿。院・親王・摂関の女むすめなどの乗用。
⇒くるま【車】
くるま‐ごめ【車籠め】
車に乗ったままであること。車ごと。蜻蛉日記下「―ひき入るるを見れば」
⇒くるま【車】
くるま‐ざ【車座】
大勢が輪になって座ること。
⇒くるま【車】
くるま‐ざき【車裂き】
戦国時代の刑。車2両に罪人の各片足を結びつけ、その肢体をひきさく。
⇒くるま【車】
くるま‐じ【車路】‥ヂ
車の行き通う路。車道。謡曲、百万「願ひも三つの―を都に帰る嬉しさよ」
⇒くるま【車】
くるま‐じかけ【車仕掛け】
器械の下に車をつけて移動しやすくしてあるもの。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃかい【車社会】‥クワイ
自動車によって生活がなりたつ社会。
⇒くるま【車】
くるま‐しゃっきん【車借金】‥シヤク‥
江戸時代、数人連帯で借金し、毎月輪番で月賦でかえしたこと。
⇒くるま【車】
くるま‐ぜんしち【車善七】
江戸時代、江戸で、えた頭がしら弾左衛門の支配下にあって、代々、非人頭を勤めた者の称。
くるま‐ぞい【車副】‥ゾヒ
牛車ぎっしゃの左右について供をする者。源氏物語宿木「かの御前、随身、―、舎人などまで禄賜はす」
⇒くるま【車】
くるまぞう【車僧】
能。車に乗って行脚あんぎゃする僧が愛宕山の天狗太郎坊と禅問答の末、降伏ごうぶくする。
くるま‐ぞうし【車双紙】‥ザウ‥
手習草紙などの、包くるみ表紙にした本。
⇒くるま【車】
くるま‐そうぞく【車装束】‥サウ‥
車に装飾をすること。また、装飾をした車。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車代】
①車を買い、または車を借りた代金。
②車に乗った賃銭。車賃。また、その名目で支払う謝礼金。お車代。
⇒くるま【車】
くるま‐だい【車鯛】‥ダヒ
キントキダイ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。鯛型で、口と目は非常に大きい。体は淡赤色で、ひれの縁は黒い。幼魚では体側に明瞭な白色横帯がある。南日本産。食用。
⇒くるま【車】
くるま‐たけたば【車竹束】
竹束の下に車輪をとりつけ、回転・進退を自由にした防御用武具。→竹束。
⇒くるま【車】
くるま‐だち【車裁ち】
四つ身裁ちの一種で、身幅を広くとるための裁ち方。両身頃の用布全部を通して一定の幅を裁ち落とし、これを襟・掛襟とする。
⇒くるま【車】
くるま‐だて【車楯】
下部に車を装置して進退を自由にした楯。
⇒くるま【車】
くるまたて‐ろん【車立て論】
車あらそい。沙石集9「僧正の牛飼、御室の御車と―して」
⇒くるま【車】
くるま‐ちん【車賃】
自動車などに乗るための賃銭。また、荷車を雇って支払う賃銭。
⇒くるま【車】
くるま‐づか【車塚】
前方後円墳の俗称。
⇒くるま【車】
くるま‐つくり【車作り】
車を製作すること。また、その職人。
⇒くるま【車】
くるま‐つば【車鍔】
車輪の形に造った鍔。
⇒くるま【車】
くるま‐ど【車戸】
下に小さい車をつけ、開閉しやすくした戸。
⇒くるま【車】
くるま‐とう【車糖】‥タウ
上白・中白・三温さんおんなど、結晶の小さい精製糖の総称。
⇒くるま【車】
くるま‐とだな【車戸棚】
下に車輪をつけて動かしやすくした戸棚。
⇒くるま【車】
くるま‐どめ【車止め】
①車の通行を禁ずること。
②自動車などを動かないように止めておくこと。また、そのための器具。
③軌道の終端に、車両が線路外に逸走するのを防止するために設置する装置。
⇒くるま【車】
くるま‐ながもち【車長持】
大型の長持で、底に車をつけて移動しやすいようにしてあるもの。
車長持
 ⇒くるま【車】
くるま‐にんぎょう【車人形】‥ギヤウ
①操あやつり人形で、人形を轆轤ろくろ仕掛けで動かす装置。
②人形遣いの一様式。一人の遣手つかいてが自由自在に回転する小さな箱車に腰を掛け、遣手の足指と人形の足とを結びつけて遣う。出語でがたりは説経浄瑠璃を使用。天保(1830〜1844)末期、八王子在に発達し、現存。
車人形の轆轤車
提供:東京都
⇒くるま【車】
くるま‐にんぎょう【車人形】‥ギヤウ
①操あやつり人形で、人形を轆轤ろくろ仕掛けで動かす装置。
②人形遣いの一様式。一人の遣手つかいてが自由自在に回転する小さな箱車に腰を掛け、遣手の足指と人形の足とを結びつけて遣う。出語でがたりは説経浄瑠璃を使用。天保(1830〜1844)末期、八王子在に発達し、現存。
車人形の轆轤車
提供:東京都
 八王子車人形
提供:東京都
八王子車人形
提供:東京都
 ⇒くるま【車】
⇒くるま【車】
広辞苑に「苦しい」で始まるの検索結果 1-2。