複数辞典一括検索+![]()
![]()
いき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ🔗⭐🔉
いき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ
〔自五〕
(→)「ゆきあう」に同じ。伊勢物語「狩りしありきけるに―・ひて」
いき‐う・す【行き失す】🔗⭐🔉
いき‐う・す【行き失す】
〔自下二〕
(→)「ゆきうす」に同じ。能因本枕草子御前に人々あまた「いづちもいづちも―・せなばやと思ふに」
いき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ🔗⭐🔉
いき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ
(→)「ゆきかえり」に同じ。
いき‐がかり【行き掛り】🔗⭐🔉
いき‐がかり【行き掛り】
(→)「ゆきがかり」に同じ。
○息が切れるいきがきれる
①息ぎれがする。転じて、ものごとに長く堪えられない。
②息がとまる。死ぬ。
⇒いき【息】
いき‐かく・る【行き隠る】🔗⭐🔉
いき‐かく・る【行き隠る】
〔自下二〕
(→)「ゆきかくる」に同じ。
いき‐がけ【行き掛け】🔗⭐🔉
いき‐がけ【行き掛け】
(→)「ゆきがけ」に同じ。
いき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ🔗⭐🔉
いき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ
〔自五〕
(→)「ゆきかよう」に同じ。伊勢物語「何のよき事と思ひて―・ひければ」
いき‐しな【行きしな】🔗⭐🔉
いき‐しな【行きしな】
(→)「ゆきしな」に同じ。
いき‐す・ぎる【行き過ぎる】🔗⭐🔉
いき‐す・ぎる【行き過ぎる】
〔自上一〕[文]いきす・ぐ(上二)
(→)「ゆきすぎる」に同じ。
いき‐ちがい【行き違い】‥チガヒ🔗⭐🔉
いき‐ちがい【行き違い】‥チガヒ
(→)「ゆきちがい」に同じ。
いき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ🔗⭐🔉
いき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ
〔自五〕
(→)「ゆきちがう」に同じ。
いき‐つ・く【行き着く】🔗⭐🔉
いき‐つ・く【行き着く】
〔自五〕
(→)「ゆきつく」に同じ。
いき‐づまり【行き詰り】🔗⭐🔉
いき‐づまり【行き詰り】
(→)「ゆきづまり」に同じ。
いき‐づま・る【行き詰まる】🔗⭐🔉
いき‐づま・る【行き詰まる】
〔自五〕
(→)「ゆきづまる」に同じ。
いき‐づめ【行き詰め】🔗⭐🔉
いき‐づめ【行き詰め】
(→)「ゆきづめ」に同じ。
いき‐どころ【行き所】🔗⭐🔉
いき‐どころ【行き所】
(→)「ゆきどころ」に同じ。
いき‐どま・る【行き止まる】🔗⭐🔉
いき‐どま・る【行き止まる】
〔自五〕
(→)「ゆきどまる」に同じ。
いき‐なり【行き成り】🔗⭐🔉
いき‐なり【行き成り】
[一]〔名〕
事がらのなりゆき。また、なりゆきにまかせること。十分考えないですること。いきなりさんぼう。いきなりほうだい。洒落本、傾城買指南所「先づおれも、たうとう勘当をくらつた。是からは―といふ世界だ」
[二]〔副〕
(近世は多く「に」を伴って)だしぬけに。突然。または、直接。じかに。浮世床初「―に胸ぐらよ」。「横道から―とびだす」「下書きもせず―清書する」
⇒いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】
⇒いきなり‐だご【生き成り団子】
⇒いきなり‐ほうだい【行き成り放題】
いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】🔗⭐🔉
いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】
(→)「いきなりほうだい」に同じ。ゆきなりさんぼう。誹風柳多留10「―男の雨やどり」
⇒いき‐なり【行き成り】
いきなり‐ほうだい【行き成り放題】‥ハウ‥🔗⭐🔉
いきなり‐ほうだい【行き成り放題】‥ハウ‥
なるにまかせてかまわないこと。ゆきあたりばったり。
⇒いき‐なり【行き成り】
○意気に燃えるいきにもえる
ある事をしようという積極的な気持が盛んになる。
⇒い‐き【意気】
いき‐ぶれ【行き触れ】🔗⭐🔉
いき‐ぶれ【行き触れ】
触穢しょくえの一つ。死者などけがれたものに行き逢ってそのけがれにふれること。ふみあわせ。ゆきぶれ。源氏物語夕顔「いかなる―にかからせ給ふぞや」
いけ‐いけ【行け行け】🔗⭐🔉
いけ‐いけ【行け行け】
(普通、平仮名で書く)
①深く考えることなく調子に乗って突っ走ること。
②派手で軽薄なこと。
おこない【行い】オコナヒ🔗⭐🔉
おこない【行い】オコナヒ
①しわざ。ふるまい。動作。
②品行。行状。身持ち。「―がよくない」
③僧侶が仏道を修めること。また、仏事を行うこと。
④近畿とその周辺で、年頭の農祈願の祭。滋賀県では、寺行事として頭屋とうや制で行なっている。
⇒おこない‐がち【行い勝ち】
⇒おこない‐ごえ【行い声】
⇒おこない‐びと【行い人】
おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥🔗⭐🔉
おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥
仏事の勤めばかりして日を送ること。紫式部日記「―に口ひひらかし」
⇒おこない【行い】
おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ🔗⭐🔉
おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ
読経する声。夫木和歌抄34「苔深きとよらの寺は山伏の―もさびしかりけり」
⇒おこない【行い】
おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥🔗⭐🔉
おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥
〔自五〕
①仏道修行にいそしむ。平家物語10「信濃の国善光寺に―・して」
②神妙らしくふるまう。殊勝げにふるまう。
おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥🔗⭐🔉
おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥
仏道修行者。源氏物語若紫「なにがし寺といふところにかしこき―侍る」
⇒おこない【行い】
おこな・う【行う】オコナフ🔗⭐🔉
おこな・う【行う】オコナフ
[一]〔他五〕
物事を一定の方式に従って処理する。
①物事をなす。とり扱う。執行する。宇津保物語蔵開中「御座所しつらはせ給ひ、事―・はせ給ふ」。源氏物語紅葉賀「宰相二人、左衛門督、右衛門督、左右の楽のこと―・ふ」。大鏡時平「左右の大臣に世の政を―・ふべきよし宣旨くださしめ給へりしに」。「試験を―・う」「広く世に―・われる」
②(規則を守って)修行する。勤行をする。また、仏事をいとなむ。宇津保物語忠乞「山にこもりて―・はむ。世の中は心うきもの」。源氏物語明石「仁王会など―・はるべし」
③施し与える。配分する。宇津保物語初秋「凉・仲忠が紀伊国の九日の禄をまだ―・はぬかな」
④(上の命令文をうけ)手はずを示す。指図する。今昔物語集19「行きてかれ搦めよと―・へば」
⑤刑罰に処する。処分する。保元物語「参ぜざらん者どもをば死罪に―・ふべし」
⑥食事をする。食べる。狂言、宗論「たけ一寸ばかりに料理して―・へば、あらうまやと思ひて涙がほろりとこぼるる」
⑦手ごめにする。滑稽本、続膝栗毛「きやつめを―・つてゐるにちがひはねえ」
[二]〔自四〕
ものごとが一定の方式に従って進行する。徒然草「しばしも滞らず、ただちに―・ひゆくものなり」
ぎょう【行】ギヤウ🔗⭐🔉
ぎょうぎょう‐し【仰仰子・行行子】ギヤウギヤウ‥🔗⭐🔉
ぎょうぎょう‐し【仰仰子・行行子】ギヤウギヤウ‥
〔動〕(鳴き声から)ヨシキリの異称。〈[季]夏〉
くだり【行】🔗⭐🔉
くだり【行】
①上から下までの列。縦の線。万葉集14「風の音の遠き吾妹が着せし衣きぬ手本たもとの―まよひ来にけり」
②文章の一行。また、それを数える語。源氏物語梅枝「ただ三―ばかりに」。「三―半」
⇒くだり‐せば【行狭】
こう【行】カウ🔗⭐🔉
こう‐こう【行行】カウカウ🔗⭐🔉
こう‐こう【行行】カウカウ
次第に進みゆくこと。また、そのさま。和漢朗詠集「―として重ねて―たり」
ゆかく【行かく】🔗⭐🔉
ゆかく【行かく】
(行クのク語法)行くこと。万葉集14「児ろが金門かなとよ―し良えしも」
ゆかず‐ごけ【行かず後家】🔗⭐🔉
ゆかず‐ごけ【行かず後家】
嫁入しないままで老いた女。
ゆき【行き・往き】🔗⭐🔉
ゆき【行き・往き】
(イキとも)
①行くこと。歩み進むこと。また、旅行すること。旅。古事記下「君が―日け長くなりぬ」
②目的の地に向かって出て行くこと。また、その道程。往路。ゆきみち。「―はよいよい帰りはこわい」「岡山発東京―」↔帰り
⇒行き大名の帰り乞食
ゆき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ🔗⭐🔉
ゆき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ
[一]〔自五〕
①進んで行って出あう。でくわす。いきあう。万葉集12「道に―・ひて」
②ぴったり一致する。愚管抄3「この仏法のかた王法のかたの二道の道理のかくひしと―・ひぬれば」
[二]〔他下二〕
行きあうようにさせる。交差させる。古事記下「鶺鴒まなばしら尾―・へ」
ゆき‐あし【行き足・行き脚】🔗⭐🔉
ゆき‐あし【行き足・行き脚】
船などが、そのままの速さで走り続けること。いきあし。「―が止まる」
ゆき‐あわ・す【行き合わす】‥アハス🔗⭐🔉
ゆき‐あわ・す【行き合わす】‥アハス
[一]〔自五〕
(→)「行き合わせる」に同じ。
[二]〔自下二〕
⇒ゆきあわせる(下一)
ゆき‐あわ・せる【行き合わせる】‥アハセル🔗⭐🔉
ゆき‐あわ・せる【行き合わせる】‥アハセル
〔自下一〕[文]ゆきあは・す(下二)
行った所でたまたま出合う。「会場で知人と―・せた」「事故現場に―・せる」
ゆき‐いた・る【行き至る】🔗⭐🔉
ゆき‐いた・る【行き至る】
〔自四〕
そこへ行きつく。到達する。
ゆき‐う・す【行き失す】🔗⭐🔉
ゆき‐う・す【行き失す】
〔自下二〕
ゆくえが知れなくなる。いきうす。
ゆき‐かい【行き交い・往き交い】‥カヒ🔗⭐🔉
ゆき‐かい【行き交い・往き交い】‥カヒ
行きかうこと。ゆきき。往来。
⇒ゆきかい‐じ【行き交い路】
ゆきかい‐じ【行き交い路】‥カヒヂ🔗⭐🔉
ゆきかい‐じ【行き交い路】‥カヒヂ
行き交う道。往来の途中。古今和歌集哀傷「かりそめの―とぞ思ひこし」
⇒ゆき‐かい【行き交い・往き交い】
ゆき‐か・う【行き交う・往き交う】‥カフ🔗⭐🔉
ゆき‐か・う【行き交う・往き交う】‥カフ
〔自五〕
あるものは行き、あるものは来る。行ったり来たりする。また、行き通う。源氏物語桐壺「御使の―・ふほどもなきに」
ゆき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ🔗⭐🔉
ゆき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ
ゆきとかえり。往復。いきかえり。
ゆき‐かえ・る【行き帰る・往き還る】‥カヘル🔗⭐🔉
ゆき‐かえ・る【行き帰る・往き還る】‥カヘル
〔自五〕
①出て行って、また、かえる。ゆききする。万葉集6「―・り常にわが見し香椎潟」
②年月など、古いものが去って、またあらたにやってくる。万葉集20「あらたまの年―・り春立たば」
ゆき‐がかり【行き掛り】🔗⭐🔉
ゆき‐がかり【行き掛り】
(イキガカリとも)
①行きかかるついで。行きがけ。
②すでに物事が進行しつつあること。また、物事にかかり合いが出来ていること。それまでの関係・事情。「―上じょうやめられない」「今までの―をさらりと捨てる」
ゆき‐かか・る【行き掛かる】🔗⭐🔉
ゆき‐かか・る【行き掛かる】
〔自五〕
①行ってかかわる。源氏物語須磨「うけひかざらむものゆゑ、―・りて空しうかへらむ後手うしろでも」
②行こうとする。行きはじめる。
③行ってそこにさしかかる。通りかかる。
ゆき‐かく・る【行き隠る】🔗⭐🔉
ゆき‐かく・る【行き隠る】
〔自四・下二〕
行って隠れる。行って姿が見えなくなる。いきかくる。万葉集6「―・る島の埼々」
ゆき‐かぐ・る【行きかぐる】🔗⭐🔉
ゆき‐かぐ・る【行きかぐる】
〔自下二〕
未詳。求婚する意か。一説に、寄り集まる。万葉集9「水門みなと入りに船漕ぐごとく―・れ人のいふ時」
ゆき‐がけ【行き掛け】🔗⭐🔉
ゆき‐がけ【行き掛け】
(イキガケとも)
①行く途中。行くついで。「―に用を足す」
②行こうとする時。「―に客が来る」
⇒行き掛けの駄賃
○行き掛けの駄賃ゆきがけのだちん
(問屋へ駄馬をひいて行くついでに、荷物を馬につけて運び、運賃を自分の所得とすることから)事のついでに他の事をするたとえ。
⇒ゆき‐がけ【行き掛け】
○行き掛けの駄賃ゆきがけのだちん🔗⭐🔉
○行き掛けの駄賃ゆきがけのだちん
(問屋へ駄馬をひいて行くついでに、荷物を馬につけて運び、運賃を自分の所得とすることから)事のついでに他の事をするたとえ。
⇒ゆき‐がけ【行き掛け】
ゆき‐かご【雪籠】
劇場で、小さく刻んだ紙を入れて日覆ひおおい2に吊す竹製の籠。紐で揺り動かし、中の紙を落として降雪に見せる。
ゆき‐がこい【雪囲い】‥ガコヒ
①草木などの霜雪の害を防ぐために、藁わら・筵むしろなどで囲っておおうこと。また、そのもの。
雪囲い
撮影:関戸 勇
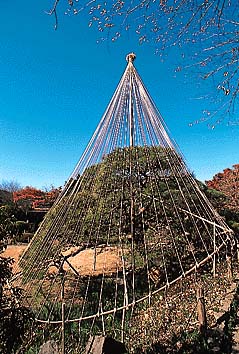 ②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉
ゆき‐かぜ【雪風】
雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」
ゆき‐かた【行き方】
①行く道順。行く方法。
②やりかた。しかた。「各人各様の―」
ゆき‐かた【悠紀方】
悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方
ゆき‐がた【行き方】
行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」
ゆき‐がた【雪形】
山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら
ゆき‐か・つ【行きかつ】
〔自下二〕
行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」
ゆき‐がっせん【雪合戦】
雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉
ゆき‐がて【雪糅て】
雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」
ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ
⇒ぎょうがまえ
ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ
〔自五〕
かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」
ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル
〔自四〕
進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」
ゆき‐き【行き来・往き来】
(イキキとも)
①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」
②交際。つきあい。「―が絶える」
ゆき‐ぎえ【雪消え】
(→)「ゆきげ」1に同じ。
⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】
ゆきぎえ‐づき【雪消月】
陰暦2月の異称。
⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】
ゆき・く【行き来・往き来】
〔自カ変〕
行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」
ゆき‐ぐつ【雪沓】
雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐに【雪国】
降雪量の多い地方。雪の多い国。
ゆきぐに【雪国】
小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。
ゆき‐くぼ【雪窪】
山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。
ゆき‐ぐも【雪雲】
雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐもり【雪曇り】
雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。
ゆき‐くら・す【行き暮す】
〔自四〕
日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」
ゆき‐ぐれ【行き暮れ】
行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」
ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】
雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」
ゆき‐く・れる【行き暮れる】
〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)
行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」
ゆき‐げ【雪気】
雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」
ゆき‐げ【雪消】
①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」
②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉
⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】
⇒ゆきげ‐みず【雪消水】
ゆき‐けし【雪消し】
旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。
ゆき‐げしき【雪景色】
雪の降る景色。雪の積もった景色。
ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ
積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。
ゆき‐げた【行桁】
橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」
ゆき‐げた【雪下駄】
雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉
ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ
奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ
雪どけの水。〈[季]春〉
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆき‐けむり【雪煙】
雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉
ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ
雪が降るようにと神仏に祈願すること。
ゆき‐こかし【雪転し】
(→)「ゆきころがし」に同じ。
ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】
(→)雪袴ゆきばかまに同じ。
ゆき‐ごや【雪小屋】
(長野県で)正月小屋のこと。
ゆき‐ころがし【雪転がし】
雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。
ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ
積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉
ゆき‐さき【行先】
⇒ゆくさき
ゆき‐さけ【雪裂け】
降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。
ゆき‐ざさ【雪笹】
ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。
ゆきざさ
②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉
ゆき‐かぜ【雪風】
雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」
ゆき‐かた【行き方】
①行く道順。行く方法。
②やりかた。しかた。「各人各様の―」
ゆき‐かた【悠紀方】
悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方
ゆき‐がた【行き方】
行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」
ゆき‐がた【雪形】
山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら
ゆき‐か・つ【行きかつ】
〔自下二〕
行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」
ゆき‐がっせん【雪合戦】
雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉
ゆき‐がて【雪糅て】
雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」
ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ
⇒ぎょうがまえ
ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ
〔自五〕
かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」
ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル
〔自四〕
進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」
ゆき‐き【行き来・往き来】
(イキキとも)
①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」
②交際。つきあい。「―が絶える」
ゆき‐ぎえ【雪消え】
(→)「ゆきげ」1に同じ。
⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】
ゆきぎえ‐づき【雪消月】
陰暦2月の異称。
⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】
ゆき・く【行き来・往き来】
〔自カ変〕
行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」
ゆき‐ぐつ【雪沓】
雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐに【雪国】
降雪量の多い地方。雪の多い国。
ゆきぐに【雪国】
小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。
ゆき‐くぼ【雪窪】
山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。
ゆき‐ぐも【雪雲】
雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐもり【雪曇り】
雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。
ゆき‐くら・す【行き暮す】
〔自四〕
日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」
ゆき‐ぐれ【行き暮れ】
行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」
ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】
雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」
ゆき‐く・れる【行き暮れる】
〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)
行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」
ゆき‐げ【雪気】
雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」
ゆき‐げ【雪消】
①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」
②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉
⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】
⇒ゆきげ‐みず【雪消水】
ゆき‐けし【雪消し】
旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。
ゆき‐げしき【雪景色】
雪の降る景色。雪の積もった景色。
ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ
積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。
ゆき‐げた【行桁】
橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」
ゆき‐げた【雪下駄】
雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉
ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ
奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ
雪どけの水。〈[季]春〉
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆき‐けむり【雪煙】
雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉
ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ
雪が降るようにと神仏に祈願すること。
ゆき‐こかし【雪転し】
(→)「ゆきころがし」に同じ。
ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】
(→)雪袴ゆきばかまに同じ。
ゆき‐ごや【雪小屋】
(長野県で)正月小屋のこと。
ゆき‐ころがし【雪転がし】
雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。
ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ
積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉
ゆき‐さき【行先】
⇒ゆくさき
ゆき‐さけ【雪裂け】
降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。
ゆき‐ざさ【雪笹】
ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。
ゆきざさ
 ゆき‐さらし【雪晒し】
雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」
ゆき‐さ・る【行き去る】
〔自五〕
去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」
ゆき‐じ【雪路】‥ヂ
雪の降り積もる路。ゆきみち。
ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ
雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。
ゆき‐しつ【雪質】
雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。
ゆき‐しな【行きしな】
(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」
ゆき‐しまき【雪しまき】
雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉
ゆき‐じもの【雪じもの】
〔枕〕
「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」
ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ
中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。
ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ
雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉
ゆき‐しる【雪汁】
雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」
ゆき‐しろ【雪代】
(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉
ゆき‐じろ【雪白】
①雪のように白いこと。
②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」
③三盆白さんぼんじろの異称。
ゆき‐すぎ【行過ぎ】
(イキスギとも)
①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。
②程度をこえてすること。
⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。
⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】
ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】
〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)
(イキスギルとも)
①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。
②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」
③程度を越す。「―・ぎた規制」
ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」
②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」
③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」
⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
ゆき‐ずり【雪摺り】
鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。
ゆきずり‐がさ【雪滑笠】
上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。
ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆき‐ぞら【雪空】
いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉
ゆき‐さらし【雪晒し】
雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」
ゆき‐さ・る【行き去る】
〔自五〕
去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」
ゆき‐じ【雪路】‥ヂ
雪の降り積もる路。ゆきみち。
ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ
雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。
ゆき‐しつ【雪質】
雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。
ゆき‐しな【行きしな】
(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」
ゆき‐しまき【雪しまき】
雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉
ゆき‐じもの【雪じもの】
〔枕〕
「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」
ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ
中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。
ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ
雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉
ゆき‐しる【雪汁】
雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」
ゆき‐しろ【雪代】
(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉
ゆき‐じろ【雪白】
①雪のように白いこと。
②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」
③三盆白さんぼんじろの異称。
ゆき‐すぎ【行過ぎ】
(イキスギとも)
①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。
②程度をこえてすること。
⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。
⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】
ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】
〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)
(イキスギルとも)
①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。
②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」
③程度を越す。「―・ぎた規制」
ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」
②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」
③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」
⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
ゆき‐ずり【雪摺り】
鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。
ゆきずり‐がさ【雪滑笠】
上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。
ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆき‐ぞら【雪空】
いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉
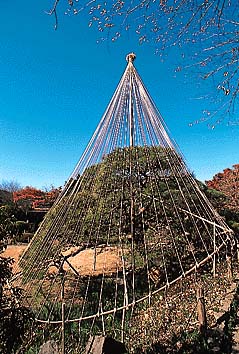 ②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉
ゆき‐かぜ【雪風】
雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」
ゆき‐かた【行き方】
①行く道順。行く方法。
②やりかた。しかた。「各人各様の―」
ゆき‐かた【悠紀方】
悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方
ゆき‐がた【行き方】
行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」
ゆき‐がた【雪形】
山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら
ゆき‐か・つ【行きかつ】
〔自下二〕
行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」
ゆき‐がっせん【雪合戦】
雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉
ゆき‐がて【雪糅て】
雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」
ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ
⇒ぎょうがまえ
ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ
〔自五〕
かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」
ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル
〔自四〕
進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」
ゆき‐き【行き来・往き来】
(イキキとも)
①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」
②交際。つきあい。「―が絶える」
ゆき‐ぎえ【雪消え】
(→)「ゆきげ」1に同じ。
⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】
ゆきぎえ‐づき【雪消月】
陰暦2月の異称。
⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】
ゆき・く【行き来・往き来】
〔自カ変〕
行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」
ゆき‐ぐつ【雪沓】
雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐに【雪国】
降雪量の多い地方。雪の多い国。
ゆきぐに【雪国】
小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。
ゆき‐くぼ【雪窪】
山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。
ゆき‐ぐも【雪雲】
雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐもり【雪曇り】
雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。
ゆき‐くら・す【行き暮す】
〔自四〕
日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」
ゆき‐ぐれ【行き暮れ】
行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」
ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】
雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」
ゆき‐く・れる【行き暮れる】
〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)
行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」
ゆき‐げ【雪気】
雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」
ゆき‐げ【雪消】
①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」
②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉
⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】
⇒ゆきげ‐みず【雪消水】
ゆき‐けし【雪消し】
旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。
ゆき‐げしき【雪景色】
雪の降る景色。雪の積もった景色。
ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ
積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。
ゆき‐げた【行桁】
橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」
ゆき‐げた【雪下駄】
雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉
ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ
奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ
雪どけの水。〈[季]春〉
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆき‐けむり【雪煙】
雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉
ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ
雪が降るようにと神仏に祈願すること。
ゆき‐こかし【雪転し】
(→)「ゆきころがし」に同じ。
ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】
(→)雪袴ゆきばかまに同じ。
ゆき‐ごや【雪小屋】
(長野県で)正月小屋のこと。
ゆき‐ころがし【雪転がし】
雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。
ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ
積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉
ゆき‐さき【行先】
⇒ゆくさき
ゆき‐さけ【雪裂け】
降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。
ゆき‐ざさ【雪笹】
ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。
ゆきざさ
②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉
ゆき‐かぜ【雪風】
雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」
ゆき‐かた【行き方】
①行く道順。行く方法。
②やりかた。しかた。「各人各様の―」
ゆき‐かた【悠紀方】
悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方
ゆき‐がた【行き方】
行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」
ゆき‐がた【雪形】
山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら
ゆき‐か・つ【行きかつ】
〔自下二〕
行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」
ゆき‐がっせん【雪合戦】
雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉
ゆき‐がて【雪糅て】
雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」
ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ
⇒ぎょうがまえ
ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ
〔自五〕
かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」
ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル
〔自四〕
進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」
ゆき‐き【行き来・往き来】
(イキキとも)
①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」
②交際。つきあい。「―が絶える」
ゆき‐ぎえ【雪消え】
(→)「ゆきげ」1に同じ。
⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】
ゆきぎえ‐づき【雪消月】
陰暦2月の異称。
⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】
ゆき・く【行き来・往き来】
〔自カ変〕
行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」
ゆき‐ぐつ【雪沓】
雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐに【雪国】
降雪量の多い地方。雪の多い国。
ゆきぐに【雪国】
小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。
ゆき‐くぼ【雪窪】
山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。
ゆき‐ぐも【雪雲】
雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉
ゆき‐ぐもり【雪曇り】
雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。
ゆき‐くら・す【行き暮す】
〔自四〕
日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」
ゆき‐ぐれ【行き暮れ】
行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」
ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】
雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」
ゆき‐く・れる【行き暮れる】
〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)
行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」
ゆき‐げ【雪気】
雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」
ゆき‐げ【雪消】
①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」
②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉
⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】
⇒ゆきげ‐みず【雪消水】
ゆき‐けし【雪消し】
旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。
ゆき‐げしき【雪景色】
雪の降る景色。雪の積もった景色。
ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ
積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。
ゆき‐げた【行桁】
橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」
ゆき‐げた【雪下駄】
雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉
ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ
奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ
雪どけの水。〈[季]春〉
⇒ゆき‐げ【雪消】
ゆき‐けむり【雪煙】
雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉
ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ
雪が降るようにと神仏に祈願すること。
ゆき‐こかし【雪転し】
(→)「ゆきころがし」に同じ。
ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】
(→)雪袴ゆきばかまに同じ。
ゆき‐ごや【雪小屋】
(長野県で)正月小屋のこと。
ゆき‐ころがし【雪転がし】
雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。
ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ
積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉
ゆき‐さき【行先】
⇒ゆくさき
ゆき‐さけ【雪裂け】
降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。
ゆき‐ざさ【雪笹】
ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。
ゆきざさ
 ゆき‐さらし【雪晒し】
雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」
ゆき‐さ・る【行き去る】
〔自五〕
去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」
ゆき‐じ【雪路】‥ヂ
雪の降り積もる路。ゆきみち。
ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ
雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。
ゆき‐しつ【雪質】
雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。
ゆき‐しな【行きしな】
(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」
ゆき‐しまき【雪しまき】
雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉
ゆき‐じもの【雪じもの】
〔枕〕
「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」
ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ
中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。
ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ
雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉
ゆき‐しる【雪汁】
雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」
ゆき‐しろ【雪代】
(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉
ゆき‐じろ【雪白】
①雪のように白いこと。
②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」
③三盆白さんぼんじろの異称。
ゆき‐すぎ【行過ぎ】
(イキスギとも)
①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。
②程度をこえてすること。
⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。
⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】
ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】
〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)
(イキスギルとも)
①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。
②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」
③程度を越す。「―・ぎた規制」
ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」
②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」
③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」
⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
ゆき‐ずり【雪摺り】
鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。
ゆきずり‐がさ【雪滑笠】
上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。
ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆき‐ぞら【雪空】
いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉
ゆき‐さらし【雪晒し】
雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」
ゆき‐さ・る【行き去る】
〔自五〕
去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」
ゆき‐じ【雪路】‥ヂ
雪の降り積もる路。ゆきみち。
ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ
雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。
ゆき‐しつ【雪質】
雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。
ゆき‐しな【行きしな】
(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」
ゆき‐しまき【雪しまき】
雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉
ゆき‐じもの【雪じもの】
〔枕〕
「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」
ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ
中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。
ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ
雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉
ゆき‐しる【雪汁】
雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」
ゆき‐しろ【雪代】
(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉
ゆき‐じろ【雪白】
①雪のように白いこと。
②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」
③三盆白さんぼんじろの異称。
ゆき‐すぎ【行過ぎ】
(イキスギとも)
①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。
②程度をこえてすること。
⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】
でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。
⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】
ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】
〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)
(イキスギルとも)
①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。
②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」
③程度を越す。「―・ぎた規制」
ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」
②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」
③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」
⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
ゆき‐ずり【雪摺り】
鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。
ゆきずり‐がさ【雪滑笠】
上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。
ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。
⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
ゆき‐ぞら【雪空】
いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉
ゆき‐か・つ【行きかつ】🔗⭐🔉
ゆき‐か・つ【行きかつ】
〔自下二〕
行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」
ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ🔗⭐🔉
ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ
〔自五〕
かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」
ゆき‐さ・る【行き去る】🔗⭐🔉
ゆき‐さ・る【行き去る】
〔自五〕
去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」
ゆき‐しな【行きしな】🔗⭐🔉
ゆき‐しな【行きしな】
(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」
ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】🔗⭐🔉
ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】
〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)
(イキスギルとも)
①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。
②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」
③程度を越す。「―・ぎた規制」
ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】🔗⭐🔉
ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】
①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」
②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」
③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」
⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】
⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】
○行き大名の帰り乞食ゆきだいみょうのかえりこじき🔗⭐🔉
○行き大名の帰り乞食ゆきだいみょうのかえりこじき
旅行の最中は贅沢ぜいたくをし、帰る時は旅費が欠乏するということ。
⇒ゆき【行き・往き】
ゆき‐だおれ【行き倒れ・行き斃れ】‥ダフレ
病気や空腹、疲れや寒さのために路上に倒れ、あるいは死ぬこと。また、その人。いきだおれ。「―の人を助ける」
ゆき‐たが・う【行き違ふ】‥タガフ
[一]〔自四〕
(→)「ゆきちがう」(自五)に同じ。
[二]〔自下二〕
(→)「ゆきちがえる」に同じ。
ゆき‐たけ【裄丈】
①衣服のゆきとたけ。いきたけ。
②転じて、物事の都合。前後の関係。
ゆき‐たたき【雪叩き】
物に積もりまたは付着した雪をたたいて落とすこと。
ゆき‐た・つ【行き立つ】
〔自五〕
(イキタツとも)
①出立する。
②物事が進行して成り立つ。できあがる。
③生活の方法がたつ。暮しが立ち行く。
ゆき‐だまり【雪溜まり】
雪の吹きだまり。
ゆき‐だるま【雪達磨】
大小二つの雪の玉を重ね、木炭・炭団たどんなどで目鼻をつけたもの。〈[季]冬〉
⇒ゆきだるま‐しき【雪達磨式】
ゆきだるま‐しき【雪達磨式】
(雪達磨を作る時、雪の塊を転がすと雪が付着して見る見る大きくなるように)次から次へと目に見えてふえて行くさま。「借金が―にふえる」
⇒ゆき‐だるま【雪達磨】
ゆきち【諭吉】
⇒ふくざわゆきち(福沢諭吉)
ゆき‐ちがい【行違い】‥チガヒ
(イキチガイとも)
①すれちがいになって、出会わないでしまうこと。「―になる」
②意志がうまく通じなくて、くいちがうこと。手筈が狂うこと。「感情的な―が生じる」「計画に―を生じた」
⇒ゆきちがい‐ざま【行違い様】
ゆきちがい‐ざま【行違い様】‥チガヒ‥
行きちがう瞬間。
⇒ゆき‐ちがい【行違い】
ゆき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ
[一]〔自五〕
(イキチガウとも)
①行き来する。行き交う。源氏物語竹河「―・ふ車の音、先追ふ声々も」
②互いに違った方向に行く。すれちがう。「―・ったまま、ついに会えなかった」
③意志がうまく通じなくて、物事がうまく行かなくなる。手筈が狂う。「計画が―・う」
[二]〔自下二〕
⇒ゆきちがえる(下一)
ゆき‐ちが・える【行き違える】‥チガヘル
〔自下一〕[文]ゆきちが・ふ(下二)
行く方向を誤る。間違えて行く。
ゆき‐ち・る【行き散る】
〔自四〕
行って別れ散る。行ってちりぢりになる。いきちる。源氏物語須磨「年月経ばかかる人々も、えしもありはてでや―・らむ」
ゆき‐づき【雪月】
陰暦12月の異称。西鶴織留1「始めて懐炉といふ物を仕出し―頃より売りけるほどに」
ゆき‐づきよ【雪月夜】
雪のある時の月夜。
ゆき‐つ・く【行き着く】
〔自五〕
(イキツクとも)
①行って目的地に到着する。ある最終的な状態に達する。「―・いた所は倒産だった」
②(命・精力・資力などが)尽きる。行きづまる。
③すっかり参る。酒酔い・恋情などにいう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「かの男に―・いて毎日百通二百通」
④くまなく付着する。能因本枕草子正月一日は「白き物の―・かぬ所は」
ゆき‐つけ【行き付け】
行きなれていること。常に行って、なじんでいること。いきつけ。「―の店」
ゆき‐つばき【雪椿】
ツバキ科の常緑低木。東北・北陸の日本海側の山地に分布。高さ1〜2メートルでツバキに似るが、枝幹はやや斜上。4〜5月頃の雪どけ後、サザンカに似た花を開く。油はツバキに劣る。観賞用で、園芸品種が多い。オクツバキ。サルイワツバキ。
ゆき‐つぶて【雪礫】
雪を握り固めて礫のようにしたもの。〈[季]冬〉
ゆき‐づまり【行詰り】
行きづまること。また、その所や状態。いきづまり。「仕事に―を感ずる」「金融の―」
ゆき‐づま・る【行き詰まる】
〔自五〕
(イキヅマルとも)
①行ってその先がつまる。行きどまりとなる。
②物事が、困難に出会って、その先へ進まなくなる。「商売が―・る」
ゆき‐つ・む【行き詰む】
〔自四〕
行けるところまで行く。
ゆき‐づめ【行き詰め】
(イキヅメとも)
①行手がふさがっていること。
②絶えずいくこと。
ゆきつ‐もどりつ【行きつ戻りつ】
行ったり戻ったり。行ったり来たり。「―思案にくれる」
ゆき‐つり【雪釣】
子供の遊戯。糸の先に木炭などを結びつけ、これに雪を付着させ、雪の塊を大きくする。〈[季]冬〉
ゆき‐づり【雪吊り】
(ユキツリとも)雪折れを防ぐために、庭木などの枝を支柱から縄でつり上げること。〈[季]冬〉
ゆき‐つ・る【行き連る】
〔自下二〕
連れ立って行く。同行する。道づれになる。古今著聞集16「山伏一人又いもじする男一人―・れて上りけり」
ゆき‐ていいち【湯木貞一】
料亭経営者。神戸生れ。大阪・京都・東京に料理店「吉兆」を展開。日本料理の向上と発展に寄与。(1901〜1997)
⇒ゆき【湯木】
ゆき‐でん【悠紀田】
悠紀に供える新穀を作る田。↔主基田すきでん
ゆき‐でん【悠紀殿】
大嘗祭だいじょうさいの時の悠紀に建てられる殿舎。↔主基殿すきでん
ゆき‐どい【雪訪い】‥ドヒ
雪の降った時、人の安否をたずね見舞うこと。雪見舞。日葡辞書「ユキドイニマイル」
ゆき‐どうろう【雪灯籠】
雪をかためて穴をうがち、その中に灯心などを入れて点火するもの。
ゆき‐とお・る【行き通る】‥トホル
〔自四〕
通って行く。踏み破って通る。万葉集11「巌すら―・るべき建男ますらおも恋とふ事は後悔のちくいにあり」
ゆき‐どけ【雪解け・雪融け】
①雪がとけること。また、その時。ゆきげ。〈[季]春〉
②(ソ連の作家エレンブルグが1956年に著した小説の題名から)東西両陣営間の対立緊張の緩和をいう。
⇒ゆきどけ‐みち【雪解け道】
ゆきどけ‐みち【雪解け道】
雪どけのぬかるんだ道。
⇒ゆき‐どけ【雪解け・雪融け】
ゆき‐どころ【行き所】
(イキドコロとも)行くべき所。行った所。行き場。「―が無い」
ゆき‐どし【雪年】
雪の多く降る年。豊年であるとする。狂言、木六駄「当年は―で御座る」
ゆき‐たが・う【行き違ふ】‥タガフ🔗⭐🔉
ゆき‐たが・う【行き違ふ】‥タガフ
[一]〔自四〕
(→)「ゆきちがう」(自五)に同じ。
[二]〔自下二〕
(→)「ゆきちがえる」に同じ。
ゆき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ🔗⭐🔉
ゆき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ
[一]〔自五〕
(イキチガウとも)
①行き来する。行き交う。源氏物語竹河「―・ふ車の音、先追ふ声々も」
②互いに違った方向に行く。すれちがう。「―・ったまま、ついに会えなかった」
③意志がうまく通じなくて、物事がうまく行かなくなる。手筈が狂う。「計画が―・う」
[二]〔自下二〕
⇒ゆきちがえる(下一)
ゆき‐ちが・える【行き違える】‥チガヘル🔗⭐🔉
ゆき‐ちが・える【行き違える】‥チガヘル
〔自下一〕[文]ゆきちが・ふ(下二)
行く方向を誤る。間違えて行く。
ゆき‐ち・る【行き散る】🔗⭐🔉
ゆき‐ち・る【行き散る】
〔自四〕
行って別れ散る。行ってちりぢりになる。いきちる。源氏物語須磨「年月経ばかかる人々も、えしもありはてでや―・らむ」
ゆき‐つ・く【行き着く】🔗⭐🔉
ゆき‐つ・く【行き着く】
〔自五〕
(イキツクとも)
①行って目的地に到着する。ある最終的な状態に達する。「―・いた所は倒産だった」
②(命・精力・資力などが)尽きる。行きづまる。
③すっかり参る。酒酔い・恋情などにいう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「かの男に―・いて毎日百通二百通」
④くまなく付着する。能因本枕草子正月一日は「白き物の―・かぬ所は」
ゆき‐づま・る【行き詰まる】🔗⭐🔉
ゆき‐づま・る【行き詰まる】
〔自五〕
(イキヅマルとも)
①行ってその先がつまる。行きどまりとなる。
②物事が、困難に出会って、その先へ進まなくなる。「商売が―・る」
ゆき‐つ・む【行き詰む】🔗⭐🔉
ゆき‐つ・む【行き詰む】
〔自四〕
行けるところまで行く。
ゆき‐づめ【行き詰め】🔗⭐🔉
ゆき‐づめ【行き詰め】
(イキヅメとも)
①行手がふさがっていること。
②絶えずいくこと。
ゆきつ‐もどりつ【行きつ戻りつ】🔗⭐🔉
ゆきつ‐もどりつ【行きつ戻りつ】
行ったり戻ったり。行ったり来たり。「―思案にくれる」
ゆき‐どころ【行き所】🔗⭐🔉
ゆき‐どころ【行き所】
(イキドコロとも)行くべき所。行った所。行き場。「―が無い」
ゆき‐どまり【行き止り】🔗⭐🔉
ゆき‐どまり【行き止り】
行手がふさがって、それから先へ行けないこと。また、その所。いきどまり。「道は―になる」
ゆき‐どま・る【行き止まる】🔗⭐🔉
ゆき‐どま・る【行き止まる】
〔自五〕
(古くは清音。イキドマルとも)
①行く途中でとまる。立ち止まる。
②行き着く。進んで行ってそこでとまる。行手がふさがって、それから先へ行けなくなる。古今和歌集雑「世の中はいづれかさして我がならん―・るをぞ宿と定むる」
③物事が行きづまる。
ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ🔗⭐🔉
ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ
行き集まること。また、その所。万葉集13「里人の―に」
ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】🔗⭐🔉
ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】
〔自上二〕
落ち延びて進んで行く。
ゆき‐ば【行き場】🔗⭐🔉
ゆき‐ば【行き場】
行くべき場所。ゆくさき。ゆきどころ。いきば。「どこにも―がない」
ゆき‐ぶり【行き触り】🔗⭐🔉
ゆき‐ぶり【行き触り】
行く時に触れること。行き合うこと。ゆきずり。道ゆきぶり。
ゆき‐ふ・る【行き触る】🔗⭐🔉
ゆき‐ふ・る【行き触る】
〔自四〕
①行く時それにさわる。行こうとして接触する。行き合う。万葉集8「草枕旅行く人も―・らば」
②行ってけがれに触れる。
ゆき‐ぶれ【行き触れ】🔗⭐🔉
ゆき‐まじ・る【行き交じる・行き雑じる】🔗⭐🔉
ゆき‐まじ・る【行き交じる・行き雑じる】
〔自四〕
行ってまじる。多くのものが行き合ってまじる。雑沓する。源氏物語夕顔「山寺こそ、なほかやうのことおのづから―・り物まぎるること侍らめ」
ゆき・みる【行き廻る】🔗⭐🔉
ゆき・みる【行き廻る】
〔自上一〕
行きめぐる。万葉集8「明日香川―・みる岳おかの秋萩は」
ゆき‐むか・う【行き向かふ】‥ムカフ🔗⭐🔉
ゆき‐むか・う【行き向かふ】‥ムカフ
〔自四〕
①次々と過ぎ去ってはまたやってくる。万葉集13「―・ふ年の緒長く仕へ来し」
②その方へ行く。出向く。今昔物語集31「若干そこばくの神人じんにん等…かの粟田口の宮に―・ひて」
③立ち向かって行く。ぶつかって行く。平家物語2「その儀ならば、―・つてうばひとどめ奉れ」
ゆき‐めぐ・る【行き廻る】🔗⭐🔉
ゆき‐めぐ・る【行き廻る】
〔自四〕
行って、あちらこちらをめぐり歩く。万葉集6「―・り見とも飽かめや」
ゆき‐や・る【行き遣る】🔗⭐🔉
ゆき‐や・る【行き遣る】
〔自四〕
あえて行く。行ききる。進行を続ける。土佐日記「行けど猶―・られぬは」
ゆき‐ゆ・く【行き行く】🔗⭐🔉
ゆき‐ゆ・く【行き行く】
〔自四〕
行きに行く。進みに進む。行き続ける。伊勢物語「―・きて駿河の国に到りぬ」
ゆく‐ゆく【行く行く】🔗⭐🔉
ゆく‐ゆく【行く行く】
①行く末。やがて。将来。玉くしげ「或は今善き事も―のためにあしく」。「―は大物になるだろう」
②(副詞的に)行きながら。顕宗紀(図書寮本)院政期点「臥しつつ泣き行ユクユク号おらびて」。「話は―しよう」
[漢]行🔗⭐🔉
行 字形
 筆順
筆順
 〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕
〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)
〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら
[意味]
①ゆく。
㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」
㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」
㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」
㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」
㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」
②おこなう。
㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」
㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」
③とどこおらない。
㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」
㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」
④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」
⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」
⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。
[解字]
解字
〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕
〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)
〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら
[意味]
①ゆく。
㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」
㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」
㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」
㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」
㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」
②おこなう。
㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」
㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」
③とどこおらない。
㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」
㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」
④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」
⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」
⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。
[解字]
解字 十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。
[下ツキ
悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行
[難読]
行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ
十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。
[下ツキ
悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行
[難読]
行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ
 筆順
筆順
 〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕
〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)
〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら
[意味]
①ゆく。
㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」
㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」
㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」
㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」
㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」
②おこなう。
㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」
㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」
③とどこおらない。
㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」
㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」
④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」
⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」
⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。
[解字]
解字
〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕
〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)
〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら
[意味]
①ゆく。
㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」
㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」
㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」
㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」
㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」
②おこなう。
㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」
㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」
③とどこおらない。
㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」
㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」
④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」
⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」
⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。
[解字]
解字 十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。
[下ツキ
悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行
[難読]
行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ
十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。
[下ツキ
悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行
[難読]
行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ
広辞苑に「行」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む